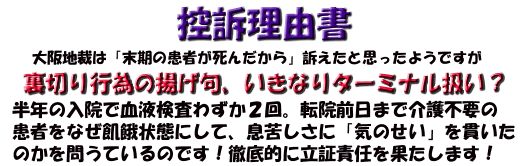11月28日、提出した、控訴審の控訴理由書。
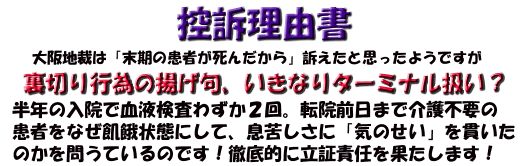
控訴審 第一回は、12月14日(木)午前10時 大阪高等裁判所 72号法廷 別館
平成一二年(ネ)第三三六八号 損害賠償請求控訴事件
(目次) 実際の控訴理由書では、細目次をも作っています。
はじめに
第一 亡淑子に対する治療方針の決定における問題点について
第二 亡淑子に対する診療行為における被控訴人藤村の注意義務違反について
第三 亡淑子の退院時前後における被控訴人藤村らの注意義務違反について
第四 結語
はじめに
一 本件の問題点(控訴人が本件提訴を決心した契機を含む。)
1 まず、本件においては、当初、平成八年三月二一日以降同年四月五日までの間に、被控訴人株式会社互恵会(以下「被控訴人会社」という。)が開設する大阪回生病院(以下
「本件病院」という。)の勤務医である被控訴人藤村隆(以下「被控訴人藤村」という。)による、乳がんを再発させた亡海野淑子(以下「亡淑子」という。)に対して決定された治療方針の
内容の適否、その決定過程(説明義務は果たされたか。不告知の方針は妥当であったか。)等が問題とされなければならない。
なぜなら、医療機関は、診療契約を締結した以上、再発がんとはいえ、その病態に応じ、十分な検査・治療もなさず、放置してはならないのであって、実際に、再発がんについて
も、現在の医療の現場では、後述のように、さまざまな治療方法が確立・実施されているからである。
また、とくにがん治療は、患者の人生そのものの選択に深くかかわるものであるから、慎重に本人ないしその近親者(特に本人に不告知とする場合)の意思を探求し、それらとの
合意形成を可能な限りで行わなければ成らず、当然ながら、その前提として、がんの病態の正確な把握のための十分な検査が必要であり、もし入院が長くなれば、それに応じて、随時
検査を行って病態の変化を把握し、それを患者に説明し、治療方針の継続や変更などについて十分な協議が行われなれけばならないと考える。
そのようなことは、決して患者側から求められるものではなく、本来、患者は諸疾患について素人なのであるから、医療者側が主体となって、積極的にこれを行うべきこともまた当然である。
しかるに、被控訴人藤村が決定した、亡淑子に対する治療方針は、その決定のために最低限必要な検査を行わなかったことに始まり、患者側に対する説明義務も果たされず、
また、本人への不告知の方針を誘導し、患者側と協議しながら治療を進めることのできる環境を作らないなどした上に、その決定された治療内容も、今日の医療水準に照らし、極めて
不適切であったと言わざるを得ないのである(これがそもそもの本件の始まりである)。
2 次に、平成八年三月二五日から同年一〇月五日までの、被控訴人藤村に対する、亡淑子に対する一連の診療行為が問題にされるべきである。
被控訴人藤村が、少なくとも、当初、控訴人との間で締結し確認した診療契約の内容(これがそもそも客観的に妥当であったかは後に検討するが。)に従って、診療行為を行うよ
う努力し、かつ、客観的にも、最小限の診療行為をしてくれてさえいれば、仮に結果的に亡淑子が本件病院において死亡することになっていたとしても、控訴人が訴訟を提起することはなかったのであるが、事実はそうではなかったのである。
控訴人は、一審判決(三頁)が言うように、被控訴人藤村が右診療行為を行ったことにより亡淑子が死亡した、ということだけをもって、被控訴人らに対し訴訟を提起したのではない。
詳細については後述するが、母であった亡淑子の乳がんの再発を知って、東京に仕事を持っていた控訴人が、被控訴人藤村に希望し、同人も了承した本件診療契約の内容は、
消極的には、体力の低下を招く抗がん剤などの使用を亡淑子にしないこと、積極的には、亡淑子を東京に連れていくことができるように体力および栄養状態を維持してもらうこと、であり、被控訴人藤村は、なんら医学的に十分な説明もせずにその希望に唯々諾々と従っていったのである。
それにもかかわらず、右の控訴人の最低限の希望をかなえるために全く足りないか、むしろこれに全く矛盾する診療行為がなされ(亡淑子に対し、アフェマによる積極的治療を開
始したために他院が引き取りにくい社会的状態をつくり、また、医療的にも体力低下・栄養不良(飢餓)状態を生じさせた。)、そのために、亡淑子は、控訴人の唯一の希望であった、東京に安全に連れて帰ることすらできない状態となり、新幹線内での心停止という事態にまで陥ったのである。
控訴人は、訴訟に先立つ保全記録から、右のような被控訴人藤村の診療行為を知り、全く裏切られていたことを知って、提訴を決意したのである(そして、その訴訟の過程で、さまざまな意見も聞いたところ、右の個別の治療のみならず、そもそもの治療方針の決定についても疑問を持つに至った)。
3 またさらに、平成八年一〇月五日、被控訴人藤村の右診療行為の結果、亡淑子は移動中に生命の危険のある重篤な状態を生じかねない体力低下・栄養不良(飢餓)状態にあったのにもかかわらず、適切な処置も指導もなさないまま、亡淑子を退院させた(実際に、亡淑子は、移動中の新幹線車中において、突然の心停止を起こし、そのために新幹線は緊急
停止している。)被控訴人らの行為には、一般的な診療義務および不法行為上の安全配慮義務に悖る行為であることは明らかであり、この点、十分な審理がなされるべきである。
控訴人が、生まれて初めて弁護士に依頼し、医療裁判に向けての証拠保全を行おうとした契機は、右のエピソードとその原因と思われた被控訴人藤村の診療行為への疑いからである。
控訴人でなくても、実の母親が新幹線車中で心停止を起こすような経験が、右のような気持ちに駆り立てても、それは無理からぬところであろう。
二 一審判決の問題点(控訴理由)
右の本件の問題点からは、本件の一審判決については、以下の点、事実誤認ないし法令違反(評価の誤り、経験則違反、審理不尽)があると言わざるをえない。
1 まず、前述のとおり、平成八年三月の亡淑子の再入院にあたり、そもそも、被控訴人藤村が決定した、亡淑子に対する治療方針は、その決定のために最低限必要な検査を行わなかったことに始まり、患者側に対する説明義務も果たさず、また、本人への不告知の方針を誘導し、患者側と協議しながら治療を進めることのできる環境を作らないなどした上に、そ
の決定された治療内容も、今日の医療水準に照らし、極めて不適切であったと言わざるを得ないのに、一審裁判所は、右の医療の基本たる重要な各点について判断をしていない。
この点、一審判決において、必ずしも争点として認識されていないようであるが、もとより、当事者に争点形成についての第一義的な責任があるとしても、裁判所にも第二義的な
争点形成責任があるというべきであり、特に、本件訴訟においては、医療機関である被控訴人(被告)側には医療の専門家が多数ついているが、個人たる控訴人(原告)にはそれは困難であるから、裁判所には、少なくとも、争点形成段階における後見的役割が要求されてしかるべきであった。
本件における被控訴人藤村が決定した治療方針が、医療行為として客観的に正当性であるかどうかは、本件において本来いかなる説明がなされるべきであったか、また、その後の個々の治療が正当性を有するかにも、それぞれ重大は影響を与えるものであるから、これ(治療方針の客観的正当性如何)を確定しなかったことは、審理不尽であるとも言いうる。
少なくとも、当事者間における、その治療方針の決定の過程、告知についての決定の過程などには、事実認定の誤りないし遺漏があり、一審判決の結論に重要な影響を与えて
いるといえるから、控訴審において、この点について審理されることを求めるものである。
2 次に、平成八年三月から同年一〇月までの、被控訴人藤村の乳がん再発後の亡淑子に対する治療行為につき、一審判決は、個々の措置ごとに、一般的医療水準に反しないとするが、まず、個々の措置を見ても、問題視されるべき行為は多く、その各評価には誤りがあると言わねばならない。
また、本来、医師の治療行為は、治療方針から全体的に把握されるべきところ、被控訴人藤村の本件における治療行為を全体的にみると、確固たる治療方針も全くない、時々の亡淑子の状態を検査もせずに漫然と投薬等の措置をしているなど(特に前後の検査を全くせずに新薬のアフェマ使用している点など)、本件のような場合に、本来なされるべき治療水準からみた場合はもちろん、仮に最小限、控訴人との間で合意された内容を実現するためという観点からみても、まったく不十分であるか、むしろ違背するものであるのに、一審判決
がこれらを問題ない、むしろ「極めて誠実に医療行為を行っていたものであって(一審判決一〇〇頁)」などとすることは、明かな、評価の誤り、ないし、経験則違反が存在する(「第二」
において述べる)
3 さらに、平成八年一〇月五日の亡淑子の退院時の処置については、被控訴人藤村が、亡淑子に重大な危険が生じることを予測していなかったとするなど、重大な事実誤認があり、かかる重大な事実誤認をも前提にして、被告藤村に退院を止め、少なくとも、適切な処置も指導もしなかったことについて注意義務違反を認めなかったことには、評価の誤りが存在すると言わねばならない。(「第三」において述べる)
三 なお、本件は、一医療事件であって、なんら特殊なものではない。
本件についてやや特別な点があるとすれば、控訴人が、いわゆるインターネット上のホームページを開設し、そこにホームページに事実および裁判の経緯を公開したことだけである。
これは、新規的であるとはいえ、まったく合法的なことであり、また、当初は、弁護士の知己もなく、また、協力してくれる医師もなく、およそ一人で医療機関に対し、訴訟を提起する
ことを考えざるをえなかった、控訴人にとってはいわばなしうる唯一の手段だったのである。
控訴審におかれては、このこととは無関係に、本件における事実を虚心坦懐に見ていただき、かつ評価を下されることを期待するものである。
一 再発乳がんに対する治療方針の決定について
1 本件の平成八年三月の再入院時の亡淑子は、「その胸水を細胞診の検査に回したところ、悪性度五(PCV)」の所見であったと一審判決(三七頁)も認定しているが(右PCV
は、PC5と表示されるべきであるが。)、これは癌性胸膜炎であることを意味し、乳癌の胸膜への転移を示唆すもので、再発乳癌と診断される。
2 しかしながら、再発乳がんとはいっても、治療をしなければいけないことは明白である。
甲三八(幕内雅敏監修「悪化するがんの治療百科」(三省堂))一六七頁以下に、がんが再発したときについての一般的治療について、同一七六頁以下に、再発乳がんに対する
治療についての記載があり、骨転移の場合でも放射線治療により転移巣が消えた例も紹介されている。
Cancer Net Japan=http://www.nagumo.or.jp/cancer/ の中の「がん情報ライブラリー」、これは、米国国立ガン研究所(National
Cancer Institute, NCI)が、乳がん治療に携わ る医師、乳がん患者およびその家族のために作成した文書が翻訳されて示されているのであるが、そこでも、「再発乳癌の治療(医師向け)」(甲三九の一)で治療方針・治療方法が示
されており、また、患者・家族向けに「ガンが再発したとき」(甲三九の二)という文書が示されているのであるが、要するに、これらにおいては、再発乳がん(これは直ちに、特に検査も
なく、末期がんとされるべきものではない。)であっても、病状に応じ、患者のQOL(クォリティ・オブ・ライフ)を著しく低下させる治療法でないかぎり、さまざまな治療に積極的に取り組む
べきであることが示されている。
甲三九の二から一部を引用すると、「ガンはその種類によって再発しやすい部位が決まっているので、その部位を中心に検査します。検査の頻度はあなたのガンの種類とひろがる様式によります。診察と検査から得
られる情報は正確な診断に役立ち、それによって最適な治療が施行されます。」と再発がんであっても十分な検査が必要であり、その検査結果に応じての治療の方針として、「再発したガンに対する治療を計画するにあたっては、ガンの初回治療の選択に影響を及ぼした多くの要因が重要となります。治療法の決定の前にガンの種類、その大きさと局
在、あなたの全身状態、そして以前に受けた治療法などが考慮されます。
多くの場合、初回治療をより強力にして再発したガンを治療することが可能です。新たな外科療法、新しい部位への放射線療法、より多くの抗ガン剤などが勧められることもあります。生殖器のガンに対しては、腫瘍の成長を抑えるホルモン療法が効果的なこともあります。
主治医と治療の目的や方法、そして効果に関して話し合うことは、あなたにとって最良の治療を決めるうえで役立ちます。質問しあなたの考えを明らかにして治療法の決定に積極的に参加することは大切なことです。」と述べられているのである。
3 また、特に、再発初期の場合は(遺憾ながら、後述するように、被控訴人藤村は、亡淑子に対し十分な当初の検査を行わなかったので、その点も確認されていないが。)、患者
のQOLを害さない治療方法ないし治療程度が考えられやすいので、なおさら積極的に治療を考えるべきであり、しかも、亡淑子は、一審判決も認定するとおり(三六頁)、本件病院にお
いて平成三年に乳がんの手術を受けて以来、本件病院に再発予防のため外来通院していたのであるから、本件病院および被控訴人藤村には、第一義的に治療をなしうる地位にあり、
かつその義務があったと言うべきである。
4 そして、右治療方針の決定のためには、前述したように、十分な検査が必要であることは言うまでもない(そうでないと、当該患者にいかなる治療が妥当するのかの選択もできないからである)。
がん再発の場合、がんの再発部位の検索、本件のような再発乳がんの際の検査として、少なくとも、「腫瘍マーカー」、「肝臓のエコー検査」、「脳CT検査」、「骨シンチグラフィ(
注.)」などの検査がされるとされている(その他、どのような検査が不可欠であるかは、現在専門医の意見を求めているところである)。
注.骨シンチグラフィ
骨に集積するRI標識トレーサを静注後、シンチカメラで全身および局所のイメージを撮影する核医学画像検査。放射性医薬品として古くは八五Sr、八七mSr、四三Kが用いられ
たが、今日では九九mTc標識リン酸化合物、とくに九九mTcメチレンジホスホネートmethylene diphosphonate(MDP)が繁用される。静注二~四時間後に撮影が行われる。正常の骨
格が描出されるが、腫瘍、炎症、外傷などの病巣部では放射能集積が増加する。ただし、骨転移が進行し、腫瘍組織が骨組織に置きかわると病巣部が欠損像を呈することもある。悪
性腫瘍の骨転移巣の診断に繁用されている。骨X線撮影より検出感度がよいからであるが、放射能集積は良性骨疾患でもみられるので、各々の病巣が転移であるか否かの断定は困
難である。同時に腎が描出されるので偶発的に腎の病巣が検出されることがある(南山堂「プロメディカ」)。
二 本件における、被控訴人藤村による、亡淑子に対する治療方針の決定について
1 この点に関する一審判決の認定部分は以下のとおりである(なお、事実の誤認ないし遺漏と考える部分については順次指摘しておく)。
(一) 「亡淑子は、平成八年三月二〇日、息苦しさなど身体の異常を感じたため(甲六)、同月二一日、本件病院に赴いて診察を受けたところ、胸水が貯留しており、(胸水の細胞診)検査の結果、がんが再発していることが判明した。」(一審判決六頁)
「被告互恵会(被控訴人会社)は、亡淑子との間で、平成八年三月二一日、本件病院において、亡淑子の再発したがんの冶療につき、診療契約を締結した。」(一審判決四頁)とある。
この時点で、診療契約、すなわち、準委任ないし請負類似の契約が締結され、被控訴人藤村にも、医術により、患者の希望に従って可能な範囲で、患者の病状の改善ないし
維持につとめるべき義務が発生した(ただし、治療方針等は未だ決まっていない)。
(二) 「その(胸水貯留により、がん再発が疑われた)ため、亡淑子は、同月(平成八年三月)二五日、再び本件病院に入院することになった。」(一審判決六頁)
「被告(被控訴人)藤村医師は、平成八年三月二五日、亡淑子の胸水一七○○ミリリットルを、二時間近くかけて抜去し、その胸水を細胞診の検査に回したところ、悪性度五(P
C・5)で腺がんの所見であり、がん再発が確定的となった。
乳がんが再発してがん性胸水が認められる場合の予後はきわめて悪く、放置すれば通常二、三か月で死亡に至るとされており、根本的な治癒を期待することはほぼ不可能で、治療はあくまでも延命のためのものとならざるをえないことから、被告(被控訴人)藤村医師は、それまでの経験等から推測して、抗がん剤の化学療法を行わない場合の亡淑子の
予後は、胸水の治療をしてうまくいかなければ、二、三か月、うまくいってもせいぜい半年程度であると考えていた。」(一審判決三八頁)のかもしれないが、控訴人はその後に至るも、
被控訴人藤村の右の所見を全く聞かされていない。
「胸水の治療がうまくいかなければ、二、三ヶ月、うまくいってもせいぜい半年程度」であると控訴人が聞いていたら、控訴人の意見は全く変わっていたはずである。
(三) 「被告(被控訴人)藤村医師は、家族に対して説明をしなければならないと考えていたところ、平成八年四月五日、看護婦から原告(控訴人)が来ている旨の連絡を受けたの
で、看護婦詰所に赴き(控訴人の記憶ではカンファレンスルームである。)、原告(控訴人)に対して亡淑子の病状等の説明を行った。被告(被控訴人)藤村医師と原告(控訴人)はこれ
が初対面であった。」(一審判決三八頁)とのことであるが、被控訴人藤村のその後の対応からは、家族に対して説明をしなければならないと考えていたとはとうてい信じられないが、その点は置くとしても、少なくとも、平成八年四月五日まで、被控訴人藤村は、患者本人である亡淑子にも、その家族にも、説明を積極的に行おうとはしていない(この点も極めて不審な点である)。
控訴人は、被控訴人藤村との初めての面会のために、カンファレンスルームに入ろうとしたとき、看護婦から「今度の先生は自分から説明しない先生だから、聞きたい事は自分
から聞いた方がいいですよ。」と耳打ちされている(乙二四・一一頁)。
(四) 「この際(平成八年四月五日)、被告(被控訴人)藤村医師は、原告(控訴人)に対し、これまでのおおまかな事実経過と、亡淑子に胸水が貯留しているがこれはがんの再発
に間違いないことを説明した。そして、亡淑子にがんの告知をするかどうかについて原告(控訴人)と話し合った結果、がんの告知はしないこと、亡淑子に対しては肋膜炎の再発である
と説明することで合意した。」(一審判決三九頁)とのことであるが、結論はそうかもしれないが、一審判決は、告知の方針についての重要な過程をことさらに認定していない(この点は後述する)。
(五) 「また、被告(被控訴人)藤村医師は、原告(控訴人)に対し、がんの治療法には手術療法、放射線療法、化学療法、ホルモン療法の四つがあるが、亡淑子はがん性胸膜炎
のためがんが全身にひろがっている状態と考えられ、局所療法である手術療法、放射線療法は効果が無く、このような場合は全身的な化学療法とホルモン療法を併用することが一般的であり、特に化学療法については、三種類の抗がん剤を組み合わせる化学療法が一般的に効果が高いとされていることを説明した、しかし、原告(控訴人)は、被告(被控訴人)藤村
医師に対し、自分はテレビ関係の仕事をしていてがんのことには詳しいが、抗がん剤による化学療法は副作用が強いだけで効果が無く患者を苦しめるだけであるから絶対にしないでほ
しい旨述べて、抗がん剤の化学療法を強く拒否した。」(一審判決四〇頁)とするが、まず、被控訴人藤村は、控訴人に対し、がんの治療法についてほとんど説明していない。
そのことは、その説明の内容についての記載が、カルテ(甲八、乙二)には一切認められないことから強く推認されるべきであり、かつ、控訴人が、法廷および陳述書において、
被控訴人藤村は、「ガンの再発です。様子を見て退院。次の治療で化学療法」「ここにポツポツとガンがあるんだろうね。」「手術はできないね。」としか言っていないと、具体的かつ明確に述べていることから明らかである(控訴人本人四四頁、甲二四・五頁)。
さらに、被控訴人藤村の「こういうガンは徐々に進行していくものですから」という言葉で、控訴人は、「ではここでは息苦しさだけとってくださいね、抗がん剤とかは使わないでく ださいね。動けなくなってしまいますから。」と、念を押していたのである(控訴人本人四三頁)。
前述のとおり、胸水の治療がうまくいかなければ、二、三ヶ月、うまくいってもせいぜい半年程度」との説明は、控訴人は全く聞いていない。もし聞いていたら、実の母親のことで
あるから、かく悠長なことは言っていられなかったはずである。
(六) なお、一審判決は、右のようにカルテの記載がないないし不十分であることについて、「(また、)被告(被控訴人)藤村医師によるカルテや指示簿の記載が十分でないという点については(正確には、これらの記載は殆ど為されていない。)、被告(被控訴人)藤村医師が自認するように必ずしも記載が十分でないところはあるものの、これらはあくまでも記録にすぎず、それらの記述が十分でないからといって患者や家族に対して直接に法的責任を負うものではないし、ましてや、裁判所が、カルテや指示簿の記載が不十分であるとの一事から被告(被控訴人)に不利な心証をとらなければならないというものではない。」(一審判決一〇二頁)などとするが、これは、医療におけるカルテ記載の重要性を全く無視する、全くの暴論であり、時代の趨勢に逆行するものと言わざるを得ない。
「カルテに記載のないことは、なされなかったものとの推定が働く」というべきである(逆に、カルテに記載のあることがすべてなされているとはいえないのであるが。)、このこと
はカルテの記載方法に関する基本的な文献には必ず記載されているし(例えば、甲四〇・田村康二編「診療録の書き方」(金原出版株式会社)二二頁など)、近時の判例もこれを前提
としている(東京高判平四・五・二六判例時報一四六〇・八五頁は「カルテは、医師法二四条により医師がその作成を義務付けられ、診察治療に際してその内容及び経過に関する事
項をその都度、経時的に記載すべきものであって、また、カルテは、看護日誌等これに付属する補助記録とともに、医師にとって患者の症状把握と適切な診療のための基礎資料として
必要不可欠なものであるから、記載の欠落は、後日にカルテが改変されたと認められる等の特段の事情がない限り、当該事実の不存在を事実上推定させる」と判示している。)。
(七) そして、一審判決は、控訴人が、副作用のみを問題にし、亡淑子に対する抗がん剤の使用をしないで欲しいと頼んだとのことであるが、それは事実と異なる。
すなわち、東京に在住し職を得ていた控訴人は、被控訴人藤村に対し、亡淑子を東京の病院に転院させそこで積極的な治療を受けさせたいという希望を告げており、転院までに副作用の強い抗がん剤治療により移動ができなくなると困るから、抗がん剤による治療はしないで欲しいと告げていたのであって(控訴人本人四〇、七五頁)、被控訴人藤村もそれは認めている(被控訴人藤村二六頁)。
つまり、控訴人は、大阪回生病院での入院は一時入院と捉え、転院をする際、本人に告知をし、亡淑子の意思で化学療法を決定させるつもりだった。患者本人が納得の上なら
ば、例え副作用があっても転院後は化学療法を受けさせたいと考えていたのである。
ただ、控訴人に、亡淑子の世話に事欠く大阪での治療は受けさせたくなく、体力のあるうちに転院させたいという希望があり、被控訴人藤村もそのことを認識していたことは、後述するように、別の箇所では、一審判決も認定している。
(八) 「被告(被控訴人)藤村医師は、原告(控訴人)は亡淑子の唯一の家族である上、化学療法を行っても根本的に治療できるわけではなく、副作用もあり得ることから、原告(控
訴人)の意向に従って抗がん剤の化学療法を行わず、もっぱら苦痛緩和を目的とする治療方針をとることにした。そして、原告(控訴人)が、東京に在住し、亡淑子を東京の病院に転院
させたいとの希望を有していたことから、被告(被控訴人)藤村医師は、胸水の治療をした上で亡淑子を退院させることを当面の目標とすることにした。
さらに、被告(被控訴人)藤村医師は、原告(控訴人)に対し、仮に胸水の治療がうまくいったとしても、がんを根本的に治療するものではないので、平成八年の年末までは(亡
淑子が生き延びることは)難しいと思う旨述べた」(一審判決四〇頁)とするが、前段はさておき、後段については被控訴人は全く聞かされていない。
2 まず、右一審判決も認めるとおり、被控訴人藤村は、胸水の細胞診を行っただけで、右の各検査は一切していない。
これでは、そもそも再発乳がんに対する、適正な治療方法を判断することはできないはずである。
3 そして、本来、従前から通院治療を受けていた本件病院の外科部長たる医師であり(もっとも、亡淑子が手術を受け、その後、長らく再発防止の治療にあたっていた医師は別人である。)、第一義的にはその適切な治療が期待される被控訴人藤村には、少なくとも、亡淑子が、当時、いかなる客観的・医療的状態であり、かつ、その場合に可能な治療方法の功罪を説明し、仮に選択の幅のある場合には患者側に選択・決定させるということが要求されていた。
しかるに、被控訴人藤村は、右に見てきたとおり、その説明すらしていないと言わざるを得ない(もっとも、本件の被控訴人藤村に説明義務を求める趣旨は、検査もせず、確たる
治療の方針も立てられていなかったことを患者側に察知させ、その治療を拒否する機会を与えるという消極的なものでもあったのであるが)。
4 以上より、そもそも再発乳がんについての転移の有無・病巣の状態の検査もしないで、被控訴人藤村が決定した亡淑子に対する「治療方針」、すなわち、一審判決(四〇頁)の
認定するところによると、「化学療法を行っても根本的に治療できるわけではなく、副作用もあり得ることから、原告(控訴人)の意向に従って抗がん剤の化学療法を行わず、もっぱら苦痛緩和を目的ニする治療方針をとることにした。そして、原告(控訴人)が、東京に在住し、亡淑子を東京の病院に転院させたいとの希望を有していたことから、被告(被控訴人)藤村医
師は、胸水の治療をした上で亡淑子を退院させることを当面の目標とすることにした。」との決定は、これが検査も殆どされずに決定されたものである点も含め、患者の基本的かつ究極的な利益に反し、診療契約に基づく義務の違反であると言わざるをえない。
ましてや、被控訴人藤村は、「これまでの経験等から推測して、抗がん剤の化学療法を行わない場合の亡淑子の予後は、胸水の治療をしてうまくいかなければ、二、三か月、う
まくいってもせいぜい半年程度であると考えていた。」(一審判決三八頁)というのであるから、右方針の決定はなおさら不当である。
すなわち、(これも検査をしない推量であったが、)仮に客観的にそのような状況であることが事実であるなら、東京へ直ちに連れて行って積極的治療をするように勧めるか、ないしは、大阪での積極的治療を勧めるべきだからである。
5 あるいは、被控訴人藤村は、控訴人に説明の上、控訴人が納得したことであると主張し、説明義務は十分果たしている、などと主張するかもしれない。
ただし、医療という専門の分野において、専門家たる医師の果たすべき説明義務は、患者に、医学的に可能な選択枝を適切に示し、その功罪を説明し、患者の選択を助けること
に資するものでなければならない。
右認定されるべき本件事実によると(一部、一審判決の事実誤認を訂正)、被控訴人藤村は、「乳がんの再発です。」と言い、また、一般的な治療法は述べたかもしれないが、亡淑子の病状についての詳しい検査をしていなかったのであるから、亡淑子に対しどの治療方法が適当であるか、その功罪等の詳しい説明もせず、さらに、亡淑子の余命についての的確な判断も示さないまま(この点も検査もせずに判断することはできないはずである。)、つまり、まったく不十分な説明のままに、漫然と、患者側の家族である控訴人に治療方針を選択・決定させているのである。
かかる状況で、患者側の家族である控訴人が望んだからと言って、専門家たる医師である被控訴人藤村が、唯々諾々とそれに従ってよいとは当然言えない。
なお、被控訴人藤村は、亡淑子の余命について、控訴人が特に聞かなかったか、さらには、聞くのを拒んだと主張するかもしれないが、そのことによって治療上の責任が軽減さ
れるというものでなく、少なくとも、余命がいつまでかに関係してくる、「退院」「転院」の問題となったときには、本人ではない控訴人との間では、それについての話しあいを避けることはできないというべきである。
三 不告知の方針の適否
1 一審判決(三九頁)は、この点につき、平成八年四月五日、病院を訪ねてきた控訴人に対し、被控訴人藤村が、これまでのおおまかな事実経過と、亡淑子に胸水が貯留しているが
これはがんの再発に間違いないことを説明した際、「亡淑子にがんの告知をするかどうかについて原告(控訴人)と話し合った結果、がんの告知はしないこと、亡淑子に対しては肋膜炎
の再発であると説明することで合意した。」とのことであるが、結論はそうかもしれないが、一審判決は、告知の方針についての重要な過程をことさらに認定していない。
がん再発を告知するかしないかは、これを告知することにより本人の自己決定権を実効あらしめ、より適切かつ適宜の治療に積極的に対応しうるというプラス面と、告知すること
によって当人の気質によっては絶望のあまり治療に対する意欲をなくさせるかもしれないなどというマイナス面とを比較考量し、慎重に決められるべきことである。
しかるに、右亡淑子に対しがん再発を告知するかしないかについて、被控訴人藤村は、控訴人に対し、不意にいきなり尋ねてきたのであって、控訴人が「母には言ってくれと言われています。(東京に職業をもっていた)私が一旦、東京に戻る中、言ってしまっていいものか。東京に来てもらう時、じっくりと今後の事を考えるべきでしょうか。」と迷っていると、被控訴人藤村は、亡淑子の気質を考えたり、控訴人とよく話し合うことも全くせずに、控訴人に対し、「中途半端が一番よくない。告知しない方針でいきましょう」と一方的に提案したので、ではその方針で、と決まったという経緯がある(控訴人本人四二頁)。
すなわち、右のような重要性を有する、本人へのがん再発告知の問題について、右のように告知することについてのプラス面もマイナス面も考慮することなく、さらに「がんの再発」とだけ聞かされどのような治療が必要かを詳しく聞かされることもないまま、およそ「話し合った」とはいえないような状況で、被控訴人藤村が一方的に決めてしまったのである。
2 右のような決定の経緯、および、本件のように、亡淑子本人はすでに乳がんの手術も経験し再発も有る程度は覚悟していたと言えるし、また、近親者である控訴人も、亡淑子を
東京に連れ帰ったあとにはきちんと説明し、積極的な治療を受けさせようと考えていたという点を考え合わせると、被控訴人藤村が、安易に不告知の方針を決定したことも極めて不当であったというべきである(少なくとも、亡淑子に対する積極的治療が必要となった時点で、告知し、積極的な治療を受けうるようにすべきであった)。
亡淑子本人に対しては不告知、そして、近親者である控訴人に対しては全く連絡しないという状況で、被控訴人藤村が、患者の自己決定権を踏まえての治療を的確に行おうとしたのかは、極めて疑問であると言わざるをえない(被控訴人藤村は、かかる、患者側の誰とも協議しなくても治療を進められる環境を自ら作り出そうとした、とも考えざるをえない)。
3 なお、一審判決は、「その(がん不告知を決めて胸水除去を開始した)後、被告(被控訴人)藤村医師や本件病院の看護婦らは、亡淑子に対し、胸水は肋膜炎によるものであり、
がんの疑いはないと説明していたが、亡淑子は、当初からがんの再発ではないかと疑って、被告(被控訴人)藤村医師らに問いただすことを繰り返した。
これに対し、被告(被控訴人)
藤村医師らは、それに対して余り詳しく説明すると、かえって矛盾してしまうことから、ある程度漠然とした説明しかすることができなかったため、亡淑子は、被告(被控訴人)藤村医師ら
が十分に説明してくれないと思ってしばしば不満を感じ、原告(控訴人)との電話でもその不満をときどき口にしていた。(一審判決四一頁)」とし、被控訴人藤村らが、がん不告知のもと、治療の努力をしていたかのように言うが、これも専門家である被控訴人藤村がむしろ決めた(一審判決の認定によっても少なくとも同意していた)、がん不告知の方針から当然に予測しえた結果にすぎず、その責めは被控訴人藤村が負って当然のことであり、むしろ、不告知に誘導した被控訴人藤村の判断が誤っていたと言うべきである。
四 以上、要するに、当初、被控訴人藤村が決定した、亡淑子に対する「治療方針」は、必要な検査を全く行わず、控訴人への十分な説明もなく、決定されたものであり、客観的にも、
まったく「方針」ないし「目的」の名に値しないものである。
一審判決は、そもそも、その決定過程における事実認定を遺漏し、または誤認し、重大な問題を看過している。
いかなる疾病についても同様であるが、特にがんについて、告知しないで欲しい、また、抗がん剤を使用しないで欲しい、といわれても、その制約の中で最善の医療行為を手配する診療契約上の義務が、なお医師にはあるのである。
逆に言うと、告知しないで、また、治療行為が制約されて、患者自身のために目指す医療行為ができないなら、ちがう説明があってしかるべきである。
たとえ、実の娘(である控訴人が)が、「抗がん剤は使用しないで」「再発を知らせないで」といっても、「はいわかりました。」ではすまされないはずである。
そしてさらに、右「治療方針」が、なんらの検査もなされずに決定されたという点は、診療契約上の重大な義務違反であると言わざるをえない。
五 そして、本件においてまがりになりにも決定された治療方針(診療契約の合意内容)は、被控訴人藤村が、控訴人の希望に唯々諾々と従ったところの、「抗がん剤の化学療法を
行わず、もっぱら苦痛緩和を目的とする(ではなく、転院を目的としていたのであるが。)治療方針をとることにし、控訴人が、東京に在住し、亡淑子を東京の病院に転院させたいとの希
望を有していたことから、胸水の治療をした上で亡淑子を退院させることを当面の目標とすることにした。」(一審判決四〇頁)ということであり、その適否は別として、本当に被控訴人藤村がそのようなことが可能であると考えていたのなら、双方の(診療契約の)合意の内容もであるから、少なくとも、その希望に添うような治療行為をすべきだったのに、後述するように、 被控訴人藤村のなした治療行為は、控訴人の右の希望とも全くかけ離れた行為だったのである。
一 右注意義務違反を考える指針について
1 およそ医師が診療行為を行うにあたっては、患者(側)と合意した治療方針に従って、患者の状態を把握した上で(必要が有れば検査をする。)、治療し、治療結果を分析し(必要
が有ればさらに検査をする。)ということの繰り返しにより、目的を達成しようとすることが必要であることには異論はないであろう。
2 本件における被控訴人藤村と、患者側の控訴人との間で合意していた治療目的ないし方針は、前述のとおり、それ自体正しかったかどうかは置くとして、「(亡淑子にがん再発 の告知をせず、)亡淑子の体力を落とさないようにし、亡淑子を控訴人の住む東京に転院させ、そこで治療(場合によっては、化学療法も)を受けることができるようにするため、早期に亡淑子を退院させること」だったはずである。
個々の治療行為についても、当然ながら、右治療目的に添うものであるかが、具体的に検討されなければならない。
本件において、被控訴人藤村は、医師としての良心に従って、少なくとも右治療目的を達成するために、誠実に個々の治療行為を行ってきたといいうるのであろうか(残念なが
ら、本件のカルテを検討された全ての医師がそうではなかったのではないか、と言われるのであるが)。
3 一審判決におけるこの点に関する事実経過の認定自体(一審判決四二頁~)は、ほぼ問題はないと思料するが、個々の治療行為の適否について、全体の基本方針との関係、 または、個々の治療行為の前提ないし結果の確認のたになされるべき検査等の措置の必要性・有無についての認定がなされておらず、それが個々の争点における評価の誤りにつな がっていると言わざるをえない。
以下、右に述べた点を基本的な指針として、本件の亡淑子に対して実際になされた治療行為についての注意義務違反と思われる点について、個別に述べる。
二 説明義務違反、ないし、患者側との間で合意した内容に従って治療を行う(変更の場合はその説明を行う)義務の違反について
1 一審判決は、シスプラチン、ピシバニール、アフェマのそれぞれの個別の薬剤の一般的説明を行った上(六四頁~)、「以上を前提に、説明義務違反の有無について検討する。」とされる。
その前提として、医師の「説明義務」の必要性とその内容について、「一般に、医師は、診療契約上、患者に対し、手術などの医学的侵襲行為を患者の身体にするにあたり、患者の自己決定権を保証しその承諾を得る前提として、診断に基づく病状やこれに対する治療方法及びその必要性、危険性などについて説明をする義務を負っており、投薬についても、
投薬の目的、効果及び副作用等について説明すべき義務を負うものというべきである。
もっとも、医師に要求される説明の程度は、予想される侵襲の重大性、重大な結果が生じる危険 性、説明をすることによって患者に生じうる悪影響の有無、医療行為の緊急性等によって変化し、個別具体的な事情により決せられるべきものである。」とされるが、その一般論につい
ては特に異論はないが、後述するように、一審判決が個々の薬剤の特性ないしその使用方法の説明をすればよいと考えている点は承伏できない(合意された治療方針との間で、患者側にその説明がなされていたかが検討されるべきである)。
その他、一審判決は、この点について事実認定の誤り、評価の誤りを繰り返されていると言わざるを得ない。
2 まず、一審判決(六八頁)は、「認定した事実を総合すれば、シスプラチンを胸膜癒着療法に用いることは、当時の医療水準において最善もしくはそれに準じる方法であること、シ
スプラチンを胸膜癒着療法のため二○ないし二五ミリグラム使用しても、重大な副作用を生じるおそれはほとんどないこと、」とするが、このような認定についての間接事実は判決に示されていない。
すなわち、シスプラチンないしピシバニールを用いての胸膜癒着療法による必要のあること、それが最善ないしそれに準じる方法であることは、そもそも全く説明されていないし、 その医療上の客観的相当性も極めて疑問である(現在、専門医に照会中である)。
したがって、右の点の一審判決の判断には評価の誤りがあると言わねばならない。
3 また、一審判決(六八頁)は、「被告(被控訴人)藤村医師は、亡淑子に対する悪影響を考慮してがんの再発を告知しない方針をとっており、あまり詳しく説明するとがんの再発を告知することと同じことになってしまい、そうでなくともがんの再発ではない旨の説明の間に様々な矛盾を露呈しかねないため、ある程度曖昧に説明せざるを得なかったことが認められ、
かかる事情のもとにおいては、そもそも被告(被控訴人)藤村医師らが負うべき説明義務の程度は相当軽減されていたものというべきである。」とするが、前述したとおり、本人への不告知は被控訴人藤村が誘導したものであり(それにより、近親者へ連絡を取らなければならなくなる不利益は被控訴人藤村において甘受されるべきである。)、仮にそこまでの認定は
されないとしても、少なくとも、被控訴人藤村は本人への不告知の方針に同意しているのであるから、本人に替わる近親者への説明をされるべきであって、説明義務の総体は軽減されることはないというべきである。
4 また、一審判決(六九頁)は、右に続き、被控訴人藤村による「亡淑子に対する」右説明は、なし得る限りにおいて最大限真摯になされたというべきであって、説明義務を十分に 尽くしたものと認めるのが相当である、とし、また、「亡淑子に対し、」シスプラチンを「炎症を抑える薬」であるなどと本来の作用とは異なる説明を行っていたことも正当な行為として是認
されるべきである、とされているが、右にものべたとおり、問題とされるべきは、本人への不告知の方針の下、前述の治療目的を家族および医療機関が共同で達成しようとすることに被
控訴人藤村は少なくとも同意しているのであるから、その治療目的に変更のありうる場合は本来の同意の相手方である控訴人にも説明をなされるべき、ということであって(控訴人との間には、不告知にまつわる説明の制限もないのである。)、亡淑子に右のように説明しただけでは足りないのである。
5 また、一審判決(七〇頁)は、ピシバニールおよびアフェマについても、それぞれ、殆ど同じ言い回しにより、右と同様、その使用に関する説明は問題ないとするが(すなわち、がん再発不告知の方針等により被控訴人藤村らが負うべき説明義務の程度が相当軽減されるものであって、それでもなお右のとおり投薬の目的、効果、予想される副作用について、亡
淑子に説明している。)、右3および4に述べたとおり、本件で決定された治療方針の下、それでは全く求められている説明義務としては不十分である(この説明があれば、控訴人は、 方針を変更して、直ちに東京へ連れ帰ることを考えたに違いないのである)。
6 また、一審判決(七二頁)は、「(さらに付言すると、)シスプラチン、アフェマにより亡淑子に重篤な副作用が出たことは認められず、(また、ピシバニールに至っては発熱が生じた
ものの)」とするが、これは事実誤認であると言わざるを得ない。
なぜなら、一審判決も認めるように、平成八年五月九日の三八・四度もの発熱(乙二・四三頁)は、同年五月七日のピシバニールの使用によるものであるが、同年四月一四日の三七・
七度の発熱(乙二・三六頁)も、同様の胸膜癒着法による措置であることから、その時期が近接していることが類似しているので、同年四月一三日のシスプラチンの使用によるものである蓋然性が高いからである。
また、「(また、)ピシバニールに至っては発熱が生じたもののそれに伴って胸水の除去という当面の最大の治療目的が達成され、亡淑子の最大の苦しみを取り除くことに成功し
ているのであるから、本件において、これらの薬剤の投与が亡淑子の死期を早めたとか亡淑子に精神的苦痛を与えたなどという事態はおよそ想定し得ないところであって、亡淑子には
そもそも説明義務違反に相当する損害が発生していないというべきである(なお、原告(控訴人)は、固有の精神的損害も主張するが、原告(控訴人)自身は説明義務の直接の相手方ではないし、近親者の死に比肩すべき損害が生じた場合というわけでもないから、そもそも説明義務違反に関する原告(控訴人)の固有の損害は無いといわざるを得ない。)」とする点 は、明らかに評価の誤りがあると言わねばならない。
なぜなら、亡淑子の右発熱(三八度台というのは極めて高熱であり、当然、大阪から東京への移動には耐え難い。)、および身体の不調(看護記録からは、亡淑子の身体の不調
は、発熱の時期とほぼ同時期に、平成八年四月から五月にかけて長時間継続している。)により、後述する栄養状態の悪化と合わせて、まさに、控訴人と被控訴人藤村との間で合意目的である、早期に亡淑子を東京に転院させ、東京で化学治療を含めた積極治療も検討する、という機会が奪われたのであるから、亡淑子にはその機会が奪われた精神的損害があり、かつ、控訴人にも、実の母親にかかる機会を与えることを奪われた精神的損害があることは明らかだからである。
ただ単に、発熱により、「直接に」死期を早めたとか、精神的苦痛を与えたか、という問題ではないのである。
7 さらに、一審判決(七〇頁)は、「(この点について、)原告(控訴人)は、抗がん剤の使用を拒否したにもかかわらず被告藤村医師は抗がん剤を使用したと主張するが、そもそも原告(控訴人)は『(副作用の強い)抗がん剤による化学療法』を拒否したものであるところ、これまで詳述したところから明らかなように、胸膜癒着療法とホルモン療法は右化学療法に当 たらないというべきであるから、被告(被控訴人)藤村医師は、原告が拒否していた医療行為を無断で行ったとは認められない。
しかも、原告(控訴人)が抗がん剤による化学療法を拒否した趣旨は、現在の医療においては亡淑子に根本的な治療の可能性がないことを知り、延命のために副作用の強い抗がん剤を使用して亡淑子を苦しめるより、対症療法による苦痛
の緩和に重点を置いた治療を望んだ点にあるところ、前記認定のとおり、シスプラチン、ピシバニール、アフェマのいずれの薬剤も、被告(被控訴人)藤村医師の今回の使用方法による限り、原告(控訴人)の抗がん剤拒否の趣旨に反するどころかむしろそれに合致するものというべきであって、被告(被控訴人)藤村医師の右医療行為が非難されるべき理由は見いだし難いのである。
そもそも、ある薬剤が抗がん剤であるか否かは抗がん剤をどのように定義づけるかにかかる相対的なものであって、その使用方法と効果、副作用等の具体的検討を離れて、単に医薬品の分類上、右各薬剤が抗がん剤に当たるのか当たらないのかという議論をすること自体全く意味がないのであり、原告(控訴人)は、単にシスプラチン、ピシバニー
ル、アフェマが医薬品の分類上『抗がん剤』として分類され得ることのみをもって、被告(被控訴人)藤村医師による適切な医療行為を事後的に非難しているものというほかはない。」とするが、
右には明らかに事実誤認があり、その誤認を前提としたさらなる評価の誤りがあると言わねばならない。
すなわち、まず、「原告(控訴人)が抗がん剤による化学療法を拒否した趣旨は、現在の医療においては亡淑子に根本的な治療の可能性がないことを知り、延命のために副作用
の強い抗がん剤を使用して亡淑子を苦しめるより、対症療法による苦痛の緩和に重点を置いた治療を望んだ点にあるところ、」とする点は全くの事実誤認である。
これまで述べたとおり、控訴人は、当初から十分な説明をしない被控訴人藤村に対し一抹の不安を覚え、被控訴人藤村に、ただ、胸水貯留による、息苦しさだけを取ることを求め、胸水抜去以上の治療を求めず、東京の病院に転院させ、そこでの積極的な治療をすることを目的としたのである(被控訴人藤村に、亡淑子のがんそのものに対しては、対症療法による苦痛の緩和であれ、一切の治療を求めたことはないのである)。
しかも、被控訴人藤村は、「胸水抜去の処置がうまくいなければ余命は二~三ヶ月、うまくいっても半年」と考えていたのである。
従って、一審判決もこれらの薬剤に多大なる副作用のあることは認めているのであるから(シスプラチンには、腎障害をはじめ重篤な副作用があり、高頻度で嘔気、嘔吐の副作
用を生ずる、とされる。なお、シスプラチンは、がん性胸膜炎における胸膜癒着療法の胸膜癒着剤として用いられることがあり、その場合は生理食塩水に溶かして胸腔内に少量を投与
が、この場合に副作用はほとんど認められない、とされるが、そもそもかかる方法が必ず選択されるべきであるかは疑問である。
ピシバニールには、高頻度で発熱の副作用を生ずる、とされる。
アフェマには、主な副作用として食欲不振等があるが、そもそも長期間の投与を前提に開発された薬剤であるため副作用が現れる頻度は低く、重篤な副作用もほとんどない、
と一審判決は認定されるが、アフェマは、平成七年六月に承認され、同年九月から発売が開始された薬剤であり、その副作用情報は確立されているとはいえない。)、これらの薬剤を使用することは、右治療方針にかかわる重大な事項であり、患者側(本人、ないし、本人への不告知の方針を同意しているなら、近親者)に説明する義務が当然生じるというべきである。
その説明を行わずに副作用の甚大なる各薬剤を用いることは、説明義務違反に止まらず、合意した治療方針に基づかない治療を行った債務不履行があると言わねばならない。
右一審判決は、「そもそも、ある薬剤が抗がん剤であるか否かは抗がん剤をどのように定義づけるかにかかる相対的なものであって、その使用方法と効果、副作用等の具体的
検討を離れて、単に医薬品の分類上、右各薬剤が抗がん剤に当たるのか当たらないのかという議論をすること自体全く意味がないのであり、原告(控訴人)は、単にシスプラチン、ピシ
バニール、アフェマが医薬品の分類上『抗がん剤』として分類され得ることのみをもって、被告(被控訴人)藤村医師による適切な医療行為を事後的に非難しているものというほかはない。」などとするが、むしろ、右一審判決こそが、控訴人の希望、かつ、合意された治療方針のうち、「抗がん剤は使用しないでほしい。」という点だけをとらえて、シスプラチン、ピシバニ ール、アフェマがそもそも「抗がん剤」であるか、または、「抗がん剤」と呼ばれるものか、ないしは「抗がん剤」としての使用されたものであるか、などの形式の問題として判断をなそうとしていると言わざるをえない。
控訴人が希望し、被控訴人藤村も同意した「抗がん剤を使用しない」ことの究極の目的は、前述のとおり、亡淑子の体力を落とさないようにし、亡淑子を控訴人の住む東京に転
院させ、そこで治療(場合によっては、化学療法も)を受けることができるようにするため、早期に亡淑子を退院させること」だったのであり、
右一審判決がいうように「シスプラチン、ピシ
バニール、アフェマのいずれの薬剤も、被告(被控訴人)藤村医師の今回の使用方法による限り、原告(控訴人)の抗がん剤拒否の趣旨に反するどころかむしろそれに合致する」などとは到底言えるものではない。
8 さらに、一審判決(七五頁)は、「(また、)原告(控訴人)は、アフェマは新薬であったのに、被告(被控訴人)藤村医師らはその旨の説明をしていないとも主張するが、新薬であるからといって危険であるとは限らないのであるから、そもそも医師に新薬であることについての一般的な説明があるとは解されないのみならず、少なくとも、本件においては、アフェマは 新薬とはいえ比較的安全な薬剤であって副作用のおそれは少ないのに対し、亡淑子にアフェマは発売されたばかりの新薬であるなどと説明すれば、ただでさえがんの再発を疑っていた亡淑子に、なぜそのような新薬を自分に使わなければならないのかなどと無用な精神的不安を生じさせるおそれがあり、本件においてアフェマが新薬であることを説明するのはかえって妥当でないというべきであるから、被告(被控訴人)藤村医師に新薬の使用についての説明義務違反を認めることはできない。」などとし、単に「新薬」であることを問題としていると
論難するが、控訴人は、新薬であることだけでなく、そのために「副作用情報が確認されていないこと」を問題としているのであって、かかる薬剤を、特に、「亡淑子の体力を維持して、東京の病院に転院させる」という合意された治療方針の下、患者側に(副作用のおそれなどにつき)十分な説明もなく使用していることを問題としているのであるから、一審判決はこの点にも評価の誤りがある。
なお、新薬であることを含め、アフェマを使用することについての説明は、被控訴人藤村も不告知を自ら合意した亡淑子に対してでなく、右治療方針を合意した控訴人に対してなされるべきことであり、この点について、亡淑子への説明を前提とする一審判決の右判示部分の理由づけも不当である。
三 本件における中心的な治療目的である亡淑子の栄養を管理する義務違反について
1 本件において双方で合意された治療の方針、すなわち、大阪では息苦しさだけをとって、亡淑子の体力を維持し、早期に亡淑子を東京に転院させ、東京で化学治療を含めた積
極治療も検討する、の下では、亡淑子の栄養状態を管理することがまさに中心的な治療課題というべきであった。
2 一審判決も認めるように、「低ナトリウム血症は、血清ナトリウム濃度が低下している状態のことで、一二○以下で重症と考えられており、電解質異常の中でももっとも頻度が高
く、高度の異常では種々の神経症状を呈し死亡することもある。したがって緊急処置が必要なことも多いが、逆に血清ナトリウム濃度の補正速度が急速すぎると中枢神経の脱髄を引き起こし、そのために死亡することもあるから注意が必要である。」
また、しかも、「低ナトリウム血症は、末期がん患者に多くみられる現象である」とされている(一審判決七六頁)。
かく血中ナトリウム値の把握は、特に、亡淑子のような、末期がん患者にとって重要なことであり、他方、一般血液検査によって容易に測定しうるものであり(後述もするとおり、その基本的な項目である。)、かつ、血液の栄養状態を見るための重要な指針とされている値であるから、一般血液検査により、少なくとも一週に一回ないしは二週に一回は測定されるべきであった(特に、食事が充分にとれず、かつ、栄養補給は輸液に頼るというようなことがなく、栄養状態を殊更に管理する必要がない入院の場合でも、少なくとも二週に一回程度の一般
血液検査はなされているはずである)。
できるかぎり頻回にナトリウム値の検査をすることにより、早期に軽度の低ナトリウム状態を看取することができ、急激なナトリウムの補正の必要もなくなる、という効果もあるのである(一審判決七七頁は、急激な補正の危険を指摘する)。
3 さらに、一審判決(七八頁)は、「末期がん患者に対する補液」として、「末期がん患者の場合、過度な輸液は逆に浮腫を増長させ、患者のクオリティオブライフを悪化させるの
で、患者の衰弱が進むと輸液を減量し、一日五○○ミリリットル程度にする方が患者としては苦痛が少なくてすむ。また、生命予後が数日と考えられる場合には、輸液を中止する方が
苦痛なく看取ることができる場合が多い。また、末期がん患者に対しては、高カロリー輸液を実施しても効果がないばかりか、逆に予後を短くする可能性があるといわれているのみならず、胸水や腹水貯留の原因となったり、高血糖による口渇が患者を悩ますこともあるので、患者の衰弱が進んでくると高カロリー輸液を中止し、普通の輸液にする方がよいとされている。」としているが、
いつの間にか、亡淑子が、生命予後が数日の、輸液を中止する方が苦痛なく看取られるがん患者となっているが、当時の亡淑子は、未だ全くそのような状態になく、
「体力を維持し、退院の上、東京での治療を目指す」という治療方針で被控訴人藤村も合意していたのであり、
右の一審判決の言うクオリティオブライフの問題よりも、栄養状態の悪化、飢餓状態を招来しないようにすることが、当時の亡淑子にとっては重大課題であったのである(一審判決はその点事実誤認があるか、または、間違った規範をあてはめようとしていると言わざるを得ない)。
そして、少なくとも、右のクオリティオブライフを悪化させない範囲で、右治療目的を実現することは、一般血液検査をするだけで可能だったはずである。
4 アフェマは、一審判決も認めるとおり(七九頁)、「副作用としては、電解質代謝異常が指摘されており、ナトリウムの低下を引き起こす可能性がある。」とされる。
さらに、一審判決は右に続けて「ただし、このような副作用が生じることは統計上、きわめてまれである。」とするが、
アフェマにはナトリウムの低下を含め、その他、いかなる栄養状態に対する副作用が生じるか、その程度も十分に報告されていない新薬だったのであり、少なくとも血液検査により、その栄養状態に与える影響をフォローすることが不可欠であった。
5 右の状況を前提に、一審判決による、亡淑子の栄養管理についての被控訴人藤村の義務違反に関する判示を見ると、一審判決(八〇頁)は、まず、「栄養管理の怠慢について」
で、「原告(控訴人)は、被告(被控訴人)藤村医師らは亡淑子の血液検査、尿検査を怠ったため、亡淑子が低ナトリウム血症に陥っていることを把握していなかったと主張するが、(前
記一、三1で)認定した事実を総合すれば、仮に、被告(被控訴人)藤村医師が平成八年九月中に亡淑子の血液検査などを頻繁に行い、ある程度予想された低ナトリウム血症の数値
を具体的に把握していたとしても、亡淑子に中枢神経症状が出ていない以上、それを補正することはかえって亡淑子に無用な危険を与えるだけで、結局、検査して数値を把握してもそれを治療に生かすことができないのであるから、本件においてあえて検査をする意味は見いだし難いといわざるを得ない。
むしろ、血液検査などをすれば当然亡淑子はその数値を気にするであろうし、そうすれば当然悪い数値を亡淑子が目にしてさらに不安を増幅させる結果を招来するのは見やすい道理であり、このような検査の必要性と予想される悪影響等を比較 考量すれば、被告(被控訴人)藤村医師が血液検査等を行わなかったことは医師の判断として合理的なものであって、少なくとも医師の裁量を逸脱するものではなく、被告(被控訴人) 藤村医師に注意義務違反は認められない。」などとするが、これが評価の誤りであることは自明である。
すなわち、ナトリウム値だけでなく全体的な栄養状況の問題であるのに、右一審判決はその補正の危険だけを問題としており(かつ、前述のように、ナトリウム値の変化を知ることは重要であり、頻回に血液検査をすれば緊急補正の危険性を回避できるのである。)、また、後段の亡淑子の不安の増大、などは殆ど詭弁である。
一般血液検査であれば、入院患者であれば自然に受け入れるし、またその目的は栄養状態の管理なのであるから、むしろそれに従って輸液を変更したり、食事量を調整する等の積極的措置をすることでなんら不安なことはないはずである(むしろ、半年に二回しか一般血液検査をしないことの方が、すでに治療の方法もないのかと、患者の不安を増大させると言いうるであろう)。
6 次に、一審判決(八一頁)は、「フィジオゾール三号の漫然補液について」として、「原告(控訴人)は、被告(被控訴人)藤村医師がフィジオゾール三号を補液として利用したのは
不適切であり、高カロリー輸液やナトリウムを多く含んだ補液を利用すべきであったと主張する。
しかしながら、(前記一、三1で)認定した事実を総合すれば、亡淑子は、がんの再発が判明してから、抗がん剤による化学療法を行っていなかったこともあって、平成八年九月ころには、がんの増殖がすすんで明らかに末期がん患者となっていたものと認められるところ、
そのような末期がん患者の亡淑子に高カロリー輸液やナトリウムを多く含んだ輸液を投与すれば、亡淑子の延命にとってはほとんど意味がなく、むしろ全身に浮腫を生じさせて心不全を招く危険性もあり、さらに同人に耐え難い苦痛を与える可能性もあったことが認められるのであるから、かかる事情のもとで、被告(被控訴人)藤村医師が苦痛を緩和するという当初の 医療方針に則って、高カロリー輸液等を用いずにフィジオゾール三号補液を選択したことは医師の判断として合理的なものであって、少なくとも医師の裁量を逸脱するものではなく、被
告(被控訴人)藤村医師には注意義務違反は認められない。
また、原告(控訴人)は、尿量の検査もせずにフィジオゾール三号を一日五○○ミリリットルと決め、それを漫然と継続してい
たことは不適当である旨主張するが、(前記三1で)認定したとおり、たとえ五○○ミリリットル以上の補液をすることが可能であり、栄養上はその方がベターであるとしても、一日五○○
ミリリットル程度とする方が末期がん患者にとってより苦痛が少なくてすむ以上、総合的な見地から補液量を少量にとどめることは十分に合理性があるというべきである。
すなわち、このような末期がん患者における補液量の決定判断は、血液検査や尿量検査の結果に基づいて原則論的(機械的)に決せられるべき問題ではなく、末期がん患者の延命効果と苦痛緩和
の比較考量に基づく総合的な判断が要求されるのであって、医師の学識経験に基づく広範な裁量が認められるべきものであり、本件において一か月間フィジオゾール三号を毎日五○○ミリリットルずつ投与していたことについて、被告(被控訴人)藤村医師に右裁量の逸脱があるとは認められない。さらに、平成八年一○月四日に一○○○ミリリットルとしたことにつ いても、(前記一で)認定したとおり、その当時亡淑子の食事量が激減していたことや、翌日に東京までの移動が予定されていたことなどからして、補液量を一時的に増やすことも明らかに不合理であるとまではいえず、被告(被控訴人)藤村医師に右裁量の逸脱があるとは認められない。」などとするが、
おそらくこの部分は医学的に糾弾されうる点をいくつも含む判示であろう(この点は、専門医に照会中である)。
まず、右一審判決も認めるように、患者側が早期退院・別病院での治療を希望していたにもかかわらず「亡淑子が、がんの再発が判明してから、抗がん剤による化学療法を行っていなかったこともあって、平成八年九月ころには、がんの増殖がすすんで明らかに末期がん患者となっていた」こと自体、被控訴人らの最大の義務の違反結果であるが(つまり、延命と苦痛緩和をそもそも目的としていたのではないのである。)、それをいったん置くとしても、
本件の場合、少なくとも、転院を前提とした、胸水処置を行うためだけの入院なのであり、栄
養のコントロールが得に重要な課題だったのであるから、少なくとも発熱(平成八年四月以降)により栄養摂取量が減る蓋然性が高くなった時点で、血液検査や食餌量を見て、高カロリ
ー輸液(IVH。経静脈栄養法)をなすべきとの判断が必要であった余地が高い。
特に、右の判示部分の最後の部分の「平成八年一○月四日に一○○○ミリリットルとしたこと」こそ、新幹線での心停止の原因である低酸素状態、さらにその原因である低蛋白血症と相まっての)肺水腫の原因であると強く疑われるのであって(現在、専門医に照会中である。)、栄養管理義務違反を越えた重大な義務違反の疑いがあり、右一審判決が言うよう に、被控訴人藤村に裁量の逸脱があるとは認められない、とは到底言えないことである。
7 また、一審判決(八四頁)は、栄養管理義務違反に関連して「アフェマの投与」として「(前記一で)認定した事実によれば、亡淑子は平成八年一○月五日当時、低ナトリウム血症に陥っていたこと、同年八月五日には同人のナトリウム値は正常であったこと、アフェマの投与が開始されたのは同年五月二七日であること、アフェマの副作用としてナトリウムの低下を招くことは極めてまれであること、末期がん患者において低ナトリウム血症はよくある現象であることが認められる。以上の事実を総合すれば、アフェマの投与により亡淑子の低ナトリウム血症が生じたとか、アフェマの投与が亡淑子のナトリウム値に影響を及ぼしたとは到底認めることができない(なお、亡淑子の低ナトリウム血症が亡淑子の死因であったとか、又 は死期をはやめたという点(因果関係)についても、これを認めるに足りる十分な証拠はない。)」などとするが、右にも述べたように、
アフェマの副作用として低ナトリウムだけを取り上げ
ているが(逆にアフェマの副作用はそれだけとは確認されていないのである。)、ナトリウム値だけでなく全体的な栄養状況の問題であるのに、右一審判決はその点だけの問題としており、かつ、控訴人は低ナトリウムだけが死因であると言っているのではないから、右一審判決の判示が事実誤認ないし評価の誤りを含むものであることもまた言うまでもない。
8 さらに、一審判決(八八頁)は、「原告(控訴人)は、被告(被控訴人)藤村医師が、亡淑子にフェロミア(鉄剤)を投与したことにより、亡淑子は食欲不振を起こしたが、被告(被控訴人)藤村医師はそれに対して何らのフォローもしなかったと主張する。しかし、(前記一で)認定したとおり、亡淑子にフェロミアが投与されたのは平成八年八月七日からであるが、亡
淑子に目立った食欲不振が生じているのは同月下旬ころからであること、末期がん患者には食欲不振は通常よく見られる症状であることが認められ、これらの事実からすれば、フェロミアの副作用で亡淑子の食欲不振が起こったとまではいえず、ほかに亡淑子の食欲不振がフェロミアの副作用によるものであると認めるに足りる証拠もない。仮にフェロミアが食欲不振
に影響しているとしても、(前記一で)認定したとおり、被告(被控訴人)藤村医師は、その後直ちに(平成八年九月一日ころ)フェロミアの投与を中止しており、適切に対処している。また、原告(控訴人)は、フェロミアは相当長期にわたって服用しなければ効果がないのに、一ヶ月も満たない期間でその使用を打ち切ったと主張するが、(前記一で)認定したとおり、被
告(控訴人)藤村医師は、亡淑子が平成八年八月五日の血液検査の結果で、軽度の貧血を非常に気にしたため、あえてフェロミアを服用しなければならないほどの数値ではなかった
が、貧血の治療というよりもむしろ亡淑子の不安を除去する目的で、同月七日から、亡淑子にフェロミアの投与を開始したのであり、一か月にも満たない期間でその使用を打ち切ったか
らといって、当初の目的からすればそれは不適切な行為ではないというべきである。」とするが、
控訴人が問題視するのは、かかるフェロミアの投与にも見られる、被控訴人藤村の、本件の治療の目的たる、「胸水コントロール後、早期転院」に反し、かつその間の栄養管理も十分にしない治療行為そのものである。
後述のとおり、確かに、鉄性貧血の傾向が、平成八年八月五日の血液検査の結果に見られるが、これも、定期的に血液検査をしておれば、おそらくそれらとの比較検討により、
心配しないでよい値であることを、亡淑子に容易に説明できたはずである。
これを置くとしても、患者の求めに応じ、安易に、本件の入院の目的(体力をつけて早期退院)に反しかねない、食欲不振を招きやすいフェロミアを処方するまでの必要があったかも、検査の不足のためにはっきりとは言えない、という状況である。
つまり、被控訴人藤村の治療は、本件の入院の目的に照らし、為さざるべきことをなし(このフェロミアの処方も、後述のアフェマの使用もその現れである。)、為すべきことをなさない(多くの検査)、まったく目的性のない治療行為であると言わざるを得ない。
四 発熱に対応すべき義務の違反
1 本件治療行為の目的である、亡淑子の東京への早期転院を最初に困難にしたのが、平成八年四月半ば頃からの発熱である。
すなわちカルテよると、四月一四日三七・七度(乙二・三六頁)、五月九日三八・四度(乙二・四三頁)の記載があり、その間にも亡淑子にかなりの発熱があったことは、控訴人の
陳述書の記載からも認められるところである(甲二四・一四頁など)。
2 このうち、後者は平成八年五月七日のピシバニール使用による発熱である蓋然性が高いが、前者および後者とも、その他の可能性も否定できず、特に胸水治療が完了した右の時期には、できるだけ早期に、発熱に対応する必要が高かった。
そのためには、当然その原因を検索するための検査、例えば胸部レントゲン写真や、尿の検査(沈渣検査と培養検査)ぐらいはやるのが医学上の常識であり、かつ、これらの検査は患者に対する侵襲性もほとんどなく、極めて容易になしうるものでもある。
しかるに、被控訴人藤村は、これらの検査も行わないまま、漫然と、ボルタレンによる対処療法を行ったことを、控訴人は問題としているのである(これもまた、本件の治療の目的
に反する義務違反行為の一つである)。
3 この点につき、一審判決(九一頁)は、「原告(控訴人)は、被告(被控訴人)藤村医師らは、約二か月間もの間、亡淑子に熱が出た際、漫然とボルタレンの投与を行っており、亡
淑子の容態把握につとめたり、ピシバニール以外の原因を探った形跡が全くないと主張する。しかしながら、(前記一で)認定した事実に証拠(甲二一、乙二、一○、一五、被告藤村本
人)及び弁論の全趣旨を総合すれば、被告(控訴人)藤村医師らは、平成八年五月初旬から六月下旬まで、亡淑子に対し、ほとんど毎日のようにボルタレン座薬を使用したが、これは 亡淑子の希望によるものであったこと、ボルタレン座薬は亡淑子によく効き、ほぼかならず熱が下がった上、亡淑子自身もボルタレン座薬を入れると楽になると感じてその使用を好んだこと、ボルタレン座薬は、強力な鎮痛・解熱作用を有し、末期がん患者の苦痛緩和のために良く用いられるものであること、以上の事実が認められ、これらの事実を総合すると、亡淑子の発熱に対してボルタレンを投与していたことは同人の肉体的苦痛を緩和するのに効果的であったばかりでなく、精神的安定にも効果があったものということができ、その投与は適切であって何ら注意義務違反は認められない。
また、証拠(乙二、一○、被告藤村本人)及び弁論の全趣旨によれば、亡淑子には、軽度の風邪はともかく、感染症などピシバニール以外
の発熱原因が特にうかがわれなかったこと、発熱が生じているのはピシバニールが効いている証拠でもあり、その効果には個人差があって一か月以上続く者も珍しくはないことが認め
られ、亡淑子は自分にがんが再発したのではないかと疑っており、検査をすればその結果を気にしてさらに精神的に不安となるおそれが多分にあったことを考え併せると、被告(被控訴
人)藤村医師に発熱原因を探るための検査をすべき義務があったとはいえず、むしろ不要な検査をしなかったことは医師の判断として適切であったとさえいえるのであって、被告(被控
訴人)藤村医師に医師義務注意違反は認められない。また、ボルタレンは刺激が強く胃腸障害を起こすこともあるが、それゆえに座薬として投与されていたこと、ボルタレンを投与して
いる間ずっと亡淑子に食欲不振が生じているわけでもないことからすると、ボルタレンが亡淑子に食欲不振の副作用を引き起こしたとは認められず、これを認めるに足りる証拠もない。」 などとするが、
これが的をはずれた認定であることはもはや明白であろう。
患者が望んだら、他の原因も検索せず、通常用いられている薬剤を処方するというのでは、医師の仕事を行っているとは言い難いところであるが、特に、本件のように、まさに転院を目的としているにもかかわらず、その転院をなすべき好機に患者に発熱が生じているのなら、その原因を検索するようにつとめなければ、当事者間の契約に基づく注意義務違反の問題ともなると言うべきである。
五 ホルモン療法としてのアフェマの使用の問題点
1 この点は、一審判決が問題とするような、当該薬剤が「抗がん剤」であるかどうかの説明義務違反の問題(一審判決七六頁)、栄養管理義務違反の問題(一審判決八四頁)にだけにとどまらず、本剤の強い副作用の可能性のある(少なくとも、新薬であり、副作用情報も確立していない。)、および、効用書で慎重使用の注意があることからは、「抗がん剤」かどうか、ということではなく、
副作用により、退院が出来なくなるかの問題があるのであって、今回の入院の当初の目的、すなわち、「亡淑子の体力を維持して、東京の病院に転院させる」という目的(これは変更されていない。)に真っ向から反しかねない治療行為である可能性がある、という点が問題である。
従って、これを使用しようとする場合には、右の方針の変更もありうるのであるから、被控訴人藤村が右方針、および、亡淑子本人に告知しないことを同意している以上(というよ りむしろ非告知の方針は被控訴人藤村が決定したのである。)、その同意の相手である控訴人に説明し、同人の納得が得られるまでは、使用するべきではなかったのである。
そして、現に、その使用時期および当時の亡淑子の状況からは、強力ながん治療薬である当該薬剤により、栄養状態の悪化等の副作用が出た蓋然性が極めて高いのである。
2 しかも、仮にその治療が許されうるとしても、強力ながん治療薬であるアフェマ使用にあたっては、その使用の前後で病巣のレントゲン等を行い、病巣が小さくなっているかどうか、を判定すべきであり、また、副作用の早期発見に努めるための血液検査を行うなどし、必要最小限度の使用に止め、または、場合によってはその使用を停止しなければいけないの
に、これらの検査を一切なさず、必要以上の投与が為された蓋然性も高い。
3 さらに、胸水除去をしただけ時点では、本人が他の病院に出向けば(たとえ紹介状がなくても)、他院に入院が可能であるのに、積極的治療であるアフェマの使用が開始されてしまえば、(医師によってそれぞれの方針がありうるので、)もう引き継ぎたくないという医療機関が多いというのも医療界の通例であり、実際、本件においても、平成八年八月、亡淑子の状況が少し改善して、控訴人は転院先を探したが、右を理由に転院を拒絶されている。
被控訴人藤村が、当初の当事者間の合意内容と異なり、もし亡淑子の転院をあきらめて、積極的治療を開始しなければいけないと思ったのなら、当然ながら、直ちに患者側に連絡、相談すべきであった。
4 従って、右アフェマの無断使用は、「胸水をコントロールした上、転院して東京の病院で治療をうけさせる」という診療目的に真っ向から反する、かつ、前後での検査も行わないという、基礎的な注意義務違反にもあたると言わざるをえない。
六 検査をすべき義務の違反について
1 現在の医療は、検査→治療→検査(効果・副作用確認)→治療(追加、変更)→検査(効果・副作用確認)という繰り返しにより実施されるべきことが常識となっているのに、被控訴人藤村らによる治療は全くこの手順に従っていないと言わざるをえない。
これまでも、栄養管理義務、発熱への対応義務、の点において一部述べてきたが、本件においては、特に、絶対的に、必要な検査を施行すべき義務、およびその回数について不十
分であるという、注意義務違反があると言わざるをえない。
亡淑子の半年間に入院中に、ルーティンとして、栄養管理、発熱の原因検索、薬剤の副作用確認のために行われるべきであった、一般血液検査は、カルテ(乙二、甲八)によると、後述の二回にすぎず、その他の検査としても、平成八年三月二三日の胸水の細胞診についてはすでに触れているが、その他、同年三月二三日の細菌検査(陰性)、同年四月二〇
日と八月五日の二回の尿検査だけである。
これでは、右の現代の治療のあり方から言って、「胸水の処置をして、体力のあるうちに東京に転院、そこでの積極的治療」の達成を全く実行できない、目的のない医療に他ならないばかりか、端的に当事者間の診療契約上の義務に違反する医療行為であるとの蓋然性は極めて高い言わざるを得ない。
2 本件入院中に行われた、たった二回の血液検査について
本件に即して言うと、低ナトリウム血症の回避、無理のない輸液により最低限の栄養状態が保たれているか、また、アフェマにより栄養状態に対する悪影響は出ていないか、その他の栄養状態の管理は、少なくとも、一般血液検査によって、低蛋白(低アルブミン)や、貧血(赤血球数、ヘモグロビン値、ヘマトクリット値)を見ることだけで、容易に観察しえ、現に、左記のように、本件病院ないし外部オーダー(と思われる)によりなされている血液検査のオーダー項目にもこれらの項目は含まれている。
ただ、縷々述べてきたように、惜しむらくは、カルテ(甲八、乙二)によると、一般血液検査は、今回の入院中に二回しかなされておらず、しかも、以下に述べるように、その少ない検査回数からでもすでに貧血状態(栄養状態不良)である可能性が疑われるのにも関わらず、適切な措置が全くなされていないことである(これは、一般血液検査の回数が少なすぎ、対比的 確認ができなかったことに由来するものと言わざるをえない)。
すなわち、
(一) 平成八年四月三〇日付け一般血液検査 (院内の血液検査と思われる)
白血球 九.三(千個/立方ミリ)→高い
赤血球 三.九一(百万個/立方ミリ)
→正常値内だがかなり低い
血色素(ヘモグロビン) 一二.〇(g/dl)
→正常値内だがかなり低い
ヘマトクリット 三五.三(%)
→正常値内だがかなり低い
MCV(→平均赤血球容積) 九二.七(μ3) →正常値内
MCH(→平均赤血球血色素量) 30.6(Pg)→正常値内
MCHC(→血平均赤血球色素濃度) 33.1(%) →正常値内
血小板 四一四(千個/立方ミリ) →高い
好中球セグ 六三.九% →高い
好酸求 二.二% →正常値内
リンパ球 二五.九% →低い
単球 七.七% →高い
(外部オーダー分。乙二でははっきりしない)
総蛋白 六.四 !マーク→正常値内だが低い
アルブミン 三.五 !マーク→低い
A/G比 一.二 →正常値内だが低い
LDH 三三五 →高い
AST(GOT) 一七 →正常値内
ALT(GPT) 七 →正常値内
γーGPT 一〇 →正常値内
AlーP 一二三 →正常値内
総ピリルビン 〇.三 →正常値内
中性脂肪 一五六 !マーク→高い
総コレステロール 一七三 →正常値内
グルコース(血漿) 九二 →正常値内
リパーゼ 六 →正常値内
血清アミラーゼ 八七 →正常値内
BUN 一〇 →正常値内
クレアチニン 〇.八 →正常値内
尿酸 〇.八 !マーク→低い
Na 一四一 →正常値内
Cl 一〇一 →正常値内
K 四.六 →正常値
(赤血球、ヘモグロビン値、ヘマトクリット値、総蛋白、アルブミン値で、すでに貧血、栄養不良の傾向が出ている。ナトリウム、カリウム値は右の段階では正常であるが、簡単な
一般血液検査でフォローできるのであれば、その重要性に鑑み、もっと頻回に血液検査を行うべきであった。)
(二) 平成八年八月五日付け一般血液検査
(院内の血液検査)
白血球 七.八(千個/立方ミリ) →正常値内
赤血球 三.四二(百万個/立方ミリ) →低い
血色素(ヘモグロビン) 九.五(g/dl)→低い
ヘマトクリット 二八.九(%) →かなり低い
MCV(→平均赤血球容積) 八四.五(μ3) →低い
MCH(→平均赤血球血色素量) 二七.八(Pg) →低い
MCHC(→血平均赤血球色素濃度) 三二.九(%) →正常値内
血小板 四八一(千個/立方ミリ) →高い?
好中球セグ 六四.四% →高い
好酸求 〇.六% →かなり低い
リンパ球 二六.九% →低い
単球 七.七% →高い
(外部オーダー分)
総蛋白 七.一 →正常値内だが低い
アルブミン 三.七 !マーク→低い
A/G比 一.二 →正常値内だが低い
LDH 二六〇 →高い
AST(GOT) 一八 →正常値内
ALT(GPT) 八 →正常値内
γーGPT 一四 →正常値内
AlーP 一四三 →正常値内
総ピリルビン @ 〇.三 →正常値内
中性脂肪 八五 →正常値内
総コレステロール 一六〇 →正常値内
グルコース(血漿) 八七 →正常値内
リパーゼ 一二 →正常値内
血清アミラーゼ 一〇三 →正常値内
BUN 一一 →正常値内
クレアチニン 一.〇 →正常値内
尿酸 一.〇 !マーク→低い
Na 一三九 →正常値内
Cl 九八 →正常値内
K 四.五 →正常値内
(赤血球数、ヘモグロビン値、ヘマトクリット値から、すでに貧血の状態であると言いうる。また、ヘモグロビン値、MCV、MCHなどの鉄欠乏貧血の指数は低いが、MCHCはそう低くな
く、鉄だけの欠乏ということではないと思われる。)
右のように、貧血状態など一応のことは伺えるのであるが、いかんせん回数が少なすぎ、確定的な判断に至ることはできないと言うべきである(なお、前述のように、亡淑子は鉄欠乏を気にしたため、フェロミアを処方した、などのことがあるが、かかる回数の血液検査だけでは鉄欠乏は判断しえず、これも血液検査の回数が少なすぎ、かえって亡淑子がその結果を重用視しすぎたためとも思われる。比較材料があればそのようなことにもならなかったはずである)。
七 以上見てきたとおり、被控訴人藤村による亡淑子に対する「治療行為」は、一審判決が争点とした部分以上に多くの問題点、注意義務違反を含むものであり、一審判決(一〇〇 頁)が言うように、「極めて誠実に医療行為を行っていたもの」であるなどとは到底言えないものである。
すなわち、一審判決(一〇〇頁)は、「(しかし、)被告(被控訴人)藤村医師をはじめ本件病院で亡淑子の入院にかかわった者が、亡淑子をいい加減に扱ったなどという事実を認めるに足りる証拠はなく、むしろ、これまで述べてきたところからすれば、被告(被控訴人)藤村医師らは亡淑子の精神的不安、苦痛をできるだけ除去しようという見地から、極めて誠実に
医療行為を行っていたものであって、なんら非難されるような事実は認められない。仮に亡淑子が、がんの再発を疑って被告(被控訴人)藤村医師らに疑問を投げかけても、十分な説明
がなされないとして不満に思っていたことがあったとしても、がん再発の告知をしないという方針のもとでは、ある程度説明が曖昧になってしまうことはやむを得ないことであり(がん再発
の告知をしないという方針は、原告(控訴人)自身も同意したものである。)、また積極的な治療ができない以上検査が控えめになるのもやむを得ないのであって(抗がん剤による化学
療法を用いずにもっぱら苦痛緩和の治療だけをしてほしいというのは、まさしく原告(控訴人)の意向である。)、これをもって被告(控訴人)藤村医師らの医療行為が不誠実であるなどということはできない。」などとする。
控訴人も、本件病院で亡淑子の入院にかかわった者がすべて不誠実かつ義務違反行為を行ったというのではない。
むしろ、カルテ(甲八、乙二)に付随する看護記録の記載を見ると、担当の看護婦は、亡淑子の状況を水準以上に観察・記載し、これはなんとか主治医に伝えようとしているとも伺える。
しかしながら、被控訴人藤村はそれにもかかわらず前述のとおりの、本件診療契約の趣旨に反する治療行為に終始し、看護婦に処置を指示することも殆どなかったのである(実際、本件カルテにおける指示簿には、看護婦に対する指示の記載が殆ど見あたらない)。
さらに、これまで縷々述べてきたところから、右一審判決のいうように「(被控訴人藤村が)極めて誠実に医療行為を行っていたものであって、なんら非難されるような事実は認められない」などということは決してないと言うべきである。
それに続く、抗がん剤治療を用いない治療法(なお、控訴人が「もっぱら苦痛緩和の治療」を求めた、というのは事実誤認であり、控訴人が求めたのは「胸水のコントロールをしてか
ら、早期退院させること」である。)、本人の不告知による治療は、(後者はむしろ被控訴人藤村からの誘導であるが、少なくとも)医療の専門家たる被控訴人藤村もこれを了解して、合意していたことであるから、これを不十分な治療の言い訳にすることは、決して出来ないはずである(そもそも、前述のとおり、この方針は被控訴人藤村が誘導したものである)。
本件のような被控訴人藤村の義務違反行為を追認する一審判決が維持されるようなことがあると、救われない(なかった)者としては、亡淑子および控訴人だけでなく、現に被控
訴人藤村の指示で医療行為を行わざるを得ない、本件病院の心あるスタッフも含まれるのかもしれない。
一 右義務に関する前提たる事実についての、一審判決の事実誤認および経験則違背
1 被控訴人藤村は、最終の診察を終えた時点において、低ナトリウム血症や呼吸困難により、東京への移動中、亡淑子に心停止などの重大な危険が生じることを十分に予測していたのであり、被控訴人藤村には遅くとも平成八年一〇月四日の時点で、また、その場に居合わせた医師及び看護婦らには遅くとも同年一〇月五日の時点で、亡淑子の退院を止めるべき義務が存していた。
2 一審判決は誤った事実をもとにして、「被控訴人藤村が、最終の診察を終えた時点において、低ナトリウム血症や呼吸困難により、東京への移動中、亡淑子に心停止などの重
大な危険が生じることを予測することは困難であったというべきであり」という認定をしている(九八頁)が、次のような被控訴人藤村及び北田医師の供述からすると、被控訴人藤村は、
最終の診察を終えた時点において、亡淑子に重大な危険が生じることを予測していたことは明らかである。この点の一審判決の事実誤認・評価の誤りは著しいと言わねばならない。
被控訴人藤村は、平成八年一〇月頃を、亡淑子の最期の時と認識していた。
被控訴人藤村尋問調書二七頁ないし二九頁によると、「私(被控訴人藤村)が原告(控訴人)と初対面した平成八年四月五日の時点で、亡淑子の余命は、胸水の治療がうまく いった場合で、ただし抗がん剤治療をやらない場合は、あと半年くらいが限界ではないかと思っていました。」「胸水の再貯留の防止の治療がうまくいっても、年末までは難しいのでは
ないかというふうには予後を伝えております。」となっている。
そして、同年一〇月の時点においても、被控訴人藤村は、亡淑子の容態について「がん末期すなわち延命措置を一生懸命講じても仕方がない状態にあった」「既に延命措置が 無効であるターミナル後期の状態であった。」と認識していた(被控訴人藤村尋問調書二二六頁・二二七頁七行目)。
さらに、被控訴人藤村は、当時亡淑子が低ナトリウム血症に陥っていたことを十分に認識していた。
すなわち、「患者さんの状態を診れば、末期にだんだんなれば、ターミナルの後期になれば、もう当然低ナトリウム血症になりますので、それで輸液もやや控えめにしてましたから、当然それは予測しておりました、退院のずっと前から。」(被控訴人藤村尋問調書二一八頁八行目から一四行目)とし、特に、同頁三行目から七行目によれば、被控訴人藤村は、
当時亡淑子の状態を診る限り、一一六メック(甲九号証)という異常な低ナトリウム値にあったとしても不思議ではないなと思っていたのである(「患者の状態診てますので、その程度はあっても不思議ではないなと思ってます。」)。
控訴人代理人の「意識障害といいますか、心停止が起こるような状態でもあったということは、ある程度予測できたんですか。」(被控訴人藤村尋問調書二一八頁八行目)、「端的に、心停止を起こすということまである程度予測はされましたか。意識障害と心停止が、起こしてもおかしくないだろうなというような予測はありましたか、患者の状態を診て。」(同尋
問調書同頁一五行目)という質問に対し、被控訴人藤村は、その危険性を予測していたことを明確に認めている(同尋問調書二一九頁一行目から七行目。特に、同頁五行目から七行目、控訴人代理人の「搬送に対する不安ということは、そういうことはある程度、危険性というのは予測していたわけですか。」という質問に対し、被控訴人藤村の「そうです。」という回答。)。
被控訴人藤村は、退院前日である平成八年一〇月四日において、亡淑子の大阪から東京への搬送に対する不安を有していたのである(同尋問調書二一六頁九行目・同二一
九頁三行目)。
すなわち、「大阪から東京という搬送をしなければ、もう少しもった可能性はあります。」「搬送したことは結果的にまずかったんじゃないかと思います。」と認めている(被控訴人藤
村尋問調書二三〇頁)。
さらに、主治医でない北田医師でも、「移動するに際しての危険性、倒れてしまう、呼吸困難に陥ってしまうという危険性」を感じており、移動がなかったとしても既に当時の亡淑子において、倒れる危険性や呼吸困難に陥る危険性が存在し、亡淑子の容態に注意が必要であったことを認めている(北田尋問調書三九頁)。
以上の事実からすれば、被控訴人藤村が、最終の診察を終えた時点において、低ナトリウム血症や呼吸困難により、東京への移動中、亡淑子に心停止などの重大な危険が生じることを予測していたことは明らかであり、この予測は困難であったと判示す一審判決には明らかに誤認がある。どのように考えても、予測が困難であったと判示することはできないはずである。
3 一審判決は、被控訴人藤村が亡淑子に重大な危険が生じることを予測することは困難であったという認定を導く理由として、(1)退院の前日まで、緊急に補正すべきような低ナトリウム血症をうかがわせる症状はなかったこと、(2)呼吸困難はあるものの数日前から同じような状態で、退院前日も自力で歩行できていたこと、(3)平成八年一〇月五日は、被控訴人藤村が本件病院に出勤するまでに亡淑子が退院してしまっていたため、診察することができなかったことを挙げている。
しかしながら、右(1)の事実の認定は全くの誤認である。
一審判決は、「(前記一で認定した)事実によれば、亡淑子は、退院の前日まで、緊急に補正すべきような低ナトリウム血症をうかがわせる症状はなかったのであり」と判示する (一審判決九七頁七行目)が、その「前記一、3、(三)、(3)」においては、「亡淑子の食事量は、平成八年一〇月二日以降、激減した。被告(被控訴人)藤村医師は、フィジオゾール三
号の投与は一日当たり五〇〇ミリリットルを限度としていたが、退院前日の同年一〇月四日だけは、亡淑子に対し、フィジオゾール三号を一〇〇〇ミリリットル投与した。」と認定している(一審判決五二頁)。
すなわち、一審判決が言うところの「総合的な判断」により、フィジオゾール三号の補液が(平成八年九月一日から)約一ヶ月間、一日五〇〇ミリリットルとされていた状況において(同三、1並びに三、2、(一)及び(二)・七六頁から八四頁)、突如として平成八年一〇月四日に至って、被控訴人藤村が、その総合的な判断によって、急遽一日一〇〇〇ミリリットルの補液を行ったのである。それすなわち、「緊急に補正すべきような低ナトリウム血症をうかがわせる症状」が亡淑子に表れたに他ならない。
一審判決九七頁七行目の「退院の前日まで、緊急に補正すべきような低ナトリウム血症をうかがわせる症状はなかったのであり」という認定は明らかに矛盾し、誤っている。
右(2)についても、確かに退院数日前からは同じような呼吸困難な状態が続いているが、変化がないことをもって、重大な危険の予測が困難であったとすることはできない。
たとえば、絶対的に何らかの処置が必要な呼吸困難な状態である場合、そのようなひどい状態が同じように継続しているからといって、今後の重大な危険を予測することが困難になるわけがない。
四〇度の熱が三・四日続いている場合に、変化がないから、今後の重大な危険が予測できないなどとは言えないことは明白である。
四〇度の熱が数日続いたことをもって、今後の重大な危険に対してさらなる注意をしなければならないのである。
呼吸困難であること自体をもって、亡淑子の容態には十分な注意が必要なのであり、被控訴人藤村は、重大な危険
を予測することに努めて、適切な措置を講じなければならないのである。
さらに、退院直前の数日間においては同じ状態であったのかもしれないが、もう少し長いスパンで見ると、九月二五日頃から呼吸困難が増幅してきたような状況なのである(被控 訴人藤村尋問調書八〇頁一四行。一審判決も五六頁において「亡淑子は、平成八年九月末ころから、頻繁に呼吸困難を訴えるようになり」と認定している。
確実に、この同年九月末日ころから、亡淑子の呼吸困難は悪化してきたのだった。
たまたまこの悪化状態が、退院直前の数日間続いていただけである。これは悪い状態であって、決して被控訴人藤村が亡淑子の重大な危険を予測することができなかったという抗弁に利用されるべきものではない。
また、一審判決は退院前日も亡淑子が自力で歩行できていたことをも、被控訴人藤村が亡淑子に重大な危険が生じることを予測することが困難であった理由に用いている。
しかし、既に述べたとおりの被控訴人藤村の供述からすれば、退院前日に自力歩行が可能であったことが、被控訴人藤村が亡淑子に重大な危険が生じることを予測できないことの理由には全くならない。
そもそも退院前日に自力歩行が可能だといっても、翌日の退院日には、亡淑子は車椅子での移動を余儀なくされているような状態であったこと(一審判決六二頁六行
目)、延命措置を一生懸命講じても仕方がないような状態すなわちがん末期の後期イコール重大な危険が生じることが明らかな状態であっても自力歩行は可能であること(被控訴人藤
村尋問調書二二五頁一二行目から同二二七頁七行目)からすれば、退院前日に自力歩行が可能との一事をもって被控訴人藤村が亡淑子に重大な危険が生じることを予測することは困難であったと導くことには著しい経験則違反が存する
右(3)については、全く不可解であると言わざるをえない。
右に述べた事実からすると、被控訴人藤村は、遅くとも平成八年一〇月四日の時点で、亡淑子に重大な危険が生じることを十分に予測していたのであり、にもかかわらず、同年一〇月五日において被控訴人藤村と亡淑子が顔を合わせていない一事をもって、被控訴人藤村が亡淑子に重大な危険が生じることを予測することは困難であったという認定の理由に用いることは甚だしく論理性に欠ける。一審判決は、右に述べた被控訴人藤村の供述をもとにしてもなお平成八年一〇月五日まで、被控訴人藤村は亡淑子に重大な危険が生じることを予測することは全く困難であったというのであろうか。
さらに、被控訴人藤村は、平成八年九月二〇日頃には、控訴人らが同年一〇月五日の朝に出発することを知っていた(被控訴人藤村尋問調書二一二頁五行目・同二一三頁一
二行目、乙第九号証「大野婦長に宛てた手紙」)。
にもかかわらず、被控訴人藤村が出勤する前に控訴人らが退院してしまっていたことを理由に、被控訴人藤村の重大な危険の予測困難性を基礎付けることは経験則に著しく反する。
4 以上のとおり、被控訴人藤村は、最終の診察を終えた時点(遅くとも平成八年一〇月四日)において、低ナトリウム血症や呼吸困難により、東京への移動中、亡淑子に心停止な
どの重大な危険が生じることを十分に予測していた。この事実に反する一審判決の認定には誤認や著しい経験則違反が存する。
二 被控訴人藤村並びにその場に居合わせた医師及び看護婦の、亡淑子の退院を止めるべき義務の存否について
1 右のとおり、被控訴人藤村は、最終の診察を終えた時点(遅くとも平成八年一〇月四日)において、(1)控訴人代理人の「意識障害といいますか、心停止が起こるような状態でも
あったということは、ある程度予測できたんですか。」(被控訴人藤村尋問調書二一八頁八行目)、「端的に、心停止を起こすということまである程度予測はされましたか。意識障害と心 停止が、起こしてもおかしくないだろうなというような予測はありましたか、患者の状態を診て。」(同尋問調書同頁一五行目)という質問に対し、被控訴人藤村は、その危険性を予測していたことを明確に認めていること(同尋問調書二一九頁一行目から七行目。
特に、同頁五行目から七行目、控訴人代理人の「搬送に対する不安ということは、そういうことはある程度、危険性というのは予測していたわけですか。」という質問に対し、被控訴人藤村の「そうです。」という回答。)、(2)被控訴人藤村は、退院前日である平成八年一〇月四日において、 亡淑子の大阪から東京への搬送に対する不安を有していたこと(同尋問調書二一六頁九行目・同二一九頁三行目)、(3)「大阪から東京という搬送をしなければ、もう少しもった可能性 はあります。」「搬送したことは結果的にまずかったんじゃないかと思います。」と認めている(被控訴人藤村尋問調書二三〇頁)ことを併せて考えれば、被控訴人藤村には遅くても平成 八年一〇月四日の時点で、その場に居合わせた医師及び看護婦には同年一〇月五日の時点で、亡淑子の退院を止めるべき義務が存していたことは明らかである。
2 この点、一審判決は(1)控訴人が東京の知り合いの医師に付き添いを依頼していたこと、(2)亡淑子の唯一の家族である控訴人が東京への転院を入院当初から強く希望していた
ことをもって、被控訴人藤村に亡淑子の退院を止めるべき義務があったとはいえないとし、ⅰ亡淑子は退院当日も自力でトイレに行くなどしており、一見して重篤な症状には陥っていな
かったこと、ⅱ付き添いのI下医師も東京への移動を反対することはおろか、特に躊躇したようにもみられないこと、ⅲ控訴人自身ももう少し待って被控訴人藤村の診察を受けてからに
しようとは考えていないことからすれば、(3)I下医師や控訴人が亡淑子の移動に伴う特段の危険性を認識していなかったことは明らかであり(仮に、特段の危険性を認識しつつ転院を
敢行したのであれば、それは控訴人とI下医師の責任の範疇というべきものである。)、このような(3)の状況の下では、その場に居合わせた医師や看護婦に退院を止めるべき義務があったとは到底いえないと判示する。
3 しかしながら、右(1)及び(3)の事実をもって、被控訴人藤村の退院を止めるべき義務を否定する理由とすることはできない。
控訴人が知り合いの医師を付添い人として連れて来たり、兼ねてより東京への転院を希望していたとしても、被控訴人藤村は、遅くとも平成八年一〇月四日の時点で、低ナトリ
ウム血症や呼吸困難により、東京への移動中、亡淑子に心停止などの重大な危険が生じることを十分に予測し、平成八年九月二〇日頃には、控訴人らが同年一〇月五日の朝に出
発することを知っていた(被控訴人藤村尋問調書二一二頁五行目・同二一三頁一二行目)いたのであるから、少なくとも同年一〇月四日の時点で、亡淑子の退院を止めるべきであったのであり、仮に控訴人及び亡淑子の転院の意思が頑なに強かったのであれば、一審判決が認定しているように、同年一〇月四日、被控訴人藤村が控訴人に対して説明をした機会に
おいて(一審判決五五頁)、少なくとも転院における危険性について十分な説明をすべきであった。
右(1)及び(2)の事実は、同年一〇月四日において、亡淑子の退院を止めるべき義務を否定する理由には全くならないが、百歩譲ってそのような理由になるにしても、同日に転院の危険性を説明すべき義務までも否定するものでは決してない。何らかの理由で、このような状況下であっても転院を敢行する場合には、主治医たる被控訴人藤村は、控訴人らに対して、十分な注意を施すべきである。
一審判決は右(3)ⅲのように、既に同年一〇月五日において、控訴人らは被控訴人藤村と会うことなく転院を敢行したことを、控訴人らの不利益な事情に勘案している嫌いがあるが、被控訴人藤村医師は、控訴人らに対して、同年一〇月四日には転院のリスクを説明できる機会があり、その機会に説明をしなければならなかったのである。
被控訴人藤村も「そういう場合はもう、リスクの説明をして、あと、できるだけ輸送が安全にできるようにというような配慮を致します。」「寝台車の準備だとか、あと酸素を貸し出したりとか、点滴をそのまま持たせて帰るとか」と供述している(被控訴人藤村尋問調書八五頁九行目から同八六頁六行目まで。)。このような配慮を、同年一〇月四日の時点ですべきであったのである。
事実、退院(転院)当日の朝、亡淑子に対して診察が必要であったことを被控訴人藤村本人も認めている(被控訴人藤村尋問調書二一四頁一行目「退院時のそういう判断というのは、その退院時の状態を診てからいろんなことを言わないといけませんし。」)。
被控訴人藤村はこの点に関し、ア)I下医師が付き添いで来られていたこと、イ)何か注意を与えよう
にも自らが出勤したときには既に退院して控訴人らが居なかったことをもって、診察・注意ができなかった言い訳をし続けているが(被控訴人藤村尋問調書二一二頁一三行目から同二
一五頁)、I下医師が付き添いで来られても、被控訴人藤村からI下医師へ何も引継ぎをしていない以上(同二一三頁七行目)、被控訴人藤村の責任が減免されるものでないことは
明らかであるし、遅くても平成八年一〇月四日の時点では、翌日の退院におけるリスクや酸素の準備等について何らかの注意・説明ができたのであるから、「言う暇がなかったです。
(被控訴人藤村が同年一〇月五日朝に本件病院へ)行ったときに(控訴人らは)いらっしゃらなかったんで。」(被控訴人藤村尋問調書二一三頁一〇行目)ということは、被控訴人藤村の平成八年一〇月四日における亡淑子の退院を止めるべき義務及び退院に際して退院のリスクや準備等について注意・説明をすべき義務を否定する理由には全くならない。一審判決は著しく経験則に反する。
右(3)に関するⅰについて、亡淑子が退院当日自力でトイレに行ったことをもって一見して重篤な状態ではなかったと認定することには、明らかな事実誤認、経験則違反が存する。
退院当日、亡淑子は車椅子での移動を余儀なくされているような状態であったこと(一審判決六二頁六行目)、延命措置を一生懸命講じても仕方がないような状態すなわちがん末
期の後期イコール重大な危険が生じることが明らかな状態であっても自力歩行は可能であること(被控訴人藤村尋問調書二二五頁一二行目から同二二七頁七行目)からすれば、退院
当日に自力でトイレに行ったことの一事をもって、亡淑子が一見して重篤な症状には陥っていなかったと認定することは早計に過ぎる。重篤な症状に陥っているかどうかは別として、少
なくとも、既に述べた被控訴人藤村の認識からすれば、亡淑子の退院を止めるべき、また退院が行われるにしても、少なくとも退院のリスクを説明すべき義務が存することには変わりない。
同じくⅱについては、付添い人のI下医師は亡淑子の退院当日に亡淑子と初めて対面したのであり、医学的所見を述べることができるような状態ではなかったこと(控訴人尋問
調書一七頁九行目)、I下医師は被控訴人らより亡淑子について何らの情報も与えられていなかったこと(被控訴人藤村尋問調書二一三頁七行目、控訴人尋問調書一七頁四行目、
同八三頁一四行目から八四頁二行目まで)からすれば、退院当日において、付添い人のI下医師が東京への移動を反対することや特に躊躇することなどを期待することは不可能である。
I下医師が石川看護婦に対して「この患者さん(亡淑子)は起座呼吸がいいんですか。」と(呼吸困難を緩和するための)医学的には基本中の基本である質問を行ったが、石川看護婦はその意味すらも分からなかったような状態である(控訴人尋問調書八四頁三行目)。
ⅲについては、本件訴訟の大テーマである控訴人と被控訴人のコミュニケーションの欠如より、午前八時五四分の新幹線で移動することが決まっていた退院当日、もはや控訴人に被控訴人藤村医師の診察を受けてから退院しようという気持ちを期待することは不可能である。
一審判決は、このような(1)、(2)、(3)の事実をもとにして、(3)I下医師や控訴人が亡淑子の移動に伴う特段の危険性を認識していなかったことを認定し、その事実よりその場に居合わせた医師や看護婦に退院を止めるべき義務があったとは到底いえないと判示する。
しかしながら、I下医師や控訴人が特段の危険性を認識していたか否かは、被控訴人らの危険性の認識に影響することはない。被控訴人藤村が、亡淑子に重大な危険が生じ
ることを予測していたことは、既に述べたとおりであるから、I下医師や控訴人の危険性の認識の欠如をもって、その場に居合わせた医師や看護婦の退院を止めさせるべき義務を免除する理由は全くない。
主治医である被控訴人藤村は、退院当日I下医師が付き添いで来ることを事前に知っており(被控訴人藤村尋問調書二一三頁二行目)、退院日も知っていたの
であるから(同調書二一一頁一三行目)、亡淑子に重大な危険が生じることを予測している以上、きちんとI下医師に対して引継ぎの打ち合わせ等をすることが必要不可欠である。
転医させる場合の転医先への情報提供義務のようなものである(岡山地判・昭和五七年一〇月四日、判例時報一〇八〇号一二一頁)。にもかかわらず、被控訴人藤村はI下医師に対して、何らの情報提供も行っていない(被控訴人藤村尋問調書二一三頁七行目)。
退院(転院)当日の朝、亡淑子に対して診察が必要であったことを被控訴人藤村本人も認めている(被控訴人藤村尋問調書二一四頁一行目「退院時のそういう判断というのは、 その退院時の状態を診てからいろんなことを言わないといけませんし。」)。被控訴人藤村は自らの情報提供義務を棚に上げて、「要するに付き添っていかれるんですから、何かあった
場合その先生が処置されるわけですから」(被控訴人藤村尋問調書二一三頁四行目)「それは付き添いのドクターが来られて、その判断でもって退院をさせられているわけですから。」 (同尋問調書二一四頁一三行目)などと、まるでI下医師が主治医の責任を負うような言い逃れをしている。
控訴人らに付き添いの医師がいたとしても、そのことをもって、被控訴人らは主治医たる責任を逃れることはできないはずである。
以上からすると、I下医師の存在を、被控訴人らの退院を止めるべき義務を否定する理由に用いることは、著しく経験則に違反する。
4 また、退院直前の深夜において、当直の北田医師が、亡淑子の呼吸困難の訴えに対して対処し、「移動するに際しての危険性、倒れてしまう、呼吸困難に陥ってしまうという危険性」を感じており、移動がなかったとしても既に当時の亡淑子において、倒れる危険性や呼吸困難に陥る危険性が存在し、亡淑子の容態に注意が必要であったことを認めている(北田尋問調書三九頁)ような状況であったこと、看護婦も立ち会っていたこと、退院の前日において被控訴人藤村は低ナトリウム血症や呼吸困難により、東京への移動中、亡淑子に心停止などの重大な危険が生じることを十分に予測し、被控訴人会社は平成八年九月二〇日頃には、控訴人らが同年一〇月五日の朝に出発することを知っていた(被控訴人藤村尋問調
書二一二頁五行目・同二一三頁一二行目、乙第九号証「大野婦長に宛てた手紙」)ことからすれば、被控訴人藤村が退院時に居合わせなくとも、被控訴人会社においては、何らかの
形で、控訴人らの退院を止めるべきであったのであり、控訴人らとの関係で退院を止めることができなかったのであれば、被控訴人会社は控訴人らに対して退院のリスクをきっちりと説
明し、しかるべき配慮をすべきであった。控訴人らがタクシーに乗って本件病院を出ていくところを見送った(一審判決六二頁)など言語同断である。
5 以上述べてきたところからは、被控訴人藤村並びにその場に居合わせた被控訴人会社の医師及び看護婦に、亡淑子の退院を止めるべき義務を全く認めず、退院の際のリスク説明やしかるべき配慮義務を全く認めない一審判決には著しい経験則違反がある。
被控訴人らのとった行動は、「がん末期すなわち延命措置を一生懸命講じても仕方がない状態にあった」「既に延命措置が無効であるターミナル後期の状態であった」(被控訴 人藤村尋問調書二二六頁・二二七頁七行目)患者に対する医療従事者の行動とはとても思えないものである。
三 退院の際の不十分な注意・説明について
1 一審判決には、誤った事実認定と評価によって、平成八年一〇月四日の時点において、被控訴人藤村が亡淑子に重大な危険が生じることを予測することは困難であったと判示し、退院時の被控訴人らの注意義務・説明義務について一切の審理を行っていない。明らかな審理不尽である。
なぜなら、平成八年一〇月四日の時点において被控訴人藤村が亡淑子に重大な危険が生じることを予測していたことは既に述べたとおり明らかであるのであるから、一審判決が判示するように「それに応じた注意・説明が必要とされる」のであり、この点の審理が不可欠であるからである。
2 被控訴人らは、同年一〇月五日朝に亡淑子が退院(転院)し、しかも新幹線によって東京へ移動することを知っていながら、控訴人らに何らかの注意を与えるどころか、
さらに驚くべきことに、「酸素補給の用意」について、登山用(携帯用)酸素の持参を指示している。
大野婦長陳述書(乙一一号証)六頁一行目から五行目には、「東京への移動について車椅子の借用と酸素の携帯について尋ねられました。そこで私は酸素については被告(被
控訴人)藤村医師に確認し、『念のため持参して下さい。』ということだったので、その旨を折り返し電話連絡し、購入先や本数についても登山用品を扱っているところで購入できること、 念のため二本は必ず持参してもらうことなど説明しました。」とある(一審判決五四頁)。
被控訴人藤村陳述書(乙一〇号証)一〇頁一〇行目には、「その後間もなく婦長より、一〇月五日に聖路加病院への転院が決まり、その際東京までの移動には控訴人の知り
合いの医師が付き添うと控訴人からの連絡が入り、さらにその際には酸素が必要かどうか尋ねて来ているということであったので、私は携帯酸素が必要なので必ず用意するよう控訴 人に伝えるよう婦長に指示いたしました。」とあり、同じく被控訴人藤村陳述書一一頁一三行目には、「一〇月に入り呼吸困難が強くなり患者輸送の心配をしていましたが、一〇月四日
夕方ナースステーションにて控訴人と会い、携帯酸素の用意を確認し」とある。
被控訴人藤村は、大野婦長からの尋ねに対し、どのような酸素を用意すべきか一切の指示を出していない(被控訴人藤村尋問調書二〇九頁四行目)。
さらに被控訴人藤村は、 「携帯用の酸素には詳しくない。」「登山用の酸素というものを見たことがないので(控訴人らが東京まで移動する際の念のための酸素として)十分かどうか分からない。」「控訴人らが 用意した酸素が一本八リットルしか入っていないことは知らない。」「控訴人らが用意した酸素というものの現物は確認していない。」とまで言っている(被控訴人藤村尋問調書二〇九
頁・二一〇頁)。
さすがに登山用の酸素ではまずいと思ったのか、「現物は確認していない。」と述べ、さらに「ボンベ」というものの貸し出しをほのめかしたが(同尋問調書二一〇頁九行 目)、そもそも控訴人がどのような酸素を用意していたのか確認していないこと自体が医師として明らかに失格であり、また明確に携帯酸素の用意を確認したとする陳述書(乙一〇号証
一一頁一三行目)に矛盾する。
乙一〇号証が作成されたのは平成一一年六月頃であり、その頃は、「しっかりと携帯用酸素の確認もした」という主張を展開する方針だったのであろう
が、今般その携帯用酸素が登山用酸素であったというあまりにも信じられない出来事に直面して、急遽大野婦長へ責任転嫁すべく、「自らは現物を確認していない。」と言を翻したので
あろうが、あまりにも稚拙である。
そしてこの携帯用の酸素すなわち登山用の酸素とは甲三六号証に示されているようなものである(控訴人尋問調書一三頁七行目)。
この携帯酸素に添付されている注意書きを見るまでもなく、この酸素は明らかに医療行為に用いられるものではない。
ましてや、これまでに述べたとおりの、がん末期後期の東京への移動中、心停止などの重大な危険が生じることが予測できた亡淑子の東京への搬送において、携帯する酸素補
給器具としては絶対に用いられるべきでない。
甲三七号証の注意書きにも明らかなように「医療用酸素ではありませんので、医療用として使用しないで下さい。」とあり、その充填量は五リットル、使用回数は一回二秒程度で
五〇回から六〇回使用するだけで終わってしまうものである。
このような携帯酸素をわずか二本だけ携帯するように指示した(乙一一号証六頁五行目)被控訴人らの指示は医療従事者として狂気の沙汰であると言われてもしかたがない。
呼吸困難に陥っている患者に対して供給しなければならない酸素の量は、最低でも毎分二リットルである(甲二三号証一五頁、被控訴人藤村尋問調書二〇六頁七行目)。亡淑
子は平成八年一〇月五日深夜、すなわち退院(転院)直前において、被控訴人らの主張によれば酸素マスク、控訴人の主張によれば鼻カニューレを必要としていた状態なのである。
現に被控訴人藤村も看護婦に対して毎分二リットルの酸素投与を指示している(被控訴人藤村尋問調書二〇六頁七行目)。
毎分二リットルの酸素を補給しようと思えば、この携帯用酸素二本ではものの五分ももたない。
被控訴人藤村ないしは被控訴人会社は、亡淑子の容態について、場合によっては毎分二リットルの酸素投与が必要であることを認識しながら、東京までの三時間という搬送に
おいて、わずか五分ほどしかもたない携帯用酸素の携帯を指示しているのである。
被控訴人藤村は一審の尋問において「大野婦長に対して『登山用』を指示したわけでない。」と主張するが(被控訴人藤村尋問調書二二三頁一〇行目)、しかし登山用以外の携 帯酸素とはどのようなものを指すのであろうか。また大野婦長が言うところの携帯用酸素がどのようなものであるか被控訴人藤村は確認していなかったことを認めている(同尋問調書同
頁)。だとすれば、携帯用酸素の携帯を指示したこと自体で当然責任を負わされるべきであり、「登山用と指示したわけでない」という主張は言い逃れにもならない言い逃れである。
そして、このような肝要な事項についての看護婦に対する指示が全く欠如している(乙第二号証二五頁)。この不適切さについても被控訴人藤村自身認めているところである(被
控訴人藤村尋問調書二二四頁)。
3 以上の事実からすると、一審判決の認定と異なり、遅くとも平成八年一〇月四日の時点で、被控訴人藤村が、低ナトリウムや呼吸困難により、東京への移動中、亡淑子に心停
止などの重大な危険が生じることを予測していた本件において、被控訴人らの、亡淑子の退院に際する注意・説明が全く不十分であったことは明らかである。この点を十分に審理されたい。
第四 結語
以上により、控訴審裁判所におかれましては、一審判決の事実誤認、および、法令違反(評価の誤り、経験則違反、審理不尽)は明白であるからこれを直ちに取り消されるべきで
あり、また、一審以来の控訴人の主張が全部容れられるべきであるから、控訴状「控訴の趣旨」記載のとおり自判されるべきである(ないしは、少なくとも右争点、および損害の有無等
を審理させるため、原審に差し戻されるべきである)。
被控訴人藤村のなそうとしたことは、右第一に述べたように、「目的無き医療」であり、もはや、医療、すなわち、医術で病気をなおすこと、少なくとも、医術により、患者の希望に従 って可能な範囲で、患者の状態の改善ないし維持につとめること、の名に値しないものであって、もともと適正な内容で治療方針を決定しなかったことには、診療契約に基づく義務に対 する重大な違反があると言わなければならない。
さらに、控訴人は、被控訴人会社ないし被控訴人藤村の、単なる「不誠実」な治療(検査を含む)行為を問題にしているのではない。
まさに、右第二、第三に述べたように、被控訴人会社(被控訴人藤村は履行補助者)の、委任者である患者との間の合意にすら(それ自体に問題があるにしても。)に全く反する
か、または、不十分な、治療ないし検査の、作為・不作為、すなわち、債務不履行行為、ないし、安全配慮義務違反行為を問題にしているのである。
原判決の結論および結論に至る経緯が、当審により、修正されることがなければ、もちろん、亡淑子および控訴人の損害が回復されないこととなるばかりか、それにとどまらず、医 療現場において、患者との信頼関係を築きつつ(その前提として、必要かつ十分な説明を前提とした、診療契約の合意、すなわち治療方針の合意があることは言うまでもない。)、医療
行為を行おうとしている、医療関係者の真摯な努力をぼうとくすることとなり、同時に、司法に対する信頼を損なう結果となるとも言わざるをえない。
一審において詳細な意見書(甲二三、甲二六)を提出されたI岡医師も右のような心ある医師の一人であるが、一審判決は、前述のような被控訴人藤村による医療行為の問題
点を直截に見ようとせず、岩岡医師ががん治療の専門医でないとか、控訴人の主張に合致するものであるとか、引用文献の一部遺漏などを問題としてその意見を退けている。
しかしながら、被控訴人藤村の医療行為の問題点は、専門医でなくても指摘できるほどの重大な義務違反を多数含むものであり、同意見書の内容が控訴人の主張に沿うのは当
然である(控訴審においては、がん専門医の複数の鑑定意見書を提出し、文献も遺漏なく準備するが、その意見も控訴人の主張を基本的に認められるものであると確信している)。
最後に、特に、一審判決が、「(被控訴人藤村が本件において)極めて誠実に医療行為を行っていたものであって、なんら非難されるような事実は認められない。」(控訴人が本件
のカルテを検討してもらった医師は全て、これに同調されなかった。)とする点は(事実誤認にも基づく)明らかな評価の誤りであり、また、「裁判所が、カルテや指示簿の記載が不十分
であるとの一事から被告に不利な心証をとらなければならないというものではない。」とする点も(前述のとおり)医学界の常識および判例の趨勢に反するから、必ずや修正されなけれ
ばならないと思料する。
以 上
医療のページに戻る