島崎藤村の「夜明け前」 に記述されている。
幕末の横浜の情景
当時の様子が「正確」に記されている。

開港直後の横浜を描いた肉筆画(1858 安政5年)波止場は現在の「象の鼻」あたり
 島崎藤村(1872--1943)本名春樹 島崎藤村(1872--1943)本名春樹
旧長野県中山道馬籠(まごめ)宿場(現在は岐阜県中津川市)の本陣、庄屋の生まれ。
「夜明け前」の幕末の横浜関係の記述
中山道の馬籠の医者宮川寛斎は、生糸の売り込みに開港後間のない横浜に来たのであった。時に安政6年10月を迎えたころであった。異人(オランダ・アメリカ・イギリス・ロシア)は、我が国に求めるものは、幾世期もかかって積み重ねてきたこの国の文化ではなく、この島に産する硫黄・樟脳・生糸・それから金銀の類なぞが、その最初の主なる目的物であったのだ。
そして「先ず日本を世界に吹聴したのは阿蘭陀(オランダ)人でした。したがって、当時は亜米利加(アメリカ)のペリイが持参した国書すら一通のオランダ語訳を添えて来たくらいであった」。
公郷村(現横須賀)の旧家の七郎左衛門は、二千人の水兵を載せた亜米利加の艦隊が初めて浦賀に入港した当時のことがそれからそれと引き出された。彼は水師提督ペリイの坐乗した三本マストの旗艦ミスシッピイ号をも目撃した人である。浦賀の奉公がそれと知ったときは、ここは異国の人と応接すべき場所でない、亜米利加大統領の書翰を呈したいとあるなら長崎の方へ行けと諭した。
けれども、亜米利加が日本の開国を促そうとしたのは決して一朝一夕のことではないらしい。先方は断然たる決意をもって迫って来た。もし浦賀で国書を受け取ることが出来ないなら、江戸へ行こう。それでも要領を得ないなら、艦隊は自由行動を執ろう。この脅迫の影響は実に大きかった。のみならずペリイは測量艦隊を放って浦賀付近の港内を測量し、更に内海に向わしめ、軍艦がそれを掩護(えんご)(敵からまもる)して観音崎から走水(はしりみず)の付近まで達した。
浦賀奉公とペリイとの「久里が浜」での会見がそれから開始された。海岸に幕を張り、弓矢、鉄砲を用意し、五千人からの護衛の武士が出て万一の場合に具(そな)えた。何しろ先方は二千人からの水兵が上陸して、列をつくって進退する。軍艦から打ち出す大筒の礼砲は近海から遠い山々までも轟き渡る。かねての約束の通り、奉公は一言も発しないで国書だけを受取って、ともかくも会見の式を終った。
その間約半時ばかり。ペリイは大いに軍容を示して、日本人の高い鼻をへし折ろうとでも考えたものか、脅迫がましい態度がそれからも続きに続いた。全艦隊は小柴沖から羽田沖まで進み、はるかに江戸の市街を望み見るところまでも乗り入れて、それから退帆の折りに、万一国書を受付ないなら非常手段に訴えるという言葉を残した。そればかりではない。日本であくまで開国を肯(がえん)じないなら、武力に訴えてもその態度を改めさせなければならぬ。日本人はよろしく国法によって防戦するがいい。米国は必ず勝って見せる。
就いては二本の白旗を賜る、戦いに負けて講和を求める時にそれを掲げて来るなら、その時は砲撃を中止するであろうとの言葉を残した。七郎左衛門の話は、容易ならぬ時代に際会したことを悟らせた。この仙境のような三浦半島の漁村へも、そうした世界の新しい暗い潮が遠慮なく打ち寄せて来ていることを思わせた。
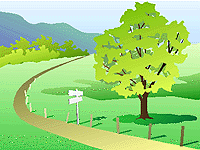
当時の横浜はさみしかった。地勢としての横浜は神奈川より岸深で、海岸には既に波止場も築出されていたが、いかに言ってもまだ開けたばかりの港だ。たまたま入港する外国の貿易船があっても、船員はいずれも船に帰って寝るか、さもなければ神奈川まで来て泊った。下田を去って神奈川に移った英国・米国・仏国・阿欄陀(あらんだ)等の諸領事はさみしい横浜よりも賑やかな東海筋をよろこび、一旦仮寓と定めた本覚寺(米国の領事館)その他の寺院から動こうともしない。
神奈川(現在の東神奈川)の牡丹屋の年老いた亭主が中山道の医者宮川寛斎に語った。
横浜の海岸近くに大きな玉楠(たまくす)(タブノキ)の木が繁っている。世にやかましい神奈川条約はあの木の下で結ばれたことなぞを語って見せるのも、この亭主だ。あの辺は駒形水神の杜と呼ばれるとこらで、玉楠の枝には巣をかける白い鴉があるが、毎年冬の来る頃になるとどことなく飛び去ると言って見せるのも、この亭主だ。


ペリーの上陸と当時のタブノキ 関東大震災で消失、その後芽が出た現在のタブノキ
当時、異国のことについては、実にいろいろな話が残っている。ある異人が以前に日本へ来たとき、この国の女を見て懸想(けそう)した。異人はその女を欲しいと言ったが、許されなかった。そんなら女の髪の毛を3本だけくれと言うので、仕方なしに3本与えた。ところが、どうやらその女は異人の魔法にでもかかったかして、到頭(とうとう)異国へ行ってしまった。
その次に来た異人がまた、女の髪の毛を3本と言い出したから、今度は篩の毛を3本抜いて与えた。驚くべきことには、その篩が天に登って、異国へ飛んで往ったともいう。これを見たものはびっくりして、これは必ず切支丹(キリシタン)に相違ないと言って、皆大いに恐を抱いたとの話もある。
異国に対する無智が、およそいかなる程度であったかは、黒船から流れ着いた空壜の話にも残っている。アメリカのペリイが来航当時のこと、多くの船員を乗せた軍艦からは空壜を海の中へ投げた。波のまにまに自然に海岸に漂着する。それを拾って黙って家に持ち帰るものは罰せられた。
一一届け出なければならない。その時の役人の言葉に、これは先方で毒を入れておくものに相違ない。さもなければこんなものを流す道理はない。きっと毒が盛ってあって日本人を苦しめようという軍略であろう、ついては、一か所捨て置く場所を設ける。心得違いのものがあって万一届け出ない場合があったら直ちに召捕るとの厳しい触れを出したものだ。それが異人らの日常飲用する酒の空壜であるということすら分らなかったという。
神奈川の牡丹屋の裏二階に残った宮川寛斎は、時には孤立のあまり、海の見える神奈川台へ登って行った。目にある横浜もさびしかった。あるところは半農半漁の村民を移住させた町であり、あるところは運上所(税関)を中心に掘立小屋の並んだ新開の一区画であり、あるところは埋め立てと縄張りの始まったばかりのような畑と田園の中である。弁天の杜の向こうには、ところどころにぼつんぼつん立っている樹木が眼につく。全体に湿っぽいところで、まだ新しい港の感じも浮かばない。
やがて寛斎等は、神奈川台に住む英国人で、ケウスイという男で、横浜の海岸道りに新しい商館でも建てられるまで神奈川に仮住居するという貿易商であった。その西洋人は、羅紗の丸羽織を着、同じ羅紗の股引(ももひき)をはき、羽織の紐のかわりに釦を用いている。寛斎等の持って行った「生糸」の見本は、ひどくケウスキイを驚かせた。この西洋人は、幽霊でもなく、化け物でもない。やはり血の気の通っている同じ人間の仲間だ。「糸目百匁あれば、一両で引き取ります」この商売の言葉に、寛斎等は力を得た。百匁一両は前代未聞の相場であった。
年も万延元年と改まる頃には、日に日に横浜への移住者がふえた。寛斎が海を眺めに神奈川台へ登って行って見ると、その度に港らしい賑やかさが増している。弁天寄りの沼地は埋め立てられて、そこに貸し長屋が出来、外国人の借地を願い出るものが二、三十人にも及ぶと聞くようになった。
吉田橋架け替えの工事も始まっていて、神奈川から横浜の方へ通う渡し船も見える。また何となく野毛山も霞んで見え、沖の向うに姿を現している上総(かずさ)辺の断崖には遠い日があたって、さびしい新開地に春の巡って来るのもそんなに遠いことではなかろうかと思われた。日本最初の使節を乗せた咸臨丸が亜米利加へ向けて神奈川沖を通過した時だ。
徳川幕府が阿蘭陀政府から買い入れたというその小さな軍艦は品川沖から出航してきた。艦長木村摂津守(きむらせっのかみ)、指揮官勝麟太郎をはじめ、運用方、測量方から火夫水夫まで、一切西洋人の手を借りることなしに、阿蘭陀人の伝習を受け初めてから漸(ようや)く五年にしかならない航海術で、太平洋を乗り切ろうという日本人の大胆さは寛斎を驚かした。その軍艦は石炭を焚くばかり、大変な評判で、神奈川台の上には人の黒山を築いた。不案内な土地へ行くために、使節の一行は何千何百の草鞋(わらじ)を用意して行ったか知れないなぞという噂がその後に残った。


左 復元した咸臨丸 横浜ぷかり桟橋にて平成11年6月2日撮影 右 横須賀自然博物館
翌日は寛斎と牡丹屋の亭主とが、江戸から来た三人を先ず神奈川台へ案内し、黒い館門(やかたもん)の木戸を通って、横浜道へ向かった。番所のあるところから野毛山の下へ出るには、内浦に沿うて岸を一廻りせねばならぬ。程ケ谷からの道がそこへ続いて来ている。野毛には奉公の屋敷があり、越前の陣屋もある。そこから野毛橋を渡り、土手通りを過ぎて、仮の吉田橋から関内に入った。
「横浜もさびしいところですね」「わたしの来た時分には、これよりもっとさびしいところでした」
瑞見と寛斎とは歩きながら、こんな言葉をかわして、高札場の立つあたりから枯れ枯れな「太田新田」の間の新道を進んだ。当時の横浜関内は、一羽の蝶のかたちに譬(たと)えられる。海岸へ築き出した二ケ所の波止場はその触角であり、中央の運上付近はそのからだであり、本町道りと商館の許可地は左右の翅(はね)にあたる。一番左の端にある遊園で、樹木の繁った弁天の境内は、蝶の翅に置く唯一の美しい斑紋とも言われよう。
しかしその翅の大部分はまだ田圃と沼地だ。そこには何か開港一番の思いつきでもあるように、およそ八千坪からの敷地からなる大規模な遊女屋の一廓も展(ひら)けつつある。横浜にはまだ市街の連絡もなかったから、一丁目ごとに名主を置き、名主の上に総年寄りを置き、運上所の側の町会所で一切の用事を取り扱っている。
横浜海岸通りの波止場から見える、西洋の船にならって造った二本マストもしくは一本マストの帆前船から、従来あった五大力(ごだいりき)の大船、種々な形の荷船、便船、漁(いざ)り船、小舟まで、二ケ所の波止場、水先案内人の職業、運上所で扱う税関と外交の港務などは、全く新しい港のために現れて来たもので、ちょうど入港した一艘の外国船も周囲の単調を破っている。
旧横浜村の村民は九十九戸ばかりの竈(かまど)を挙げてそちらの方に退却を余儀なくされた。それもどこの新開地に内外人の借地の請求が頻繁となって来た意味を通わせた。大岡川の川尻から増徳院脇へかけて、長さ五百八十間ばかりの堀川の開鑿(かいさく)も始まった。
横浜も海岸に寄った方は既に区画の整理が出来、新道はその間を貫いていて、町々の角には必ず木戸を見る。帰り路には、寛斎らは本町一丁目の通りを海岸の方へ取って、渡し場のあるところへ出た。そこから出る舟は神奈川の宮下というところへ着く、わざわざ野毛山の下の方を遠回りして帰って行かなくてすむ。牡丹屋の亭主はその日の夕飯にと言って肉を横浜の町で買い求めて、それを提げながら一緒に神奈川行きの舟に移った。
安政の大獄以来周囲の空気は重苦しく、厳重に町々の取り締まり方と、志士や浪人の気味の悪い沈黙がある。前年の年の七月の夜には横浜本町で二人の露西亜(ろしや)の海軍士官が殺され、同じ年の十一月の夕には港崎町(こうさきまち)の脇で仏蘭西(ふらんす)領事の雇人が刺され、最近には本町一丁目と五丁目の間で船員と商人との二人の阿蘭陀人が殺された。それほど横浜の夜は暗い。外国人の入り込む開港場へ海から何か這うようにやって来る闇の恐ろしさは、それを経験したものでなければ解らない。
その後、港は発展の最中だ。野毛町、戸部町なぞ埋め立ても出来、開港当時百一戸ばかりの横浜に何程の移住者が増したと言って見ることも出来ない。この横浜は来る六月二日を期して、開港一周年を迎えようとしている。その記念には、弁天の祭礼をすら迎えようとしている。牡丹屋の亭主の話によると、神輿はもとより、山車(だし)、手古舞(てこまい)、蜘蛛の拍子舞などいう手踊りの舞台まで張り出して、出来るだけ盛んにその祭礼を迎えようとしている。
誰がこの横浜開港をどう非難しようと、まるでそんなことは頓着しないかのように、一旦欧羅巴(よーろっぱ)の方へ向って開いた港からは、世界の潮が遠慮会釈なくどんどん流れ込むように見えた。羅紗(らしゃ)、唐桟(とうさん)、金巾(かなきん)、玻璃(はり)、薬種、酒類なぞがそこから入ってくれば、生糸、漆器、製茶、水油、銅、及び銅器の類なぞがそこから出て行って、好かれ悪しかれ東と西の交換がすでにすでに始まったように見えてきた。

以上 <原文のまま>
 
開港直後の野毛 前の方は田圃か? 開港直後の横浜町 現在の中華街付近
|