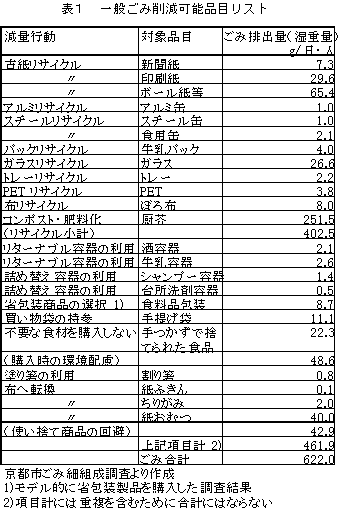
○鈴木靖文、高月紘、酒井伸一
Yasufumi SUZUKI, Hiroshi TAKATSUKI, Shinnichi SAKAI
ABSTRACT : Citizens' cooperation rates
for individual waste reduction actions are very important to evaluate
the reduction of municipal solid waste. In order to estimate the
cooperation rate, a basic model on environmental behavior of citizens,
based on game theory was made, and confirmed by a questionnaire
survey. The model indicated that the degree of citizens' environmental
concerns doesn't directly affect their actions, and that the cost
of action and one's perception about how many people are cooperating
on the action is much more influential. The perceived cooperation
rate was lower than the real cooperation rate. If people can
get more accurate information about cooperation rate, more citizens
will begin to act and the total cooperation rate will rise.
生活系廃棄物の発生量は増大の一途をたどり、処分場の逼迫等の問題から量的な削減が大きく求められている。各種製品のリサイクル率は毎年向上しているが、それ以上に消費が増加しており、よりいっそう削減に向けた努力が求められている。
ごみの削減に向けては、市民や自治体、製造や流通などの企業が協力して取り組む必要があることはいうまでもない。しかしこの中で市民の協力については評価が難しいため、実際に対策を進めるにあたって目標や責任の設定が非常に困難となっている。今回は廃棄物削減策として市民の協力に帰属する項目にしぼり、削減の効果とその協力率についての検討を行った。また、市民の意識と行動に関してゲーム理論に基づいた基礎的なモデルを作成し、ごみ削減の対策としてあげられる手法の位置づけについて検討した。
「廃棄物減量のために何ができるのか」という問いに対して、一般的に多くの削減の取り組みが答えられるが、それらは大きく、対象物の廃棄量を直接削減する取り組み(減量行動)と、その取り組みを間接的に促進させる取り組み(促進行動)に分けて考えることができる。これは廃棄物の削減量を求めるにあたっては、減量行動により削減可能な廃棄物量に、協力率を掛け合わせる必要があることにほぼ対応している。削減対象物については定量的な値が求めやすいが、その減量行動に対してどれだけの協力が得られるのかは評価するのは困難である。
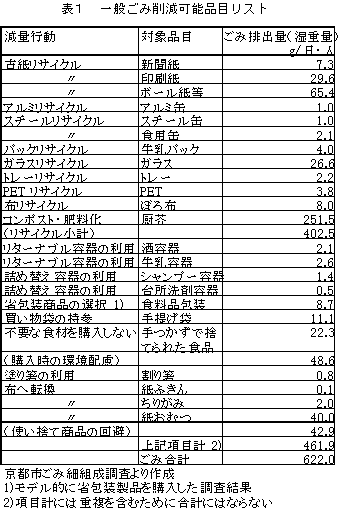
一般廃棄物の発生については、多くの都市で組成・品目別に測定が行われており、削減対象物の定量的な評価が可能となっている。京都市の細組成調査と排出原単位をもとに、現在削減の可能性が考えられる品目と減量行動を列挙したものを表1に示す。
排出時点での重量の点で評価を行うと、コンポストをはじめとしてリサイクルの効果が非常に大きくなっている。もし完全にリサイクルが可能な場合には、湿重量で65%もの削減が可能となる。しかし、実際にこれらすべてをリサイクルできるかどうかについては、回収方法や受け入れ側の需要についても配慮する必要があり、一方的にリサイクルをすることだけで削減ができるということは言い切れない。逆に現在の古紙回収の行き詰まりの状態などを考慮に入れると、再生品の利用用途を整備しないと、現状でリサイクルに回されていたものも廃棄物ルートに出されることも十分考えられる。
リサイクル以外の取り組み項目としては、購入時点での配慮、および使い捨て商品を使用しない取り組みとしてまとめられる。これらは合わせても11%程度とリサイクルに比較して効果は小さいが、最大限に取り組みが行われた場合でもシステム的に限界がなく、生活者の協力率によって制限される。またこの取り組みはいずれも、ごみになった時点で減量を考えるものではなく、購入の時点に立ち返って取り組む点で共通しており、環境配慮型の販売や製品を推進する点でも効果がある取り組みとされている。
上記の各減量行動に対してどれだけ生活者の協力率が得られるのかは別途考慮する必要がある。ここで、減量行動がどのように導き出されるのかをモデルを作成して検討した。
環境問題の状況を説明するものとして「囚人のジレンマ」がよく引き合いに出され、協力して取り組めば望ましい結果を導き出せる一方で自分が取り組むのに負担がかかる場面で、総論ではすべきだが結果的に取り組まないという状態をよく表している。ジレンマの問題を解決するためにはこの状況をどうにかして脱する必要がある。
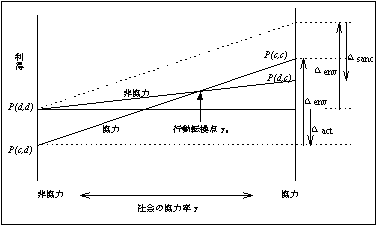
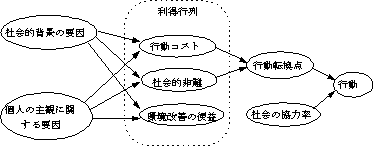
ここで自分対社会全体の社会的ジレンマの利得行列を考える。ある環境行動についての利得行列に影響を与えうる要素としては、(1)全体の協力率のみに依存する要素、(2)自分の行動のみに依存する要素、(3)全体の協力率と自分の行動の両方に依存する要素,、に分けて考え、それぞれ代表的な意味を配慮して、
(1)環境改善の便益
(2)行動コスト
(3)社会的非難
と設定した。社会的非難については、自分が協力しない場合にのみマイナスとして与えられるもので、非難の大きさは社会の協力率に比例しているものと仮定した。
ここで、もし社会的非難

またこの場合、行動転換点に対しては環境改善の便益は全く影響を与えないことがモデルから導かれる。
なお実際にはこれらの変数は、減量行動の各々について、また個人ごとに異なる値が設定されることになる。
アンケートは1995年の12月に実施し、京都市南部版の電話帳より無作為抽出した564人に郵送でアンケートを行い、ふだん買い物をしている方362人(64%)の回答を得た。環境行動としては「包装の少ない野菜類を購入する」行為にテーマを絞り、各種の質問を行った。モデルの各パラメータについては、CVMを用いて金額で回答を求めた。
アンケートの集計、およびそのモデル的検討から、消費者のゲーム構造については主立ったものとしては以下の知見が得られた。
(i)周りの協力率が行動に影響を与える
「周りで全ての人が取り組んでいた場合あなたは取り組みますか」という質問には、9割以上の人が「取り組む」と回答した。具体的に数値の質問では「周りで5割くらいの人が取り組んでいたら自分も取り組む」とした回答が多く、利得行列の構造は囚人のジレンマではなく「安心ゲーム」になっていることが示された。
モデルの行動が導かれる部分の検証で、周りでどれだけの人が協力していると思うか(認識協力率)と行動の間、および行動転換点と行動の間には有意な相関が見られた。
(ii)行動コストが行動転換点に影響を与えている
アンケートで回答された行動コストと行動転換点の間には有意な相関が見いだされた。しかし、モデルで関係があるとされている社会的非難との関係は有意には見いだされなかった。
(iii)環境改善の便益は行動に直接的影響を与えない
環境改善の便益については、モデルで示されたように行動や行動転換点に影響を与えられていないことが示された。
(iv)環境改善の便益と社会的非難の間に相関がある
モデルでは環境改善の便益と社会的非難は独立の変数として扱っているが、相関係数は0.48であり、関連があることを否定できないことが示された。
モデルで設定された各種のパラメータを変更することにより、協力率がどのように変化するのかを検討した。パラメータについては現状回答額の1/10から10倍まで変化させて検討した。同時に、自分を含めた全員が取り組みを行っている状態と、全員が取り組んでいない状態のどちらが望ましいか、考え方の変化も合わせて検討した。
また、今回のアンケートは野菜類の包装についての取り組みであり、先に検討した廃棄物削減量のうち「省包装製品の削減」に対応するとみなし、協力率の変化と削減量について評価した。
(1)認識協力率の変化(図3)
モデルより周りの協力率は、行動に大きな影響を与える。全体の利得値を配慮すると6割程度まで認識協力率をあげて考えることにより、負担なく実際の協力率を上げられることが示された。
アンケートの結果では集計による協力率は58%であるのに対し、認識している協力率の平均は40%となっており、協力率を実際よりも低く見積もられている。よって正確な情報によってより協力が進むことが言える。「取り組むことが普通である」ことを宣伝すること、自分も取り組んでいることを話すことなどもプラスの効果を与えると考えられる。
現状の協力率を正しく認識することによって22%の協力率の向上で5.7g/日・人の削減が見込まれる。
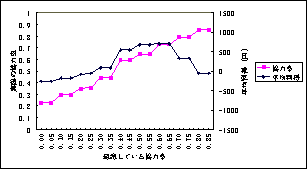
(2)環境改善便益の変化(図4)
環境を重視すること、行動が効果があると認識することなど、行動を始めるにあたって基礎的な要素であることは明らかだが、今回のモデルでは協力率向上に影響をあたえるようにはなっていない。
協力率に対しては影響を与えないが、この値が小さくなると「全員が取り組む状態より取り組まないほうが望ましい」といった考えを持つ人が増えており、協力率も増えないことが予想される。この点を含めた検討は今後必要である。
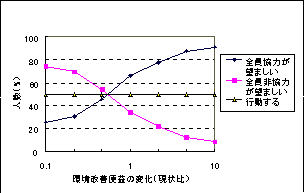
(3)行動コストの変化(図5)
外部的に比較的操作がしやすいパラメータで、直接的に行動を導き出す大きな要素となる。行動コストを下げることは、協力率を上げるとともに、最終的な協力状態をより望ましいものとする。
アンケートにおいて、店に包装が少ない商品が並べておいてあった時の行動コストについても尋ねたところ、9割以上の人が積極的に取り組むように態度を変更した。この場合には、ジレンマの状況自体が解消された。
具体的な活動としては、取り組み方を情報として得ることや、実際に取り組んでいる人の話を聞いて自分もやれそうだと考えることも、結果的に行動のコストが下げる効果を与えている。
コストの認識を平均で1/2にすることにより、協力率が80%まで向上し、5.2g/日・人の削減となる。
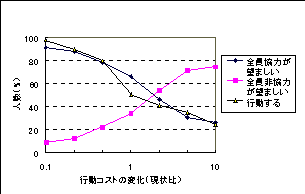
(4)社会的非難の変更(図6)
お互いの行動がチェックできるような仕組みを作ることにより、社会的非難の値を上げることでもジレンマの解決に大きく寄与する。
比較的消費行動については、個人の自由に任されることが多く、他人のチェックがなされることは少ないと考えられる。環境家計簿等を用いて家族でチェックするなどの行動で、この値は大きくなるものと考えられる。
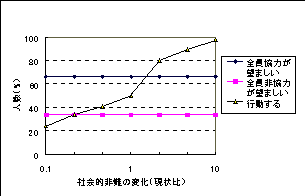
各個人が行動転換点といった行動の傾向を持ち合わせていて、同じ取り組まない人でも「絶対に取り組まない」人から「きっかけがあったら取り組む」人まで多様な考えを持っている。しかも周りの人と同じ行動を取る傾向があるため、現実の協力率の変化はかなりダイナミックなものになると考えられる。今回のモデルには含めきれなかった環境意識の面については、こうした背景的要素の一つとして重要な役割を果たすものと考えられ、意識高揚の行動が意味づけられるよう検討を進めたい。
なお、定性的議論は可能であるが、定量的評価を行うにあたってはまだ問題が多く、今後の検討が必要と考えられる。
参考文献
鈴木靖文:ライフスタイルの変更による環境負荷低減の可能性、京都大学大学院工学研究科修士論文、1996
Taylor, Michael:The Possibility of Cooperation、Cambridge
University Press、1987(松原望訳:協力の可能性、アテナ社、1995)
(この文章は環境経済政策学会97年講演論文集に掲載した物です)
お問い合わせ、感想などありましたら鈴木(ysuzuki@mti.biglobe.ne.jp)まで。お気軽にどうぞ。
[ホームへ戻る]