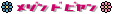それは、いえ、その方は、ほんとうに突然、彼の部屋に佇んでいました。
舞い降りた…と申し上げた方がよいのかもしれません。なぜなら、その方の背には白い大きな羽根がありましたから。
それはけっして飾りなのではなく、その方の身体の一部であると一目見れば分かりました。最初は驚きましたけど、不思議と悪い感じはしませんでした。悪いかんじというのは、不安とか恐怖、嫌悪などの感情のことですけれど、そういう感じはしなかったということです。
不思議と言えば、彼の態度もそうでした。たとえその方の姿がどんな神秘的であろうとも、彼ならすぐさま身体検査を始め、この未知の生命体を調べることに夢中になるだろうと、私はその方を見たとき直感的に予想していました。
けれど、彼はそれをしなかったんです。なぜ?それは私にも知る由はありません。ただ、そのとき彼は生まれて初めての恋に破れて、友情に傷ついて、いつもよりいっそう物憂気な感じでした。それに、長い髪や羽根の羽毛を優雅に風に晒すその方のまわりは時がゆっくりと流れている感じがして、彼も私も、ただ何をするわけでもなく、何を語るわけでもなく、どこを見るわけでもなく佇んでしまうのです。でもそれはごく自然なことのように思えました。今でもそう思います。その方の前では私たちは、よい意味でなす術がなかったのでした。
彼は長い眠りにつくために私に仕事を引き継ぎ、準備もすっかり整っていたのですが、その方のために地下のカプセルに入るのを延ばしていました。仕事はもうすでに私が代行していたので、彼は何をすることもなく、数日間をその方と過ごしました。
その間、ふたりが何をし、どんなことを語ったのかも、私には分かりません。結局私は最後までその方の声を耳にすることはありませんでしたし、視線さえ、合ったかどうかもはっきりしません。ただ、あるとき、私は忘れられないだろう光景を目にしました。
通常、彼が眠っている間に、彼でなければ決済できない仕事が発生したときは、彼が目醒めるまで何とか決済を引き延ばすのですが、あのとき、彼はまだ眠りについていなかったので判断を仰ぐため、私は件の書類を携えて、その方が現れてからはじめて、昼間のうちに彼の部屋を訪ねました。
ノックをし、声をかけ、返事を待たずにドアを開けました。彼はソファで、その方と寄り添うように眠っていました。
心持ちあごをあげて、縋るような表情をのこした寝顔。
白くやわらかな羽根に、頼るかのように埋もれる頬。
このときの彼の表情と、それを見てしまった私の心の中にうずまく感情は、まるで正反対の様子でした。
見てしまった、と思うくらいの、あまりに安らかな弱々しい彼の表情に、私は、どうしていいか分からないほど胸が痛く、苦しくなりました。この平和な佇まいに、なぜこんなに嫌な気持ちが渦巻くのか、分かりませんでした。
でも、今なら分かります。それは嫉妬という感情でした。自分は彼のそんな表情を見たこともないし、させたこともないのに、出会ってほんの数日のその方がなぜそんなにも彼に寄り掛かられるのか、理屈を考える間もなく、嫉妬したのです。
やはり私は、彼のことが好きなのだと思い知りました。彼のどんな表情も一人占めしたいほどに。優しさをもって彼を包むことに満足していたはずなのに、そうではなくなったことに気付いたのが嬉しいのかそうでないのかは、いまだによく分かりません。どちらにせよ、私はいつまでも、どこまでもこの気持ちをかかえて生きていくのだろうということは分かりました。
そして、その方が彼の部屋からいなくなったと分かったのは、その翌朝のことでした。
いつものように私が彼を起こしに部屋に入ると、その方の姿はなく、いつもその方が佇んでいた窓辺に白い羽根がひとつ、残されているばかりでした。彼が目を醒まし、着替えてから、私が羽根を差し出してあの方は帰られたのですか、と聞くと、彼は、その開けられたままの窓辺に歩み寄って空を見上げ、しばらくしてから私に振り返り、そうみたいだね、と言いました。
そのとき私に見せた、彼の寂しげな表情は、昨日のあの表情に似ていました。見ているこちらが、いたたまれなくなってしまうほどのその顔に、残酷なことかもしれませんが、私の心につかえていた苦しいものは瞬時に溶けてなくなりました。
と同時に、彼はやはり眠りについたほうが良いと思い始めました。眠りについて、少しの間だけでも心を占める切なさを忘れて、いつもの彼に戻って欲しいと思ったのです。
私の望んだとおり、彼はその日のうちに地下のカプセルで眠りにつきました。睡眠薬の投与をけっして止めるなと言い残して。
彼の傷の深さを痛々しく思いながら、私は彼の意識を天へと飛ばしました。
きっとあの方も、大きな翼で天へ舞い上がって行ったことでしょう。
カプセルを閉じたとき、私は心の中で、ある詩の一節を唱えていました。
天に
まします
我らの父よ
どうか
そこに
止まり給え
だが 僕らは
地上に止まろう
ときには
かくも美しい
この世に―
いつか彼は目醒めるだろうと確信していました。
そして、それを地上で待てるこの身が嬉しかったのです。