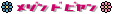薄暗い部屋の奥。
手足を投げ出すようにしてベッドに俯せている麗しのいとこに不躾に声をかける。
窓辺から射し込む月光に片頬を照らし、ユラリと起き上がる、響谷、薫。
彼女の取り落としたグラスを拾い上げ、斜めに見下ろすのは、響谷、祐樹。
それは半時前。
恋と夢に破れて、渡米を決意し、その挨拶のために立ち寄った家。
おじは留守、めずらしくもおばがい、どこの学校に行くだとかの説明だけをし、一方的に会話を終わらせた後。
いつも思いつめた目をして遠くを見ている、あの麗しのいとこに会って、刺激的な会話を楽しもうと、自分にはまだそれくらいの余裕はあるのだと、ドアをノックしたが、いっこうに応答がないのだ。
メイドの話では帰宅してから部屋にこもりきりとのことだった。
不審に思いながらも、鍵はかかっていなかったので開けると、明らかにアルコール臭。
見ればベッドから伸びた右手のグラスには、薄く琥珀色の液体が揺れている。
「ひどい顔だな」
乱れた前髪が濃い影を落とす目元とは裏腹に、唇は微笑みのかたち。狂気的なアンバランス。
「人のことが言えた義理か」
でも、まだ声には張りがある。祐樹はこっそり安堵の息を漏らす。いい勝負ができそうだ。
彼女が苦しい恋をしていることは気付いていた。相手は知らないが、自分も、ついこのあいだまで言えない恋をしていたから分かったのだ。今は、恋じゃない。苦しさだけだ。はやく、どこかに葬ってしまいたい。
「オレは、酒に逃げたりしない」
「同じだ。…アメリカだって?」
知っていたのか。皮肉げな声に言い当てられて祐樹は窓辺へ歩み寄り、月を見上げながら反撃を考える。
「逃げてるのは認めるわけだ」
月光を背に振り返り、薫の目を見つめる。何かに傷ついた、自分とよく似たその目を。
さっき、ひどい顔と言ったのだって、最近の自分とまるで同じような表情だったからだ。
特に何かあったわけではない。ひどく、やりきれないのだ。毎日、毎日。
「別に、逃げてるわけじゃない。どちらかと言うと、楽しんでるんだ」
ベッドの端に腰掛け、髪を掻きあげ、吐息を漏らす。今夜は素直にも話すつもりらしい。
「楽しんでる?」
促すと、頷く。サイドボードの酒瓶を見つめて、とつとつと語るのだ。
「時々は、酔って、いやなこと考えるのを忘れて、幸せな考えに耽ることもできる。ほんとに、時々、少しの間だけだけれど、浸れるんだ」
そのわずかな時に縋るしかないほど、やりきれなさに弱っているのだ。
「随分、割が悪い話だな」
会話は続く。自分を慰めることは出来ないけれど、自分と同じような暗い目をした彼女を励ますことは出来る、と思いたい。
「留学は、割に合うのかい?」
語らせるつもりが、即こちら側へ切り返してくる。そう、これだ。楽しくなってきたじゃないか。
「他に、思い付かないんでね」
身体を離せば、想いもいつか振り切れるに違いない。次、会うときは穏やかな思い出になっているはず。
「ムキになって、突っ走るからさ」
非難しているわけではない、むしろ甘やかすような言いぐさだ。そんなのも、嫌いではないと。
薫の視線は、心を見透かすようで、祐樹の指先から上にあがり、その眼差しを捕らえる。
恋か、ピアノか、どちらにより夢中だったのか。どちらをより早く忘れられるか、それとも忘れられないのか、今はまだ分からない。
「酒に夢中になるよりは、健康的だと思うね」
使い物にならない手をかかえた自分が健康的だとは自嘲の極みだ。勝負の雲行きはあやしい。
「まぁそう言わないで、ちょっとご覧よ」
なにしろ相手は未成年の飲酒というものに、微塵も後ろめたさを感じてないのだ。
ふらふらと頼り無気に壁の本棚へ歩み寄り、開け放たれた扉の中を覗き込む。
暗闇の中で目をこらすと、そこには酒瓶がいくつも並んでいた。
「この、不良が」
思わず尻上がりの口笛を吹いてからそう言うと、目の前にずいとグラスが突き出された。
「餞別には悪くないだろ」
「酔っ払いに気を遣われるとは思わなかったぜ」
「不幸ヅラしてるやつには、酔っぱらいで十分さ」
痛いところを突き合いながら軽口が飛び出す。グラスに液体が滑り落ちる。
傷を嘗め合うんじゃない。明日また立ち上がるために、お互いを利用するだけだ。この、鏡を見るように同じ表情をしたこいつを。
カチンと音をたてて合わせたグラスの端、その向こうで、夜は更けてゆく。