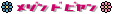カタン、と音を立てて桐箱の蓋が、畳に転がる。
突然の不自然な音に、彼は顔を上げると、男の大きな手のひらが頬に触れた。
近付いてくる男の広い胸に部屋の明かりは遮られ、彼の白い顔に影を落とす。
「なんだ?」
男は無言でもう片方の腕を伸ばし、彼の髪をかき上げてきた。
そのまま後頭部にまわされた手が、彼の頭を引き寄せようとした。
「なんだと言っている。勝手に触るな」
男の肩に額が触れそうになり、彼は後頭部に回された腕を払う。
しかし、それまでやんわりと指先だけに込められていた男の力が、急に強引になる。
男は身をかがめて両手を畳につき、立てた膝をにじり寄せ、彼の手首を捕らえる。
「な、にを…んっ」
男は下からのぞきこむように顔を近付けたかと思うと、すばやく彼の唇を奪った。
押し付けるようなキス。逃れようと引けば、追ってくる。
「んっ…やめっ、…女丸」
彼は必死で顔をそむけてもがく。その代わりに差し出された首筋に男の顔が埋まる。
彼はその頭を両手で引き剥がそうとするが、正座をしたままのけ反っているので上手く力が入らない。
「やめろっ、美女丸!…っ、どうしたって言うんだ、急に」
「急でなければいいのか」
「!?」
◇
ふいに口をきいた美女丸に、その内容に、シャルルは一瞬目を見開いた。
美女丸はもう一度身を乗り出してきた。シャルルは逃れようとして正座を崩し、しりもちをつく。
「あっ、んんー!」
放り出された足の膝を割るように手が置かれ、それに抵抗している隙に顔が近付き、唇が重なる。
今度は引けば、完全に押し倒される。かと言って、このまま唇を許している状態も耐え難い。
身動きできずにいるシャルルをいいことに、美女丸はキスを深めてくる。
きつく閉じた目からは何を考えているのか分からない。
そしてとうとう身体を支えていた腕を取られ、ドサと畳の上に倒れこんでしまった。
「…なにを、しようって、言うんだ」
「分からないか?」
「!…どうかしてる」
こんな、いきなり、こんなこと。
「そうか」
美女丸はつぶやくように言いながら、シャルルのタイをほどく。
手早く襟元をくつろげ、鎖骨の間にキスをし、少し、舌を這わせた。
不覚にもシャルルはビクッと反応し、美女丸は薄く笑う。
「ゆっくりするから、分かれよ」
そう言って服を剥がすのも、二の腕の内側に口付けるのも、どこかぶっきらぼうで。
訳が分からないまま、身体だけ、熱をおびていった。
◇
風にそよぐ髪が頬を撫でるのに、シャルルは目を覚ました。
全身が鉛のように重たく、視線だけをさまよわせる。
澄みきった空に、白く、雲よりも薄い、消えそうな下弦の月が見えた。
「気がついたか」
頭上から声がする。シャルルは、美女丸の膝枕で寝ていた。
しかも、誰に見られるとも知れない障子を開け放った縁側で。
「…っ」
「急に起き上がると辛いぞ」
がば、と美女丸の膝から起き上がろうとして、シャルルの下肢に痛みが走る。
服は着ている。が、この、刻み込まれたかのような違和感は。
「この…変態っ…」
シャルルは起き上がるのは諦めて、美女丸からはなれた所であおむけに寝転がる。
それでもかなり辛いのだが、しようがない。
シャルルは、大仰にからかわれたのだと思っていた。
美女丸は、不器用にも、愛おしんのだと思っていた。
「変態、か…」
フッと笑みを浮かべる美女丸は悪びれた様子もなく、
シャルルは大きなため息をついて、忘れることにする。
「気をつけたほうがいい。下弦の月も、人を狂わせるようだ」
身も世もなく魅せられ、理性は、その眩しさに溶けて消えてしまったのだ。
あの、南中に白む月のように。