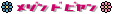触れた唇は冷たく、吐息はかすかに混ざり合い。
それは、思いがけない一瞬だった。
熱くなる顔や全身を持てあまし、彼に背を向けて走り出した。
唇にかすかに残る感触が、この胸の動悸が、私をして、何もかも分からなくさせる。
彼のすがるような顔と、呆然とした顔が交差して。
強く目をつむって、この混乱を、すべて水で流し落としてしまおうと。
奪った唇さえも。
・・・
コンコン、と低めにドアをノックする。
自然と手を、はやる鼓動を押さえるかのように胸に当てて。
「誰?」
「…あたしよ。開けてもいい?」
「!…どうぞ」
ドアを開けたものの、その場に立ちすくんでしまう。
どうやってこの気持ちを伝えたらいいのか分からないまま、とりあえず謝ろうと口を開く。
「あの…さっきは、ごめんね」
上目遣いに彼の表情をうかがえば。
わずかに小首をかしげた彼の艶やかすぎる微笑が、胸に痛いほど浸み渡る。
「どういたしまして。とても嬉しい事件だったよ。今、乾杯しようと思ってたところだ」
「…悪いけど、それ、やめて」
「なぜ?」
「だって…あたしね、つい、その…してしまったんだもの。つい、ふらふらっと。だから、やめて」
「本気じゃなかったってことかい?」
「…分からない」
「オレには分かるよ、マリナちゃん。君は、少なくとも最初の頃よりは、オレのことを好きになりはじめてるってことがね」
「…」
「自然に、君の思うようにしていたらいい。きっと、そのうち分かる」
「呪文みたいに唱えるのはやめて」
「術にかかるかどうかは君の自由だよ」
「シャルル!」
思考をからめとられそうで、抗議の声をあげてみるけれど。
彼から押し寄せる波に、切ないくらい甘いその想いに、飲み込まれてしまう。
「ここへ来て、マリナ」
過ちを犯した私を許すというの。本気じゃなかった私に、傷ついているはずなのに。
「シャルル、あたし…」
「だまって」
彼が腕を伸ばして私を捕らえる。私には振り払えるはずもない。
「…君にキスしても、もう怒らない?」
彼の誘うような息遣いに、囚われていたいのは、私。
「逃げないでいてくれるなら、するよ」
深まる夜の中で、愛をささやく私の恋人。
あなただけが欲しいと想えたなら、どんなにか。