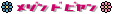強い風で、髪が頬や額を打つ。
「おいで」
差し伸べられた手。
(一緒に還ろう)
その先には、しがらみのない、魂だけの甘美な世界が待っている。
◇
目が覚めたのは、無機質な空気を感じたせい。
すべてが除菌・消毒された部屋の空気は、潔癖すぎて、肌に刺さる。
「薫」
名前を呼ばれて、そちらに目を向けようとするが、なんだか頭が重い。
視線を動かすだけなのだが、ひどく緩慢になる。
目が見えるのに慣れる前に、ぼうっとした頭が声の主を思い出した。でも、そんなまさか!
「起きたか」
同じほうから違う声。足音が近付く。
力をこめて目をつぶり、思いきって首を声のほうに回す。
おそるおそる瞼の力をゆるめていく。全てが見えたとき、さっきの記憶が間違いだったらこわい。
「どれ」
そんな薫のふるえる目もとに気づかいもせず、おもむろに手首を掴み、脈をさぐる腕。
彼女がやっとのことで開けた目でみたのは、白衣のそで口と、色白い手首、手のひら、そして指。
その持ち主の顔は、白金髪をゆらしたシャルル・ドゥ・アルディ。
「正常だ」
言って彼が振り返った先に、いるはずのない人が、いた。
ドクン、と鼓動が強く、喉元まで響く。
「う、そだ」
かすれた声で、ようやくそれだけ言った。
今のうちに、嘘だと言ってもらわないと、後がもたない気がした。
自分のベッドから1歩だけ離れて静かに笑顔を見せている、あの人の存在が。
「幽霊じゃないぜ」
シャルルはわずかに得意げな笑みを浮かべて、自分の作品を誇るかのように、彼の背中を押してベッドの側に引き寄せた。
1歩近付いてきた彼の顔、姿、形…、最後に見たときと幾分も違わない。
最後。
最後っていつのことだ。何があった。どうして。ここはどこだ。
「―」
沸き上がる疑問・感情に咽が干上がって、声が出ない。
出来たのは、脈をはかられたほうの腕を、彼のほうに動かすことだけ。
「薫」
その手を両手で優しく包み、しゃがんで視線を合わせ、ふたたび彼が名前を呼ぶ。
声も、触れるてのひらと同じくらい、あたたかくて優しい。
だめだ。
みるみるうちに薫の瞳に涙が浮かび、まばたきをすると、耳の近くへこぼれた。
かすかに目の奥に痛みを感じるのは、今までまばたきもせずに見つめていたせい。
「もう少し寝て、落ち着け。2時間経ったら起こしに来る。検査だ」
気を失うかのように薫はふたたび眠りに落ちた。
◇
実際、シャルルのほかに死刑の執行された囚人を生き返らせることなど、誰にも出来まい。
薫が先に目覚めて、瀕死の兄の姿を見てまた発作を起こしては…という配慮も医療行為をスムーズにするためだと言い張る彼に、薫は素直に感謝した。
覚醒後の検査は、およそ1ヶ月続き、その間、薫は兄とは会えないでいた。
というのも、治療に使われた様々な薬の副作用で寝起きは最悪、目が覚めても吐き気や目まい、ひっきりなしに続く検査が終わったころには疲れ果て、死んだように眠るという毎日の繰り返しだったからだ。
そんな症状も軽くなり、昼間はしっかりと目が覚め、具合の悪いところもなくなった頃、薫はようやく兄の病室へ行こうと思う余裕ができた。
ドアのノブに手をかけ、ためらって、コクンと唾を飲み込む。
ノックもせずに、おもむろにドアを開けると、ベッドの上に兄の巽が座っていて、窓のほうを見ていた。
ささやかな風に揺れる髪、白いシャツにすける肌色、振り返る眼差しと微笑。
彼は無言でベッドの自分の隣の場所に薫を手招いた。
彼女はだまって隣に座る。その重みで彼の身体が自分のほうに傾いて近付き、肩が触れあった。
「具合、どう」
どんな感情よりも、まず一番に、ここにこうしていられる喜びにかすれた声で、薫は言った。肩が熱い。
「いいよ」
聞き慣れた、でも今までで最も近いところから、声が聞こえる。
まっすぐに顔を向けられないでいる薫に、巽は向き合うように座りなおして、今度は膝が触れた。
「おまえこそ、少し顔色が悪い」
指先でさりげなくあごをしゃくられて、薫は巽の顔をまともに見てしまった。
「こう毎日病人扱いされちゃ、いやでも気分が悪くなる」
焦ってその手を払いのけ、立ち上がった薫の後ろで、クスと巽は笑った。
穏やかな時間。他愛のない会話。一気に心を満たすものは、恋の成就への期待だった。
兄がこの状況について、何も考えていないわけがない。むしろ、このいつもと変わりない穏やかさは、すでに何かを決心しているためだろう。でなければ、薫に会おうとしないはずだ。分かっていた。でも、今だけ…
そう思って振り返ろうとした薫の肩に、巽がカーディガンを羽織らせた。と同時に、彼の両腕は彼女を背後から抱いた。驚いて半分後ろを向いたままの彼女の背中に、ぴったりと寄せられた彼の胸から伝わる鼓動が、はやい。
「薫…」
安堵や愛しさは言葉にならない。ただ名前を呼んで、両腕に力を込めるだけ。彼女が生きていることを確かめるように。
薫は、首筋に纏いつく髪の感触で我に返った。
彼の腕が直接触れず、カーディガン越しに肩から鎖骨を取り囲んでいるのに気付く。期待に負けて、兄の胸に寄り掛かりそうになっていた彼女の上半身が強ばった。
「薬の時間だから」
腕を解いて、身体を離す。動揺を押し隠すのが精一杯の顔で、部屋を出た。
抱擁はまだ、兄妹と恋人の狭間。いつ、どちらへ傾ぐのか。
◇
自分はさぞ物欲しげな顔をしていたに違いない。兄はそれに気付いたはずだし、また予想もしていただろう。その上で、一人で何を決めたんだろう。
「いっそ全身の血を入れ替えるか」
思い悩んで暗い顔をした薫に、シャルルが過激に呟く。
血のつながりさえ、愛しく、誇らしい。
すべてにおいて、兄を愛しているのに。
◇
「あなたはもう十分な刑を受けた。その後に何をしようが自由だろう。ヒビキヤ、どうしてカオルを愛さない?」
「愛しているよ」
「妹としてか、それとも…」
「どちらも」
「じゃぁ、なぜ」
「やり残したことを、再びできる機会をくれた君に、とても感謝しているよ。でも、激情にかられて抱き合えば、後悔する」
この余裕は何だろう。何も持たずに、日々の生活を人に頼る状況に甘んじるような人間ではないのに。
「オレは、これから出かけなければならない。しばらく戻って来られないだろう。治療は信頼できるチームを作っておいた。カオルはもちろん、あなただってまだ完全じゃないんだから無理をしないように」
早口で言い切ったシャルルを、巽はポケットに両手を入れて、上目遣いに見た。
「君も」
シャルルは目を見開いて、巽を見た。自分が命を賭した闘いに出かけようとしていることを、鋭くも見抜いた彼を。
「薫を治せるのは、君しかいない」
静かに、でも真剣に見つめ返す眼差しに、シャルルは生きて帰ってくることを約束させられたと思った。
◇
「ヴァイオリン?」
「そうだ」
あのとき以来、体調のすぐれぬ振りをして部屋に引きこもったままの薫のところへ、午後になってから巽がいきなりやって来た。そして、シャルルが発ったことを告げた。さらに、彼が戻ってくるまで、アルディ家所有のヴァイオリンのメンテナンスを兄が引き受け、薫にもそれを手伝えと言うのだ。
「僕も、おまえも、長く眠っていたせいで体力が異常に落ちている。少しでも身体を動かさないと」
久しぶりに見た兄のスーツ姿に、薫は思い出していた。
拘置所ではじめて面会したとき、襟元をゆるく開けた彼の作業着姿に胸が痛んだことを。
それが薫を素直にさせ、兄の言うことに頷いて承知させた。
本邸の中にあるヴァイオリンの展示室へ入り、ズラリと並べられたヴァイオリンを見て、薫は体中にあの音色が響きわたるのを感じた。と同時に、艶やかな、琥珀色の身にいつしか自分も溶けこんで弾いていた頃が、ずいぶん昔にも思えた。兄のことしか考えられないでいた薫の心に、ヴァイオリンが入り込んできて、音をまき散らす。嫌だった。
「奥は楽譜の部屋だ。原譜のコレクションと、ピアノがあるから、そこで音出しをしよう」
室内のもう一つのドアに目配せして、兄が言った。そして鍵束の音を立てて、ガラス張りの扉を開け、ヴァイオリンを薫に渡す。反射的に受け取ってしまったが、彼女は嫌悪に息苦しくなっていた。
無造作にヴァイオリンをぶら下げてピアノの前まで歩く。鍵盤を軽くたたいて音を確かめる兄につられて薫も弦を弾いて、音が出た途端、前のめりにグラッと倒れそうになった。
「どうした!?」
とっさに抱きとめた兄の胸の中で、涙がにじみ、ヴァイオリンが音を立てて落ちた。その大きな音に、不安がかきたてられる。強くつぶった瞼からこぼれた涙が、頬を伝った。
「い、やだ」
涙も、溢れ出す気持ちも、止まらなかった。
◇
スーツの裾を握りしめ、涙を見せまいと自分の胸に顔をうめる薫の背中に腕をまわして、巽はあのときの続きをする覚悟を決めた。大切に、慎重に、この子が壊れないように。
「言ってごらん。何が嫌なんだい?」
大きく息をついて、より深く包み込む。彼女の背中の力が抜けた。
「弾いたら、こいつだけ残して、兄貴がいなくなる」
人生の支えとして、自分の代わりに持たせたヴァイオリンだった。だが、薫にとっては、もうそれだけの、代替物というだけの存在ではなくなっているはずだ。それを忘れるほど、自分の刑が執行されたときの喪失の傷は深く、癒えていないのだった。
「いなくならないよ」
はっきりと言った強い声に、裾を握りしめていた彼女の手の力が緩み、指先が空を彷徨う。
それを捕らえて自分の背中にまわさせ、よりいっそう強く抱く。衣擦れの音が、その先へと煽る。
「ここにいる。そして…」
ぼかした語尾、頬の涙を拭った親指の後を、唇が追いかける。
「こうして触れている」
そのまま顎に指をおろして、少し、唇を開かせる。信じられないというように見開かれた目の前で、ゆっくりと瞼を閉じて首を傾け、口付けた。痛いくらいに甘い感覚が、ふたりの身体を貫く。しばらく呼吸も忘れて、相手の唇の感触に酔っていた。
「好きだ」
告白は、こぼれ落ちる熱い涙と、背中にまわされた手に込める力をもたらす。
もっと触れたくて、何度も何度も角度をかえて唇を重ねる。
溶け合いたくて、吸い寄せる音が、ふたりの吐息の中に響いた。
「…言って」
ねだるように口元に唇を寄せて囁く。
焦らされて、薫は言った。
「私も、…」
好き、は唇の動きだけで。
「ずっと、こうしたかった」
続いた涙声とともに、彼女からのキス。
しばらく、離れられそうになかった。
◇
ひと雫、心に染みて傷を癒す。やがて小さな水たまり、池、湖へと内包物を育てながら、海になる。
海は多くのものを生み出すだろう。その確信を得るために必要なのは、嵐を起こす強い風。
荒れ狂う波の痕に静穏が戻ったら、海は心に生き続ける。
―彼は、そのための最初のひと雫を彼女の心に落としたのだった。
◇
ヴァイオリンの音が聞こえる。のびやかな旋律は、職務に忠実なはずのアルディ家の使用人の足を止める。
それは豊かな音色。時には優しい思い出に浸り、時には愛情をのせた眼差しを交わし合うことができると期待し、確信した薫の豊かさだった。
「いいね」
うっとりと目を閉じた巽に彼女は満足し、息をつく。この顔へ戻って来られるなら、死ぬまで弾いていてもいい。
しっとりと汗で濡れた毛先を纏い、上気に染まる肌。彼は魅せられて感じずにはいられない、すべてを捧げてもいいと。
「次は?」
「いや、疲れただろう。それより、渡すものがあるんだ。待ってて」
横を通り過ぎるときに動いた空気が汗ばんだ肌に触れ、ヒヤリとする。少し、熱く弾いたかもしれない。その残り火が、さっきまで巽が座っていたピアノの前の椅子に身体を突き動かす。横長のそれに薫は上半身を伏せ、頬を押し当て溜息をついた。その瞳は、初めて抱きしめあってキスをしたときのふたりの姿を思い映している。
扉を開けて、巽は息をのむ。
彼女の潤む瞳が夢見るようで、心持ち開いた唇がなにかを求めているようで。
渇望の実が、ふたりの内で熟しきっていることは知っている。だから、踏み出すための、この贈り物をふたたび彼女に。
カタンと音をたてて、持ってきたヴァイオリンケースをピアノの上に置く。
「それ…」
物音で飛び起きて、薫は言った。見られていたことを知って少し頬を染めている。
「そう。おまえにやった、僕のヴァイオリンだ」
真珠色のその表面を見つめていると、様々なことが思い浮かぶ。
手紙の、兄の考えているだろうことについては、考えたくもなかった。まだ、夢を見ていたい。夢、なのかもしれない。
「弾いても?」
「ああ、もちろ」
そこまで言って、思わず巽の頬が緩む。こちらを見上げた薫の頬に、椅子の布地のひだ跡を見つけたからだ。
「?」
笑みを浮かべた口元を手で押さえる兄の視線の先が、自分の右頬だと気付いて、手をかざす。
「ここ」
とうとうクスと笑って、彼は彼女の頬に指先を触れた。
瞬間、電気が走ったかのようにはっきりと、薫の身体がビクリと痙攣した。
「―」
全身で兄を求める空想をしていた直後には、刺激だった。知られてしまったことへの羞恥よりも強く、恋しい気持ちがつのる。
巽は、頬に触れたまま、少し戸惑っている。制御しきれなさそうな情熱を託すヴァイオリンは、もはや白く眩しいばかり。
ほんのわずかな間の沈黙でも、何時間にも思えるほど長い。咽にこみあげるものを、どうやってぶつけたらいいのか、薫は術を知らない。
「薫…」
美しく耳朶に響く声に呼ばれ、薬指であごをしゃくられ、薫はたまらなくなって、目をつぶった。
そして、巽の手の甲に自分の手を重ね、導き、その指先をそっと唇に捕らえた。
誘い方を知らなくて、ただ一番そばにある彼を愛おしむその仕種は、したほうにとっても、されたほうにとっても、驚くほど官能的だった。
巽の指先がピクリと曲がる。濡れた唇が音をたてる。響く。痺れる。
「ごめ」
拒まれたと誤解して謝りかけた途端、さらうように抱き寄せる腕。
いつにない力強い抱擁に、薫の胸には悦びが広がる。
せつないくらいの愛しさにあふれた吐息をもらす唇が、髪に触れる。
「だれも、見てない」
首に腕を巻き付けて、ふたりはひとつの影になる。
「だれも、知らない、から…」
踵をおろして、おそるおそる、顔をのぞきこむ。わずかに乱れた髪が覆い隠す彼のその瞳は、暗い欲望をのぞかせていた。
少し、泣きそうなその表情に、キスしようとする自分を、薫は止められない。
しかし、それよりも素早く、深い口付けが、彼女を襲う。
「…んっ」
強引に顔を上向かせられて、背中は壁まで追い詰められる。唇は息つく間もなく、何度も塞がれる。
しばらくそのまま、指先まで痺れるほど、長いキスを受けていた。
やがて、カクンと薫の膝の力が抜けた。
「降参?」
恍惚とした顔をそのままに、自分を見上げて座り込む薫の二の腕を掴んだまま、巽は言った。
濡れた唇を、少しとがらせて、彼女は横を向く。目の前に向けられた白い首筋は、突然寒くなった唇を誘う。
じゃれるように、彼女の首筋に頭を擦り寄せてから、軽く唇を押し当てると、身体をふるわせた。
「…もう、止めてあげられないよ」
心の闇に、雷鳴が轟く。
◇
夕陽に染まる廊下を、薫は夢見心地で歩いている。この廊下が永遠に続けばいいと、思っている。
肩は巽の上着ごと、抱かれ、寄り添っている。指先は時折、何かを確かめるように唇に触れる。
本当は、手を、つなぎたかった。
いくつかの長い廊下と階段を過ぎ、使用人棟の最上階の使われていない一室へ辿り着いた。
鍵はかかっておらず、扉を開けた巽は、薫の手を引いた。懐かしく優しく、そして少し甘い仕種だった。
室内に屋根裏への梯子があり、先に上がった兄の手が差し伸べられる。見上げる妹の顔には無邪気な笑み。
狭い屋根裏部屋を隅々まで照らす大きな出窓には、市街が小さく収まっている。
ガタン、と音を立てて巽がその窓を開けた。冷たい風が差し込む。冷やさねばならなかった。
一方、薫は寒さを怖がるかのように、上着の前見ごろを掻き合わせる。何も、考えたくなかった。
「ここへ座ってごらん」
開いた窓を少しだけ閉めて、枠に腰掛けた巽が言う。
美しい夕暮れ時を見せたくて、言っているのかと思ったが、違った。
向いに、斜めに座った薫の頬を、いきなり冷たい指先の両手が包み、引き寄せたから。
「ちょっと待」
夕陽で明るい窓辺で風に晒され、隠すものは何もない。薫は躊躇った。
「見られてもいい」
早口で言った彼の顔が近付く。思わず引いた彼女の顎から鎖骨の窪みへ、唇が滑り落ちる。
肌に生暖かいものを感じた薫は驚いて、巽の頭を持ち上げる。唇が離れた場所に、風が吹く。
「寒い」
見つめた窓を乱暴に閉じる腕。背中を支えるように抱き直す腕。
「今だけだ」
情熱は、触れ合う箇所から伝播してゆく。
◇
重なり合う肌が心地よい。
唇に、項に、肩に胸に、想いのままに散らばせた刻印に、息遣いも荒くなる。
幾度も切ない吐息を漏らした唇は、開いたまま。瞳には涙をため、こぼすまいと必死に上を向いている。
「我慢、しなくていい」
末期への甘い陶酔を味わえるのは、自分だけ。
彼女は自らの意志で、心に迫り来る哀しみと恐怖を、身体を侵す快楽に変えることは出来ない。
「泣いていい」
下肢へと移る唇から、くぐもった言葉。
足の付け根から、膝の裏へと撫で上げる指先。
「あっ」
涙が零れ落ちる。
巽は、膝の内側に口付け、薫の涙を唇で拭う。胸が、重なる。
「…や」
勢いづいて膝が上がる。快楽に濡れた音をかき消そうとする弱々しい声。
口付けが深くなるたびに触れる、情熱の中心。
「愛してる」
重ねた唇の上の囁きは、繰り返され、
「薫、かおる、かおる」
一気に沈む巽の身体に、薫は声を失った。
◇
けだるさの中に残る喘ぎ。指先さえも破裂せんばかり。もてあましている。
寝息をたてる妹の横顔がつぶやく声は、暗く、重い雨雲を呼ぶ。
「にい、さん…」
激しい雷雨。嵐となるだろう。
◇
シケイハ、マダ、オワッテイナイ
「!」
不吉な直感に目覚めた薫は、カーテンの向こうに、風になびく影を見つける。
近付こうとすれば、昨夜の爪痕が疼く。確信させる。夢は、終わってしまった。目を醒まさなければよかった!
床に叩きつけたてのひらから、心に、ひびが入ってゆく。
バンという音に振り返った影。窓枠に取りすがる手。
「…いや」
止めようとするのに恐怖で目がかすむ。
「いやだ」
拳に握りしめて白くなる指先、かなしいほどかすれた咆哮、頬には幾すじもの涙。
「兄貴!」
屋根のへさきに立ち上がった巽に、悲鳴のような嘆願。
◇
愛しい人の、その涙は永遠に自分のものになるだろう悦びに、彼の心の奥はうちふるえる。
穏やかすぎる微笑のわけは、生涯一度の言葉を今、投げかけることができるから。
「おいで」
薫は目を見開く。
彼女の盲目的に望む恋の成就と、彼の見据えた未来への望み。くい違いはこんなにも鮮やかだ。
わずかに畏縮した彼女を見止めて、彼の愛は、解放を迎える。
カオル、イツマデモ、アイシテイル
呪文を唱えて。
手を差し伸べたまま。
空に、揺らぎ倒れる身体。
「待っ、」
届かない指先。
(行かないで!)
声にならない叫び。
髪の先を最後に、見えなくなった、その姿。
愛の始まりを告げる嵐は、薫の心の海をかき乱し、瞳は波底の群青色のように虚ろに変わる。
空に乗り出せば、涙がいくつも彼の後を追い、身体は吹き上げる強い風に抱かれるよう。
「おいて、いかない、で」
その先には、しがらみのない、魂だけの甘美な世界が待っている。