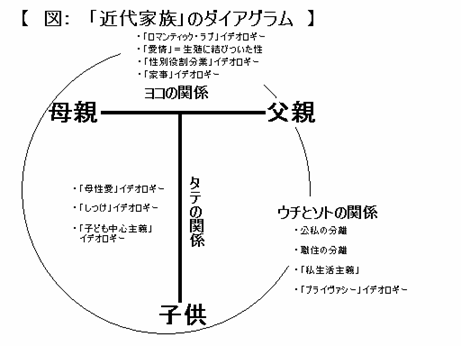家族・社会学・無気味なもの
石飛和彦
0:はじめに
「家族」について、社会学的な視点からは何を見ることができるだろうか? 例えば、「こころと家族」という主題 − これは、筆者が参加しているリレー形式の講義のテーマでもある − をめぐって、社会学的な視点は、わたしたちに、何を見せてくれるだろうか? 本稿は、その見取り図を素描することを目的とする。
1:「家族」という現象
まず、出発点となるのは、そもそもわたしたちがごくふつうに「家族」についてどう見ているか、ということだろう。そこで、上で触れた講義で受講生に書いてもらった小レポートの答案から、それを読み取っていくことから始めよう。
1−1:「家族」のイメージ
この小レポートは、筆者の授業の第一回のはじめに実施したもので、論題は、「「家族」とは何か、定義しなさい」というものだった。その際、「授業の第一回なので、専門的な定義はまだ知っていなくてもかまわないので、自分の考えたように書いてください。なるべく面白いことを書いてくれると面白い」と言い添えた。すると、例えば次のような答案が集まった(より多くの例については【資料】を参照):
・「家族」とは、両親がいて、その子供がいて、お互いに支え合って、一番信頼のできる存在。そして、一人一人が必ず持っているもの。自分自身の一番大切な存在。
・家族は社会の中で、一番小さい集団であって、生き物にとっては、とても大きな存在であると思う。家族は、血のつながりのある人間同士の集まりだけでなく、まったく血がつながっていなくても、家族といえる。世の中には、色々な形や様子の家族があると思うが、私の中での家族は、「私」を受け入れてくれて、「私」の居場所があり、包み込んでくれるような、あったかいものに感じる。
・愛し合う男女が結婚して子供が産まれ、みんなが支えあいながら生活していくもの。他の何にも代えられないほど大切なもの。
・家族とは子どもの小さい頃の生活環境の土台となる存在である。親は家族のために働き、子どもに学校に行かせ養っていかなければならない。そういった事よりも家族に精神的に支えられる部分も多いはずだと私は思う。
・私の立場から見たら、父、母、兄弟、祖父母などが一つの家に集まり、父は社会で働き、母は家事をし、父の稼ぐお金で家族全員が生活すること。また子供は、父から援助され、学校へ通い勉強する。家族全員でよりそい、互いに助け合うということだと思います。
これらの答案から見て取れる第一の点は、これらの「定義」が非常に均質な一定のパターンを反復している、という点である。すなわち、家族とは、一般的には両親と子どもからなる小集団であり、しかし血のつながりより心の絆が重要であり、お互いに支え合い信頼し合うものであり、夫婦、親子が互いに無償の愛情を与え合い、特に親は子どもを無償の愛情をもって育て、そのなかで人の成長が決まる場であり、暖かな居場所であり、・・・等々、というわけである。あるいはまた、「家族は言葉にできない心のつながりだから、ひとそれぞれだし、形の上での定義などできない」という言い方じたいもまた、均質に出現する。この均質性は、小レポート実施時に「自分の考えたように書いてください」とあらかじめ指示していたことを考慮すれば、それ自体、興味深いひとつの社会学的な現象である。すなわち、学生たちは、「自分で考えて」書いたにもかかわらず、互いにきわめて似通った、ある「家族」のイメージを、過不足なく再現しているのである。
1−2:「近代家族」のイデオロギー
これを、社会学的な視点からは、さしあたり、「イデオロギー」と呼ぶことができるだろう。「イデオロギー」という概念じたい、すっきりとした定義がむずかしい術語なのだが、さしあたりここでは、「ある社会が成員に供給し、それによって成員を捉えている、一定のパターンに型付けられたものの見方・考え方」という程度に理解しておこう。そして、そうした「イデオロギー」の中でも、ここで学生たちが捉えられているのは、いわゆる「近代家族イデオロギー」である、ということができる。小レポートから読み取れる第二の点は、わたしたちがごくふつうに「家族」を見る際に捉えられている、「近代家族」というイデオロギーの姿である。
現代社会の家族を「近代家族」として捉えて分析する、という視点は、現在の家族社会学ではほぼ不可欠のものとなっている。この「近代家族」という概念もまた、それじたいすっきりした定義がむずかしいのだが、さしあたりここでは、次のような簡便な図式を描いておくことにする(【図】参照)。
夫婦とその子どもからなるこの三角形的な図式は、いわゆる「核家族」の構造を持っている(ただし正確には、「近代家族」の定義に「核家族」を含めることには議論の余地が大きい。明治期以来の「家」制度との関わりも含め、日本社会の「近代」と「家族」を検討する際の重要な論点となっている。落合(2000)参照)。この三角形は、3つの関係軸からなっている。まず、夫婦(父親と母親)を結ぶ「ヨコの関係」。次に、両親と子どもを結ぶ「タテの関係」。さらに、家族の三角形と外界を結ぶ「ウチとソトの関係」。この3つの関係軸それぞれに、「近代家族」のさまざまな要素が組み込まれている。例えば、上に引いた小レポートの「愛し合う男女が結婚して子供が産まれ」云々、という文言は、夫婦を結ぶ「ヨコの関係」が、ひとえに男女間の「恋愛感情」を起源に持つものだ、という「ロマンティック・ラブ・イデオロギー」のヴァリアントだと見ることができるだろうし、また、恋愛感情と性と生殖とが一致するという「夫婦愛」のイデオロギーの表現でもあるだろう。また、「家族とは子どもの小さい頃の生活環境の土台となる存在である」云々、という文言は、親子を結ぶ「タテの関係」こそが人間形成の重要な場である、という「しつけ」イデオロギーと呼ぶべきものを示している。「父は社会で働き、母は家事をし」という文言はやや当世風ではないが、「性別役割分業」のイデオロギーを誇張して示している。男女の役割は異なっており、そのために家族の三角形的図式もまた左右対称ではなく、より妻=母親側にシフトし、妻として「家事」を取り仕切り、また母親として「母性愛」を示して子どもと家族全員を包む、という役割を当てられる。一方、夫=父親は、家族のウチとソトの両側を行き来する位置に置かれる。従って、同時に、「社会で働き・・・家族でよりそう」という文言は、「ウチとソトの関係」を正確に示している。すなわち、「家族」はいわゆる「社会」から分離された、互いの愛情で満たされた「私生活」「プライヴァシー」の場であり、「ソト」で過酷な労働と競争を生きた者が「ウチ」で癒される、という構図が、やはりイデオロギー的に表明されているのである。学生の小レポートは、書き手のほとんどが(意識してか否かはともかく)自分を「子ども」の立場に置いているために、特有のバイアスはかかっている(例えば、「家族は一般に血がつながっているものの集まり」という言明は、夫婦という「血がつながっていない」関係を忘却している、等々)が、それでも、約200人の受講生の小レポートは総体として、ひとつの「近代家族」図式を構成する諸「イデオロギー」を、きれいに浮かび上がらせている。
これらの「イデオロギー」は、まさに「イデオロギー」でしかない。すなわち、社会成員(ここでは、学生)のあいだではまさに自明で自然なこととしか感じられないにもかかわらず、具体的な事実の次元(例えば、アリエス(1960=1980)以降の歴史学の成果が際立っている)では容易に反証され、ただ私たちの属しているこの社会の内部において、その主観的な構成要素として、初めて存在しうる。にもかかわらず、そうした事実をこの社会は私たちに見せようとせず、代わりに、暖かい「家族」のイメージを与える。このイメージは、私たちの感性のすみずみにまで浸透し機能している。例えば、同じ小レポートの答案に次のようなものがある:
・家族は、ラーメンである。父親が麺である。母親はスープである。子供は、具である。器は家である。親は子を乗せ、子は親を美しくする。家は家族をばっちり包むのである。
ここに描かれている、暖かい湯気の出るラーメンのイメージは、同時に、完全に「近代家族」の三角形的な図式を反復している。このことは、「近代家族」のイメージが、それと気づかれることのない比喩形象の次元にまで浸透して私たちの感性を操作しているということを示すだろう。学生の小レポートに現れる「近代家族」のイメージは、このような意味において、強力な「イデオロギー」だといえるのである。
さて、ここで社会学は、こうした「イデオロギー」を、どのように扱うか? 「イデオロギーは事実と違うマボロシなのだから、とにかく事実を追求しよう」 − というのが、一つのアプローチである。しかし同時に、この「イデオロギー」そのものに注目する、という視角が重要である。歴史的にどれだけ限定されているにせよ、この「近代家族」こそが、ほかならぬこの時代のこの社会に生きる私たちにとっての「家族」なのだ。この社会がこの「家族」を私たちにどのように供給し、私たちがどのようにそれに捉われ、それによってこの社会がどのように円滑に運転しているか、を見ていくこと、事実を土台にしてではなく虚偽を歯車としてこの社会がいかに作動しているかを見ること、これが社会学のイデオロギー論の、独特のリアリスティックな視角だといえる。
こうした視角をさらに肉付けしていくために、次節では、補助線として、「家族」に関するいわゆる「社会構築主義的アプローチ」からの研究、グブリアム&ホルスタインの議論を参照しよう(グブリアム&ホルスタイン(1997);苫米地(2002))。
2:「語られるもの」としての「家族」 − 「構築主義」的アプローチ
2−1:グブリアム&ホルスタイン『家族とは何か What Is FAMILY ?』
「社会構築主義」の視角からアプローチするグブリアム&ホルスタインは、「家族」というものを「イデオロギー」というよびかたでは扱わないが、やはりイメージの次元における「家族の言説 FAMILY discourse」として扱っている。
彼らはその著書の第1章で、SF小説のような舞台を設定する。登場人物は、家族社会学者キャスウェル博士と、異星からやってきたサイボーグの「ボーグ」。「家族」というものは歴史・文化的に様々な形をとりながらも人類にとっては一貫した構造と機能とを有しているのだ、ちょうど新旧大小さまざまのテーブルがすべて「テーブル」であるのと同じように、と主張する博士に、ボーグは反論する:
「でも、キャスウェル教授。私にも、そして学生たちにもテーブルは見えますが、私は「家族」[the family]はおろか、どんな家族[family]も見た覚えがありません。あなたがこのテーブルを見本にして別のテーブルを探してほしいといえば、私はたぶん別のテーブルを見つけてくることができるでしょう。でも、あなたが一組の家族を見せてくれても、あるいは何組分かの家族の写真を渡してくれても、テーブルの場合と同じようなやり方で、他の家族を見つけることはできないと思います。」ボーグは、自分が地球上をブラブラ歩き回ったときにも、家族など目にしなかった。ただ、たくさんの人間を見ただけだったと付け加えた。 / キャスウェルは、授業で使っている家族社会学の教科書を手に取った。たいていのその種の教科書と同じように、そこには多彩な文化的、歴史的出自を示すさまざまな家族と世帯の色鮮やかな写真が載っていた。キャスウェルはその本のあちこちを開いて、ボーグにこれらの写真が、さまざまな形の家族を見つけ出すという彼女の使命の手引きになるだろうといった。 / 旅立つ前に、ボーグは、その写真の中に見えるのは人間と家だけだと繰り返した。教室や街角で目にしたのはたくさんの人間と家だけだったが、教科書の写真の場合も同じことだというのだ。ボーグは、どうすれば任意の人間の集まりから、家族を構成する人間の集まりを区別できるのかといぶかった。・・・
(邦訳書、p.5.)
このような問いの立て方から出発して、「家族が人間たちにとって何であるかは、家族ということばが彼らにどう 使 わ れ る か によるのではないでしょうか」という見解に到達するボーグは、要するに、ヴィトゲンシュタイン的な立場をとっているといえるだろう。著者たちはそこから「構築主義者」の視点を導く:
人びとが言及するものを「見る」ためには、彼らがどんなふうにことばを使い、自分たちの社会関係を記述するのかを、とくに彼らの記述に影響を与える諸要因に注意を払いながら聞かなければならない。ボーグはうっかり、キャスウェルを正面から見据えて、「キャスウェル、見るためには聞かなければならないのですよ」といってしまった。
(同、p.12.)
さて、大略このようなやりかたで、グブリアム&ホルスタインは、「家族」研究の視点を、具体的なあれこれの家族(物象化された、という含みで定冠詞をつけて「the family」と書かれる)の様態にではなく、「家族の言説」に置く、というわけである。
こうした「構築主義」の研究方針は非常に強力である。例えば、前節で紹介した学生の小レポートで繰り返し出現した論点、「家族は、血のつながりのある人間同士の集まりだけでなく、まったく血がつながっていなくても、家族といえる」という論点を、クリアに扱うことが可能となっている。ある人たちにとっては血のつながった親子兄弟が家族であるが、別の人たちにとっては、離婚と再婚を経て直接血のつながりのない人たちの集まりが家族であり、あるいはペットもまた家族であり、あるいはながねん同居している遠縁の親戚や、血縁関係のない親友、あるいはマフィアの”一家”の親分子分兄弟分の関係もまた家族であり、また、「老人”ホーム”」に入居した者にとって、残してきた子どもたちの家にではなく”ホーム”の中にこそ家族があることもあるだろうし、また、ある場合には、血がつながっているにもかかわらず(あるいは同居しているにもかかわらず)「あんなやつは家族ではない」と絶縁することもあるだろうし、また、形の上での家族を保ちながら家庭崩壊状態に陥って「こんな状態では本当の家族とは言えない」ということもあるだろう。こういったケースのすべてを、「構築主義」の視点は、等しく「家族」の現象として捉え、そこで「家族」という言葉=「家族の言説」がこの社会のさまざまな場面においてどのように「語られているか」を辿っていくのである。
また、この「構築主義」の視点は、「家族」を社会学固有の次元で捉えようとするものでもある。つまり、この視点からは、「家族」の現象を心理の次元で捉えることの困難が見えてくるのである。たしかに、「家族」は具体的客観的な次元で存在するわけではないというのなら、すぐさま思いつくのは、「心の中で「家族」だと思っている集団が「家族」なのだ」、と言いたくなる。だが、私たちが実際に出会うケースに当たってみれば、例えば、夫は「家族」のために働いているつもりでも妻や子どもからは「家族」とは思われていない、あるいは、他人から見れば「家族」と思われなくても自分たちは「家族」と思っている、あるいは、ある人たちを「家族」と呼ぶ場合に様々な意味が時と場合によって使い分けられる、等々 − ようするに、「家族」であるかないか、それはどんな「家族」であるか、ということは、誰かの「心」の中を探っても、見つからないものなのである。それは「心」の中にあるというより、互いに「語り」合い、「記述」し合うという社会的な言説流通プロセスの中にはじめて浮かび上がるものだ、というわけである。
さて、では、そのような「語り」の次元において − 「家族」とは何だろうか? グブリアム&ホルスタインは、まず、「家族」イメージが3つの大きな想定を含んでいると言う。第一に、「大文字化された「家族」」、すなわち、「家族」は個々のメンバーから独立したそれ自体の存在であり、家族一人一人が「家族」の命令に従わなければならないような、また、「家族」の雰囲気・気分・空気によって一人一人が深く影響されるような、いわば独自の生命をもっているような存在である、という想定がそれである(先の学生の小レポートでいえば「「私」を受け入れてくれて、「私」の居場所があり、包み込んでくれるような、あったかいもの」「家族とは子どもの小さい頃の生活環境の土台となる存在である」といったイメージの側面)。第二に、「世帯[household]」、すなわち、「家族」のもっとも真正な所在地は「家」であり、家族メンバーが外でどのような社会生活を営んでいようとそれとは関係なく、やはり「家族」は「家」を基盤にする、というわけである(小レポート「家族とは、自分が家に帰ったときに安心できるもので」といったもの、あるいは逆に、「一緒に暮らしていても血縁関係がなくても「家族」であったり、離れて暮らしていても血縁関係であれば「家族」であったり」といった言い方)。第三に、「特権的なアクセス」、すなわち、「家族内の本当のことは家族にしかわからない」、という想定(あるいはその逆に、「家族の中にいるために”逆に”客観的になれない」というひとひねりした言い方)がある(小レポートでいえば、「こちらからはたらきかけなくても、相手のことがわかる以心伝心みたいな感じ」「一番の素の自分が出せる場所」といったもの、また「家族にはいろんな形や、事情やいろんなものがあって」という言い方)。
こうした一群のイメージをともなって「家族」は「語られ」る。しかも、それはただ単に漫然と「語られ」るわけではない。ふだんならあまりになじみぶかい[familiar]ものとしてわざわざ口にだして「語られ」ない「家族」が「語られ」るとき − それは、私たちが社会生活の中で、「家族」というものが問われ[challenge]るときである。ここでグブリアムとホルスタインは、医療施設や社会福祉施設(ナーシング・ホーム、情緒障害児のための居住治療センター、リハビリ専門病院、アルツハイマー患者の介護者のための支援グループと自助組織、地域精神保健施設、等々)を中心とした彼らのフィールドワークからの豊富なデータを援用する。痴呆の妻の介護にすべての時間を奪われる夫は、自分の顔さえ忘れてしまった妻を見て、また、近所に住みながら(あるいは遠方に住むために)救いの手を差し伸べない子ども達を見て、「家族とは何か?」と問い直す。あるいはそうした両親の「家」を訪れた子どもが、掃除にまでとても手が回らないために「竜巻が通り過ぎたように」散らかり荒廃した部屋の様子を見て「ここにはもはや「家庭」は残っていないのではないか?」と問い、それに対して父親は「掃除など問題ではない、ここが私たちの「家庭」なのだ」と答える − 前節で紹介した学生の小レポートは授業の課題という人工的なセッティングの中で書かれたものであるが、グブリアム&ホルスタインが描き出すのは、このような現実社会のいたるところで日々「語られ」続けている、現実的な「家族の言説」である。
それゆえに常にこの「家族の言説」は、それぞれの「語られ」る社会的場面の位置する社会的組織の中に「埋め込まれ」ている。たとえば、家族メンバーのあいだでは、痴呆の妻を「自分たちの家で」最後まで介護することこそが「家族」のつとめである、と語るかもしれない。一方、その同じ家族を、医療専門家は、現実を否認し続け混乱し真正さを失った状態と見做すかもしれない。その場合には、むしろ、「現実を受け入れ」て医療専門家の介入を受け入れることこそが、本当の「家族」の回復である、というふうに「語る」かもしれない。あるいは例えば、ある精神科の患者の措置入院の判断を下す審理において、地域精神保健センターで彼の主治医をしている医師は、精神医学的な知の制度的文脈を背景として、患者の回復は地域の環境の中で「家族」のもとで生活してこそ進む、と主張するであろうし、一方、判事は、司法的な知の制度的文脈を背景として、患者が深刻なトラブルをもし起こした場合にその「家族」は責任を取って対処できるか、という観点から反論する − それによって、患者とガールフレンドと二人の間に生まれた子ども、ガールフレンドのおば、という4人の生活が、患者の回復プログラムを支援する「家族」と看做されたり、逆に、患者の起こしうるトラブルにとうてい監督責任を取りえない人たちと看做されたりする。このように、ひとことで「家族の言説」といってもその意味内容は、それを「語る」者の位置や利害関心、その場の組織文脈等々によって異なるのであり、さらにそれらがしばしば互いに争いあい、巧みに接合[articulate]しあい、その場ごとの「家族」がそこに実践的に達成され、場面ごとに効力を発する。さらに、そうした「家族の言説」は、一般的なものとして社会に流通することにより、逆に、あるべき「家族」の姿として、私たちを社会的に統制することにもなる − 訳注に挙げられているケース、ヒラリー・クリントンが選挙期間中にどれだけ「家族責任を放棄する女」という攻撃と戦わねばならなかったか、というケースがわかりやすい例だろう。
まさに、「家族」は「家」の中に存在するのでも「心」の中に存在するのでもなく、それが語られ流通する社会のいたるところの組織の中に、多様な形で、存在するのである。グブリアム&ホルスタインの「構築主義」アプローチによれば、「家族」を理解するとは、したがって、それらの社会的場面に注目し、その組織の諸力の中で「家族の言説」がいかに織り上げられ、いかなる効力を発しているかを辿ることにある、ということになるのである。
2−2:課題 − 「familiarなもの」の射程
こうしたグブリアム&ホルスタインのアプローチは、新たな具体的な経験的研究にそのまま利用することのできる、非常に強力であり実践的なものである。しかし、それでは以上の議論がそのまま、「家族」を見ていこうとする者を十分に納得させるか、というと、かならずしもそうはならないように思われる。
非常に直感的に言うならば、「これは本当に、私たちの「家族」についての研究なのか?」という疑問が、当然出てくるだろう。福祉や医療の領域で採集されたフィールドデータは、確かに著者たちの議論には適合するが、「しかし、それは特殊な家族の話」あるいは「アメリカのように「家族」が崩壊した社会の話」であって、「私たちの「家族」はふつうの家族なので疑いを持たなくていい」「家族を信じられない著者たちの主張はとても哀しい」「やはり家族は信じあい支えあうことではじめて本当の家族となるのだ」という具合に。
より内在的にグブリアム&ホルスタインの議論を辿るならば、そうした直感を何が誘発しているか、理解できる。異星からやってきたボーグを登場させ家族社会学者キャスウェル教授と対決させた序章によって、彼らは、「家族」というものに対する懐疑主義的な視点を設定している。「家族」とは私たちが当たり前に感じているようなものではなく、じつは「言説的に構築されたもの」であり、その意味内容はその言説が用いられている社会文脈によって多様であり、したがって、「家族」を理解するには、私たちの馴染んでいる「家族そのもの」ではなく、「家族の言説」の語られる社会的な過程にこそ照準しなければならない・・・という著者たちの議論の全体は、まず序章の中でボーグとキャスウェルに論争をさせ懐疑主義的な視点を確立することによって成立しているのである。ところが、かりにこのキャスウェルが学者ではなく、「ふつうの人」だったら、この序章は − つまり、著者たちの議論の視点の設定、ひいてはその議論の全体は − 成立しなかったのではないか。ヴィトゲンシュタイン流の懐疑主義を経由して「家族」の定義をその言語的用法のうちに見る、という視点の設定は、それ自体、非常に論理的な操作である。キャスウェルが学者であったからこそ、ボーグとのそうした「論争」に巻き込まれることができたのではないか。「ふつうの人」にとっては、「家族」をそういうふうに論理的な操作の俎上に乗せようとすること自体が、非常識のしるしである(あるいは、ヴィトゲンシュタイン流に言うならば、「それは別の言語ゲームに属する」のである)。そこで、「ふつうの人」からは、「異星人」や「社会学者」は歪んだものの見方をする、やはり「ふつう」ではないのだ、というトートロジカルな反応を誘発するしかなくなってくるのである。
いうまでもなく、「ふつうの人」のそのような感覚こそ、まさに「イデオロギー的」である。その感覚の中には、「私たち=ふつう」「異星人・社会学者・精神病患者・アルツハイマー患者・・・およびその家族=特殊」という形で、常識的想像力の地平からの異者の排除の力学が含まれており、その排除を施した上での「私たち」のありようだけを「自然」とみなすような仕組みが成立している。著者たちの「構築主義」的「家族」論は、そうした「ふつう」のイデオロギー的な力学に対して十分な戦略を持っていただろうか?
著者たちは、同書「まえがき」で、次のように言う:
過程と家族の言説とに焦点を合わせることによって、私たちが読者に示したいのは、いかになじみ深いもの[the familiar]が自明視されてしまうか、ということである。家庭内のシーンから法廷での審理やアルツハイマー病患者の支援グループの会合にいたるあらゆる場面で、日常の行為(実践)において何が家族と受け取られるかは、決して固定された変化しないものではなく、日々の生活の条件や理解からその意味が引き出されるのだということを、私たちは知る。私たちは、家族について語ることを通じて、家族のさまざまな意味を具体化し、現実化するのだといってもいいだろう。私たち著者のねらいは、家族的なものの領域の中で、語りと意味と具体的な現実との間にどんなに密接な関係があるかを明らかにすることである。
(邦訳書、p.iii-iv.)
著者たちがここで(あるいは同書の中で幾度も)、いわば掛け言葉として用いているように、「家族的なもの=馴染み深いもの=the familiar」である。「構築主義」は、さまざまなモノや現象をとりあげ、それらを人々がいかに「familiar」だと見做しているかを確認したうえで、それが「社会的に構築されたものである」と視点を変更してみせ、「いかになじみ深いもの[the
familiar]が自明視されてしまうか」を示してみせる:
家族の秩序が社会的に構築されるのなら、家族を記述する日常の行為の研究者である私たちの課題は、数多くのバージョンを持つ家庭の現実を、その記述に使われるさまざまな言語と、それによって世帯の真実が産出される過程へと「脱−構築」することである。脱構築は、一種の逆もどりの作業である。それは、現実が構築される過程を明らかにしながら、自明視されている日常生活の社会的現実から、それを作り出す記述という行為へとさかのぼる。私たちが家族の言説と記述という行為を分析する目的は、世帯内の事柄が世帯内の事柄として公共的に認識され、理解される仕方を 目 に 見 え る も の に す る ことである。
(同、p.59.)
その意味において、「構築主義」は、「家族」を扱うかいなかにかかわらず、「familiar」なものを対象とし、それをあらためて知的な懐疑論の俎上に載せることを条件として成立しているといえる。このことは決定的に重要ではないだろうか?
グブリアム&ホルスタインのように「構築主義」的アプローチを「家族」に応用する、というより、むしろ「家族的なもの=馴染み深いもの=the familiar」というものの中に、「構築主義」の対象と「構築主義」の成立条件とがそっくり含まれているのではないだろうか?
次節では、この点について、フロイトの「無気味なもの[Das Unheimliche]」(1919)という小論を参照しながら検討してみよう。
3:家族・社会学・無気味なもの
3−1:「heimlich/unheimlich」という構図
私たちが「無気味」と感じるのはどのようなものか? 私たちが「無気味さ」を体験するメカニズムはどのようなものか? − フロイトは、「無気味なもの」という小論において、このような問いを立て、答えようとしている。そのさい、ひとつの手がかりとなるのが、「無気味なもの=Das Unheimliche」という語そのものである。「heim」、すなわち英語で言う「home」という語を基にしたこの単語について、フロイトはまず次のように言っている:
ドイツ語の「無気味な」unheimlichは明らかに、heimlich[秘密の・家庭の]、heimisch[故郷の・気がおけない]、vertraut[親しい・熟知した]の反対物であり、したがって、何事かが恐ろしいと感ぜられるのはまさにそれがよく知られ馴染まれて い な い からである、とただちに結論を下すことができる。
(邦訳書、p.323.ただし独単語の訳注は簡略化した)
本稿の文脈にひきつけるならば、「unheimlich」とは、ほぼ「unfamiliar」と置き換えることができる語であり、「家族的な=馴染み深い=familiar」(ないし「at
home」)の否定形、と理解することができる。
ところが、フロイトはそこからさらに分析を進めていく。「無気味の心理学」の著者イェンチュを批判して次のように言う:
イェンチュは、大ざっぱにいえば、無気味なものの、新しい・親しまれないものにたいするこの関係のところで立ち止まってしまった。彼は、無気味な感情の成立するための本質的条件を知的不確実さの中に認める。無気味なものとは元来いつも、人がいわばそれに通暁していないような何ものかではなかろうか。人間はその環境に通じていればいるほど、その環境中の事物や出来事から無気味という印象を受けることが少ないであろう。これがイェンチュの考えである。/この定義が不十分であることを判断するのはたやすい。われわれはだから無気味なものイクォール親しみのないものというこの方程式を越えて進んでいってみよう。
(同、p.324.)
フロイトは、「heimlich」というドイツ語の古い用例を調べ、次の点に注目する:
・・・われわれにとってもっとも興味深いのは、heimlichという語が、その意味の幾様ものニュアンスのうちに、その反対語unheimlichと一致するひとつのニュアンスをも示しているということである。すなわち、親しいもの、気持ちのいいものdas
Heimliche が、気味悪いもの、秘密のものdas Unheimliche となることがそれである。たとえばあのグツコーの例をみていただきたい。「われわれはそれをunheimlichというのですが、あなたはheimlichというのですね」 そこで、われわれは、この語heimlichは一つの意味しか持っていないのではなく、二つの表象群、すなわち、親しいもの・快いものと、秘密にされているもの・隠されているものという二つの表象群に属し、これら二つはたがいに対立的ではないが、互いにまったく無縁なものだという事実に注意させられる。unheimlichはただ第一の意味の反対語として使用されるだけで、第二の意味の反対語としては使用されることがない。この二つの意味のあいだに何かの発生史的関係を想定することができるかどうか・・・先の引用文中のシェリングの言葉 − [隠されているはずのもの、秘められているはずのものが表に現れてきた時に、なんでもすべて無気味な(unheimlich)と呼ばれる(シェリング)] − に注意を向けたい。・・・これにしたがえば、無気味とは、秘密で、隠されているべきはずのものが外に出てきてしまったような、そういったもの一切のことだというのである。
(同、p.333.)
こうした語源学的探索からフロイトは、「このheimlichという語は、一種の両立性にしたがってその意味を発展させた言葉であって、ついにはその反対語のunheimlichと合致するにいたるのである。unheimlichはつまりheimlichのある一種類なのである」(同、p.334.)という命題にいたる。すなわち、もともと「馴染み深さ」と「無気味さ」のアンビバレントな混合体としてあったheimlichという語が、その言語的発展の過程において二つの意味を分離させ、ついに「無気味さ」のほうの意味が分離独立されて「unheimlich」という語が成立し、もとの「heimlich」はもっぱら「馴染み深さ」のニュアンスを主に強調され、あたかも「heimlich/unheimlich」が対立項であるかのように整除された、というわけである。unheimlichという語の接頭辞[un]は、フロイトによれば、こうした過程において刻み込まれた「抑圧の刻印」(同、p.350.)なのである。
グブリアム&ホルスタインが、「家族的なもの=馴染み深いもの=the familiar」に対して異星から来た懐疑論者ボーグを対決させることで設定した「構築主義」の議論の地平は、いわば、イェンチュが提示した「heimlich/unheimlich
= 既知/未知」という対立軸を基にしているといえるだろう − 家族とはほんらい多様なものであるが、「家族の言説」は唯一の「家族」だけを「真理」として「構築」し自明化してしまう、そこで、その「構築」の過程を「脱構築」(逆もどり!)して、それほんらいの多様性・相対性へとさしもどす、というわけだ。
しかし、私たちは、フロイトに倣って、「heimlich/unheimlich = 既知/未知」という構図そのものを産出する「家族/無気味なもの[Das
un/heimliche]」にこそ、注目することにしよう。
3−2:認識主体の成立と近代家族の三角形
上に辿ったような語源学的探求をおこなったうえで、フロイトは、実際に「無気味」という印象を与える事物について精神分析的な視点から検討している。その際、E.T.A.ホフマンの卓越した幻想物語「砂男」が大きな手がかりを与えている。フロイトによる「砂男」の巧みな分析の手つきについてはフロイト自身のテキストを参照されたいが、本稿の文脈上興味深いのは、フロイトがそこから導き出している結論である。
「この小説の中心点には・・・この小説の題名にもなっているモティーフ、重要な箇所では絶えず繰り返し出てくるモティーフ、すなわち子供の眼玉を抜く砂男というモティーフが立っている」(p.335.)「無気味の感情は直接砂男という人物に、したがって、眼玉を奪われるという観念に密着しており、そしてイェンチュの意味における知的不確かさは、この効果となんの関係もないことは明らかであろう」「われわれは、詩人がわれわれ自身にもあの怪しい眼鏡売りの望遠鏡、あるいは眼鏡を通してものを見させようとしていることに気がつく。いや、彼自身がかつてはこういう器具でものを覗いて見たことのあるらしいのに気づくのである。小説の結末は、かの眼鏡売りコッポラは実は弁護士コッペリウス、したがって砂男であったことを明らかにしている」(p.338.) − そして:
精神分析上の経験は、子供が持つ不安の中に、眼を害いあるいは失うという、恐ろしい不安があることをわれわれに教えている。・・・ところで、夢、空想、神話などを研究してみると、眼を失う不安や失明する不安は、しばしば去勢不安の代理となっていることがわかる。神話の犯罪者エディプスが、自分の手で自分を失明させるのは、贖罪法にしたがって彼に課せられることになっていた去勢の罰に対する軽減にすぎない。・・・
いったいなぜここで失明不安が父の死ともっとも内密な関係を保っているのか・・・なぜ砂男はいつも恋愛の妨害者として登場するのか・・・この小説のこの点や、その他多くの特徴は、失明不安の去勢への関係を否認すると、気儘な無意味なものに見えてくるが、砂男のかわりに、去勢を実施しかねなかった恐い父親を置き換えてみると、逆にきわめて意味深いものになってくる・・・そこでわれわれは砂男の無気味さをあえて小児の去勢コンプレクスの不安に帰着させようと思う。
(同、p.339-340.)
こうして、「無気味なもの」は、一方で、エディプス・コンプレックスに、すなわち、父−母−子の三角形的なエディプス図式、先に本稿で「近代家族の三角形」としたあの形象の焦点に、結び付けられる。しかし、フロイトの探求はそこにとどまらない。
ホフマンの物語で「無気味」な効果をあげる別のモティーフ、それは「あらゆるそのニュアンスと形態とにおける二重自我人格[ドッペルゲンガー]のモティーフである。すなわち、外見が同じために同一視されざるをえない人物が登場すること、これらの人物の一人から他の一人へと心の中の出来事がとび移って−いわゆる精神感応である−その一人が他の一人の知識・感情・体験を共有することにより、この関係が強化されること、・・・絶えざる同一事の反復、相似した顔付、性格、運命、犯罪行為の繰返し、いや相継起する幾世代ものあいだ名前さえも繰り返されるというあの現象である」(p.341.) それは、弁護士コッペリウス−眼鏡売りコッポラとして幾度も同じように反復する砂男の出現に見られるものであり、また、物語を離れた日常生活の中でも、ただの偶然と片付けがたいような意図せざる繰返しや、ある種の「予感」、あるいは心内で願ったことが即座に現実に起こってしまったときの気味悪さ、あるいは子供の「あるやり方で人形を、できるだけ強く見つめていれば、人形は生きてくるにちがいない」という確信、あるいは自分が内心不安を抱いているときの他人の視線の「目つきの悪さ」、・・・こうしたものにまといつく「無気味さ」のモティーフでもある。ここにフロイトは、「観念の万能」と名づけうるアニミスティックな原始的心性の働きを見る:
無気味なるものの個々の場合の分析は、われわれを古代の世界観・アニミズムへと連れ戻していく。世界を人間の霊で充満せしめることによって、また自己自身の心の内部の出来事を自己陶酔的に過大評価することによって、観念の万能およびその上に打ち立てられた呪術のテクニックによって、また念入りに段階づけられた魔法の諸力を他の人物や事物(マナ)に配分することによって、あるいはまたこの発展段階にある無制限の自己愛が、それをもって、現実から間違えようのない抗議に抵抗するところの、あの創造物のすべてによって特徴づけられている、あのアニミズムである。そしてわれわれすべてはそれぞれの個人的発展のうちに、原始人のアニミズムに相当する一時期を通過しているのであって、またこの一時期は、いまだに何かの折に外に現れる力を持った残滓や痕跡などを残すことなくしては、われわれすべてから消えてなくなることのないようなものなのである。今日われわれが「無気味」と見えるものすべては、このアニミズム的な心理活動の残滓に触れ、これを刺激して外に出させる条件を満たしているように思われるのである。
(同、p.346.)
したがって、フロイトの結論はこうである − 私たちは生まれたときにはまずもってアニミスティックな自他未分化の世界を生きており、そこでは眼で見て心に思うことがすなわち実現するような魔術的な「観念の万能」の原理が支配していた − しかしそうした世界は、エディプス的な父親の介入によって去勢され、まさにその段階を経由することによって、原始的なドッペルゲンガー的自我の拡散が消滅されそのかわりに自己の内面に「自己観察。自己批評の役割を果たす」超自我の眼として形成され − 自己愛を克服し客観的な認識の能力を獲得したわれわれ、成人した「人間」が誕生する。「無気味unheimlichなもの」とは、抑圧され意識から消されたはずの「去勢」の経験あるいは克服されたはずのアニミスティックな心性が、何かをきっかけとして再び意識の表面に回帰してきたときに感じられる。砂男が子供の全能な眼玉を抜き取って、その代わりに、眼鏡売りコッポラとして再び現れて望遠鏡を与える、という物語は、こうして、自他未分化の状態の克服、すなわち、エディプス的布置における認識主体 − および、その相関物としての、主体から視覚的距離を確保された均質的な座標空間 − その空間の中で、主体は客体を「構築」したりしなかったりするだろう − の暴力的成立のアレゴリーと読み直される。
「un/heimlich=un/familiarなもの」はそのとき、「主体が客体を構築する」という、グブリアム&ホルスタイン流の「構築主義」や「脱構築主義」(!)の可能性の条件が誕生した瞬間の記憶につながる、「臍の緒のようなもの」の位置を占めることになるだろう。「家族的なもの=馴染み深いもの=the
familiar」というものの中に、「構築主義」の対象と「構築主義」の成立条件とがそっくり含まれている、といったのは、このような意味においてである。
したがって − 本稿冒頭の問いに戻るならば − 「家族」について、あるいは「こころと家族」について、社会学的視点から見た構図は、奇妙な認識論的捩れをもって私たち自身の認識の眼そのものに食い込んでくることになるだろう。
4:「こころと家族」の問題構成
私たちは、あたたかなこころの絆としての「家族」を好ましいものと感じているだろうし、厳しい「ソト」の世界で傷ついた心身をあたたかく迎え入れ癒す居場所としての「家族」をもとめているだろう。しかし、そうした「家族」のイメージは、「近代家族」と呼びうるひとつのパターンであり、「家族」について社会学的視点から見る、とは、私たちにとっては、とりもなおさず、そうした「近代家族イデオロギー」を問う、ということである。
グブリアム&ホルスタインが指摘するとおり、そうした「家族」イメージは、「家族の言説」として、この社会のいたるところで語られ、機能している。例えば高度経済成長期に、日本の企業が「家族」をユニットとして労働者を取り込み、それによって父親たちが「家族のため」という言説を語りながらより深々と「会社人間」になっていったことを想起してもいい。「家族」とは、他のさまざまなユニットと同じように、この社会 − 近代社会 − を円滑に運行させる歯車ないし部品の一部なのである。そうである以上、「家族」を社会学的に見るためには、「家族」の成員どうしの人間関係やら心のつながりやらやりとりやらだけに注目しているわけにはいかない。むしろ、そうした注目を促すところのひとつの問題構成、すなわち「こころと家族」という問題の立て方自体を、批判的に問い直さなければならない。「家族」は「こころ」(しかも、「心」ではなく平仮名で表記される「こころ」)の場である、あるいは、あるべきである、といった前提自体が、「近代家族イデオロギー」の一つの側面なのであり、その枠内で思考する限り、私たちは「家族」について、トートロジカルな命題 − 例えば、「子どもには愛情を注がなければならないが過干渉もよくない、ほどほどのバランスをとるべきだ」といった − を語ることしかできない。むしろ私たちが問題としなければならないのは、言説としての「こころと家族」が、どのような社会的な場面で組織的に語られ、そこでどのような機能を果たしているのかを、辿っていくことだろう。グブリアム&ホルスタインの「構築主義」的アプローチは、その具体的なプログラムとして私たちを導くだろう。
そしてその探求にともなって − グブリアム&ホルスタインが予測した以上の深さにおいて − 「こころと家族」への問い直しは、私たちを「無気味なもの」に直面させ、私たちの認識論じたいを揺るがすだろう。「家族」という、自分にとって最も馴染み深いもの、自分のルーツ、原点であるものを問い直そうとするとき、そこで私たちが出会うのは、一つのタブー、抑圧、である。その抑圧の蓋を開けて私たちが眼にするのは、近代以前の − フロイトはそれを「原始的」と呼ぶのだが − アニミスティックな空間の中に溺れ込んでいる 自 分 の 姿 である、かもしれない。あるいはまた、そのような自他未分化の地平から決別し、完全な 故 郷 喪 失 者 、heimatlosとなった自分の姿であるかもしれない。あるいはまた、そのような両者のあいだで引き裂かれ 宙 吊 り になっている自分の姿を見ることになるのかもしれない。
私たちが触れることになる「無気味なもの」がそのいずれであろうと − あるいはそのすべてであろうと − それによって私たちは、「こころと家族」というイデオロギー的な問題構成から決定的に離脱することになるのである。
【 文献 】
アリエス、Ph.(1960=1980)『〈子供〉の誕生』みすず書房
フロイト、S.(1919=1970)「無気味なもの」『フロイト著作集』人文書院
グブリアム、J.F.&ホルスタイン、J.A.(1990=1997)『家族とは何か』新曜社
落合恵美子(2000)『近代家族の曲がり角』角川書店
苫米地伸(2002)「相互行為における家族」伊藤勇・徳川直人編『相互行為の社会心理学』北樹出版 所収
【 資料:小レポート答案より 】
・「家族」とは、両親がいて、その子供がいて、お互いに支え合って、一番信頼のできる存在。そして、一人一人が必ず持っているもの。自分自身の一番大切な存在。
・家族は社会の中で、一番小さい集団であって、生き物にとっては、とても大きな存在であると思う。家族は、血のつながりのある人間同士の集まりだけでなく、まったく血がつながっていなくても、家族といえる。世の中には、色々な形や様子の家族があると思うが、私の中での家族は、「私」を受け入れてくれて、「私」の居場所があり、包み込んでくれるような、あったかいものに感じる。
・目に見えない強い絆で結ばれているもの。こちらからはたらきかけなくても、相手のことがわかる以心伝心みたいな感じである。気を使うことなく、自分にとって真の心のより所である。
・無条件の愛を与えてくれる人、または人達の集団だと僕は思う。
・「家族」とは、”一番近くにいて常に私の味方をしてくれるもの”、”私を心配して私を助けてくれるもの”、”私に無条件の愛情を注いでくれるもの”、”とても居心地が良くて安心できるもの”だと思います。でも、あくまで私の中での”定義”です。その他、書くときりがありません。
・家族とは、何でも言い合えて、何でもわかり合えて、失った時一番深い悲しみを覚えるものであり、また生活を、互いに支え合って、共にしていくものである。さらに、いちばん落ち着ける場所であり、他人とは違った不思議なあたたかさがある。
・家族はやすらぎの場である。特に家族の前では私は非常に無防備になる。他人の前ではやはりどうしても他人の自分に対する評価が気になってしまう。ひょっとしたらその評価が低いためこれからの社会生活が非常にやりづらくなるかもしれないことだってあるかも。その点家族には社会の評価などあまり関係ない。まぁ虐待などがあるのなら話は別だが私の家族にはそんな事はないので、一安心だ。一番の素の自分が出せる場所である。
・どこにでもあるような答え方をするならば「家族とは」、帰る場所、心安らぐ場所である。
・家族は、一言で言うと「私」を支える存在、血のつながりがあり、人間の心の奥深くにあるものを発見してくれる(導いてくれる)存在、そうする事によって、様々な深い体験ができる。こういった大切な、かけがえのない存在である。また「安心」や「安らぎ」を与えてくれる存在と感じる。
・「家族」の定義、あるようでない気がする。一般的には一緒に暮らしていて、血縁関係にあるものが「家族」である。でも、一緒に暮らしていても血縁関係がなくても「家族」であったり、離れて暮らしていても血縁関係であれば「家族」であったり、友達や知り合いの家に何回も遊びに行くうちに「家族」の一員になったりする。私は「家族」というのは、形や血のつながりではなく”心の絆”であると思う。
・家族とは血縁関係の有無に関係なく、同じ時間を過ごし、愛情によって結びついている集団である。そして、お互いの心のよりどころとなれるような存在である。
・私が考える「家族」っていうのは、形からいくと両親がいて子どもがいて・・・という形だと思います。でも、両親がいて子供がいてというのが全てではないと思うし、「家族」の基準ではないと思います。現実には両親がいなくて施設にいる人もいるわけだし。施設にいる人は家族じゃないといえばそうじゃないと思う。きっと施設の先生はお父さんお母さんみたいだろうし、一緒に住んでる人たちは兄弟みたいだと思うだろうし。血がつながっていても家族だしつながってなくても家族だと思います。形もそうだけど、形よりも相手のことを思いやったり、考えたり相手と一緒に笑ったり、悩んだりなどすることができるのが家族なんだと思います。
・私には定義とか、そんな形ばったもんはわかりません。だから定義なんて言われたらかけないですけど思う所を少し書きたいと思う。家族にはいろんな形や、事情やいろんなものがあって、たとえば父も母もいる祖父母もいて子どももたくさんいる家族や、母ひとり子ひとりとか、年老いた母と40すぎてもまだ独身の息子とか・・・でも、そこには色々事情があるけど共通して愛だとか、思いやりだとか、いかりとかにくしみとか、いろんな感情がまざりあっててそれでもともに生きていける関係。それが、家族。かなぁとか、実は今、書いたことも何を書いたのかわかってないんですけど。まあそんな所だと思います。
・家族の定義は文化や国によって違うと思う。例えば日本の家族は子どもを一番大切にして、子どものために働いているようなものだと思う。しかし欧米へ行けば夫婦の関係を一番大切にして、二人の愛の結晶みたいなものが子どもだと思う。しかし、一つだけ共通点があるといえば、家族はお互いに支え合って、一番、自分を理解してくれるものであると思う。やっぱり最終的に何かを解決しようと思ったら、大多数の人は自分自身の家族に頼るに違いない。そして私の意見として、「恋人、友人も、ペットも家族の一員」だと思う。家族って紙切れで決められたものだけではなく、お互いに信じあって支え合うことが出来る人どうしだと思うから。
・愛し合う男女が結婚して子供が産まれ、みんなが支えあいながら生活していくもの。他の何にも代えられないほど大切なもの。
・自分がいて、自分を産み育てた、父、母、又、兄弟の組織。家族というのは、きってもきれぬくされえんの関係にあると思う。人は(年をとり)結婚すれば、2つ「家族」を持つ。→1、自分が子供の立場の「家族」 2、自分が親の立場の「家族」
・家族とは、切ってもきれないとても強い絆で結ばれているものだと思う。例えば、子どもの成長を見守る親の愛情など。
・家族とは一般的には血のつながった親と子または兄弟、姉妹、の関係にある集団のことで生涯支え合って生きていく。親は子どもを育てまたその子どもも大きくなれば結婚し親となり新しい家族をもつようになる。家族とは、他人とは違い強い信頼関係のある集団だと思う。子どものいない場合は養子という形で家族を持つことができるようになり、この場合は血がつながっていなくても信頼関係があればりっぱな家族といえると思う。
・家族とは子どもの小さい頃の生活環境の土台となる存在である。親は家族のために働き、子どもに学校に行かせ養っていかなければならない。そういった事よりも家族に精神的に支えられる部分も多いはずだと私は思う。
・人間養成所。生きること死ぬこと全てをたたきこまれ、しこまれる。自分の本音を出せる場。まさにユートピアといえる。これが理想。
・死の弔いの責任を負うもの、また、その責任を任せられる人、もしくは集団。その責任に、出世の事実は関係ない。
・私の立場から見たら、父、母、兄弟、祖父母などが一つの家に集まり、父は社会で働き、母は家事をし、父の稼ぐお金で家族全員が生活すること。また子供は、父から援助され、学校へ通い勉強する。家族全員でよりそい、互いに助け合うということだと思います。
・家族とは、自分が家に帰ったときに安心できるものでまた心配ごとや悩みがあったりしたときに一番安心して相談できる、自分にとって支えたりしてくれるとても大切なものである。また、家庭をもったときに自分は「家族を養っていくために働く」という目標をもって仕事に取り組んで、また、それが「源」となるような大切なものである。
・家族は、ラーメンである。父親が麺である。母親はスープである。子供は、具である。器は家である。親は子を乗せ、子は親を美しくする。家は家族をばっちり包むのである。