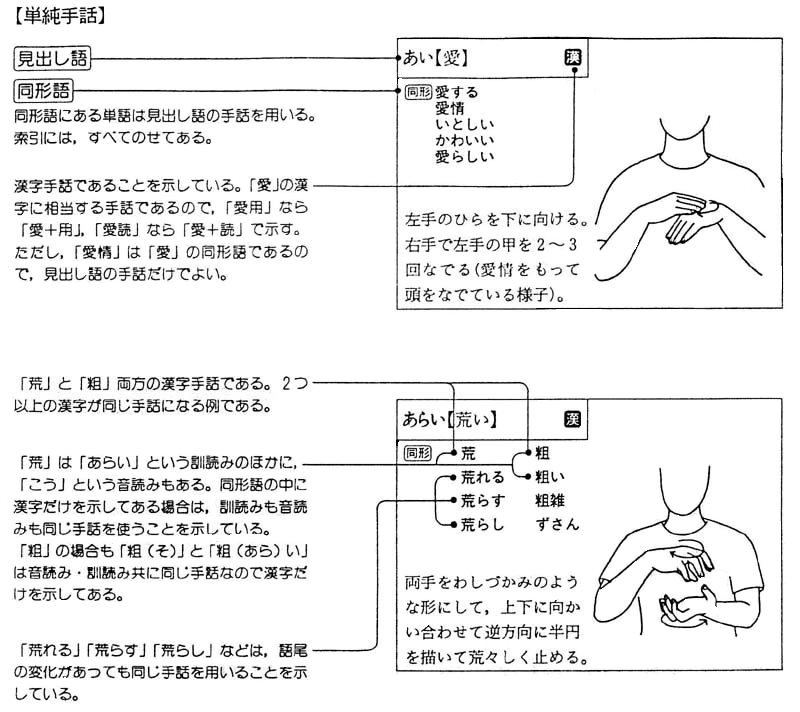
日本語対応手話では、日本語の文をそのまま手話に置き換えて表します。つまり、基本的には、その文章の単語に一つひとつ手話を当てはめていけば良いわけです。いくつかの基本的なルールを覚えてしまえば、それほどむずかしいものではありません。
この章では、そのルールを一つひとつ説明しながら、実際の表現を練習してみましょう。この章ではイラストをつけますが、必要に応じて辞書も参考にして、自分で手を動かしてみてください。
<単語例・練習文の見方>
まず、手話で表そうとする日本語を「……」でくくって示します。次に日本語の単語に対応する手話を並べます。『新・手話辞典』に掲載されている手話については【 】に入れ、指文字で表すときは《 》に該当の指文字を入れて示します。
例:「謝」【謝る 15】
「謝」の手話は、「謝る」という見出し語で15ページに載っているという意味です。
例:《に》《は》
例えば、助詞の「には」は指文字で示すという意味です。
*第3章までは日本語を全部手話で表現する形で説明します。
第1節 単純手話のひき方
『新・手話辞典』では、「単純手話」と「指文字結合手話」に分けて、それぞれイラストを "あいうえお順" に並べ、説明を加えてあります。
「単純手話」は、一つの(または一続きの)動作で一つの意味を表す手話のことです。「指文字結合手話」は、簡単に言えば、花とか魚など、あるグループに属する単語を表現する際に、左手でそのグループを表す手話を、右手でその単語の頭文字を指文字で表すというものです。指文字結合手話の表現については、後に練習します。
まず、単純手話をひいてみましょう。
次のページに『新・手話辞典』から単純手話の凡例を引いたので見て下さい。
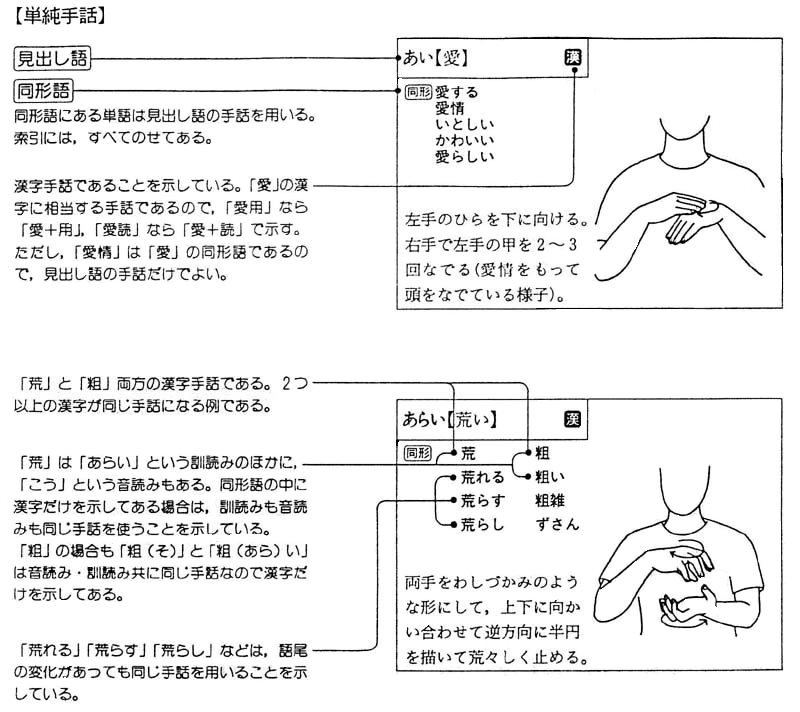
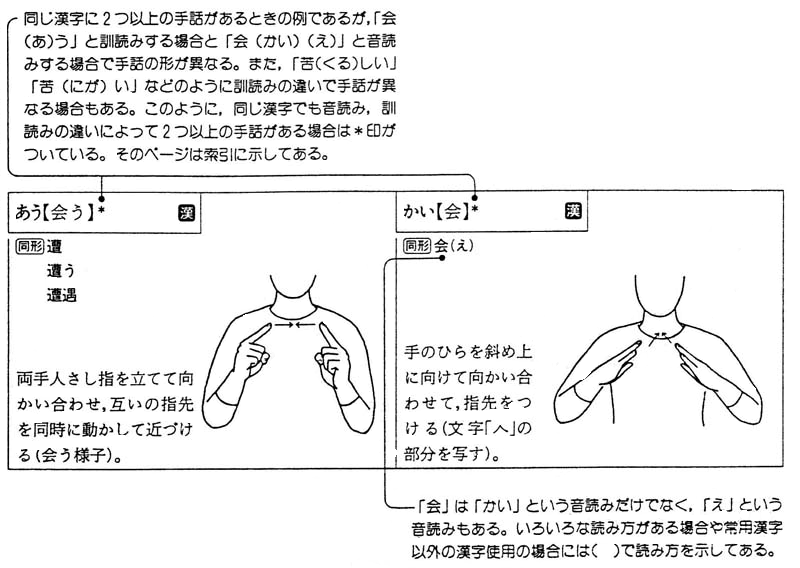
動詞、形容詞などのように活用のある語は、一般の国語辞典と同じように終止形で掲載してあります。手話では動詞などの活用は特別な場合以外は表現しません。次節を参照してください。
第2節 活用のある語の表現上の注意
(1)動詞の活用の表現
動詞の活用は口型で表示し、命令形以外は手話では表現しません。例えば「学習する」というサ変動詞は次のように活用しますが、( 部分が活用)
学習しない (未然形)
学習させる (未然形)
学習し、 (連用形)
学習する。 (終止形)
学習するとき (連体形)
学習すれば (仮定形)
学習しろ (命令形)
命令形以外は「学習」に「する」をつけた形で、全部同じ表現になります。
| 例:「学習する」 | |||
| まなぶ【学ぶ】 漢 | やる【遣る】 | ||
| 〔同形〕 学 学習 学業 学問 校 学校 |
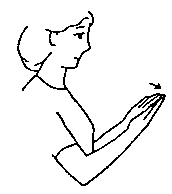 |
〔同形〕 する 実施 |
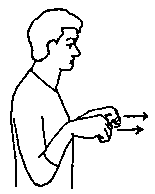 |
| 「学習」【学ぶ 460】 | 「〜する」【やる 498】 | ||
サ変動詞(名詞に「〜する」がついたもの)の命令形の場合は、「〜する」の後に「命令」の手話をつけ加えます。この場合は煩瑣になるので、「〜する」の手話は省略してもかまいません。
| 例:「学習しろ」 | ||
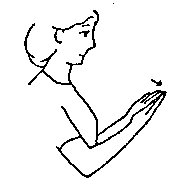 |
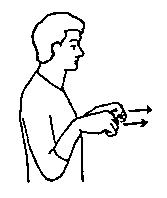 |
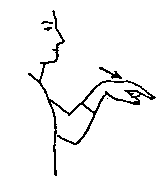 |
| 「学習」【学ぶ 460】 | 【やる 498】 | 【命令 479】 |
サ変動詞以外の動詞の命令形は、動詞の手話に命令を意味する手話をつけ加えて表します。
| 例:「走る」 | 例:「走れ」 |
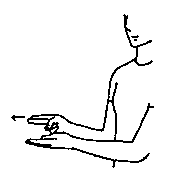 |
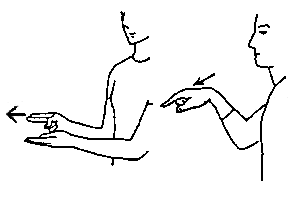 |
| 【走る 381】 | 【走る 381】+【命令 479】 |
「学習すれば」などは、【学習】【やる 498】に「〜ば」を表す【仮 101】の手話をつけて表しますので、仮定形だということは自然に分かります。(参照:助動詞の活用)
| 例:「学習すれば」 | ||
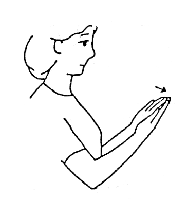 |
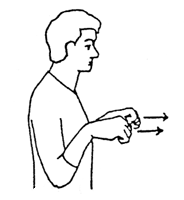 |
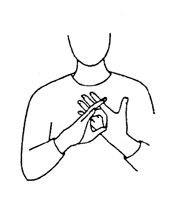 |
| 【学ぶ 460】 | 【やる 498】 | 「〜ば」【仮 101】 |
(2)活用による自動詞と他動詞の区別
日本語では、活用形の違いで自動詞と他動詞を区別することがあります。手話では、原則として同じ手話で表現し、活用の違いは口型で区別します。
| 例:「建つ」(自動詞)と「建てる」(他動詞) | ||
| たつ【建つ】 漢 | ||
| 〔同形〕 建(けん) 建(こん) 建てる 建設 建立 築 築く |
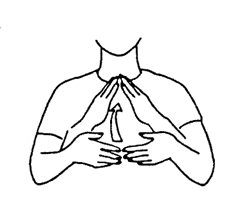 |
どちらも |
| 【建つ 282】 | ||
活用の違いは口型で区別しますが、必要なときは指文字で示します。
(3)形容詞と形容動詞
形容詞と形容動詞の活用変化は口型で区別することになっており、手話では特に表示しません。
例えば、形容詞「高い」の場合は、その活用変化は、「高かろ/高く/高い/高い/高けれ」となります。この活用の変化を、口の形に気をつけて、実際に発音してみてください。活用語尾の母音は「A/U/I/I/E」となっており、それぞれ口型が違うことがわかります。一つ一つ手話で区別しなくても、口の形を読みとることで十分区別できます。確実に区別することが必要な場合等には、指文字で示します。
また、音声語と同じく次に続く語でも区別できます。例えば、仮定形の場合は、次に「〜ば」(【仮 101】)がつくので区別できます。(参照:助動詞の活用)
| 例:「高い」 | ||
| たかい【高い】 漢 | ||
| 〔同形〕 高(こう) 高(たか) 高まる 高める |
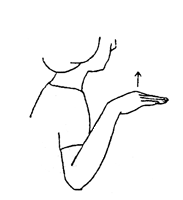 |
高かろ(未然形) 高く (連用形) 高い (終止形) 高い (連体形) 高けれ(仮定形) |
| 【高い 277】 | ||
形容動詞も形容詞と同じく、活用の変化は口の形で区別します。
しかし、例えば、「あからさまだ」と「あからさまな」は口型では区別できないので、必要に応じて指文字を加えます。
| 例:「あからさま」 | |||
| あからさま | 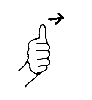 |
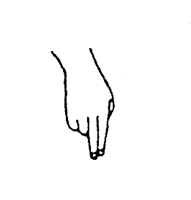 |
|
| 〔同形〕 あらわ |
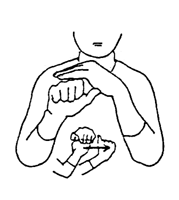 |
||
| 【あからさまな 4】 | 指文字「だ」 or 指文字「な」 | ||
(4)助動詞の活用
助動詞の活用は、命令形以外は手話では特に表現しません。命令形以外は口型と、次に続く語で区別できます。例えば、「着させる」は次のように活用しますが、:の後に書いてある理由により特に活用形を表示しなくても分かります。
| 子どもに服を着させない。 | (未然形) | : | 「〜ない」が続く |
| 子どもに服を着させ、学校に出す。 | (連用形) | : | 動詞が続くか、 休止がある(連用中止法) |
| 子どもに服を着させる。 | (終止形) | : | 文が終わる。 |
| 子どもに服を着させるときは、 | (連体形) | : | 名詞などに続く |
| 子どもに服を着させれば、 | (仮定形) | : | 「〜ば」に続く |
| 早く子どもに服を着させろ! | (命令形) | : |
命令形だけは【命令 479】の手話をつけ加えます。
| 例:「早く子どもに服を着させろ!」 | ||
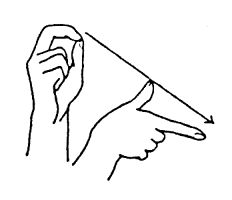 |
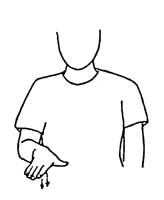 |
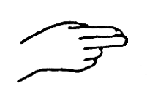 |
| 【速い 389】 | 【子供 169】 | 《に》 |
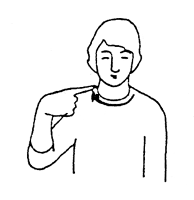 |
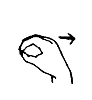 |
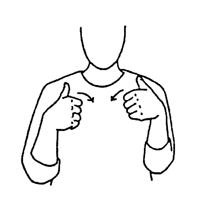 |
| 【シャツ 212】 | 《を》 | 【着る 126】 |
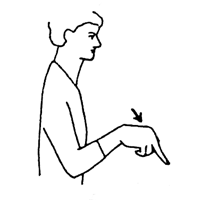 |
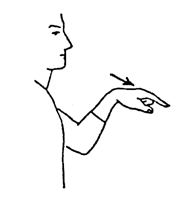 |
|
| 【〜せる 255】 | 【命令 479】 | |
(5)活用語のある例文
では、次の例文を日本語対応手話で表現してみて下さい。活用の変化は、口型ではっきり示すように注意すること。
「簡単な回路で作りやすく、アンテナ線なしで鳴るスピーカー・ラジオ」
| 簡単な | 回 | 路 | で | 作り | やすく、 | |
| 【易しい 495】 | 【回 76】 | + | 【道 467】 | 《で》 | 【作る 306】 | 【易しい 495】 |
| アンテナ | 線 | なし | で | 鳴る | ||
| 【アンテナ 19】 | 【線 256】 | 【無い 346】 | 《で》 | 【鳴く 349】 | ||
| スピーカー | ラジオ | |||||
| 【スピーカー 242】 | 【ラジオ 510】 |
第3節 漢字手話
日本語を完璧に手話に置き換えて表現することを考えるなら、一つの単語に対し一つの手話が対応するのが望まれます。つまり、日本語の単語数と同じ数だけの手話単語数が存在するのが理想的です。しかし、日本人(成人)の理解語彙数は、平均5万語ほどもあり、その5万語のことごとくに対応した手話を創り出すのはまず不可能です。仮に5万語の手話が存在したとしても、それを全部覚えるには、たいへんな努力が要ります。
この問題をどのように解決したらよいか、あれこれと模索するうちに、日本語は漢字と仮名の組み合せによって表記されるという点に着目しました。漢字ならば、まだ数が限られていますし、手話と同じく視覚で認知するという点でも、手話表現の可能性に結びつきそうです。そこで考案されたのが、一つの漢字に一つの手話を対応させた「漢字手話」です。
第1項 漢字手話の有用性
漢字を手話で表すことができれば、いろいろなメリットが生まれます。
まず、日本語には漢字の熟語が非常に多いので、それぞれの漢字に対応した手話があれば、その漢字手話を組み合せることで、いろいろな熟語が表せます。
この漢字手話の組み合わせをうまく活用すれば、比較的少ない手話で日本語の多くの語彙に対応することができると考えました。
また、漢字手話の視覚的な形から漢字を連想させ、さらにその漢字の意味を想起するという過程を経ることによって、抽象性の高い言葉を表現しやすくなるというメリットも生まれます。
次に、漢字手話の熟語の例をあげますので、実際に表現してみてください。
「事」と「物」という漢字手話を組み合わせて「事物」という言葉を表現することができます。同じようにして、「品物」や「事実」などを表現するのに、同じ漢字手話を組み合わせれば良いことが分かります。
| 例:「事」 | 例:「物」 | ||
| こと【事】 漢 | もの【物】 漢 | ||
| 〔同形〕 事(じ) 事(ず) 事柄 |
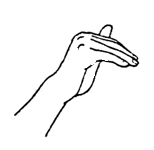 |
〔同形〕 物(ぶつ) 物(もつ) |
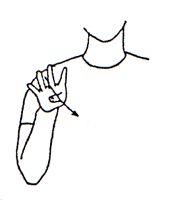 |
| 【事 168】 | 【物 489】 | ||
| 例:「品」 | 例:「物」 | ||
| しな【品】 漢 | もの【物】 漢 | ||
| 〔同形〕 品(ひん) |
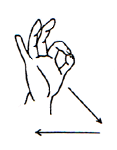 |
〔同形〕 物(ぶつ) 物(もつ) |
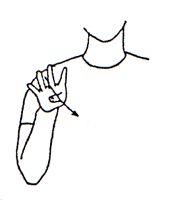 |
| 【品 206】 | 【物 489】 | ||
| 例:「事」 | 例:「実」 | ||
| こと【事】 漢 | じつ【実】 漢 | ||
| 〔同形〕 事(じ) 事(ず) 事柄 |
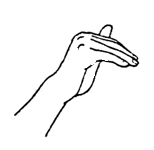 |
〔同形〕 実質 |
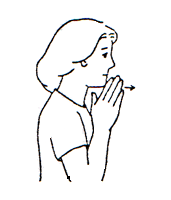 |
| 【事 168】 | 【実 204】 | ||
第2項 常用漢字の漢字手話
『新・手話辞典』に収められている漢字手話は1,621語です。 これは、常用漢字1,945の内、1,621を漢字手話化したものです。
使用頻度の少ない漢字や、異なる漢字でも意味が近く同形の手話で表せる漢字は、手話化の対象とはしませんでした。例えば、むかしの天皇が一人称に用いた「朕」のように、一般にはほとんど使われないような常用漢字は、あえて手話化する必要はないと考えました。
一方、「服」という漢字は、いろいろな漢字と結びついて多くのことばを創り出す重要な役割を持っています。ところが、その意味があまりに多様にわたっているために、一つの手話では、とてもその意味全部を表しきません。「服」は、一般的には「きもの(衣服)」という意味で使われていることばですが、別の漢字と結びつくと、従う(服従)、飲む(服薬)などの意味をもつようになります。例えば、「服薬」を「着る」という手話と「薬」という手話の組み合わせで、違和感なく表現できるでしょうか。「薬を着る」というような手話になっても、かえって不自然で意味が伝わりにくくなります。このような場合は、あえて無理に一つの手話にまとめることはしませんでした。
また、昔から使用されてきた手話で、そのまま漢字手話として利用できるものは、できるだけ尊重しました。
第3項 漢字手話作成の方針
このように、漢字手話は新しい発想のもとに考案されたものなので、次の原則を設けて、慎重に作成しました。
(1)原則
(2)例外
<音読み・訓読みそれぞれを指文字で表現し分ける例>
| 例:「通」 | ||
| 「ツウ」と読む場合 | 「とおる・とおす」と読む場合 | 「かよう」と読む場合 |
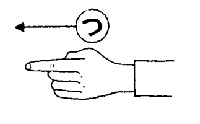 |
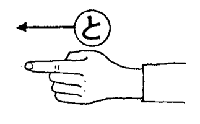 |
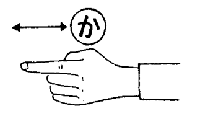 |
| 左手人差指の上を 「ツ」でなぞる |
「ト」でなぞる | 「カ」で往復させる |
<音と訓の違い・訓の違いで意味を明確に区別できるので、別の手話をつくる場合>
| 例:「治」 | |||
| 「おさめる・おさまる・ジ・チ」と読む場合 | 「なおる」と読む場合 | ||
| おさめる【治める】* 漢 | なおす【なおす】* 漢 | ||
| 〔同形〕 治(じ) 治(ち) 治まる |
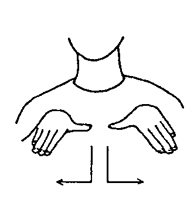 |
〔同形〕 直る 修正 訂正 修理 いやす 治す 治る 維新 改 改まる 改める 改革 改訂 |
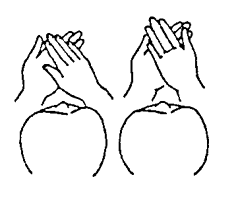 |
| 手のひらを下に向けた両手を 開きながら下へ |
両手を手のひらを向い合せにして 交差させて重ね、右手を裏返す |
||
第4項 漢字手話を使った例文
「この度は、お買い上げ頂きまして、誠にありがとうございました。
この説明書をよくお読みの上、正しくお使い下さい。」
| こ | の | 度は | お | 買い | 上げ | 頂き |
| 《こ》 | 《の》 | 【度タビ284】 | 【御 157】 | 【買う 79】 | 【上がる 4】 | 【頂 26】 |
| まし | て、 | 誠に | ありがとう | ござい | まし | |
| 【〜ます 456】 | 《て》 | 【誠 455】 | 【有り難い 16】 | 【居る 33】 | 【〜ます 456】 | |
| た。 | こ | の | 説明 | 書 | を | |
| 【〜た(過去) 271】 | 《こ》 | 《の》 | 【説く 334】 | 【書く 83】 | 《を》 | |
| よく | お | 読み | の | 上、 | ||
| 【良い 504】 | 【御 157】 | 【読む 507】 | 《の》 | 【上 36】 | ||
| 正しく | お | 使い | 下さい。 | |||
| 【正しい 280】 | 【御 157】 | 【使う 304】 | 【願う 363】 |
(註)・「度」の漢字手話は「ド」と読む場合と「たび」と読む場合では分けて作ってあります。見出し語に「ど【度】*」(p.326)、「たび【度】*」(p.284)と「*」印で表示してあります。
・「お」などの敬語の表し方については後で説明します。
第4節 漢字語の表現
「漢字語」という聞きなれない言葉が出てきますが、『新・手話辞典』では漢字だけの熟語のことを、便宜的に「漢字語」という呼び方をしています。
第1節の例文では、「回路」は漢字手話「回」+「道」の組み合わせで表現されていますが、「簡単」は一語の単純手話で表現されています。
索引を見れば、漢字手話の組み合わせで表現するのか、それとも一語だけの単純手話で表現できるのかを調べることができますが、この区別は、基本的に次のような考え方にもとづいていることを理解してください。
(1)漢字語を漢字手話の組み合わせで表す場合
その漢字語を表す手話がなく、漢字手話の組み合せでも違和感のないもの
これとは逆に、漢字手話の組み合わせでは、その言葉を不自然に分解してしまって、返ってわかりにくくなる場合があります。そういう場合は漢字手話で表すのではなく、ひとつの手話で表現した方が意味がスムーズに伝わります。例えば、「先生」という単語を手話化するとき、「先」という漢字手話と「生」という漢字手話を組み合わせて「先のナマ」などど表現しても、手話を見る側にとってはピンとこないでしょう。「先生」という従来通りの一語の手話の方が、すっきりと意味が伝わります。
同じように「意味」という単語を表す時なども、「意」と「味」の漢字手話をそれぞれ組み合せたところで、「意見の味とは何だろう?」と思われてしまいそうです。「先生」という語も、「意味」という語も漢字を組み合わせてできている熟語というよりも、ひとつの独立した単語とみなされ、使われていると考える方が適切です。こうした単語を「一語感の強い語」という言い方をしています。
即ち、「一語感の強い語」は1つの独立した手話で表現する、漢字の組み合わせと考えても違和感のない語については、漢字手話の組み合わせを用いる、と覚えて下さい。どちらか判断に迷うような場合は、索引で調べてください。
なお、索引に載ってない漢字熟語の場合は、原則として漢字手話の組み合わせで表します。
(2)漢字語を漢字手話の組み合わせで表す例
漢字語を漢字手話の組み合わせで表すのには次のような例があります。
「日本画」というような単語と単語が結合した複合語では、元の単語の手話を複合させます。
例:日本画=日本【日本 358】+画【画 47】
(3)漢字語を単純手話で表す場合−その1
一語感が強いとき
「自動車」の手話のように、その漢字語を表す単純手話がすでに広く使われている場合は、漢字手話の複合にはしません。
また、一つひとつの漢字の意味の合成では、その熟語の意味が示せないときも、一語感が強いと考えます。例えば、「先生」という語の意味は、「先に」+「生まれる」という普通に使う漢字の意味の合成とは離れています。
例:「自動車」= 単純手話【運転 46】
「先 生」= 単純手話【教える 62】
(4)漢字語を単純手話で表す場合−その2
漢字一字でその熟語の意味がほぼ表せるとき
例えば、「謝罪」という漢字語は、「謝」の漢字手話だけでほぼその意味が表せます。「謝罪」の「罪」はこの場合、省略して支障がありません。
例:「謝罪」= 謝 【謝る 15】
(5)漢字手話を使った例文
「旧山手通りが環状7号線と交差する角」
| 旧 | 山 | (の) | 手 | 通り | が |
| 【古い 428】 | 【山 497】 | 《の》 | 【手 315】 | 【通る 333】 | 《が》 |
| 環状 | 7 | 号 | 線 | と | |
| 【環状 107】 | 【七 103】 | 《ゴー》 | 【線 256】 | 《と》 | |
| 交差 | する | 角 | |||
| 【交差 161】 | 【やる 498】 | 【角 93】 |
*山手(ヤマノテ)は読み通りに漢字手話と指文字の組み合わせで表します。
*「環状」と「交差」は単純手話です。
*7号線の「号」は指文字で表し、ここは漢字手話と同様に組み合わせて示します。
第5節 指文字結合手話
ことばの中には、同じグループに属する語がたくさんあります。例えば、「すいせん」と「なでしこ」は、「花」という同じグループに属する言葉です。このようなグループをカテゴリーといいます。
このように、同一のカテゴリーに属する語がたくさんある時には、左手でカテゴリーを示す手話を、右手でその言葉の最初の1文字か2文字を指文字で表すという方法をとることにしました。このような手話を「指文字結合手話」とよんでいます。
いいかえれば、「指文字結合手話」とは、左手の手話をそのカテゴリーを示す「枠」とし、それを右手の指文字で「分化」させるわけです。
「指文字結合手話」の約束によって、たくさんの単語を表すことができ、記憶の負担が減少します。また、動作量も少なくすみます。
第1項 指文字結合手話の例
指文字は、同じカテゴリーに属する他の語と混同する恐れのないときは。その語の最初の1文字だけを示します。最初ないし2番目以降の文字が同じで、口型での区別もむずかしいような場合は、最初の2文字か必要に応じては3文字以上を指文字で示します。
| 例:<花というカテゴリーに分類される植物名> 【花 535】 | |
| 「すいせん」 | 「なでしこ」 |
| 例:<魚というカテゴリーに分類される語> 【魚 540】 | |
| 「サバ」 | 「サンマ」 |
「日本語対応手話」では、次のようなカテゴリーに分類される語を指文字結合手話で表すものとします。『新・手話辞典』でひく場合は、P.534 に、次に示すものと同じカテゴリーの一覧表が掲載されています。
植物名:花、樹木、草類、野菜、果物類、根菜類、豆類、きのこ類、海藻類
動物名:獣類、鳥類、虫類、魚類、貝類、その他の生物
薬品名:医薬品、農薬、化粧品、塗料
食品類:酒類、肉加工食品類、めん類、揚げ物、揚げ物、パンに塗る物、調味料、栄養素
地 域:国、都道府県など
自 然:あられ等、大陸等、宝石類、色、元素、原子など、金属類
身 体:身体部位、味覚、発疹、
その他:歌、弦楽器、クイズ類、トランプ類、縫い方、和服類、ランドセルなど、時代名、ワープロ等
第2項 指文字結合手話の引き方
『新・手話辞典』では、単純手話と文字結合手話に分けて、それぞれイラストをあいうえお順に並べて説明がしてあります。
単純手話の引き方は前に説明しましたので、ここでは指文字結合手話の引き方を説明します。
| 1 花 | 例 | ばら | |||
| 左手は指を開いてやや丸くし、手のひらを右に向ける。〔花〕の右手をとった形で「花」を表す。 右手で、花の名前の最初の音を指文字で表す。 樹木で表したい場合は「2 樹木」で草で表したい場合は「3 草」で示してもよい。 |
|||||
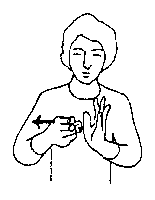 |
朝顔〈朝+顔)アネモネ アマリリス あやめ カーネーション カンナ ききよう ☆菊 金せん花 グラジオラス クロッカス けいとう けし コスモス 桜草(桜+草) サルビア 三生すみれ(三十色+すみれ) シクラメン シネラリア しゃくやく ジャスミン しょうぶ 水仙 スイートピー すいれん すずらん すみれ ゼラニウム ダリア たんばば チエーリツプ なでしこ 菜の花 はぎ 浜ゆう ばら ひなげし ひまわり 百日草(百十日+草) ヒヤシンス 福寿草(福+寿十草) フリージア ぱたん マーガレット まんじゅしゃげ ゆり よいまち草 りんどう れんげ | ||||
| このグループに属する単語。この例ては花の名。ここに掲げた単語は『角川・類語新辞典』の中からとりあけた。ここに掲げていない単語を同じ方法で示してもかまわない。 「朝顔(朝+顔)」とあるのは、指文字結合手話の形式て示してもよいし、「朝」と「顔」の漢字手話の複合で示してもよいという意味である。 「☆菊」は、指文字結合手話で示してもよいが、単純手話の中に「菊」という形て示してある。必要に応じ、どちらを用いてもよい。 「アネモネ」と「アマリリス」のように語頭音だけで混乱しそうなときは、「アネ」「アマ」など2音を示す。 |
|||||
第3項 指文字結合手話を使った例文
「うちの庭には、春は桜草、秋は菊が咲きます。
池には鮒がはなされ、あひるもいます。」
| うち | (の) | 庭 | に | は、 | 桜 | や | |
| 【家(いえ) 21】 | 【庭 359】 | 《に》 | 《は》 | 【桜 182 OR 535】 | 《や》 | ||
| すみれ | が | 咲き | ます。 | 池 | に | は | |
| 【すみれ 535】 | 《が》 | 【咲く 182】 | 【〜ます 456】 | 【湖 466】 | 《に》 | 《は》 | |
| 鮒 | が | はなさ | れ、 | あひる | も | い | ます。 |
| 【鮒 540】 | 《が》 | 【放す 387】 | 【〜れる 521】 | 【あひる 13 OR 538】 | 《も》 | 【居る 33】 | 【〜ます 456】 |
*指文字部分は省略可能です。
*この例文の中で、「菊」などの花は指文字結合手話の「花」の類で表すことができます。P.535「1 花」というカテゴリーに、花の類に含まれる語句があげられていますが、その語句の中で、「☆菊」を見ますと、☆印がついています。これは単純手話で表すことも出来るという意味なので、単純手話で【菊113】で表してもかまいません。また、「桜草」などは漢字手話の結合【桜 182】+【草131】で表すことができます。
*「放され」の受身の表現【〜れる 521】は省略可能です。
*「〜います」は【〜ます 456】だけで表現することもできます。