| 各 | 国 | の | 努力 | も |
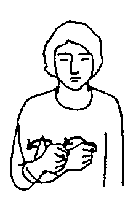 |
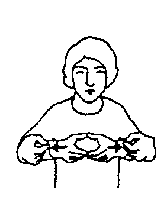 |
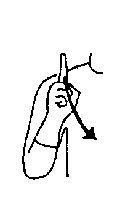 |
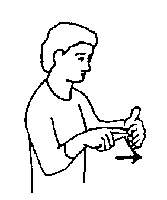 |
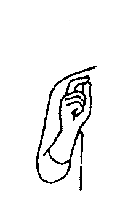 |
| むなしく | CO | 2 | は | 増加 |
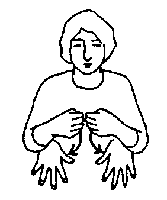 |
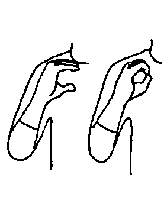 |
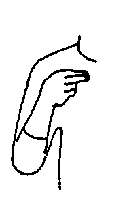 |
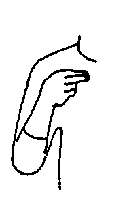 |
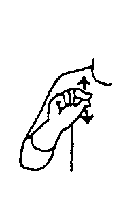 |
| し、 | 地球 | の | 温暖 | 化 |
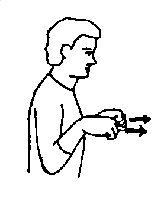 |
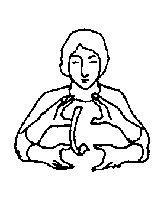 |
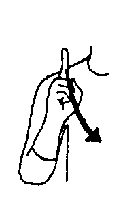 |
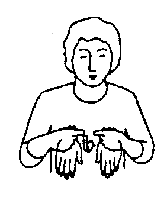 |
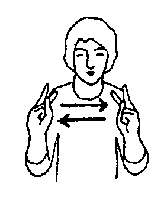 |
| が | 進ん | で | いる | と |
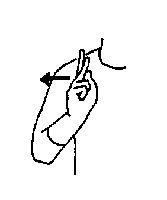 |
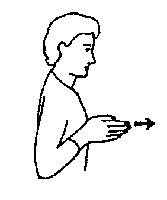 |
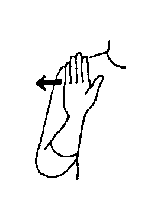 |
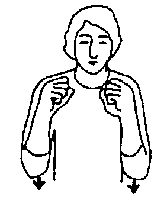 |
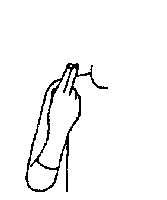 |
| 言わ | れ | て | い | ます。 |
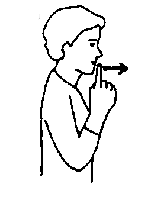 |
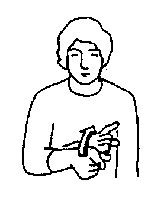 |
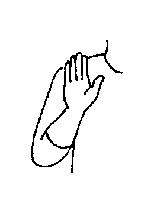 |
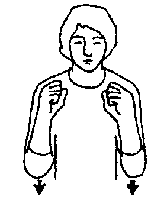 |
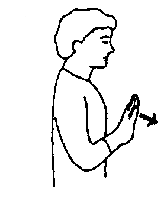 |
手話表現の実際では、文を全部手話で表現する場合と助詞などの手話を省略する場合があります。聾学校などで日本語を習得する段階では、文を全部手話で表現することが必要ですが、その他の実際の手話コミュニケーションの場面では、口話のペースに手話を合わせる、手話の量を減らして疲れを少なくするなどの観点から、助詞などの手話を省略して表現します。
第1節 文を全部手話で表現する場合
「各国の努力もむなしくCO2は増加し、地球の温暖化が進んでいると言われています。」
| 各 | 国 | の | 努力 | も |
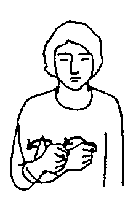 |
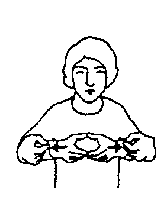 |
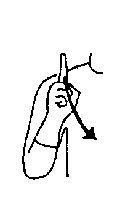 |
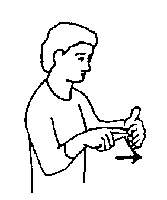 |
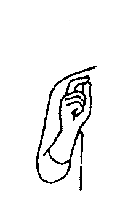 |
| むなしく | CO | 2 | は | 増加 |
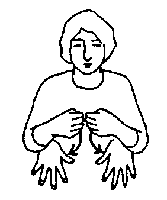 |
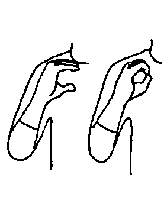 |
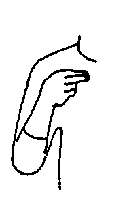 |
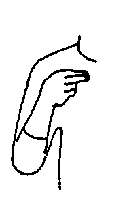 |
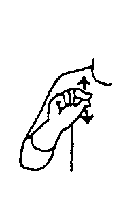 |
| し、 | 地球 | の | 温暖 | 化 |
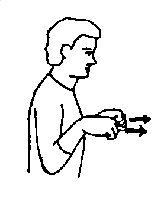 |
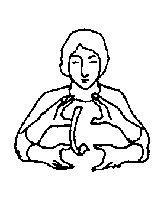 |
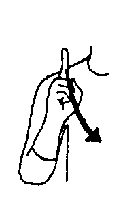 |
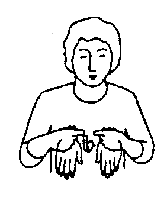 |
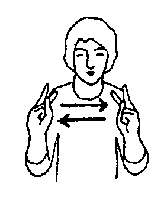 |
| が | 進ん | で | いる | と |
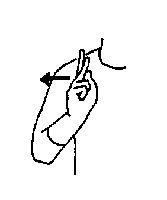 |
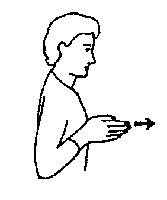 |
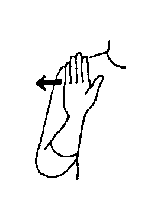 |
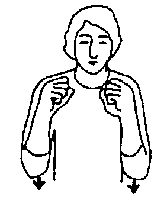 |
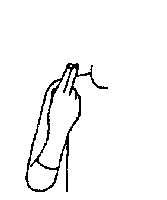 |
| 言わ | れ | て | い | ます。 |
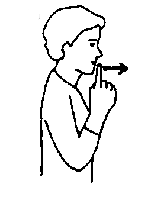 |
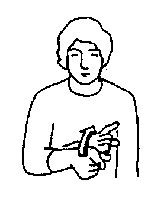 |
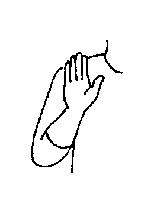 |
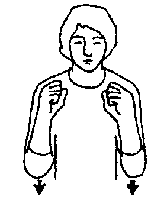 |
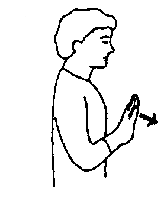 |
第2節 省略した表現例
手話で伝えようとする相手に言語力や読話力があったり、残存聴力の活用ができれば、前ページと同じ文を、助詞などの手話を省略しても、口型や音声(聴能)などに依存して、十分に伝達することができます。
手話を省略する部分は、文脈、話題、相手などに応じて変えます。
「各国の努力もむなしくCO2は増加し、地球の温暖化が進んでいると言われています。」
| 各 | 国 | の | 努力 | も |
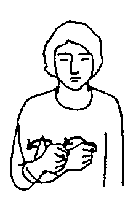 |
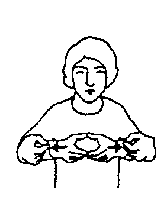 |
口型などの依存 | 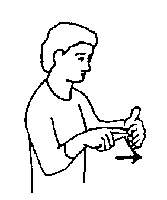 |
口型などの依存 |
| むなしく | CO | 2 | は | 増加 |
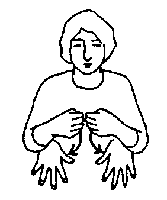 |
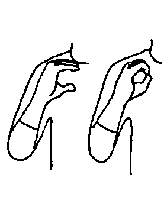 |
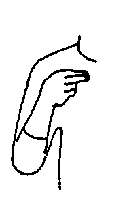 |
口型などの依存 | 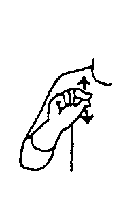 |
| し、 | 地球 | の | 温暖 | 化 |
| 口型などの依存 | 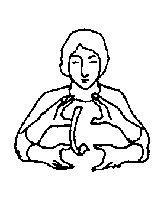 |
口型などの依存 | 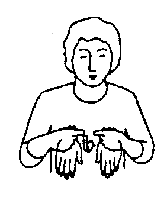 |
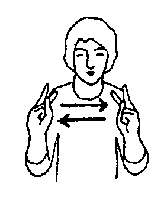 |
| が | 進ん | で | いる | と |
| 口型などの依存 | 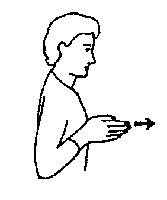 |
口型などの依存 | 口型などの依存 | 口型などの依存 |
| 言わ | れ | て | い | ます。 |
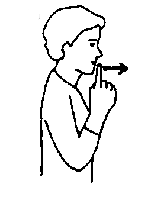 |
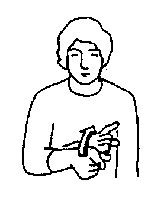 |
口型などの依存 | 口型などの依存 | 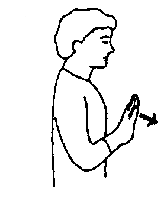 |
少し長い文で、「文を全部手話で表現する場合」と「省略した表現例」を見てもらいました。次に短い文で個々の表現について練習します。
第3節 付属語の表現
名詞、動詞、形容詞などのようにそれ自体で独立した意味をもつ言葉を自立語といいます。
助詞、助動詞など自立語について、自立語同士の関係や話者の意志をつけくわえる言葉を付属語といいます。
従来の手話では、付属語は手の位置関係や顔の表情などで表されることがありました。そのため、日本語の付属語に相当する手話がないということもありました。
日本語対応手話では、原則として付属語も全部表現することができます。
助詞、助動詞は、普通は文中での役割がは少ないので、自立語の手話の後で軽く短時間に示します。(特に強調したいときは大きく示します。)
第1項 助詞
(1)1音の助詞は原則として指文字で表します。
例:~は=指文字「ハ」 あなたは
~が=指文字「が」 わたしが
~と=指文字「と」 本と雑誌
終助詞も指文字で表すことが原則ですが、状況に応じて、どんな終助詞も、前の語が終わった位置で、指文字「サ」で示してよいことにしました。
(2)1音節の助詞でも次の語は手話を使います。
例:「~か。」
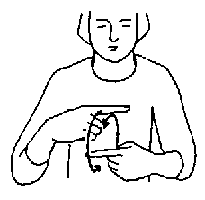 |
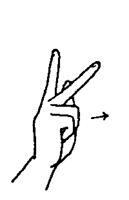 |
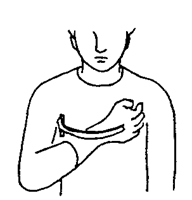 |
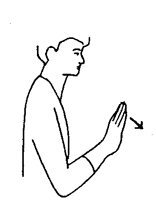 |
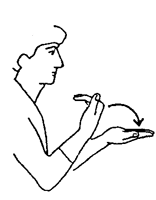 |
| 【手話 218】 | 《が》 | 【出来る 318】 | 【~ます 456】 | 【~か 75】 |
2音以上の助詞は、できるだけ既成のものをとり入れるか、音形を残す形で手話化しました。
(3)2音節以上の助詞で既成の手話を取り入れたもの
例:「~から」
「ここから900メートル」
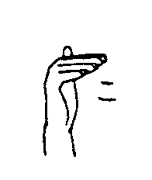 |
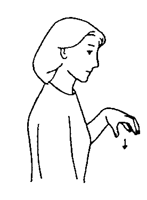 |
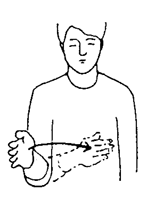 |
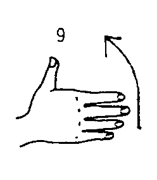 |
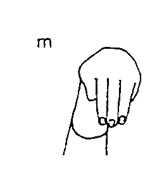 |
| 《こ》 | 【所 380】 | 【~から 99】 | 【900数詞 24】 | 【メートル】 |
例:「~けれども」
「あなたはだらしないけれども」
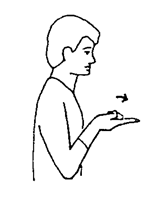 |
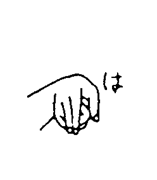 |
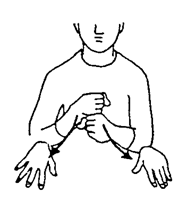 |
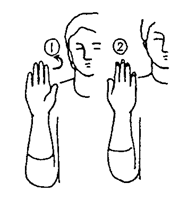 |
| 【あなた 12】 | 《は》 | 【だらしない 287】 | 【~けれども 151】 |
(4)音形を残す形で手話化したもの
例:「~しか」
「1時間しかいない」
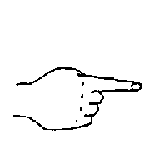 |
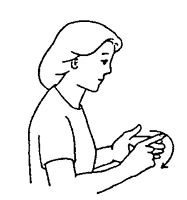 |
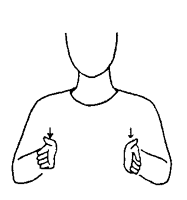 |
| 【1数詞 24】 | 【時 333】 | 【間 2】 |
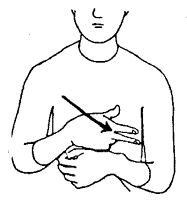 |
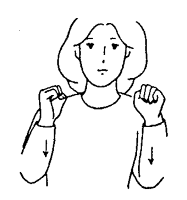 |
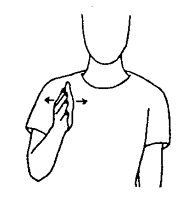 |
| 【~しか 197】 | 【居る 33】 | 【無い 346】 |
(5)指文字の連続で示す助詞
例:「など」(指文字の連続)
「狆やコリーなどの犬は」
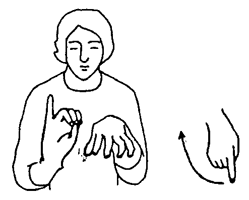 |
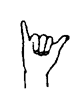 |
 |
||
| 【獣 538 +《ち》《ん》】 | 《や》 | 【獣 538 +《こ》《りー》】 | ||
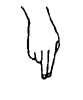 |
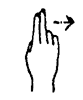 |
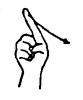 |
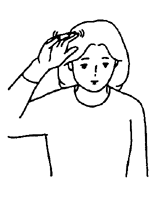 |
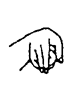 |
| 《な》 | 《ど》 | 《の》 | 【犬 29】 | 《は》 |
第2項 助動詞
助動詞は手話を作ります。活用の表示は口型によります。
例:「~たい」
「行きたかった」
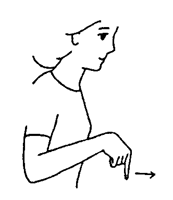 |
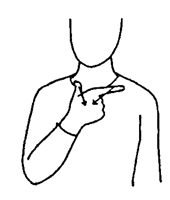 |
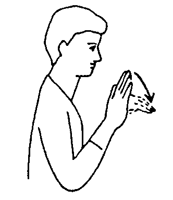 |
| 【行く 23】 | 【好き 235】 | 【~た(過去) 271】 |
連続して使われることの多い助動詞は、次のように連続した動きとして示します。
例:「~でしょう」
「明日はよい天気になるでしょう」
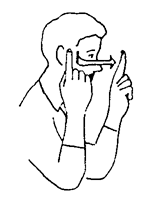 |
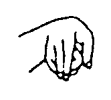 |
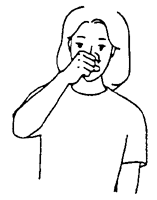 |
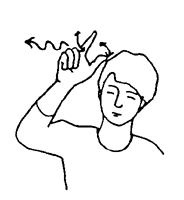 |
| 【あした 8】 | 《は》 | 【良い 504】 | 【天気 323】 |
 |
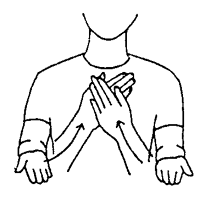 |
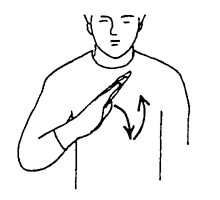 |
|
| 《に》 | 【成る 354】 | 【~でしょう 319】 |
第4節 敬語を使った表現
敬語も日本語の通りに手話を当てはめて表現します。また、手話の動作全体を丁寧に表す必要があります。
敬語では「お」や「ご」を付け加える例が非常に多くみられます。これをすべて手話で表現してしまうと、指文字などで手の動きが煩雑になり、見苦しくなります。要点だけ「お」や「ご」を付け加え、敬語であることを表しましょう。
尊敬の助動詞「~れる/~られる」は動詞に続けて表示します。受身の助動詞「~れる/~られる」と同形です。
「お慶び申し上げます」
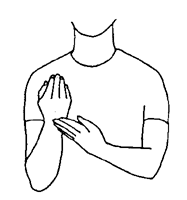 |
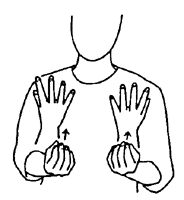 |
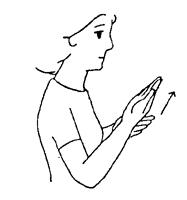 |
| 【御(ご) 157】 | 【祝う 33】 | 【申す 486】 |
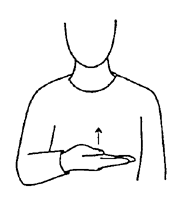 |
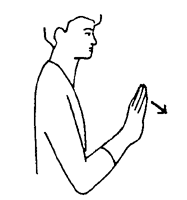 |
|
| 【上がる 4】 | 【~ます 456】 |
第5節 固有名詞の表現
地名・国名・人名などの固有名詞は、その固有名詞独特の由来をもつ手話と、漢字手話や指文字結合手話で表す手話があります。
『新・手話辞典』では、固有名詞としては、大陸名、国名、県名、東北や関東など地方名を掲載してあります。
都市名、河川、山岳、人名、企業名等は、次のような約束で表すことにして、特に辞典には載せてありません。
(1)都市、市町村名
・現地で使用している手話が通用するなら、それを用います。
例:ソウル
・漢字手話の組み合わせが通用しやすいときは、それを用いてよいことにしま す。その場合、末尾に「市」「町」「村」等の手話をつけることもできます。
例:北京=北+京
・カタカナ表示などの場合、指文字結合手話で示すことにします。
【左手の甲の上に、都市名の語頭音を指文字でしめす】
例:ロンドン
(2)河川・山岳等の名称
・現地で使用している手話が通用するなら、それを用います。
・漢字手話の組み合わせが分かりやすいときは、それを用いてもよいことにし ます。
(3)人名
・原則として、人名の漢字は漢字手話で、"かな" は指文字で表します。
「藤」は常用漢字外ですが、【藤 421】を用います。
・アルファベット(例:S.フロイト)はアルファベット指文字を用います。
・愛称形や慣用形は場面に応じて用いてよいことにします。
(4)企業、政党、団体名等は人名に準じて表現します。
第1項 国名
『新・手話辞典』に掲載したものの例として「国名」について説明します。どんな考え方で国名の手話を掲載したか分かれば、手話表現の参考になります。
(1)外国の国名については、既成手話で定着しているものはその手話で表現します。
| 例:「アメリカ」 | 例:「イギリス」 |
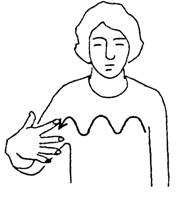 |
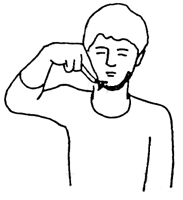 |
| アメリカ手話では 別の形を使っている |
イギリス手話では この形を使っている |
(2)既成手話にない国名は、その国で使用している国名の手話を使います。
| 例:「エチオピア」 | 例:「ケニア」 |
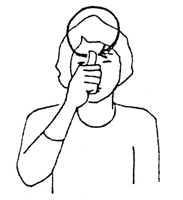 |
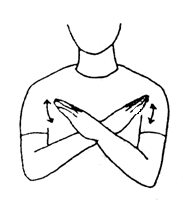 |
| 「エチオピア」の語源 「日焼けして顔の黒い人」から |
ケニア国旗にある「勇気」の 象徴の槍を示す |
(3)指文字結合手話を使う。
(1)(2)で表せない国名については、左手で「世界」の手話の半分の形を示して国名のカテゴリーを表し、右手で国名の最初の1~2文字を表します。(2)の手話で通じにくい時は、この(3)の方法で表現してもよいこととします。
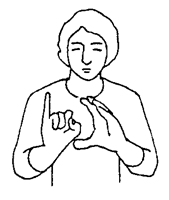 |
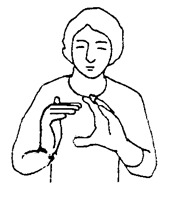 |
| 例:イスラエル | 例:コスタリカ |
(4)国名の漢字部分は漢字手話の組み合せで表現します。
| 例:モナコ公国 | ||||
 |
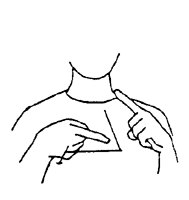 |
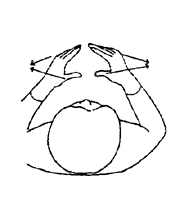 |
||
| 《も》《な》《こ》 | 【公(おおやけ) 58】 | 【国(くに) 137】 | ||
第2項 人名
(1)漢字の人名については原則として漢字手話で表します。
| 例:「竹下 登」 | ||
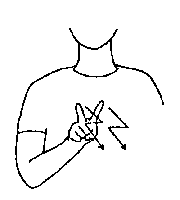 |
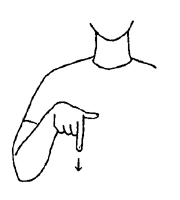 |
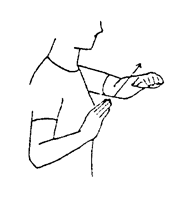 |
| 【竹】 | 【下】 | 【登】 |
(2)ひらがなやカタカナの名は指文字で示します。
(3)ただし、親しみをこめた愛称としてその人の特徴的なしぐさなどを表す手話を 使ってもよいこととします。
| 例:水戸黄門 | 水戸黄門のあこひげを示す |
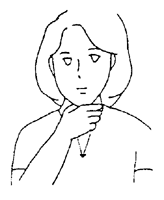 |
第3項 地名
辞典に掲載されてない地名として、例えば「筑波」があります。これは、現地でよく使われている手話ですが、筑波山の男体山と女体山を表します。
| 例:「つくば」 |
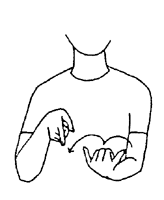 |
「東京」の手話は「東」(太陽が上る)を2回繰り返します。
| 例:「東京」 |
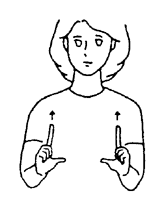 |
現地の地名の手話が不明なときやあまり知られていないときは、漢字手話の組み合せで表現してもよいことにします。
| 例:「岩手県」 | 例:「岩手の現地での手話」 |
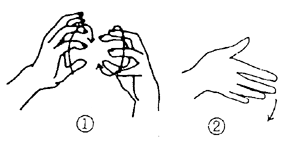 |
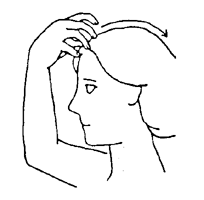 |
| 漢字手話「岩」と「手」の組み合せ | 岩手県出身の原敬首相の頭髪を示す |
(岩手を表す現地の手話は全国的には理解されにくいので、漢字手話の組み合せで表してもよいこととします。)
第6節 外来語の表現
日本語の中ではカタカナ書きの外来語がたくさん使われています。カタカナ書きだからといって、これを全部一つひとつ指文字で表現すればいいというものではありません。あまり手の動きが多すぎると、返って手話が読みとりにくくなってしまいます。そこで、外来語の表現については次のようにします。
(1)外来語に既成手話があり、造語原則上も問題がなければそれを用いる。
| 例:「オリンピック」 | 例:「マイク」 |
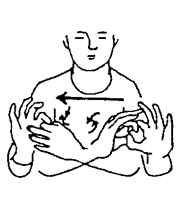 |
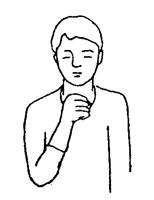 |
| 【オリンピック 71】 | 【マイク 452】 |
(2)外来語の訳語に手話があり、外来語と訳語に意味上の違いがほとんどないときは、その手話を使います。ただし、こういう場合でも、特に外来語であることを示したいときは指文字で示してもかまいません。
| 例:「リコーダ-」は「笛」の手話を使う |
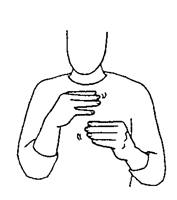 |
| 【笛 417】 |
(3)外来語の「ドクター」は、「医師」と「博士」の2つの意味で使われるので、「ドクター」に「医師」や「博士」の手話は使えません。この場合は、指文字で表します。
例:「ドクター」は指文字で表す。
(4)外来語を指文字で示すときは、語頭より3音を示すことを原則とします。
単語によっては、2音でもかまいません。
半濁音、濁音、拗音は1音、長音、撥音、促音は前の音と合わせて1音と数えます。『新・手話辞典』で指文字を○で囲んで示すときは、同じ数え方で1音ごとに囲んであります。このテキストでは印刷の都合上〔 〕で1音を囲んで示してあります。
例:〔ギョ〕で1音
例:〔ア-〕で1音
例:アニメーションは〔ア〕〔ニ〕〔メ〕で3音
(5)アルファベットが日本語の中で定着しているときは、アルファベット指文字を用います。
・大文字なら従来日本で用いられたアルファベットの表示法を用いる。
| 例:「PTA」(日本式アルファベット 23) | ||
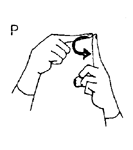 |
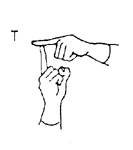 |
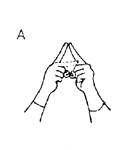 |
・単位など小文字のときは国際指文字による。
| 例:「㎝」(国際指文字) |
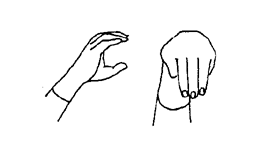 |
(6)複合外来語を指文字で示すときは、前部を2音、後部を1音にすることを原則にします。
例:「アタッシュ・ケース」=〔ア〕+〔タッ〕+〔ケ〕
第7節 助数詞・単位の表現
助数詞の表現
助数詞とは数を表す語に添えてどんな種類のものの値かを示す接尾語です。
(1)「10人」とか「100万光年」とかは漢字手話がそのまま使えます。
例:「~人」 【人(ひと) 405】
「~光年」【光(ひかり) 399】+【年(とし) 336】
(2)「熱が38度ある」の「度」は、漢字手話の「度」では不自然なので、指文字 「ド」で表すことにとします。
| 例:「熱が38度ある」 | |||
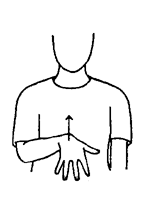 |
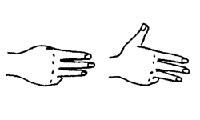 |
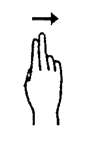 |
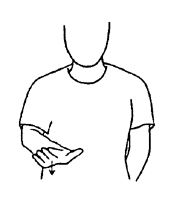 |
| 【熱い 10】 | 【38数詞 24】 | 《ど》 | 【有る 16】 |
*日本語対応手話では、この「熱」を「体温計を腋の下に入れて熱をはかるしぐさ」で表すことはしません。特に違和感がなければ、一つの単語に一つの手話という考え方からです。
単位の表現
(1)外来語の単位で、文字数が少ないときは指文字で表します。
文字数が多いときは単純手話をつくりました。
| 例:「~トン」(指文字) | 例:「~マグニチュード」(単純手話) |
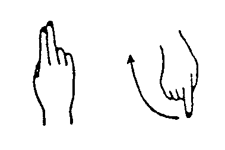 |
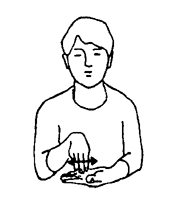 |
| 指文字「トン」 | 【マグニチュード 454】 |
(2)アルファベット表示が定着しているときは国際指文字にし、特に単純手話にした方が分かりやすいときは、それを用いることにします。
| 例:「~㎝」(国際指文字) | 例:「~カロリー」(単純手話) |
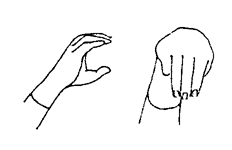 |
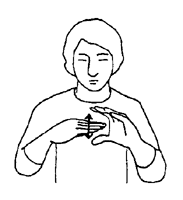 |
| 国際指文字 22ページ | 【カロリー 102】 |
第8節 擬態語・擬音語の表現
擬態語は、人の動きなどや状態などを音声で感覚的に模写して表現したものです。例えば「こそこそ」した様子を表すとき、従来の手話では、手話をする人の演技力にまかされていました。それはそれで手話の表現力として尊重すべきですが、人によって表し方が違いますし、演技力がなければ表現するのがむずかしくなってしまいます。
例えば、「こそこそ」という言葉は、それを知ってさえいれば、日本語では語彙として表現できます。それと同じように手話も、個人の演技力に関わらず、語彙を学習しさえすれば、だれでも表現できるものであるべきです。そこで『新・手話辞典』では擬音語・擬態語も日常生活上の頻度の高い語は積極的に取り上げました。『新・手話辞典』にないものは指文字で表現するようにします。
| 例:「こそこそ」 | 例:「ごそごそ」 |
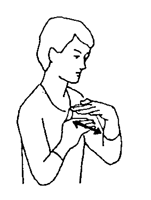 |
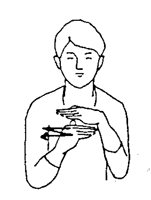 |
| 【こそこそ 166】 | 【ごそごそ 166】 |
くり返しのある語は、くり返しのない語を基本にして表現するようになっています。清音は前後の動き、濁音は片手の左右の動きまたは両手の動きで示すようにして区別しました。類似した状態を表す語同士は、手の動きも類似したものにして、指文字で区別するようにしました。
漢字手話で表現した方がよい場合は、漢字手話を用います。
| 例:「堂々」=堂+堂 | |
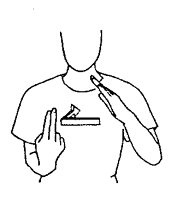 |
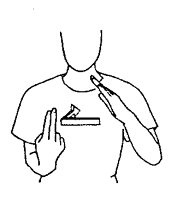 |
| 【堂 328】 | 【堂 328】 |
擬態語は同じ音の繰り返しだけではありません。次のような例もあります。
| 例:「ぬっと」 | 例:「ねっとり」 |
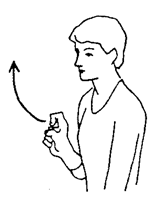 |
 |
| 【ぬっと 362】 | 【ねっとり 365】 |
物音や人や動物の声などを音声で感覚的に模写して表すのが擬音語です。擬音語も擬態語と同様に考えて手話化しました。
| 例:「がんがん」 | 例:「とんとん」 |
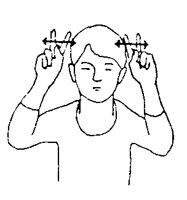 |
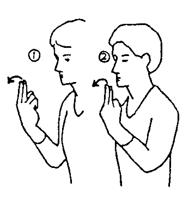 |
| 【がんがん 105】 | 【とんとん 344】 |