| (枠記号) | (分化記号) | (同形語) |
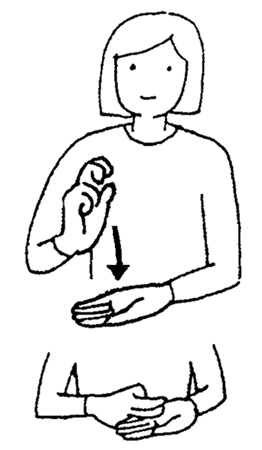 |
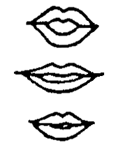 |
|
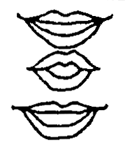 |
||
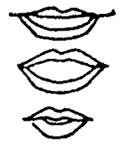 |
次の(1)〜(5)を基本原則として手話単語を作成しました。
(1)1単語1手話の原則
手話は、日本語を音声で表すのと同じように、日本語を手の形で表したものですから、日本語の一つの単語には一つの手話表現を原則としました。手話を文脈の中での意味に応じて使い分けるということをしないですむように、日本語の単語の持ついろいろな意味を表せるように手話の形を考えました。
ただし、手話では手の形や動きの方向がどうしても意味を持ってしまうために、日本語の1単語に複数の手話が対応する場合も出来てしまいました。
(2)相互補完の原則
「手話」も「読話・発語・聴能」も、どちらかを単独で用いるときよりも、併用したときの方が分かりやすく、意味も細かに伝えることができます。「手話」を「読話・発語・聴能」と併用することで相互に補完しあうことができます。日本語対応手話では、口話と手話の併用を前提にして、手話の意味を口型などで変化させて同形語を示すことにしています。
日本語の単語は何万語とありますので、それを全部手話化することはできませんし、手話化しても記憶の負担が大きくなります。そこで意味の似ている単語を同じ手話で表す場合がありますが、そのようなときは口型によって区別することを原則とします。その結果、手話の読み取りも、読話も、聴覚弁別もいっそう容易になります。
例:「法律、条例、規約」 これらは同じ手話を用いますが、口型が違うので区別できます。
| (枠記号) | (分化記号) | (同形語) |
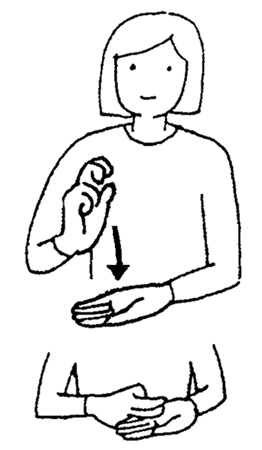 |
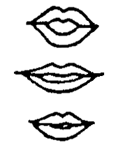 |
|
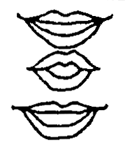 |
||
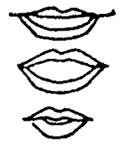 |
(3)動作経済の原則
手指の動きは発話する際の唇の動きに比べてどうしても労力と時間の負担が大きくなりがちなので、ひとつの動作の動きがなるべく小さくなるように工夫しました。手話表現の動作量が大きいことは、見分けやすくなる利点はありますが、一方、日本語を音声で表すときに比べて、手を用いる手話の表現は労力からも時間の面からも負担が大きくなります。このことは、口話と手話を併用するときにマイナスになります。そこで、動作量が少なくてすむように、1手話1動作を原則にしました。
例:「父」
| 従来の形 | 日本語対応手話での形 |
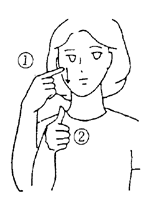 |
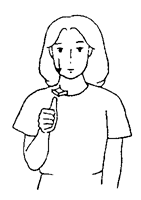 |
| 人差指で頬をなでて、 親指で頬をなでて、 親指を前に出す そのまま前に出す |
「父」【父295】 |
(4)記憶の負担軽減
『新・手話辞典』の日本語対応手話は、聴覚障害者を対象にして作成しました。聴覚障害者には生まれつき聞こえない人の他に、難聴者や中途失聴者を含みます。その難聴者や中途失聴者はもちろん、手話通訳者なども成人に達してから手話を習得する場合が多いことを考えて、手話を記憶する負担を軽くするように努力しました。
(5)既成手話の尊重
手話は、聴覚障害者の日常生活に密着した言語ですから、それを尊重して、できるだけ既成の手話をとり入れました。また、既成手話が造語原則からみて問題があるときでも、少し形を修正すれば原則と矛盾しないときは修正してとり入れました。