固体のソリトン 『エネルギー等配分の原理は正しいか?』 99/1/
ソリトン研究のブームの火付け役は、1955年の金属中の格子振動と電子の動きに関する研究だった。格子上のソリトンの問題は
「エネルギー等配分」が成り立つかどうかという学問的な興味から生じた。
古典統計力学(熱力学)の根本的な仮定のひとつが「エネルギー等配分の原理」だ。等配分の原理は、ある体系にエネルギーが
注入されたとき、おのおのの自由度へのエネルギーの分配のされ方を規定する。与えられたエネルギーは体系全体にすみやかに
均一に分配されると考えた。この原理は、なぜ物事は平衡に向かうのか、なぜ鉄の棒の一端を熱すると反対側まで熱が伝わるのか、
なぜ初期に活力のあった体系がしだいに活力がなくなってしまうのかといった疑問に答える。この原理は普遍的に成り立つと理解
されてきた。最近までは、実際に分子から分子へどのようにエネルギーが伝わるのかを調べる方法がなかったので、物理学者は
頭ごなしにこの原理を信じてきた。
しかし、コンピュータの発達で、分子中のエネルギーの移動を見ることが出来るようになり、エンリコ・フェルミ、スタニスラム・ウラム
、J・バスタなどがこの解明に取り組んだ。
金属中では原子は格子状に並んでおり、熱エネルギーにより原子の振動が大きくなる。このとき各々の原子はまとまった動きをし
波のように振動する。波の波長はいろいろな値を取りエネルギーを担う。等配分の原理によれば、ある波長の波にエネルギーを
与えると、そのエネルギーは他の波長の波に伝わり、全部の波に均等に伝わらねばならない。ところがコンピュータ・シミュレーション
の結果は予想に反し、エネルギーは等配分されずに、一つのモードの波に集中してから別のモードの波に移動することを示した。
さらに衝撃的だったのは、結果が非線形の強さには依存せず、非常に弱い非線形相互作用でも、強い非線形相互作用の時と同じように、
体系全体の振る舞いが全く非線形特有のものになってしまたことだ。十分長い時間がたつと、体系は何度も繰り返し初期のエネルギーが
局在した状態に戻ってしまうという点で、非線形の格子がある種の記憶を持っていることを示唆していた。
類推して考えると、大洋の大きな波も、たまたまいろいろな波が重なり合ってできたのではなく、初期の記憶を維持した
ソリトンの自己集中によって生じるものだとも考えられる。
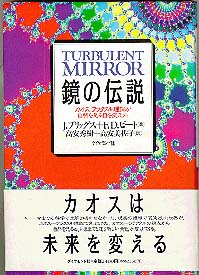 固体中の原子の格子を伝わる振動の研究が進み、金属の棒の一端を強く叩くと、力学的エネルギーがソリトンとなり棒の他端に
伝わり、急激な熱の変化もソリトンになることが分かってきた。
固体中の原子の格子を伝わる振動の研究が進み、金属の棒の一端を強く叩くと、力学的エネルギーがソリトンとなり棒の他端に
伝わり、急激な熱の変化もソリトンになることが分かってきた。
【いよいよ 本題!】
光と物質が非線形に相互作用したときに起きる『自己誘導透過性』
レーザー光のような高いエネルギーの光を物質に当てると、光は吸収されずにパルスになって透過する。
(★透明なガラスなどが光を透過させるのは当然だが、本来光を通さない物質でもレーザー光ソリトンなら透過するという意味だ)。
レーザー光は原子を
励起し、光と非線形に相互作用し合い、一体となって波のように動く。この結果生じるソリトンは、正確には光でもないし、
原子の振動でもない。両者が渾然一体となったソリトンで<ポーラリトン>と呼ばれるものだ。
NECが開発した「光ソリトン半導体レーザー」は、上の原理を利用して、情報を持ったレーザー光を、ポーラリトンの
状態で光ファイバーの中を何10kmも伝えようとするものだと思う。今まで解説したソリトン・孤立波の性質を使えば
複数のソリトンが途中で交じり合ってしまうこともないので、出口で選り分けることが出来るはずだ。「時分割多重」や
「波長多重」を同時に行うのにソリトンは最適だ。
ポーラリトンの透過性は、核融合でも利用できると考えられているようだ。木星に大気ソリトンが見つかったように、
太陽の内部にはポーラリトンによる核融合が行われているのかもしれない。
★ このソリトンに関する解説は、『鏡の伝説』J・ブリッグス+F・D・ピート著(ダイアモンド社1991)を参考にした。
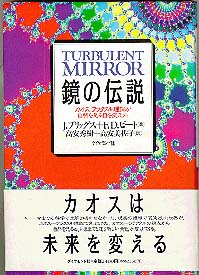 固体中の原子の格子を伝わる振動の研究が進み、金属の棒の一端を強く叩くと、力学的エネルギーがソリトンとなり棒の他端に
伝わり、急激な熱の変化もソリトンになることが分かってきた。
固体中の原子の格子を伝わる振動の研究が進み、金属の棒の一端を強く叩くと、力学的エネルギーがソリトンとなり棒の他端に
伝わり、急激な熱の変化もソリトンになることが分かってきた。