カオスから見た時間の矢
田崎秀一著 ブルーバックス(2000/4 第1刷)
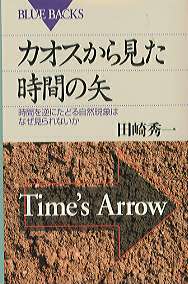 20世紀初頭に活躍したイギリスの天文学者・物理学者アーサー・エディmトンは、「過去」と「未来」が区別される
という時間の性質を、過去から未来に向かう「矢」という意味で「時間の矢」と表現した。
20世紀初頭に活躍したイギリスの天文学者・物理学者アーサー・エディmトンは、「過去」と「未来」が区別される
という時間の性質を、過去から未来に向かう「矢」という意味で「時間の矢」と表現した。
 物理現象には、「時間の矢」の向きーー「過去」と「未来」に違いがあることーーを読み取れるものと,読み取れないものがある。
物理現象には、「時間の矢」の向きーー「過去」と「未来」に違いがあることーーを読み取れるものと,読み取れないものがある。
前者を【不可逆現象】、後者を【可逆現象】という。
たとえば、人は年々老いてゆき決して若返る事はないし、「腹水盆に返らず」のことわざ通り、容器がひっくり返って流れ出た
水が自然に容器に戻っていく事はない。人の老化や水がこぼれる現象では、どの場面が古く、どの場面が新しいか、はっきり
区別できる。現象を見ているだけで「時間の矢」の向きが読み取れる、つまり不可逆である。
 これに対して、物質を構成する原子・分子の(微視的)運動は可逆である。可逆とは、たとえば、原子・分子の運動の様子を
ビデオに録画してとき、逆再生画面で見られる運動が自然法則にしたがって起こり得るという性質の事である。
これに対して、物質を構成する原子・分子の(微視的)運動は可逆である。可逆とは、たとえば、原子・分子の運動の様子を
ビデオに録画してとき、逆再生画面で見られる運動が自然法則にしたがって起こり得るという性質の事である。
一例をあげる。実験者Aが分子の衝突過程を記録したビデオを2本用意し、被験者Bに2本のビデオの再生画面を見せたとしよう。一方は順再生し、もう一本は
逆再生する。このとき、AがBに「どちらのビデオが順再生で、どちらのビデオが逆再生か当てよ」と質問すると、被験者Bは
(あてずっぽうではなく)確実に答える事は出来ない。なぜなら逆再生した画面で見られる現象もうまく実験を工夫すれば
起こすことが可能だからである。この性質が可逆性である。
 『「時間の矢」の向きが読みとれない微視的運動をもとに、「時間の矢」が読み取れる巨視的現象をどう説明すればよいか』
という疑問は『不可逆性の問題』として約100年ほど前、ボルツマンの理論
に対する批判から始り、今も解決されていない。
『「時間の矢」の向きが読みとれない微視的運動をもとに、「時間の矢」が読み取れる巨視的現象をどう説明すればよいか』
という疑問は『不可逆性の問題』として約100年ほど前、ボルツマンの理論
に対する批判から始り、今も解決されていない。
最近の研究によれば、問題の鍵となる二つの概念、『ギッブス集団』と『カオス』を援用することで、かなり理解が進んだ。
−−はじめに よりーー
以上の前置きから、約250ページにわたり最新の研究の成果が、素人にも分り易く?展開される。
興味のある人には本書の購読(¥900)をお勧めし、もくじの一部を掲載しよう。
 目次
目次
第1章 「時間の矢」と不可逆性の問題
ボルツマン・ゲーム、熱力学の法則とエントロピー、可逆性のパラドックス、再帰性のパラドックス など
第2章 時間反転の実験
ロシュミットの魔、原子核のスピン運動、スピンの木霊、カーとパーセルの実験、スピンの歳差運動 など
第3章 ギッブスの見方ーー統計集団の考え方ーー
気体の性質とダイレクトメール、ブラウン運動、ギッブス集団ー熱平衡状態を表すギッブスの「雲」、孤立系の
熱平衡状態ーーミクロ・カノニアル集団 など
第4章 カオス
単振り子のギッブス集団、3体問題とカオス、ローター付き振り子の運動、水滴落下運動のカオス、ぱいこね変換、
など
第5章 拡散という不可逆現象
臭素の拡散と濃度勾配、フィックの法則、酔歩、ローレンツ気体、回帰写像の特徴ーーカオス性と可逆性 など
第6章 分布に刻まれる「時間の矢」
熱平衡に向かう不可逆性ーー閉じた多重ぱいこね変換、ギッブス集団で不可逆性が現れる理由、非平衡定常状態と
フラクタル分布、分布に刻まれる「時間の矢」、論争は続く など
 感想に代えて
感想に代えて
・本書がテーマとしている「時間の矢」「不可逆性の問題」を十分理解できたなどとは言わない。 が、面白く、知的好奇心を
満たしてくれる本だ。
・本論は別として、物理学の論争の流れや最新のカオス・複雑系理論との接点が分り興味がつきない。
・特に、第2章は「MRI(核磁気共鳴装置)」の原理が平易に書かれているので勉強になった。
・休日、昼食の「やきそば」を担当している。フライパンの中でそばと粉末ソースがまんべんなく混じるようにかき混ぜるとき、
「ぱいこね変換(理論)」の実践だ!と気合を入れながらやっている。。。。。
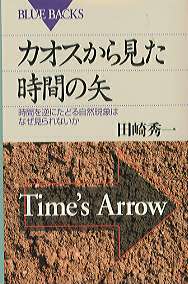 20世紀初頭に活躍したイギリスの天文学者・物理学者アーサー・エディmトンは、「過去」と「未来」が区別される
という時間の性質を、過去から未来に向かう「矢」という意味で「時間の矢」と表現した。
20世紀初頭に活躍したイギリスの天文学者・物理学者アーサー・エディmトンは、「過去」と「未来」が区別される
という時間の性質を、過去から未来に向かう「矢」という意味で「時間の矢」と表現した。 物理現象には、「時間の矢」の向きーー「過去」と「未来」に違いがあることーーを読み取れるものと,読み取れないものがある。
物理現象には、「時間の矢」の向きーー「過去」と「未来」に違いがあることーーを読み取れるものと,読み取れないものがある。 これに対して、物質を構成する原子・分子の(微視的)運動は可逆である。可逆とは、たとえば、原子・分子の運動の様子を
ビデオに録画してとき、逆再生画面で見られる運動が自然法則にしたがって起こり得るという性質の事である。
これに対して、物質を構成する原子・分子の(微視的)運動は可逆である。可逆とは、たとえば、原子・分子の運動の様子を
ビデオに録画してとき、逆再生画面で見られる運動が自然法則にしたがって起こり得るという性質の事である。 『「時間の矢」の向きが読みとれない微視的運動をもとに、「時間の矢」が読み取れる巨視的現象をどう説明すればよいか』
という疑問は『不可逆性の問題』として約100年ほど前、ボルツマンの理論
に対する批判から始り、今も解決されていない。
『「時間の矢」の向きが読みとれない微視的運動をもとに、「時間の矢」が読み取れる巨視的現象をどう説明すればよいか』
という疑問は『不可逆性の問題』として約100年ほど前、ボルツマンの理論
に対する批判から始り、今も解決されていない。 目次
目次 感想に代えて
感想に代えて