yosinogari History MUSEUM
2016.10.

復元された「主祭殿」:吉野ヶ里の政を司る最重要施設(高さ16.5㍍)
魏志倭人伝の時代と重なる吉野ヶ里遺跡 観光資源としての吉野ヶ里遺跡を観る!
「佐賀県神埼市」と「神埼郡吉野ヶ里町」にまたがる丘陵地帯にあり、2000年(紀元3世紀頃)の歴史を紐解く。 弥生時代後期には40㌶を超す国内最大規模の「環濠集落」として発展。遺跡の整備と保存は、平成3年5月に特別史跡に指定され、翌年4月から「国営吉野ヶ里歴史公園」として整備保存がなされている。
現在、国営公園約52.8㌶、県立公園44.3㌶を合わせて97.1㌶の史跡公園として年間60万人の入館がある。
弥生時代後期には40㌶を超す国内最大規模の「環濠集落」として発展。遺跡の整備と保存は、平成3年5月に特別史跡に指定され、翌年4月から「国営吉野ヶ里歴史公園」として整備保存がなされている。
現在、国営公園約52.8㌶、県立公園44.3㌶を合わせて97.1㌶の史跡公園として年間60万人の入館がある。
吉野ヶ里遺跡は弥生時代の巨大遺跡。南北1km以上、甲子園の10倍となる約40ヘクタールの土地から、周囲を二重の堀で囲まれた大環濠集落や王族の墳丘墓、約3千もの甕棺(かめかん、昔の棺)が見つかっている。また、高さ12mの物見やぐら跡があり、傷を受け首がない人骨や鉄の矢じりも出ており、文献に残る邪馬台国のように戦争していたことが分かる。 『魏志倭人伝』の邪馬台国に類似した大型遺構(主祭殿・物見櫓・東祭殿・祀堂・高床倉庫・竪穴建物~王の妻の家・煮炊屋)や遺物が次々と発見され復元されている。
神埼市の人口32,089、世帯数11,569、議員定数20人(H28.9.30)。大化の改新以降、神埼市の平野部では、人々に一定の土地を割り与える班田制が施行され、この遺構としての条里制の坪名が今も残り、奈良時代に大宰府政庁へと続いた「西海道」の官道跡も残っている歴史と文化の町である。
○「北墳丘墓(きたふんきゅうぼ)」
 北墳丘墓の規模は南北約40m、東西約27m以上で長方形に近い形で、すっぽり外観を鉄筋コンクリートの構造物で覆い、墳丘墓のままの姿形で保存し、内部は発掘時の本物の遺構と甕棺(かめかん)が見られるように、遺構面を保護するために、地面に触れる部分は30cm以上の盛土を行なったうえ、八角形の平面形状を持つお椀をひっくり返したような、基礎のない特殊な構造で遺構展示空間を確保しています。
北墳丘墓の規模は南北約40m、東西約27m以上で長方形に近い形で、すっぽり外観を鉄筋コンクリートの構造物で覆い、墳丘墓のままの姿形で保存し、内部は発掘時の本物の遺構と甕棺(かめかん)が見られるように、遺構面を保護するために、地面に触れる部分は30cm以上の盛土を行なったうえ、八角形の平面形状を持つお椀をひっくり返したような、基礎のない特殊な構造で遺構展示空間を確保しています。
内部の北墳丘墓は、黒色土を1.2mに盛った上に幾層にも様々な土を突き固めた版築(はんちく)技法で築かれています。内部の現存高2.5mですが元来4.5m以上の高さを持った墓であった可能性があると考えられています。
これまでの調査で、弥生時代中期前半から中頃にかけての14基の大型成人甕棺が墳丘内から発掘されています。このうち、8基の甕棺からは、把頭飾付き有柄(ゆうへい)細形銅剣や中細形銅剣を含む銅剣8本やガラス製管玉79個など、被葬者の身分を示すと考えられる貴重な副葬品が出土しています。また、埋葬されていたのは成人だけであったため、おそらく特定の身分、それも歴代の首長および祭事をつかさどる身分の人の墓ではないかと思われます。
本物の遺構を露出展示するために、ポリシロキサン系樹脂を遺構麺に撒布し、ヒビ、カビ、コケの発生を防いでいます。また遺構面の湿度を80%に保つために専用の空調も整備されています。 吉野ヶ里遺跡発掘調査HPより
○甕棺墓

甕棺墓(紀元前200年頃、弥生時代中期) 弥生時代の北部九州の墓制には支石墓、土壙墓、木棺墓、箱式石棺墓、甕棺墓などがある。中でも大型の甕を棺として利用する甕棺墓は、北部九州に特有の墓制であり、縄文時代晩期の壷棺葬にその起源を求めることが出来る。 甕棺墓は、弥生時代前期末に棺専用としての甕が作られ始めてからは、中期以降爆発的に増加し、100基以上密集して集団墓を形成する場合が多い。しかし弥生時代後期から衰退し、末期にはなくなった。 丹塗り土器も見つかっている。(魔除け・悪魔払い)
○丹の検証
魏志倭人伝(原文)から見る興味深い弥生人の生活習慣!
赤色「朱(しゅ)」や「丹(に)」について!

魏志倭人伝に見る比定又は伝承地(北九州)
●魏志倭人伝に見る比定又は伝承地(北九州)
●佐賀県、吉野ヶ里遺跡について。
弥生時代:魏志倭人伝との関係!


弥生後期には40㌶を超す環濠集落ができていた。




97.1㌶の吉野ヶ里遺跡(平成3年5月に特別史跡:「国営吉野ヶ里歴史公園」)
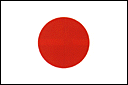
Copyright© T.Kiku Office 2016,
Web pages Created by tamio kiku
2016.10.

復元された「主祭殿」:吉野ヶ里の政を司る最重要施設(高さ16.5㍍)

魏志倭人伝の時代と重なる吉野ヶ里遺跡 観光資源としての吉野ヶ里遺跡を観る!
「佐賀県神埼市」と「神埼郡吉野ヶ里町」にまたがる丘陵地帯にあり、2000年(紀元3世紀頃)の歴史を紐解く。
 弥生時代後期には40㌶を超す国内最大規模の「環濠集落」として発展。遺跡の整備と保存は、平成3年5月に特別史跡に指定され、翌年4月から「国営吉野ヶ里歴史公園」として整備保存がなされている。
現在、国営公園約52.8㌶、県立公園44.3㌶を合わせて97.1㌶の史跡公園として年間60万人の入館がある。
弥生時代後期には40㌶を超す国内最大規模の「環濠集落」として発展。遺跡の整備と保存は、平成3年5月に特別史跡に指定され、翌年4月から「国営吉野ヶ里歴史公園」として整備保存がなされている。
現在、国営公園約52.8㌶、県立公園44.3㌶を合わせて97.1㌶の史跡公園として年間60万人の入館がある。吉野ヶ里遺跡は弥生時代の巨大遺跡。南北1km以上、甲子園の10倍となる約40ヘクタールの土地から、周囲を二重の堀で囲まれた大環濠集落や王族の墳丘墓、約3千もの甕棺(かめかん、昔の棺)が見つかっている。また、高さ12mの物見やぐら跡があり、傷を受け首がない人骨や鉄の矢じりも出ており、文献に残る邪馬台国のように戦争していたことが分かる。 『魏志倭人伝』の邪馬台国に類似した大型遺構(主祭殿・物見櫓・東祭殿・祀堂・高床倉庫・竪穴建物~王の妻の家・煮炊屋)や遺物が次々と発見され復元されている。
神埼市の人口32,089、世帯数11,569、議員定数20人(H28.9.30)。大化の改新以降、神埼市の平野部では、人々に一定の土地を割り与える班田制が施行され、この遺構としての条里制の坪名が今も残り、奈良時代に大宰府政庁へと続いた「西海道」の官道跡も残っている歴史と文化の町である。
○「北墳丘墓(きたふんきゅうぼ)」
 北墳丘墓の規模は南北約40m、東西約27m以上で長方形に近い形で、すっぽり外観を鉄筋コンクリートの構造物で覆い、墳丘墓のままの姿形で保存し、内部は発掘時の本物の遺構と甕棺(かめかん)が見られるように、遺構面を保護するために、地面に触れる部分は30cm以上の盛土を行なったうえ、八角形の平面形状を持つお椀をひっくり返したような、基礎のない特殊な構造で遺構展示空間を確保しています。
北墳丘墓の規模は南北約40m、東西約27m以上で長方形に近い形で、すっぽり外観を鉄筋コンクリートの構造物で覆い、墳丘墓のままの姿形で保存し、内部は発掘時の本物の遺構と甕棺(かめかん)が見られるように、遺構面を保護するために、地面に触れる部分は30cm以上の盛土を行なったうえ、八角形の平面形状を持つお椀をひっくり返したような、基礎のない特殊な構造で遺構展示空間を確保しています。内部の北墳丘墓は、黒色土を1.2mに盛った上に幾層にも様々な土を突き固めた版築(はんちく)技法で築かれています。内部の現存高2.5mですが元来4.5m以上の高さを持った墓であった可能性があると考えられています。
これまでの調査で、弥生時代中期前半から中頃にかけての14基の大型成人甕棺が墳丘内から発掘されています。このうち、8基の甕棺からは、把頭飾付き有柄(ゆうへい)細形銅剣や中細形銅剣を含む銅剣8本やガラス製管玉79個など、被葬者の身分を示すと考えられる貴重な副葬品が出土しています。また、埋葬されていたのは成人だけであったため、おそらく特定の身分、それも歴代の首長および祭事をつかさどる身分の人の墓ではないかと思われます。
本物の遺構を露出展示するために、ポリシロキサン系樹脂を遺構麺に撒布し、ヒビ、カビ、コケの発生を防いでいます。また遺構面の湿度を80%に保つために専用の空調も整備されています。 吉野ヶ里遺跡発掘調査HPより
○甕棺墓

甕棺墓(紀元前200年頃、弥生時代中期) 弥生時代の北部九州の墓制には支石墓、土壙墓、木棺墓、箱式石棺墓、甕棺墓などがある。中でも大型の甕を棺として利用する甕棺墓は、北部九州に特有の墓制であり、縄文時代晩期の壷棺葬にその起源を求めることが出来る。 甕棺墓は、弥生時代前期末に棺専用としての甕が作られ始めてからは、中期以降爆発的に増加し、100基以上密集して集団墓を形成する場合が多い。しかし弥生時代後期から衰退し、末期にはなくなった。 丹塗り土器も見つかっている。(魔除け・悪魔払い)
○丹の検証
魏志倭人伝(原文)から見る興味深い弥生人の生活習慣!
赤色「朱(しゅ)」や「丹(に)」について!

- ★ 「広辞苑」の「丹」記事と考古学者の見解。
- 「朱」--① 黄ばんだ赤色。② 赤色の顔料。成分は硫化水銀。天然には辰砂(しんさ)として産する。水銀と硫黄と苛性加里・苛性曹達とを熱して製し、また水銀と硫黄とを混じて、これを昇華させて製する。銀末。
 考古学者によると、「朱」は硫化水銀。市毛勲氏によると、「赤色」のことで、分類すると、① 水銀朱・② べンガラ(赤鉄鉱)・③ 鉛丹の三者になる。
考古学者によると、「朱」は硫化水銀。市毛勲氏によると、「赤色」のことで、分類すると、① 水銀朱・② べンガラ(赤鉄鉱)・③ 鉛丹の三者になる。 - 「丹」--①赤色の土。あかつち。あかに。和名抄に「丹砂(邇)」とある。② 赤土で染めた赤色。万葉集に「さにぬりのおほはしの上ゆ」とある。また、右と関連する「辰砂」・「埴(はに)」については、次の如く記されています
考古学者によると、「丹」はべンガラ。市毛勲氏によると、辰砂(天然水銀朱)、「倭人伝」に見える「丹」。
- 「朱」--① 黄ばんだ赤色。② 赤色の顔料。成分は硫化水銀。天然には辰砂(しんさ)として産する。水銀と硫黄と苛性加里・苛性曹達とを熱して製し、また水銀と硫黄とを混じて、これを昇華させて製する。銀末。
- 【魏志倭人伝:原文11】
- 『倭地温暖 冬夏食生菜 皆徒跣 有屋室
- 父母兄弟臥息異處 以朱丹塗其身體 如中國用粉也 食飲用邊豆 手食
- 其死有棺無槨 封土作冢 始死 停喪十餘日 當時不食肉 喪主哭泣 他人就歌舞飲酒 己葬擧 家詣水中澡浴 以如練沐』
- 【魏志倭人伝:古語訳11】
- 倭の地は温暖にして、冬・夏生菜を食す。皆徒跣なり。 屋室有り。
- 父母兄弟の臥息処を異にす。朱丹を以てその身体に塗る、中國の粉を用うるごとし。食飲にはヘン豆を用い、手もて食う。
- その死するや棺有れども槨無く、土を封じてツカを作る。始めて死するや、停喪すること十余日なり。時に当たりて肉を食わず。喪主コツ泣し、他人就いて歌舞し飲酒す。已に葬るや、家をあげて水中にいたりてソウ浴し、以て練沐の如くす。
- ●参考資料へリンク
- 吉野ヶ里歴史公園へリンク(国の特別史跡)
- 吉野ヶ里歴史公園全体図(拡大図)
- 神埼市歴史文化遺産を活用したまちづくり基本計画(平成22年2月22日)
- 神埼市吉野ヶ里歴史公園周辺景観条例
- 佐賀ミュージアムズへリンク(博物館と美術館併設)
- 佐賀県/県土整備部/都市計画課(佐賀県美しい景観条例)(平成20年4月1日施行)
- 佐賀県遺跡地図(埋蔵文化財包蔵地)(文化財保護法に基づく)
- 九州の景観行政ネット
- 神埼市HP(人口32,089人:2016.9.30.調)
- 吉野ヶ里町HP(人口16,229人:2016.10.1.調)
- 観光社会資本の事例(国土交通省)
魏志倭人伝に見る比定又は伝承地(北九州)
●魏志倭人伝に見る比定又は伝承地(北九州)
- 長崎県対馬市・対馬國~1,000戸○
- 長崎県壱岐市・一支國~3,000戸○
- 佐賀県唐津市・末蘆國~4,000戸○
- 福岡県糸島市・伊都國~1,000戸○
- 福岡県春日市・奴 國~20,000戸○
- 福岡県糟屋郡・不弥國~1,000戸
- ? ・投馬國~50,000戸
- ? ・狗奴国~12,000戸
- ? ・邪馬台国~70,000戸
●佐賀県、吉野ヶ里遺跡について。
弥生時代:魏志倭人伝との関係!

- BC1
・丘陵南部で青銅器の鋳造がおこなわれる。
・北墳墓丘が築造され、有柄銅製やガラス管玉等が副葬される。 - A.D.1
・外環濠が掘削され始め、大規模な環濠集落が成立する。 - A.D.107.
・内濠が掘削され、南濠が成立する。物見やぐらが建てられる。 - A.D.147.
・南内郭は堀直され、新たに北内郭も成立する。大型建物が建てられる。 - A.D.239.(明帝景初3年)
・卑弥呼が魏の国へ使い送る。「親魏倭王」から称号と金印授与、銅鐸賜る


弥生後期には40㌶を超す環濠集落ができていた。




97.1㌶の吉野ヶ里遺跡(平成3年5月に特別史跡:「国営吉野ヶ里歴史公園」)
| Ⅰ. 佐賀県神埼市 |
Ⅱ. 神埼群吉野ヶ里町 |
| ■ 風に吹かれて!Link 寄稿・投稿・紀行文 | ||||||||