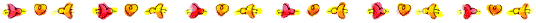SFのページだよ☆
SFのページだよ☆
 SFのページだよ☆
SFのページだよ☆
| 本のタイトル | 作者 | 出版社・その他備考 | 点数 |
| エンダーのゲーム | オースン=スコット=カード | ハヤカワ文庫SF | 95点 |
| 失われた世界 | コナン=ドイル | ハヤカワ文庫SF | 75点 |
| 鋼鉄都市 | アイザック=アシモフ | ハヤカワ文庫SF | 70点 |
| グッドラック | 神林長平 | 早川書房 | 90点 |
| アンドリューNDR114 | R=シルヴァバーグ | 創元SF文庫 | 100点 |
| エンダーズ・シャドウ(NEW!) | オースン=スコット=カード | 創元SF文庫 | 90点 |
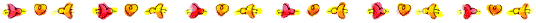
|
『エンダーのゲーム』他『ゼノサイド』『死者の代弁者』 彼の作品はみんな好きなんですけどね。「ワーシング年代記」も読みふけったですが、まあ紹介の最初は「エンダーのゲーム」から。 人口過剰で子供は二人までしか許されない地球で、特別に認可された3番目の子供、アンドルー。苛烈な、あまりに過酷な訓練は彼の精神を蝕んでゆく。そして、彼が最後に見るものは……。 いつもひとりぼっちで、全編を通して漂っているさみしい雰囲気が好きです。その後、彼はアウトサイダーのまま、生き続けます。続編「ゼノサイド」「死者の代弁者」でも、兄のピーターと姉のヴァレンタインは出てきても、バトルスクールの仲間とか「師」メイザー=ラッカムなどは回想にすら出てこないし。思うに、その後「代弁者」を続けながらも彼は、人に深入りし、人に接するのが怖かったのではないでしょうか? 結局、惑星ルジタニア(ポルトガルの古名)で人間関係の深みにはまりこむわけですが、すると今度はまたまたバガー戦争再来の危機に陥るし(落ち着くと災難が起きるイナゴみたいな人だね)……。 |
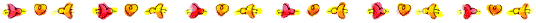
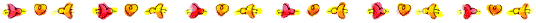
|
『失われた世界』 いまさらかもしれないけど、紹介します。ジュブナイル版で最初に読んだときと、印象がそう変わらぬあたりがすごいですね。SFとしての要素はさすがに劣化していますが、冒険小説としてのおもしろさは決して劣化しないのではないでしょうか? シャーロック=ホームズ物にも、ドイルのそういったすごさが現われていますね。いわゆる「古典」のミステリで、ほぼ同時代の物を較べてみれば、「ルパン」はもう読むに耐えないし、チェスタトンは面白いけど何か白人/白人文明至上主義が鼻につく。ソーンダイクやバン・ドゥーゼンは(確か「シャーロック=ホームズのライバルたち」とかいうシリーズで、どっかからでてましたっけ?)、もはや化石のようにかえりみられることもない……。 でも、ドイルは違う。確かに白人至上主義の時代の人間ですが、彼は彼なりに公平でフェアであろうとしているように思えます(それがイギリス式啓蒙主義、である点も事実ではあるが)。ホームズの「思い出」の「黄色い顔」などは私の大のお気に入りの話です(……まあ、非常に啓蒙的でイヤラシイ話なんですけどね。ちなみに一番好きな話は「瀕死の探偵」と「赤毛連盟」です)。 主人公が恋をして、その女性に認められるために冒険に出て帰ってきたらつまらん男と結婚していた、という導入とオチが好きです。失意の主人公に話しかけるロクストンの口調からすると、彼もまた失恋の失意から冒険野郎になったという経緯を抱えているのでしょうか? 船便で届く原稿の新聞連載、という形式もまたいいです。当時としてはリアリズムの追求として、今ではノスタルジーをそそるおおらかさとして。奇妙な形のガーゴイル(実は翼竜)がロンドンの空を飛んでばあさんが腰を抜かしたなど、いかにもサンあたりが一面に乗せそうなエピソードが語られるくだりなど、読んでいてゾクゾクします。チャレンジャー教授は単なる野蛮人、というのも楽しい。「博士」だの「教授」だのに求める理知的でクールな反応がまるでないのも、パロディじみていておもしろいです。進化論の講演で「異議あり!」と叫んで場をブチ壊し、「恐竜は生きている」と言い出すあたり、我田引水で子供じみていていいです。何せ、進化論の講演の内容自体とチャレンジャーの恐竜の話とは全然矛盾しないので(別に恐竜が生きていることが進化論を否定するものではない)、最初から喧嘩を売りにそこに行ったということが見え見えでいいです。ほんっとうにワクワクしながら読める本です。それは間違いないです(笑)。 |
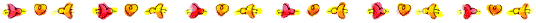
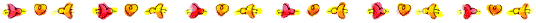
|
『鋼鉄都市』 いまさら……第二弾(苦笑)。でも、みんな読んでるので安心して話ができる(笑)。私がSFに触れたのは小学校の頃、図書館にあったジュブナイルのSF全集の「不死販売株式会社(フリージャックス)」です(……今にして思えばなんて本を……)。その全集の中に無論「鋼鉄都市」はあったはずなのですが、不幸にして全部読む前に卒業してしまいました。だから、実は読んだのは遅いです(高校のとき)。 う〜ん……この作品って、ジュブナイルではどんな訳になっていたのでしょう? 「失われた世界」同様、子供に読ませても充分理解できる名作なので、やたらめったら削られていて欲しくないなあ。ロボットと人間の違いを(差別的に)常に意識していながらも、いつしかロボットに友情を感じる主人公。アシモフの作品は大抵連作なので、著作が新しくなるにつれてどんどん面白く、ヒューマニズムにあふれる話になっていきます(まあ、もっとも暴力より謀略によって歴史は動く、という彼のスタンスは変わらないので、登場人物はそれなりにみんなあざといです……これも著作とともにエスカレートします)。ついには、このロボットは主人公との約束――人類を守る、という約束を果たすために何万年も稼働し続けるのですから。 |
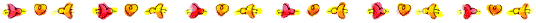
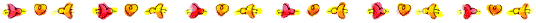
|
『グッドラック――戦闘妖精・雪風』 ついに。ついにあの作品が帰ってきた。ハヤカワのことだから、すぐに文庫に落ちるだろうことは予測できてめちゃめちゃ悔しいのだが、思わずハードカバーで買ってしまった。 だが……いいのか? 前作のまるで救われないオチが、見事に逆転している。零が、まともな人間になっているのだ。これでは、「敵は海賊」とのストーリーの差別化(雪風=無口なラジェンドラという気がする……)ができない。ラストも、こんな終わり方でいいのか? 次回作も期待していいのだな? と問いたくなる(笑)。帯の、「この戦いに、もはや人間は必要ない。」のあおりは無駄だったね。それは、前作「雪風」につけるべきあおりだ! 今回のとは少々テーマが違いすぎる気がする。 |
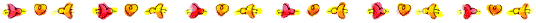
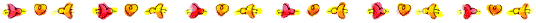
|
『アンドリューNDR114』 とうとう「エンダーのゲーム」を超える評価のSFが出てしまった(笑)。アシモフの「聖者の行進」収録の「バイセンティニアル・マン」を焼きなおして長編にした作品だが、これが焼き直しとは思えないほど香ばしい。原作のエグみも非常にいいものだが、これはうまくそれを除去してある。アシモフの作品を通好みの究極の一品料理とすれば、これはまさに誰もが認める究極のごちそうである。 ロボットは、人間になることを望む。それだけで、人間とは何か、自由とは何か、生きて死ぬ意味とは何かなど、次々とSFを超えた哲学の刃が読者に突きつけられる。この200年という歳月に、丁度アメリカ合衆国という国家の歴史が重なっているということはいうまでもない。とにかく奥が深く、問いかけは作者からの挑戦となって、読後にいつまでも残る。これはもはや文学だ。 ちなみに、日本ではこの手のロボット物は描かれまいと思う。鉄腕アトムとドラえもんが、すでに日本人のロボット観を塗り替えてしまった。ある意味、この無節操なまでの共存はすごい。ドラえもんは、人を傷つけることができるのだから!(笑)。まあ、そんな友人を許容してしまうのが日本人なのかもしれない。 |
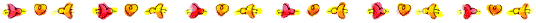
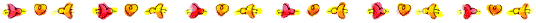
|
『エンダーズ・シャドウ』 タイトル訳があかん(笑)。「エンダーの影」と言っても、エンダーが黒い影を世界に投げかけるわけではない。彼に付かず離れずの副官の物語である。 前作、というか並行作とでも言うべきか、『エンダーのゲーム』では、エンダーは唯一無二の孤独の存在だった。だが、今回はビーンという主人公を得て、エンダーは常に相対的な位置に置かれる。やはり超人なのだが、内面が描かれないぶん前作のような神秘体験もなく、あくまで生身の人間として世界に放り出される。その辺の相対化が徹底化されていて、文字通り影のような作品に仕上がっている(笑)。 ファンとしてはどう反応すべきだろうか。「エンダー」を完成した映画フィルムとみるならば、本作はさながら台本を読むが如しである。物語の都合上、最後の最後に来るオチが早々に開示されてしまっているところが痛い。極端な話、エンダーマニアのための本になってしまってる感も否めないのだ。……といいつつ、単体でも楽しめそうな気もする。妙に複雑である。 見所は、主人公・ビーンの徹底的な脇役ぶり(笑)。とにかく凄い。野心に満ち満ちている癖に徹底的に脇役なのである。 <追記>一夜明けて、また新しいことを考えてしまったので記す。いずれにせよ、一晩で読破しただけでは真に理解したとは言えぬほど、この小説は消化作業に時間を費やす必要がある。それだけに、名作と言える。 やはり、『エンダーのゲーム』ならびに『無伴奏ソナタ』収録の「エンダーのゲーム」(短編)より先に本作を読んではいけない。この話のオチは、前2作にとって命である。繰り返す。未読の読者には、まず最初に前2作を読んでおくことを強烈にお薦めする。 一夜明けた感想はというと、主人公ビーンは強烈にタフだという印象しか残っていない、ということである。脇役の強みとでもいうのだろうか。あの強烈なオチ、大人たちの悪辣すぎる陰謀を知り、結局それに荷担しながらも平然としている。あのエンダーですら、事実を知った途端に途方にくれるというのに。そう、ビーンの第二の特徴は、放っておくと(無論、ひたすら隠しに隠そうが)何でも最後まで知ってしまう、という恐るべき帰納的推理能力の持ち主であるということなのだ。とても、たった7歳の子供の所業とは思われない。 前作は、ピーターとヴァレンタイン、そしてエンダーの「恐るべき子供」の三位一体の物語だった。ピーターは父であり、暴君であり、そしていかにエンダーが逆らおうとも勝利する。さながら巨大企業の社長の家族の葛藤劇でも見ているような雰囲気ではある。とにかく、この小説の中で、世界には語るべき知恵の持ち主はたった3人しかいないのだ。そこに、新たにビーンが加わった。ピーターはいかにするか? 恐らく、彼はビーンが無力なうちに排除するだろう。この話はエンダーの物語として完結はしているものの、ビーンの話としては全然解決していない。何よりもアシルという、ビーンにとってピーターのような存在が生き残っている。ピーターなら彼を利用するだろう。だが、ピーターも強烈にタフなのである。いずれは、ピーターを背後から討つ。そんな物語の展開を予感させられている。 あとがきの、煩悶するような久美さんの反応も笑える。特に、「カードは女性が描けない」というくだりは爆笑物である。まったくその通りだと思う。本作でもしかり。というより、性別の臭いのする、動物としての人類は一切出てこないような気がする。肉体上の問題を口にしつつ、彼にかかれば、いずれもっと本源的な論理に変質してしまう。そんな気がする。 |