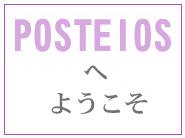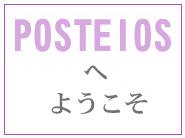浄土真宗の宗祖親鸞聖人は、1173年にご誕生、波乱に満ちたご生涯にあって念仏の灯をともし続けられ、90歳でお浄土に還帰されました。
そのご遺骨は京都大谷に納められ、聖人の遺徳を偲ぶ人々の聞法の集いがもたれるようになります。
第3代宗主覚如上人は、聖人の33回忌を勤めるにあたり『報恩講式』をあらわされ、その集いは「報恩講」と名付けられました。
(築地別院ホームページより)
報恩講の、特に日中・逮夜などの六時の法要についてお話します。
報恩講六時法要について関西地区では、「逮夜(たいや)参り」という法要式があります。
【「逮夜」の(逮)は明日に逮(およ)ぶの意で、逮夜とは翌日の火葬につながる夜、つまり火葬の前夜をいう。転じて、年忌(ねんき)や月忌などの忌日の前夜をさすようになった】(『岩波仏教辞典』)とあります。
関西地区で営まれる逮夜参りとは、月忌の前日に法事を営むことを言います。
総じて逮夜法要とは、午後に営む法要のことをいいます。
親鸞聖人の毎月の命日や、歴代宗主の祥月命日の勤行は、命日の前日午後に勤まる逮夜法要と、ご命日の午前中に勤まる日中法要でひと組になっています。
数日間勤まる報恩講ですと、午後の法要を逮夜法要と言い、最後に勤まる満日中前日の午後の法要を大逮夜といっています。
「明日はいよいよ」と心を引き締めて勤行にのぞみます。キリスト教のクリスマスイブと同じ趣でしょう。
報恩講では、朝のお勤めを晨朝(じんちょう)勤行といい、午前中の法要を日中(にっちゅう)、午後の法要を逮夜(たいや)、夜の法要を初夜(しょや)といっています。
この晨朝・日中・日没・初夜と言う言葉は、昼夜六時に基づくものです。
六時とは晨朝・日中・日没・初夜・中夜(ちゅうや)・後夜(ごや)と24時間を6つに分けた時刻表記法です。
現在では1日を24時間に分けて時間を表記していますが、江戸時代の時刻法は、「九つ・八つ」と言う十二分法です。
「明け六つ」「暮れ六つ」は、午前6時、午後6時ころです。これは十二は十二支に基づいています。
昼夜六時を24時間に配分すると、晨朝が午前8時、日中が午後0時、日没が午後4時、初夜が午後8時、中夜が午前0時、後夜が午前4時の時刻となります。
この昼夜六時の考え方は、「阿弥陀経」にも「昼夜六時而雨曼荼羅華」とあるように、古代インドの時間の単位です。最も短い時間の単位が刹那(せつな)です。これは七十五分の一秒と記憶しています。百二十刹那が一恒刹那(だんせつな)、六十恒刹那が一臘薄縛(ろうばく)、三十臘薄縛が一須臾(しゅゆ)、五須臾が一時、六時が一昼夜という具合です。
この六時を勤行修行の時として取り上げたのは、最も有名なのは中国の善導大師で、往生礼讃が晨朝偈・日中偈・初夜偈・中夜偈・後夜偈と、その時刻に応じて阿弥陀如来を讃嘆する偈をつくりお勤めしたようです。
「往生礼讃」は、巻頭に「勧一切衆生願生西方極楽世界阿弥陀仏国六時礼讃偈」と述べられ「六時礼讃」と言い、経論や大切なご文を六時に配して、昼夜六時に阿弥陀仏を礼拝し讃嘆する僧侶の日常勤行の定めたものです。
この六時の行法は、中国では弥天の道安(314〜385 中国,前秦の僧)が創始者だと言われ、「往生論註」に「菩薩の法は、つねに昼三時・夜三時をもつて十方一切諸仏を礼す」と示されているように曇鸞大師や道綽禅師、また道安を師と仰いだ慧遠法師も実践されていたと伝えられています。
ちなみに六時に「往生礼讃偈」を勤めていたものを蓮如上人(第8代宗主)が、吉崎時代(1471年7月建立)正信偈を朝夕の勤行とし、文明5年(1473)3月、三帖和讃に正信偈を加えて4帖とし開版。これが本宗における聖典開版の初めであり、今日の正信偈読誦の基礎となったものです。
また現在の正信偈は、昭和6年11月1日、勝如上人伝灯奉告法要を機会に、現在の真、行、草の3譜に改定し、念仏和讃は、往生礼讃の中夜偈の譜から編曲されたと言われます。
蓮如上人が、往生礼讃から正信念仏偈にお勤めを変えるとき、六時礼讃(往生礼讃の呼称)に習い、和讃を六種引かれたことも伝統の味わいがあります。
また築地別院報恩講や本願寺御正忌のお晨朝には、この六時の礼讃が順次お勤まりになります。
話がだいぶ流れましたが、最後に築地別院と本山(11月11日〜16日)報恩講期間における六時に関る法要内容を資料として添えておきす。
|
|
|
|
|
|
|