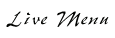MR.BIG
25th Anniversary Japan Tour 2014

|
Eric Martin - lead vocals, guitar
Paul Gilbert - guitar, vocals
Billy Sheehan - bass, vocals
Pat Torpey - drums, tambourine, percussion, vocals
Matt Starr - drums, vocals
|
2011年3月11日。 日本人には忘れられない日。忘れてはならない日。 地震が、津波が、放射能が日本を襲い東北を壊した。 3年半が過ぎた今でもその傷から、癒やされていない。 震災直後、当然の事ながらエンターティメントの世界は自粛ムードとなり、外国のアーティストにいたっては放射能汚染を恐れ、軒並みキャンセルとなった。そんな中、来日公演を行った数少ないアーティストの一つがMR.BIGであったのだ。 彼らが岩手(盛岡)、秋田、そして会館が壊れた事により中止になってしまったが仙台と東北を周ったのは日本のファンにとって、この上もない喜びとなった。 また「The World On the Way」というチャリティソングを製作、ライヴでも披露して当時、マスコミでも話題になったのは記憶にあたらしい事である。 東北を周る事に関して非難もあったようだが、最近、ビリー・シーンが雑誌に 「自分たちがライヴをやることで東北の経済復興に役立つのは微々たるものだが、それでもライブをやることで帰りに食事しようとか、飲もうとかで地元にお金が落ち経済が少しでも回るなら意味のある事だった」 と語っていたのを見て、とても感心したのだった。 あれから3年。バンド内でも色々な事があったようだ。 かねてからのポールの難聴の症状は悪化し、前作の長期間に渡るツアーはバンド内の空気を再び、不穏なものにした。それにより各個人のソロ活動や、ビリー・シーンにおいては「The Winery Dogs」の活動に重きを置くようになった。そんな硬直した状況の中で、動きがあったのは昨年の年末である。 ニューアルバム製作の為に、再び集結したメンバー達。ポールの難聴ゆえ、一時はアコースティックアルバムとツアーを考えたようだが、WHD Entertainment(現WOWOW Entertainment)のA&R 深民淳氏の説得もありいつも通りのエレクトリック・ロックアルバムとなった。しかし、好事魔多し。 ドラムのパット・トーピーがパーキンソン病を発症し、病状が芳しくない事が判明したのだった。 それにより、楽曲制作も方向転換を余儀なくされ(ドラムはパット指揮によるプログラミング)その件はずっと秘匿された。 やがて、ニューアルバム発売の予告と、日本公演の発表が為されたのが数ヶ月前。その広告には『バンド史上最も重要なツアーが、今始まろうとしている』と書かれていた。 これを見て「次のツアーで、やはり解散するのか」と思ったファンは多かったに違いない。 だが、MR.BIGから発表されたのはパット・トーピーがパーキンソン病を発症し、ドラムを以前のように叩けなくなった事、ツアーには代役を立て、パットもツアーには帯同する。というものだった。 当然ながら、MR.BIGファンを中心に洋楽ファンは茫然自失、大きなショックに襲われた。 ある意味、それは解散よりも切ない話であった。 9月24日、ニューアルバム「...The Stories We Could Tell」発売。 1ヶ月ほど後の11月、バンドはライヴの為に再び、日本の土を踏んだ。 結成25周年とも謳われた今回のツアー。 自分のようにデビュー時から追っかけてきたファンから、友達に連れて来られてメンバーの顔と名前が一致しないファン予備軍のような若い娘(私も実際に耳にした)まで会場には年齢も、性別もバラバラの多彩な人々が集った。 それを証明するかのように、入り口前のフロアには列が何重にも連なり、入場するまでにも一苦労であった。会場内のフロアにいたっても人が溢れ、グッズ列が2階、3階と続く様はかってないものであった。 開演時間まで5分を切ってグッズ購入を諦めた私は、ようやく会場に入っていった。 座席の階段を降りていくと暗がりの中にそびえるステージの全景が見えてきた。 本日の席は9列目、中央ブロックの端であった。前回、4列目から比べると後ろに下がってしまったが中央寄りゆえ、ステージ全景を見渡すには快適そうだった。 開演時間になると場内アナウンスが客に着席を促し、いよいよライヴが始まるのを肌で感じた。 オープニングSEとなったブライアン・アダムスの「Summer Of '69」に合わせた手拍子が鳴り響く場内が、暗転。 歓声に包まれながら、ステージ後方に据え付けられた3枚の大型LEDパネルにメンバーをモチーフとしたアメコミ調のショートアニメーションが映し出された。(下記参照) アニメが終わりを告げると、大仰なオーケストレーションのメロディと共にメンバーが姿を表した。 膨れ上がる歓声。ギターアーミングの轟音が突き刺さった。 「Daddy, Brother, Lover, Little Boy」は、やはりMR.BIGの代表曲の一つであると同時に 「Lean Into It」のツアー以来、ライヴのオープニングを告げる曲として相応しい。 サビの判りやすい歌詞に、声も枯れんばかりに観客みな唄いまくる。 もちろん、自分もそのうちの一人であった。 中間部のソロ − ギターの速弾きからのポールとビリーのマキタ製(愛知県安城市本社)ドリルを使った”エレクトリック・ドリルソロ”で最高潮を迎える。大型LEDパネルには例のポールのヘタウマイラストが踊っていた。 2曲目にはいきなり新曲「Gotta Love the Ride」。 「...The Stories We Could Tell」のアルバムトップを飾る曲だ。MR.BIGのライヴは、直近のニューアルバムの1曲目がライブ1曲目を担うというのが暗黙の了解になっていたが(以前、CBCラジオ「トップリクエスト」にエリック・マーティンらが来た時、私もハガキでその件について言及した事がある−なんてのも懐かしい思い出だ。)、今回は「Daddy, Brother, Lover, Little Boy」に譲ってしまったが、その約束事は2曲目において守られていたというのもニヤリとさせられた。 3曲目は前アルバムのリーダートラックであった「American Beauty」4曲目「Undertow」と2011年のツアーを思い起こさせる曲選択であった。 「Undertow」と終了と同時に始まる、ポールとビリーの掛け合いのセッション。 お互いのフレーズを注意深く聴きこんで、それぞれがアドリブで応酬する。センスが問われる瞬間でもある。 ポール十八番の速弾きを封印したブルーズ調のフレーズに倣って、ビリーの速弾きベースが火を噴くとエリックが叫んだ。 「パット・トーピー!」 遂にタンバリンを持ったパットが登場したのだった。沸き起こる盛大な拍手。私はもう、ここで泣きそうになってしまった。 始まった曲は ブルーズ・セッションそのままに「Alive and Kickin'」である。 バンド結成当初から標榜したブルーズ・ロックをMR.BIG流に解釈した名曲である。 ドラムセットの右横にセットされたパーカッションセットに立ったパットは その後も其処に留まってタンバリンを振り続けた。 新曲「I Forget to Breathe」、お馴染み「Take Cover」そして「Green-Tinted Sixties Mind」。 「あの特徴あるドラムビートで曲を始めよう!」 とエリックの掛け声で始まった「Take Cover」を(パットの代役である)マット・スターがドラムを叩き始めた。 その横でパットがタンバリンを懸命に振る姿に、私は改めてドラムがパットでないことに切なさを覚えた。 サビのコーラスで客を煽るエリック。 「Green-Tinted Sixties Mind」...ポールのタッピングで始まるこの曲も、MR.BIGのライヴにはなくてはならない曲だ。 しかし、随分、久しぶりに聞いた感じがするのはポールの単独来日公演も最近では遠ざかっている所為だろうか。 だが、いつ聞いてもこの曲に初めて触れた−アルバムリリース時の新入社員研修での東京生活の風景を思い出す。見事に自らの思い出と結びついている曲でもある。 短めのエリックのMCを挟んで、タンバリンで参加した「Out of the Underground」のアウトロはそのままポールのギター・ソロコーナーへと繋がった。ここでのポールはペンタトニック・スケールを使ったブルースロック的なフレーズを中心としたソロを組み立て、昔のようなストリング・スキッピングを多用したテクニカルなものは皆無であった。 最近のポール・ギルバートの音楽的志向がそうさせたと思うが、途中に「Merciless」のイントロや「Take A Walk」のリフを差し込んでくるあたりは昔からのファンを狂喜させるものであった。 ニューアルバムから「The Monster in Me」の後、エリックの叫び 「Rock & Roll Over !」が響き渡った。 デビュー・アルバムに深い思い入れがある自分にとっては、この曲の登場は待ってましたの感じである。 「We rock & roll over , over & then !!」 当然、サビの部分では一緒に唄い弾(はじ)ける。ポールの複雑なフィンガリングのアウトロソロも一瞬も見落としてなるものかと 凝視した。最高の時間であった。 新曲「As Far as I Can See 」が終わると、ポールはアイバニーズのセミハコタイプのギターに持ち替えた。 エリックはエレアコを、パットはタンバリンを持ちステージ前方に集合。大きな拍手が沸き起こる。 ポールが音を確かめるように爪弾き始めるとそれは聞き慣れたリフへと変化した。 Rolling Stonesの「Jumpin' Jack Flash」だ。おそらくこの曲の披露は名古屋だけだったと思うが、1コーラスだけでもこれは嬉しいサプライズであった。 このままアコース・ティックセットはCat Stevensのカバー「Wild World」へと繋がった。 「To Be With You」のヒット再び−とばかり、当時、レコード会社からの要請でアルバム収録した「Wild World」であったが 今も、こうして観客を巻き込んで唄う事が出来る曲になるとは思いもよらない誤算であったかもしれない。 ポールのフラメンコギター的な早いパッセージをバックに、パットがこの日、初めてマイクの前に立った。 「来てくれてありがとう。皆に会えてうれしい。次の『East/West』 はニューアルバムから。ファンに捧げた曲だ。特に日本の皆に向けて。カンパイ!」 −と、会場に集ったファンに感謝を伝え、曲を始めた。パットが詞を書き、ファンとの絆を歌ったというミディアムテンポのロッカバラードなだけにその感動はより大きくなっていった。 そして、遂にパットがドラムセットに座る時間がやってきた! 盛大な拍手が一斉にパットに贈られていく。 それを確認した後、ポールがクリーントーンで繊細にイントロを爪弾き始めた。 「Just Take My Heart」である。優しさに力強さが備わったこの曲に、パットのドラム参加は似合いすぎている。 ある意味、反則?か(苦笑)。しかし、感動的に見ている私達に対し当のパットのドラムは明らかに昔のようなプレイが 出来ない事を表していた。時折、苦痛に歪む顔を見てこの過酷な現実に慄然とするばかりであった。 次のニューアルバムからの曲「Fragile」でも、パットはドラムセットに留まっていた。 しかし、この曲は「Just Take My Heart」よりはハードな曲であるのに、先程よりリズムはしっかりしていたように感じたのは自分だけではなかったと思う。パットのこれからの未来に、微かな希望が見て取れたような気がした。 「パット・トーピー!」 エリックが客を煽る。もちろん大歓声だ。パットは照れながら、ドラムセットを離れ、マット・スターと交代した。 その間、エリックとビリーがマイクを取った。 「ツアーに出て5週間くらいになるけど、どこを周ってきたんだっけ?」のエリックの問に対し「あちこちに行ったな。イギリスだろ、フランスだろ、オランダだろ、」とビリーがあの特徴的なディープボイスで応えるとエリックは「それってこの辺りかい?」(と自分の下半身を指差す。)と返した。もう完全に漫才の域である。 ビリーはエリックの応えは華麗にスルーしながら「スペイン、イタリア、ロシア、フィリピン、韓国・・・」。 するとエリックはそれを待っていたかのように「そして 日本、ナゴヤ〜 ジャパン!」と叫んだ。 この煽りが次の曲のスタートを促した。「Around the World」である。 ファストな曲が勢いよく始まった。 サビの歌詞「Round the world we go」で大合唱。 そして、ソロではこれでもかとばかり、ビリーが一心不乱にベースを弾きまくっているのが視界に入ってきた。ベース&ギターの掛け合い、ユニゾンプレイが気持ちを粟立たせた。なんという熱いプレイだ。 ポールのテクニカルなアウトロから、ビリーの高速ピッキングへ移っていくともはやビリー・シーンの世界へと誘われているのを気づいた。 スラッピング、高速タッピング、ピッキングハーモニクス....あの独特な歪んだ音でもはや、お馴染みとなった超絶技巧をこれでもかと繰り出していく。そんな夢幻な時間が5分以上続いただろうか。 もうそろそろと思った時、”あの曲”のイントロに続くであろうというタッピングのフレーズが響き渡った。 しかも、その始まりを最前列で踊りまくっている若い男性二人にベース・フレットを触らせスタートとするという粋なファンサービスを行ったのだ。当然のことながら、一生に二度と無い機会を得たその二人は狂喜乱舞。この時ほど羨ましいと思った事はなかった。 デビューアルバム「MR.BIG」の1曲目。 25年前「Addicted to That Rush」に出会わなかったら、きっとMR.BIGのファンにはならなかった事だろう。 あの曲のインパクトはそれぐらい大きなものだった。(そう思っているファンは絶対、多くいる筈だ。) そんな感傷に浸りながら見ていると、マットのドラムの連打をバックにして、ビリーのフレーズにポールの速弾きが切り込んでくる。 その後は、恒例のビリーとポールの掛け合いフレーズが続き、やがてユニゾン調に重なるとタッピングフレーズへと展開する。カントリーにアイデアを受けたという一風変わったリフが始まれば、アドレナリンが沸騰するのを感じる。 これが聞きたかったんだと改めて思うのだった。 曲中間部でブレイクすると、ここでエリックによる煽りが始まった。 「Are you addicted to that rush ?」の問い掛けに、 エリックが「オンナノコ!」と叫ぶと「Yeah!」と応える女性陣。 「オトコ」であれば、同様に野太い声で「Yeah !」で返す我々である。 最後は「ミナサン!」で会場中が大熱狂して曲に戻るとベースとギターの丁々発止に、エリックの熱唱が乗っかり、大団円を迎えた。 拍手の中、ステージを去っていくメンバー。 拍手はやがてアンコールを求める手拍子に変わっていった。 暗転したステージに「MR.BIG」の文字が輝く中、その手拍子に押されメンバー達も程なくしてステージに復帰した。 エリックの名古屋のファンへの謝辞に続き、メンバー紹介がマットからポール、パット、ビリーと進んだが、やはりパットへの拍手が一番大きかった。それは手拍子となり大きなうねりをもたらした。 アンコール1曲目は、ヒット曲「To Be With You」である。 冒頭から、場内は大合唱である。しかも、3面のLEDパネルスクリーンには、懐かしきこの曲のPVが流されていた。20数年前の若い彼らと、目の前の今の彼ら。時の流れを感じながら感傷に浸るのも無理もないことである。というか、この演出は反則だ(苦笑) 2曲目はアコースティックな響きから一転させるファストナンバー「Colorado Bulldog」。 イントロの高速ユニゾンフレーズを、ポールやビリーでさえも「せえーの」と一心に集中しないと、弾く事が出来ない難曲であったというレコーディング時のエピソードも今では懐かしくさえ思える。 時折、エリックの犬の遠吠えを真似た叫び声を上げるのもこの曲のポイントである。 曲が終わり、メンバーがステージで行き来をする。ポールはドラムセットへ、ビリーはポールからギターを受取り エリックはベースのストラップを肩に掛ける。マットもポールのギター(白のPGMだったか?)を持っていた。 (この時、エリックは受け取ったベースを即席オークションをして、客に手渡そうとする暴挙にも出るのだが 笑) つまり、MR.BIG恒例の楽器交換タイムである。 やがて、ステージの袖からパットが黒の革ジャンにサングラスという出で立ちで出てきた。拍手に包まれるパット。 そのパットはステージセンターに立ち、マイクを持った。 「ポール・ギルバート!」 の掛け声で、ポールがリズムを刻み始めた。始まった曲は聞き慣れたJudas Priestの「Living After Midnight」であった。 革ジャンにサングラスという、ロブ・ハルフォードに成りきったパットが歌いながら、客を煽っていく。 パットがステージの端から端まで小走りする様子に、だれが不治の病に侵されていると思うのだろう? ビリーのギターも当然ながら巧く、ポールのドラムもタイトで巧い。そんな中で、気持良く歌い上げるパットの声で客席は最高に盛り上がったのだった。 「Living After Midnight」が終わると、それぞれが元のポジションに戻った。だが、パットだけは違っていた。 「パット・トーピー Lead Vocals !」 パットはそのまま残り、なんとエリックとのツイン・ボーカル体制になったのだ。 曲はニューアルバムから「The Light Of Day」である。 元々、ドラムソロコーナーでBeatlesを歌いながらプレイしたこともあるパットだから、声も折り紙つきだ。 この豪華な組み合わせに私は、始まる前から心躍った。 この勢いのあるロックンロールナンバーはライヴの最終盤を大きく盛り上げるだけでなく、マット・スター今回唯一のドラムソロを含み、マットの存在証明を果たす事に寄与したのだった。 エリックは興奮が収まらなかったのか、曲が終わっても客の手拍子に煽られて「The Light Of Day」のサビの歌詞を歌い続けている。よっぽど喉の調子が良いのだろう。ノッているのが判ってこちらも嬉しくなってくる。 その間に、パットがドラムセットに座りスタンバイをする。 するとエリックがこう言ったのだった。 「さあ、上に登ろう!ポールも、ビリーも早く!」 その言葉に倣い、ポールとビリーがステージセットの最上段へ、左右にセットされた階段を昇り、ドラムセットに位置するパットの後ろに3人が並んだ。 「なんて、粋な事をするんだエリックは。」と思わずにはいられなかった。 そんなエリックが「僕ら全員がずっと君に付いている − We are behind You all the way」と呟いたのも もう泣けといわんばかりであった。 エリックが告げた最後の曲は、やはり「M・R・B・I・G」。バンド名に由来するFreeのカバーソングであった。 パットのドラムで曲が始まるというのも何かと意味があるのかもしれない。右手に不安を感じるものの力強くリズムを刻むパットに私は手拍子で応えた。 そのパットをポールとビリーが熱い演奏で支え、エリックはソウルフルに熱唱した。 正にMR.BIGのライヴの終演を飾るに相応しい曲であった。 曲が終わり、大歓声の中、パット、マットがステージに降りてエリック、ビリー、ポールと肩を組み一礼。 一段と歓声が大きくなった。 そして、ビリー側にメンバーが横並びに勢揃いする中、ビリーがバンドを代表し 「ナゴヤ アリガトウ !」 と今夜のライヴのお礼と共に、この25年間の絶え間ない応援に感謝を伝えた。 手を上げ、ステージを後にするメンバーに私達は、いつまでも拍手で見送るのだった。 パットのパーキンソン病公表後初の日本ツアーは最後の福岡公演まで無事に取り行われた。 だが、パットが実際に叩けた曲数には日々、変動がありパーキンソン病がどれだけ負担を強いているのか詳らかになるもので、切なさも感じる事になってしまった。 上記のように、明らかに苦痛に歪む顔や動きの悪い腕を見るにつけ、切なさよりも哀しさが溢れた。しかし、それを悟られないように精一杯、笑顔でパフォーマンスを通したパットのプロとしての矜持には ただただ脱帽するばかりであった。 最善の治療がまだ見つかっていないパーキンソン病は、今後悪くなる事はあっても、劇的に症状が改善することはないだろう。特にドラムという全身を使う楽器では、致命的だと言わざる負えないのは悔しいが現実である。だからこそ、この一瞬、一瞬を目に焼き付けようと思ったしパットもそれを承知で精一杯、パフォーマンスを行ったんだろうと思う。 ビリー・シーンは雑誌で「MR.BIGは解散しない。パットはずっとメンバーだ」と語ったが、今はそれを素直に信じたい。ツアーに出られなくとも、MR.BIGのジャケットや、ライナーノーツにパットがクレジットされるように(曲作りにも参加できるように)願うばかりである。 今回、終演を知らせるSEとしてQueenの「The Show Must Go On」が流れた。 「The Show Must Go On」=「ショーは続けなければならない」「後戻りはできない」という意味である。この曲を選ぶあたり、バンドの、パットの前向きな気持ちが感じられ嬉しくなったのだった。 パット・トーピーに幸あれ。 |

「Daddy, Brother, Lover, Little Boy」 お馴染み ”マキタ” ドリル ソロ



「Alive and Kickin'」前の 長めなGuitar & Bass Duel

これぞ ビリー&ポールの真骨頂

遂にパット・トーピー登場!




「Addicted To That Rush」の光速ツインタッピング。いつ見ても最高だ!



懐かしのPVをバックに 「To Be With You」は反則だった(笑)

今回も実現した−恒例の楽器交換コーナー。

ロブ・ハルフォードばりに熱唱するパット。

Living after midnight, rockin' to the dawn 〜♪♪

「The Light Of Day」でのエリック&パットのツインボーカルはMR.BIG史上初なのではないか。

『上に登ろう!ポールも、ビリーも早く!』とエリックに促されてパットの後ろに並ぶ3人。

『僕ら全員がずっと君に付いている』と呟いたエリック。泣きそうになった。


デビュー25周年の感謝を述べるビリー・シーン

感動的なスピーチであった。
| SET LIST | |
| ◆ | S.E. Summer Of '69 (Bryan Adams) |
| ◆ | Opening Animation
|
| 1 | Daddy, Brother, Lover, Little Boy (The Electric Drill Song) |
| 2 | Gotta Love the Ride |
| MC | |
| 3 | American Beauty |
| 4 | Undertow |
| 5 | Guitar & Bass Duel |
| 6 | Alive and Kickin' |
| MC | |
| 7 | I Forget to Breathe |
| 8 | Take Cover |
| 9 | Green-Tinted Sixties Mind |
| MC | |
| 10 | Out of the Underground |
| 11 | Paul Gilbert Solo (include Merciless 〜 Take A Walk) |
| 12 | The Monster in Me |
| 13 | Rock & Roll Over |
| MC | |
| 14 | As Far as I Can See |
| 15 | Jumpin' Jack Flash (The Rolling Stones) 〜 Wild World (Cat Stevens) |
| MC | |
| 16 | East/West |
| 17 | Just Take My Heart (Drum : Pat Torpey) |
| MC | |
| 18 | Fragile (Drum : Pat Torpey) |
| MC | |
| 19 | Around the World |
| 20 | Billy Sheehan Solo |
| 21 | Addicted To That Rush |
| ・・・Encore・・・ | |
| MC | |
| 22 | To Be With You |
| 23 | Colorado Bulldog |
| MC | |
| 24 | Living After Midnight (Judas Priest) (Part Change) |
| MC | |
| 25 | The Light Of Day |
| MC | |
| 26 | Mr. Big (Free) (Drum : Pat Torpey) |
| MC | |
| ◆ | Closing S.E. The Show Must Go On (Queen) |
|
24曲目のパートチェンジはボーカル=パット、リードギター=ビリー、リズムギター=マット、ベース=エリック、ドラム=ポールという布陣で行われた。 パットはサングラスに黒の革ジャンというロブ・ハルフォードを彷彿とさせる姿だった。 グリーン色の曲は、パットがタンバリン、パーカッションあるいはボーカルで参加した曲である。 |

MR.BIG Facebook より |