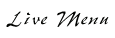PAUL GILBERT
SPACE SHIP ONE Tour
|
|
|
�@�u���܂����v
�@�J�ꎞ�Ԃ�1���Ԃ��ԈႦ�Ă����������̉߂��ɋC�Â����̂� �N���u�N�A�g���ւÂ��K�i������Ă��鎞�������B �@���i�ł������Ȃ�A���̊K�i�ɂ͊J���҂l�X�̗i���� �K���܂ŘA�Ȃ��Ă�����̂��������Ɍ����đS���l�����Ȃ��B �@����ɕǂɒ���Ă��锤�̐����ԍ��𑣂����莆����Ȃ��B �@�s���ɂȂ�A�K�i���삯�オ���Ă����ƁA�N�A�g���͊��ɊJ�ꂳ�� ������̌W���͎莝���Ԃ����ɕ��Ă����B �@����ł悤�₭��݂Ȏ��ɂ��S�Ă̏��c���o�����̂������B �@�u�J�ꎞ�ԁA�ԈႦ�Ă����̂���v(��j �@20�N�ȏ�̃��C�����ł��A�S�����蓾�Ȃ����̏��S�ғI���ԁB �@���̎��̋C������[�I�ɕ\������ΐ���䩑R�����ƌ������Ƃ��낾�����낤�B �J�����`�F�b�N�̌�A�����̈Èł������ɓ����Ă����ƁA������ ���Ɍ����Ɏx�z����A���C���̊J�n��k���Ȃ���҂��Ă���F�l���m�� �J�b�v���̘a�₩�ȕ��i�����������œW�J����Ă����B �@�����������͓��j���ł���B��ЋA��Œx��Ă���Ă���҂Ȃ� �قƂ�ǂ��炸�A�x�������z�Ȃǎ������炢�������Ȃ��悤�� �v���A����Ƀt�@�����i�̂悤�Ȏ��s�I�ȋC�����ɂ����Ȃ��Ă��܂����B �@����ȏ�����A��������_���Ă������ƈ֎q���L��قڐ��ʂ��� �ϐ�i�H�j�o���鏈�Ȃǖ����Ȃ��ē��R�ł������B �@���������z���炩�����ꂽ������ڂ̑O�ɂ����Ȃ�A�����C������ ���邵���Ȃ��B����͂��Ȃ킿�t���A�ɏo�Č��邵���Ȃ��Ƃ������ł���B �@�����̋͂�3�i���炢�̊K�i���~�葽���A�Ⴍ�Ȃ��������t���A�ƂȂ��Ă���B �@���������̃N�A�g���̃��C���q�Ȃ��B �@�X�e�[�W�O�ɂ͊��ɔM���I�ȃt�@�����ꕔ�̌����Ȃ����сA���������͂܂�ŕʐ��E�B �@�����t���A�Ƃ͌����A���ɂ���ȃt�@���ɍ������Č���̗́A�C�͂��Ȃ����� �t���A�̌��̕��i����ł��X�e�[�W����5�A6m���炢��������Ă��Ȃ����j �Ō��邱�Ƃɂ����B �@�������A�X�e�[�W�������ĉE���i��������j�A�|�[�����w�����łł���B �@�J���܂ł��ƁA�ق��10�����Ɣ��������ł����͂����̂悤�� �����當�ɖ{�����o�����B�{�̃^�C�g���͉��c �p�N���u��������v�B �@80�N����e�[�}�Ƃ����t�O���t�B�e�B�B���܂��Ɏ�l���͖��É��l�Ƃ��� �����Ƌ��ʓ_�������ϋ����[���{�Ȃ̂����A����͓ǂ�ł��Ă� �قƂ�Ǔ��e�����ɓ����Ă��Ȃ������B �@�����܂��������ɂ����ĐÂ��ɖ{���A������X�^���f�B���O�œǂ�ł��鎖 ���́A�[���猩����ٗl�Ȃ̂����i�j���̎��̖{�ɑ���W���͂� SE(�ȁj�������ɑł��ӂ��Ă��ꂽ�|�S������Scorpions�̃A���o���uBLACK OUT�v����̑I�Ȃ̓��^������������30��ȏ�A��l�ȃt�@���̐S�ɉ�_����ɂ͏\���Ȃ��̂ł������̂��B �@���C���͒荏�ʂ�6�F00�Ɏn�܂����B �@�q�d�������A�X�s�[�J�[����͑剹�ʂ��uSummerTime Blues�v�B �@�I���W�i����The Who����HR�F����������Rush�ŁuSummerTime Blues�v�� �|�[���E�M���o�[�g�̃��C���̃C���g���ɂ͓I���I�Ȃƌ������B �@�ϋq�͂����́|������v�����X�ł������̓o��Ȃł��邾���Ȃ̂Ɂi���������� �o���h�����t���Ă���Ƃł����Ⴂ���Ă���̂��H�j�ٗl�ɐ���オ��B �@�Ȃ��ŏI�R�[���X�ɓ����������肾�낤���A�����o�[���Èł̒��A���ꂽ�B �@�����ɂ͂������|�[���̎p���������B �@��Ăɕ����オ��劽���B�����Ĉ�u�A���ꂪ�r���Ɠ����ɃX�l�A�E�h������ �A�ł���1�Ȗڂ��n�܂����B�uMasa Ito�v���B�������A����HM�]�_�ƁAHM�`���t�̈ɓ��������̎����S�����Ȃł���B2�N�O�̃C���X�g�A���C���ł�1�Ȗڂ͊m���ɂ��̋Ȃł��������c�A�[���C���ł����̋ȂŃX�^�[�g����Ƃ͋������B �@���̈ɓ�������������̔ԑg�̃e�[�}�\���O�Ƃ��Ă���炵�����A��x�ł������� �@���̓��l��ڂ̑O�ɂ��ĉ��t���Ă��鏈�����Ă݂������̂ł���B�Ȃ�Ȃ�X�e�[�W�ɐ�������������..�Ƃ����̂�������������Ȃ��B �@�����[����ϑz���c����A�ȍŌ���u�}�A�}�A�}�A�}�T�`�C�g�[�v�Ƌq�ɉS�킹�Đ���オ��͂����Ȃ�g�b�v�ɓ����Ă������B �@�ӊO�������I�Ȃ����ʓI�ɂ͑听���B���̗]�C���y���ނ��ƂȂ����h���[�̂悤�� 2�ȖڂɌq�������B �@�C���g���̃e�N�j�J���ȃV�[�P���X�t���[�Y�����̂��S�n�ǂ����������uSpace Ship One�v�̓j���[�A���o������̃^�C�g���g���b�N�B�i�R�b�g�����n�ŏo���Ă���J�X�^�����C�h�́j�����F�����̈ߑ��ɐg���|�[���ɂ͑S�����������Ȃł���B�܂��A�|�[������ɂ���A�C�o�j�[�Y�̃��B���e�[�W�M�^�[�A�t���C���O�u���f�����h���P�b�g���[���U�h�Ƃ́A�����牽�܂ŁwSPACE�i�F���j�x�������Ă���ł͂Ȃ����I �@�u�A���K�g�E�`�i�S���v�̃|�[���̊|�����Ŏn�܂���3�Ȗ��uSVT�v�͏��߂ĕ������������ΐ���オ��A���C���f�����邾�낤�Ǝv���Ă����Ȃ��B �@Ampeg�Ђ̃x�[�X�A���v�̂ЂƂł���SVT���ȂɎ��グ��|�[���Ȃ�ł͂̑I������������ꂽ���A�Ȃ͏��R����W���[�_�X�E�v���[�X�g���݂̃w�r�[���^���B �uSVT�v�u�w�C�@�w�C�@�w�C�v�ƃR�[���X�����ł͊ϋq�ƌ����ɃV���N������B �@4�Ȗ��uI Like Rock �v�͑O��̃c�A�[�ɑ����Ẳ��t�B���͂�C���ł͒�ԂƂȂ����������炠��B������ɂ���uI Like Rock �v�Ƃ����P���ȉ̎��͉�X�A���{�l�ɂ͎���₷���A�S���Ղ��B���̂�������l�����Ă̑I�ȂȂ̂�������Ȃ��B �@�uI Like Rock �v���I���A���x�~�B �N���[�����n���ꂽ�m�[�g�i�J���j���O�y�[�p�[�j�������A���悢��\�́h���{��ɂ��hMC�^�C�����B �@�u�o���h�̃����o�[���Љ�܂��v�i���F�Ȍ�A�|�[���Ɍh�ӂ�\���āA�����ĕ������E�����\�L�Ƃ��܂��B�j �@�ƃ|�[������o���A�x�[�X�����C�i�X�i�I�u�E�n���E�b�h�j�A�h�������W�F�t�i�{�E�_�[�X�j�̖��O���Ă��x�ɑ傫�Ȑ������q�Ȃ��瑡��ꂽ�B �@�u�`���[�j���O���Ȃ��Ƃ����܂���v �@�ƑO����4�Ȃ̔M���ʼn��̋������M�^�[�����Ă��鎞���|�[���͉��̂��������������I�ɓ������������b���y���݁A��������B��S���O�������Ȃ��B �`���[�j���O���I���A�Z���ȏЉ�̌�A�������t���n�܂����B �@�uPotato Head�v�B�|�[����������Produce�������{�̃o���h�uMR.ORANGE�v�̋Ȃł���B�����A�c�A�[���C���ł͏���I�̋Ȃł��낤�B �@�Ȃ��I���A�Ăуm�[�g��������MC���J�n�����B �@��┭�������ɉ���������������̂́A����ł��t���Ă��n�łȂ����{��͏\���A���h�Ȃ��̂ł������B �@���{��MC�ŏЉ�ꂽ�uI'm Not Afraid Of The Police�v�͂�����O��̃c�A�[�ɑ����ăZ�b�g���X�g����B�㔼�̒Z���������̃M�^�[�\���̓|�[���̎�ȂW�������悤�Ȃ��̂ł��������L�����ƌ�����̂��������悤�Ɏv�����B �@�u���̋Ȃ̓��[�T�[X�̋Ȃł��v �@�ƏЉ���ΐ���オ��Ȃ���ɂ͂����Ȃ��B �@�|�[���t�@���ɂƂ��āA"Racer X�h�͂��܂ł����ʂȑ��݂ł���B �@�uScarified�I�v �@�ƃ|�[�����Ȗ������Ԃ̂��������A�W�F�t�̋���ȃh���~���O���n�܂�A ���̂�����݂̒ቹ���𒆐S�Ƃ����X�P�[���e���P�����t���J��o������ �uYeah�v�Ɗϋq������𐺂Ō}�����B���t���I���A�X�g�����O�E�X�L�b�s���O�̉��V�ɖ��x�̎��Ȃ��爠�R�Ƃ�������B �@����ɂ��̋Ȃ̓M�^�[����łȂ��x�[�X�ƃh�����ɂ����x�ȋZ���v�������Փx�͍����B �@���Ƀh�����̃W�F�t�́A���R�[�f�B���O�ɂ��Q�������}���R�E�~�l�}�����c�A�[�ɂ͑ѓ��o���Ȃ��Ƃ������Ƃŋ}篁A�I�ꂽ��ށB������I�ꂽ���R�����́uScarified�v�ł̃h���~���O���|�[�����C�ɓ���������ƌ��������ɉ��t�͎��ɑ��̍������f���炵�����̂ł������B �@�r��鎖����8�Ȗ��uEvery Hot Girl Is A Rockstar�v�̓j���[�A���o������̋ȁB �@�|�[���͓��R�A�S���̂��Ă���ׁA�o�b�L���O�Ȃǂ͕��ʁA�i�M�^�[�\���ɔ�ׂāj���낻���ɂȂ肪�������A���̋Ȃ͒n���ł͂�����̂̌��\�A���G�Ȏ�������Ă���̂��悭�������B����ł��Ď��Ƀ����f�B�A�X�ȃ��C���B�|�[���̎��������Ȃ̒[�X�Ɋ���������Ȃł������B �@�Ăѓ��{��MC�^�C���B��͂���{����I�������̂��낤�A����͈ȑO����MC�̉������悤�ȋC������B �@�u���̋Ȃ�7645�ȏ�̉����ŏo���Ă��܂����A�����͂����ƒe���܂��v �@�Ƃ�����ȏЉ�Ŏn�܂���Racer X���uViking Kong�v�͎����ɂƂ��āi�������CD�ł͕����Ă��邪�j���C���ł͏��߂ĕ����Ȃ��B���Racer X�̗��������ɍs���Ă��Ȃ����ɂ͉����������C�����B �@�㔼�̃C���O���F�C���ۂ��S�̂悤�ȃ\���t���[�Y�₨���ӂ̃X�g�����O�E�X�L�b�s���O�A�܂��G�f�B�E���@���w�C�������n�̃^�b�s���O�E�n�[���j�N�X�ƃ|�[���̃��[�c�E�I�u�E�M�^�[������1�Ȃł������B �@����C���X�g��������Ȋ�Ŕ�I�������MC�B���{�l�A�[�e�B�X�g���݂Ƀg�[�N�̎��Ԃ������ăt�@���Ƃ��Ă͊y���������̏�Ȃ��B �@�u�V�����J�o�[�\���O�������ς����K���܂����v �ƌ����ďЉ�ꂽ�̂̓|�b�v�\���O�ƃ��b�N�\���O��2�ȁB���ꂪ�G�킾�����B �@�|�b�v�\���O�͌��킸�ƒm�ꂽBeatles�́A�Ƃ�����George Harrison�̑�\�Ȃ̈�A�uSomething�v�B �@�|�[����Beatles�̃R�s�[�o���h��Dream Theater�̃}�C�N�E�|�[�g�m�C��ƌ������X�e�[�W�Ŕ�I���Ă��邾���Ɏ��ɍI���B�I���W�i���𒉎��ɍČ����Ă���̂��D�������Ă��B����A���̊������ꂽ�ȂɃA�����W���{���Ƃ����̂͊��ɖ���������̂��낤�B �@���e�����|�b�v�\���O�̌�̓��b�N�\���O�uHeat In The Street�v�B �@PAT TRAVERS�̃J�o�[���B �@�Â�����̃t�@���Ȃ�m���Ă��邾�낤���|�[���̓t�F�[�o���b�g�E�M�^���X�g��PAT TRAVERS��������قlje�����Ă���Ƃ����b�ł���B���͂��̋Ȃ̃I���W�i�����c�O�Ȃ��畷�������͂Ȃ����A��قǂ̕�����������@���������e���l�q�Ƀ|�[���Ȃ�ł͂̃A�����W���{����Ă���悤�Ɋ������B �@�u�W�F�t����@���C���h�ȃS�����݂����Ƀh�������Ԃ��āI�v �@�ƃh�����̃W�F�t�ւ̉����������i�j����Ďn�܂����uJackhammer�v��CD�ŕ����������炩�Ȃ�C�ɓ����Ă����B���̋Ȃ̎���́i���������ɂ�����悤�Ɂj���炩�ɃW�F�t�E�{�E�_�[�Y�ł���B �@CD�ł̓}���R�E�~�l�}�����@���A�r���̕ϔ��q�I�ȃI�J�Y�̃t���[�Y���̑�Ȃ�W�����E�{�[�i����f�i�Ƃ������ɋ����[�����������̂����A����ɑ��A�W�F�t���{���]���n������������p���t���ȃh���~���O���\���Ɏ��̌܊����h�������̂������B �@�|�[�� �u�݂�Ȃ̓��͉��ŏo���Ă��܂����H�v �@�ϋq �u�g�}�g�`�v �@�|�[�� �u�݂�Ȃ̃n�[�g�͉��ŏo���Ă��܂����H�v �@�ϋq �u�C�`�S�`�v �@�|�[�� �u�l���v �@����Ȃ����Ŏn�܂����uBoku No Atama�v�Ƃ����Ȃ̓j���[�A���o�����^�Ȓ��A��A��𑈂��قǒ��ڂ��ꂽ�g���b�N�ł������B����̓^�C�g�����������悤�ɓ��{��̎����t�����Ȃł���������Ȃ̂��B �@���@�I�ɂ͂��ςȕ��������邪�A����ȏ�ɉ̎��̃��j�[�N���ɂ܂��͎���D���锤���B �@�l�̓��̓g�}�g�ŏo���Ă��� �@�l�̓��̓g�}�g�ŏo���Ă��� �@�ł��@�g�}�g�̕����i�X���D������ �@�l�̃n�[�g�̓C�`�S�ŏo���Ă��� �@�l�̃n�[�g�̓C�`�S�ŏo���Ă��� �@�ł��@�C�`�S�̕����i�V���D������ �@���Ȃ��̓��͉��ŏo���Ă��邩�H �@���Ȃ��̃n�[�g�͉��ŏo���Ă��邩�H �@�̎��̎��ʂ������Ă���Ɓu�Ȃ�̂�������H�v�ł��邪 ���ꂪ�|�[���̒e�������E�ȃ����f�B�ɂ̂�Ǝ��ɃC�C�̂��B �@���C���ł����̗ǂ��͎���ꂸ�A���{�ꎍ�ł���ɂ��ւ�炸�A�ϋq�͈ꏏ�ɉ̂��Ƃ�����菃���Ƀ|�[���̉S���y���ނƂ��������ł������̂���ۓI�������B �����E�ȉ��t�����]�A14�Ȗڂ��uTerrible Man�v�B������j���[�A���o������̋Ȃ��B �P���ȉ̎��̕��A�e�N�j�J���ȃM�^�[�t���[�Y�����Ɏc�����B �@�����u�w�r�[���^���E�X�^�C���v�Ɛ錾���Ďn�܂���Racer X���uTechnical Difficulties�v�͌l�I�ɂ͍���̃��C���ň�ԁA����オ�����Ȃł������ƌ����邾�낤�B �@�v��ʑI�Ȃł��������Ƃ��m�������A�P���Ɍ����ċȎ��̂��J�b�R�C�C�̂ł���B �@�����ӂ̃X�g�����O�E�X�L�b�s���O�Ƀ^�b�s���O��g�ݍ��킹�镡���Z�������Ɍ��܂��Ă����B ����ɂ��Ă�Racer X������3�Ȃ���I����Ƃ́B�t�@���Ƃ��Ċ��ł����̂��ǂ��Ȃ̂�....�B�i����3�ȂƂ��C���X�g�Ƃ���������́A�|�[���̍A���x�܂���Ƃ����̒��I�ȗ��R���������悤���B�j �@���������t�ō��g���ꂽ�M�^�[���`�F���W����|�[���B �@�p�ӂ��ꂽ�M�^�[�������A�C�o�j�[�Y�̃��P�b�g���[���U�B��قǂ��C�ɓ���Ȃ̂��낤�B �@�M�^�[�e�N���|����ŃM�^�[�`�F���W���s���Ԃ��A���x�̓x�[�X�̃��C�i�X�����ǂ����\�����������A�ϋq�ɂ���ׂ肩������ƈ�u����Ƃ���X��ދ������Ȃ��̂͗��ł������B �@�u���ɉ��̋Ȃ��������A�����ĉ������v �Ɨ����ȓ��{��ʼn�X�Ƀ��N�G�X�g�𐿂��A�҂��Ă܂����Ƃ���q�Ȃ̕��X����F�X�ȋȖ����R�[�������B�wDaddy , Brother , Lover , Little Boy�x�@�wDown to Mexico�x�@�wAlligator Farm�x��Mr.Big��\���Ȃ��A�Ă���钆�AABBA�́wDancing Queen�x�܂ŋ�����Ώ���͏��ɕ�܂ꂽ�B �@�i���Ȃ݂Ƀ|�[���́wDancing Queen�x���uAcoustic�ESamurai�v�A���o���ŃJ�o�[���Ă���B�j �@����Ȏ�O����ȃ��N�G�X�g����I�ꂽ�̂̓j���[�A���o������̋ȁA�uOn The Way To Hell�v�ł������B �@�����A���̎��Ԃ͂��Ƃ��ƃo���h�Ő����ɉ��t������Ƃ����\��ł͂Ȃ������̂�������Ȃ��B �@�{�����[�����i���ăN���[���g�[���ň�l�Œe�����uOn The Way To Hell�v�̓A���o���ŕ��������Ƃ͑S���Ⴄ�n�[�g�E�H�[�~���O�ȕ��͋C�ʼn����ݍ��B�i�����ł̃��C�i�X�Ƃ�2���̃n�[���j�[�͓��M���ׂ����̂ł��������Ƃ��t�������Ă������j �@�u5�̎��A��ԍD���ȃo���h�̓I�Y�����h�E�u���U�[�Y......�̋Ȃ�..My Drum�v �@�Ǝn�܂����̂́A�ȑO�����C���Ŕ�I���Ă���THE OSMONDS���uMy Drum�v�B �@�Ȗ��ǂ���A�㔼�ɂ̓h�����\�����L��Ȃ�Ƃ����^���R�Ƃ��Ă���B�I���W�i���͒m��Ȃ��̂�������������A�|�[�����ɃA�����W���Ă���̂��낤�Ǝv�����B �@18�Ȗ��uIndividually Twisted�v�B������݂̋Ȃ��B �@�C���g���ɂ����Ȃ葁�e���������Ă���Ƃ������Ȃ�m�M�ƓI��i�ł���B �@�Ȓ��͂��p���N���ۂ��A�����g�A���Ȃ�C�ɓ����Ă���Ȃł�����B���ׂ̈ł��낤���A���t�̊ԁA���̋Ȃ̖��d�s�v�c��PV�̉f�����]���𗩂߂Ă������B �@�uIndividually Twisted�v���I���A��p�����ɒቹ�����~���[�g����8�r�[�g�̃��t���J��o����ϋq�́u�w�C�w�C�v�Ƃ����|������U�������B �@�uSuicide Lover�v�͍ŋ߂̃|�[���̊y�Ȃł͍ł��D���ȋȂ��B���ꂾ���ɋC���͍ō��ɐ���オ��B �@�����ă|�[���̎ߌ��Ɉʒu����A���v�ނ��������ԋ�����p�ɂ��̋Ȃ��T�|�[�g����ӊO�Ȑl�������ꂽ�B �@�������|�[���ɃJ���y����n������A�M�^�[�����̎�`�������Ă����M�^�[�e�N�̂�������i�W�F�C����j�B���̐l�ł���B �@���̂������u�`Lover�v�̃R�[���X�̏��ł��̋�����悩��}�C�N�������ĂЂ���������o���ꏏ�ɉS���Ă���̂��B������R�[���X�̓x�ɉ��x���A���x���B���̃R�~�J���ȗ������U�镑���Ɏ������łȂ��ϋq�̒N�����Ί�ɂȂ����̂ł͂Ȃ��낤���B���ꂮ�炢���̂�������͖ڗ����Ă����̂ł���B �@�Ȃ��I���A�~�l�����E�H�[�^�[�ōA���������|�[�����uNagoya.......�v�Ƒ����I�ɉS���n�߂��B �@�������A����I�B�܂������É��ׂ̈����ɍ��ꂽ�Ȃł͂Ȃ����낤���A�u�i�S���v�Ƃ����̎��������f�B���C���Ɍ����Ƀn�}�b�Ă����͈̂ӊO�������B �@���̒e�����͎���ɒ��������Ƃ̂���Ȃւƌq�����Ă������B �@�u1�A2�A3�v�̃J�E���g�ʼn��߂ă��E�X�^�[�g����Ƃ�����uBliss�v�B�A���o���uBurning Organ�v����̃t�@�X�g�i���o�[�B �@������������������ɂ͂����Ȃ��Ȃł���B�i�䂦�Ƀ|�[���ƃn�����悤�ɃA���o���ʂ�uYeah�v�Ƒ傫�Ȑ��ŋ���ł��܂������ł���B�j �@������ɟ��݁A���̖т��z�ɂւ�����炢�̃|�[���̔M���͂����ł��J��Ԃ���A��X�ϋq�ɂ����̔M�C�͓`�d���Ă������B�����͋Ȃ��I���Ƌ��ɍX�ɑ傫���Ȃ�A�|�[���A���C�i�X�A�W�F�t��3�l�͂��̊�����w�ɂ��Ȃ����U�A�X�e�[�W���~��Ă������B �@�������A�����͈������炸�A�蔏�q�͂��������傫���Ȃ����B �@���̉��ŃA���R�[����]�܂Ȃ������s�͂��҂Ȃǂ��₵�Ȃ��B �@�傫���Ȃ����̐��Ɉ�����Ă킸��3�������낤���A3�l�̓X�e�[�W�ɖ߂��Ă����B �@�����Ă����ނ�Ɏn�܂����Ȃ́A�N������x�͎��ɂ�������������A�L�����B �@��ۓI�ȃ��t�����܂ł����Ɏc�郍�b�N�E�N���V�b�N�X�uJumpin' Jack Flash�v�B �@�������Rolling Stones�̋Ȃł���B�|�[����Rolling Stones�̋Ȃ����Ƃ����̂��ӊO�����A�����̓|�[���A���������ɃI���W�i�����R�s�[���邾���ɂ͎~�܂�Ȃ��B�M�^�[�\���ɓ���|�[���̐^�����B �@���ߑ����o��قǂ̑��e�����I���A�ϋq�����|����B���ɁA�M�^�[�������グ��ɂ܂Ŏ����Ă��Ēʏ��u���e���v�Ƃ����r�����m�e�N�j�b�N�ł́A���̐����ɂ������R�Ƃ��鑼���������B �@�Ȃɂ��A���ʂɎw�Łi�s�b�N���g���āj�e���ɂ������A�h�b���ƒb�B�h��K�v�Ƃ���Sweep �s�b�L���O�i�܂��̓X�g�����O�E�X�L�b�s���O�j�����ł���Ă��܂��Ă����̂�����B�M�^�[���u���҂ɂƂ��Ă��̍r�s�ɂ͂����~�Q���邵���Ȃ��Ƃ������̂ł������̂��B �@�u Rock 'n' Roll !�v �@�Ō�Ƀ|�[�����������Y���т͂��̋Ȃ𐳂����ے����Ă����ƌ�����B �@�A���R�[��2�Ȗڂ̓|�[���̏f������A�W�~�E�L�b�h�Ƌ��������uPlay Guitar�v�B �@�ȑO�̃��C���ɃW�~�f��������ѓ����Ă����������܂���������v���o�ł���B �@�u���[�Y���b�N�Ƃ������e�ɑ������A�����̃|�[���̃X�^�C���Ƃ͎���قɂ��邪�A���̋Ȃ��I����Ă݂�|�[���炵������₷���A�y�����Ȃł������B �@�uPlay Guitar�v�̌���x�ނ��ƂȂ��A�h���P�b�g���[���U�h�͖葱�����B �@�P���ȃ��t�����݂Ȃ���A�C�̌����܂܉����߂ɂ��n��l�X�ȁi�I�J�Y�j�t���[�Y���J��o���Ă����B �@��X�A�ϋq��|�M���邩�̂悤�ȉ��t�ɋ�X�������Ȃ���A���̑�D���ȁh�W�~�w���h��̃��t���������Ă������͋����̗]��A��⋩���Ă��܂����������B �@�uDown To Mexico �v�̓|�[���̃��C���ɂ͌��������Ƃ̏o���Ȃ��A��ԋȁA�����Ȃ��B���C�����I���Ɍ����ĉ����I�ɐ���オ���Ă����̂Ŋm���Ɋ���������B �@���̋Ȃ��I���ĂсA�X�e�[�W����ɂ���Ɓu�|�[���v�ƌĂԐ��̐��܂����͐���̔�ł͖��������B �@����̓X�e�[�W�ւ̋A�Ҏ��Ԃ̒Z������������炩�ł������B �@�X�e�[�W�ɗ������|�[���́A�M�^�[�e�N�u�W�F�C����v�AMixing�u���X����v�A���j�^�[�u�j�V����v�ƃX�e�[�W�X�^�b�t���Љ�Ă������B�o���h�����o�[�Љ�Ȃ画�邪�A�X�^�b�t�Љ�Ƃ͋������Ɠ����ɂ����ɂ��|�[���̃A�b�g�z�[���Ȗʂ��o�Ă����悤�Ɏv�����S�̂��a�₩�ȕ��͋C�ɕ�܂ꂽ�B MC���I���A�M�^�[�̃����O�g�[�����������B �@���炩�ɃX�e�[�W��ɗp�ӂ��ꂽ�G�t�F�N�^�[�i�A�^�b�`�����g�j�ݍ��Ǝv���鉹�̕ω����`���A�|�[���̎w�悪�M�^�[�̃t���b�g�̂悤�Ɍy�₩�ɒ��ˉ��B �@���̗L���ȃ^�b�s���O�t���[�Y�������n��Ώ�����uOH�`�v�Ƃ����劽���ɕ�ݍ��܂ꂽ�B �@�u�������@�܂����̋Ȃ��c���Ă����v�ƒ��N�̃t�@���ł���Ȃ���A���L���Ȃł����uGreen-Tinted Sixties Mind�v�̑��݂���������Y��Ă������͂��̏�Ȃ���S�̒��ŏ����p�����̂������B �@Mr.Big�̋Ȃ͂��̂܂�EL&P���uKarn Evil #9�v�Ɍq�������B �@������ȑO�̃��C���Ŕ�I���Ă���Ȃ�����Փx�͍����B�������̂悤��EL&P�̓L�[�{�[�h�i�L�[�X�E�G�}�[�\���j�A�x�[�X�i�O���b�O�E���C�N�j�A�h�����i�J�[���E�p�[�}�[�j�Ƃ���3�s�[�X�B�ǂ��ɂ��M�^�[�����荞�ޗ]�n�͂Ȃ��B �@�������|�[���̐������́A�L�[�X�E�G�}�[�\���̃L�[�{�[�h�t���[�Y���M�^�[�ɒu�������Ă���̂ł���B���߂ĕ������͌�����ȏ�Ԃł��������炢�������B���ɍ���͂������ꂽ���̂Ƃ��������Ōy���e�����Ȃ��Ă���悤�Ɍ��������������̂͐����B �@�����A�t�@���Ƃ͏���Ȃ��̂ŁA���낻���_�ȃA�����W�̑��̃J�o�[�Ȃ����������Ǝv�������A���̍��ł�����B �@�uKarn Evil #9�v���I���A�|�[���̓M�^�[��u�����B �@�����2���Ԃɓn��@�����Ȃ�����w�y�����x�ƐS��A�����o�������C���̏I���������Ă����B �@�i���C���P��́j����g��ŋq�ȂɈ�炷��3�l�ɂ́A����̃��C���̏[���Ԃ��\�����̂悤�ɏ݂����ڂ�A��������肽�C�����Ō��鎄�B���݂ȏΊ�A�Ί�Ɉ��Ă����̂������B �@�O��̃��C���̎��A���̓|�[���E�M���o�[�g�Ɂw�G���^�[�e�B�i�[�x�Ƃ��Ă̐����������������Ə��������A��������{����w��MC�ɏے������悤�ȁw�G���^�[�e�B�i�[�x�Ƃ��Ă̕З��f�킹�����̂́A3�s�[�X�Ƃ������b�N�o���h�ŏ��P�ʂł̃p�t�H�[�}���X�̓��b�N�E�~���[�W�V�����Ƃ��Ă̒�͂���������ꂽ�����������B �@�������A����͋C�S�̒m�ꂽ���C�i�X��LA��MI�ŋ��ڂ������Ă�����̘r�����W�F�t�̋��͂ȃo�b�N�A�b�v�����������炱���̌��ʂł͂��邾�낤�B �@������ɂ��Ă������Đ��E�ő��ƌ���ꂽ�M�^���X�g�A�|�[���E�M���o�[�g�͖����A�����ߒ��̒i�K�ł��鎖�͊ԈႢ�Ȃ��B �@�ł͎��̐i���^�͈�́A�ǂ�Ȃ��̂��H���̋����͂܂��܂��s�������ɂ��Ȃ��B |
| SET LIST | |
| 1 | Masa Ito |
| 2 | Space Ship One |
| 3 | SVT |
| 4 | I Like Rock |
| 5 | Potato Head (MR.ORANGE) |
| 6 | I'm Not Afraid Of The Police |
| 7 | Scarified (RACER X) |
| 8 | Every Hot Girl Is A Rockstar�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@ |
| 9 | Viking Kong (RACER X) |
| 10 | Something (BEATLES) |
| 11 | Heat In The Street (PAT TRAVERS) |
| 12 | Jackhammer |
| 13 | Boku No Atama |
| 14 | Terrible Man |
| 15 | Technical Difficulties (RACER X) |
| 16 | On The Way To Hell |
| 17 | My Drum (THE OSMONDS) |
| 18 | Individually Twisted |
| 19 | Suicide Lover |
| 20 | Nagoya |
| 21 | Bliss |
| �E�E�EEncore �E�E�E | |
| 22 | Jumpin' Jack Flash (Rolling Stones) |
| 23 | Play Guitar |
| 24 | Down To Mexico |
| �E�E�EEncore 2�E�E�E | |
| 25 | Green-Tinted Sixties Mind |
| 26 | Karn Evil #9 (EL&P) |