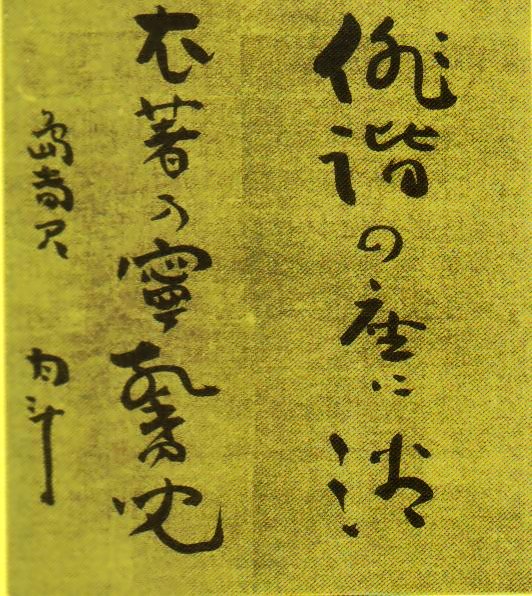�@���l�搶
���{���t
���l�搶�Ǝ�
�����\�N�́A�،��l�搶�̌\����ɓ�����B�t���ɂɂ́A���̐��ЂŊ�����͎��������A���l�搶�̏����ꂽ���̂��A���ꂱ���A���ł̕M�Ձi�I�e�̎�͂�������Ă���j�Ƃ��A�������A���ԂȂ��̉��M�𗠕Ԃ��Ďg��ꂽ���́i�n�̕����͂悢�������G���Ƃۂ�ۂ낷��j�⎆���̗ǂ����܂��g�������̂Ȃǂ܂ł��ۑ����Ă���B
�����悪�Z������ƌ����āA�������Ȃ炠�Ƃ͓��t�����邩��U�킵�Ȃ����낤�ƁA�O���֑����Ċ�z���ꂽ�Â����l�̕�������B����Ԃ̂ł͂Ȃ��B�����ɑS�l�I�Ȏt��݂̍�悤������B
���������Ă̓�ʂ̓d����c���Ă��āA�u�Z���Z�C�q�r�@�j�X�C�W
���N�Z���������v���A���a��\�l�N�O���\�����ߌ㎵����\����t�Ŏ�M�͏\���l�\�ܕ��A��������ꂽ�\����ɂ��ꂪ�������킯�����A���ԊO�Ȃ̂ŗ����̔z�B�ł���B������ʂ̓E�i�d�ŁA�\����ߑO�㎞�O�\���́u�Q�@�c�g�V�X�q�~�c�\�v�����v�ł���B
���̓�\���̑�a��F�ɂł̖����ɂ́A�}篕��������삯�t���Ă��ʂ�������B�傻���₦����������ƕ����B�����Đ��O���ɂ��A��ɂ͂Ȃ�Ȃ��������́A�l�V�����ł̖{���ɂ́A���Z���̎������ɓ��������B�l���\�����ŁA�{�V�̒뉀�ɂ��̔N�͒x�ꂽ���������Ă������ƁA�����Ԃ��̒��������������ƁA����Ɛ����n�搶�̕��e�̋L��������B
���̈ȑO�A�搶�̕a�Ă��Ƃ������ƂŁA�O���ܓ��A�}�O�̈�����������Ɠ���Ⴂ�ɁA��F�Ɉꔑ�̂��������ɕ��ƒ��w�ɓ���O�̒j�Z�N���s�����B�搶�ɋ�����Ē������炵������A�Ⴕ�����āA�搶������{����ꂽ�Ōォ���m��Ȃ��B
���v���A�����搶�̉��e�ɐڂ����Ō�̋@��́A���̑O�N�̏��a��\�O�N�܌��A���X�v�l�Ƃ��ꏏ�ɉ䂪�Ƃɂ��炵���Ƃ��ɂȂ�B���˓c�k�O���ł̎ʐ^������B�j�Z�N�����N���ʂ��Ă���B
��O����A�搶�́A�����o��s�r�̓r�����܂��ĉ䂪�Ƃɂ��������ɂȂ�A�C�y�ɔ����ĉ������Ă����B���͑��Ŏt�������w�����セ�̂܂܂ɁA���U�A�搶���h���A�搶�ɊÂ��Ă����B�����q�������́A�搶�����}�����闼�e�̗l�q�����āA�Ƃɂ����̂��搶���ƁA�c�����ɍ��ݍ���ł����̂ł���B
�I�풼��̐��Q�ʼn䂪�Ƃ����A�߂��̑P�����̗��̕����ʂ��蛉��Ɉڂ��Ă������a��\��N�Ă��A���̗��X�N���A���̎��Â����˂ĉ��H�ƕ��H�Ƃ����蒸�����B
���̖{���ŋ�������̂ŁA�J���݂�ȂŎ蕪�����Ĉē��ɉ�����肵���B�w���l�x������܍��ɁA���ˏt���i�t�a���j���v�j�����t���i������j���g�j���X�A�搶���u�O�r�O�t�v�Ƒ肵�A�u�����̒��j�̓��t�͕��̑剹���̗Y�قɎ����A�Â��ȁA���ɂ����܂ق��������ȁA���̌��͂��̒��w���ł���B�Ƃɂ����Ă����ł����̖����悭�āA�悭���������B������ȂقŒ��X���܂��B���t�͖{���ł���v�Ƃ���̂́A��\��N�Ă̋��ł���B
�c���������ƌI���G�ς���ƁA���̎q�K���ɍs�������Ƃ�����B���c���\���L���̎��̓����̑O�������́A�Z�H�m�̈��Y�����A���ꂪ�C�ɓ����ĊO�����Ȃ������Ƃ�������A�c�t���̍����낤�B�V���������������ړ��ĂŁA���̐Ȃł͎��͂̒N�ނ��܂킸�A�����A�����������Ƃ������Ƃ邩�A�����������܂ǁA�ƑO������{���点���������̂������ŏ@�c�瓕����Ɏ���ꂽ�肵�A�����́u���̌��͂��v�ǂ��납�A�����ӋC�ł����肾�����A�炵���B
�@�搶�͓��t�̃S�b�h�t�@�[�U�[�i���t���e�j�ł���B�g�E�V�����ƓǂށB���͓͂��o��ۂɁA�搶�������ꂽ�ʂ�Ƀ��r��U�����̂ŁA���̎��Ȉ�Ђ����r�t���ł���B�吨�̒��ŗ�̑吺�Łu�����A�g�E�V�����I�v�ƌĂ�鏭�N�́A������x�̍Ό��͂��ꂪ���S�ł������B���ł����A�����Ɠ������������̓V�}�n���͂�ƌĂ�ł����B
���̐��܂ꂽ���́A���B�������̊ԋ߂ŁA���t�c����C�ɏ㗤�̍Œ��Ȃ̂����A�u�k�Ђ̏T���w���^��\���I�x�Ō��Ă݂���A���̓��̓��^�́u���w�Z�̗m�����y�ړI�Ɏq���ޗ���n�݁v�Ƃ܂�Ȃ��B
�w���Y�t�H�x��E����l�j���c���Ă��āA���ʂ́A���I�A���V���ƁA��C���ρA�c�����ÎE�Ȃǂ��ڂɕt���B�����̉̐l�́A�O�c�[�邪�u�ЂƂ�̂킩���̂��A��C�ɑ���Ƃ��ӂ̂��A�����������̑��̖��B�v�ȉ��A�y���������u��C�̂������̎ʐ^�����݂�͖��G�������ɕ���l���Ă�v�Ǝn�܂�B�Ƃ��낪�A�o�l�͌��l�A��łł��邪�A��ł̂ق��́u�~�����M�Z�����p�ӂ��āv�Ƃ������ȋ߉r�܋�ŁA�o��͔o��ł���Ƃ�����B
���l�搶�̂ق��́A�u�����O�l�v�Ƒ肵�āA�u���㉡���ɂ��鐳��B���j�������Đ����Ђ���Γ��t�Ɩ����ā@���̏t�����g�̊�Ȃ�v�ȉ��O���t������̏\��ŁA�����ɂ��搶�炵���B�搶�̃l�[���������~�����o��O�̌����A����ڂ�������������ɂ͑�̂����ł���B
���̂�������I�ȑԓx�A����͓����̉����Ёw�o�匤���x�ɉ�����ꍇ�ɂ�������B�G�������������A���Ɂw�o��O��W�x�̑I�ɂ������Ă̂��ꂱ��ɁA���̌�����m�邱�Ƃ��o����B�Ȃ�m����̂�ɂ���̂ł���B�����Ĉ�̕]���͕S�N��̒m�ȂɈς˂�̂ł���B
�O�g�́w����x���펞�p�����w�t���x���o��O�̐풆���A�����ɕM�ŏo���F�߁A����ɐ搶�������đI�̏�ԑ����Ă��������Ƃ����������������B���̌`�̂܂܁w�t���x�̌��l�I�Ɉ����p�����B
���̍��̎��̋�e�Ɂu���ׂ̕��C���������Ȃ�ɂ���v�Ƃ����̂������āA���̘e�ɁA��M�Łu����ŋ�Ƃ��Ă͂悢���A����ᔻ����@���͗\�͍̂�Ȃ��v�Ƃ���B���w���̎��ɑ��āu�\�͍̂�Ȃ��v�̌�́A���l�搶�̔o��ɑ���ԓx�A�l�i�I�Ȏ��g�݂��\��Ă���ł͂Ȃ����B
���́A�u�t�H�̔ފ݂̑O�̊������ȁv�ƁA���l�����H�̎q�K�������Ɍ��������C���ė����B���O�Ō�̎l�\�O������́A�����炭�̂�҂��Ă̎l�������ł������B�Ď��̏j�������˂Ă̂��ƂŁA�@�ǎ_�f�z���ɎԈ֎q�̐g�Ȃ���A���̋C�͂͏\���ł������B
���l�搶����邱�Ƃ́A�����ĒP�Ȃ�Ǖ�A�ǑP�ɂƂǂ܂���̂ł͂Ȃ��B�����Č���ߋ��������Ƃ��K���Ƃ������B
(�����\�N�O��)
���̌p����
���l�����ł���B�\�N�O�̈�����ɓ�����A�����n�搶�Ɂw���l�{�x�Ƃ�����ʂ̕��͂�����B�̉��̖L���Ȏ��R���l�Ԉ����̂���Ƃ��āA����ɂ����ɂ��e���݁A���R�ɂ͌����ɁA�l���ɂ͏��^�ɐ������A���݁A�O���A�D�܂��l��ڕW�Ƃ��āA�������Ɍ������Ĉ���ł��߂��i�݊��H�v�����˂Ȃ�ʁB��͐l�������A�l�͋��������ƁA���̌p���҂Ƃ��Ă̎u���q�ׂĂ�����B�����A�����l�͂��Ƃ��A��ƂƂ��Ă̎����I�҂Ƃ��Ă̊��́A���l�搶�Ɠ������A�ꓪ�n�����݂ł���ꂽ�B
�́A�����s���x���f���H�c�̌܋�Ƃ����l���Ǝv�����A���l�͏��w�Z���t�̂悤���ƌ������炵���B���̖{�ӂ͕ʂƂ��Ă��A�i�i�ɗD�ꂽ��Ƃł���̂ɉ����A��ē������݂ł���Ƃ����ʂ�������B���n�搶�́A����G�r���͎��̐S�����ł��萶�����ł���A���Ђ̑I�҂Ƃ��āA�ق��Ȃ�ʎ����̑I��ڎw���҂ɉ�����A�Ɠ��邱��ɟӐg�̏�M�𒍂��ꂽ�B�܂��ɋ����҂̐������ł���B
���H�A��a�H�𖾓����֒H�����ہA���ɘA�Ȃ�R�̌����������l�搶�̖v����ꂽ��F�ɂ��ƌ�������B��̒j�Z�́A�������ɘA����āA�a�Ă��搶�̂��������ɎQ�������A���͂��̒n���Ƃ��Ȃ��B�s���̂��s���R�ȍŔӔN���炳��A���ɏI���̒n�ƂȂ�̂��A���łȂ���F�ɂł������搶�̂����O���@����A���̋C�����ɂ͂Ȃ�ʁB
�������̑�F�ɍs�����O���ܓ�������A���̒����
�O��������
�ՏI�̒���肯��@�@���ɂ���
�ՏI�̒���̗�����
������B���ɂ�����t�̐�
��������ƂȂ�ʏt�̐�
���A�搶�̋咟�ɋL���ꂽ��Ƃ��Ă͍Ō�Ƃ����B�a��̒��A����O�ɉ��Ƃ������ȍ�i�ł͂Ȃ����B
�@�\�����̊����́A������t�q�K�̏H�̂���Ɠ������A�ފ݂̓���̑O���ɓ�����B�������͈������\�l���܂ŁA�R���ɂ��t�g�̒�����ം��Ă���B��̒����Ԃ��Q�Ђ��Ђ��ƁA���Ɋ������g�~�͊J���Ă܂�œ��̉Ԃ̂悤���B�₪����������ł��낤�B�[�S�̢�~�͂��������A���͂܂������ȣ�ł���B
�傪�l�̐^�̎p�ł���Ȃ�A�ӔN����邻�����̎��Ђ͎茳�ɂ��邪�A�ƒ�̂��Ɛ����̂��Ƃ̔@���́A�j�ƕ]�҂͂Ƃ������A����҂̖₤�Ƃ���ł͂Ȃ��낤�B�������߉e�𒀂����Ɩ܂�A�ł���B
(�����\��N�O��)
�u���l��v
���̔o�l�A�،��l�̕�́A�����̕悪���鋞�s�������ɂ���B�����́A�m�Ԃւ̎v���ł��颉�������Ĕ�ɕӂ��ތ͔��ԁ@������́A���̎��̔m�Ԉ��ւł���B�����̋�ɓ����锭�z�̏��Ȃł��낤�B�����A��ؑ]�a�ƒ˂��Ȃ�ׂģ�̔m�Ԃ͔m�Ԃ炵���A���ɂقƂ肹�ޣ�̕����͕����炵���ƁA���̎�����v�����Ƃ��A���̂���A���l�t�炵���Ƃ������A���l��q�炵���Ƃ������A�D���a���炵���Ƃ������A����Ȃӂ��Ɏv�����[�܂�B
�푈�����̋�P���A��ނȂ��搶�͑�F�ɂ֑a�J�����Ɏ������B���A�邱�ƂO�ǂ�قǖ]�܂�Ă������A�@����ɗ]��B�����āA�Ȍ�̐搶�́A�l������A�܂������l�ł������Ɗ�����B�g�ӂ��r�܂ꂽ�ŔӔN�̋�̂قƂ�ǂ́A����𗷋�Ƃ��ĉ�����悢�ƁA�����͎v���B
�搶�̋咟�ŁA���������܂ލŌ�̋��͎O�������ł��邪�A���̈�T�ԑO�Ɂu�ՏI�̒��V�ƒ����Ɓv�̋傪�L����Ă����B�u��V�ƒ����Ɓv�Ƃ͌��݂̉����̎���ł���B�͂�W�X�Ƒ�F�ɂł̎����m���ċ����邩�̂悤�ŁA�����z�b�Ƃ��邪�A�悯���ɗ܂��܂���������B
�O����\�������Ɠd���āA�Ō�̂��ʂ�ɋ}篕��͑�F�ɂ��������B�ܓ��ɒj�Z�Ɣ��܂�|���̂��������ɎQ���Ă��͂�������ł���B�����̐�������A�u�Ԃ̗������č݂������ȁ@�����v�̋傪����B
�v���A���a��\��N�Ɂw���l�x�������A�搶����㏉�̒�����B�ᗷ�ւƔ����ꂽ���̋I�s�ɁA�u�O���`��菬�D���ɂđ�O���w����B��O���̑�R�_�_�Ђ͈ɗ\��̋{�Ƃ��ӁB�������l���̗̕��֗��ċ���Ȃ�B���͌����ʂ��B�����Ȃ������B���ق�������B�_�ЎQ�q�B����ٌ����B�������قɏ��Ē��H���B�v�̕���������B�`����_�Ђ܂ł̓������̏h�ŁA��ŕ����畷�����Ƃ���ł́A�u�������فv�̊Ŕ��ꌩ���ꂽ�搶���A�u�₠�R���v�N��ȁv�Ƌ����������B�ق�Ƃ͋���(���Ȃӂ�)���قƂ����̂����A�搶�ɂ́A�����̋������̂���ł������B
���́A������̔N�̏��a��\�ܔN�H�Ɍ������ꂽ�B�쐣��ю��̔z���s�͂��傫���B����l�棂͐搶�̎��ŁA���ʂ̢���̐l�@�ؐV��@���l�Ќ��V��͗��n�M�ł���B����̓_��@�v�ɂ́A���̔N��w�֓����Ė����Z�܂��̎����A�O������̕��Ƌ��X�ɎQ����B�����\�N���z�������ƂɂȂ�B
���̋������̒n�A�搶�̂�����ɂ͂悢�B
(�����\�O�N�O��)
���ɖ�͂�
���q�̂悤�Ɍ��l�搶�͂��S���Ȃ�ɂȂ钼�O�܂ŏt���o��̑I�����ĉ��������B�����ɐ����������̂���M�őI��Y�킳��A�ԑ������̂ł���B�\�R�Ɍf��������Σ�̐�����e�́A�O���ꍆ(����O)�f�ڂ̋�ŁA���w�ȗ��O�\�N�̋�����o�Ă̊����ł���B�����ČǍ����悵�Ƃ���̂ł͂Ȃ����A����͎��M���ȂĎ����̓���i�ނƂ����p���ł��낤�B
���a��\���N�̌��l���ȏ�A�����O��ɂ́A���l�搶���璸�����Â��t�����Љ�ꂽ�B������Ђ��O��W���o���Ă���A�]�͉���ɂ����B�o�匤���̑I���f�����B�����ɂ����Ă���B�o������ʁB�o�̏�̂₤�ȏ��Ɍ݂���̂͊��ւʂł͂Ȃ����B�S���ɐ���Ƃ��������������B�ߌ�l���̏Ҋ��̕��C��S䇓��B�S䇂̋�����ꂽ����S䇓��Ƃ��ӁB�ߌ�l���A���Ƃ���Ƃ����ʎ��Ԃ��B�̂��Ă��飁B���̏j��H�͑�_�s�G�Ƃ������B
���������́w�o��O��W�x�̐R�����@�����A�������āw���l�x�͔o�d����y����������B�펞�p���̍ۂ́w���݂̂��x���̓���(�ҏW���s�l)���ނ��A���Ԃ͈قȂ邪�A���Ђ̃��[�_�[�Ƃ��Ă̓�����̌����ł��낤�B
���ꂪ���݂̂悤�ȎЌ��@�ւƂ��Ă̔o�d�Ȃ�Ƃ������A���ƌ��Ђ̔o�嗝�O�Ɋ�Â��ꍇ�Ȃ�ł���B�����Ƃ��A�~�ނȂ����[�_�[�Ƃ��Ă̔������A���܂����̐^�ӂɓY�����̂Ƃ���A�ڂ̊J�����A�S�̓͂�����q�̑��݂̕K�v�͌����܂ł��Ȃ����Ƃ��O��ɂ͌����Ă����B
�@��������o�����A�����ЁA�P���ٓ������ꂩ��萢�ɏo�Ă������Ƃł��낤�搶�́A���������Ȃ����R�̢�\�͋�̐_�l�������s�ݖ����s�݂Ȃ̂��B������Ƃ��ӌꂪ���邪�A�\�͍���������ģ���A���܂ł����̕����ʂ��������Ă����̂ł́A�搶�̌ËH���@�Ɋ��s���ꂽ�w���l���叴�x���L�蓾�Ȃ������̂ł���B���O�Ԃɍ���Ȃ������͎̂c�O�ł��������B
�@���E�s��̐X��Òj���̏t���ɂ̌ÒZ����ނ��@���ɁA�w�o�l�̏�����p�x�掵����q�K�(���l�W�p��)�ɘa�c�Ύ��搶���M�ŁA��A�R�A�ɓ��A�X�A�nj��Ƌ��Ɍ��l�搶�̏������t����鎖�ɂȂ����̂́A�v��O�\�N�A�����̕ł������B
�ȗ��A�ߎ��A���l�������U������̂͊������B���Ɂw���������x�̕ҏW�A�̂��w������x����ɂ��Ă̊p���Y�N�̂��̕��ʂ̐s�𑽂͂Ƃ������B
(�����l�N�O��)
���l�l�\�Z�����
����A���c���l�搶�Ɂw�o�~�k�R���x��A�ڂ��Ē����ċ���A����͊��ɖ������@�A�{�{����芧�s����Ă��邪�A���~���ڂ������Ȃ��ꂽ�R�Ŏb���̋x�M�͗҂����B
���̍�N�\�ꌎ������l��ӏܣ�̕����ŁA�щA��終ɂ�錎�l��i�]�߂̋�̏o�T���s���Ƃ���Ă��邪�A����͂ǂ�������a�l�N�̉����Ёw������{���w�S�W�x��O�\���я���(��Ń����N�Ōv�Z�\�Z��)�ɋ�����̂Ǝv����B���̖{�̏��ɁA��̑I���͢�����o�l�ɂ����Ă͎��I����У�Ƃ���̂ŁA���ꖘ�̈ꉞ�̑�\��ƌ����邪�A�щA��絗����Ƃ����������̌��l��ɂƂǂ܂�ӏ܂Ƃ������ƂɂȂ�B
�����Ƃ��Ă̌��l��̏W��Ƃ��Ă�����́w���l���叴�x�́A�ޑ�́w���l�o��A���A��O��W�x���̑S��Ę^�ł���B����W�ł��鏺�a�Z�N�́w���l�o��W�x�́A�����Ђ̍Ύ��L�ȂǓ��l�h�̗��Ɉ�����Ă��邪�A���l��͎�ɏ��a�ܔN�̍삩��̂������̂ɉ߂����A��l��W�w���J�x�̔ӔN�̋������ɓ����Ă��Ȃ��B
�厏��ޑ��W����̒��o�͖ʓ|�ł���A�P�s�{�ɂ܂Ƃ߂Ă��Ȃ���Ƃ̕]���́A�c�Ɍ����`�����Ă͍s�����A�s�v�ƌ�������܂ł����A���ɂ́A�����鐢�ԓI�ɂ͓���悤���B�t�̈╗�̌����Ƃ͂ǂ��������Ƃł���̂��B
���̑n�������w���l�x�͍��N�ʊ����S�\�����}���邪�A���l�t�]���ɂ��A���āA�����́A�e�n���Ő�t��炢�J��s��������Ȃ���A�t�̍Ύ��L�ɢ���l������킵�Ă��邱�Ƃ�Q���āA����O�̋P���������l�̖��́A���o�d�ł͗҂����Ȃ��Ă��܂��Ă��B����ɂ͂��낢��̗v�f������A�������ł͗����邪�A�����剺�Ƃ��ẮA�剺�̂�����茆�ꂽ��Ƃ���������邱�Ƃł���B�搶�͒n�����A�����A����Ȃ��Ƃ͂ǂ��ł�������Ȃ����A�Ɛ\����Ȃ�����A���S���҂��Ă���T�C�����ĂȂ�ʣ�ƌ������B
���l�搶���ݐ����A��ɂ���w���l�x�̑��ɂ��̔��s�������������Ă̌��l�莚�̂��̂́A��O�͊�_�̍��������́w�V���x�Ɛ����́w����x�A���ł́w�t���x�ƒ}�O�̈��������́w�����l�x������B�w�t���x�̑莚�͂��̂܂g���Ă��邪�A���{���편���A�Â����ʂ���̕��ʂȂ̂Ŏc�O�ł͂���B
�搶�̊����C���邱�Ƃ��A�o���̌p�����A�剺��Ƃ̌��o�������Ă̂��Ƃł���̂͌����܂ł��Ȃ��B�ǂ���Ƃ̔y�o���w�t���x�͔O�肷��B
(�����Z�N�O��)
�t�ɕ키
�挎�͌��l�����Ȃ̂ŁA�\�����ɌÂ�����̏ё�����f�����B��[���l�Z��̋Y�ꏑ�̎��̕��͓�����ŁA���̖{���f�s����̖���X�ɂ������������ƋL���Ă���B�Z���̕��͐ԏ��ٍ�攌�̕M�œ����f�A�،��l�A�O�D���l�A�`�Ԑ��A�̎l�l�̊��`�������̂̏㔼���ł���B�吳���N�邾����w���l�x�n���̓�N�O�ł���B�f�̉E��͗�̕����̋�����L�Z�����B���l�̍���͂܂�������u�ł���B���̏\�N�O�̕��ɁA����˂Ƃ͂��ւʂ₤�ɂȂ����B����͑S���F�l�̌�A�ł���B�H���S�j�A�H���k���A�H���n���A�H���f�c�c��ƁB
��\���̋L�O�ɁA�搶�̌Â������̕M�Ղ������ڂ��Ă䂭���Ƃɂ���B�����l�\�N�l���ȑO�����e�ƍ����Ă���B���ł������ł̐搶�̖����̓Q�b�g�[�ƌ�����グ�Ă̗͋������̂ł������B�����̋��̖����̂��ڂ����́A����ւ̐ӔC�s�݂ł���B
����܂��]�k�����A�e����l�ւ̉����ɓ������āA���l�̑��ɂ��낢��ƃg�A�g�E�̉��̎��ɂ��Č��ׂ��Ă��āA���̒��ł����A���A���ق��ɂ͈����邪�A���̎��`�̏�ł����`�̊Ȗ����ł��u�l�v���׃X�g�ł���B���������c�H�����H�o�Ɖ��߂��B��͂莚��̒P�����ł��낤�B�Ȃ��T�c���u������������m��Ȃ������Ƃ��B
�������t���d��ꂽ����ł������B�����A�ޕr�����Ȃ��Ȃ��Ă̏H�̢��ח�����Ƃ��A��͖��Ŏ�萳���s�������Ă̢���֓�����X�p�o����̂��������ς����A���̢�o����̌���������Ȃ��Ȃ����̂͗ǂ��B�����܂����̃p���f�B�Ƃ��Ă͏G�킾���A��X�������ɂ����ƍ���B�͂��܂���Ŏv�������Ԍ�͊D�_�y���炢���B
�@���āA���e����̒Z������͔~�̗��Ԃ⏉�������I�ɋ��������肽�鐗�̂ʂ���Ɖ����R�攌�̒ޏ��̊G�ɢ�ފ݉���ɉ��ޓV��������f����B�������͖����O��N(��\��)���̏��Ƃ����B
�j�I�ȈӖ��]�X�����A�M����t�̐��Ȓf�n�������Ԓ�q�Ƃ��Ă̐S������������B�w�т̓��A�t��̓��͏c�^�ł��邱�Ƃ������Ɍ���̂ł���B��q�͉����тŁA�����O�������Ď�������̂ł���B
栂��͈������A�����������ڂɂȂ�قǂɍD�܂������߂邱�Ƃł���B������O��ɂ̌�����A����Ēʂ��ΐ痢���ꗢ��킸�A��܂��痢�Ƃ������̂ŁA���̕����y�Ȏt���s�H�ł�����B���l�A���������X�ɏq�ׂ鏊�Ȃł���B
(�������N�l��)
�o��͖��Ǝp
���l�搶�ɂ͐\����Ȃ����A�����f�����搶�̒Z���̒��̈ꖇ�́A���́A���ʂɢ�������ĕ����̓��ɗV�т���A�̏����磂ƋL���Ă�����̂ł���B
�@���傤�Lj�N�O�́w���o�x�[���ɏ��Ƃ̍唜�R���A��n�̔��\�I��̓��ɁA����͐F��������������ĕ����̓��ɗV�т���@���l����ڂ��āA����̏��ɂ͏t�̕����i�m�n�i����������Ŋy�����B�����Ď��̍���ɐ��킳��飂ƌ����ċ�����̂��A���������j�Z�N���蔲���đ����Ă��ꂽ�B�搶�̖����}�X���f�B�A�ɏo�邱�Ƃ͊�Ȃ̂ŁA�F���������������̂ł���B
����ꐇ�̌�A�搶�́A�Ô~���́w�g�Ԗn�x���Ƃ��Ɩ������Ȃ��ɁA�������́w�����x�̕��Z���A�Z���̊��|�Ɋ|������B�ӂ����Ƒ������ĉ����ڂ��̏�Z���ɢ����ƈ�F�����ꂽ�Ƃ���ŁA�M���~�ߑ傫�ȑ�������āc�c�B�M�p���̌��������Ȃ��̂ł������Ēu�����B�ȉ���ĕ����̖߂�[����@���l��ƁA����̋���s�����Ă̋A�蓹�̋�Ɍ����ɕϐg���Ă���B�Ăє��R����̕������肷��Ƣ�a���̃R�[�g�̂�������āA"������"�𑫂ɂЂ������āA�����������l�̎p���ڂɕ����ԣ�ł͂Ȃ����B
�@��W�w���J�x�̏����̌��Ѣ����̔o��A��X�Ƃ��āA�V�����ɑ��Ă��B�S�N�ɒʂ����͂Ȃ��B���ƒ�����鏊�Ȃł��飂���A���l�搶�̂�����b�g�[�Ƃ��������������悭�������邪�A�����Z���̋�Ɍ���Ƃ���ł́A���S���Ȃ�ɂȂ�O�N�̒W�H�s�̍ۂ̢�t�̌��o��͖��Ǝp���ȣ�������o�������B�p�Ƃ́A���ׂƂ����ʂƂ��p��p�@�����܂\���̂�����ł��邩��A���l�o��Ƃ������p�̋�ł���Ɛ\���������悢�悤���B������͌f�����Z���̋�ʼn����Ă������������B
�@���l�搶���A���̒��w�q�K����]�߁x�̏����ŁA�q�K�̏��ɂ��āA����m�ݐ����́A�N���ނ��A�͕킵�����̂ł���B�Ɍ�˂̏��ȂǁA�ł����Ă��B�i���Ȃǂ����A�p���Ȃǂ����A�}�_�Ȃǂ����A��������̂����Ƃ��Ƃ����Ђ������Ă��Əq�ׂ���B����Ƃ��Ƃ����Ђ������Ă��Ƃ��������ɒ��ڂ���B���ׂĎt���Ƃ������Ƃł͓����悤�Ȃ��Ƃ������B
�o��Ə��ƁA�ӏ܂ɂ��Ă͈Ⴄ�̂��낤���A���Ǝp�Ƃł͎��ʂ��Ă��邩���m��Ȃ��B�����āA������A���̖��Ǝp�������邽�߂ɂ́A�w�ԁA�^���ԂƂ����ߒ����o�˂Ȃ�ʂ悤�ł���B
�@�X�Ɏv���B���F�A�ǂ���Ƃ��Z���ɏ�������(����ȋ�Ƃ����ے��I�Ȍ�������)�Ƃ������Ƃł��낤���B
(������N�O��)
��������
�O�����f�ڂ̒Z���̋墎R���⣂ɂ��ẮA���������\���Ɍ��l�搶�̎���������B���́w���l�o��W�x�����������a�Z�N�O�����̋���r�ŁA���Ȃ݂ɂ��̌��̎���ɔ��\���ꂽ��́A��\����̋���ɑ�����Ȃlj����Ė�S�\��ɂ���鎞���ł���B
�@�@�R����������Ă��t�̈Ł@�@�@�@�@���l
��R���̋�A�����Ȃ炸��Ƃ��ӂ���B�\�H�ہB�W�X���������ɂ܂��̂Ȃ�B��R������ď����t�̈ţ��R���⏪�̒����t�̈ţ�����삹�����A���Ă̢�R����������Ă��t�̈ţ���o�傹���Ȃ�B�x�����I�ɕ��āA�R���̖�͐Î₻�̂��́A�t�̈ł̔Z�����n�̔@����z�ӂׂ���ƕt�L����Ă���B
�w�������x�̖}���̢��ނ��ւ̂��̉J��ɒu����������⣁A����ɂ́w���̏����x�ɂ��颌Òr�⣢�R���⣂̂��ƂȂǂɂ��A�z���y�Ԃ��A���̢�R���⣂��A�Ȃ��ߑR�Ƃ��Ȃ���A�����̖�����������̗��邱�Ƃɘւ݂̂ł���B
�@��t�̈ţ�͢�t�̖�̂����ݣ�ł���B���ƌ����A�����Y�́w�ł̊G���x(����)���v���B���̖`���ł́A�ł̈Í��̒��Ɉ�����ݏo���̂ɢ�������H��Â��飏�M���K�v�Ȃ̂����A���̈ӎu���̂ĂĂ��܂��ƁA�ł̕��i�͈����ƂȂ�A���тł́A������s��̂ǂ��֍s���Ă��d���̌��̗���Ă���𔖂������v�͂Ȃ��ł͂���Ȃ��̂ł��飂ƁA�O�\�Β��O�̔ނ̈łւ̊��o�A�����W����B
�@�t�̈����A�����Ђ̋��q�ҁw�o�~�Ύ��L�x�t�̕��ł́A����̂Ȃ��t�̖鍠�̎��₤�ȈÂ���ŁA��H���ȏ�����֕�_�炩���A�Ȃ�����������ţ�Ƃ܂Ńz�g�g�M�X���l�̉���ɂ���B�G��̉��߂Ƃ́A�Í������̋�ɕ\�ꂽ�G�߂̌��t�̎��ϔO�̂���ő��������A����̈ł̂悤�ɋ��|������g�܂ňꐡ�C��ς��������œ����Ă͖��B����ŁA���̂��Ƃ����ŁA�Í��̂����������m��ʂ��B
�@�]�k���łɁA������Ղ��t�̋G��ő����������ł���B�G�����i���O�j�����͢�V�n���ێ������邭�N�炩�ɔ����������킽��L�l��A�����͢�����₩�ɘa���ȓV�n�����̑���ł���A�Ƌ�J���Ă���B
�@�Â��w���l�x���̑��������ɁA���ꂪ�������B
�@�@���͗��������͖����Ֆ�@�@�@�@�@���l
��̂ق��͌����Ă���̂ł��ˁA�ƒN�����������B
�@�����ɘւ��Ƃ́A�o�喡��������Ƃ������Ƃł��낤�B�o�喡�Ȃ���̂ɁA�ܕS���A���S���ɂ��čs�������A����Ɩ����������Ƃ�����̂ł��낤�B
(������N�l��)
�����_�o�̓���
�M���M�E�����Ăł������B�t���ɐՂ̈ꕔ���ɁA����܂ňڂ��Ēu�����Â����̂����[���悤�Ƃ����̂ł���B
�����ނ͍ŏ����ɂ��A�|�P�b�g�^�C�v�̃t�@�C���ɁA���a��N�́w�哨�x����w�t���x�̌��݂܂ł̃o�b�N�i���o�[�����ĕ��ׂ��B�o���͋�W�ƈ���āA���Ԃɒʗp����i������͂Ȃ����A�n���̌X�̑̉����ۂ���Ă���̂��悢�B���e�E���Ȃ́A���l�A���]�̂قڑS�āA�Â��͊��O�A����~�A�����ؓ��A�ԏt�A�����A���\�A���l��w����x�ȗ��̕\���G�̉����A�ߓ��_��H�A�O��A���c���l�Ȃǂ��悭�ۑ����Ă���B���Ɨt���́A��K�ܗЂ���Q�~�܂ł̎������啔���Ŗ�ܕS���A�����t���l�͕S�l�\�]���𐔂���B�T�~�i���Q�U�j�ȍ~���͔N���ǂ��ăt�@�C���ɐ������ł���B
���x�̓]���̒��A�����肽�t���B�̕M�Ղ��A�����́A���ЂƂ��Ăł͂Ȃ��厖�Ɏ����������Ă����B�悭���Ă���ƁA��̍�����̍��ɂ���Ĉ�Ă�ꐬ������ߒ����悭�킩��B
���̕����Ɍ��l��u�o�哹��v�̊z���f�����B�����ÂтĔ������F�ɂȂ��Ă��邪�A���ΐS�g�����܂�B��͋�̍��̏��Y�ł���B
���l�搶�̔o��ς̈ꂩ���ɁA�u���S�ł��鎖�B�a�I�łȂ����B���܂����łȂ����B�����_�o�̓����͂Ƃ�Ȃ��v������B�搶�̌��t�́A����ꕪ�͂��ĉ��߂����A������������ŔF�����˂Ȃ�Ȃ��B�����ł͂Ȃ��A���H�I�ȕ��@�ł��閡����v����B
�����_�o�̉ӏ������āA�ʐ���r���]���ł̊ϔO���z�Ԃ̂��A�ȂǍl�����肷��Ɠ���Ȃ�B���S�Ȍ܊��̊��o�Ő������Ώۂ𑨂���͓̂��R�̂��Ƃł���B���������A�����݂����Ȏ��̂̂Ȃ��ە��ɂ́A����Ǝ��U��Ȃ��̂ł���B�O���̉��������̕������p�������I�őS�̓I���ӂ̃R�����E�Z���X�ɒʂ��邩���m��Ȃ��B�Ƃ�����A���Ԍ���H�i�ł͂Ȃ��s�Ղ̐^����ڎw����������������̂ł���B
����Ɉꂩ���A�u���N�ł��鎖�B�����X�B�I���X�ł��鎖�B�j���I�ł��鎖�B���ōs�����B�ڂ���B�����l���̔����͓Z�͂Ȃ����v�����l�ł���B�����X�Ɉ�������I���X�́A���O���Ƌ��Ɍ��l�搶�̂��D���Ȍ��ł���B�o����I���X�����O�����Ƃ����Ă��A�܂�Ō��������Ȃ����A�����̂��܂�����G�ł����Ă͂Ȃ�Ȃ��̂��Ǝv���B
�搶�͢��͐l�Ȃ裂Ɛ����ꂽ�B���S�A���N�̔o��ς͂܂��ɐ搶�̋�A�搶�̂��p���̂��̂ł���B
(�����\��N�㌎)
�o��̂䂭��
�X�Ȃ����낪�������S�������������A���̎��G�ɂȂ�ƁA�C�`�S��T�N�����{��~�j�g�}�g���p�b�N�ɓ����đ�K�̓X�[�p�[�ɐ���������B
���̖O�H�̎���ɂ����āA�����A����҂ɍL���ܔ������_�앨������������Ƃ��āA�������ĉ������ƁA�����H�ׂ��邱�ƁA���ɂ��܂�Ȃ����ƁA������̔_����Ƃ̎R���y�ꎁ�͋�������B
���̓����̂��ꂼ��́A�g�b�s���O���ĖڂɊy�������A��̋Z���v��Ȃ����A�w���V�[�݂����ŁA�����̐l�ɍD�܂�ē��R���Ǝv����B�Ƃ��낪�A���Y�҂ł��鎁�̌����ɂ͔_�̍s���ւ̒Q����������B
���Ĕ���Ȃ�A�킪��������A�������a��������_���ς�������A�c�ŋȂ����āA����ɂ͖j�����A����ň��݉����A���܂ł��������̂����̂́A�����̍D�݂łȂ����甄��Ȃ��̂ł���B
�������A���������������l�דI�ɑ����Ȃ��Ă��Ă���B��ɉ����ω����Ă��Ȃ��ƁA�i���Ƃ��ď��ƃx�[�X�ɏ��Ȃ�����ł���B�����Ă�������ƂłȂ��r�r�b�Əu�Ԃ̃t�B�[�����O�ŏ������B�X�}�[�g�łȂ��Ă͂Ȃ�ʁB��ԉɂ͗v��Ȃ��ŃA�C�f�B�A���B���̌̍��͂����Ă͍���B���i�̗ʂ��D�悷��B�_�̐l�ɂƂ��Ă͕s�{�ӂȂ��Ƃ��낤�B
�����A���������L��ȐH���i����������Ă݂�@��������B���̉ʎ������́A���R�ƃO���[�v��������Đl�H���ɂ��炫��P���Ă����B�����ɂ���H�v������̂��낤�B�C�`�S���T�N�����{���~�j�g�}�g���A���ʂ����Ƃ���̊X���̉ċG�Ƃ��������ł���B�����̂̔��S������̃g�}�g��Ė�������f�̈�ۂɔ�ׁA���炩�ɂ��ꂼ��̑����͎�܂��Ă���B
����҂̃j�[�Y�ł͂��邪�A�}�����X�X�܂̏��i��e���r�̂悤�ȑ僁�f�B�A�̈�����r�������ł���B�{���A�o��͔����Ȋԍ����d����B�L���傫���X�s�[�f�B�ɂȂ�A���������������W�ʂł͐l�ڂ������Ȃ��B�����t��������邩�ǂ��炩�A�����Ȋԍ����̌��肪�o���Ȃ��̂ł���B
���l�p��̂Ȃ��Ɂu�w�G�v�Ƃ����̂�����B�������̒���l���̃h�C�c���w�ɋ���_�l���痈�����̂ł���B�l���́A�s���s���i�s���s���j���|�p���̖{�̂ł���Ƃ����ŏq�ׂĂ���B�r㻂��̂ɁA�n�Ă�ΐG�i���j�A�ꑱ���ł���B���Ă��܂܂ł͐�Ȃ��̂ł���B�n�������͔̂w�A��ɕ������B���҂������ɑ��݂���A���̊Ԃ̏����ł���B
�C�`�S�炵���C�`�S�A�T�N�����{�炵���T�N�����{�B(�����\�O�N�Z��)
�����̂�����
���l�搶�́A�u�H�v�Ƃ������̂łȂ��A�Εɝӂ��т̐�����p����ꂽ�B�w���l�x���ʂɂ܂ł��ꂪ�y�Ԃ̂́A���a�\�N��̂��Ƃł���B��O�́w���l�x�������n�k��牽���ō��s���Ȃ̂����A�w���l����W�x(����)�͢�H��ŁA�w��O�x(���\��)�͐������p�����Ă���B�G���ŏH�G�̋�̍��Ƃ��Ȃ�Γ����̈�����͊�������ς������낤�B
�������ɐ��͂����͍s���Ȃ��������A�w�t���x�ł͓���������ɂ��S�M�Ő�K���ō��肾��������A���l�搶�́A���͂ɂ������ł͎g���ʐ������g���Ċ�e���ꂽ�B��ԣ�����A��飂����͂������A�����u�ׁv�����u�t�v�̌Î������Ȃǂ܂ł������B
�H�̐����́A���[�v���̂h�a�l�̕����Z�b�g�ꗗ�ɂ��������A�E�F�u�́w���̕������x�����荞�݁A�����w�势�a�x���H�̐����̔ԍ��Q�S�X�S�P�Ŏ��݂�Ε\���ł����B�d�g�݂͂킩��Ȃ����A���ꂪ�ʏ�̃t�H���g�̢�^��̎��ɓ�����B�i���Ȃ݂ɁA���݂��������t�H���g����t��̑�֊����͂Ȃ�Ƣ���Y����I�j
���䂦�����܂łƎv���B�����̂h�a�l�̕����Z�b�g�ł͎��̂�V�A���A�{�A�ÁA���A��A�ʑ̂ƕ��ނ��Ă���B�V�A���Ƃ����͓̂��p�����̂��̂����瑭�ɗނ��邪�A���ꂼ��̏��ł̂����̎g���������낤�B�������ɑ����͕��ꂽ�`������A�Z���`�ŁA�����Ԃ��Ƃ���͉��������m��Ȃ��B�����搶���H�̐����̎g�p�͉��������̂��B
�����A�����Ƃ��ĔF�߂��Ă��鎚�́A����͎���������̂ł���B�Î��������߂Ă���B�ӎ����āA���̋G�߂�\����̎g�p��o��̒��ōs���Ƃ������Ƃ́A���E�̎����ɐG�ꂶ�Ƃ���ԓx�Ƃ����ׂ����낤�B�܂��A�o��̕]���ɂ����āA���Ԃ̃X�P�[�������g��̖ڐ���ōs�����Ƃł�����B
���|�Ƃ��ẮA�`����s�̃X�y�[�X�̔o�傾����A����̓����b�g�ł͂��邯��ǂ��A�V���G���Ȃǂ̃R�����ɕ֗��A���f�̏ꍇ�ł������������g���āA�u�[���ɂ��Ȃ�Ղ��B�Z���`�ł́A���ՂƂ��X�Ƃ����䂫�N�����A�o�含�̊�ߊg�U����ɜ���Ă��Ȃ��Ă͂Ȃ�܂��B
�o�~�t�Ƃ��Ĉْ[�A�ƕx�R�t�搶��������m�ԁA��͂藣���̕����A������r�����q�K�A�V�������������l�ƁA���o�ɂ܂݂�ʌn��������B�搶���H�̐����́A������\�������̌`�ł������낤�B
�w�t���x�͎t�̂Ђ��݂ɕ킢�A�S���ĐՂނ��肾�B
(�����\�l�N�\�ꌎ)
�s���s��
���͂����镶�w�N�ł������킯�ł͂Ȃ����A����ł��u�k�Ђ̕��|�G���w�Q���x���A���l�O��̓�N�ԍw�ǂ������Ƃ͈ȑO�ɂ��L�����B�ŏ����������Ɂu���㕶�|�Ɩ���v�Ƃ����ʍ��t�^���������B����Ȃɏڂ������̂ł͂Ȃ��A���Ƃ��Έ�_������w����b����x�̍�i���ɂ��L���ł������B
���̍�i�̏��o�͑吳�\��N�����A���̌㖄��A�}���́w������{���w��n�x�Ɏ��^���ꂽ�͎̂����w�Z���o����ł���B���́w���E���w��n�x�̂ق��𑵂��Ă����B���̒��x�̂��Ƃł͂��邪�A���̃^���z�ƌ��l�̔��w�A�������ł͋L���Ă����B
�u�w�G�A�o���B���R�̏����ׂ��w�͂��Ă��v�Ƃ́A���l�搶���w���l�x�̃��b�g�[���q�ׂ����߂�����̌�ł���B�܂�őT�ⓚ�����A�w�G(�G�w)�͈ȑO�ɂ����������A�o�������ڂł̖������痣���̂�����A�����̋��ɋ��Ď��R�̂ł���悤�ɁA�����I�ə��f���Ă��A���ȏ�Ɍq������̂����邱�Ƃ��B
����l���w�G�w���w�x�̔��ɁA��R�a���́u����|�͑��G�s����|�͑��w�v�Ƃ���B�|�����Ƃ́A�n��������Ƃ���l�͍���Ă���ƌ���̂����A�|�ɐn�Ă邾���ł͍��Ȃ��̂�����A���Ă��n������邱�Ƃ��܂�����Ă���̂ł���B��ɂ��Ĉ�A���̗��\�̂悤�Ȃ��̂ł��낤�B
��_����́A���a��N�ɁA�w�`���y�ѓ��e�Ƃ��Ă̊����ʐ^�x�\�������A�u���̌�A���s�̔o�l����l���̐G�w���w��m�������Ƃɂ���āA�����̕K�v�ɔ���ꂽ�v�Ƃ��āw�l�̐G�w���w�x�ɉ��߂Ă���B
�l���́w�G�w���w�x�́A�O���́w�o�~���w�x�̌ܔN��A�����l�\�l�N�̔��s�ł��邪�A�o�d�I�ɂ́A�Ɍ�˂̐V�X���A�����ċ��q����ɕ��A���鎞���ł���B���l�́A��Ɏ��w�ԕS���x�Ɓw�J���^�`�x�̂͂��܂ŁA�l�����܂ߔo�l�⑽���̕��l��ƂƂ̌�V��ʂ��A���̔o��ς�[�߂Ă��������ł���B�l���̘_�́A���Ƃ��Ύ��������̘X�l�`���|�p�Ƃ͎��Ĕ�Ȃ�Əq�ׂ�B�l���������A�|�p���̖{�͕̂s���s���A�͌��l�o��̈�L�[���[�h�ł���B
�f����u�L�f�����̓����������U���ԂƋU��ԁv���Ƃ��鑫��́A�f��ł́A���Ԃ͎��Ԃ̉�]�ɂ܂Œ��ۂ���邩��A���e�ł����Ԃ����ꂾ���̗l������v����Ƃ��A����ɍł��ӂ��킵���̂͏��ł���ƁA�ǂ����쌀���������B�`���b�v�����̂���łȂ��̂������[���B�����炪��݂̓_�ŁA���l�o��ɐG�꓾�Ȃ������̂ŁA�܂��q�ׂ�B
(�����\�ܔN�l��)
�G�w���w�̂���
�u�^�X���G�w���w�ǂݖO�����@�����v(����O)�́A����l���́w�G�w���w�x(���l�l)�̂��ƂŁA�u�ǂݖO�����v�͎t���l�Ƃ̏����ɂ��̂ł����B
�l���͓ƕ��w�҂Ŕ��w�ҁA����s�o�d�̐e��u�����̔@���l�����v(���l)�ł������B���̒�����w�́A�|�p�ł���܂��˂��܂�Ă������z(���o�A����)���������̖{�̂ł���Ƃ��A���ꂪ�s���s���̂��̂ł���̂��|�p�ŁA�u�m�炸���炸�͕�̂��߂ɋ\�����̌��z�Ȃ�B�̂ɂ��̍�i�́A�B�����R�ɑ������Ȃ��ĖړI�Ƃ��A����đz���������D�܂��B(��)�s���������ȂĎ��Ƃ���v�̂���|�p���Ɖ]���B
��_����́A���̖{�̕\�����荞�f��_�w�l�̐G�w���w�x(���O�\)�ŁA�u�l���́A�g���������ʐ^���Ԓ������w�E���Ă���B�G�w�Ƃ������̂��Ƃ����A�ނ͉f��̓����Ƃ��āA���ꂪ�s���s���ł͂Ȃ��A�����܂ł��s�������ɂ��邱�Ƃ�ǂݎ���Ă���B�����s�ՂłȂ������s���̂��̂ɗ��r���Ă��邩��A����|�p�I�ӏ܂Ɋ����ׂ����̂łȂ��v�ƁA�l����~������B
�吳��N�n�����̌��l�w���l�x�̋�́A�����́w�z�g�g�M�X�x�̏��q�ώʐ��������Ŏ����o���A���ꂪ�B�����R�ɕs����������ԓx�ł͂Ȃ��Ƃ��Ă��A��ׂāw���l�x�̋�́A��苭���A����đz�������ق����D�Ɖ]����B
���l���ł̐������A�ɂ��A��吳�����ɂȂ�ƁA�z�g�g�M�X�ɂ��炴��ΓV���ɂ��炸�A�Ɍ�˂̐V�X�������ɂȂ��Ă���A�ʐ��A�ʐ���Ƃ������А��̒��ŁA�����������n�߂����́u�ʐ����y�����邱�Ƃ�������ƃI�[�o�[�����v�Ƃ̌���������B
�܂��A���l���w�q�K����]�߁x(���\)�̒��ŁA���m�̋�̓��F�̈�Ƃ��āA�u�G��I�ł���B�G����ʐ��ł���B���̖n��ł͂Ȃ��B�ʐF�̎ʐ���ł���B�n��͎�ϓI�̂��̂ł��邪�A�G�̋�̎ʐ���͋q�ςł���A���ʓI�ł���v�Ƃ��]���Ă���B
���߂�Ƃ���́A�l���́u�G��͈�����`���͕�̓w����v������A���̈���ɔV���ׂɐ�������|�p�̌��o��r������̍H�v�Ȃ����B�z���͑������̈��i�ɂ����͕�ɑ���������w���Ȃ�B�̂Ɏ��R�ɑ����ɔ������R�ɗ����Ȃ��B�v�́A�z���Ƃ��������ł������낤�B
�z���̌�́A�V�X���o���_���钆�ɂ����邪�A�����ł͋��`�̋G���T���͔o���������̂ł͂Ȃ��B��r�Ƃ����`�̋��Ⴊ�w�ǂł��錎�l�o��ɂ����āA�z���Ƃ́A������Ɍ��Ԃ��ƂɂȂ낤�B
(�����\�ܔN�܌�)
�o��̊�
�u�����ʐ^�́A�����ɗނ����銈������Č����ɗނ������Ԃ������v�ƁA����l���́w�G�w���w�x�̒��ŁA�����ʐ^�Ɨ��̎����Ƃ��r���Ă���B���̢������Ƣ��ԣ���A�^���z�i��_����j�̂��������ʐ^(�f��)�́u�㐔���v�Ɓu���v�ɏƉ������Ă݂��B
�^���z�̂��������ʐ^�ɂ������㐔���Ƃ́A�u�F�B�̎���ӂ�����A�{�[�g�̒��ʼnS���̂����肷��v�悤�Ɂu���l�ɂ��m����₷�����́v�ł���A���Ƃ́A������̂ӂƂ����Ƃ��A�J�̔��˂��ĂƂ����X�p���܂����Ă䂭�{�M�[�d�ԣ�̂悤�Ɂu���R�E��ʂ��Ă�����X�݂̂������Ă�����́v�ł���B
�^���z�́A�@�B���g�������ʐ^�ɑ����������e�Ƃ́A�l�Ԃɐꑮ�̢����A�܂�쌀�ł���A�l�Ԃ̔߈������[���A��Z���`�����g�ɕ��炷���҂������i��ŁA�ǂ����쌀���w�ɂ܂ł����炵���ƁA�����[��V�[�����̖���������B�����f��́w�I�Y�̖��@�g���x(�M���A���ݍ�)�̊ē剉�҂ł���B
�ł́A�W���f�B��K�[�����h���h���V�[�������邠�̑z���o�̉f��́A�������ƃu���L�̖���ƃ��C�I���̏�ʂ���A��̏�̗������菜���āA�I�[�g�}�`�b�N�ɉ������Ƒz���ł���Ȃ�A�^���z�̂����f����������邩������Ȃ��B
��X���f����ςċ����̂͂��̏�ʁX�X�������ł��邱�ƂɈ˂��Ăł���Ƃ����g�[�}�X��}���̌����A�^���z�͈��p����B���A�������ĕ��f����Ă��邪�A�ϋq���܂���̂́A�|�p�]�X�Ƃ����O�ɁA�����߂��Ă���̂�����̓���ɂ��̂��Ƃ�������(�����Ɍ����������Ȃ��)�ɂȂ�B
�o��̊ӏ܂����l�ł��낤�B��҂̐��������A�u���ꂽ�����A�f�ނł���a��n��푈�Ƃ��A������Ȃǐl�ς̏�̂��̂ւ̋����ƁA�o�傻�̂��̂̊����Ƃ̓C�N�I�[���ł͂Ȃ��B
�^���z�̔o��ς́A�w�V�Ύ��L�̕����w�x�i���O���j�̖`���́u����̊Ⴞ�̎����́A�������̂̂�����Ƃ����Ȃ�Ђ��݂̈�ۂɍ���Ă���̂ł���B�����Đ���̖ʗ����Ƃ��S�ӋC�Ƃ��ɑ��Ăł͂Ȃ��B�܂��ĉ����l�i��v�z�ł��낤���v�������Ēu���B
���l�A�l���̉��Ƀ^���z��A�˂āA���̉f��ł̌��n���g���A����҂Ƃ��āA�o��̕s���s���l�����B
�^���z�́A�u�|�p�Ƃ�����ė������I�u�ԁv�ɗ��̂ł���B�o����A����ɗ����X�g�[���[�́u�����l�I�ɒu���ꂽ��ԓI�u�ԁv������o���̂ł͂܂�Ȃ����ƂɂȂ�B
(�����\�ܔN�Z��)
�Ύ��L�̗��
���̕��@�Ƃ��āA���a�����ɁA����͎��ł͂Ȃ��V�Y�ł���Ƃ܂ł���ꂽ��r���A�ߎ��A�G��ƌď̂���Ȃ���A�G��Ƃ����p�ł̕����X���ɂ���B
�G��Ƃ́A�G�߂�����o���Ă���G��Ɠ������̂ł͂Ȃ��A�����o�l�����X�ƑH��ŗp���邱�Ƃɂ��A�n�������肵�A�₪�ďے��I�ȈӖ������Ɏ����������ɂ�����p�T�̔@���A�{���L���ȁA�G��̒��ł�����r���e�[�W���̂��w���B
�Ύ��L�ł̋G��̗��݂̍肩���ɂ��āA�u���S�҂̎w�j�ƂȂ�A�Ύ��L�̎��ۓI���l�����E����v(���q�w�V�Ύ��L�x)�̌��������邪�A�����̌l��W�Ƃ����}�̂̊ȕւ��ŁA��ƕʃA���\���W�[���G��ɂ��d�������悤�ȗ��̗̍p�����͑����悤�ł���B�����āA�����錻��o��̋G�ꕪ�z�́A�G�����Ƃ͂������A���Ȃ苷���Ȃ悤�Ɍ�����B
��O�A���l�h�̋�́A���̖w�ǂ����Ђ̗ޑ��W������p���ꂽ�B���l�搶�̋���A�͂���̐�������̂���Ă���A������Ȃ��͔ۂ߂Ȃ��B
�w������{���w�S�W��O���сx(�����Ё@���l)���̎��I�ɂ�錎�l�o��Z�\�Z��ƁA����ɑ����\�N�Ԃقǂ����߂��w���l���叴�x�Ƃ����Ă݂�ƁA��҂̐��S���\�]��i�ޑ��W����̘̍^�̂����ŋG��͘Z�S�l�\�����邪�j�̓��A���ӂ炵����́A�e�A�ԁA��A���}���A���l�A�~�ĂƂ����吔�̏��ƂȂ�B�ȉ������Ă��A���̃A�N�Z���g�ɂ͈Ӗ�������B
�Ύ��L�́A���̋G��̊���̑�������������Ƒ��������̗�傪���݂���A������̂��ꂱ��͗v��Ȃ����ƂɂȂ�B�ޑ��W�̌`�ōςނ̂ł���B����ȍΎ��L�̗��ƂȂ���ڎw���˂��l�߂Ă䂭�A�����ғI�ȋ��������Ǝv���B
�Ύ��L�̗��ɑ���������́A�R�[�i�[�������A�����ŋG��̐^���ɂ�������ʂ������̂ł���B�a�I�łȂ��A���܂����łȂ��A�����_�o�̓������悵�Ƃ����A���S�Ŗ��N�ŋ�����ł���ׂ����낤�B���݂ɂ���́A���l�搶�̋�̎咣�ł���B
�G��ʂɂ��āA��Ƃ̎d�������ł���̂��������B�q�K�̔o�啪�ނ�����A���̋G��̔��e�ŁA�Í������̔o�l�̗͗ʂ��A��̗ǂ����������肠��Ɣ���B��r�́A���̒��ԓ��ɓ��肱�������ƂɂȂ�B
���X�A��r�����W���邱�ƂƂ����B���ꂼ���̋G��̋�Ƃ����������߂�B��Ɍ����ɋ߂Â��čs�����Ƃ������̖{���ƈ�v������̂Ǝv���B��r�́A�䓙���R���֓o�郋�[�g�̈�ł���B
(�����\�ܔN����)
��ڗ��Ɨ���
���l���w�q�K����]�߁x(��}�t�A���\)�̒��ɁA�q�K���m�ɏA���āA�u��ڗ��Ȃǂ̉̋Ȃ����܂�D����Ȃ������ƕ����B���̑���ɗ��ꂪ�D���ł������������B��m�����_������v�Ƃ�����������B�q�K�̋�̌X���Ǝv�����킹�A��̋Ȃ��b�̕����A�����̒��q�ł���B�ʐ��I�A�����I�ł���B���e����]���Ă��A��ڗ��͗܂ł���A����͏ł��飂Ƃ����B
���łɎO�\�O����ƂȂ�A���l�́A�t�q�K�̋�����q�ςł���悤�ɂȂ����Ƃ��A�q�K�̋�ɂ������̖R���������̂悤�Ɍ����Ă���B
�q�K�ɗ����r��͑������A�u�X�Ƃ��āA���ݓI�ɔY���́A���ɂȂ������́A���H��H���Ă���悤�Ȃ��͖̂R�����B���߂��Ă���悤�ȁA�p���炤�Ă���悤�ȁA�H���Ȃ��́A���́A���ݍ��ɓO����悤�Ȃ��́A�����ꂵ�����̂Ɖ]�������ɁA�[���Ȃ��̂͛��Ȃ��v�Ƃ܂ŏq�ׂ�B
��͏�ڗ��ł��菗���I�ł��낤�B�Ⴆ�Ό��l�Ɠ��N�̉̐l�o���q�̍�i�ł���B�u�R��o���q�́A�҉̂��r�ނ��߂ɐ��܂�Ă����悤�ȉ̐l���Ǝv���v(�|�����q)�͎����ł���B���̏�O�܂����̈ӎ��ȂǁA�o��͐[���ɂ͂Ȃꂸ�A��͓H�炷�قǂ�������Ȃ��B
�q�K(�|�̗��l)�̒Z�̂́A�o����Ƃ������A�q�ϓI�ȉ̍ނt���ɉr���ĒP���f�p�ł���B���̍��ݔh�̒Z�̂́A�q�K�v��b�����Ė����h�ɕ�����B�̂ł���낤�Ƃ���Ⴂ�l�݂͂ȏ��q��̉̂Ɍ������悤�ȁA��z�A��M���^�������Љ����ɂ������ƁA�ē��g�͓W�]���Ă���B�����O�\�Z�N����l�\��N�Ɏ���g�����h�ł���B�ؗ�ȏ����̐l���y�o�����B
����A�����o�l�̂ق��͎����ď��Ȃ��B�Ⴆ�A�w������{���w�S�W�x(������)���ڂ́A�����吳�̔o�l�S���\�Ƃ̂����A�͂��ɂ��ӂЁA���]�A�v���A���ȏ��𐔂���݂̂ł���B�S�s(�鏗�A�����q�A�A���q)���܂��o�ꂵ�Ȃ��B
�v���ɁA�����̏����o�l�͂��̎��������w�����ł���A�������Ĕo��Ɍq�������̂ł��낤�B���w�����͂�͂�Z�̃^�C�v���낤����A���̔o��ɂ͊o�傪�����āA�����o�����蓾�Ă���B�����S�����Љ����ŏ����o��͏������悤�ȍ��������B
���N�����͂S�s�ɂ����̐��܂ꂾ���A�O���ŏq�ׂ��悤�ɁA�e�̖ڂ𗩂߂ċ��������B���|�̒��ł��Ƃ�킯�o��ɂ́A����Ȃ������Ƃ����Ƃ��낪�������B�������Ȃ�Ĕo��^�C�v�̌������͂Ȃ��B�������Ƃ����Ƃ���ɁA��̂����̕������o��B
(�����\�ܔN�㌎)
�L�ӎ��̔�
�@�u�����_�o�̓����͂Ƃ�Ȃ��v�Ƃ������l�搶�͉̒�����������������Ȃ��B���R�A���S���̒m�o�̂��ƂŁA����������A�����_�o�A�܂��]�̓����݂̂̋���ɂȂ�悤�ɕ������邩��ł���B�܊��ňȂĂ̎ʐ���g��Ƃ���o�傪�ƌ˘f�����낤�B
�@���̑O�́u���S�ł��鎖�B�a�I�łȂ����B���܂����łȂ����v����@����ɁA����Ȋ��o�}�Ǝv���A���o�̊�ق����ł邱�Ƃ����߂�̂ł���B�V���n�̋Ȗʋ��ɉ䂪�p��`�����ނ̂͂�����Ɩʔ������A���̖������́A���̂��߂̎d�|�����Ɣ��邩��ł���B�O�x�ڂƂȂ�Ɩ������͂��قǂł��Ȃ��Ȃ�B
�@�O�ɂ��q�ׂ�����l���w�G�w���w�x�́u��|�p�̌��z�͖��ӎ��̌��z�Ȃ�B�m�炸���炸�͕�ׂ̈߂ɋ\�����̌��z�Ȃ�v�Ƃ́A��]�����܂�����āA�K���X�Ђ��_�C���Ɍ����邱�Ƃł���B���̌��z���L�ӎ��̌��z�łȂ��Ă͂Ȃ�ʂ���A���悻�u�����_�o�̓����v�ɍ��E����Ă͂Ȃ�ʂ̂ł���B
�@�@���ɖk����߂������肯��@�@�@���l
�@�@�Ԃ��e�q��������ڂ��@�@�@�@�@�@��
�@��]�ƌ����Ă͐g���W���Ȃ��̂ŁA�����O��ɂ̌�����A��o��́A�����̎R���n�����A������ł������ɕ\�����ׂ��v�������ė��悤�B�����܂��͑z���ɂ��R��̑n���Ƃ͂����A�N�ɂ�����S�̉��̎R��̌��^�Ɋ�Â����̂ł���A����������ɕ\������Ƃ����̂́A�������A���ӓI�Ɍ��t��c�Ȃ��Ȃ��Ƃ����o��ԓx�ł���B
�@���l�o��́u��͐l�Ȃ�v�̃t���[�Y�́A�C�{�_�̂悤�ȉ��߂ł悭�g���邪�A���|�_�Ƃ��āA��L�̔o��ԓx�̍s����������Ă���̂ł���B
�`���̔��A���Ǝp��[��������v���Z�X�ł̋�́A�ꌩ�A���}�ŋ����A���\��Ŗv���A�����Ń��m�g�[�����X�ł͂��邪�A���̌������ɕʂ��Ă̌�������A����͋�i�A��i�ƌĂԂׂ����̂ł��낤�B����́u��͐l�Ȃ�v�Ƃ������ق��ɉ�����������B��ނƂ��X�^�C���Ƃ��������^�����Ă��Ă��A�Ȃ��Ȃ��ɋy�Ȃ��̂͂��̌̂ł���B
�@�f��w���l�̎��x�Ƒ�̓h���}�w�{�{�����x�̖`���V�[���Ƃ̗ގ����b��ɂȂ��Ă���B���ނ��āA�p���f�B�ł��Ȃ��A�����C�N�ł��Ȃ�����A���p���A����A�I�}�[�W��(���h)���Ƃ���������B
�@���l�剺�̋�̏ꍇ�̓I�}�[�W���ł���B�����������B�������ꎚ�ł͌��l�̕M�ƌ������̂��Ȃ��̂�����B����A�t�ւ̑S�l�I�ȌX�|�ł���B
(�����\�Z�N�O��)
����E�����E����
�@�������͂��~�����c��������A��N�A���߂̓y�j���ŁA�u�t�����m�v�ɖ�R�̉Ԃ��������A���d�ɐ����������A���������B
�@���m�̌ď̂��A�G�g�̑��}�̂悤�ɂ҂�����Ȃ̂��q�K����Ƃ���ł���B���q�Ɂw�q�K���m�Ɨ]�x�w���Ύ��Ǝ��x�̕��͂�����B�l���́w�q�K���Η��搶�x�ł̖{���́A�q�K���m�Ɵ��ΐ搶�ł���B���q�́A�͂��߂́u�����ʂ�̖��Ŏq�K���Ăv�i�q�K�G�L�j���A��A���j��̐l�ɂȂ��Ă����̂ŁA�p���ďd����u���S���Łu�q�K�v�ƌĂԂ悤�ɂȂ����ƌ����B
�ŁA�����̊��Ƃ����ܕ����̐����킹�͂��₾���A�u�t�����v�͂Ƃ����ƁA��O�́w����x���w�t���x�Ɖ��߂čďo�������Ƃ��ɁA�������ӎ����Ȃ������킯�͂Ȃ��̂ŁA�~�̏t������[���킯�ɂ������ʁB
�����t�������A�Ɍ�˂́A��̕����́u�l���v�ɉ萶���A�u����v�Ɏ}��A�u�t���v�u���M�v�ɉԂ��J���A�u�Ёv�ɓ����Č��������v�i�w��l�����x�������p�ЁA���܁j�A�Ƃ��܂��������Ă���B���M�Ƃ͋����̂��Ƃ�����A�t��������d�̖��������Ƃ���ӂ��B
�Ɍ�˂́A�����̋傪����j��A���C�����Ȃ̊����̂܂܂Ɋ������g�������̒���͂��Ă���̂́A�C���ł͂Ȃ��u�ނ̐S�����疗y���v�i�w��l�����x�j���ƁA���ꂪ���擲�ۂɒʂ��邱�Ƃ��q�ׂ�B
�����̕��l�悪�����ʐ��ƕ`�ʖ@���K�͂Ƃ��Đ��܂ꂽ��悾���A�����́A���̐��n�ʼn悢���R���Ɠ������A����܂������⊿���̋��n�ɗV�Ԃ̂ł���B
���l��Ƃ͐E�Ɖ�ɑ��Ă̏̂ł���B���Ԃ̍D�݂ɉ����Ȃ���ł���A�l�i�������\���B��������ŁA�����@�̌��l�o��́A�����̑��o������Ύ����ƌ��o����Ƃ���̌i���ʂ��Ƃ������ԓx�ł���B
���X���D���⏾��t�@�@�@�@�@�@�@���l
�@�@��J�ᐰ�⍡�N�|�@�@�@�@�@�@�@�@��
�@�u���X���D���v�́w�Ɋޘ^�x��Z���_��\�ܓ��̌ꂾ���A�u��J�ᐰ�v�͉��z�C�̎��u��J�ᐰ�Ԏ����v����ŁA������u���N�|�v�̋G��ŋ�ɂ����B���͝R��Ȃ̂ɁA���̕����͑T�т̂���Ɏ��Ėʔ����B��́A�ǂ���̏ꍇ���A���ꂪ��@�Ƃ��Ă̏ے��I�ȓ��������A��̓��e�i��I�Ȃ��̈ȏ�Ɏ����グ��B���̂悤�ɁA�����E�����E���T�ɍP�ɐe���߂A�����̋C���L���ɂȂ�A��i���������邱�ƂɂȂ�B
���l�搶�͊Ȗ�w�����x�����E�ɁA�����̐����̕ʂɌ����������B���̐�̌R����ɕ֏悵�����p�����A���㉼�����������܂ꂽ�B�����̕\��ł���B
(�����\�Z�N�\��)
�吳�����̌��l�̋�
�o��l���Ƃ����������������āA���ꂪ���Ȃ��Ƃ��S���A�����Ĉ�疜�Ƃ͜����B����Ȃ������ł́A���X���\������̂��ׂĂ����ĉ]�X����͍̂���ł���B䩁X����X�тł́A�傫�ȌQ��𐬂�����ł������Ȃ��ƋC���t���܂��B
���f�B�A�ŁA�捏�b��̂m�Ƃ`�����A�m�ł́A���Ԃ��̔o��ԑg�̎���������͂����o���A��Ղ���疜�����疜�ƌ��Ă���̂��낤�B�`�ł́A��ܕS���Ƃ��A�u�o��`�v�́u�T���`�v�̘Z���̈�̕������B�o������������肱�߂镪��ƂȂ����B
�`���̑��ʂɂ��鎍�l�ɂ��A���\���W�[�͍ŏ��[�֓I�ŕ]���������B�A���\���W�[�̖ʔ��݂́A���̕Ҏ҂̊�͔@���ɂ�����B���X���ꂪ�d�r�ꂵ�āA��ɐG���l��W�Ȃǂɗ���ȗ͉�����A�}�ɕn���ɂȂ�͎̂d�����Ȃ��̂����B
�����Ƃ�����́A���Ƃ��Ɠ��e�[�������W���I�Ȑ�发�̂��Ƃ����A�u�����ɂ��v�Ƃ����̂͋C�ɂȂ錾�������B�y�[�p�[��}�K�W���łȂ��u�b�N�Ƃ��Ȃ�A���Ђ��钆�g�Ɍ�����炵���B
�����l�̋吶�U���c�Ɍ���ɂ́A�咟����G���ɔ��\�������̂��A��{�ɓZ�܂��ċ���Ε֗��ł���B
���l�\�N�]�̋���̓��A�B��̌l��W�w���l���叴�x�ƁA�O���⊮��������Ёw������{���w�S�W�x�Ɠ��l��W�w���J�x�ƂŁA���a���͂قڃJ�o�[�����邾�낤�B
�����鐬���Ɍ������Ă��閾���吳���̌��l��ɂ��āA���˂Ċp���Y�N����d�b��Ⴂ�Ȃ���A���l������ɂ͂��łɏ[�����낤���A�w�t�ďH�~�x�Ȍ�̋����X�E���̂́A�������\�̐V���G�����U�킵�Ă��邩��A�ǂ��Ȃ�Ɠ����Ă����B
���ꂪ�����x�݂ɁA����A���\���W�[�I�ȏ������M���āA�Ï����T��A���䔐�Y�҂̋�W�Ō��l��̊���ɏ��Ζʂ����B�q�K�v��̓�\���N�ԁA�����̎�ȐV���G���̔o�嗓����I�яW�߂ĕ҂A��A�̋G��ʋ�W�ł���B
��̑����́A�ʓI�ɂ͎q�K�̔o�啪�ނ̏\��ɑ�������B���̒�����A���l�i�e�j�̖��̍s���E�����Ƃɕׂ߂Ă���B���͌����҂łȂ�����A��o�l�̎�Ɩڂ�ʂ����傩��̑������Ƃ����A�T���v�����O�̑e���͎d�����Ȃ��B
�������́A�t���l�̕M�Ղ�厖�ɕۑ����Ă����B�`�����̂��̂Ԃ킯�ł͂Ȃ��B���l���k���ďN�W����c�݂��A���̈ӂ͕��Ɠ����ł���B
�i�����\���N�l���j
���E������̃��[�c��
�@�吳�\�N��̌��l�A���N�t�̋��q�ƁA���҂̒���s�̂��Ƃ͈ȑO�ɋL�������A���w���������o���Ȃ��������q���}���̐ȑ��ɂ��Č��邱�Ƃɂ���B
�@�@�t�̓���g�̂��Ԃ��̂����鑐�@�@�@�@���@��
�@�@���₩���j�����肵�t�̓���@�@�@�@�@�Ε��O
�@�@�t�̓���ǂ����҂����_粒��@�@�@�@�@���@��
�@�@�t�̓��̖��邳���͕��ɂ���@�@�@�@���@�t
�@�@�t�����z�W�߂ēǂ݂ɂ���@�@�@�@�@�@�g�@�X
�@�@�t�̓��₤���ق������̕�ꂸ�@�@���@��
�@�@�y���ɏt�̓��̂Â����։���s���@�@�c�m�p
�����̑I��ŁA���q�̏o��͎��̂悤�ł���B
�@�@�t�̓����������Ԃ���ĂƂ�������
�@�@�t�̓������Ƃ����l�łɗ���
�@�@�ł̏t�̌䂠���������܂�
�@���q�́A���A�Łu�o��͏\�����Ƃ�����������̐M���Ƃ��Ă���v�ƌ������B�ꎞ�V�X���ɂ������c�m�p�̋�ł́A�u�����̋������Ƃ͌��t�̏�ɋ��߂��ɁA��̓����ɐ��݂���悤�ɐS�|���ׂ��v�ƁA�Ȃ��Ȃ����}���Ȃ��f���ɕ��R�Ɍ��i���ʂ����@���q�ׂ�B�Ɍ�˂Ɏ^���Ƌ��q�ɒǏ]�Ƃɓ��ꂽ���������ł��߂��Ă��āA�w���O�痢�x�ȗ��̒n���̋�ɉe����^������O�ւ̗��������Ƃ�����B
�@�k���Ă��̐V�X���̂��Ƃ����A����ŕɌ�˂Ƃ��̉Ƒ��Ɍ��l������̂́A�����l�\�O�N�t�ł���B
�@�@���̓��c�ɎU���賎q�[�����@�@�@�@���@�l
�@�@�@�Δ�ё��͗l�s��賎q�@�@�@�@�@�@�@�Ɍ��
�Ƌ������Ă���B�V�X���������A���ڂ̔o��I�ɂ́A���i�Ɍ��l�ƕɌ�˂Ƃ̊W���������Ƃ͂Ȃ��B�����̈�ʕ����ł���B���̎����̗�ŁA��Ɂw���l�x�ɋ����������̐l�����̋�������Ă݂�B
�@�@�鏋�������Ԃ葐�Ԃ̂���@�@�@�@�@�@�����p
�@�@�p�_�c�b�܌��J�����̂ɕ�������@�@�����Y
�@�@����Ց|���ׂ��肵��[���Ă�@�@�@�@�����_
�@�@��s�̖������̉j�����ȁ@�@�@�@�@�@�@��@�J
���̋咲�́A�吳�ɓ���⎩�甖��A�₪�Ă��������l�����o���オ���Ă䂭�B�O�L�̐l�����͂���ɐ������B���q���q�ώʐ������������ł���B��̌��l�͂��̂����肩����n�߂�悢�B
�q�K�Ȍ�̕Ɍ�ˁA���q�̗���ɑg�ݍ��܂�Ȃ��o�l�����̓��ł��A���l�Ƃ������݂́A���̐l�Ԗ��ɂ��Ƃ��낪�����B���ׂĂ��l���̂��̂ɋA�ꂷ��B�Ȃ����l�o��̕]���ɂ��ẮA���ė��n�搶����������Ă���B�����͑S�l�I�ɋ���w�B
�i�����\���N�Z���j
���l�`�u�����v
���S�ꍆ�ݏo�����ӂ����߁A�������̎G�r�I�҂ł��錎�l�搶�̏����̏o�̉敝��\���G�Ɏg�����B���̎����őn�����Z�\�N�ɂȂ邪�A�̂ɉ��x�����������o���������ŁA���b�L�[�Ȑ��ɂȂ����̂ł���B
���o�������邩���m��Ȃ����A���̊G���́A�w���l��O��W�x�i���ꎵ�j�̌��J���̌��l��u�ɓ��R�ɂāv�̗��\���A�������ł���B�����A���a�\���N�ɐ搶���������ۂɂ��肢���āA���`�����A�搶���̈ɓ��̏����A��������o���Ƃ�A�Ƃ�����������悤���B
�搶�́A�u�o�`���k�v(�w�o��u���x���O)�̒��ŁA�u���l��Ɠ����₤�ɁA�\���Z�I�̗��K�����I�ɑ���Ȃ��Ă��A�o��I�ɏo������Ă���v�ƁA�q�K���m�̃X�P�b�`���ʔ����̂́A���A�s�܁A�R��̕a���ł̊G�̘b��������Ŏn�߂��̂����A���̐l�i�A�o��Œb���グ�����U�̕\��ł��邽�߂��Ƃ����B
�搶�̔o��͐����Ȃ����A�q�K���l�Ɏʐ�����ŁA���̊G���낤���Ȃ��̂łȂ��̂́A�e�����F�l�̉�Ƃ������A��^�̖��ʼn�������̂Ɖ�l��������͌����B�ٍ�A��Y�A�P�x�A�P�R�A�|�F�A��X�A�؛��Ȃǂł���B
�搶�̏���𐢂Ɏ��������̂́A�w�o�l�̏�����p�x�V�q�K(���l�A�W�p��)�ł���B�a�c�Ύ��搶���Ҏ҂ŁA���̊��ɖ�A�X�A�nj��A���l�A�R�A�ɓ��̂��̂��t���ꂽ�B���l�̊|���l�A�F����A��ʈ�A�Z���O�_�ŁA���ƕ��c���l�Ƃ̉����������̂ł���B
�搶�̒Z���Y�p�����A�����̎����ɕx���̏����̐����́A�吳�̏��ߍ����Ǝv���邪�A���͏ڂ炩�ł͂Ȃ��B��������אg�̏��̂Ō��l�����̒Z������́A��Ŏ��������ł��Ȃ��ł���B���ɂ��āA��|�A�NJ�������邱�Ƃ����������B
�吳��N�\���A�{���O�����w�����V���s��x��n���A�O�S���Ō����G���ɑ��������A���̐V���̕��|���p����搶�͒S������Ă���B���ɕ��l���Ɖ�ƂƊe�E�̉����҂ɂ��s��̃T�����I�Ȃ��̂����݂��A����ɊO�����ڂ�t�����̂ł��낤���B
�����Ō����Ă����A���l�傪�u���O���ʂ̊�����r�Q����l���m��A�y�V��`�̎��l�v�u�N�w�I�v�z�I�@�v�i���n�j�Ől�X�Ɏ��̂́A�O�ɍD�܂��l���ɍ��v���邻���������y���̂���������B����͊��|�̏��ɂ��ʂ���Ƃ���ł���B
���������l���̕\��ł���B��N���A�����吳�̌��l�������N�߂Ă݂����A���̋�̃X�^�C������܂��Ă����̂���͂�吳�������̂悤�ł���B
(�����\���N�ꌎ)
��͐l������
�t�����Ă��������n�搶�̊����ł���B�o��ɂ͍�Ҏ��g�̕������Ȑl���ςƂ������ׂ����̂��K���܂܂��Ƃ����搶�ł������B��O�́u���Ă����O�̕��ƂȂ�ʁv�́u��O�v�̑[���ɂ���������Ƃ���ł����āA���n�w���l�x�ɂȂ���B
�@���l�w���l�x�̗ޑ��W�́A�X�e���I�^�C�v���̋傪���ƌ�����̂́A������V�����[�����߂���̓��ł͎d������܂��B�u�傪�o�҂�ΐl���o�ҁA�l���o�҂�傪�����ĘҁA�C�̙B�͂�҂�Ȃ�v�i���l�j�́A���ƉC������߂˂Ȃ�ʁB�@
���l�o�傪�N�w�I�v�z�I�Ȃ��̂��u���@�v�i���n�j����̂́A��㒬�l�ł��錎�l�̐l���ςł���B�u��̕i�i�Ƃ��ӂ��̂�������˂悭�Ȃ��B��i�͎���l�ɂ�����̂ł���B�l�i�����͂�ł���v(���l)�̔o��ԓx�́A���m�̕��Y�ɂ݂鋁���̎p�ł���B
�悭���̐l�̑�\��Ƃ����ꍇ�ɂ́A�ő���I�ȋ�Ƃ͏���������̂̂��̂��������̂ł���B���q�́u���N���N�т��_�̔@�����́v�́A���q�������_�̔@���Ƃ͕ϓN���Ȃ��Ƃ������Ƃ��낤�ɁA��т�����]�O�ɓN�w�I�v�z�I�������̂��낤���B
���l�́u�t�D�������Α����v�̋傪�ʂ��čD�܂ꂽ�̂��A���m�I�R��ɂ�⎗���F�����������A��������܂ق��ƔO���čm���䂦���낤�B
���a�����A�H���q�́A�u���R�̉Ȋw�I�T���v�ɉ߂��Ȃ��q�ώʐ�����A���(���R�ɑ����҂̊���)�̋P������Ƃ��邱�ƂŁA����ף���d�鐼�m�I�R��������B�R��I��������Ӗ�����̂Ȃ�A���l�o��͂������l���Ɍ�������̂ƌ����Ă����B
���l�o�傪�����A�ʐ��ɒ����A�����I�ȂƂ�����ȂāA������߁A��ނ����풃�ю��߂��ċ����{�ʂ��Ƃ��A���l���̕s�����w�E����̂ł���B����𗇔n�搶�́A�����ł͂Ȃ��̂��A�t�Ɏ��l���̉ߏ�A�������̉ߏ�ɂ����̂��Ɛ�Ԃ��B
�l�݂Ȃ��A���܂�ɂ��c�t�����ĕ��ʂ����Č��߂����Ă��܂����⎖�ł����A�������Ċy�����Ă��܂�Ȃ��̂��ƌ����B�l�Ԃ���D���Ŏ��R����D���ŁA���O���ʂ̊���̂܂܂ɉr�Q�ł���̂��ƌ����B���N���K�A�l���m��A���l�o��͌��l���̐l�ł���B
�呦�l�̊�{�͗��n�o��ł�����Ȃ��B���n�o��͉̂����Ƃ����Ȃ��B�R��̎��A��̒��ׂ̎��ɂ����āA���m�I�Ȃ���ƈقɂ��ēN�w�I�v�z�I�ł���A�`�͒�����o��I�ł���B�w�t���x�̃��b�g�[�ł���u�a���s���v���A�܂��ɂ����呦�l�̑ԓx�ɑ��Ȃ�Ȃ��B
(�����\���N��)
�������[��`
�č��̃������[��`�́A�吳�\��N��A�����̐V�嗤�ւ̊��ɑ���A�������[�哝�̂̋��ې錾�Ɋ�Â����A��ɓƑ��Ƃ����F�������o�Ă���B���l�w���l�x�́u�������[��`�v�i���n�j�́A�y���Ȍ����ŁA�ꕔ���̍�����`���w�����̂ł���B
������o��l���̑����́A�o�啶�w�̎������Ƃ��čm���Ƃ��낾���A���Ƃ����荞��ł��邱�Ƃ��\�ɂ����B�o�判�D�Ҍ����̎G�����A���e�����ғI�ȑԂ̂������āA����ނ�����鎞��ł���B
��O�̉����Ђ́w�o�匤���x�́A�Ȃ��Ȃ��̌��ЂƋݓx�������Ă������A�������̎��M�ɂ���A��O��W���o���Ă���A�]�͉���ɂ����B�I���f�����B�����ɂ����Ă���(���l)�̌�C�̌������́A���ꂪ�A�o��̉��l�F���̖�肾����ł���B
�w�o��O��W�x�ւ̘̍^���@�����A�R�����Ƃ��āA���l�E���E��━E���Q�E��ŁE�����E�ΓC�E���m��E�H���q�E���b�̏\�����A�����B���q�͕ʊi�Łw�z�g�g�M�X�x���瓌���e�ꖼ�ł���B����ɉ����āA�����l�̎��I�A���E��A�m���l�̏o�吔�����悸�͂悵�Ƃ��悤�B
���́A�̘^���\�l���O�l�ȏオ�I��ɂ������Ƃɂ���B��ʂƒm�����킹�]���A�O�\�l������O�l�ȏ�̑I�ł́A���ۂɂ͋吔�����肸�A��l�ȏ�̑I�ɕύX���ꂽ�B��_�ƌĂ��ʂ̗̕��ł���B�Q�[���Ȃ�Ƃ������A��̕]���͂������ɂ���̂ɁB
�_���̑����́A�����v���ʂقǂ̖��傩�A�����́A�����|�s�����Y���ƌĂ��ނ̋傾�B��ʂɎw���҂��Ղދ��́A���̑I�ɓ��邱�Ƃ��F���I�Ƃ����B�I���Ƃ����w���҂Ƃ��Ă̎����ɑ����ׂ����A�����I�҂̍��Z�́A�M��u���I�҂ɑ��Ĕ��Ǝv���B
�w���l�x�͓����̔o�d�Ɖ����A���ʓI�ɂ͉����ꂽ���ƂɂȂ����B�܂��펞���̑��̔o�������ł́A�����ɔ��s�l�،��l�ƈ��������̒E�ނł���B�����������ۂ������Ƃ������̂ł��낤�B
�w���q�x(���x�j�@���O��)�ɁA�H���ʼn��͂�����A�͔��͖k�C�܂ŗ��ď��߂ĊC�������B���̍L�傳�ɋ����A���܂ł̌Ȃ�k�C�̎�i�W���N�j�ɒQ���B��́A��̒��̊^���C�����Ȃ��̂͋��鏊�ɓD�ނ��炾�A�Ē����X�����Ȃ��͎̂��ɍS�邩�炾�ƌ����B
���̎�́A�܂�����J�߂����Ƃ͂Ȃ��B�V�n������m�邩��ł���B�ʂɂ���͂Ȃ����͎~�܂�Ȃ��̂ŁA�召�Í��͔�ׂ悤���Ȃ��B����A��̒��̊^���̑�C���̌����Ă��F���Ȃ��̂ł���B
(�����\���N�O��)
�����E�q�K�E���l
�q�K��ɂ�苌����E�����o��́A���w�N�����ɂ͐V�̎��A�a�̂Ȃǂɔ䂵�Ă��A���͓I�ł������B
���l(���e)���A�ԓ��̐�����A�ꂽ���߂Ă̋�B�̌ڋq���ŁA�����w�ŋD�Ԃ�҂ԂɁw��B�����x(�F�{)�̔o�嗓��ǂ݁A������[�߂��Ƃ����B����ƋƂ�S�����̋����������������̂��낤�B�������R����F�{�ɕ��C���ė��ċ������Ă��������ɓ�����B
���N�A���̟��́w�V�������x�����ɏo�ĕS�N�ɂȂ�B�q�K�v��l�N�ځA���̑S����l���y�[�W��t�^�Ƃ����w�قƁT�����x��㊪�掵���́A�����ĘI�ɂ��w���_��W��сx���O��y�[�W�ƁA�����̌ܔ{�̑���ł���B��O��y�[�W�̖{���ɂ́w��y�͔L�ł���(�\)�x�������Ă��āA��A�Ɍ�ˁA�̑I�ɂ���W�o�傪�A���ʓI�ɂ͘Z�y�[�W��ł���B
���e�����s�֓��債�Ďb�����āA�w�قƁT�����x�̔��s�����R���瓌���ֈڂ����B��W�o��́A�q�K�ق��̑I�҂ŁA�G��Ǝ����тƌ��݂̏o��ł������B����Ɍ��e�������I�����̂́A����(���O��)�̖�I���(�H�G��)��Ƃ���邪�A��⌵�I�̎q�K�I�ɓ���̂͑掵���́u�؉�v�ł���B
�q�K�́A�I��́w��W��u�̉�v�ɏA���āx�ŁA�u�̉�͋�����ɂ��ĕω�����B�̂ɕ�W����ߔ��͗ދ喔�͙��ދ�Ȃ肫�v�ƌ����B�u�˂̌Ê��Ɂv�u�m��ʒ�������v�u�ĐՂɁv�u�͂ꂽ��Ǝv�Ђ��}�v���X�̎���́A�������邱�Ƃɂ���đނ��Ă���B�O���́A
�֗����ċˉ���ӂ����̋��@�@�@�@�k�B
�j���̖ڔ��ƌ��̉肩�ȁ@�@�@�@�O�q
�̉�ӂ��Ə��̌�铒�a���ȁ@�@�@�Ë�
�Ƃ�������ł���B����Ƃ͑f�ނ̔z���ł���A�����т̏o����A�q�K�̔o�啪�މ��j�̔��\�ƘA��������ނŁA���̎����A�V����̐V��������߂��̂ł���B����͉��̕����֍L����V�Ƃ�����B
�ɓ��×Y�����_�ŁA�q�K�͋����̒m���E���̋��r���邽�߂ɁA�m�Ԃ̋�̎�ρE�ے��ɑウ�ċq�ρE�ʐ��̑ԓx�����A�����̋����ނ̍L���Ɩ͕�Z�p�̍I�����̎��_�Ő��������A����͎q�K�̎ʐ���`���A�|�p�I������r�����u�v��ϓI�ȋ@�B�I�`�͕ۖ�v�̎咣�ł͂Ȃ����Əq�ׂ����a�̏��ߍ��A�����́w���l�x�̌��l�Ɏt�����Ă��āA�����́w�z�g�R�M�X�x�̏����q�ώʐ����m�Ă��Ȃ������B
�q�K�̐��������ԂƂ������Ƃł́A���l��̂���̔@���A�����̎R���ׂ�ԓx�A�[��Ƃ����c�̕�����T�����̂ł���B
�i�����\���N�㌎�j
�u��͐l�Ȃ�v
�����O�N�\�����𐳟��Ǔ����Ƃ��Ċ��s�A�Ȍ�A���t���p�����āw�t���x�͎��N���o�߂����B�Z�Ղ̐��I�ɂ͂Ƃ������A���ߕ��̓��̐��I�ɂ͂��݂��t�H�����߂Ă����邯��ǂ��A�o���̐����Ƃ����ׂ��G�r���̊�����������A��C��m��ʂ��A�苖�Ŏ����ɔ�r���Ă݂āA�]���͂Ȃ��\���Ƃ���˂Ȃ�ʁB
�@�����O��ɂɂȂ��鉏�ŁA�x�R�t�搶�ɂ́A���a�\�l�N�㌎�����̓�\�N�ɂ킽�钷���N���A�����ʂ�̏����ɂ��l���\������A���̊w���͌��t�ɐs�����Ȃ����̂�����B���O�̐����O��ɂ��ێ����y���݂Ɂu�n�NJߖ��v���Ă������Ƃ��v���B
�m�Ԕo��ɂ��āA���̔o�~�Ƃ��Ă̌��n���̉��`�̂��Ƃ�A�`���I�ȕ���S�Ɋ�Â��y���̋��n�ȂǁA����q�K�}�Ƃ��ẮA���X�ɂ܂Ȃ��J���������邪�A�����̔o��E�̗l����肵�āA�m�Ԃ̐l���Y�p�ɁA�����̊w�ԂƂ���͑傫���B
�y�R�搶�́A�����m�Ԃ��u�ْ[�̔o�~�t�v�Ə̂���Ă���B���Y�I�ȏ������Ɛ����I�Ȗ����Ƃ́A�������ꂴ����̂�����B�����̓_���o�~�́A�t�ƒ�q�Ƃ��������X�ƌڋq�̊W�ɑ��Ă����B�m�Ԃ��A�����鏤�ƓI�Ȃ��̂����₵�A�����ĉB���Y���̋��U�ɐg��u�����p���A�x�R�搶�́A�ԕ��o�~�Ɛl�Ԕm�ԂƂ͈�̂ł���A�ْ[�Ǎ��ƌĂ��̂ł���B
�u��͐l�Ȃ�v�ƌ��l�t�͐\���ꂽ�B�S�l�o��́w�t���x�̖ڎw���Ƃ���ł���B�K���ɂ������Ԃ�����B���̒��̈������ł��݂���������̂ł���B�t����i���́A�ÎQ�卋�Ƃ����ǂ������g���ŁA���������T�C�Y�ŏI�n���Ă���B���ʗ���u���A�I�҂�����҂��y�ł͂��邪�B
��̑I�ɂ��āA���Č��l�t�̞H���A�u��҂��m��Ă��ƁA�ߑR�Ƃ��č̂��傪����B�悢��ł���B��҂��m��Ă��ƁA���ʂ̋�A�����͂���ȉ��̋�ł��̂�B�e���A�s�e���A����͕���ʁB��҂������Ă��̂Ă�傪����B�ނɂ��Ă͐قȂ�Ǝ̂Ă�B�e���A�s�e���A����͕���ʁv�ƁB
�e�Ǝ�邩�A�s�e�Ǝ�邩�B�I�҂̌��t�Ƃ��Ắu����ʁv�̐^�ӂ�����˂Ȃ�ʁB���������炸�Ɏ�������̂ł���B
�����Ɂu���R�a����v�Ƃ�����������B�u��R���_���@���_��R�Z�@���_�I���T�@��R�`�s�m�v�Ƃ���B�܂�A���R�͔����_�̂��₶����ŁA�����_�͂��̂��ǂ����B�����Ȋ��Y�����ǂ��̉_�ɁA���������m���Ղ�����Ă���̂��A���₶����̎R���B
(�����\�N�\��)
���̎�
��t����͖{���Œʊ���l�����𐔂���B�n���̎����A���a��\��N�����\��N�ɂ����āA�����̔o��N�ӂɂ��ƁA�o�Ă����o��G���͂����炭�l�S���ܕS��Ɛ��肳��Ă���B���̂Ȃ��ō����c���Ă���̂́A��͂肻�ꂾ���̗��R�A�P�Ƀu�����h�Ƃ��Ă̌`�[�ɋ߂��̂����т�������̕K�R�̌p���܂ŁA�F�X���邩��Ȃ̂��낤�B���݂̐��͒m��ʁB
�����O�\�O�N�́w�z�g�g�M�X�x�Ŏq�K�́A����ʂ̐l���o�嗲���Ȃǐ\���́A�����͔o���҂̑������邱�ƁA�����͔o��c�̂̑������邱�ƁA�����͔o����ڂ���V���G���̑������邱�Ƃ�\�����Ɍ�B���ꂪ�o��̗����Ȃ�A�o��̗����Ƃ������Ƃ͕��w���茩�Ĉꕶ���K�̉��l���Ȃ����̂Ɍ�ƌ����Ă���B���ʂ��������ł͂���B���Ȃ݂Ɍ��l�́w�ԕS���x�����̗��N�ɓ�����B
�t�����œW�������悤�ɁA�w�t���x�͐�O���̑O�g�����X�������B�O��ɂ͎Ⴂ������o���Ă����o��G�������o����`��W�Ԃ��Ă����B�����̐V�������˂���X�������z�n�����ꂪ�A�������z�ł����Ă��������Ȃ��B�o���̑n���Ƃ͗��z�ւ̕����ɂ�����̂ł���B
�W�ςɁA���̍���e�����o�l�̏��ȁA�Z���A���e���������ׂ��B�c�����O�A�y������~�A�v���ԏt�A�勴�e���A�Ԗؕ��e�A�G�̒����ؓ����X�B���ɍ��̔o��j�̕\�ɂ͂��Ȃ����A�l��W�ƂĂȂ��̂��������A�ߗ��ɂȂ����ق���̂̔o�l�Ƃ����Ă����B�����̎��͂ɂ͂���Ȑl�B���W�܂����B
���킹�āA���l�搶�̂��̂ƁA���̌��_�ɋ߂��o�l�̖k���A�S�j�A�����A��^�A�H���Ȃǂ���X�A�I���A�l������ɉؐ��A�Ó��A�f�A�v�҂ȂǂƁA���Ɓw���l�x���I�҂̒Z����W�ς����B�w�t���x�ɓ`���{���̌n���A�o�l�̍��Ƃ������̂���������Ē��������Ǝv��������ł���B
����̎壂Ƃ́A�O��ɂ��悭���ɂ�����ł���B�������������邩��ɂ́A�B�̎Ќ��Ƃ���ɗ��܂��Ă͐ɂ����ł͂Ȃ����Ƃ����B
�O���s�̘V�l��w�̔o�啔�̍u�t�Ƃ��Ĉ˗����ꂽ�܂���A�݂������̈ӂɂ͕K�������Y��Ȃ����������m��Ȃ����A�����^���Ɏw�����Ă����B���̐l�łȂ���Ώo���Ȃ���������c�����߂ł���B
�����Ă��܂�ʊy���݁A���������̂��̂łȂ������o��Ƃ��Ă��̐��Ɏc���A����͏t�H�����҂ł��M�S�ɂ��Ώo���邱�Ƃ��������̂ł���B
(�����ܔN�O��)
�S�̕x�M
���̍��̖`���ɁA���l�搶�̋�M�A�ޗnj���F�ɍ����R�����̌܌������t���̗t���A���f����B�����R���́A���������낷�R�̏�A������ׂ̎Ж����̓�Ԃ̕������C�U���Ă̔N��������̏Z�܂��ŁA�����s�ւŐΒi��S�\�i�����ē̉ƂŖႢ���A�d�̔z�����l���̓������X�v�l���唪�Ԃ̌㉟�������ĂƂ����L�l�B�Ă����ĂࢎR�������ČÕz�q��ł���B
�����������Ŋ��Ɂw���l�x���������鎖�Ȃ������ŕ����A�Z�����{�A���l�搶��㏉�̐����ɂ��������̍ہA�����Đ�O�́w����x����w�t���x�Ƃ��čďo������B
�@�s�헂�N�ŕ��̖R��������ł������B�O�N�̕����Q�ʼnƂ������Ẳ����ɁA�搶����s�����}�����Ă��\���Ȃ��Ƃ͏o���Ȃ��B�������߂�����Ɣ��m���ƖΖؔ��f�̂����₩�ȐH���傫����ꂽ�B���̎��̢�t�������������⒃�Ё@���l��̒Z�����A�t���ɂ̒�̋��ɂȂ��Ă���B��B���̕��H�����炭�؍݂��ꂽ�B�搶�͋��ւƂ���v���Ă������̓��̕ꂪ�A����ٓ��������グ�Ȃ��ģ�ƁA�D�Ԃŋ}�ɔ����ꂽ�搶�̂��ƁA���ɋ������̂��v���o���B
�����́A�����t�����ȋZ�H�p�̃y�[�p�[����u���V�Œ��Â̓S�M���k�𐮂��āA�Â������Ō������A�Ƒ����ĔS�鍕�C���N�Ŏw�������Ȃ���A���m�����\���قǂ̗��\�������܂Ŏ��Ԃ������č������B���s����Ώd�ˍ��肷��قǎ��͋M�d�������B
��O�̓y�j��͊e����p�̖n�قƕM����������A�풆���A��Ⳃ͎�����������̗̂����g�����B�u���̐�����̗p���Ȃǂ܂ł������肵���B�����ċ��e���Ɏv���Ă���̂ł͂Ȃ����A���Ŏ���厖�ɂ���Ȃ͍��ɑ����Ă���B�t�����������ł���B��L�ɢ�o�傻�̂��̂̂₤�ȣ�ƋL���Ă��邪�A�f�p�ł����ē��e�L���ȎG���́A���������Ă���Ƃ���ł���B
�@���ƂĂ������ŁA����̖��������]�܂����B���N�\���A���N�͌\���N�Ɖ]�����ƂŐu����鎖�����邪�A���ܓ��ɃC�x���g���l���Ă͂��Ȃ��B�z�e���Ȃǂł̉X�������ł́A�S�̕x�M�͂ނ��뎸����C�����Ȃ��ł͂Ȃ��B
�@�ڂ��ڂ��G��̐@�Ђ͂�����Ƃ��ڂ��Ďg���ׂ��ł��낤�B�����A�{��G���Ȃǂ�R����S�~�ƌĂԂ̂ɂ́A�����ɂށB���������́A���̏㏭�Ȃ��Ƃ��G�̏�ɒu���A���ɏ�ɉ��ɂ�����̂ł͂Ȃ������B�̂Ă��Ȃ�����i��ۑ�����Ă������B�t�����̂���܂ł́A���F�����̈ꊪ�̏����ƐS���Ă���B
(�������N����)
�t����Z�\��
�w�t���x�̑O�g�́w����x�́A���a�\�ܔN�㌎�Ŕp�������B�ꎏ�w���l�x�́A��㔪�o�����ꎏ�ɓ�������^�т̒��A���a�\��N�l�����Ŕp������B���ǂ̈ӂ́A��펞�Ɏ����ܑ̂Ȃ��Ƃ����̂ł��낤���A����ŕ��w�����͂�m���������̂Ƃ�������B�f�ڋ�u�A�l���l����ނ��̂��Ȃ��H���ԁv�ɂ��āA�w����x���s�l�����͌x�@�ɌĂꂽ�B�}��Ɖ����邩�A�Ԉ�ւɐS�x�܂����ł͂��邪�B
�S�̎�`�̐��Ƃ͂����A�����������̎��ߖ�̂��߂Ƃ����̂ł͓���B�w�����x�i�Ð�j�w�R���ԁx�i�؍��j�w���t�x�i�쐤�j�w���߁x�i�Ӓفj�w�o�сx�i���j�w���x�i�Ӓ��j�w�ΐ��x�i�\�x�j�w���l�x�i���l�j�̓��A���s���ҏW�l�ɐ����ꂽ�،��l�́w���l�x�́A���\�̏�������̂��o��Œ��O�ɓ������ނ����B
�@�����́A�u�������ĂȂ���v�ƌ��l�̖����A���ʑ�p�̔i������Еz����w����x��֖̕@�̂܂܂ŁA�㌎�Ɂu�������l��v��݂��A���l�̑I�]��Y����o���e����K���ō���ł��̋�\�����B���A���̌`�Łw�t���x�ƂȂ�B�Đ�̌R��{�ǂ̋���v�����B
�č������[�����h��w�̃v�����Q���ɂ́A���{��̉�����Ɏ��W���ꂽ�������A���{�I������A�v�����Q���m�ɂ���Ĉꊇ�ۑ�����Ă������̂ŁA�I���̎l�N�Ԃɔ��s���ꂽ���ׂĂ̏o�ŕ��i�}���E�G���E�V���E�p���t���b�g���̑��j����������B
���a��\��N�����n���́w�t���x���A�w���l�x�≤���w�����l�x���X�A���{�G���ꖜ�O��]�^�C�g���̎����Ɋ܂܂�Ă���B���͂́A����ړI�̕����֍�����U�������i�Ƃ��āA����ɓs���̈����`�������̔r���ɂ�����B������v�͂���ɕ֏悵���B
���̐l�����͐H�ו��ɂ������ɂ��Q���Ă��āA�v�����Q���ɂŌ���O���̏o�ł͖�O�\�^�C�g���ƁA�n���ł͑����ق������A�w�ǂ���ИJ�g�W�̔��s�ŁA�n���w�Z�������A�T�˂͈�A�ʼn��p�����Ă̐��ł���B�o��͂����̕��|���ɂ������͂����B�w�t���x�̏ꍇ�́A�l�̔��s�����玩�݂ŁA�ŏ����̑̍ق����炽��������A���X�҂��Ă��ĉ����邩�痧���~�܂�Ȃ������B
�����ł́A�o����A�l��������������������i�Ƃ������ēI�|�p�ς̑��ɗ��悤�Ɍ�����B�������w�t���x�́A���܂��ɁA����́u�����`�v�̋����ł���A���\�̏�ł���o���́u�a���s���v�̓���ł���ƁA�W�Ԃ�������̂ł���B
(�����\���N�ꌎ)
���͐_�ɒʂ�
�@���F���Ȃ��ĕ��ꂻ���Ȏ��́w�ꒃ���ԓ��L�x(�M�Z���y���o�ŎЁ@�I�����v�Z��) �Ƃ������ɖ{���o�Ă����B���Z�̂Ƃ������������̂����A�قƂ�Ǔǂ`�Ղ��Ȃ��B�����炱�̎����ł��c���Ă����̂��낤�B
���t�̕��������Ă��邪�A���a��\��N�ꌎ�̑O����������A�\���̏�����������Ԃ��Ă���B�]�k�����A�{�����w���t�x�Ɠǂ܂ꂽ�肷�邪�A�G�z�̕����̂悤�Ɉꎚ�ʼn��s�̏c�����Ȃ̂ł���B�{��G���ŁA�{�����c�����ł���Ȃ���A�\����������̉������ł͌��ꂵ���B
�����ʼn��ł��̖{���Ƃ����ƁA�V�ˑ��Y�ƌĂꂽ���J�쑾�Y������O���̒����ē������܂ɁA�ꒃ�̋傪�ǂ��ƕ���������ł���B���̏ꍇ�A���R��J�ł̕����A���������ł̑��_�ł͂Ȃ������킯���B
�܂�A����̐́A��J�A�����̓�ҁA��Ɍ����ĞH�B�o��̏��l�@���B��H�B��Õ�����椂߁A�������Â�A���̎�����含����ׂ��ƁB��ҋ��ɛ��O������^椂��ċ咟ਂɎ��V���K���(��،��l)�ł���B��C�ł͂Ȃ����ł���B�C�����Ė{���߂���Ȃ���A���S�͎��ɂ��y�ԁB
�풆���͂Ђǂ����s���ŁA�w�Z�Ŏg�����ʂ́A���M�̐c�������~����Ɣj��邵�A�������ɓ��炸�A���ނ̗��ʂ�܂�Ԃ��ĒԂ��Ďg���Ă����B���܂��ɕЖʂ������܂܂̎����̂ē�v���������Ȃ��B
�풆�̏����̌��R�Ƃ����A�{�͉��x���J��Ԃ��ǂނ��̂ł��������A����̖{�́A�݂��Ɋ����ɋQ�����ܐl�݂̑���Ō܍��ɑ��������B�������A�l�����ލ����A�Ⴆ�Ώ�ɉ��ɂ��Ēu���ɂ��S�O������̂��B���ꂪ�A�����A��V���G���͔R����S�~��Ƃ��������Ɋ���ė��Ă��鎩���ɋC�Â��B
�����ӂ�Ɏg���A���Ɉ�����ꂽ�����܂ł��y���Ȃ��Ă��܂��Ă���B���Ƃ��Ƃ́A���������ɕ����������������A�����I�H���I����E���āA�����A���H�����ׂđg��ōs���Ƃ����A���������B�̎��Ƃ��琶�܂�Ă����̂ł���B���Օi�̔��e�ɓ���悤�ȓ��e�ł̓o�`��������Ƃ������̂��B
���A�w�t���x�͎���̍E�ł��甭�������B�����ɂ͐����O��ɂ̓S�M�ɂ�鞲���̕M�����U���Ă����B���сA�ꂽ�ꎚ�ꎚ���d���Ƃ��邱�Ƃ́A�������獡���܂ł��̋C�����ɕς�͂Ȃ��B
��s�̋�Ԃ����ɂ���Ŏg�����B�o����A��҂Ń����N�t���A���̕����T�C�Y�ō��ʂ����ȏK�킵�͎��Ȃ��B�����������o�����Ɉ��������B
�i�����\���N�\�ꌎ�j
�u�����ڂ��v
�m�g�j�̒��̃h���}�̂������܂����e�[�}�Ȃ́A�����قǂ̎��͂悭�������Ȃ����A�ނ�����悭�w�сA�悭�V�ף�ƕ�������Ă����̂��v���o���B
�������́A�\�͂�����̂ɓ����Ȃ��łԂ�Ԃ炵�Ă���Ӗ������A���̖��ׂ��Ӑ}�I�ł�������A�X�ɉ̂�����x������Ƃ��Ȃ�̂ł���B���̂����A���̂悤�ɁA�D���ȕ�����������Ɖj�����Ɏ���B
�~�ĐS�͉_�ƗV�Ԗ�@�@�@�@�@�@�@�@�@���l
�������̐S�V�Ԃ⋞�O��@�@�@�@�@�@�@���@
����̏t�Z�\�N����ɗV�с@�@�@�@�@�@����
��ɗV�Ԃ��ƂɌ����V�̏H�@�@�@�@�@�@��
�O��ɂ������т������ƕ��ׂČ����܂��Ƃ��������܂����Ƃ́A�����łȂ����������̂��Ƃ̈ӂł��낤�B�����ɢ�܂��ƣ��l�������œ]�����Ă����ɂȂ�A���A�^�A���A�M�͂��ߑ����̊���������Ă��āA�Ӗ��̍ő�����킩�邾�낤�B
�R�͌��ɋ��ŁA���͚ЁA�ނ����邩�ق��������Ƃ������ڂ݂ł��邩��A����������̂܂܂Ƃ������ƂȂ�A����͌��e�̐��Ƃł���B���Y�͋��ɋ��Ď����s���̂�����A�o����ɂ́A����ΐ����O��ɂ̢��������������K�v������B�����̏�ɗ����ĉR�������̂́A����͋��U�ł����āA���Y���܂�������͍ł������B�܂������ɍ݂��Ă��A���Y�ɂ�����u���v��H�܂Ȃ���A����͊䕨�ł���B�u���Ɂv�Ƃ́A�܂��u��ɗV�ԁv�Ƃ͌����̋ƂȂ̂ł���B
����Ƃ������ƂŁA�v���o�������A
�������o�傳��ǔo����ڍՊ��@�@�@�S����
�̎��厩����ǂ�ŁA�o����u�������o��v�ƌy�Ă���A���ɃR�`���Ƃ����Ƌ���ꂽ�^�������B�|��ŁA�u����ǔo���v�͌����Ȃ������̂��낤�B
�u���S�̍����V�����E���������A�q�K���ɂ���S�ɕς�͂Ȃ��v�ƁA�S���̎����͂��̂悤�Ɏn�܂�B�����āu����������o��̂��Ƃł������B����������̂��Ƃł������B�V�������ł��܂���������̂����������B�@��̋S�͂��̎w�������ڍՊ���ƌ��ԁB
��㵂Ƃ����ꂪ���邩�ǂ����A��Ɋ�㵂Ȃ����Ă͎��ȕ\�����o���ʂƂ������i�̎�����łȂ��Ɨ�������̂����m��Ȃ��B�����ɂ́A���U�����Ď��������A�������o��d������̋S�A�E�c�S��������B��������́A�S�Ƃ��ċ���ɂ��炸���āA�����ɑ����Ƃ̉��Ƒ������Ƃ���˂Ȃ�܂��B
���āA��̢���̎w�����ꣂ́A���݂������q���̂����ь��t�ł���B
(�����\��N�O��)
��嗧���̔o��
���̒��ł̂��Ƃ��A��������܂��܂ƌ���ẮA�������͂��Ƃ������Ȃ��ł���B���A�����ɁA���l���X�قƓǂ߂�ԗ����̌���������̂������B�����̊X���̂悤�����A�S�����肪�Ȃ��B������邤���ɁA�ق̎p�͐t�ɂ�鑾�����̎��ɕϗe�����B
�Ƃ���ŁA���l��\����̒ƂȂ�ƁA�������D�ɗ����Ȃ����̂��B��W�w���l���叴�x�ɂ��A�Ȃ邪�A�搶�̋�ƂƂ̂���ł���B����́A��t�D�������Α����@���l��̏�����u����邱�Ƃɂ�����B�搶�̍앗�ɑ��Ă̒�q�̂���܂ق��I�ȕӂ���o����̂��낤�B
���̔o��ɂ́A�K�������ɏՂ��ꂽ�悤�ȕ������܂߁A������Ƃ����������₤��������B�A��Ƃ����`����A�O�����Ȃǂ̊O�ɂ��A�⊮���鉽���̂������̎���ɂ͂���B���Ƃ��A�Z���ɋL���ꂽ���ƂɈ��邠���̊����ł���B��́A�����Ԃɂ�鎩�����A���������낤�B�����̑��݂����܂߂āB
�]�k�����A�ۑ������p�͂Ƃ������A��ʊӏܗp�̋�W�Ȃ�A��ň�傪�悢�B��W�̈���ɂ́A�œK�K�͂̍s��������A���傩�ŕł߂Ă���̂ŁA�ӏ܂ɂ́A���ꂪ�ǂ��呵���Ȃ����B
�����O��ɂ́A�����I����O���O�A�����̎��ɢ�����̋�͓��t��C��̂��ƂŁA��W�́A���W�͗v���A��肪������ƌ������B�S�N��̒m�Ȃ�҂��A����`�A���̎���������̂ł���B���F����V��ʼnʂ����Ȃ��������A���Ƃ��ƒZ���ɂ�������W�߂Ă̋�W���l���Ă����B�ꃖ���قǑO����A�M�ƌ����x�b�h�Ɏ����ė������ĒZ�����c�����B�u�Z���S�������ė������|�ꂽ����Ɖr���A����Ȃɏ����Ȃ������B
�Z���̋�ɂ́A����M�ՂƂ�����́i�R���v�������g�j�̍�p������B�O��ɂ͐풆�ɂ����ČÒZ���̎��W�ɓw�߂��B�Ðl�̎菑���͌Ðl�ɍł��߂��Ƒ��̂ł���B�Z���͌`�����A����ȍ�p�́A���܂��܂̏��ł�������B���ȏ�A���錎�̎G�r���A�O��̋���тȂǁA����̒��Ŕ����ȗh�ꂪ����B�����Ă���͂����g�̉��̋��e�ł͂Ȃ��B
���l�搶�̒Z��������Ɍf����̂́A���l�o��́A�ꖇ�̋�Z���A��Ȃ̋���̂������ŁA���̂𖡉����ׂ��Ƃ���̂ł���B�菑���̎��łȂ��A�����ɂȂ�A���{����āA�����Ԃ�Ɠ��������悤�Ɍ������肷��͔̂o��Ɍ���Ȃ��B�����������Ƃł͂Ȃ��B�o��̓����Ƃ��Ăł���B����Z�̂����`�̏������o��̎��A���̊낤���������܂��ʔ����B
(�����\��N�Z��)
���̔o��
��L�ŕҏW�q�����I�̑ւ��ڂ������ċ����ە����Ă���Ă���B�����O��ɂ͔ӔN�u�V�̏t��\�ꐢ�I�Ɂv�Ƃ����]���ł̈ӎ������Ă��邪�A�S�N�O�̎q�K�́A���̓��t���Ȃ�����A���������ɂ��Ă����N���ǂ����߂��Ď����Ԃ��Ȃ����܍ɐ����ꂵ����Ƃ̂ݕa��̒��ŋL���B���A���z���O���S���I��Ɉڍs���ĎO�\�N�ɂ�����ʓ����A�V���I�͐��������ɂȂ������̂ł��낤���B
�@�����s���ɓ��ɂ��̐�����������̂��A����ɕ�А����V���ɂ��_�サ��i���l�j�Ɛ����͂����B�s���̍�����v�ȑO�ɑn���́w�t���x������A���������⌻�㉼�������Ƃ����l�ׂ��A�����v���������낤�B����ɂ��Ă��A�������߂Ɏ��[���������c�t���ł́A�~�J�������x�ꂽ�牀�����e�䂳��������ւB
�@���s��������]�˕����ցA�����ւ̑J�s�A�����ܔN�̐V��{�s�Ƃ�����ɐ��ڂ��āA��܂��ȕӂł������ė��������Ă����Ύ��L���A�����A���Ԃ̎��Ԃɉ����Ă�����Ət�ďH�~�̋G��̏������������Ƃ����b���������A�f�W�^������Ƃ͂����A�h���Ԃ�������Ă�����قǖ��C�Ȃ��͂Ȃ�Ȃ����B
�@���������{�ʂɋG��̎�́A�l�G�̕��ʁA�G�̌����ژ_���q�́w�V�Ύ��L�x�i����j�́A�G��̔r��͌��ʂŁA�A�z�܍s���ɂ��G�̋�ʂ�����B�G�߂��Ƃ̑}�G�͓~�A�t�A�āA�H�A�~�ƌܖ��ɂȂ邪�A�ꌎ�̓~�́A��K���݉Ԃ�`���Ă���̂ŁA���ƂȂ��]���̐V�N�t�ďH�~�����ł���B�������A�����̂ق��ɁA�O�ȓ��̔��ӂłƋG�蕪�ލ�����t���Ă���B�P���̃A�s����邩�A�V�N�̎������邩�B
�@���l�搶�́A�o��Ɨ�@�ɂ��āu�G�̔o��ł͂Ȃ����B���̔o��ł͂Ȃ����B�����̔o��Ƃ͈�Ӂv�ƌ�����B���Ƃ́A�G�肪�܂�ł���悤�ȁA�o��̓`���I�Ȕ��ӎ��ł���B����̐l�ɒʂ��鉿�l�ςł���A�ߑ㊴�o�̃r�������Ă�̂ɐ���y���ČL������s�������͑��v���낤�B
�@�t�̌������ł́A�o����o��̖��������̈�̃W�������i�����j�Ƃ������ƂɂȂ�B�����͒Z�̕����̈����̔o��������悤�����A���A���C�����������ɒ����ł����ł͂Ȃ��B�o��̍��ۉ����A�o��̖��̍��ۉ��ł���˂A�m�ԁA�����A�q�K�����ʂ����̂łȂ���A����͕ʂ̃W�������̒Z���ł��낤�B
�l�ׂ��䂪�߂�̂͊������ł͂Ȃ��B��Ƃ�f�B�A�����グ�闲�����������B�Ђ�߂���v���t�������łȂ��A��������Ǝύ��ނ��Ƃ̈Ӌ`���v���B
(�����\��N�\��)
����Ɣo��
���C�Ȃ������̂��d�����g�p����A����Ɗ��������̐������鐢�̒��ɂȂ����B���[�v�����o�ă^�C�v���C�^�[�������A���Ȃ�����[�}���_�҂ɂ�銿�������̗���̈�͎���ꂽ�B�告�o�̎l�Җ��̊����݂����ɁA��ʓI�ɕ������ĘF�~��Ƃ����̂��Ȃ��A�������t�ɂ��A�V�сA�������o�邱�Ƃ��낤�B
�m�ԁA�����A�q�K�ɕ킢�A����r���邱�Ƃ̋������l�搶�̂��Ƃ�����A�Ȗ�w�����x�����p����āA���������̕ʂɂ������������������B������A�s���A��̌R�Ƃ��̌��͂𗘗p����҂ɂ���ċȂ���ꂽ���ꍑ���̖��A���������ƌ��ォ�ȂÂ����̂��Ƃ��S�Q����A���������C�̊����ł͂܂�ŕʐl������悤���ƌ��������̂ł���B�����A���ʔň���́w�t���x�́A���̓_�ł͌b�܂�Ă����B
����������́A���̂̂��ƂƂ��������A���Y�����҂��Ɏx�z����邱�Ƃւ̌����Ƃ����ׂ����낤�B�w���l�x�h�́A��O�̂����鑍���G�������グ���o�d�ɑ���y����A�풆�̍���ɂ��o�������ւ̋��┽���ɂ����Ď���B
�P�[�^�C�A�����\�L�����ق��������̂��낤�A�d�b�́A�����Ƃ������o�����łȂ��A�����Ƃ������o�ł�����`���邱�Ƃ��ł���悤�ɂȂ����B�����́A���h�̔��|�����炢�̕\���ʐς́A�o��̔@���ł���B������A����ɂ�������Ӗ����l�ߍ��ނ��߂ɁA���[�v���ϊ��̊������p�p�����B��܂Ƃ��Ƃł����ƁA������ɂ���������̂ł���B�����̏n��ɉ����̋L�������邾���ł��ӂ͒ʂ���炵���B���[���̕��͂��̂��̂��A�u���I�N���v�̓d�����������ϗe���Ă���͓̂��R���낤�B
���������X���ł͌����ĂȂ��A�G������������A�o�厩�̂̑����Ƃ��āA����̎g�p�́A�o��̐��藧���ɗ͂�t�^�����B����͖����Ƃ��āA��̎p�ƒ��ׂ𐮂��A�ی`�Ƃ��Ė��킢�B�ő̂ł���A�܂�͌����ł��邩��A��^���ɑ��������B
�@�������Â�ďt�邽���Ȃ�ˁ@�@�@�@���l
�@���ڂ����ɏt�̓�������Ɓ@�@�@�@�@��
�O��̉��܂́u���v�̛ߑR�`�̌��тł���B�w���l���叴�x�́u�����Ȃ�ʁv�̌�A�������Ő����Ă��������B
�ǂݕ����Ȃ��풆�̏��N���t�́A���ɂ͕��́w�����x���o���Ă��āA���̊����̐}���Ǝ��P�����߂ċ����B�P��݂Œ����̂ɓтւ�Ɏ݁A�T�J�Y�L�m�T�P���c�N�X�ɋ�������B����Ɂu�����v��t���Ďl�����̕��̋傪���锤���B
(�����\�l�N�O��)
�y���݂Ə�B
�@�����́w�����{�x�V�������̘A�ڂ����Ă��邪�A�����̐V���Ђ̗���͈�ʂւ̌[�ւƂ����`�ł���B���݂͔o��r�M�i�[�̃j�[�Y��ǂ������āA�`�V���Ђ�����o��G�����o�邻�����B�p�\�R���G���̕��͍L�������邪�A����͔o��l���̂����������̢�y���݂Ȃ����B��������V�F�A�̊l���ɗ���̂��낤�B
�����吳�̍��̐V���́A�|�p�ʂɂ܂ł��Ў�̌������F�Z���o�Ă��āA���l�͓��쐌���̕s��V��(�Ў�͋{���O��)�̕��w����p�������B�ԏt�����̉��ɂ����B�o�l�̕��͂��c��Y��ߓ��_��H��m�F�̉�Ƃ̊G���ڂ����B���̎���̔o��́A���|���p�̒��ɖ{�i�I�ɑg�݂��܂�A�o�l�͕��w�l�ł������B
�]�k�����A���`���̌��l(���e)���o��G�����s����z���Ă���B��O������������A�{���\��͖k���A���e�A�S�j�A�ٍ��ŁA�Ȃ�Ə�����̗\��ɂ͓����̉̐l�A��ƁA���ƁA��Ƃ̈ꗬ�̖���ԗ����Ă���B�Y��Ƃ͂����A�����̔o��N�̗��z��������悤���B
�@����A���l�́w���{�x�A�����́w������X�x�����������A�V����ʂ��ċ�̎t�Ƃ̉�������Ă���B����n�����͌��l�t�̎v���o�Ƃ��āA�Ɛl���A�ڂ̢�}�_���}�L��̂��ߎ���Ă����w���V��x�ŁA�����O��N���l�I�Ɏ��݂ɏo�����𑽂̂��̂�ꂽ�̂����̎n�߂Ə����Ă���B�̂��ɒ��ł��ł����I�������Ɍ�˂́w���{�o��x�̐V�X���ɋ��邱�ƂɂȂ�B
�@�f�������e���Ȃ́A�a�̎R�����|���ՊU���ŁA���̒ǐL�ɁA�F�l�̍r�؈�^���w�I��V��x�ɋ��邱�Ƃ�A�ޗǂ��V����Ƃ����V���ɂ��������I���˗�����Ă��邱�Ƃ�`���Ă���B����o�d����ɐ\���Β��߂���ɂĊ��C�R������y��y���ɐQ�ނ�邳�܂Ɍ���V��������U�����e���́A�q�K�v����̏����A�w�ԕS���x���p���ɂȂ������ŁA�o��G���̉^�c�������������̐V���o�d�̖���������B�w�s��x�̂悤�Ɏl�ł̂����̈�łw���p�Ő�߂�Ƃ����V���̓ǎґw�́A���݂Ƃ͈Ⴄ�̂ł���B
�@�V���̘b�ɂȂ��Ă��܂����悤���B���āA�Y��őI�҂ɔ����邱�����݁A�����������ɂȂ�̂��y���݂Ƃ����y���ݕ��ł́A�������A�������B�����őO��ɂ̌�^���Čf����B
�@���X�́A�����ꏭ�Ȃ���A�o��Ɉ˂��ċ~���Ă��B�o��́A�����Âł���B���Ă��Ɗy�������̂ł���B�����Âł���B����ɂ͕s�f�̐��i��v����B�o��́A���U���i�𑱂���A���U��B������̂ł���B�o��́A��X�U�y���܂��Ă���飁B
(�������N�܌�)
�o��̑傫��
�@�n�����A�́A���U����̉�Ɂ@���l�A�̒Z�����t�|�ɂ���B�w���̍��A�ŏ��̉��h��̎�l���A����l�T���̎��́A�̂����l�̎��Ƃ͈���Ă܂��i��ƌ������̂��v���o���B��O�̊��̐V���́A�����������l�̏��Ȃǂ𐳌��̕t�^�ɂ��Ă����̂ŁA���l�̖ڂɐG���@������������悤���B
���̋�̓ǂ݂́u���������A�I�q�g�O�T�̃����R�r�Ɂv�ł��邪�A�����N������S�̋�����A����������\�E�Z�C�̃K�Ɍ��l(��)�裂ƁA�����܂ł��߂Č��܂ɓǂ݉��������b������B
���̋�͔����������A���̂悤�Ɋ������g����ƁA�\�����̔o��͏\��\�l��������̂̂Ƃ��낾�낤�B�\�����C�N�I�[���o��Ƃ��āA�g�т̃��[�����A�Ⴆ��������͉����ėV�т܂�������ɒu��������ƁA���͈ꎋ�_�ő���邵�A���͈�ǂő����傫���ł���B���t�ɂ��Ĉ��͎����甪���炢�̌ꐔ�Ő��藧���Ă��邩��A��u���b�N�Ƃ��ĈӖ����e�Ղɔ]�̉��܂œ���Ղ��B
���ꂪ�o��ł���ꍇ�͂ǂ����B�u�����̉�Ɂv�͂悭����Ƃ��āA�u���U��v�����́A��ʂɂ́u��ʂ���r�Q�����߂�v�킯�����A�o��ł͂���ɔ����ŁA���̂҂��Ɣ�щz�������Ŏ������䂽�����A�o��͂�������������̏�ł���B�u���U�v�̂悤�ȁA�o��ɂ����銿��̎g�p�̂��ƂƋG��̂��ƂƁA�����ŐG��Ă������B
�o��́A�S�̂������ɔ]�̉��ɓ���ʂƂ��́A���_���ړ����Ȃ��Ă��ēǎO�ǂł���B�S�̂������Ă��āA�ēǂ͓r������ł������I�ɂ��e�Ղł���B�o��͂������̂悤�ɓǂ݉����Ă���B�ӎ������ēǂłȂ��Ă��A��ǂɂ��Ċ����x���ǂ�ł���̂ł���B���̔o��͂������������Ȏ������Ԃ����Ă���B���������^�̃����b�g�ł���A����͔o��̖{���ɂȂ����Ă���B
�}���K�G���́w���N�W�����v�x�̖k�Ĕł����s���ꂽ�������B�y�[�W���ł����w�t���x�̏\���{�͂䂤�ɂ����āA�����܃h����������A�o������ʐl�ɂ́A�w�t���x�Ɣ�ׂāA�}���K�G���قǗ����Ȃ��̂͂Ȃ��낤�B����͉��\�����̔��s�Ƃ����X�P�[�������b�g�̂����ł���B
����ł���������Ɠǂݎ��҂ɂ́A�w�t���x�͉��Ƃ��������Ȃ�B�ܓx�〈�����\�Z�y�[�W�́A�Z���I�ɕS�O�\�y�[�W�ɑ������邪�A�q�ׂ��悤�ɁA�o��I�ɂ͂���ɑ�����͂��Ȃ̂ł���B
(�����\�ܔN�ꌎ)
�o���ǂ�
�@�吳��N�n���̌��l�w���l�x�́A�O�\�N�̗�����o�Ă̑n�n�Җv��́A�p���҂̗��O�̂��ƂɁA���n�w���l�x�Ƃ��ĐV�������Ƃ����Ă悢�B���͂��̉ߒ���ʂ蔲������l�ł���B
���a��\��N�l��������ꍆ�̌��l�I�ɁA��퓗���X�u������M�̐^�������m���ׂŒނ�グ�ɂ���G�L������I���Ă���B�\�l�ł������B
���n�I�͏��a��\�l�N�\��������ŁA��l�ގj�ǂނɉΉ闈�ę{���߂��飢�Ή�܂ގw�ɂÂ��Ɩт̔�����������I�A�ȗ����n�I�ւ̓���͐�₳�Ȃ������B���̓͗��n�����ł���B���̗��O�́A���̔o��`���̏�ō������Ȃ��A�����̔o��X�^�C���͂����ނ˂����ɗR������B
�@�����n��W�w�����x(���O�O)�́A�Γc�g�����땶���L���Ă��邪�A���̒��ŁA��勫�̒�A���@�̗ތ^������ɔj�낤�Ɠw�߂Ă��錻�ꣂƂ��Ȃ�����A����ɂ��Ă��ƁA���Ö��ɓ܂�Ύ}�^�i�Ӂ@���n��̂悤�ȋ�̢�j��������́A���͂ǂ����Ă��A���悫�����̔o���z�����邱�Ƃ͂ł��Ȃ���Ƃ����ӏ����������B���̂��Ƃɂ��ďq�ׂ�B
�@�g���́A�o��͢���̏̉̂ł��苫�U���Ƃ̎���ł���Ƃ�������ł��邪�A��壂͢�̣�⢎���ƈ���āA�������ƌP���邱�Ƃ͂ł��Ȃ��B������A�o��͉̂⎍�ƈ���āA���������]���Ƃ���܂������ɂ��āA����ȂɌ��Ȃł���K�v�͂���܂��B��ɂ́A������ł���ȏ�Ɍ����ł���ꍇ�̂ق����������Ƃł���B�������̃T�C�Y�ł͂Ȃ�����A�o��́A�ڂň��S�̂��z���ɓ���Ǘ����Ă���̂ł���B
�@����A�o��́A���ł����A�i�b�c�ނ̂悤�ɏ������̒��ř��Ė��키���̂����A��������ł����A�j�������̔��e�ɂ��邩��A�o��(��^����)�����Ƃ������Ƃ̈ӎ��t���ɂ��A���̋�́A���܌����ɁA���ݗ��̃R���g���[�����Ȃ���Ă���B��������_�̕�̂����ނɖT�ώ҂���@���n��́A�����ɂ��T�ώғI�ȓ��ݗ��ŕ\�o�����傾����ǂ��A�ǂݎ�́A���̏\�������O�ݗ��ŕ�ނ悤�ɂ��Ě�������B
�v���ɁA����悤�ƍ\����Ƃ��A�����Ƃ����`�������Ɍ���Ă���炵���B���n�����������a�ⓚ�̂��d�|����ꂽ�Ƃ��̢�J�K�i�w�e�A���j�n�R�R�m���A�q�j�n�g���J����̂悤�ȋ�ł���B��}�g��ʂ��Ă��牽���ڂ��ˣ�͏\���������A����ɂ͂��������\���̓����͂��Ȃ����낤�B���̂�ǂނƂ��������ŁA�o��́A�o���ǂނƂ����\���œǂނ̂ł���B
(�����\�ܔN��)
�o��̍\��
���a�����́u���ȏ��o��Ƃ��Đ��E������v�ɂ��Ă̊w�ҁA����ҁA���Y�l�̓���������ɁA�m������̂��������ŁA�����Y�́A�펯�A���j�A�N�w�A��̌��n����A�u�đ��╺�ǂ������̐Ձ@�m�ԁv�������Ă���B
���l�搶�́A���̐������������ɂ���@������𐄂��A�q�ςƎ�ς̂�����ɂ��Њ�炸�A�[�����C�������Ȃ�����N�ɂł������ł���A�ĎO�Ďl�u���đ�햡���o�Ă����ł���Ƃ���B���̂�����͑Ó��Ȃ��̂Ƃ�����B
�����̋��ȏ��o��́A���^�吔�Ō��Ă��傫����A�q�K�A�ꒃ�A�����A�m�Ԃ̏��ł���B�ȗ߂ɁA�u����n���ʃm����A����{�m�m�����y���̓��m���V�����m�j�v�z���\���X���m�\���{�q���e�q�����[���X�����ȃe�v�|�g�X�v�Ƃ��邩��ŁA���핁�ʂƂ͂����Ȃ��o��̋����͓�������낤�B
�����̑��q�►�����́A���l���^���̌��t�̌`�Ŕo��̒��ɓ������B�w��܂�A����̂ŁA��E���ȁE�������ȂǁA�o��Ƃ����`���I�Ȍ��t�̌`��͕킵���̂ł���B�`�ɂ��邱�Ƃ����ł������B�e����q�֔o��Ȃ���̂̍��荞�݂������āA�ꂫ������o��ɂȂ����킯�ł͂Ȃ��B
�o��́A�����̑������̃W�������̉C����U���������߂ɁA���R�̂łȂ��A�o����r�ݖ��ǂނƂ����g�\�������āA�r�ݖ��ǂ�ł���B
�h�ƊĎ��r�f�I�́A��O�҂�����A�J���������Y�̘g���̉f�������A���^�C���ɗ���邾���̑��u�ł���B�Ƃ���ŁA��ʑ̂ł���l�̂ق����A�����̂͂��݂ŃJ�������ӎ����Ă��܂��ƁA�Ƃ���ɐg�\���ē��삪�������Ȃ��Ȃ�B�͔��Ԃ��H��ƂȂ�悤�ɁA�����Y�͊Ď��҂̊፷���ɕς��B�����悤�ɁA�Ԓ������̂ق����A�o��̑ΏۂƂ��Ĕo�l�Ɍ��߂���Ƃǂ��܂�����炵���B����ȋ傪�悭����B
�o�l�̊፷���ő������A�o�l�̌��t�ɒu���������A�o��Ɏd���Ă���ߒ��ŁA�o����r�ނƂ����\������ɑ�������̂�����A�\���̐c�ɂ��錴�^�ɑ������`�Ŕo�傪�o���オ��̂ł���B
���̍\���͓`���Ƃ�������܂��ċ���A���̍��g�ݐv��p���Ĕo��͌`�ƂȂ�B���Ƃ����O�q�̕����ɂ͌��^�͓��R�����̂ŁA����̗���Ƃ������͈̂���I�ɓ`���̑��ɂ���B�o��́A������łȂ��ꂩ��o�����i�ނ̂ł����āA�O�q�Ɠ`���Ƃ̒��ԓ_�Ƃ�������͂Ȃ��B
(�����\�ܔN�O��)
�o��Ƃg��������
�@�u����Ȃ��Ƃ͂Ȃ��ł����v�Ƃ����y�������ł�����s�����́A�{�X�����Y���̋��q�̗t��������B�p���w�҂ŋߏ����̖|��Ƃł���{�X�����Y(���K)���́A�펞�a�J���ŁA�悭����K�˂Ă��Ĕo���o�l��o�~�j�̘b�����Ă����̂ŁA���̐܂ɔo�d�̉\���������ڂɏƉ�����Ƃւ̕ԓ��̂悤���B�k�_�����A��㏉�߂Ă̌��l�����ᗷ�̍ہA�����L�ɁA����́u���^�͓��K������̌��C�œƐ肵���v�Ƃ���B
�@�����Ђ̒j�q���ł̍u�b�ɁA�������ł����������Ƃ�����B���͒N�����H�ו��ȊO�ɂ��Q���Ă��āA�Ƃ�킯�p�ꌗ�����ւ̓��ۂ������������A�鑠����㑺�����̉掲�������āA���{�̗ǂ����Ƃ��Ƃ��ƌ��̂�����A��Î҂̊��҂ɂ͔��������낤�B
�@��A�s�������̉p�ꋳ�����J����Ă��āA�������X�o�Ȃ������A���̎��ƂŔ������p��b�̓��e�́A���{����̂��Ƃ��i�C�`���Q�[���Ƃ����Ă��A�N�A���̖����͂��邳������̂悤�ɗD��Ȃ��̂ł͂Ȃ���A�Ƃ�������������B
�@���̒��w�p��E�Í��o�����x(���܁A������)�́A����܂ł̊O���l�ɂ��o��̊O���o��̐��_��`���Ă��Ȃ�����Ƃ���A�O���͓��{�l�̎�ɂ��˂Ȃ�ʂƂ��A�ܒ~�Ɨ]�C�������́u�Ȍ����̂��̂ł���o��̎p�����̂܂ܔ@���ɉp���Ɉځv�����B�ȒP�ɉ߂��ĊO���l�ɂ͏\���ɉ���Ȃ��Ƃ�����A�ނ炪�o���m��Ȃ�����ŁA�|��̂����ł͂Ȃ��B
�@�����Ĕo��̂悤�Ȏ��`�͐��m���w�ɂ͂Ȃ�����ƁA�g���������ƃ��[�}���ŒԂ�ꂽ���A���̂g���������Ƃ͖{���̔o����Ӗ�����B�{�����A��Ƃ��āA��p���w��U�҂��钘�҂̎�ɓK������̂��̣�������l�܋���f���Ēu���B(�p��)
�@�@�������M�s�������
�@�@���_�̕���肷�⌎�̑O
�@�@���̒��ɐQ�Ă��܂Ђ��鏬������
�@�@�ђ������̕��W�͋�������
�@�@���Ƃ�Ƃ���ؓ����ʏ�������
�@�O���ꕔ���݂��č��۔o����Ɩ��ł̂��ߍ����s�����A�O����ō�����g����������|�Ċӏ܂����̂�����ƁA���{��ɒu������ہA�o��I�Ȏv�����݂ɂ��ώ����N�����Ă���悤�ȋC������B
�@�O����o��ł���g���������́A��͂�O���ꕶ���Ŋӏ܂��ׂ����낤�B�܂�A�Ȍ��Əȗ��̓_�ł͓����ł��A���{�̔o�啶���������ʂ��̂́A�o��Ƃ͕ʂ̃W�������ɂȂ�Ƃ�����B
(�����\�Z�N�Z��)
���l���_
��^�́A���ł����R���{���[�V����(�������)�ŁA�G��`���l�Ƌ�������l�Ƃ̑g�ݍ��킹���A���炩�̕t�����l�ݏo�����ƂɂȂ�B
�Ⴆ�A�R�����q������ʐ����́w�o�����x(�ۈ�Ё@���l�Z)�́A���Ƃł���ʐ̔o��ɁA���q���o����^�������̂���e�Ƃ���B�Ƃ��낪�A�ʐ̔o��ɁA���q�����̑�\����ȂĎ^�Ɏ����Ă�������A�R���{�Ƃ��č��ЂƂʔ����Ȃ��B
���q�̎^�̋傪�A�o��Ƃ��Ċ�������Č����Ȃ����Ƃ�����B���R���̐l�����̒Z���̂��A�^�Ƃ��Ďg�����肪�悢�̂͂����炾�낤�B���̂��Ƃ�����B�������傫�ȗ��R�́A���q���A���Ɣo��Ƃ́u���ʂ̐��_��Ձv�́u�ے����v�A�܂�S�̂��ŁA������P���ŕ\�����邱�Ƃ��Ƃ���̂ƁA���l�悾�Ƃ����Ƌʐ̗���Ƃ̈�a�ɂ���悤���B
�ʐ��A���̖{�̑����Ƃ��āA�Ⴂ����Ɏt�������،��l�́w�o�斟�k�x���A�u���鎞�A���鏑���v�̌f�ڂ��u�����̒�����E���o���āA�Q�l�ɋ����v���Ƃ��Ă��邪�A�����ɂ��Ă͑S���ŁA����ł��đ����̗L�ӂ̏C����������̂ŁA�{���Ɍ��������^�����B
�W�p�Ђ́w�o�l�̏�����p�x�i�S�\�@���܌܊����j�̎����W�߂ɂ݂����X��Òj������̒ŁA�w�o��u���x�i�����K�E�X�c�P�F�ďC�@���O�j��ꊪ�Ɏ��^���ꂽ���̂ł���B�ʐ́u���鎞�A���鏑���v������ŁA�{�i�I�ɊG���w�����ɓ�����B
���l��Ƃ����������́A�E�Ɖ�Ƃ̊G��Ƌ�ʂ�����̂ł������B�т̎�Ƃ��Ȃ��̂ŁA�S�������ۂ��Ƃ��o����B�]���ɉ����ẮA�S����ł����ċZ�͏]�ł���Ƃ���n���ł���B���͐l�Ȃ�A��͐l�Ȃ肪���̑ԓx�ł���B
���l�o��́A�����I�Ȏʎ��ł͂Ȃ��A���m���l�̎��R�ϏƂ̋�ł���B��Ƌ�̕����d�����B���a�����ɂ͐����Ȃ���Ɣo�l�ɂȂ��Ă������A�����̂���Ƃ͈Ⴂ�A���������A���Ɣo�����������A�����ɛZ�т邱�Ƃ��Ȃ������B���l�o��͕��l�o��ł���B
�o��́A�Z�@�Ƃ��Ă͌��M�ł��邩��A��ނƂ��ė��|��`���A�`��I�ɂ͒N�̂��̂ł���������B���|���ł͕��}�Ƃ����Ƃ�������B�ߑ�A�[�g�ł͐\������A�����������I���o��ԓx�ɉ����ẮA���̓��e�̐[����u�l�Ȃ�v�Ƃ����O�͂Ȃ��B
����킵�����̂ɁA�����̂�����L���l�����̔o��u�[��������B�M��������̂Ń��f�B�A�ɏd��Ă��邪�A������]���Ă���̂ł͂Ȃ��B
�i�����\��N�O���j
�l�Ƌ�i���i
�É͕��̈��W�w�����ʁx(���\��)�́A�O����ɓ�����A���̋���]���W�߂āA�m�ӂɔЂ��ꂽ���̂ł���B���c�A�ޘV�t���ӂ̛����ŁA�㎿�a���ɓ�F����̘a���̋咟���(�e�،��l����)�ɁA�Ɏ��߂��щe�Ɖ撟�ƐF���̕�����Y����Ƃ����A�����n�̂��ƂŖΖ�~⾂ɂ��ҏW�Ƒ����́A��풆�Ƃ��������i�Ȉ���㓣�ʂƂ���j�z���Ă���B
�̍ق����ł͂Ȃ��A���l���A���n��L�Ƃ͍����ł���A�{���ɂ��̏������ڂ��Ă����B��L�̂ق��́A�搶�̐��M�W�ɂ��锤�ŁA�o�l���Ƃ��Ă̐l�ƂȂ肪�A����̃G�s�\�[�h�Ō���Ă���B
�u�ԁv�̑I�ҋ�܋�̂��߁A���\��]�����ꂽ�̂ɁA�u�^�钆�ɏ�������f�r���Ė���̐^��T���A�����s�R�Ƃ����ď����ɒN������ꂽ�v�É͌ՔV���j�݂ł������B�����̋��k�U����v�������������B
�@�����܂炷�R�̉Ԃ̗�@�@�@�@�@�@�@���a�l�N
�@�ʂ���݂��Ђւʂ����̉�
�@�ԎU��⒋���������C��
�@�ɂ��ĉ��R�����Ԃ���
�@�������d�̉Ԃ̏Ƃ��
���n�搶�́A�u���q�̋吶���͂��Ƃ��ƑT�ƕ��s����ꂽ�A���ӏ��̔o�T�ꖡ�ł���v�Əq�ׂ���B�u�Y�X�Ƃ��đ��Ǒō����A�H�v�ٓ��ɖv�����ׂ��v�Ƃ���ԓx�ł���B�u�V�n�̐��ɋ���A�厩�R�̐^�ɖʂ肵�Ē��ϒ�����������v���̂ł���B
�^�ʁi�܂Ƃ��j�Ƃ������t������B�l�́A��������̂悤�ɁA����̖ʂ̐l�����ɉc��ł��āA���̂ǂ�������̐l��\���Ă͂��邪�A�������Ď������̂Ƃ��āA�����ł͔o�l���ł��낤�B
��̍I�ق��ğ��ݏo���i�E��i�Ȃ���̂́A�܂��Ɂu�l�Ȃ�v�Ƃ����ق��͖����B�u���̋��m���Ė������̐l������ꂽ���Ƃ̂Ȃ��v�喴�c�̓y������~�́A���a���i��ŁA�u�x�m�R�ƕ��q�����Ă��玀�ɂ����v�Ɗo�債�ē��サ���Ƃ����B
���n�搶�́A�u����S�N�ɂ��ď����ł��悭�A�ł��������A���ł����肵���܂܂Ȃ�̐l��`�ӂ�v�̂͂��̋咟�ł͂���܂����ƌ����B�É͍����O��ڂ́u�ł����肵���܂܁v�̎p���A��̕��Ƃ́B
��ł̖��������߂Ȃ�����A�e�Ղɂ��̋��n�ɒ����ł����̂ł��낤�B���������啗�ł������B�v���ɁA����̎p�͂Ƃ������A�o����̒��ɖ{�R�̎����������A����ȋ�����o�l�������A���l�A���n�A�����ɘA�Ȃ���炪�ڎw���ׂ��Ƃ���ł���B
�i�����\��N�l���j
���l����
�@�w���l�o��W�x�i���Z�j�̌��l���̒��́u���l����v�̌�́A�u���l����v�̌�A���A���Ԃ��p�ł���B�E���J���ڂ��ŊԈႢ�Ղ����A����w�����x�ɁA���̓^�e�A�t�Z�O�̈ӁA���͏����I�Ɂc�j������B
�ՂɁA�u���l����A���v���A�u�ǂ�����A��ɂ����Ă��v�Ɠǂ݁A�u��������ґ��g���čs���ɗǂ��Ƃ���B�n���Ɋւ���������ؐ�������̌ꂾ�낤�B
�@�������O�X�܁X�����ށ@�@�@�@���l
���̌��Ћ�W�̏��ɑウ�A���̋���ȂĂ��̈ӂ������Ă���B
�u�������v�́A�܂��ɓ��l�Ƃ��Ă̌����ł���A�L�X�Ƃ�����ʂɁu�O�X�܁X�v�́A���X�Ƃ��Ă悢�B���ꂼ�ꂪ�ǂł͂Ȃ��A�Ƃ����Č����đ����g��ōs�i����킯�ł͂Ȃ��B
�@���������������X���ɂ����ẮA�����͕����Ȃ�����A�{���̔o�l�ɂƂ��ẮA�S��u���ɓs������c�삪�悢�B�����͋��̌ە��Ƃ��Ȃ蓾�悤���A����ł͔o�傪�҂��߂��悤�B�����A��Z�\��N�ɓ������w�t���x���܂��A�n���ȗ��A�u�������v�ł���A�u�O�X�܁X�Ɂv�ł���A�u���ށv�ł���B
�@�����Ȃ�O�ɁA�t�����m�̏\��������C���邱�Ƃɂ����B�ܐl�̎q���������W�܂�A�������Γ��R�o��̂��Ƃɂ��y�ԁB�����剺�̑���q�Ƃ������ƂɂȂ�킯���B���t��j�Z�́A�����ė��n�o���g�ɐ��ݍ��܂��鎞�����o�Ă��邪�A���̌�͊F�w�t���x�Ƃ����������̔т�H���Ă���B
�@���w�̐Ԃ������́A�Ԃ�����H�ׂ�����Ԃ��̂����̐^�������A�l�̂̍\���́A���z��H�ׂ��甯�������Ȃ�Ƃ������̂ł͂Ȃ��B�\����\�܂ł̂��傤�����ܐl����������킹��悭����B�Ƃ����Ă��̌`���s���̂��̂ł��Ȃ��B���ɒ����N���������ē���ւ���Ă��Ȃ���ڂɕt���Ȃ��̂��\���ł���B
�@�o����A�o��̒��Ԃ��������Ƃł���B�|���̋��̎l�l���A���̗�ł��낤�B���w���̔o�咇�ԁA�����A���L�A��`�A�́A���̌セ�ꂼ����̓����قɂ������A���L���āA�ӔN�A������ɂ����čĉ�A���U���̕��݂����ɂ����B
�@�o��̐��E�͞D��ł���B���ӂ����~���Ȃ��A���邭��炩�Ȃ��̂ł���B�^�̋��҂͂ǂ������ʂ��Ă��āA�����ɒ��ԂɂȂ��Ă��܂��B
�������A���蒇�Ԃ́A����̒��ɊF�̎p���͂�����ƔF�߂��邮�炢���悢�B�w�t���x�قǂ̋K�͂́A���݂��̋�̏������ʂ������邩�炿�傤�ǂ悢�B
�@ (�����\��N����)
�������邱��
�o����͌��t���g���̂�����A�y��삵��c����Ɏ���Ă���Č�����悤�ɂ͂䂩�Ȃ��B�V�l��w�̔o�勳���Ȃǂł́A���S�̐l�ɁA�G��Ƃ��̗��������āA�悸�͎w�܂��Č��܂�����Ă��炤�B
���̍ہA���ɂ́A�����I�ȏ�o������łȂ��Ǝ��グ�Ȃ��B���̂��炢�ł��F�Ȃ���͑��v�ł���B�ÓT�͋K�͂ł���B�Ə����߂�̂ɁA�����ڂ̑O�̈�_���ȂĂ����Ȃ�A�傫�Ȍ덷��I�ɐ����邩��ł���B
�i�q�����{�̊u�����̍L�w�u���[�V�O�i���x�ɁA�����ʂ��ڂ܂�R�̐������ȁ@�@�@�@���l
�̋傪�ڂ��Ă���B�V���[�Y�u�����тƂ̍Ύ��L�v�̍��N�͋��Z�i���Ət���j�A�����i�̉ԁj�A�m�ԁi�u�j������A���l�������ÓT�̂����ɓ���炵���B
���̋�́w���l�o��W�x�i���Z�j���ڂ�����A�\���̍�ł���B���͖͂����������A���l��̃L�[���[�h�Ƃ��������������A���N���Ȗ������������A���������������A�l�����������������l���W�߁A������`�̑ԓx���Ƃ����ƍ�҂��Љ�Ă���B
���̃y�[�W�̏Ɖe�Ƃ��Ē����̂́A�������ɗ���̍ۂɎB�������̂ŁA�搶���җ�̂��a���������̉��e�ł���B�������������Ƃ��Q�Ԑl�Ƃ��Ẵj���[�A���X�ŁA�ƌ��������B
�����A�q��͐l�Ȃ�r�����l�t���[�Y�Ƃ��Ĉ�l�������Ă��銴�����邪�A�]������A��͐l�Ȃ�A���͐l�Ȃ�A���͐l�Ȃ�Ɖ]���A�E�Ɖ�Ƃɑ��镶�l��Ƃ̌n�����Y�p�ԓx�ł���B����������Ȃ�A�I���W�i���d���̌���ւ̑R�ɂ܂Ř_�|���y�˂Ȃ�܂��B
�w�H�q���`�B�x�ɂ́A��������ɂ͕ʂɕ��@�͂Ȃ��A�u��������ǂ߂A�����̋C���㏡���āA�s���̋C�����~����B�`���w�Ԃ��͍̂�����T�܂˂Ȃ�ʁv�Ƃ���B�q��͐l�Ȃ�r�Ƃ͒E���ł���B
�M�n�ɂ͑A�e�A�s�̎O�C�����ށB�e�C�Ƃ́A�߂��ė��������Ȃ��ׂɕi�ʂ��������]���A�s�C�Ƃ́A�I�݂ɉ߂��ěZ�Ԃ�悵�E�����ʂ��]���B�u�J��e�C�������Ă��A�s�C���炵�߂Ă͂Ȃ�ʁv�Ƃ́A�u�s�Ȃ�Ƃ��͑��C�������v����ł���B
�������Ƃ��A���Ƃ��܂Ƃ��A����g�����ʼn��g�ł����X�̔o��C�x���g�����s�ł���B�قڂ����܂�̓_�҂ɂ��A���Ă̎G�o�̋��s��낵���A�s�C���X�ł͂Ȃ����B�u����̔o��A��X�Ƃ��āA�V�����ɑ��Ă��v�i���l�j�悤�ȋC������B
�i�����\��N�\�ꌎ�j
���Ƃ���
�ق��ʂ��Â���������B�܍��e�̑Ίp���̈�𔖔ŋ敪���āA�܍��̔����i���Ȃ����j���ʂ��̂ł���B�N�H�[�^�[�̋敪���B����܂ŁA�S���P�ʂ̐ߖڂ͈ӎ����Ă������肾���A�t���ʊ����S�\���Ƃ����O�N�H�[�^�[���ƁA�����������l�����ł����邱�Ƃ���A���Z�̓��ɒԂ荇���Č`�ɂ����B
�\�����̐搶�̋�̐F���A
�@�@�@���t�N
�@�o�~�̍��ɗ��ߒ��̔J�]�Z�@�@�@�@���l
�̎��͏\�l�B���̐F�������A�ʉf���̂Ōf���邱�Ƃ͂Ȃ������B�������̗�ɂȂ�������ǂ��낤�B