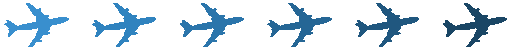懢暯梞愴憟偺擔杮偺愴摤婡夝愢
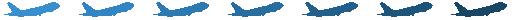
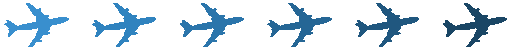
愴憟弶婜乣
奀孯
楇幃娡忋愴摤婡
晲憰丗7.7mm婡廵亊俀丄俀侽mm婡廵亊俀傗13mm亊4,20mm亊俀摍
嵟崅懍搙丗俆俁俁倠倣/倛乮俀侾宆乯
偙偺愴摤婡偑丄偁偺桳柤側乽楇愴乿偱偡丅懢暯梞愴憟彉斦丄擔杮奀孯偼偙偺愴摤婡傪奐愴偐傜廔愴傑偱巊偄懕偗傑偟偨丅愴憟彉斦丄偙偺愴摤婡偑乽嵟嫮乿
偲尵傢傟偨棟桼偼偄偔偮偐偁傝傑偡丅
嘆婡摦惈偑偲偰傕椙偄
嘇峲懕嫍棧偑挿偄
側偳偱偡丅懠偵傕偄偔偮偐偁傝傑偡偑丄偙偺俁偮偵偮偄偰夝愢偟偰偄偒傑偡丅
嘆偺婡摦惈偑椙偄偲偄偆偙偲偼丄彫夞傝偑棙偔偲偄偆偙偲偱偡丅摉帪偺嬻愴偱偼丄憡庤偺攚屻偵夞傝崬傫偱寕捘偡傞偲偄偆愴朄偑婎杮偱偟偨丅偮傑傝丄婡摦惈偑椙偄傎偳桳棙偵側傞丄偲偄偆偙偲偱偡丅
嘇偺峲懕嫍棧偑挿偄偲偄偆偺偼丄擱椏曗媼傪偣偢偵偳傟偩偗旘傋傞偐偲偄偆偙偲偱偡丅偙傟偼丄懢暯梞偱愴憟傪偡傞偵偼戝曄廳梫側偙偲偱偟偨丅側偤側傜丄懢暯梞偼奀懕偒側偺偱丄棨偺傛偆偵擱椏偑愗傟偨傜拝棨丄偲偄偆偙偲偑偱偒側偄偐傜偱偡丅塣傛偔拝悈偱偒偰傕丄嬤偔偵搰傗桭孯偑偄側偄尷傝僷僀儘僢僩偺柦偼幐傢傟偰偟傑偄傑偡丅傑偨丄峲懕嫍棧偑挿偄偆偙偲偼慜慄偵嬻曣傪弌偝側偔偰傕丄屻曽偺婎抧偐傜愴摤婡傪敪恑偝偣傜傟傑偡丅埲忋偺偙偲偐傜丄峲懕嫍棧偺挿偝偼僛儘愴偺棙揰偱偟偨丅
僨儊儕僢僩
偟偐偟丄偙偺愴摤婡偼偙傟傜偺偙偲傪桪愭偟偨偨傔丄憰峛偑敄偔側偭偰偄傑偡乮婡摦惈傪椙偔偡傞偨傔偵偼廳偄憰峛傪晅偗傜傟側偄乯丅偱偡偐傜丄懢暯梞愴憟屻敿偵偼丄暷孯偺暔検愴傗堦寕棧扙愴朄乮柤慜偺捠傝丄揋偐傜尒偊側偄偲偙傠偐傜媫崀壓偟偰堦寕傪壛偊偰棧扙偡傞愴朄丅僛儘愴偼憰峛偑敄偄偨傔丄偁傑傝抏偑摉偨傜側偔偰傕捘棊偟偰偟傑偆乯摍偱師乆偲寕捘偝傟偰偄偒傑偟偨丅
嬨嬨幃娡忋敋寕婡
晲憰丗7.7mm慜曽婡廵亊俀丄俈丏俈倣倣屻曽慁夞婡廵亊侾
嵟崅懍搙丗係俁侽km/h
偙偺敋寕婡偼丄懢暯梞愴憟彉斦偵妶桇偟傑偟偨丅偙偺婡懱偼丄敋抏傪壓傠偡偲愴摤婡暲偺婡摦惈偑敪婗偱偒傞傛偆偵側偭偰偄傑偡丅
偙偺婡懱偺尒暘偗曽偼丄乽懌乿傪尒傞偲傢偐傝傑偡丅偙偺婡懱偼丄幵椫偑奿擺幃偱偼側偔丄旘峴拞傕業弌偟偰偄傑偡丅媫崀壓拞偵丄婬偵乮杮摉偵婬偱偡偑乯懌偑攋懝偡傞偦偆偱偡丅娡偙傟偺悙朠偺偁偺僙儕僼偼丄偙傟偺偙偲偱偡丅
戝愴弶婜偺乽僙僀儘儞壂奀愴乿偱偼丄偙偺婡懱偑搳壓偟偨敋抏偺柦拞棪偑87亾偩偭偨偦偆偱偡丅憐憸偟偰傒偰偔偩偝偄丅摦偄偰偄傞揋娡偵懳偟偰丄徠弨婍傪巊偭偰姶妎偱搳壓偟偰87亾偱偡傛両丠惁偔側偄偱偡偐両丠
偙偺婡懱傕楇愴偲摨偠偔丄婡摦惈摍傪桪愭偟偨偨傔丄憰峛偑柍偔丄愴憟廔斦丄儀僥儔儞僷僀儘僢僩偑尭彮偟偰偔傞偲乽嬨嬨娀壉乿偲屇偽傟偰偄偨偦偆偱偡....
嬨幍幃娡忋峌寕婡
晲憰丗屻曽7.7mm婡廵
嵟崅懍搙丗俁俇俈km/h
偙偺婡懱偼丄悈暯敋寕丄棆寕傪偡傞偨傔偵嶌傜傟傑偟偨丅偦偺偨傔丄慜曽偵偼晲憰偑偁傝傑偣傫丅恀庫榩峌寕偱偼丄嬨嬨娡敋偲偙偺嬨幍娡峌偺摨帪峌寕偵傛傝傾儊儕僇孯傪崿棎偝偣傑偟偨丅偙偺婡懱傕婡摦惈偑椙偄偱偡丅恀庫榩峌寕偵偼丄愴娡挿栧偺朇抏傪夵憿偟偨敋抏傗嫑棆偱戝愴壥傪偁偘偨偦偆偱偡丅偟偐偟丄偙偺婡懱傕廔斦偵偼憰峛晄懌偱師乆偲寕捘偝傟偰偄偒傑偟偨丅
愴憟拞婜乣