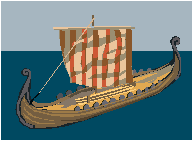富津市売津って昔はどんなところ?
当店は千葉県富津市売津にあります。
昔は相川の入り口の押出し(おんだし)で商売をしておりましたが、
昭和20年に湊川が氾濫した際、たび重なる被害に頭を痛めた先々代が
売津に求めてあった土地に住み始めたのが売津地区との御縁の始まりです。
そのため屋号は押出し(おんだし)、油や(あぶらや)です。
菜種油の油売りから始めた商いだったからです。
売津はもとは潤う津(うるうつ)だったと八雲神社の宮司さんから
教わりました。湿った土地にある津(みなと)。
妙見山が大昔に崩れて扇状地になっているため
良い水が出る場所がたくさんあり、潤沢な土地だったのでしょう。
かの徳川光圀が47歳の時に延宝2年甲寅の年に
水戸から房総勝山を経て鎌倉の祖母の墓参をし
江戸に戻った時の紀行文には天羽地区の地名や
名前の由来、名所の様子などいろいろ出ているのですが
売津については「(湊の)旅館を出づ。南の方に宇留戸川を渡る。」
と一文書いてあるだけ。湊川ではなく宇留戸川と呼ばれた時期も
あったのかなと推測されます。
また十返舎一九の「金草鞋」に
「天神山、此ところを湊村と云ふ。天神の社あり。
此あたりも押送船おほくいづるなり。
狂歌 金銀は海からあがる鯛ひらめ運は天神山のはんじょう」
とあります。これは小湊参詣の房州紀行文です。
天神様はお隣海良地区になりますが、川を使って
海運業で繁盛していたため商売の売るという字を
あてて売津になったと聞きますから、
かなり昔から船で向こう地(むこうじ)、今の神奈川へ
いろいろ運んでいたのでしょう。
薪、炭、房州石(売津石)、米などのほか
渋柿が名産で昔からの原木が一本今も不入斗の久縄に
残っているらしいですが、渋柿だけで一船出したというから
かなりのものですよね。そして向こうに着くころ
ちょうどいい加減に渋が抜けたとか・・・
ひとつ弘法大師様の逸話があります。
弘法大師様がこの地を訪ねた時、
「何か困ったことはないか」と聞かれ、
「田圃にヒルが多く困っています」と答えると
「この地のヒルよ、血を吸うな!」と一喝して下さり
その後、売津のヒルは血を吸わなくなったと。
血を吸わないヒルは絶えますから売津の田圃に
ヒルはいないと云われています。
ま、田圃にはヒルもタニシも現在はいませんが。
調べたら売津ももっといろいろなお話があるかもしれませんね。
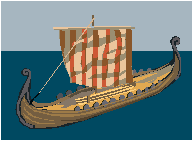
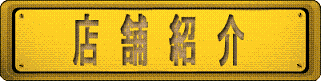 木炭・玄米・地酒のことなら(有)鳥海商店
木炭・玄米・地酒のことなら(有)鳥海商店