出典: 『道教事典』
野口鐵郎・坂出祥伸・福井文雅・山田利明 編
(平河出版社)
老子
中国上代の思想家、道家の祖、『老子』(『老子道徳経)2巻の著者。伝記は史記に見えるが、悉く漢代人の 虚構であって実像とは殆ど関係がない。老子とは、本来老先生を意味する匿名であったと考えられることからすると、その経歴は永遠の謎といえよ う。ただ『老子』18章に<大道廃れて仁義有り>と見えることから推して、その書が孟子(前4世紀後半)以降の作であることは確 かである。なお後世に成立した道教では、その教祖とされ、太上老君等の尊称を与えられている。
【老子の実像】
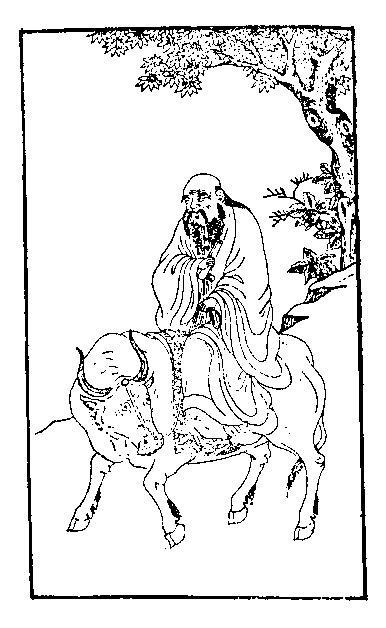
老子の実像は著書とされる『老子』に拠って求める以外にないが、固有名詞を全く含まない同書にそれを期 待することも、また困難である。『老子』の内容から推すと、著者の本質は、戦国の世相を睨む批評家たるにあり、社会の一隅にあって富国強兵に 狂奔する世の君主を戒め、行き過ぎた人知文明の弊害を憂い、乱世に処する生き方を説いた人である。老子とは老先生を意昧する普通名詞であっ て、世に名を著すことを好まなかった著者の匿名であったらしい。匿名の老子は複数であった可能性もある。ともあれその言論がまとめられて一冊 の『老子』となったのは前3世紀前半の頃と思われるが、万端の事象を包括的・根源的にとらえようとする道の思想、特有の逆説的論法などによっ てたちまちに流行し、戦国末の思想界に大きな影響をもたらした。一方、改めて匿名老子の正体が問われることともなり、その伝説がさまざまにつ くられるようになった。例えば老耼の名は、『礼記』曾子問篇で孔子に喪礼を教えたとされる老耼を即ち老子であると解したことに始まり、かの孔 老会見(孔子問礼)の伝説はこれから生じているらしい。老子を始祖とする道家の系譜は漢代に入って作られたものであるが(先秦の世には道家と 称する学派のまとまりはなかった)、『史記』の老子伝は、その始祖老子に相応しく、虚構された伝説の集成である。
【老子の伝説】
『史記』老子伝は次のようにいう。
①楚の苦県(河南省鹿邑県)の人。姓は李、名は耳、字は耼。周(東周)の守蔵室の史(一説に柱下の吏)。
②若き日の孔子が周都洛陽に遊学したおり、老子を訪れて礼の故実を問うたが、老子はそれには答えず、孔子 の気負いと思い上がりを戒めた(孔子世家をも参照)。
③老子は道と徳を修め、名声を上げないことを信条としていた。周に仕えること久しきに及んだが、その衰運 を見定めて周朝を去った。
④某関所(河南・陜西省境の函谷関、或いは陜西省西端の関所)にさしかかると、老子の正体を見抜いた関令 (関守)の尹喜が、隠退の前に教訓を書き残すように要請する。そこで老子は道と徳とに関する上下2篇5000余宇の書(すなわち『老子』)を 著して与えた。
⑤かくて老子は関所を後にするが、その後彼の消息を知る者はいない。
⑥孔子と同じ頃に老莱子とよぶ隠者がおり、また孔子より180年後に太史儋なる予言者がいたが、世間には この2人を老子と見る説がある。
⑦老子は道を修めて寿を養ったおかげで、160歳~200余歳の長寿を保った。
⑧老子の子孫は連綿と続いて漢初に及ぶが、数えて8代目の解は膠西王(前153没)の太傅であった。
以上のうち、まず①は郷貫・姓字・官職に関する記事であるが、いずれも先秦の書には見えない。②は『荘 子』諸篇に頻出し、漢代に流行していた孔老会見講を鵜呑みにしたまでのことであり、④の関令尹喜をめぐる『老子』伝授の物語は、『荘子』等に 見える道家思想家の関尹が、同時に関所の長官をも意昧することから生じたものと思われる。何よりも問題は、①から⑤に至るまでで老子即ち李耳 の伝記として完結するかに見えながら、⑥では老子に擬せられる別の人物を挙げたり、⑤で出関の後消息を断ったと述べながら⑦では200余歳と いう寿齢を記し、⑧では八代にわたる子孫の系譜を記す、というようにその叙述に混乱の見えることである。しかし後世になると、上記の老子伝は 『史記』の権威によって、殆どそのまま老子の実録と考えられるようになった。『史記』老子伝を疑うことは、わずかに清朝考証学者に見えるが、 本格的には近年に入ってからのことである。そればかりでなく、その伝記はさらに拡大解釈されて発展を遂げていく。例えば前漢末のころ老子は神 仙化するが、それには主として⑦の記事が関連しており、後漢末に生じたと思われる老子化胡説は⑤の出関伝説に由来する、というようである。道 教における神としての老子には、太上老君・玄元皇帝・混元皇帝等の尊称があり、それに相応しい神怪な伝説が付会されている。しかし、その場合 でも常に『史記』の所説が基本となっていることに注意すべきであろう。なお道教における老子伝としては、『混元聖紀』(道蔵:洞神部譜録類 551~553)『猶寵伝』(同上555)等がある。
執筆者:楠山春樹