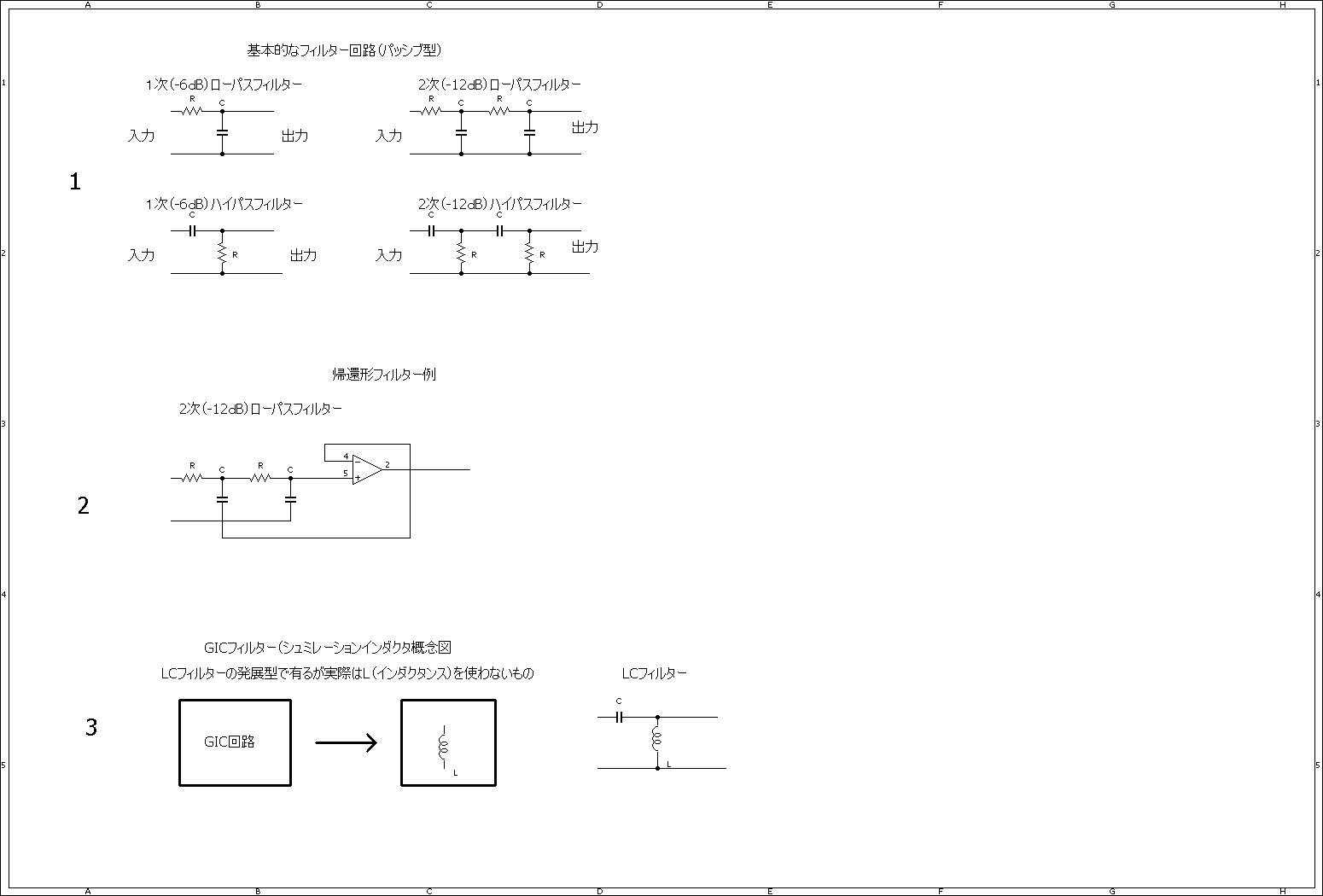
はじめに
チャンネルデバイダーのフィルター回路方式は古く(昭和40年代)からたびたび論争を引き起こして来ました。雑誌などではカリスマ性を持ったライターが○○式と称して結局のところ次数の少ない-6dBに軍杯を上げて来ました。それらは当時の技術としては段数が少ないので、音質劣化が少なかっただけではないのかと思われます。それと、また多くのオーディオメーカーもチャンネルデバイダーでは、クロス周波数が簡単ににスイッチで切替出来るようにCR型や帰還形を採用してきました。現在に至っては、その多くは接点の劣化、部品の劣化で測定してみると初期の性能から大きくずれているのも事実です。(30年以上たてば当たり前ですが)実際にその時代の、電話や通信回線のフィルター(テレタイプやFAX)では急峻な特性の高精度LCフィルターが使われてきました。スピーカーのネットワークもLCフィルターです。最近わかったことですが、マルチアンプやチャンネルデバイダーの役割を全く理解していない人も、少なくはありません。低次(-6dB)のCRフィルターが音が良いと言うので、話を良く聞くと中音域を6dBオクターブと12dBオクターブでは減衰量が違うので当然耳で聴けば低域高域まで伸びているでしょう。言い方を替えれば減衰していないフィルターという話です本当に低次なお話でした。スピーカーに内蔵されているネットワークは-12dB型が多いです。なぜチャンデバでは-6dBの緩やかな特性で良いのでしょう。おかしな理屈が通ります。周波数の分割ですから分割後は耳で聞いて音質判断はその帯域のみでは難しくなります。全体域空間で合成されたときにはじめてフルレンジの耳で聞いて音質の良否が分かるようになります。チャンデバは、複雑なので音が悪いと決めつける方もいます。音質を劣化させないために複雑になることも必要なのです。
図1 基本的なCR型パッシブフィルターと呼ばれるものです。
抵抗、コンデンサーだけの簡単な構成です。一応これでフィルターの役割は果たします。ただし入力出力に何がつながれるか分からない、レベル調整をするボリュームがつながるでは、思うような特性が得られません。
パッシブ型で2次のバンドパスフィルターを構成するには2段重ねますが、これも実用的には思うような特性が得られにくくなります。
ちなみにパッシブ型で2次(-12dB)のバンドパスフィルターを構成した場合、ローパスとハイパスが直列になり4段のCRの繰り返しになることがお分かりいただけると思います。もちろんパッシブ型ですから、次段の影響は避けられません。そこで段間に緩衝増幅回路を入れて実用的にしたのがCR型フィルターのチャンネルデバイダーになります。ここでもう賢明なオーディオ諸兄の方々は、お気づきのことと思いますが、いくら音質の良い抵抗、コンデンサー、増幅回路を使っても何段もCR素子、増幅回路を通過しては、著しい音質低下があります。さらに周波数切替スイッチの接点が入ればその分の音質の低下と雑音の発生は免れません。
図2 帰還形フィルター(セ(サ)イレン・キー型)
セイレンとキーによって発明された回路で真空管の時代(昭和30年)から現代まで使用されている回路です。この回路は真空管3本程度必要でしたが、IC化(オペアンプによって広く使われるようになったと言えます。長らく高級高性能チャンデバと言えばこの回路でした。ただしこの回路でも、CRの繰り返し、帰還アンプ、緩衝アンプの繰り返しで音質は劣化していました。
図3 GIC型
Lをシュミレーションするもので、(等価的にはLの性質を持つ回路)簡単にいえばLCフィルターになります。前述の通りLCフィルターは優秀ですが大きなコイルが必要となりました。GIC型は、通過帯域では、増幅回路を通らないフィルターとして大変音質的に有利なものとなります。ただし回路が複雑なのと計算がむずかしい(正規化素子表からは比較的容易)のと、低次のフィルターでは不経済な欠点があります。もともと脚光を浴びたのがCD誕生時の連立チェビシェフ型の9次〜11次の出力スムージング用としてでした。しかしこれもデジタルフィルターの出現で低次のフィルターで良くなり簡素化された経緯があります。またGICのバタワース減衰特性では雑音レベルまで跳ね返りなく減衰するのも大きな特徴です。GICフィルターのチャンデバは、デジタルチャンデバが出ると同じ頃にA社が発表していることはご存じとは思いますが、今でもそのチャンネルデバイダーが中古市場に出ると破格の値段で取引されています。(特にフィルター多数付属の場合)このことからも音質上有意で或ることは実証されると思います。
その他の方式(ステートバリアブル型)
一時期連続でクロス周波数を可変出来るステートバリアブル型のフィルターを応用した安価なPA用チャンデバが、海外各社から発売されていたことがありました。最近では雑誌の付録で付いたものがあります。固定抵抗で周波数切替ならまだしも、2連ボリュームで変えるものなので周波数精度は大体です。低価格、自由なクロスオーバーと利点はあるのですが、音楽再生オーディオに向いているかは、ご自分で判断といったところです。
まとめ
GIC方式は、他のフィルター回路と音質比較し、実際多くの音楽ファン、オーディオ愛好家が実感し、導入しています。特に言いたいことは、マルチアンプを何十年もやってきて中々思うように行かなかった方々が、簡単に成功しています。中には高級デジタルチャンデバからこのアナログGICチャンデバに替えた方までいます。回路の集積化が進み、演算器で処理するデジタル方式のデジタルチャンデバもありますが、アナログ式には特有の音質があります。現実的に超高級プリアンプでさえアナログ方式に戻っています。このように優秀なGICアナログフィルターですが、その性能を引き出すには部品実装、配置にアナログのノウハウが必要です。簡単に回路どうり作っても上手く動作しないのがアナログの醍醐味ですが、相当の部品点数で測定環境がないと容易でないため動作試験済み、部品実装済み基板でも提供しています。フィルターに関しては、測定は不可欠です。自作でチャンネルデバイダーは、簡単ではありません。特にパッシブ型はいくら高精度のCRを用いても前段後段の影響を受けます。-6dBオクターブというのはたとえば1KHzクロスだと500Hzで-6dbですからパワーにすると500Hzで半分にしかならないわけです。それでは試聴するまでもなく、音質も濁ることがお分かりいただけると思います。ユニットに再生対域外の入力があるわけです。スピーカーは再生帯域外は、暴れが多いのは、特性表を見れば誰でもわかります。ここにわざわざその帯域の音を入れ悪くしていることにも気が付かないのは悲しいことです。マルチの要はフィルターです。余計な周波数ははきちんと切って空間で合成されたとき初めてその音質再現性がわかります。
その他
なぜGICフィルターは、チャンデバであまり採用されないか疑問に思った方も多いと思います。それはコンデンサーの値の相対偏差を小さく抑えるために、必ず部品選別が必要です。それが大変手間がかかります。抵抗は、高精度のものが比較的容易に入手出来るので問題はありません。1%級以下のコンデンサーを入手出来ない場合選別は不可欠です。そうしないとリップルの多いフィルターになってしまいます。それでも当工房が作り続けているのは、それなりにマルチをやる人が増えているからです。一度、二度失敗した方が成功していますオーディオ機器の中で、最も売れないチャンデバに、こんな面倒なことをする大手メーカー、中小メーカーはありません。今は残念なことに大手メーカーしか出来ないデジタル方式の独壇場となっています。ですから可能な限りアナログチャンデバを作り続けます。
私がこのフィルターをなぜ製作することができるかと思われる方もいるでしょう。それは、精密な連立フィルターの製造現場にいたからです。当時はコンデンサーを選別し、グループ分けし、セラミック基板に印刷した抵抗体をレーザートリミングして、定数合わせをしていました。超精密な容量のコンデンサーは製造できないので、ばらつきの分布で一度コンデンサーをグループ分けして、それに合わせた抵抗を作るということをします。そうしないと無駄なコンデンサーが
大量発生する訳です。ですからGICフィルターは不経済な設計を強いられるのです。こういった実情を理解できない人が性能を無視して、複雑な面のみデメリットとしてネガティブキャンペーンを繰り広げます。
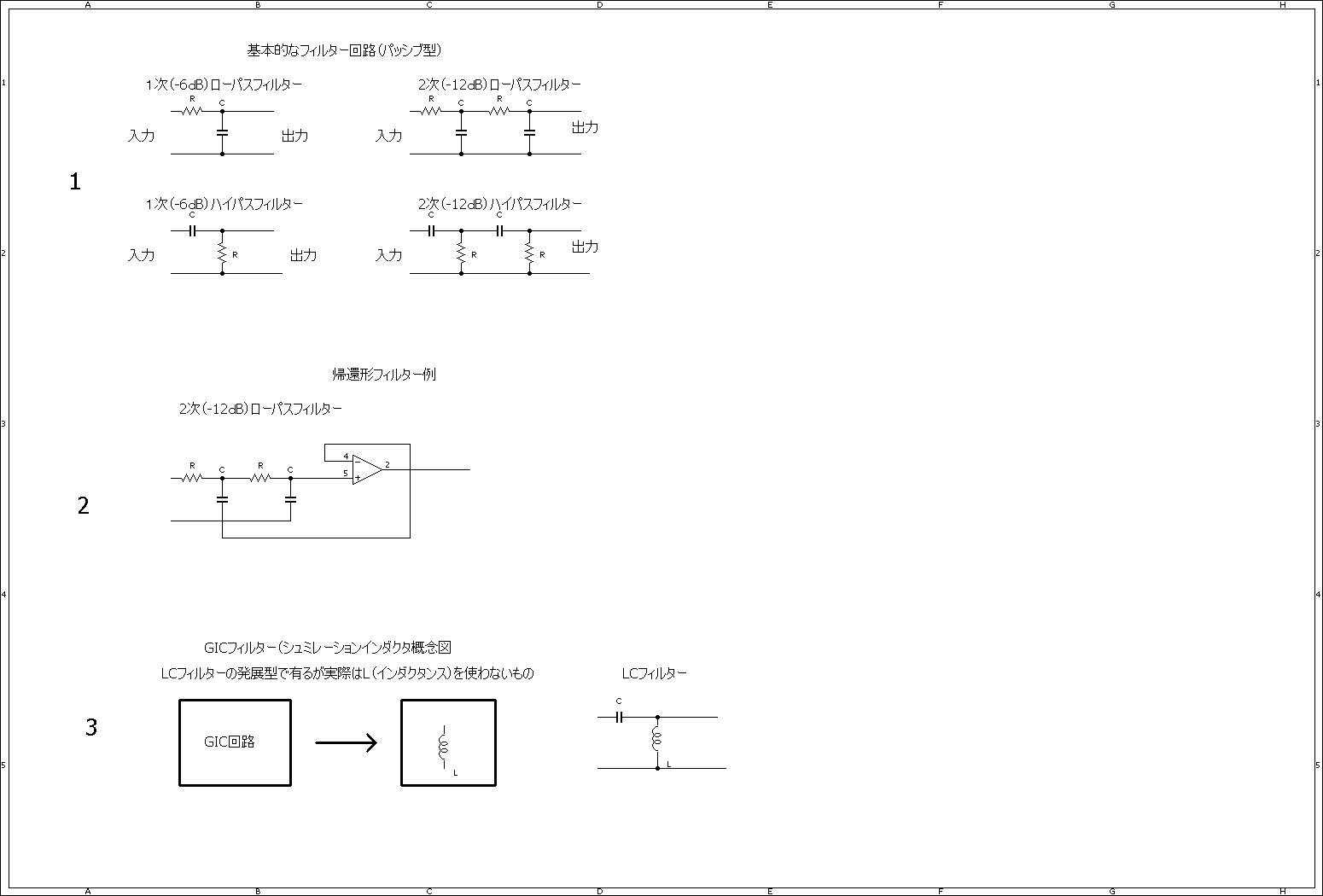
| フィルターの試験は測定器がないと不可能。超能力でもないと出来ない。 しかし耳で調整出来ると言い張る人は少なくない。 耳で聞いてオクターブ下または上の減衰量が分かりますか? 例1KHzの半分が1オクターブ下ですから500Hzで-18dB減衰することの確認ができますか? はっきり言って無理です。 最低限発振器とオシロスコープ、2針式のレベル計が必要。 2針式のレベル計はクロスポイントを確認するのに必要だ。オシロスコープで 波形の高さが同じになるポイントでも良いが針のアナログメーターは見やすい。 ついでにデジタルのほうが見やすいのは、マルチメーターと周波数表示のカウンターである。 写真は2ウェイ基板の試験風景 |
|
| フィルターの事前動作試験が出来るのも冶具があってのこと。 完成品での動作試験は意外に面倒なもの。 |
|
| 2ウェイ〜4ウェイ対応機製作例 | |
| 2ウェイ機組立て例 | |