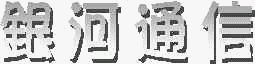 |
30号 2000年3月
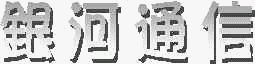 |
|
|
|
|
「叢書列伝」はその名の通り、翻訳SFシリーズを巡る解説&ウラ話なんだけど、考えてみれば、海外SFの安定した供給源としては、いまじゃハヤカワ文庫SFと創元SF文庫の両老舗ぐらいなもの。あとは各社文庫から、まるで編集者が会社をダマしたかのように(笑)たまに出るのを待つばかり。いやもちろん、ハードカバーの早川書房〈海外SFノヴェルズ〉は出版され続けているし、アスキー/アスペクトやソニー・マガジンズなど、意欲を見せる出版社も存在する。が、残念なことに、今のところそれらはあくまで単発に過ぎない。〈海外SFノヴェルズ〉だって統一装幀をやめてから、シリーズとしての意味合いは弱い。
しかし『スター・ウォーズ』フィーバーに象徴される、“SFブーム”に沸き立った1970年代後半~80年代前半は、数々のSF叢書が妍を競う群雄割拠の時代であった!
その、時代を彩ったSF叢書を追ったのが、第1章「空想科学小説叢書列伝」であり、世界の翻訳SFを順に紹介したのが、第2章「バベルの塔から世界を眺めて」である。こちらは“英米以外の翻訳SF”というコンセプトで、古くは明治元年(1868年)に訳されたジヲス・コリデス『新未来記』や、明治16年(1883年)のアルベール・ロビダー『第二十世紀未来誌』から始まり(古すぎるっちゅうねん!笑)、時間軸も縦横に多彩な作品を取り上げている労作。
特筆すべきは、ジュヴナイルにも目配りが行き届いていること。正直な話、これが無けりゃ本書の魅力は半減だ、とさえ思えるほどである。言うなれば、過去に例を見ない、画期的な本なのであ~る。
それだけに、リストや索引が装備されていないことは、惜しんでも惜しんでも惜しみ切れない位、実に残念で惜しいことである(しつこい)。だって、いざ“使う”段になったら、該当ページを探さなくちゃいけなくて不便なんだよね。ともあれ、SF求めて古本の大海原にまで乗り出す/出した諸氏にとって、必携の羅針盤となろう。
お次は『思考する物語』(森下一仁著、キイ・ライブラリー、東京創元社2000年)の登場だ。めるへんめーかーの表紙にダマされてはいけない。〈SFマガジン〉連載時(1995年5月号~1997年1月号)の、吾妻ひでおのイラストにもだ。
ジャンルを語ることが困難なこの時代に、森下一仁は「SF」に真っ向から勝負を挑む。あるいは不器用と言い換えてもいいその姿勢に、ぼくは驚きと喜びと、ある種の目眩を感じる。このSF論は骨太だ。
本書における一貫した探求テーマは、「SFとはなにか?」という根源的な命題である。繰り広げられる作業は、気の遠くなるようなものだ。「センス・オブ・ワンダー」の考察からスタートすると聞けば、頷いて戴けるだろう。
これまでのSF論は、程度の差こそあれ、論旨に見合わない作品に目をつぶってしまうことで、理論の整合性を補強してきた点があったと思う。『乱れ殺法SF控‐SFという暴力‐』(水鏡子著、青心社文庫SFシリーズ1991年)に共感したのは、それらの矛盾を「いいかげんさ」に託し、全てを許容してみせた所が新鮮だったから。しかし森下一仁は、それらをひとつひとつ丹念に掬い出し、多数の引用を織り交ぜ検証する。ここが目眩の源だ。その生真面目さは、執筆の動機が、なにより「自らを納得させるSF論をまとめよう」という、妥協の許されない目的にあったからではないかと思われる。
その分、理論のアクロバティックな斬新さとは、若干の距離がある。「ワイドスクリーン・バロックこそ、十億年の宴のクライマックスだ」とか、「SFの上にSFが築かれる」や「探求すべきは内宇宙だ」といった、派手なアジテーションは存在しないからである。そこにあるのは、「SFとはセンス・オブ・ワンダーの文学である」という確信であり、長年の疑問に答えるための地道な歩みなのだ。
「一SFファンとしては、距離をおいて波(註.ニュー・ウェーヴ)が通り過ぎるのを観測している、という立場もあっただろう。だが、私の場合、運の悪い(?)ことに、すぐそばにニュー・ウェーヴに巻き込まれて(飛び込んで?)悪戦苦闘している人がいた。学生時代、毎週のようにその人と会い、話をするという生活をしていると、いやでも自分の身と引き比べざるを得ない。SFが生き方であることを、身をもって教えられたわけだ(その人――伊藤典夫は、当時からの課題であったサミュエル・R・ディレイニーの『アインシュタイン交点』を二十数年かけて翻訳した)。/おそらくそれが決定的影響となった。」(235ページ)
森下一仁は、作家的資質と評論家的資質を併せ持つ才能である。連載と同時進行した社会情勢(オウム事件)をヴィヴィッドに反映しつつ、〝評論家″森下一仁により結実昇華されたSF観の集大成が、『思考する物語』として目の前にある。その活動に、完成は無いかもしれない。でも読者は知っている。森下一仁が第2期〈奇想天外〉1979年6月号(39号)以来、20年以上に渡る最長不倒レビュアーであり、SFへの静かなる情熱が限りなくアツイことを…。圧倒的蓄積による超ド級書評集、『現代SF最前線』(双葉社1998年)でさえ捉えきれない未踏の歩みを進める著者は、これからもSFに正面から向き合い続けると信頼させる。
胸に迫るSFへの真摯な姿勢、継続する行動力において、森下一仁もまた「SFが生き方である」ことを、身をもって教えているに違いない。そしてぼくは、思わず自分の身と引き比べて…、アァ!
しかし不思議でならないのは、ナゼ早川書房は自社で単行本化しないんだろ?ということだ。『SF万国博覧会』は、北原さんの本が過去に青弓社から出ていた関係ってコトで、何とか分かる。評論の器もキイ・ライブラリーしか無いしな。いやそれにしたって…と思っていた矢先、やっぱり〈SFマガジン〉に連載された科学エッセイ『われ思うゆえに思考実験あり』(橋元淳一郎著)が、早川書房から単行本化されたので驚いた。さらに続けて、唐沢俊一の『とても変なまんが』も出るじゃない。
ならばナゼ手放した、早川書房よ!とでも言っておきたいところだけど、ここはむしろ、連載のみで埋もれてしまいかねない作品を、他社からこうやって見出すシステムと余裕が、今のSF界に出てきた事実を噛み締めるべきであろう。
あとがき 日頃の遊びすぎがたたって、ださこん3には参加できなくなってしまいました。とほほ。でもSFセミナーは行くぞ!(コンベンションを渡り歩く母>おい) (安田ママ) |