 |
俁係崋丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂俀侽侽侽擭俈寧
丂
 |
丂
|
丂
|
丂
|
丂
|
 |
丂僯儏乕僂僃乕償偵娭偟偰側傜丄乹婫姧俶倂乚俽俥乺偺庩偵弶婜僫儞僶乕偼丄婎杮拞偺僉儂儞偺婎慴帒椏偲尵偭偰偄偄偩傠偆丅偆乕傓丄乹埆杺塣摦乺擖庤埲慜偵偼撉傫偩偼偢偱傕丄傏偔偺傾儞僥僫偠傖偪偭偲傕堷偭偐偐傜側偐偭偨偪傘偆偙偲偱偡偐偄丠 婣戭屻丄憗懍戞俀崋傪傔偔傞丅偳偙偩丄偳偙偩!? 偍偍偭丄偙傟偩18儁乕僕丅偦偺侾儁乕僕偺僐儔儉乽俶倂丒俶倂丒俶倂乿偵丄傏偔偺媮傔偨慡偰偑偁偭偨丅
丂乽10擭嬤偔傕愄偺62擭偵丄偡偱偵俽俥傪乽僗儁僉儏儗僀僥傿償丒僼傿僋僔儑儞乿偲峫偊傛偆偲偡傞榑暥傪敪昞偟偰偄偨恖偑偄傞丅挌搙僶儔乕僪偺乽撪塅拡傊偺摴偼偳傟偐乿偲摨偠擭偱偁傞丅乛乽埆杺塣摦乿偲偄偆儕僩儖儅僈僕儞偵敪昞偝傟偨乽俽俥榑彉乿偑偦傟偱丄挊幰偼彫杧麊惗偲偄偆恖偱偁傞丅乿
丂乽傓傠傫丄僗儁僉儏儗僀僥傿償丒僼傿僋僔儑儞偲偄偆梡岅偑敪柧偝傟偨偺偼僴僀儞儔僀儞偵傛偭偰偱偁傞偑丄偦傟偑尰嵼偺乽僯儏乕僂僃乕償乿偺傛偆側嶌昳偲側偭偰搊応偟偨偺偼僶儔乕僪偵傛偭偰偱偁傞丅偟偐偟僶儔乕僪偲摨帪偵擔杮偵墬偄偰丄摨偠傛偆側堄枴偱俽俥傪僗儁僉儏儗僀僥傿償丒僼傿僋僔儑儞偲峫偊偨偄偲偄偭偰偄偨偺偼丄堦偮偺敪尒乿
丂偁偁乣乮椳乯丄偮傑傝僫儞偱偡偐丄傏偔偼巐敿悽婭傇傝偵摨偠乽敪尒乿傪丄嬌傔偰屄恖揑偵偟偨偩偗側偺偹丅偟偐傕徯夘偺暥柆傑偱嬤偄婥偑偡傞偟丄乹埆杺塣摦乺偐傜偺堷梡傕摨偠売強偩偟乮徫乯丅婥傪庢傝捈偟偰懕偗傛偆丅乽偝偰丄偙偺彫杧麊惗偲偄偆帹姷傟側偄柤偺挊幰偼扤偐丠乿乽憑偟偁偰偨偲偙傠丄戝媣曐偦傝傗巵偺傕偆堦偮偺儁儞僱乕儉偱偁傞偙偲偑敾偭偨丅乿偭偰丄戝媣曐偦傝傗偱偡偐乣乣!!
丂俽俥奅偵娭傢傝偁傞恖暔偑晜偐傃忋偑偭偨偺偱媡偵嬃偄偨偗偳丄奆偝傫偼偳偆丠 偲傝偁偊偢乽傎傫偲傂傒偮乿偱偼丄嶰懞旤堖偝傫傎偐悢恖偺曽乮偩偗乯偼斀墳偑偁偭偨偺偱堦埨怱丅屻偱乹埆杺塣摦乺戞俀崋傪尒捈偟偨傜丄偍偍偔傏偦傝傗柤媊偱乽僂僣僣偐傜僒僔僟僔傊乿偲偄偆偺傕宖嵹偝傟偰傞偠傖傫丅
丂偟偐偟妋偐偵丄尵傢傟偰傒傞偲壗偐傜壗傑偱摉偰偼傑傞丅暥復偑偊傜偔撉傒偵偔偄強偑摿偵乮徫乯丅儂儞僩尵偆偲乽俽俥榑彉乿偵偼丄堷梡偲偄偆敳偒彂偒偺忬懺偱乬巊偊傞乭暥柆偼丄傏偔偑乮偦偟偰乹婫姧俶倂乚俽俥乺偑乯巊梡偟偨売強埲奜偵尒摉偨傜側偄丅堷梡偑廳暋偡傞偺偼傓偟傠昁慠偱偁傞偺偩丅
丂乽師崋偱偼摉慠偙偺乽俶倂乚俽俥乿偺愭嬱幰偵搊応婅偆偮傕傝偱偁傞偑丄摉恖偺搒崌偝偊偮偗偽丄偍偦傜偔巵偺擄夝側暥偵愙偡傞偙偲偑偱偒傞偙偲偲巚偆丅偲傕偐偔丄偙偙偱偼傂偲愄慜偺巵偺僄僢僙僀偵宧堄傪昞偟偰偍偒偨偄丅乿偲乽俶倂丒俶倂丒俶倂乿傪寢傫偱偄傞捠傝丄戝媣曐偦傝傗偼戞俁崋乮1971擭俁寧乯偵乽嫟嶻庡媊揑俽俥榑乹忋乺乿傪堷偭採偘丄俽俥奅傊僇儉僶僢僋傪壥偨偡丅儎儖側両
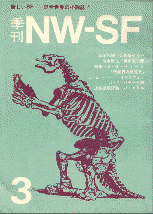 |
丂偟偐傜偽摉慠丄戞係崋乮71擭俉寧乯偑拞偐壓偵側傞偼偢偐偲巚偊偽丄偝偵偁傜偢丅乽楢嵹昡榑戞俀夞乿偲柫懪偨傟丄屻婰偵偰乽師崋戞俁夞偱廔椆梊掕偺丄戝媣曐偦傝傗巵乽嫟嶻庡媊揑俽俥榑乿偼丄梊掕傪曄峏偟偰挿婜楢嵹偵側傝傑偟偨丅乿偲偄偆曬崘偑側偝傟傞丅偦偙偱偼摨帪偵丄乽巹乮曇廤恖嵅摗徃乯偑巵傪朘偹偨帪丄俽俥偵墬偄偰偦偺巚曎偺曽朄偑栤戣偱偁傞丄偲偄偆傛偆側偙偲傪尵偭偰偍傜傟傑偟偨偑丄偙偺昡榑偼丄摉慠崱傑偱偺俽俥奅偵偼柍偄丄巵撈摿偺尩枾偝傪傕偭偨俽俥榑偱偁傝丄偝傜偵巵偺堦楢偺寍弍榑偺廤戝惉偲偱傕偄偆傋偒傕偺偵側傝偦偆偱偡丅乿偲傕晅婰偝傟丄挊幰丒曇廤晹憃曽偺巚傢偔偺堦抂偑巉傢傟傞丅
丂偙傟偑傑偨丄挿婜傕挿婜偺戝楢嵹傊敪揥偡傞偙偲偵側傞偺偩丅戞俋夞乮74擭俋寧乯宖嵹偺楢嵹戞俈夞枛旜偵偼丄乽崱夞偵偰彉榑偑廔傝丄師崋偐傜偼偄傛偄傛杮榑偵擖傝傑偡丅屼婜懸壓偝偄丅乮曇廤晹乯乿側傫偧偲偄偆徴寕偺捛婰乮徫乯傪敪尒偟偨傝丄戞16崋乮80擭俋寧乯宖嵹偺楢嵹戞14夞偐傜偼丄怴偨偵乽乗備偐偘丒傓偮傠傑乿偲偄偆暦偒姷傟側偄暃戣乮俁抜慻侾儁乕僕偺乽暃戣偵偮偄偰乿偁傝乯偑壛傢偭偨傝丄慡偔廂懇偡傞婥攝偑側偄丅偦偟偰偮偄偵丄乹婫姧俶倂乚俽俥乺偺媥姧戞18崋乮82擭12寧乯傑偱堦搙傕搑愗傟傞偙偲側偔丄11擭埲忋偵搉傞16夞偺楢嵹傪懕偗丄側偍枹姰偺傑傑偱偁傞丅仸拹丄婛偵偍婥晅偒偐偲巚偆偑丄乹婫姧俶倂乚俽俥乺偑擭偵係夞弌傞偲巚傢傟偨曽偼乹婫姧俶倂乚俽俥乺傪娒偔尒夁偓偰偄傞丅栆徣傪朷傓<偭偰僆僀両
丂戝媣曐偦傝傗偼偦偺屻丄亀撪懁偺悽奅亁乮儘僶乕僩丒僔儖償傽乕僶乕僌挊丄僒儞儕僆俽俥暥屔86擭乯偺東栿乮嵢偺彫愳傒傛偲嫟栿乯傪暔偡偑丄昞晳戜偐傜巔傪徚偡丅恎嬤側乹婫姧俶倂乚俽俥乺娭學幰偺丄俽俥僙儈僫乕幚峴埾堳挿丄塱揷峅懢榊偝傫乮俶倂乚俽俥儚乕僋僔儑僢僾忢楢丄80擭俀寧戞15崋偵乽廁傢傟偺帪娫乿敪昞乯偵巉偭偨偲偙傠丄乽嶳栰峗堦偺桭払傜偟偄偗偳丄傏偔偼柺幆側偄偹乿偲偺偙偲偱偟偨丅
 |
丂乽俶倂丒俶倂丒俶倂乿偐傜嶡偡傞偵丄偳偆傗傜乹埆杺塣摦乺偼丄傏偔偺強桳偡傞戞俁崋傑偱偺敪峴偲尒偰傛偝偦偆偩丅偦傟偐傜乹婫姧俶倂乚俽俥乺媥姧傑偱20擭丅偙偺挿偄帪傪旓傗偟丄戝媣曐偦傝傗偼壗傪庡挘偟傛偆偲偟偨偺偐丠
乽撉傒愗偭偨搝偼偄側偄乿乽偄傗丄俁恖偩偗偄傞乿側偳偲丄僨傿儗僀僯乕偺枹栿偺戝嶌亀Dhalgren亁傪椊偖乮徫乯塡偑傑偙偲偟傗偐偵殤偐傟傞乽嫟嶻庡媊揑俽俥榑乿偩偗偵丄撉傫偱傕撉傫偱傕暘偐傜側偄偳偙傠偐丄撉傓偙偲偝偊愨懳揑偵嫅愨偝偣傞擄夝偝偵枮偪偰偄傞丅僥僉僗僩偁傟偳丄塱墦偺撲側偺偩丅丂
丂
偁偲偑偒
|