 |
36号 2000年9月
 |
|
|
|
 |
それにしても、いったい何故今、SF文庫が出てきたのであろう?前述の通り、文庫創刊ラッシュのタマのひとつということもあろう。新しいジャンルの開拓という意味で。が、文庫だけにとどまらず、徳間書店はムック「SFJAPAN」を発行したり、日本SF新人賞を創設したりと、SFに対して妙に意欲的である(笑)。これは、やはり今年の「SFセミナー2000」で、角川春樹氏が予言したとおり、「これからはSFブームが来る」という表れなのだろうか?
さてその角川春樹氏だが、かねてよりハルキ文庫で日本SFの旧名作を続々と復刊させていたが、この9月より、書き下ろしSFの新シリーズがスタートした。こちらも高瀬彼方、妹尾ゆふ子などの若手SF作家たちである。
このシリーズも装丁に気を配っていて、ビジュアルから手に取ってもらおうという出版社の作戦がうかがえる。徳間と同じく、やはり若い読者を狙っているようである。
 |
電撃文庫や、富士見ファンタジア文庫の読者を、もっと本格SFに引き込もうという目論見なのだろうか。この目のつけどころはとてもいいと思う。
さてさて、それで、実際のところ、これらの文庫を買ってくれている読者の年齢層はどうなんだろうか。正直なところ、私はここが最も気になっている。若い人に読んでもらおうという、出版社の試みは果たして成功しているのだろうか?
今までSFを読み続けていた、いわゆるSF大会などに参加するような年代のSFファンには、大いに歓迎され、受けているようである。もはや、書いてる著者たちも同じ世代(あるいはそれ以下!)であることだし。昔好きだったが、既に絶版になっていた本が復刊されればそれだけでもうれしいし。なにせ夢物語であったのが、現実になってしまったんだから!このあたりの、かつて日本SFが熱かった頃を知っている年代が懐かしがって、あるいはその当時のような新作ラッシュぶりを喜んで買うのはまあ予想通りと言えるであろう。
が、私よりひとつふたつ下の世代の読者達に、この志はきちんと届いているんだろうか?願わくば「ああ、活字SFって結構面白いじゃん!」と思ってくれる読者が一人でも増えますように。次の世代に、バトンをきっちり渡すことができますように。その中から、私たちを楽しませてくれる新たな日本SF作家が現れますように!
|
 |
早速22号(1968年11‐12月号)を見てみよう。アレクサンドル・ベリャーエフ「ワグナー教授の発明」、イワン・エフレーモフ「ギリシャの謎」ほか、エムツォフ&パルノフ、イリヤ・ワルシャーフスキイら全7篇を収録。エフレーモフの「『アンドロメダ星雲』への道」や、ストゥルガーツキイ兄弟との対話「科学的予言の道」など、未だ紹介の機会少ないロシア・ソビエトSFの、貴重な4本のエッセイの部「作家は語る」も併録。意外とも言える豪華さに、あなたはきっと目を見張るだろう。そしてこの特集号は、幸運にも、ほんの前触れに過ぎなかったのだ。
〈ソヴェート文学〉はSF特集を、27号(69年10月号)で第2回目、第3回目は34号(71年1月号)と、快調なペースで送り出していく。
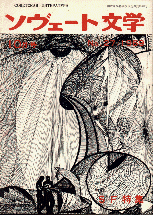 |
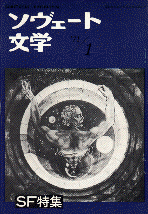 |
27号は5篇収録。34号には短篇7篇のほか、エフレーモフ・インタビュー「SF文学を考える」を揃える。だが何と言っても興味を惹くのが、国際SFシンポジウム(1970年)に来日した旧ソ連代表団の一員、ワシーリイ・ザハールチェンコおよびエレメイ・パルノフによる報告だろう。
代表団メンバーは帰国後、作家同盟において報告演説を行い、〈文学新聞〉紙上に全部の基本的報告を掲載。さらに、ザハールチェンコが編集を務める雑誌〈技術青年〉(発行部数180万)の71年第1号は、全号あげて国際SFシンポジウムを特集(!)したという。
第4回目は、45号(73年夏号)で。
 |
この号は262ページと、以前の特集号の倍はある大冊となっている。原因はひとえに、ストルガーツキイ兄弟の長編『リットル・マン』(深見弾訳)400枚一挙掲載ゆえであり、過半を占める。
それにしても、このパッと見ウサン臭げ(笑)な〈ソヴェート文学〉とは、一体全体どんな雑誌なのか? 誌名や作家名の表記は、原音主義からなのだろうか。「本誌ソヴェート文学は、多民族ソヴェート文学の、多様で豊かな稔りを広くわが国読者に紹介することを目ざしています。」(27号「編集部から」)の言葉通り、毎回特集主義を貫き、旧ソ連邦のありとあらゆる文学の諸相を取り上げている。
なにしろ、志が違う。最初のSF特集である22号の編集後記に、「つねにソヴェート文学の最新の成果の紹介を心がけてきた本誌では、この新しいゆたかな未来をもつ文学のジャンルへのアプローチのいみで、このソヴェートSF特集を企画した。」「もとよりこの初めてのささやかな特集でソヴェートSF全体を紹介しえたとうぬぼれるつもりはないが、(中略)独自の世界をきずきつつあるこの国のSFの現状の、一端なりとお伝えできたものと思う。」と述べられている通り、ある種の使命感に似たものさえ感じられる。
また、4号全てに翻訳で登場の深見弾より、絶大な援助があった旨記されているのも見逃せない。
〈ソヴェート文学〉自体は、ぼくのような細切れでしか見ていない者には、謎な部分も多い。やたらと発行元が変わった雑誌で、22・27号は創刊以来の理想社から。34号はソヴェート文学日本発行所からで、45号は東宣出版に移行している。但し、この両社は実質同じ系列である。でも35号(71年3‐4月号)を見ると、印刷所に過ぎなかった東銀座印刷出版が発行元も兼ねる旨お知らせしていたり、もうワケが分からない。
また、創刊は64年11月(季刊でスタート)なのだが、それ以前に少なくとも5冊、ほとんど同体裁(帯が付く)の〈ソヴェート文学〉が刊行されているのもナゾだ。一貫して編集を担ったソヴェート文学研究会(代表/黒田辰男)が、初期には早稲田大学文学部内に設置されていたことから、この創刊以前号は研究室の機関誌として、発表の場となっていたとも考えられる。しかし、こちらもやはり理想社が発行所となってるのだった。
終刊は確か、ぴったり100号。その間際の98号(1987年1月、群像社)を〈ソヴェート文学〉は5度目のSF特集に充て、再び大輪の華を咲かせ飾ったのだった。
 |
ストルガーツキイ兄弟の中篇「火星人第二の来襲」を始め、全6篇。SF画の紹介や対論もあり、現代的な編集では随一の出来。ぼくはこの号を、群像社に注文して取り寄せた。5〜6年前の話だけどネ。
そこはかとないイデオロギー的感触も皆無ではないが、以上5冊のSF特集号は、ロシアSFというマイナーさに加え、媒体の入手困難さともあいまち、ファン必携の即買いオススメ品なのだ!!
あとがき
|