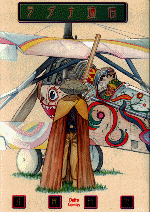『ハローサマー、グッドバイ』☆☆☆☆ (マイクル・コニイ サンリオSF文庫 80.9月刊 品切れ)
絶版となったサンリオSF文庫の中でも、特に傑作との誉れ高い、誰もが絶賛する1冊。私にとっては、ごおおっという感動というより、静かにじんと心に沁みた1冊であった。しいて言うなら、『エンジン・サマー』(ジョン・クロウリー、福武書店、品切れ)に似た読後感。美しく、詩情豊かな香り高い物語であり、同時に見事な構成のSFである。
最初の「作者から」という一節にあるとおり、この小説は「恋愛小説であり、戦争小説であり、SF小説であり、さらにそれ以外のものでもある」。この言葉がすべてを語っている。赤い海のある、とある惑星でのドローヴという少年とブラウンアイズという少女との瑞々しい「恋物語」であり、彼の町の外で起きていて、やがて彼らにもその影が忍び寄ってくる「戦争小説」であり、この惑星におけるなんとも驚嘆すべき「SF」であり、さらに「それ以外のもの」なのだ。そう、これはとても大きな「物語」なのである。
語り口の美しさは筆舌に尽くしがたい。主人公達少年少女のみならず、その親たち大人も含め登場人物たちの心の描写が、実に生き生きとして鮮やかなのだ。そう、人物の心だけはリアルに書いてある。それ以外は何気にぼやかしてあるのは、後になって…。
ラストで、物語は壮大なSFへと昇華する。ここではあえて詳しくは触れない。
深くて厚みのある豊かな物語を読み終わった時の、なんともいえぬ静かな感動に包まれた。こういう物語をもっともっと読みたい、と心から思う。
『ブロントメク!』☆☆☆1/2 (マイクル・コニイ サンリオSF文庫 80.8月刊 品切れ)
「コニイはストーリーテラーである」との思いをさらに強くした1冊。不思議な吸引力で、読者をひきつけて離さない。
うーん、この話はどう説明したものやら。とにかくいろんな要素が入っているのだ。アルカディアという奇妙な惑星のSFであるのはもちろん、アヤシゲな巨大企業に乗っ取られようとする小さなコロニーの住民たちとの社会的戦い、主人公の恋愛、ひとりでヨットに乗り込んでこの惑星の不思議な海を1周する男のサスペンス…。とにかくもろもろのピースが融合し、とあるコロニーでのひとつの物語を形成している。
そういう話なので、読者の着眼点によって、いろんな風に読める。ある意味、あっけない幕切れのハッピーエンドとも読めるが、私自身は、やはり何とも切ない話だなあという印象。ひょっとして…とは思っていたが、やはりそうであったか。
しかしラスト間際で、表紙イラストのでっかい耕運機、ブロントメクがいつ活躍するのかと待ってたのに、あれれ?(笑)
なんとなくつかみどころのないヘンテコな話、ではあるが、それでいてめっぽう面白いのは確か。マイクル・コニイ、なんとも不思議な作家である。さて、『冬の子供たち』と『カリスマ』を探さねば。
『ルート225』☆☆☆ (藤野千夜、理論社 02.1月刊)
えっ?マジで?と、読了後しばし呆然としてしまった。これはかなりの衝撃的問題作ではなかろうか。作品に問題があるとか、そういうことではない。普通、こういう終り方はしないと思う。その締め方を選んだ作者に驚いたのだ。いったい、彼(彼女か?)はどういうひとなのだろう、どういう作品を書く作家なのだろう、と無性に思ってしまった。
中学生と小学生の姉弟が迷い込んだ、日常からほんの少しだけズレたパラレルワールドの話である。ほんの少し、というのがポイント。妙なリアル感がある。微妙な年頃の主人公たちの書き方もなかなか。ちょっと醒めた、斜めに見ているというよりは物事に少し距離を置いて、自分から切り離して客観的に見ているような感覚。ここにいる自分と、それを客観的に横から見ている自分のふたりがいる、というか。こういうのが今の子たちなのかな。実際のところはよくわからないが、いいセンいってるように思う。
しかししかし、このラストは!私にはとても冷静には受け止められない。もし私が彼らのような状況に置かれたら、とてもこんな風にはふるまえないであろう。こりゃ堂々たる「SF」だ。しかも救いようのない。コワイよ。すごくコワイよ。でも彼らはこれをまともに受け止めるというよりは、例の醒めた感覚でもってあまりストレートに痛みを感じないように自分でセーブしつつ、現実にきちんと向き合っている。そこんとこに、驚愕してしまうのだ。なんという強さ、いや逞しさ、図太さ、軽さ?なんにせよ、やっぱり強いよ。
とはいえ、彼らだって本当は…と、その心の奥を想像すると、うわあああっ!と叫びたくなってしまう。これは切ないよ。
中学生くらいのお子さんの感想をぜひ聞いてみたいものです。この主人公たちの選んだ道に共感するのか否か。
『青空の卵』☆☆☆1/2 (坂木司、東京創元社 02.5月刊)
装丁の美しい本。「名探偵はひきこもり」という帯が印象的。そう、ワトスン役の保険営業マンである主人公に対して、このホームズ役の友人は、人ぎらいで家にこもりぎみのプログラマーなのだ。で、そんな友人をきづかって、外界への興味を持たせようと、主人公はあれやこれやと謎を持ち出して、なんとか連れ出そうと日々努力しているわけである…が…。
むむ、これは!このふたりの友情は、どう考えても普通のレベルを超えてるぞ(笑)。やお○と聞いてはいたが、こりゃマジでラブだよ、このふたり!(どっちも♂)若干でも、血液中にそれ系の血が流れてる読者にはたまんないかも(笑)。
それを脇に置けば、いつもの東京創元社お得意の「日常の謎」派ミステリとして楽しめる。「冬の贈りもの」の謎解きなどは、はたと膝を打った。「夏の終わりの三重奏」みたいな社会問題系の話より、この著者にはこっち路線のほうが向いてると思う。
主人公たちがやや感情的に過ぎる(そんなにぽろぽろ泣かんでも…)など、若干気になる点もなきにしもあらずだが、さまざまな小さな事件を解決していくうちに、だんだんと彼らに人の「輪」ができ、それが広がっていく様は微笑ましい。加納朋子あたりとはまた少し違った、独特の暖かさを感じる。なんとなく、手ざわりが今の若い人の感覚なのだ。よっぽど心を許す相手以外には、自分の感情の扉を全開にはしないところとか。自分の領域をかたくなに守り、侵入を許すのは限られた信頼できる人間のみ、でもそれでもやっぱり他者と接点を持ちたいとも思う、その葛藤や矛盾。そう、他人との距離のとり方が独特なのだ。自分と他者との間に、薄い透明な壁があるような感じ。
ちょっと新しいタイプのミステリではなかろうか。「かつくら」読者あたりに強力オススメ。