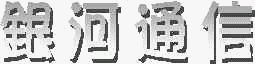 |
第22号 1999年7月
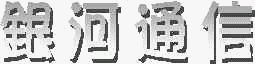 |
|
|
|
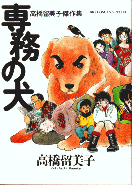 |
「日常」というものは、誰しも何も考えずにただのほほんと過ごしがちだが、実はそれの積み重なりこそが人生なのだ。作者はそれの断片を切りとって見せることにより、登場人物それぞれの人生を、その人なりの生き方を浮き彫りにしてゆく。
表題作の主人公は日頃は全く冴えないダメ男なのだが、そんな彼にも確固たるポリシーがあり、愛する者を救うため、いざという時にはちゃんと戦うのだ。たとえ自分はどうなろうとも。これが、彼の生き方なのだ。
「茶の間のラブソング」などもいい味出してるので、ぜひご一読を!
|
|
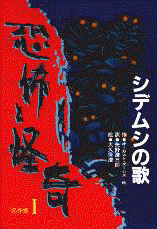 |
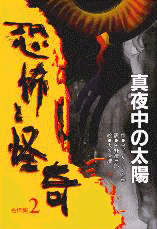 |
 |
| オーガスト・ダーレス他 | ロッド・サーリング他 | ジェローム・ビクスビー他 |
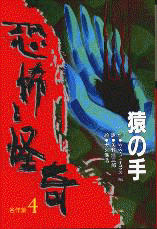 |
 |
 |
| W・W・ジェイコブズ他 | レイ・ブラッドベリ他 | ロバート・ブロック他 |
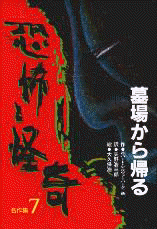 |
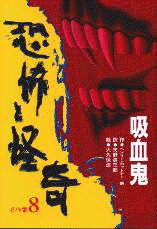 |
| シルヴァーバーグ他 | ヘンリー・カットナー他 |
 |
 |
| ベン・ヘクト他 | フリッツ・ライバー他 |
聞いたこと無くとも無理はない。出版社は岩崎書店だから、児童書なのです。でも、じゃあオレいいや、と判断するにはまだ早い。まあ見てくださいよ。素晴らしく正統派の、怪奇小説アンソロジーに仕上がっているのだ、これが。
各巻3〜4篇収録の全36作品。構成としては、いわゆる文豪の作品(キップリング、ディケンズ、ロレンス他)や怪奇小説の古典(ストーカー、ホジスン、ブラックウッド他)を始め、〈ウィアード・テールズ〉作品(ダーレス、ラヴクラフト、ブラッドベリ他)はもちろん、テレビシリーズ『ミステリーゾーン』(『トワイライトゾーン』)の原作(サーリング、マシスン)ばかりか、知る人ぞ知るマイナー作家の佳作まで、バランスの良い精選集として見逃せまい。
選択から翻訳まで、一貫して矢野浩三郎が手掛けているという点でも、なかなかポイント高いぞ。巻ごとでテーマ・アンソロジーとしても読め、ジュヴナイルながらも、これだけアンソロジー・ピースが並ぶとちょっとした壮観である。
気になる翻訳なのだが、いくつか既訳と比較してみた範囲では省略などは特に見受けられず、完訳と言って差し支えないものであった。また、以前の矢野浩三郎訳であったカール・ジャコビ「黒の告知」(『黒い黙示録』収録 国書刊行会87年)と、第8巻『吸血鬼』収録の同短篇の比較でも、漢字や言い回しなどで対象年齢層に配慮したと思われる形跡がうかがえるが、逆に言えば、だいぶ手直ししてるってこと。かなり気合の入った仕事振りと、ぼくは見た。
そうそう、刊行ペースも気合入ってたね。こういう児童書のシリーズ物は図書館需要が最大のターゲットなので、まず春に完結することが絶対条件となる。そこから逆算して、1巻目の奥付が98年6月30日。月イチで4月には完結の予定でした。ところが第3巻で早くも一月遅れとなり、第5巻が2月15日。こりゃあ、取り返しが付かんわィ、と思ってたら、その後の快進撃がスゴかった! 6巻目から順に、4月25日、4月15日、4月20日、4月25日、4月30日!! 一体、本の製作でこんな離れ業、可能なのか? 第6巻と第9巻の奥付が一緒なのはご愛嬌。ちゃんと巻を追って発売されてたから、時空を歪めて奥付を遡らしてしまう程、現場は修羅場だったことが想像出来よう(笑)。名高い作品ながらも、今新刊で読むためにはこのシリーズしかない!というのも多数収録された『恐怖と怪奇名作集』。大型書店でも揃えてる所はマズ無いから、迷わず注文しよう!
続いては、気合の入っていない刊行ペースで、やっと6月に完結した…なんてウソです嘘ですゴメンナサイ! とにかく出版されたという事実だけで、もう何も言いますまい。ぼくはそれだけで、純粋に嬉しい。その叢書の名は《魔法の本棚》(全6巻 国書刊行会)。掉尾を飾るは、アレクサンドル・グリーン『消えた太陽』(沼野充義・岩本和久訳)。
この、待ち望まれた最終配本にこぎ着ける迄の道程は、決して平坦ではなかった。イキオイでまた奥付を確認してしまおう(笑)。第1回配本、A・E・コッパード『郵便局と蛇』(西崎憲訳)が96年6月20日で、以後隔月にて刊行される予定であった。ヨナス・リー『漁師とドラウグ』(中野善夫訳)、H・R・ウエイクフィールド『赤い館』(倉阪鬼一郎・鈴木克昌・西崎憲訳)までは順調だったが、第4回配本リチャード・ミドルトン『幽霊船』(南條竹則訳)が97年4月25日、第5回ロバート・エイクマン『奥の部屋』(今本渉訳)は97年9月20日。そしてズルズルと延びてしまっていた、待望の最終巻『消えた太陽』が99年6月25日。3年に渡った大団円である。
ご覧の通り、少数の人々に愛されて来た作家たちゆえ、本邦初訳多数収録にして本邦初単行本、あるいは初作品集ばかりである。失礼ながらも、冒険を伴う意欲的事業だというのは想像に難くない。
しかしそれ以上に特筆すべきは、この叢書の「書物」としての美しさだ。内緒だけど予告の段階では買うつもりが無かった。でも初めて現物を目にした時…。かつてこれほど秘密めいた本があっただろうか。華奢な造りの函に、ちょっと擦れただけで霞んでしまう帯を纏い、脆く儚く、それゆえ虜にして離さない魔力がいや増すばかり。ハッキリ言って、一目惚れ。手にする度にその美しさを堪能し、喜びと、ある種エクスタシーに似たものさえ感じるのだ。「…前から心配だったけど、アイツは思った通り(以上に)ヤバイらしい」と避けられたって、かまうもんか!
長文の解説は作家論としても充実、書誌も完備して言うことなし! 装幀者妹尾浩也、編集者藤原義也、辛抱強く完結させた国書刊行会と支えた読者たち、皆に感謝しよう。
「怪奇と幻想、人生の神秘とロマンス、失われた物語の愉悦と興奮を喚びもどす、書斎の冒険者のための夢の文学館。」(内容見本の惹句)という言葉に相応しい、まさに魔法の香りのする書物である。
あとがき前号にひきつづき、またしても更新が遅くなり、まことに申し訳ありませんでした。1周年記念アンケートがあったり、SF大会レポートを書いたりと、何かと忙しかったんですう(言い訳)。ああ、ホントならもう8月号をアップしなきゃならないと言うのに〜(涙)。 |