秋刀魚(2)
一般に魚の雄雌の見分け方は大抵難しいですが、サンマの場合、雌は下顎(したあご)の先端が淡黄緑色をして鋭くとがっています。一方、雄の下顎は橙黄色で鈊い円形をしています。
また美味さを極めるためには目利きをしなくては叶いませんのでまず、
①魚体に光沢がある、
②目が黒く澄んでいる、
③大きくて身に張りがあり、尾まで太い、
④口先や尾のつけ根が黄色くなっているものは「大漁秋刀魚《と呼ばれ、脂の乗りも最高。
また(1)でも申しましたがサンマは回遊魚なので、7月頃に北海道東岸沖に現れ、三陸沖を南下して10月には常磐から銚子沖にに達します。そして南下の終点は四国、九州沖と言われています。この南下の途中で産卵し、孵化した稚魚は北上を始め、夏に再び北海道沖に現れます。
サンマはこのように広範囲を回遊しているため、日本の各地では地方色豊かに様々な調理法が工夫されているのです。
サンマ漁についてですが、現在は主に棒受け網漁という漁法で行われていて、この漁法は敷網漁業の一種で方形あるいは台形の網の1辺に向竹(むこうだけ)と呼ばれる竹をつけて水面に支え、反対側にはいわ(沈子)綱とよばれる漁具を下方に引っぱり、水中で所要の形状を保たせるために用いられるおもりをつけ、このおもりは網漁具を海底に固定するためにも用いられるのでおもり、しずみ、ちんしなどともいって、沈降力が大きいことが材料の備えるべき第一条件だが、こわれにくいこと、加工が容易なこと、
供給が豊富で安価なことも必要であり、鉛、鉄、石、陶器、コンクリートなどが昔から用いられているそうです。
このいわ網をつけて水中に沈めておき網全体を向竹の両端に直角にとりつけた2本の張出しざおで支え、
網の両わきは適当な間隔で鉄輪をつけて矢綱を通し、いわ綱には8本ほどの引綱をつけ、船内に保持しておく。
さらに漁は撒餌(まきえ)をしたり、夜間集魚灯をつけたりして、網の上に対象魚群を誘導し、ころあいをみて、両わきの矢綱を締め、同時に引綱をあげて、網の四方をすべて水上に出し、魚群を包囲するのです。
この漁法は、サンマが光に集まる習性を利用して、夜間に集魚灯でサンマを集め、下から四つ手網ですくい上げる方法で一般的な秋刀魚の漁法だそうです。
他の漁法としては刺網漁とうのがあって、サンマの通り道に網を仕掛け、サンマがその網に刺さって抜けなくなるという漁法も行われています。また「つかみ取り漁《という伝統的な興味深い漁法もあります
サンマの群れはエサ(動物プランクトン)が多く、流れ藻が漂っている潮流の境目を通り道にしています。この性質を利用して、船の脇に海藻を付けた筵(むしろ)を浮かべ、これに集まってきたサンマを筵に開けた穴から手を突っ込んでつかみ取ります。
これを「つかみ取り漁法《というそうで、現在でも佐渡や北海道の奥尻島に残っているのだそうです。ちなみに、なれたプロの漁師さんは一度に数匹をつかみ取ることができるのだそうです。
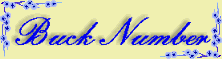 ◆バックナンバー集◆
◆バックナンバー集◆
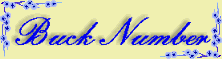 ◆バックナンバー集◆
◆バックナンバー集◆