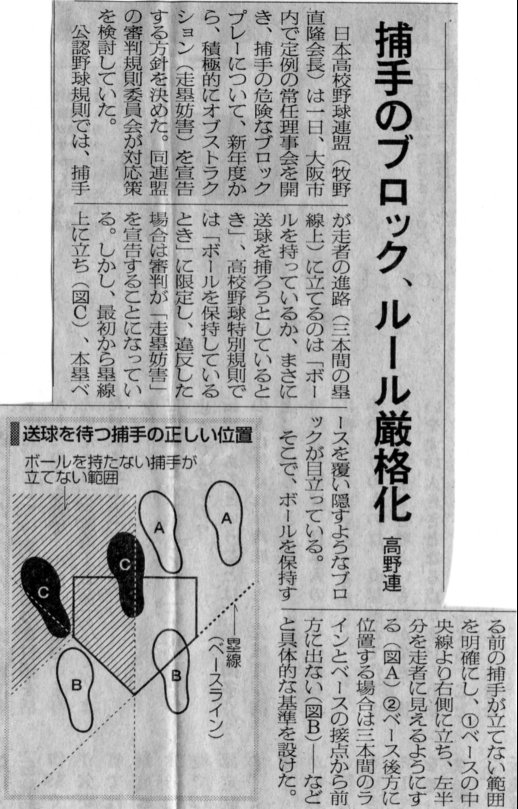�R���͂炢��I
���N�싅�Ƃ����ǂ��싅�͖싅�B���̕��G�ȃ��[���͎��Ƃ��ĔY�܂��܂��B
�܂��A�O���E���h���������Ƃ��������ʂȃO���E���h���[���A�z�肵�Ă��Ȃ����N���܂��B
�q�������́i���ɒ�w�N�j���[���̂قƂ�ǂ�m��܂���B�@���̂悤�ɒm��Ȃ������ł͍ς܂���Ȃ��Ƃ����悤��
�ێq��K�I�Ȕ��������̂��ǂ����Ǝv���܂��B
�����āA�����̐R���͑��̏ꍇ�A�O��̎����̃`�[���̊ēE�R�[�`�ł����A�K���������[���ɐ��ʂ��Ă���Ƃ͌���܂��A
�R���Ƃ��Ă���Ȃ�ɐU�������Ƃ͂܂��ʂ̂��Ƃ��Ǝv���܂��B�����Ƒ厖�Ȃ��Ƃ͊�{�I�ɏ��N�싅�ł͂��������������͊F����
�x���ԏ�ŕ�d���Ă�������{�����e�B�A�ł���A���q����̕���ł���Ƃ������ƖY��Ă͂����Ȃ��Ǝv���܂��B������Ƃ�����
�K�����Ȃ�����A�Ԉ���Ă��Ă������Ƃ������Ƃł͂���܂���B
�����ł́A���قȃv���[�ŐR��������ɋ������ꍇ��[���ْ̍�⏈���̊ԈႢ�������A
����ɂ��̋��P�����悤�ɂ�����̂ł��B
�Ȃ��A���̂Ƃ��̐R���̕��X�ɑ��ċ��e����悤�ȋC�����͑S������܂���B���̎����ɂ���
�W�҂��킩��Ȃ������ꍇ�������A���Ԃ������Ė싅�K���ׂ�]�T�ȂǑ��Ȃ��̂ł�����B
���̂��߂ɁA����ɑ��Ă͕K�v�ȃv���[�̐����݂̂Ƃ��A���Y�`�[������R�����ɂ��Ă͖��炩�ɂ���K�v��������
�l�����L���Ă��܂���B
������A�싅�K���̖����͌������Ȃ��Ǝv���܂��̂��i7.04C�j�̗l�ɕ\�����܂��B
�܂��A�{�����m�ɏ����ƒ����Ȃ�悤�Ȍ��i��F���̐�L���Ă����ۂɁE�E�E�j���u���̗ۂɁv�̗l�ȏ������ɂ��Ă���
�ꍇ������܂��B
���炩�ɓK�p�����Ԉ���Ă���悤�ł�����A����������B
�lj��L�^
�Q�O�O�S�N�R���@���̂V�A���̂W�lj��A���̂S�ɒNjL
�Q�O�O�S�N�S���@���̂X�A���̂P�O�A���̂P�P�lj�
�Q�O�O�S�N�T���@���̂P�P�lj�
�Q�O�O�S�N�X���@���̂P�Q�C�P�R�A�P�S�lj�
�Q�O�O�T�N�P���@���̂P�T�lj��A���̂W�ɒNjL
�Q�O�O�T�N�S���@���̂P�U�lj�
�Q�O�O�U�N�R���@���̂P�V�C�P�W�A�P�X�A�Q�O�lj�
�Q�O�O�U�N�W���@���̂Q�P�lj�
�Q�O�O�U�N�W���@���̂Q�Q�lj�
�Q�O�O�V�N�P���@���̂Q�R�lj�
�Q�O�O�V�N�P�P���@���̂Q�S�lj�
�Q�O�O�W�N�P���@���̂Q�T�lj�
�Q�O�O�W�N�R���@���̂Q�U�lj�
�Q�O�O�W�N�R���@���̂Q�V�lj�
�Q�O�P�O�N�Q���@���̂Q�W�lj�
�Q�O�P�O�N�R���@���̂Q�X�lj�
�Q�O�P�T�N�R���@���̂R�O�lj�
�Q�O�P�U�N�S���@���̂R�P�NjL
�Q�O�P�V�N�T���@���̂R�Q�NjL
�Q�O�P�W�N�R���@���̂P�U�폜�i���[�������ɂ��j
�Q�O�P�W�N�X���@���̂R�R�NjL
�Q�O�P�X�N�S���@���̂R�S�A�R�T�NjL
�Q�O�Q�P�N�T���@���̂R�U�NjL
���̂R�U�@�����Ƌ����Ăق����ł�
���̑����P�ێ�����Ă��āA�P�ۃ����i�[���������ɉE�����x�[�X�̌��i�t�@�E���]�[���j�ɒu���Ă�����҂��Ă����̂ŁA
�ƂɋA���ė��Ă���u�����ƃC���t�B�[���h���ɑ���u���Ă��Ȃ��Ƃ��߂���v�Ƌ�����Ɓu�N���ꂪ�������ɂ��ėǂ����Č����Ă��v�Ƃ̂��ƁB
����ɂ͂����Ɩ싅�K��5.02����ʒu�̍��Ɂu�����J�n�̂Ƃ��A���͎������{�[���C���v���C�ƂȂ�Ƃ��ɂ́A�ߎ���������ׂĂ̖��̓t�F�A�n��ɂ��Ȃ��Ă͂Ȃ�Ȃ��v�Ƃ���܂��B
�����j��������ƌ����ē��i�̔����͂Ȃ����A�����Ƃ��Ăق������̂ł���B
���̂R�T�@���N�싅�ł͈Ⴄ�Ǝv���܂�
�����܂Ōl�I�Ȉӌ��ł����A����̍ۂǂ��{�[�N�܂����̌����A���R�ȑ�����x���낵�Ă�����x�グ�Ă��瓊����Ȃ�
��点�Ă���`�[��������܂���������ƈႤ�Ǝv���Ă��܂��B���[����ł̉ۂł͂Ȃ�
�u���N�싅�Ƃ��Ċ�{�I�ȓ������������Ƌ����o��������v�ׂ����Ǝv���܂��B
���̂R�S�@������ƌ����ɂ�����ł����NJ�����
�싅�Ɍ��炸�A�X�|�[�c�͔N�X�i�����Ă��܂��B�g���[�j���O�̎d���A�p��A���[���ȂǍ��̗��s�ł͂���܂��A���a���畽��������
�ߘa�ɂȂ��Ă����ς���Ă����܂��B
�����Ŏ���ɂ܂�Ȃ����Ƃ�m��w�E���������Ƃ�����܂��B����͍��ł��Â������⌾���`�������̂܂܂܂������Ă�����������Ƃ������Ƃł��B
�P�j�{�[�����O���u�ɓ������Ă�����G���[�A�G��Ă��Ȃ���q�b�g
�Q�j�P�ۂ��삯�����Z�[�t�ƂȂ�����A�t�F�A�O�����h���ɋ��ă^�b�`���ꂽ��A�E�g�ɂȂ邩��t�@�[�����ɂ���B
�Ȃǂ͂悭������܂��ˁB�Ⴂ�܂���B
���̂R�R�@�܂�Ȃ���
����A�����̋��R�����ɉ����Ȃ��I���A���̎��������Ă������̂��ƁB
�����P�ۂłQ�X�g���C�N�B���̓����łP�ۑ��ғ��ہA�o�b�^�[�͋�U�肵�ăz�[���x�[�X��ɂ�낯�Ă��܂��L���b�`���[�̑�����W�Q�B
���R�����̗l�ȃw�{����Ȃ��Ă����Ƃ��Ă�����ł悩�����B�������Ȃ�A
�u�o�b�^�[�O�U�A���ۂ����P�ۑ��҂�߂��Ď����ĊJ�v�Ƃ����Ǝv���B
�������Ȃ���A���������u��
�u�o�b�^�[�͎O�U�ŃA�E�g�A���W�Q�ɂ��P�ۑ��҂��A�E�g�v�ƂȂ�܂��B
�R���u�K��ł��悤�ȃV�`���G�[�V�������ȂƂ������Ă��܂������A�U�����̕s���v���傫���̂ŁA�R���ɐM�p�Ȃ��ƂȂ��Ȃ����m�ȏ��u���Ă����߂������ȂƎv��������ł��B
���̂R�Q�@�����̏I����
��U�`�[���������Ă���Ƃ��̏I�����Ȃ�ł����ǁA���낢��ȏI����������܂��B
�@�V��i�ŏI��j�\���I��������_�ŏI��
�A�T�œ_���̃R�[���h
�B�T�Ŏ��Ԑ�
| �@ |
�U |
�V |
�A |
�S |
�T |
�v |
�B |
�S |
�T |
�v |
| �` |
�O |
�P |
�| |
�O |
�O |
�O |
�| |
�O |
�O |
�O |
| �a |
�O |
�� |
�| |
�O |
2x |
10 |
�| |
�O |
0x |
�T |
�A�̏ꍇ�͂Q�_�ڂ����������_�ŃR�[���h�ɂȂ莎���I��
�B�̏ꍇ�͂��̉�̍U�����Ɏ��Ԃ������̂Ŏ����I��
���{�ł͂��Ə����܂����A�����ɂ̓A���t�@�Q�[���Ƃ����A�R�A�E�g�܂ł�����牽�_�������̂��s���Ȃ̂Łu���v�Ƃ������Ƃł��B
�܂��A���Ԑ�̃^�C�~���O�����̎��̑Ŏ҂����������Ă�����i���ɏ��N�싅�ȂǂŒ�w�N�̎��j�ꍇ�ɂ́A�����łR�A�E�g�ڂɂȂ邱�Ƃ�����̂ŁA���̏ꍇ�͎d���Ȃ��ŏI��ɂ���
�t�L���Ȃ��ꍇ�����邩������܂���B
���̂R�Q�@�X�R�A�[�u�b�N
�ŋ߁A���ꂳ�ܕ����t���Ă���`�[���̑����X�R�A�[�u�b�N�B�싅�ւ̗����Ƃ��A���q����Ƃ̉�b��������
�����̐U��Ԃ�Ŏ���ŃX�R�A�[������Ƃ������b�g�͑傫���Ǝv���܂��B
���C�I���Y�����Ȃ�O���炨�肢���Ă��܂����V�[�Y���O�ɂ̓X�R�A�[���u�K��N�s���Ă��܂��B
���N�v�����Ƃ́A�X�R�A�[�t����ɂ́u�p��v�u���[���v����͂�厖�ȂȂƎv���܂��B
�܂��A���ꂳ����������p���ł������ƂŁu�����������Ȃ����ǁA����ɂ���ē����邱�Ƃ���������v
�݂����Ȃ��̂��`�����Ă�����`�[���Ƃ��Ă�������Ȃ��ł��傤���B
�����A��͂����̂Łu�ŏ����炿���Ƃ���v�݂����Ȃ��Ƃ͌���Ȃ��ł��܂��B
���̂R�P�@�Ȃ��Ȃ��ʔ�������
�Ƃ肠�����A�N�C�Y�`���ŁB
��ʂ͓A���҂R�ہB�U�ԑŎ҃J�E���g�R�|�Q�i�Q�X�g���C�N���厖�j
���̓�������U�肷����A�ߋ����ꂸ�U�蓦����ԁB�����������ւR�ۑ��҂��{�ۂ֑����Ă����B
�R�ۑ��҂��{�ې��O�A�E�g�ɂȂ����B�R�A�E�g�`�F���W�B
�Ŏ҂͓��ɑ����Ă������Ƃ��Ȃ��o�b�^�[�{�b�N�X�ŗ����Ă����B�i�T�[�N������͏o�Ă��Ȃ��j
�@
���āA�������炪���B
���̉�͉��ԑŎ҂���ɂȂ�̂��H
���̂R�O�@ �ŋߋC�ɂȂ鐺
���v���Ԃ�ł��B
�����Q�N���炢�ł��傤���A�������C�ɂȂ�u�|�����v������܂��B�@�����
�u���邼�I�v�@�ł��B
��������A�o���o���Ȃ�ł��B�@�u�G���[���邩������Ȃ����v�@�ƌ����Ȃ����牓���������āB
�s�����ɂ܂�Ȃ��B�����ۂ������B
���x���̒Ⴂ���싅�̂������������x�����B
�P�ۋ삯������I�@�ł���B
���̂Q�X �R���u�K��
�t�A�R���ɂȂ�Ɗe�A���ŐR���u�K��s���܂��B���������܂��ƁA�ʓ|�������̂ł����A�s���Ȃ���Ȃ�Ȃ��̂�
�����Q�����܂��ƁA���\�M�������Ⴂ�܂��B���ɍŋ߂͍u�t���ɂȂ邱�Ƃ������A�ӔC�d��H�ł��B
���āA�R�[�`�ɂȂ��ē����A���߂ču�K��ɏo����Ƃ��̃A�h�o�C�X���B
�P�j�ĊO�A�m���Ă��邱�Ƃ��u�Ԉ���Ă��邱�Ɓv�ł���ꍇ�������̂ŋC�����Ă��������B
�Q�j���ԂɐR���̓�������K���܂����A�p���������ł����v��������Ԉ���Ă�������ł���Ă��������B����ɂ��Ȃ��Ɗo���Ă��Ȃ����̂ł��B
�R�j���̕�������Ă���̂����ă~�X�����̂����̂ł͂Ȃ��A�u����͉�����肻�����ȁv�Ǝv���Ă��������B
�S�j���̕��ƌ��Ȃ���f�B�X�J�b�V�������Ă��������B
�T�j�S���o���悤�Ƃ��Ȃ��Ō��\�ł��B�����ł��B���̌���ۂɐR�������Ƃ��Ɂu�����I�v�ƂȂ�ƂȂ��v���o���Ă��炦��B
���̂Q�W �������������[�����܂���i�������̐��œǂށj
��
�Ƃ��鎎���ł̂��ƁB�R�ۂɃ����i�[�����܂����B���肪�܂��ɓ����悤�Ƃ������ɍU�����x���`����u�E�G�X�g�������v�̂悤�Ȋ|������������܂����B
�싅�ł͔z���Ɋւ��邱�Ƃ�Ŏ҂ɓ`���Ă͂����Ȃ��̂ŁA������ē��R�c�ɍs���܂������A���̂܂܃J�E���g���i�݁A�p������܂����B
�Ƃ茾
�������������[�����܂���I
���̂Q�V ����̂���
��
�Q���̎����ł��B���肪�Z�b�g�|�W�V�����Ƃ��Ă��瑖�҂��C�ɂȂ�̂ł��傤�A�Ȃ��Ȃ������Ȃ��̂ł��B
���R�A����r�����]���]�Ɠ����܂����A�܂����ӂ������������i�[������Ă��܂��܂����B���炭���Ă���x���`��
���ӂƌ��������肢���Ă����܂����B
�Ƃ茾
���͂��̓��肾���łȂ��A�ŋ߂悭��������̂����̃^�C�v�̓���ł��B�p�������Ȃ���䂪�`�[���ɂ����܂��B
�����i�[�ɋC��z��̂͂����̂ł����A�C���g�������đŎ҂ɂ����Ɠ������Ȃ��Ȃ��ł��B
�P�j���܂�ɓ��ۂ��ꂽ���Ȃ��ăZ�b�g�|�W�V�������~�܂�Ȃ��B
�Q�j���҂ɋC������ĂȂ��Ȃ��Ŏ҂ɓ������Ȃ��B
�����P��
�R�j�Z�b�g�|�W�V�������猡������ۂ̑��̊O�����������Ȃ��^�C�v�B
���̂Q�U ����ȂɃ{�[�N���D���ł����H
��
�Q�C�R�ۂŃZ�b�g��������̑����m���Ƀs�N�b�Ɠ����܂����B�܂��A����Ȃ��Ƃ͏��N�싅�ł͂����̂��ƂȂ̂Ŏ��܂���ł������A
���̌�_�����邩�Ǝv�����̂ł����O�_�B���̓Z�b�g�̎~�܂�̂��Â������̂��ȁH(�����Ă��Ȃ�)����蒍�ӂ�����A
����`�[������u���ӂ���H��݂����ȃN���[���B�͂��͂�����܂�����B���̓Z�b�g�̊O������������̂Ŏ��܂����B
�Ƃ茾
���N�싅�̊ēR�[�`�̊F����͖{���Ƀ{�[�N����D���ł��B���ɑ���̓���̂ˁB
�`���b�g��������u�{�[�N�A�{�[�N�v�Ƒ呛���B����ȂɃ{�[�N������ă����i�[�i�߂ē_���~�����̂��I�ƌ��������B
���C�I���Y�̏��N�̓{�[�N����Ă��W�Ȃ����X���X�키�݂̂ł���B(���ނ��炵�Ȃ��ŗ~����)
�{�[�N�����Ă������Ƃ����킯�ł͂���܂����B�łĂ��铊�肪�S�Ẵ{�[�N��m���Ă���킯�ł͂Ȃ���(�ēR�[�`���H)
���̂悤�ɐU�������Ƃ��o����킯�ł͂Ȃ��̂ł��B
���̂Q�T ���R�����悤��
��
�F����ېR�͂��Ă����̂����ǁA�Ȃ��Ȃ����R�����Ă����R�[�`���E�E�E�E�B
�Ƃ茾
���R�ʼn������₩�ƌ�����
�P�j�g���u���ɂȂ��ĝ��ߎ��ɂȂ�̂����₾�B
�Q�j�X�g���C�N�A�{�[���̔���Ɏ��M���Ȃ����A���匾����̂����₾�B
�R�j�P�ɂ��Ȃ���܂����A���������[����m���Ă��鎩�M�������B
�܂��A���ꂪ�R���Q�ł��傤�ˁB�i�p���������Ƃ������邩�ȁj
���l�̂����ɂ��Ă͂����Ȃ���ł����ǁA�R���ւ̃N���[���Ƃ��A�쎟������ł��B�ƌ������A�����Ɗē���͗�Âł��ė~������ł��B
�^�C���Ƃ��āu���̑ŋ��͑��ɓ������Ă��܂���ł������H�v�ƕ����Ă���������ł����A�͂Ȃ�����
�u�����A���̂͑��ɓ������Ă邾��I�v�݂����ɂ����Ȍ����̊ē���̑����ł��B
�Z�b�g�|�W�V�����Ŏ~�܂�����Â��Ƃ����u�{�[�N�A�{�[�N�v�Ƃ��A�u���͎̂~�܂��Ă˂���A���ꂶ�ᑖ��˂���Ȃ��v�Ƃ��ł������̓Ƃ茾�Ƃ�
�����ꂵ���ł��B
�����������Ƃ��A���R���Ȃ��Ȃ�����Ă���Ȃ������Ă���悤�ȋC�����Ă��܂��B
���́A�����R���C�I���Y�̃R�[�`�����̂悤�Ȏ�������Ȃ��悤�Ɂu�R���i����ς�j�����v�Ƃ��Ă�����Ă��܂����A���R�͂Ȃ��Ȃ�����Ă���܂���̂�
��J���Ă���܂��B
���߂�����Ƃ����i���̓I�A���_�I�j�ł����ǁA������Ɗ���Ă���ƁA���\�y�����ł��B����̐l�����R�͑�ςł���˂ƌ����Ă���Ă�����Ƃ����D�z�������邵�A
�Ȃɂ���A�싅�ɑ���m����l�����[�܂�܂��B
�l�I�ɂ͐R���u�K������ł��B
���̂Q�S ���߂�Ȃ���
��
�Q���̎����B�o���R���̎�R���Ă��܂����B������I�ɂȂ肩���Ă��āA�����̃`�[���������Ă��܂����B
���āA�����Ă���`�[���̓���̃Z�b�g���m���ɂ�������~�܂��Ă��Ȃ������ł������l�q�����Ă��܂����B
�����A����`�[�����u�~�܂��Ă��Ȃ���Ȃ��v�Ƃ��S�`���S�`�����邳���̂Łu�����������Ƃ�����Ȃ炿���ƃ^�C������Č����Ă���E�E�E�E�v
�Ƃ����Ă��܂��܂����B����Ɓu�킩���Ă���Ȃ����������Ȃ����E�E�E�v�Ƃ��ԂԂ����Ă��܂��B
���������܂��B�u�L���܂����v���̌チ�`���N�`���ł��B�����������Ă�����u�A��v����ł����B
�Q�i���[�V�������P��ڂŋC���t���Ē��ӂ���͂��������̂ł������Y��āA�Q�x�ڂł����Ȃ���܂����B�������ł��傤�ˁB
��U��U�Ȃ������Ⴂ���Ď����I��点�悤�Ƃ��܂����B�ނ����đ����I��点�悤�Ƃ���������������������������܂���B
����̋��P
�o���R���̎�R�͂��Ȃ��Ɍ���Ƃ������Ƃł��ˁB�i����ł��ꂩ���炸�ɍςނ����j
���̂Q�R �g�����
��
����Q���ł̎����B�Ŏ҃����i�[�͂P�ۃZ�[�t�B���������Ă������P�ێ肪�m�ہB�Ŏґ��҂͂P�ێ������邩�̂悤�ɋ삯�������ׁA���C�������ɗ����Ă������A
�Q�ۂɂ��������C�z�͖��������B����������P�ێ�͑Ŏґ��҂Ƀ^�b�`�B�R�����A�E�g�̃R�[���B�����ŁA�U�����ē���u�Ŏґ��҂͂Q�ۂ����������Ă��Ȃ��̂�
�Z�[�t����Ȃ�����ƐR���Ɋm�F�̗v�����܂����B
���̏�̔��蓙
����̒ʂ�A�E�g
����������
�Ŏґ��҂Ɍ���P�ۂ̋삯�������F�߂��Ă��܂��B�m���ɁA�삯��������ɂQ�ۂ���������������������
�ԈႢ�Ȃ����K�́u���ҁv�ƂȂ�܂��B�������A��������Ȃ��i�����Ń��C���̊O�����Ƃ��������Ƃ��ƌ������ƂłȂ��j�ꍇ�ł�
���₭�A�ۂ���K�v������܂��B���̏ꍇ�A�Ŏґ��҂��A�ۂ���ӎv�������Ȃ������̂Ń^�b�O����Ă��܂����̂ŃA�E�g�ł悢�Ǝv���܂��B
����̋��P
�Q���̎����Ȃǂŕs����ȑI�肪�ʏ���Ȃ��悤�Ȗ}�~�X�����Ă��܂����ꍇ�A���̍l���ł́u�����ď����Ă�����v�悤�Ȏ��͂����A�A�E�g�ɂȂ��Ă��܂����Ƃ�
��������ƃ��[����}�i�[�̎w���̋@��Ƒ�����悤�ɂ��Ă��܂��B
���̂Q�Q�@�C�ɂȂ��Ă��܂�
�p�^�[���P
�^�C���������邩�t�@�[���{�[���̌�A���̓����O�ɋ��R�̓v���C�������܂����A���̃v���C��������O�ɑ��҂͈�x���^�b�`���s���`���͂���܂����A
�v���C��������܂ŗ��ۂł��Ȃ��킯�ł͂���܂���B�펯�I�Ȕ͈͂Ń��[�h���č\���܂��A�Ȃ����u�v���C��������܂Ńx�[�X�ɕt���Ă��Ȃ����v��
���ӂ���R�����ɂ߂đ����B�킴�킴�߂��̂Ŗ��ʂȎ��Ԃ������Ȃ�B�������A���ӂ���R�����ɂ߂đ����̂ŁA
���ꂪ�������Ǝv���Ă���R���͂������A�ēR�[�`�������悤���B�������肵�Ă���B���_��͎��̗ۂ̐��O�Ńv���C��҂��Ƃ��\�����A
����͏펯���O���Ă���킯�ŋ��R�͂��̏ꍇ�ɂ̓v���C�������܂���B
�Ȃ��A�A���ɂ���Ă̓��[�J�����[���ŐG�ۂ��Ă���悤�ɂ��Ă��邱�Ƃ�����悤�ł����B
�p�^�[���Q
�l���Ǝ������Ĕ�Ȃ���̂ł��B
�{�[���t�H�A�ɂȂ�Ƃ��̑Ŏ҂͂P�ۂ܂ł͈��S�ɐi�ۂł��錠���������������łP�ۂ܂œ��B����`��������܂��B
�Ŏґ��҂��P�ۂ֒B���A�S���҂��������������ɏ��߂āu�^�C������������܂��B
�l���ɂȂ��Ă����C���h�s�b�`�ȂǂŃ{�[���f�b�h�ɂł��Ȃ�Ȃ�����u�C���v���[���v�ł��B�v�o�Ń{�[�����t�B�[���h��]�X�Ƃ��Ă����
���̊ԁA�i�ۂ��č\���܂���B������A�l���̏ꍇ�A�P�ۂւ͑S�͎����ł��B
�����͑Ŏ҂��P�ۂi�ތ����i���S�i�ی��j�܂��B
�������g�̂ɐG�ꂽ�u�ԂɃ{�[���f�b�h�ƂȂ�܂��B
�^�C���������������ƂƓ����Ȃ̂ł��̏�Ŏ��Ó��s���č\���܂���B
�i���������œ|��Ă���̂ɂP�ۂ֍s������Ȃ�Ă��ƂȂ��ł����)
�i5.10C�@�t�L�j�ɂ��A�{�ۑŖ��͎����̂悤�ɂP���͂���ȏ�̈��S�i�ی����F�߂�ꂽ�ꍇ�A���҂��s���̎��̂̂��߂ɁA
���̐i�ی����s�g�ł��Ȃ��Ȃ����ꍇ�́A���̏ꂩ���㑖���o�����Ƃ��ł��܂��B
���̂Q�P
�ŏ��̊ԈႢ
��
�^�s�t�G�����B�^�g�k�`�[���A�T�ԃo�b�^�[������Ƃ���A�U�ԃo�b�^�[�������Ă��܂��܂����B�U�ԃo�b�^�[�͎l���ŏo�ہB�V�ԃo�b�^�[���ŐȂɓ������Ƃ���ő���i�e�`�[����
�ŏ��Ⴂ�ɋC�����܂����B
���̏�̔��蓙
���̂܂܌p��
����������
�V�ԃo�b�^�[�ɂ܂�����������Ă��Ȃ��̂ŁA�T�ԃo�b�^�[�A�E�g�B�U�ԃo�b�^�[�ł������B
����̋��P
�ŏ��ԈႢ�͂߂����ɂȂ����߃��[���̋L���������܂��̂悤�ł��B�i�e�`�[���R�[�`�����������f������Ă����̂ł����A�R���c�A�O���E���h�ӔC�̔��f��
�i�߂Ă��܂��܂����B�m���ɏ������Ԃ�������܂����A���ׂĂ��画�肷�ׂ��������Ǝv���܂��B
�Ȃ��A�Ԉ���Ă���U�ԃo�b�^�[���܂��ŐȂɂ���ԂɋC�����Đ\��������̃J�E���g����T�ԃo�b�^�[���łB
���̂Q�O�@�Ƃ茾�S
�t�F�A�ȑԓx
�R������Ă��āA�C���������ł��B
�u�ŋ����ɓ������ăt�@�[������Ȃ����v�u�����o�E���h�ŕ߂��Ă��邶��Ȃ����v�u�{�[�����Ƃ��Ă��邾��v�u���ꂪ�Z�[�t����v�E�E�E
���ۃ~�X���Ă��鎞����܂��B���ǁA�䖝���Ă��������B
���������āA����ȃ��W����ꂽ��l�ł��A�肽���ł��B�i���S�҂Ȃ̂Łj�܂��Ă�܂��n�߂ĊԂ��Ȃ����������R���Ń��W��ꂽ���x�Ƃ���Ă���܂���B
�ēR�[�`�̕��͐悸���w�̌��U������߂����Ă��������B�Â��ɂȂ��Ă���^�C���������Ċē��u�m�F�v�����ɗ��Ă��������B�R���c�����c���铙����
���锻�����������ǂ���̃`�[�����i�C�ɓ���Ȃ���������܂��j�u�킩��܂����v�Ƃ����Ĉ��������Ă��������B
�q���������u����������������Z�[�t����Ȃ��́H�v�Ƃ������ł��傤�B�����[����������w������̂��ēR�[�`�ł��B
�q���ƈꏏ�ɂȂ��Ă͂����܂���B�q���������^�����܂��B
���̂P�X�@�Ƃ茾�R
�T�h���f�X
���ʉ������[��������T�h���f�X�i�T�h�����X�ł͂���܂���j�����̂ł����A��������Ƃ��Ȃ�Ȃ����Ǝv���܂��B
���̂��ƌ����ƁA���ʉ����̓t���C�j���O�܂��͎��Ԑ�Łh���������h�ɂȂ��Ă��鎞�ɂ���̂�����A���łɎ��Ԃ�
�����Ă���Ȃ킯�ł��B�����ŁA�_������₷���悤�ɂƁA�u�������ہv�u�ꎀ�Q�C�R�ہv�̂悤�Ȍ`�ł��̂ł����A
���ȏȂ̂Ń��`���N�`���_���������肵�܂��B�ǂ���ɂ��Ă����\����Ď��Ԃ�������܂��B�i�X�N�C�Y���s�Ń_�u���v���[�Ȃ�
�ő����I��邱�Ƃ��L��܂����j
���������āA�������܂ł͊ēR�[�`���ꂼ��Q�l���o�āI�u�S�{�̒�����P�̓�������������������v�ł����Ǝv���܂��B
�I��X�l�ɃN�W���������ā����������������Ƃ���Ƃ��������܂����A�N�������Ƃ��C�ɂ���̂ł����͊ēR�[�`�������ł��傤�B
�܂��́A�T�h���f�X�łR�l�U�����ē_���̑������i�������l�����͐l���Ɋ܂߂Ȃ��j�Ȃǂ��l�����܂��B
���̂P�W�@�Ƃ茾�Q
���Ԑ���
�싅�͂X��i���N�싅�͂V��A�T��Ȃǁj�܂łƌ����Ă��āA���̒��ŏ��s�����߂�̂ł����A�c�O�Ȃ���
�O�����h�̓s���Ȃǂłǂ����Ă����Ԑ���������Ď������s���Ă��܂��B
�����ŁA�������[���i���������Ȃ����[���j�̂悤�Ȃ��̂�����܂��B�i���̃��[���̐����͖ʓ|�Ȃ̂ł��܂���j
���̃��[���A�C�����͂킩��̂ł��B�������A���̃��[�����K�p���ꂽ�ꍇ�ɂ͂��̌シ�������Ԃ�������̂ł��B
���܂łȂ�A�ǂ̂悤�ȏꍇ�ł����łɎ��Ԃ��߂��Ă���Η��U���`�[�����t�]����Ύ����I���ł��B
�i��U�`�[���������Ă��ė����n�܂�O�܂��͍U���r���Ɏ��Ԑ�Ȃ炘�Q�[���j���_�ł������T�h���f�X�ɓ���܂��B
�������A�������[�����K�p��ԂɂȂ����ꍇ�͎��̕\�̉���s���܂��B�����Ő�U���ǂ����Ȃ���ΏI���B�������A���_�A�ċt�]����
�ꍇ�͍X�ɂ��̗������Ȃ���Ȃ�܂���B�����ŁA�āX�t�]����ΐ���ăT���i�������B���_�ŏI������ƃT�h���f�X�B
���Ԑ�̂��߂̃��[���Ȃ̂ɗ]�v�Ɏ��Ԃ�������̂ɂ͔[���������܂���B�������A�q�������ɂ��̃��[���͂킩�肸�炭�A
���̏ꍇ�A���H�T���i����������Ȃ��́H�������Ȏ����N���܂��B
��������A�P���Ԍo�������_�łT������Ă�����V��܂ł��B�S��\�Ȃ�T��܂łƂ����߂����������B
�������A�U��܂łɂ��Ď��Ԑ��������i�R�[���h����j�������Ǝv���܂��B
���̂P�V�@�Ƃ茾�P
���݂Ȃ�l
�悭��������K���Ɂh�ؐ��̃o�b�g��p�ӂ��邱�Ɓh�Ƃ����̂�����B
�ǂ����A�������Ă���Ƃ��Ɂu�����o�b�g�v�ł͊�Ȃ�����Ƃ������Ƃ炵�����A�͂����茾���B
�u���l�́A�����o�b�g�ł��낤���ؐ��o�b�g�ł��낤�����\�������ɗ����܂��B�v
�ǂ����̃o�b�g�ł��낤�������鎞�ɂ͗����A�������玀���o��ł��B�i�����Ă�����������́j
�́A�싅���Ă����I��̖X�q�̓V�ӂɗ������B�V�ӂɋ�����Ă��邩�痎�����ȂǂƂ���ꂽ�悤�ł����Ⴂ�܂��B
�O���E���h�Ȃǂ̕���ȂƂ���ɐl��Ȃǁu��яo�Ă�����́v�ɗ����₷���̂ł��B���̓V�ӂ����������Ȃ̂ł��B
������A�o�b�g�������Ă���i�Ō��p�����Ƃ��Ă��āA�o�b�g��������ɂȂ��Ă���Ƃ��j�ȂǂƂ����͍̂ň��ł��B
���N���͐�~�̃O���E���h�Ŏ�����Ă���Q�ێ�ɗ����Ă��܂����B�ē��u�o�b�g��ɑւ����Ƃ���ł����v�Ȃǂƒ��C�Ȏ������Ă��܂������A
�ɑւ��ăo�b�^�[�����������̂ł͂Ȃ��A���R�ɂQ�ێ�ɗ����������ł��B
���������炷���ɂ�߂�̂��B��̑�ŁA�̃o�b�g�������đ�����Ƃ����̂́u�����o��ł��v�Ƃ������Ƃł��B
���R����Ă�����ɂ��������Ƃ������܂��B
�������A�U�����ŋ߂��ɋ���l�����d���Ռ��܂������ɗ����Ă͍���̂ł��B
�l���Ă݂Ă��������B���������đI�肪�d���B�u�̃o�b�g�ɑւ��Ă���������͂Ȃ��ł��v�Ȃ�Ă������Ƃŋ����܂����H
���̂P�U�@����̂Q�i���[�V����
��
�Q�O�P�W�N�A���[�������ɂ�蓊���2�i���[�V�����ɂ��ċL�ڂ��Ȃ��Ȃ�܂����B
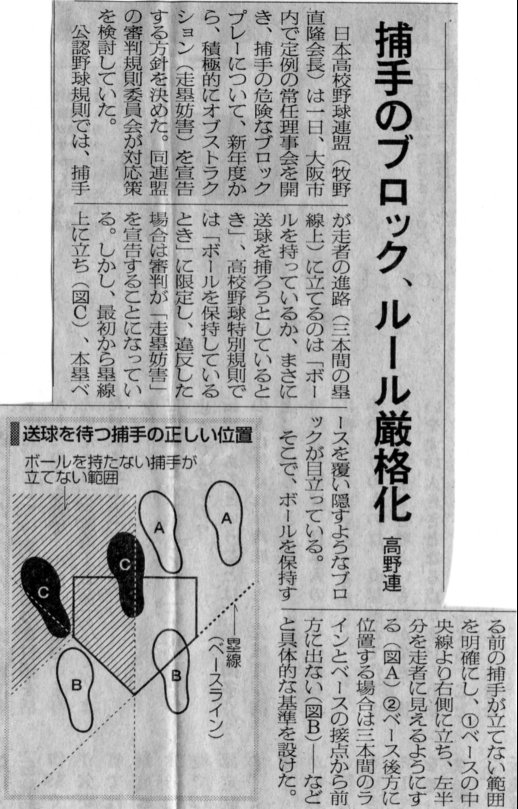
���̂P�T�@�ߎ�̃u���b�N�@
��
�ߎ�̃u���b�N�ɂ�鑖�ۖW�Q�����ꂽ�ۂɁA���������̍R�c�������Ό����邽�߁A
�����ɁA�����P�Q�N�R���Q���t�����V���f�ڂ̋L�����ڂ��܂��̂ŁA�W�e�ʂ͎��m����������Ǝv���܂��B
�Ȃ��A��{�I�ɂ̓u���b�N�͑��ۖW�Q������܂��B����́A���҂��ߎ�����N�싅�ȂǃA�}�`���A�ł͔���
�g�̂ɑ��Ċ댯�ȏɂ�����܂��B�_���������ł͂Ȃ��A�I��̉���h�~�̂��߂ł��B�����Y��Ȃ���
�w�������������B
���F�K���́u�܂��ɑ�����߂낤�Ƃ����Ƃ��v�Ƃ����̂��g����߂��Ȃ��l�ɂ��A���K�[�X��Q�����悤�ɂ��Ă����ꍇ�Ȃǂ�
�F�߂Ă���킯�ł͂Ȃ��l�Ɏv���܂��̂ł��݂��C�����܂��傤�B
���̂P�S�@�������m�Œɂ��I�@
��
�����i�[�Q�ہB�q�b�g���̂�����łQ�ۃ����i�[�͂R�ۂ��R�������A�Ȃ�ƃ{�b�N�X����o�Ă����R�ۃ����i�[�R�[�`�ƏՓˁB
���̏�̔��蓙
�A�E�g
���������f
���̏ꍇ�A�����i�[�R�[�`�͂R�ۂŎ~�߂����͖����A�P�Ƀ{�P�����܂��ĂԂ����������ł���̂ŁA
����s���ō\��Ȃ������B�i�Ԃ��������Ƃł��łɑ����Ă���)
�����i�[�ƃR�[�`�ł̖��ł͎��̍��ڂ��Y�����邪�A
(7.09i)���̏ꍇ�͑Ŏ҂܂��͑��҂ɂ��C���^�[�t�F�A�ƂȂ�B
(i)�R�ۂ܂��͂P�ۂ̃x�[�X�R�[�`�����҂ɐG��邩�A�܂��͎x���邩���āA���҂̂R�ۂ܂��͂P�ۂւ̋A�ہA���邢�͂����̗��ۂ�
���̓I�ɉ��������ƐR�������F�߂��ꍇ�B
���Ȃ킿�A�ڐG�����ł͂Ȃ��A���̓I�ȉ����i�Ȃ����������錾����^^;)���L�������ǂ����������B
����̓A�E�g�ɂ͂��Ȃ��ėǂ������Ɣ��f�����B
���ɁA�����i�[�R�[�`���~�܂���w�����Ă�����ڐG���������ŃA�E�g�Ƃ���邾�낤�B(�قƂ�lj��������Ƃ�)
���̂P�R�@�C��t���ā@
��
�����i�[�Q�ہB�������ˏオ�����{�[����ǂ��������V����ƂQ�ۃ����i�[���Ԃ������B�{�[���͍������ˏオ���Ă���
���炩�ɓ͂������ɂ͖����B
���̏�̔��蓙
����W�Q�ŃA�E�g
���������f
���҃A�E�g�ł����ł��傤�B
���̏ꍇ���҂̓A�E�g�ɂȂ�܂��B
���҂��E�E�E�܂��͑ŋ����������悤�Ƃ��Ă�����̖W���ɂȂ����ꍇ
�t�F�A�A�t�@�[���̋�ʖ����A�ŋ����������悤�Ƃ��Ă�����̖W���ɂȂ����ƐR�����ɂ���ĔF�߂�ꂽ���҂́A
���ꂪ�̈ӂł����������������̋�ʖ����A�E�g�ɂȂ�B(7.08b�@�����P)
�����P������Ƃ��Ȃ茵�����̂�����܂��B�t�@�[���{�[���ł��_���ł��B
���̉��߂ł́A�{�[�����߂�邩�߂�Ȃ����ł͂Ȃ��A���͑ŋ��ɑ��ďW�����Ă��胉���i�[�܂ŋC�����܂���B
�ł������҂͖���ŋ����m�F���đ���܂��̂ł悯��`��������A���̂��ƂŏՓ˂Ȃlj�����A����ʉ����h�����Ƃ��o�����
�l���܂��B
�Ƃ茾
�A�E�g�ɂȂ��đŖo�����Ă͊�������Ȃ��B�C�����悤�B
���̂P�Q�@�I�C�I�C�I�@
��
�����i�[�Q�C�R�ہB�ɂ�������炸�Q�ۃ����i�[����^^;�@
����Ă��R�ۃ����i�[�́A�_���_���Ƃ��������łQ�ۃ����i�[����ŐÎ~�������B(��Ŏ~�߂��Ƃ�����)�ŁA����ĂĖ߂��Ă������B=3=3
���̏�̔��蓙
���ɖ����B
���������f
�Q�ۃ����i�[���R�ۃ����i�[��ǂ��z���Ă͂��Ȃ��̂Ő���s���ł����ł��傤�B
(7.08h)��ʂ̑��҂��A�A�E�g�ƂȂ��Ă��Ȃ��O�ʂ̑��҂ɐ���ꍇ�B�i��ʂ̑��҂��A�E�g)
�u����ꍇ�v�ɂ��Ẳ��߂͂͂����莦����Ă��Ȃ����A���炩�ɐ�s�����ƐR���������f������Ƃ������Ƃł�����ł��傤�ˁB
���̂P�P�@�{�[�N�H�@
��
�P�ۃ����i�[�����邽�߃Z�b�g�|�W�V�����ł̓����B�i�������j���肪�X�g���b�`�ɂ͂���Z�b�g�|�W�V�������Ƃ������Ƃ�Ȃ��������Ȏ���
���R�ȑ����P�ۂɓ��ݏo���ĂP�ۂ����s�����B�i�����͂͂����Ă��Ȃ��j���āH
���̏�̔��蓙
���߂��炵���̂Œ������E�E�E���݂܂���f�O���܂���
���������f
�{�[�N�ł͂Ȃ������Ȃ��ł��B���̏ꍇ�ŏd�v�ȓ_�́A���R�ȑ����ǂ̂悤�ɂ������ł���A�Z�b�g�|�W�V�����Ŏ~�܂������ǂ����͂��ł�
���W�ł��B
�{�[�N�ɂ͂P�R���ڂ����Ăb���Ɂu����ɐG��Ă��铊��͂��A�ۂɑ�������O�ɁA���ڂ��̗ۂ̕����ɓ��ݏo���Ȃ������ꍇ�B�v(8.05c)
�Ƃ���܂��B���Ȃ킿�A�ۂɓ��ݏo���Ă��Ȃ��ƃ{�[�N�ł����A����͓��ݏo���Ă���̂łn�j�ł��B�i�Q�l����E�����p��(8.01b,c)
�j
���ɃZ�b�g�|�W�V�������Ƃ������_�Ŏ~�܂������ǂ������d�v�ɂȂ�̂͑Ŏ҂Ɍ������ē�������Ƃ��ł���B(8.05��)
�Ƃ茾
�{�[�N�Ȃ�ĒN���l�����I
���̂P�O�@�B���_�}���ǂ��@
��
���ۂő��҂͂R�ۂ֓��B�B���������Ă������߃��t�g���łR�ێ�͑�����߂����B���炭���ĂR�ۑ��҂��ۂ𗣂ꂽ�Ƃ����
�R�ێ肪�^�b�`���A�E�g��鍐���ꂽ�B
���̏�̔���
����s���̒ʂ�B
���������f
���[����ł͉B���������Ă͂����Ȃ��ȂǂƂ������Ƃ͂Ȃ��̂ł����A���N�싅�Ȃǂł͔�X�|�[�c�}���I�v���[�Ƃ���
�F�߂Ȃ��̂����ʂ��Ǝv���܂��B�R���͑���������ăv���[����i���������_�ł����ɓ���ɕԂ��Ȃ��悤�ł����
�B���B���Ȃ��ɂ�����炸�ԋ��𑣂��ׂ��ł��B�t�ɓ��肪����ߕӂɂ���ꍇ�͕���킵���v���[�Ń{�[�N���Ƃ邱�Ƃ��o���܂��B(8.05i,f)
�ǂ���ɂƂ��Ă������������Ƃ��Ȃ��悤�ɐR���͒��ӂ��Ă��������B
�Ȃ��A�����܂Ńv���[���~�܂������ł���A���҂��I�[�o�[�������Ă���Ƃ��Ƃ��̓v���[�ɂȂ�܂��B
�������A�U�����̃����i�[�R�[�`�A���҂̓{�[���̍s���ɒ��ӂ�ӂ��Ă͂����܂���B
�⑫
�{���u�B�����v�Ƃ͖��炩���x�����Ƃ���ӎv�����̃v���[�ł���ƍl���܂��B
���Ă�����̂ɓ���̋U��������̂P�ۑ����̋U���i�R�ۑ��҂�����Ŕ�яo���ėU���o�����j������܂��B
���̈Ⴂ��������Ƌ����Ă��K�v������Ǝv���܂��B
���̂X�@�₶�@
�ȑO����ϐ�A�R�����Ă���Ƃ��ɋC�����Ă���̂��u�₶�v�B���́u�₶�v�͂������ł����A
�ĊO�C�����Ȃ���Ȃ�Ȃ��̂��A�w����|�����Ȃ̂ł��B�ēA�R�[�`����Ă�����X�͑��
�싅�o���҂ŁA���싅�Ȃǂ�����Ă��邩�Ǝv���܂��B���̂Ƃ��ɉ��C�Ȃ��u�₶�v�Ȃǂ����Ă���̂ł����A
���ꂪ�������N�싅�̏�ł�����o���Ă��܂��܂��B�ׂ����悤�ł������N�싅�̏�ł͂����ӂ��������B
�܂��A�R���A�O�����h�ӔC�ҁA�ēR�[�`�͂����ɂ��ċC�z������肢�������܂��B
�P�A���炩�Ɏq���̎�_��˂��悤�Ȃ���
��j
�L���b�`���[���ア����ǂ�ǂۂ���I�E�E�E�E�u�ǂ�ǂۂ���v�ł���
���̃o�b�^�[�łĂȂ�����ǐ^�s���B�E�E�E�E�u�ǐ^�s���v�ł���
���̃o�b�^�[�O�U�ˁ[(�I��̊|�����j�E�E�E�E�����ȂƂ���ł�
�s�b�`���[�A�m�[�R���ˁ[�E�E�E�E����̓_��
�Q�A����ɑ���s����R�c
��)
���̂P�ېR������������ˁ[���H�E�E�E�E�_���ł�
�^�C�~���O�����Ŕ��肵�Ă邶��ˁ[�H�E�E�E�E�_���ł��B
�s�b�`���[(�Z�b�g�|�W�V�������j�~�܂��Ăˁ[��I�E�E�E�E�����Ɗē����R���Ɋm�F�ɗ��ĉ������B
���ꂪ�X�g���C�N����I�E�E�E�E�u���̐R�������̓X�g���C�N��邼�v�Ȃǂ��܂������Ă݂ĉ������B
���̃y�[�W�̖`���ɂ�����܂����A�R�����͕K�������R���̐S��������l������Ă���Ƃ͌���܂���B
���߂Ă̐l�ȂǕs����Ȑl���S�����Ă��邱�Ƃ�����Ǝv���܂��B���������Ƃ��Ɍ��������W�����ł��܂��Ǝ�����C��
�Ȃ��Ȃ��Ă��܂����Ƃ��l�����܂��B�����̃`�[���̐R�����������悤�Ȗڂɂ����Ă����C�����͂��Ȃ��ł��傤�B
�m���Ƀ~�X�W���b�W���Ȃ��Ƃ͌����܂���B�������ēR�[�`���������Ƃ͎q���������^�����܂��B���炦�Ă��������B
�R�A�����c�̊���
���[�[�I���ł��ꂪ�A�E�g�Ȃ́[�H�i���ꂳ����ɑ���)
����̗������œ_���������Ƃ��̑呛���B�E�E�E�E�C�����͂킩��܂������Ƃ����q���̂��Ƃ��l����
�t�Ƀt�@�C���v���[�Ȃǂɂ͓G�����Ȃ����肵�Ă����Ă��������ˁB
���̂W�@���������I�@
��
���ۂœ���͑O�i����̐��B�ł����ŋ��͂����炦�����̃V���[�g�S���B�Ǝv�������g���l���B�ƁA���̌���𑖂��Ă������҂̑��ɓ������ă��t�g���߂������A�S���i�ۂ����B��������瑖�҂̑��ɓ������Ă���̂����瑖�҃A�E�g�ł͂Ȃ����ƍR�c�������B
���̏�̔���
����s���̒ʂ�B
����������
�ʏ�ł́A���҂ɑŋ������������ꍇ�A���҂̓A�E�g�ł���B�i7.08f�j
���������̏ꍇ�͗�O�K�肪����A�i5.09f��O�j�A�E�g��鍐���Ă͂Ȃ�Ȃ��Ƃ���B
�i�P�j������������̐G�ꂽ�t�F�A�{�[���ɐG�ꂽ�ꍇ�B
�i�Q�j�P�����ɐG��Ȃ��ł��̌ҊԂ܂��͑�����ʉ߂����ŋ��ɂ��̌���ŐG��Ă����̃{�[���ɑ���
�@�@�@���̂�����̓������������@����������ƐR���������f�����ꍇ�B
����͂���(�Q)���K�p�Ƃ���A�{�[���C���v���C�ł���B
�NjL�@�i�Q�j�ɂ���h�ҊԂ܂��͑����h�͌���ł���A���(����)�͊܂܂�Ȃ����Ƃɒ��ӂ��K�v�ł��B
���P
�߂����͕̂߂�Ȃ��Ƒ�������B
���̂V�@��ł��@
��
�Q�X�g���C�N��A�C���R�[�X�̓�����ł��ɂ�����(�X�C���O����)�������炵�Ęr�őł����悤�Ȃ̂����A�ŋ��͂P�ې���]����t�F�A�{�[���łP�ێ肪�߂�x�[�X��
�A�E�g�ƂȂ����B�U�������瓊�����g�̂ɓ������Ă��邩��{�[���f�b�h�ł͂Ȃ����ƃA�s�[�����������B
���̏�̔���
����s���̒ʂ�B
����������
�O�܂��͂P�X�g���C�N�̏ꍇ�A�u�X�g���C�N��i2.72e�j
�Q�X�g���C�N�̏ꍇ�A�u�A�E�g�v(���̏�Łj�i6.05f�j
����̏ꍇ�A���ʂ̓A�E�g�ł悩�������A���ۂɂ́A�{�[���̂�����ɂ�����炸���̏�ŃA�E�g��鍐���Ă悩�����B
�Ƃ茾
�ɂ��v���܂ł��đ呹���ȁB�łׂ����̂őłƂ����B
���̂U�@�����I���I�@
��
�����Ă����U�`�[���̍U��(�T��)���I�����A�������Ԃ��c��Q���B���K���ł́A�h�W�O�����߂��ĐV�����C�j���O��
����Ȃ��h�Ƃ����K���B�����ŁA���̉�(�U��\)�̓������K���Ɂu���Ԃ�������Ȃ��H�v�Ƃ�����U�`�[���̍R�c��
��R���u�W������������B
�o���̌�����
���R�͂U��\�́u�v���C�v��������O�Ɏ��Ԃ������̂Łu�W������������B(�T��I�������ԑO�͔F�߂�)
��U�`�[���́A�T�̏I��(�R�A�E�g����)�������Ԃ��W�O�����O�Ȃ̂�����U��ɂ͂���ׂ��Ǝ咣�B
�i�����A����̂悤�Ƀv���C�O�Ŏ��Ԑ�ɂȂ�̂ł���Γ�����ȂǂŎ��ԉ҂����邱�Ƃ��\�ɂȂ��Ă��܂��j
����
���[����̉��߂ł́A��U�`�[���̍l�������������悤�ł��B
�������A����̂悤�Ɏ�R���u�W����������Ă��܂����ꍇ�A�����̌��茠����R�������Ă���ȏ�i���̐ӔC�҂��s��
�Ȃ̂�)�A����ɏ]�����Ƃ��܂����[���̏���ɂȂ�Ǝv���܂��B(���̎����͂R�l�̗ېR�����`�[������̏o��������
���߂ɋ��c���o���Ȃ������j
����̑Ή�
�s���F�R���̑ł����킹�ł��b���������悤�ɁA�����I�����Ԃ��߂Â��ė�����A���߂ɗ��`�[���ɑ��A
�u���̉�ōŏI��Ƃ��܂��v�Ƃ��A�u���̉�ŏI���ɂ���ꍇ������܂���Ȃǂ̃A�i�E���X�����Ă���
���Ƃ��d�v�ł��B����̑��̋K���́A�����悻�X�O���̎������Ԃ�z�肵�āA�W�O���ŐV�����C�j���O�ɓ���Ȃ��Ƃ���
���Ƃɂ��Ă���̂ł����āA�W�O���ŏI��点��Ƃ����K���ł͂���܂���B�������A���̂悤�ȃA�i�E���X�������
���͂����Ȃ������Ǝv���܂��B���̑��ł͂����悻�X�O�����ŏI��点��悤�ɍl���Ă��܂��B
���̂悤�Ȗ��́A�_�������Ȃ����������������ȏꍇ�ɋN����̂ŕ����Ă���`�[���͂��Ƃ�藼�`�[���Ƃ��_�o��
�ɂȂ�̂ŁA���R�E�ӔC�҂͎����̏I���ԍۂ͏��f�悭�����̏I���ɑ���A�i�E���X������ׂ��ł��傤�B
�܂��A�����ɂ͏o���邾���A���̃O�����h�ӔC�҂����邱�Ƃ��]�܂����Ǝv���܂��B
���̂T�@��ʓ��_
��
�^�Ẳ��V���̒��̎����A�A�E�g���Ƃꂸ�A�P��ɂQ�O�_�ȏ�����Ă��čU�����Ԃ��S�O�����z���Ă����B
�Q����I����ĂT�T�_����A���Ԑ�ƂȂ������A�������͂P�T�O�����z���A����͗ܖڂɂȂ��Ă����悤�������B
�ēɂ͓��������P�Q�O�����z���Ă���̂ŎQ�l�ɂ���悤�ɂƍ��������A�^�C�����|�����A�����������B
����̑Ή�
���������܂ōl���ċ��Z�K���͍���Ă��Ȃ��̂ŁA��͂肻�̏�̐R���c�A�O�����h�ӔC�A���`�[���̊ē�
�Ώ����Ȃ�������Ȃ��̂ł��傤�B
�܂��A���[�J�����[���ő�ʓ��_�Ⓑ���ԍU���i����j�A�������ߑ����R���g���[�����邱�Ƃ��K�v�ł��傤�B
���ɂ���Ă͂V�_���[���i�P��̍U�����V�_�ɂȂ�ƍU���ցj��K�p���Ă���B���ꂾ�����ƕs�s���ȏꍇ������̂�
���ǂ��K�v�ƍl���܂��B
�V�_���[���̉��ǔł��l����!
���̂S�@��Ȃ��Ƃ�����
��
�^�Ẳ��V���̒��ł̎����B�����͈���I�Ŏ�������Ȃ��Ȃ��A�E�g����ꂸ���Ȃ蒷���Ԏ�������Ă���B
���ۂ̂Ȃ��A������ꂽ�{�[���̓����o�E���h�ƂȂ�ߎ�͕߂肻���Ȃ�����Ƀm�h�ߕӂɓ��Ă������Ă����B
�{�[���͕ߎ�̖ڂ̑O�ɂ��������ߎ肪���ɍs���Ȃ��̂łR�ۃ����i�[�̓z�[���֑����Ă����B
���̏�̔���
�P�ېR���͂����Ƀ^�C������胉���i�[��߂��āi�ߎ�̎��Â����āj�ĊJ�B
���荪��
�P�A���V���̒��ł̒����Ԃ̎���ł��Ƃ��Ƃ悭�Ȃ��ŋN�����B
�Q�A���炩�ɕߎ�͓����Ȃ��Ȃ��Ă����B
�R�A�]�������{�[���͕ߎ�̖ڂ̑O�ɂ���A�ʏ�ł̓z�[���ɓ˂����ނ��Ƃ͍l���ɂ����B
�ȏ�R�_�����i5.10c�j�˔����̂ɂ��v�����[���v���C�ł��Ȃ��Ȃ邩���邢�́E�E�E�E�E�i�ȉ��ȗ��j��K�p������
�������Ƃł悢�̂ł͂Ȃ��ł��傤���B
�⑫�P
�����ő厖�Ȃ��Ƃ́A�u�q���̐g�̂��ŗD��ł���Ƃ������Ɓv
���ɁA�ߎ肪�߂葹�˓��������{�[���𓊎肪���ɍs���z�[���֑���Γ��_�͖h�����̂�����
�^�C�����|���Ȃ��̂������̂ł͂Ȃ����Ƃ����ӌ������邩�Ǝv�����A���N�싅�ł͂��ꂪ�ł����
�����̂����A���̏ꍇ�ߎ肪�|��Ă��܂������ƂɋC���s���Ă��܂����]���Ă��Ė싅�ǂ���ł͂Ȃ��Ȃ��Ă���B
������~�߂�̂͐R���ȊO�ɂ͂��Ȃ��̂ł���B
�⑫�Q
���ɂ��̏ꍇ�ŁA�]�������{�[���̓o�b�N�l�b�g�����֍s���Ă��܂����Ƃ��āA�ߎ肪�܂����������Ȃ������Ƃ�����ǂ������炢�����B
�����~�߂Ă��܂��āA�ߎ�̎蓖�ĂȂǂ�����A�{�[���̍s�����R���c�ŋ��c���ă����x�[�X��^����Ȃǂ��Ă͂ǂ����낤�B
�܂��A��l���҂��ĂȂ����ς��Ȃ��悤�ł�������Ń^�C�����|���Ă������Ǝv���B���f�Ƃ��ẮA�ߎ肪�������������ǂ��Ȃ����̂�����ɂ���ׂ����ƍl����B�����l�̂��錄�ɓ��_���悤�Ƃ���l���́A�X�|�[�c�}���V�b�v�ɔ�����Ƃ����F���ł������ł��傤�B
���̂R�@�@���v���[�I�i������k�ҁj
��
�Q�X�g���C�N��
�Ŏ҂��X�C���O���ă`�b�v�ƂȂ����ŋ����ߎ�̃}�X�N�Ɍ����ɋ��܂����B
���̏�̔���
�t�@�E���{�[���i�ʂɍR�c�͖����������j
����������
�t�@�E���{�[��
�}�X�N�ɋ��܂����ꍇ�͐��K�̕ߋ��ƂȂ�Ȃ��̂Ńt�@�E���{�[���ƂȂ�B
�⑫
�����A��U��i�������j��������U�蓦����ԂɂȂ�̂ŁE�E�E�E�ǂ�������ǂ��ł��傤�B
�U�蓦����Ԃł���A1�̐i�ۂ��^������B�U�蓦����ԂŖ����ꍇ�͎O�U�B�i6.05b�c�j
����̋��P
�}�X�N�ɋ��܂�Ȃ��悤�ɋF��܂��傤�I
���̂Q�@���߂�X�N�C�Y
��
�����A�R��
�Ŏ҂̓X�N�C�Y�����s�B�R�ۑ��҃z�[���C���A�Ŏґ��҂͓��S���łP�ۃA�E�g�ɂȂ������A�Ŏ҂��o�b�^�[�{�b�N�X��
���݉z���ăo���g���Ă����Ƃ������Ŕ����Ō��B���āE�E�E�H
���̏�̔���
�R�ۑ��҂̓X�N�C�Y�ł̑Ŏ҂̎���W�Q�Ƃ������ƂŃA�E�g�B�Ŏ҂͌����ɃA�E�g�ɂ���Ă���̂ł�͂�A�E�g�Ń_�u���v���[�B
����������Ə���
�R�ۑ��҂̓X�N�C�Y�ł̑Ŏ҂̎���W�Q�Ƃ������ƂŃA�E�g�B����͐������B�i6.06c)���������̌�̏����ɖ�肪����B
�Ŏ҂͖߂���A�X�N�C�Y�̃v���[�̓m�[�J�E���g�Ƃ��ăX�N�C�Y�������̃J�E���g�ōĊJ����B
�Ⴆ�A�P�|�Q�ŃX�N�C�Y���Ă��̃v���[���N�����ꍇ�́A�܂��P�|�Q����ł������ƂȂ�B�i7.08g�A���j
�⑫
�P�D�X�N�C�Y���悤�Ƃ��ē��݉z�������A�o�b�g�Ƀ{�[����������Ȃ������ꍇ�͎���W�Q�ɂ͂Ȃ�Ȃ����Ƃɒ��ӂ��A�X�g���C�N�A�܂��̓{�[���̔��������B�Q�X�g���C�N��̏ꍇ�͒��ӂ��K�v�ł���B�i7.09a�j
�Q�D�X�N�C�Y�����{�[����ߋ����R�ۑ��҂��A�E�g�ɂ����ꍇ�͎���W�Q�������������̂Ƃ����̌�̃v���[�͐���s���ƂȂ�B�i6.06c�A���j
�R�D�X�N�C�Y�����ۂɂ͖��͖����A�Ŏ҂�����o���ăo�b�^�[�{�b�N�X���o���Ƃ���őŋ��ɐڐG�����Ƃ��́A
�Ŏ҂͂��łɑ��҂ƂȂ��Ă���A���҂̖W�Q�Ƃ������ƂƂȂ�Ŏґ��҂��A�E�g�B�R�ۑ��҂��܂ޑS���҂͂��Ƃ̗ۂɖ߂����B�i7.08g�A���R�j
����̋��P
�X�N�C�Y�v���[���s����ɉ����Ă͋��R�A�ېR�̓v���[�ɑ��Ŏ҂̑����A�ߎ�̑Ō��W�Q�A�ߓx�ȃu���b�N�ȂǍX�Ȃ钍�ӂ��K�v������B�܂��A���_�����邩����Ȃ����̑厖�ȏ�ʂł̔���ƂȂ�̂ŁA���m�ɂ����₩�ȑΉ������߂���̂Ŗ싅�K�����ō���x�m�F�������Ɨǂ��ł��傤�B
�Ƃ茾
�X�N�C�Y�����{�l����Ȃ��ĂR�ۑ��҂��A�E�g�ɂȂ邩�畁�ʂ̃~�X�ɔ�ׂĔ��͏d���B���R�̌����ꂩ���ˁB
���̂P�@�@���̃z�[�������H�i�����Łj
�O���E���h
�H�����i�����F���C�g����L���a���_�C���N�g�ʼnz����ƃz�[�������A�����o�E���h�œ���ƂQ�x�[�X�A���Ȃ��j
��
�A�E�g�J�E���g�s���A���Җ����B�i�����Â�����ׁ̈B���ʂɔ���ɊW�Ȃ��j
�ŋ��͑傫�����C�g�����ɏオ��E����͔w�����D�߂������A�����ő����ĕߋ������܂܂k���a���z��
�z�[�������]�[���ɓ����Ă��܂����l�Ɍ������B�i�ߋ����_�ł̓t�B�[���h���Ƃ���O�Ƃ��������j
���̏�̔���Ɛ���s��
�܂��Q�ۗېR�̓A�E�g��邵���B�i�Ƃ肠�����_�C���N�g�ŕߋ������̂Łj���̌�A�U��������z�[�������]�[���ɓ����ĕߋ������̂�����
�z�[�������ł͂Ȃ����ƍR�c���������B
��R���Q�ۗېR�ɕ߂����ʒu���m�F�����Ƃ����O�ł���Ɛ邵���̂ŁA����̓z�[�������ƂȂ����B
�������A������͐�ɃA�E�g�Ɣ��肵�Ă��邱�ƂƁA�ߋ������ʒu�������Ȃ��Ɓi�t�B�[���h���ƌ����Ă��s���R�ł͂Ȃ������j������A
�[�����s���Ȃ��B
����������i�����j
�Q�ۗېR���ߋ��ʒu����O�ł���Ɗm�F���Ă���ȏ�A�ߋ����Ă͂��邪�z�[�������ł���B
�⑫�P
�������A�t�B�[���h���ŕߋ����Ă���A�E�g�ƂȂ�܂��B
���Ȃ݂ɁA�����E�ꎀ�Ń����i�[�������ꍇ�A�t�@�[�����̕ߋ���Ƀt�F���X���z������A�x���`�ɓ����ē|�ꂱ�ꍇ
�����x�[�X���^�����܂��B�i�|�ꂱ�ꍇ�Ƃ����̂������ł��B�|��Ȃ���Η^�����܂���B�j�i7.04c�j
�⑫�Q
�����P�R�N�x�̐\�����킹�ɂ��A�H�����O���E���h�ł͂ǂ��ŕߋ����Ă��A�E�g�Ƃ���O���E���h���[���ɂȂ��������ł��B�i�����O���E���h�ׁ̈j
�ӂ�
����O�̋L���ɂ͏d��Ȏ����F��Ɍ�肪����A�W�e�ʂɂ����f���������������܂����B
����A���R�ɂ��̎����̎�R�̕��Ɖ�@�����A��͂肻�̎��̎��͂悭�����Ă���ꂽ�ׁA�m�F���邱�Ƃ��o���܂����B���肪�Ƃ��������܂����B

Copyright(c) 2004 Kazuo Nishimura All Rights Reserved.
20/feb/2004 BY.KAZUO