 神格化した”神” 風神・雷神像 神格化した”神” 風神・雷神像 |
[年代] 鎌倉時代中期 建長~文永年間(1249~1274)
[法量] 桧寄せ木つくり 木造彩色 像高:風神112cm 雷神99.8㎝
[作者] 湛慶統括
[所蔵] 三十三間堂蔵
[解説] 風神・雷神像 国宝
インド最古の教聖典「リグ・ウエーダ」に登場する神で、自然現
象を”神格化”した原始的神。
風神は数頭立ての馬車で天を駆けて悪神を追い払い豊貴栄達を
授ける神。雷神は水神の神。仏教では仏法を守る役目で悪を懲
らしめ善を勧めて、風雨を整える。
(文:三十三間堂の公式ホームページより)

|
 神格化した”神” 風神・雷神屏風 神格化した”神” 風神・雷神屏風 |
[年代] 江戸時代 17世紀
[法量] 紙本金地著色 二曲一双 横154.5㎝ 縦169.8㎝
[作者] 俵屋宗達筆
[所蔵] 建仁寺蔵
[解説] 風神雷神図 国宝 雷神拡大
三十三間堂の風神雷神像や、江戸期になって、 「北野天神縁起絵」
(弘安本系)が流布をする。これらを抜き取って屏風にした俵屋宗達。

 神格化した”神” 風神・雷神屏風 神格化した”神” 風神・雷神屏風 |
[年代] 江戸時代 18世紀
[法量] 紙本金地著色 二曲一双 横181.8㎝ 縦164.5㎝
[作者] 尾形光琳筆
[所蔵] 東京国立博物館蔵
[解説] 風神・雷神屏風(光琳模写) 重文 雷神拡大
風神・雷神はもともと千手観音の眷属で、他の二十八部衆ととも
に尊崇された。これは宗達の最高傑作を光琳が模写したもの。

 神格化した”神” 風神・雷神屏風 神格化した”神” 風神・雷神屏風 |
[年代] 江戸時代 文政3年(1820)頃
[法量] 紙本金地著色 二曲一双 横170.2㎝ 縦170.7㎝
[作者] 酒井抱一筆
[所蔵] 出光美術館蔵
[解説] 風神・雷神屏風(酒井模写) 雷神拡大
風神・雷神はもともと千手観音の眷属で、他の二十八部衆ととも
に尊崇された。これは光琳の模写を酒井抱一が模写したもの。

 神格化した”神” 風神・雷神図 神格化した”神” 風神・雷神図 |
[年代] 鎌倉時代 承久元年(1219)
[法量] 1幅、絹本着色、縦81cm・横41cm
[作者] 不詳
[所蔵] 北野天満宮蔵
[解説] 北野天神縁起絵巻(承久本) 清涼殿霹靂時平抜刀 雷神拡大
図は、清涼殿に壮絶な稲妻がたてつづけにおこり左大臣藤原時
平は独り太刀を抜いて天神となた菅公に睨みながら語りかける
場面である。
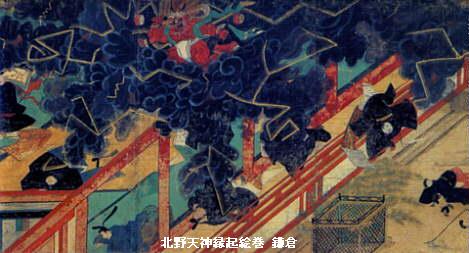
 神格化した”神” 風神雷神図 神格化した”神” 風神雷神図 |
[年代] 近世初期
[法量]
[作者] 不詳
[所蔵] 京都府 常照皇寺蔵
[解説] 天神縁起絵巻 風神雷神図 雷神拡大
図は、右端の風神によって暴風雨が惹起きされ、お召しのかか
った尊意が洪水の中を禁裏へ急ぐ。風神雷神を一画面で描いた天
神縁起は他にもあったと思われる。宗達はこの種の絵巻物から着
眼したと考えられています。
