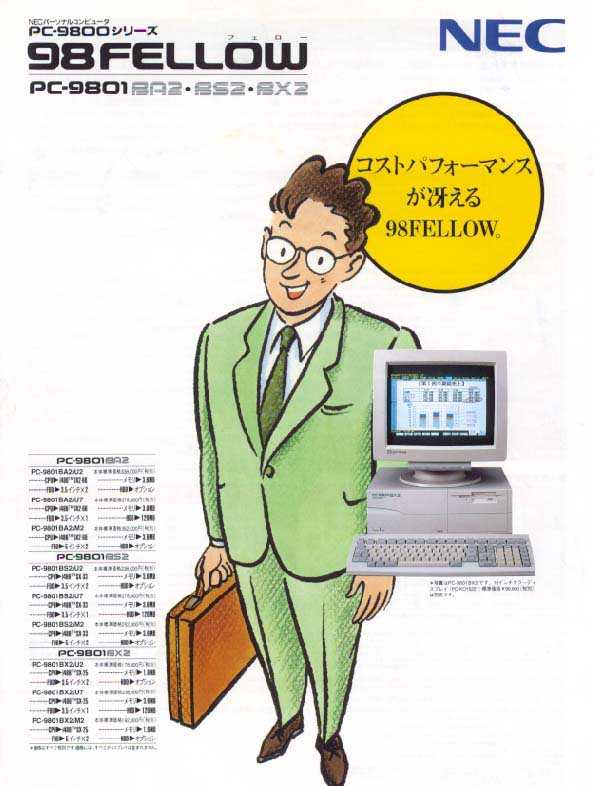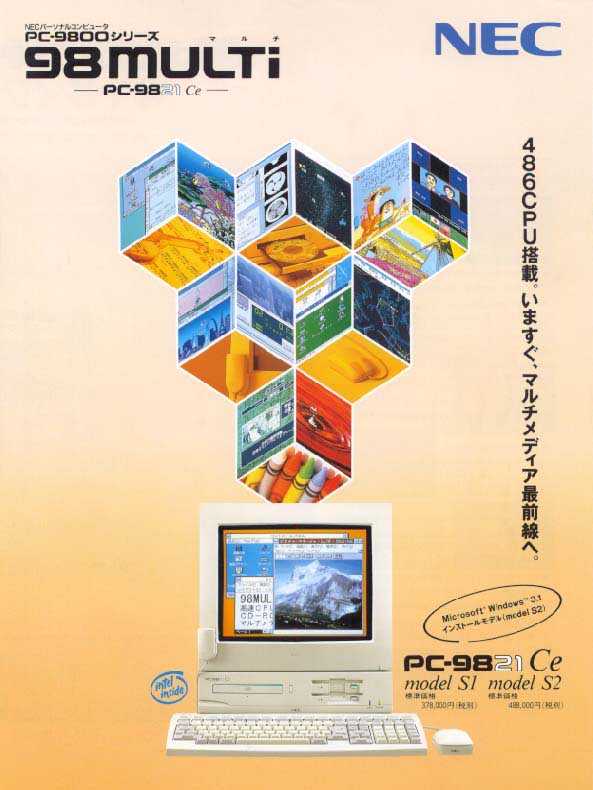月刊
98パンフレットマガジン
1998年2月号(第二号)
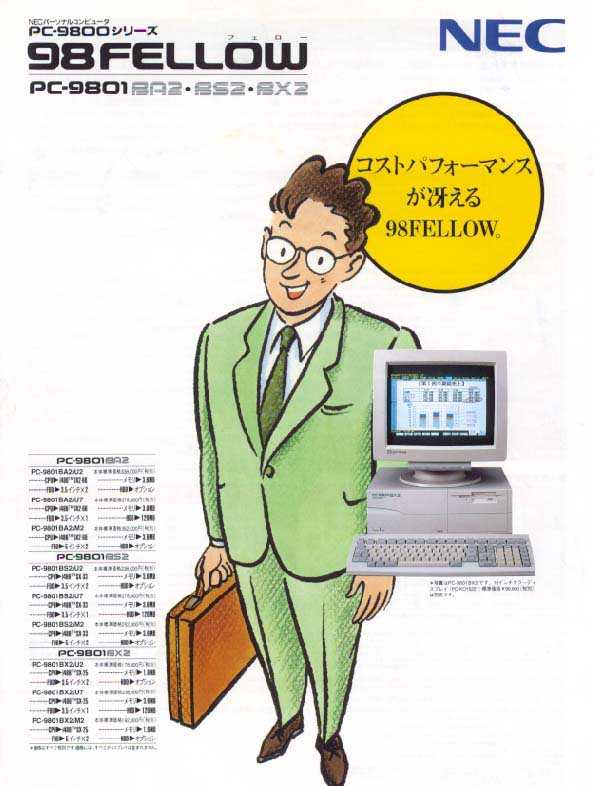
NECが本格的にコストダウンして、世に送り出した98FELLOW。その圧倒的なコストパフォーマンスを更に向上させ、ラインナップを豊富にしたのが、BA2、BS2、BX2です。
それぞれi486DX2(66MHz)、SX(33MHz)、SX(25MHz)を搭載し、一番下位のFDDモデルを除き、メモリを標準で3.6MB搭載させました。もっとも安いもので178,000円でした。このモデルから現在のPC-9800シリーズと同様に、専用メモリボードを廃止し汎用SIMMソケットを採用、新たにファイルベイ機器を内蔵可能とし、内蔵HDD共々IDEインターフェイスを採用しました。その他に、GDCとVRAM間のBusを32bit化したり、プリンタポートの形状が現在と同じものになりました。また、メモリの上限14.6MBも廃止され、このモデルがWindows95を実用レベルで使用可能なボーダーラインと言えるでしょう。もちろんCPU等をパワーアップさせてですが。

高性能、高機能型Windowsマシンとして登場した98MATEの第二シリースです。
ラインナップは98FELLOWとほぼ同じですが、高性能サウンド機能や32bit拡張バスを搭載したり、640×480(256色)をサポートしたり、Windows仕様が標準になっていました。また、上位クラスにはCDドライブやWindowアクセラレータ(86C928)を標準で搭載していモデルもありました。CPUソケットにSocket3を採用したのもこの時でした。但し、内蔵機器のインターフェイスはIDEではなく、SCSIを採用し、ファイルベイもNEC独自のファイルスロットと呼ばれる専用のものでした。当時は良かったのですが、現在ではIDE(バルク品等)を主流とするため、この点が仇となっています。メモリは標準でFDDモデル以外は5.6MB以上(CPUボード上のSIMMソケット)搭載していました。

低価格でWindows環境を使うことができる、98MATE
Bシリーズです。
全モデルとも標準でメモリ5.6MB、HDD120MB以上、Windowアクセラレータ(GD5428)、マウス等をオールインワンモデルとなっていました。もちろんWindows3.1もインストール済み。98MATEシリーズの中でも意外と売れたシリーズでした。筐体やハード仕様は基本的に98FELLOWと同じで、マザーボードもコストダウンのため同じものが使用されていました。マザーボードについては若干相違点があり、Windowアクセラレータが搭載されている事、SIMMソケットが一つ多い(3つ)事、そしてCPUソケットにSocket3を採用してる事です。
※98MATE Bシリーズ裏話。98MATE
BシリーズはもちろんPC-9821シリーズですが、PC-9821専用DOSゲーム(いわゆる256色専用)ではBシリーズは必ず除外されています。理由は簡単で、上記で述べた通り98FELLOWとマザーボードが同型のせいです。256色専用DOSゲームはGDC(256色用)と呼ばれるPC-98専用VGAを使用しているため、それを搭載していないPC-98(PC-9801、98FELLOW)ではできません。つまり、Windowアクセラレータを搭載していても、256色専用DOSゲームでは意味がありません。一応、一部の256色専用DOSゲーム(アリスソフト等)ではWindowアクセラレータに対応していました。PC-9821シリーズで唯一256色用GDCが搭載されていませんでした。

日本で初めてPentiumを搭載して発売されたパソコン、PC-9821Afの後継機がPC-9821Bfです。
Pentium(60MHz)、セカンドキャッシュを256KB搭載し、メモリとHDDの容量を多少増量しましたが、ハード仕様は通常のMATE
Bシリーズと変わりません。つまり、本体をAfの時の様に特殊な専用のものではなく、通常製品と同じものを使用した事により、価格を従来の半額(600,000円)に抑えられました。このBfは当時としてはとても処理が速かったので企業等で多く導入されました。
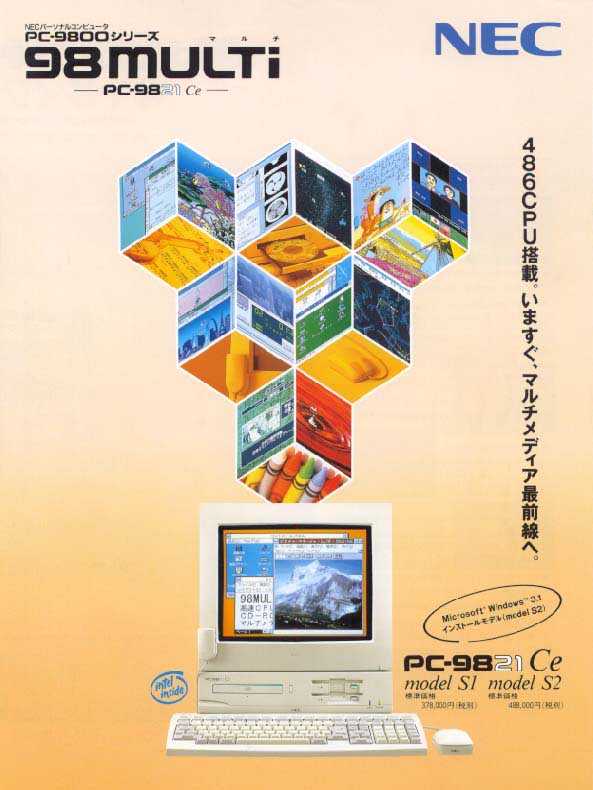
本格的なWindowsマルチメディアパソコンとして登場した98MULTiである初代PC-9821、それの後継機がPC-9821Ceです。
前者との相違点は、CPUがi486SX(25MHz)搭載し、メモリやHDDが
増量されました。98MATE
Bシリーズもアールインワンでしたが、ディスプレイは付属していませんでした。しかし、98MULTiは、ディスプレイはもちろん一般ソフトウェアも初めて標準で付属(インストール済)していました。CDドライブ等が固定されているため、将来的な拡張性が多少犠牲になってしまいますが、パソコン初心者には扱いやすく、学校等で導入される事が多かったです。