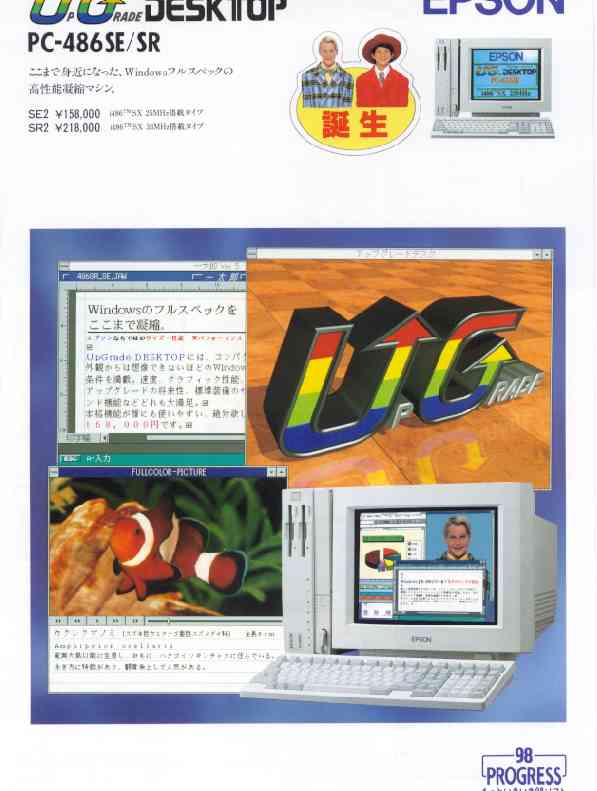月刊
98パンフレットマガジン
1998年12月号(第十二号)

PC-98ユーザーあこがれのPC-98と言っても過言ではない機種が、PC-9821Rv20です。
Rv20は、何と言っても高拡張性という点が最大の人気の秘密です。PCIバスは3スロット装備し、その内1スロットはMillennium(ビデオカード)で占有しています。また、UltraSCSIインターフェイスもオンボード実装しています。つまり、PC-98では驚異の4スロットもPCIバスを装備している事になります。「3スロットではないか!」と言いたい方もいるとは思いますが、PC-98ではHDDインターフェイスの性能が極端に低いため、SCSIやIDEのHDDインターフェイスを装備するのは必須なので、4スロットと言えるのです。また、標準搭載のMillenniumはPC-98で搭載可能な少ないビデオカードの1枚であり、2D描画では最高峰(もちろんPC-98の中で)に位置するので、この点もPC-98ユーザーにとってはすばらしい事です。デスクトップ機(XaやRa)では、PCIスロットは2スロットしかなく、その2スロットはビデオカードとHDDインターフェイスカードで埋まってしまい、空きスロットが無くなってしまうので、PC-98ユーザーは辛い状況でした。それをRvは、上記の2つを搭載しても2スロットの空きがあるので、3Dカードやビデオキャプチャー等を更に搭載可能です。ですから、自作AT互換機に匹敵する最強のPC-98と言えるのです。また、Cバス4スロット、ファイルベイ(5インチベイ)2スロットと、この文句無しの拡張性が、現在の中古市場において、PC-98ユーザーがRvシリーズを血眼になって探す理由でしょう。

最強のPC-9821Rv20にPentiumII(266MHz)を搭載し、磨きをかけて「真の最強」になったPC-98、PC-9821RvII26です。
基本的に、Rv20とはCPUの違いとHDDの容量等が違うだけで、高拡張性は以前のままです。現在、PC-98を愛する真のユーザーは、秋葉原の中古店でこの機種が売りに出されたら値段に関係なく即購入という大変貴重なPC-98と言えます。それ位人気もあり、台数も無いというのが現状です。自作AT互換機並の高拡張性に、PentiumIIをデュアル搭載可能な機種ですから当たり前です。余談として、多くのPC-98ユーザーがタワー型のPC-98を継続販売して欲しかったというのが本音だと思います。しかし、RvII26のマザーボードや筐体を見れば一目瞭然で、あまりにもコストがかかり過ぎていて、NECも継続販売する利点が無いのです。つまり、サーバ機のタワー型が欲しい方は「MateNXを購入して下さい」という事ですね。ちなみに、RvII26だと下記の様な環境が可能です。
| PC-9821RvII26 3Dゲーム仕様 |
| CPU |
PentiumII(266MHz) |
| メモリ |
EDO-DRAM(ECC) 256MB |
| HDD |
6.4GB(SCSI) |
| ファイルベイ |
32倍速CDドライブ(SCSI) |
| 12倍読/6倍書CD-Rドライブ(SCSI) |
| 640MBダイレクトオーバーライトMOドライブ(SCSI) |
| PCIバス |
UltraSCSIインターフェイス(オンボード実装) |
| 10/100BASE-TX LANボード(オンボード実装) |
| MGA:Millennium(RAM:4MB)or各社ビデオカード |
| 3Dfx:Voodoo2(RAM:12MB) |
| 各社ビデオキャプチャーカード |
| Cバス |
PC-9821-118orWaveStar |
| Roland:SuperMPU-IIN |
| 各社高速RS-232Cインターフェイス |
| (空き) |
この仕様ならば、現在(1998年11月現在)のWin98ライフ、
又は3Dゲームライフを十二分に満喫できるでしょう。
もちろんPC-98のMS-DOS環境を継承しながら(これがメインですね)。
懐かしの名機シリーズNo.9(EPSON98互換機特集第4回目)
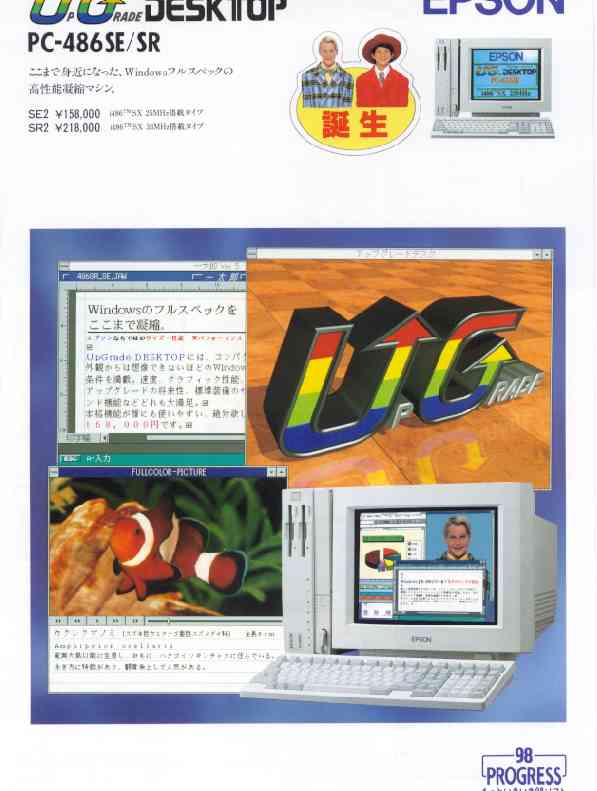
i80486SX(25MHz)を搭載し、158,000円の定価を実現したのが、PC-486SEです。
この486SEはコストパフォーマンスにすぐれ、本家NECの98FELLOWの対抗機種として登場しました。オーバードライブプロセッサによるアップグレードの正式対応や32bitローカールバス(内蔵型)の採用、640×480ドット16色のサポートと高速ビデオ回路等、98FELLOWを超える性能と省かれていない機能(FDDドライブやインターフェイス等)が特徴でした。特にFM音源が標準搭載されているのがゲームユーザーにうれしい限りです。また、i80486SX(33MHz)を搭載し、メモリも2MB多いSRもありましたが、定価が218,000円と少々割高なので、SEより人気がありませんでした。しかし、オーバードライブプロセッサでアップグレードする際、ベースクロックが33MHzなので、IntelDX4(100MHz)やAMD5x86(133MHz)等を搭載できるので、SRの方がその点は有利でした。ちなみに、後期にはHDD、メモリ、ビデオカード等をオールインワンにしたEPSON版Win3.1モデルも発売されましたが、その頃には大ヒットした初代98MateXが登場し、EPSON PC(98互換機)の衰退期に突入しました。でも、根強いEPSONユーザーが、Pentium搭載98互換機のMMX化(K6化)を現在でもチャレンジし続けています。
今月のコラム「特別長編版」 第3回目
PCの消える原因を考える。
僕が初めてコンピュータに触れたのが、MSXが全盛期の時代でした。MSXはホームコンピュータと位置づけられ、マイコンとも呼ばれていました。パーソナルコンピュータと呼ばれるものは、企業等に導入される様な高級な機種で、この時代には既に発売されていたPC−9800シリーズは正真正銘「パソコン」でした。値段で考えると実売30万円以上の小型コンピュータをパソコンと呼びました。
MSXは、マイクロソフトとアスキーが提唱した規格で、コンピュータを手軽に楽しめるというのをコンセプトしていました。この時代ではライバルはPCというより、ゲーム機のファミリーコンピュータでした。そのため、ファミコンよりは少ないとしても、MSX用のゲームはPC−9800シリーズより、年間タイトル数が多い時もありました。そして、メインRAMの容量を上げたMSX2が登場し、3.5インチFDDが搭載されたMSX2+、16ビットCPUを搭載したMSXtruboRと進化しました。しかし、MSX2+までがMSXの全盛期で、truboRを発売した後は1〜2年で姿を消しました。理由は、他社PC(PC−9800、X68000、FMタウンズ等)の方が、有利な点が多かったためです。
X68000は、シャープが発売したゲームマシンPCです。なぜゲームマシンと呼べるのかは、スプライト処理が可能なためゲームの特性に向いているためです。実際に多くのアーケードゲームが移植され、X68000はスーパーファミコンをライバルにしたと言っても過言ではないでしょう。
FMタウンズは本格的なマルチメディアPCで、グラフィック能力等のマルチメディアには欠かせない機能の性能が高かったです。よって、多くの学校等に導入され、グラフィック能力を生かし、教育現場に使用されました。
PC−9800シリーズは、何と言ってもビジネスにも強く、豊富なソフトウェアが魅力でした。基本的に、ゲームならX68000、マルチメディアならFMタウンズ、ビジネスならPC−98というのが当たり前でしたが、PCゲーム市場では18禁ゲームが人気なため、18禁ゲームに限っては16色表示でも640×400ドットでは十分に奇麗に表示できるので、ゲームでもPC−98ということで、ビジネス、ゲームと二つのタイトルを取りました。さらに、PC−98は一新改革(98MATE等の登場)を行ったので、マルチメディアも市中に入れ、日本のPC市場をリードしてきました。そして、X68000はWin3.1が発売された時、FMタウンズはWin95が発売された時に姿を消しました。PC−98は・・・、Win98が発売され、消えかけています。
姿を消す理由として考えられるのは、OSが大幅に進化する時に、PCがそのOSの機能をフルに引き出せなくなるからです。例えば、X68000はスプライト(ゲームに有利)の処理能力は高いですがCPUの性能が低いので、ビジネスソフトがメインのWin3.1環境を処理する能力が低く、Win3.1が普及した頃には姿を消しました。FMタウンズはWin95発売時、Win95環境を処理する能力はありましたが、FMタウンズ用のDOSアプリケーションが終わりを告げ、ユーザーはFMタウンズを買う理由が無くなり、製造元の富士通もFM−Vに完全移行したので、名実共に姿を消しました。逆に、PC−9800シリーズはDOSアプリケーション(主にゲーム)が、まだ現役だったので、Win95もできてDOSもできるというメリットで消えませんでした。しかし、Win98が発売した現在、ついにPC−9800シリーズが消えようとしています。
PC−98が消える最大の理由は、DOSアプリケーションの新製品が無くなった事が最大の理由です。ビジネスアプリケーションは、既に1997年には新製品はありませんでしたが、ゲームに限っては1998年の前半まで新製品がありました。特に美少女ゲームと呼ばれる18禁ゲームが発売されていました。Win98が登場した現在、ついに新製品が発売されなくなったのはなぜか?逆にWin95が発売された当時、まだ新製品を発売していたのはなぜか?を考えてみましょう。
Win95が発売された当時(1995年〜96年)は、PC−98は国内シェア50%近くはありました。しかし、Win95が快適に処理が可能な機種は5%以下でした。アップグレードをしても10%が限度で、DOSかWin3.1がメインでした。ですから、PCゲームのメーカーはもちろんシェア50%のPC−98をターゲットにゲームを発売するのですが、そのPC−98が、Win95環境を快適に処理できる機種より、DOSやWin3.1の機種の方が多いので、DOSベースで発売したわけです。この当時、PC−98:50%(DOS:40%)、AT互換機:35%、MAC:15%のシェアがあり、PCゲームメーカーがPC−98DOSベースのシェア40%をターゲットにするのも納得がいきますね。ちなみに、Win3.1はゲームを快適に処理する事(描画が遅く、グラフィックAPIが無い)ができないので、それほどゲームは発売されませんでした。
ところが、1997年頃から事情が変わってきました。理由は、VALUESTARの人気と、シェアの低下です。NECはPC−98の出荷台数を確実に上げました。特にVALUESTARはオールインワンモデルの先駈けと言え、V13が大人気で一番多く出荷されました。ところが、AT互換機陣営も出荷を大幅に延ばしたのでシェアが低下してしまいました。なぜならば、PC−98は200万台、富士通は100万台、IBMは50万台、その他が100万台出荷したと考えた場合、メーカー個々で考えるとNECが出荷台数No.1ですが、PC業界全体(アーキテクチャー)で考えるとAT互換機の総出荷台数より少ないので、シェアが下がったと言えるのです。この当時は必ず「NECのシェアが下がった、もうNECは駄目だ」などと言われましたが、PC−98対AT互換機で考えれば、NEC以外のメーカーはPC−98を作っていないのですから、勝ち目が無いのは当たり前です。むしろ、メーカー個々で考え、PC−98でもNo.1の出荷台数というNECの業績を誉めたいものです。このVALUESTARの人気は、PC−98でもWin95は完全OKというを証明したわけですが、この証明がDOSアプリケーションの新製品がなくなるという自滅の道を進むのです。自滅の道の理由はおわかりだと思いますが、PCゲームメーカー(ここから先はPCゲームメーカーで考えます)はPC−98用のDOSゲームを発売する理由が無くなったからなのです。Win95(1995年〜96年)当時では先ほど述べた様に、PC−98のシェアは50%近くあり、その内9割がDOSまたはWin3.1でしたが、Win98の発売が近づくにつれPC−98のシェアは35〜40%になり、VALUESTARの好調な結果、その内6割はWin95が快適に処理できる機種になりました。35〜40%で6割と言っても、500〜600万台はあります。ですから、DOSやWin3.1の時とは逆で、Win95が快適に処理できる機種の方が、快適に処理できない機種より多くなったのです。これは、PC業界全体にWin95マシンが普及したとも言え、PC−98:40%(DOS:15%)、AT互換機:50%(Win95:40%)、MAC:10%のシェアですから、PC−98とAT互換機双方のWin95ベースのシェアをたすと50%以上にもなり、文句無しにPC−98DOSベースのシェアを超えるのです。これはWin95発売後、Win95インストールPCの総出荷台数がうなぎ登りだったからで、PC−98のVALUESTARも同様に好調だったからです。VALUESTARでもDOSアプリケーション(DOSゲーム)がもちろん動作するので、1997年の夏頃まで、まだDOSゲームは多く新製品がありました(Piaキャロも97年です)。しかし、この時期を境にDOSゲームの新製品が極端に減っていき、Win95ゲーム(18禁)の全盛期が始まりました。なぜ97年の夏頃が境なのかは、PC−98DOSベースのシェアをPC−98全体のシェア(40%)と考えたとしても、AT互換機のWin95ベースは40%はあるので、PCゲームメーカーはDOSゲームではなくWin95ゲームを開発してもどちらでもいいのです。ですから、この時期を境にWin95マシンのシェアがより多くなっていったために、97年が最後のPC−98DOSゲーム時代と言えるのです。また、何よりもPC−98の40%というのは、VALUESTARを無理にDOSベースにしたもので、本来ならWin95マシンですから完全にWin95ベースで発売しても、VALUESTARはもちろん、Pentium搭載のPC−9821なら問題は無いのです。
Win98が発売され、完全にPC−9800シリーズの新機種開発の理由は無くなりました。NEC自身もPC−9800シリーズの存在理由を明確(それほど必要で無い事です)にし、PC98−NXに移行したのです。新機種の必要性を考えてみると、DOSアプリケーションや周辺機器等の過去の資産を重要視してきたPC−9800シリーズですが、そのDOSアプリケーションでは、PentiumII等の高性能CPUは必要ありませんし、USBやACPI等も活用する事はできないので、DOS環境を重要視するならば現行のMATEシリーズで全然問題無いのです。ですから、今まではWin95とDOSの両方とも同じPC−98で活用するという事でしたが、これからは、Win98は最新のPC98−NXで、DOS環境は現行のPC−98という具合に、使用する環境によってユーザーが機種を選ぶのです。
例「Win98:PC98−NX,Win95/Win3.1&DOS:PC−9800」
また、昔は機種にソフトウェア(OSを含む)を合わせてきましたが、現在はソフトウェアに機種を合わせるという逆の考え方になりました。具体的に言えば、3Dゲームを快適に処理するために3Dカードを搭載してアップグレードするというのが良い例でしょう。昔ならば、いかにPC−98の低いグラフィック能力(少ない色数)でも奇麗に表現できるかPCゲームメーカー等は工夫を凝らしたものです。余談として、640×400ドット16色でも奇麗に見える、代表的な技法がタイルパターン(細かい点でグラデーションを表現する技法)です。現在は6万色やフルカラーですから、その様な技法は必要無くなりました。ですから、自分がやりたい事(使いたいソフトウェア)に合ったPCを購入するという時代になったのです。
最後に、現在PC−9800シリーズの最高峰の機種はタイプ別に、
タワー型 PC−9821RvII26:PentiumII(266MHz)
デスクトップ型 PC−9821Ra333:Celeron(333MHz)
ノート型 PC−9821Nr233:MMXPentium(233MHz)
携帯ノート型 PC−9821Ls150:MMXpentium(150MHz)
以上の様になっていて、デスクトップ型とノート型の機種に限っては、MS−DOSをベースにしている企業等で、まだ需要が十二分にあるので、Windows98プレインストールモデルとして最近発売されたものです。特にRa333はCPUとチップセットがPC−9800シリーズの中では、1998年現在でも通用するレベルなので、98ファンの中では欲しい方がいらっしゃるでしょう。ただし、デスクトップ型で拡張性が低いので、グラフィックカードとHDDインターフェイスで2基あるPCIバスが早々に埋まってしまうという悲しい機種です。ですが、それでもRa333は、PC−98環境最高峰の処理能力を持っているので、PC−98を買うなら「これしかない!」と言えるでしょう。例え、メルコやアイオーデータから発売されているK6−2(333MHz)アクセラレータをXaシリーズ等に搭載しても、CeleronのPentiumIIコアには到底及びません。チップセットも、PC−98の中では上位ランクの440FXなので、PCIバスの転送能力も高く、3Dゲーム等も快適にプレイが可能でしょう。但し、あくまでもPC−98環境の中での話なので注意して下さい。つまり、AT互換機の自作機市場と比較すれば、Ra333は時代遅れ(特にチップセット)となっていますので。
では、今月のコラム「特別長編版」はこの辺で・・・。