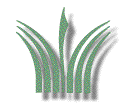太古の時代からヒトは薬草や自然界の鉱物などを用いて自らの病を癒やすことを識り、それらは何千年もの時を経て薬剤となり私たちの生活に深く根付きました。今回は薬の飲み方について普段皆さんからよく尋ねられることにつきお話しします。
薬の飲み方やタイミングは正確には「用法」ということばで表現され【食後・食直後・食直前・食間・起床時・就眠前】など様々な種別があり、中でも「食
後」の指定が最多です。口から飲む薬は原則として、食道〜胃を通過した先の小腸の粘膜から組織内に吸収されて初めて効力を発揮します。ですから本来は胃や
小腸に食物が入っていない「空腹時」に飲むのがもっとも吸収され易いことは想像していただけると思います。ではなぜ「食後」指定が多いのか? それは日常
の生活でわざわざ食事時以外に服用することが煩雑なことと、それから一部の薬が引き起こしかねない胃粘膜障害を避けるために敢えて食後の服用が勧められて
きたという歴史的(?)経緯もあります。これは実際には薬剤コーティング技術が進歩した現在では殆ど問題になりません。また、近年増えた一日一回投与で緩
徐なコントロールを目指している薬剤では服用時刻はあまり問題にされません。すなわち極言すれば、飲むタイミングについてはあまり気にしなくて良い薬剤も
かなり多いといえます。
しかしながら逆に食事との関連を強く意識すべき薬剤もあります。まず第一に、上に少し触れた「吸収」が良くない薬剤です。たとえばある種の骨粗鬆症治療
薬の場合、必ず空腹の「起床時」に飲み、その後30分~60分程度は何も口にしないようにせねば飲んだ意味が全くありません。また漢方薬の多くも吸収が良
くないため食前の服用が勧められています。次には、糖尿病治療薬では食事との関連が非常に重要です。食前に飲むことで血糖の上がりすぎを防ぐ薬剤がありま
すし、逆に積極的に血糖を下げる薬剤などでは空腹時に飲むと低血糖という重篤な状態を引き起こしかねない場合もありえます。
服用タイミング以外で注意すべきなのは、かならず十分な水・お茶で薬を飲み下すことです。特に高齢者では唾液の分泌が減少傾向にあるため、食道に薬が長
く留まった状態ではその部の粘膜障害がつよく懸念されます。なお「お茶で薬を飲む」ことについては昔から是非の議論がありましたが、現在では議論のあった
「鉄剤」のほとんどでもお茶で飲むことに問題がないことが解っていますので、水・茶の違いはあまり気にされなくて良いでしょう。今後、採血や検査などで
「食事抜きでの受診」を求められた際には、たとえば朝の薬を昼食後にずらして服用するというような工夫も良いかと思いますので、以上を参考にし担当医にお
尋ねください。
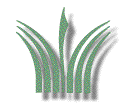 大西内科クリニック
大西内科クリニック
_______ ■ September 〜 November 2018 ■_

_______ ■ September 〜 November 2018 ■_