1853年 日本へアメリカのペリーが来航
隣国の中国清朝は、1840〜1842年のアヘン戦争でイギリスに敗れ、日本へもヨーロッパ列強の進出が迫っていた。
日本の鎖国中も国交のあったオランダは、日本が鎖国を続けることは困難だと考え、1844年7月にオランダ政府から徳川幕府へ開国を勧告する国書を送った。幕府では活発な論議が行われたが、老中阿部正弘のもとで祖法順守派が大勢を占め、鎖国政策をやめるつもりはないとの回答を送った。老中首座であった水野忠邦などの受け入れ派はのちに処分されている。
オランダは、ペリー来航についても、事前の情報を得ていた。その情報は、1852年6月に、オランダ商館長が毎年重要事項を記載して幕府に提出している「別段風説書」によって、幕府へ伝えられた。しかし、幕府の老中首座であった阿部正弘は、幕閣の合議制であった会議を動かすことができず、結局、財政難であった幕府は、情報の信頼性が疑がわしいとして、全くの無策であった。
アメリカ東インド艦隊司令官ペリーは、遣日特使として軍艦4隻を率い、1853年6月3日(旧暦)に三浦半島の浦賀(現在の神奈川県)に入港した。
なお、この時のペリーは、太平洋の横断ではなく、アメリカ東海岸から大西洋とインド洋を経て日本へやって来た。(出典:
ペリーは戦闘準備を行って、武力で威嚇しながら、徳川幕府に開国を迫り、国書を渡して、来年の春に返書を受け取りに来ると告げて帰った。
ペリーは、1854年1月16日(旧暦)に7隻で再度来航した。ペリーは礼砲・祝砲の名目で55発の大砲を発射するなど軍事的な威圧を加えて交渉を行い、同年3月3日(旧暦)に幕府と日米和親条約を締結した。条約の内容は、
箱館(現在の北海道函館)と下田(現在の静岡県伊豆半島)の開港、
漂流民の救恤(きゅうじゅつ)、
薪水・食料・石炭などの供給、
両港における遊歩区域の設定、
アメリカ船の必要品購入許可、
アメリカへの最恵国待遇の承認
などである。
さらに、イギリス、フランス、ロシア、オランダともほぼ同様の和親条約を結んだ。このうち日露和親条約には、千島列島の択捉(エトロフ)島と得撫(ウルップ)島の間を両国の国境とし、樺太は両国雑居の地とする国境問題が含まれていた。
ここに、日本は二百数十年にわたる鎖国に終止符を打ち、開国することとなった。
その後、日本国内は動揺を続け、1867年に徳川幕府は大政奉還、1868年に明治維新を迎える。
【ペリー以前の来航】
1739年、ロシアのベーリング探検隊の分遣隊として、シュパンベルクの率いる4隻が時々別行動をとりながら、東北・関東の太平洋側付近を調査した。上陸して住民と物々交換も行っている。
1792年、ロシアのアダム・ラクスマンがエカテリーナ号で根室に来航した。難破してアリューシャン列島のアムチトカ島に漂着した伊勢の船頭である大黒屋光太夫ほか2人を送るとともに、日本との通商を求めた。
1796年、イギリス海軍中佐ブロートンが指揮するプロビデンス号が、日本沿岸測量の途中に絵鞆(えとも、現在の北海道室蘭)に来航し、薪水を補給した。
1804年、ロシアのレザノフが軍艦ナデジュダ号で長崎に来航。ロシアに漂着した石巻きの漁民津太夫ほか3人を送るとともに、日本との通商などを求めた。
1808年、イギリス船フェートン号が長崎に侵入。オランダ商館員2人を一時拉致し、長崎港内でイギリスのボートがオランダ船の捜索を行った。オランダはナポレオン戦争でフランスの支配下にあったため、フランスに敵対するイギリスはオランダを敵国とみなし、アジアにおけるオランダの地位を脅かしたものであった。日本は希望どおり食料と薪水の供給を行い、オランダ商館員2人は解放された。この事件の責任をとって、長崎奉行が切腹している。
1811年、ロシアの測量船ディアナ号が、択捉島に上陸して薪水と食料を求めた。二度目に国後島へ上陸した際、艦長ゴローニンが松前奉行所と会見中に誤解されて捕らえられた。松前奉行はロシア政府の関与を疑っていた。艦長ゴローニンは箱館(現在の北海道函館)へ送られたが、1813年に釈放された。
1824年、イギリスの捕鯨船の乗組員12人が常陸の大津浜に上陸し、水戸藩に全員逮捕された。密貿易の疑いをもたれたが、食料と薪水を求めたもので、2か月足らずで釈放された。
1825年、幕府が外国船打払令を出す。
1828年、シーボルト事件。
1837年、モリソン号事件。浦賀にあらわれたアメリカの貿易商社の所属船モリソン号に対して、浦賀奉行所が外国船打払令に従って砲撃を加えた。モリソン号は漂流してマカオで保護された日本人漁民7人の送還と通商・布教の意図を持っていたが、かなわなかった。
1840〜1842年、隣国の中国清朝がアヘン戦争でイギリスに敗れる。
1842年、幕府が外国船打払令を緩和し、状況に応じて薪水の給与を認めた。
1843年、ロシア船が択捉島に漂流民を護送してくる。
〃 イギリス艦サマラン号が、八重山諸島(現在の沖縄県)に上陸し、測量を行う。
1844年、フランス艦アルクメーヌ号が那覇に来航して通商を求める。
〃 オランダからの国書が届く。
1845年ころ〜、外国船が頻繁に日本の沿岸に現れるようになる。
1846年、アメリカ東インド艦隊司令長官のビッドル提督が率いる軍艦2隻が浦賀に入港。日本に開国の意志があるか打診して帰った。
〃 幕府が、琉球と諸外国の貿易を容認する意向を、薩摩藩に内々に伝える。
1849年、イギリス軍艦マリナー号が、浦賀沖に入り江戸湾の測量を開始した。食料の提供を受けただけで、調査を行って立ち去った。
1852年、オランダ商館長がペリーの来航を予告。
1853年、ペリー来航。軍艦4隻(蒸気船2隻、帆船2隻)。
【アメリカの事情】
イギリスから始まった産業革命は欧米諸国に波及していったが、アメリカの綿工業は中国市場で優位にあったイギリスを追いあげつつあった。
アメリカは1848年にメキシコとの戦争に勝利してカリフォルニアを手に入れた。そこで、カリフォルニアから太平洋を横断して上海・広東を結ぶ汽船航路の開設を目指した。当時の汽船は石炭を大量に消費したため、途中での寄港地を必要とした。石炭の積載量を減らすことができれば、その分の商品貨物を積めるからである。こうして、アメリカは日本に寄港地を求めようとしていた。
日本に開国を求めたもうひとつの理由は、捕鯨業であった。アメリカは北太平洋での捕鯨業が盛んになっていたが、遭難して日本にたどりついた者は帰還させるまで拘束状態におかれ、病死者や自殺者もでていた。アメリカでは人道的な問題として世論を刺激していた。
なお、ペリーは1853年の航海で日本に開国を要求したほかに、小笠原諸島の父島に貯炭所の土地を確保し(注)、琉球政府に貯炭所の設置に同意させている。

 NHKテレビ「そのとき歴史は動いた 大江戸発至急便 黒船あらわる」2004年6月23日放送
NHKテレビ「そのとき歴史は動いた 大江戸発至急便 黒船あらわる」2004年6月23日放送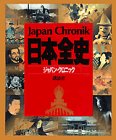
 「90分でわかる日本史の読み方」
「90分でわかる日本史の読み方」