本講座へお申し込みありがとうございます。
この講座は、20世紀のアメリカで誕生し現在では世界中で聴かれ、演奏されている音楽芸術「ジャズ」について、特に1960年代以降の発展について代表的な録音資料を聴きながら解説していきたいと思います。全四回、計10時間の講座です。


まだ百年あまりの歴史しかない「若い」芸術ジャンルですがその歴史を見ると、1920年代には「ニューオリンズ・ジャズ、デキシー・ランド・ジャズ」と呼ばれる集団即興演奏を主体とするスタイルが確立され、1930年代には「スイング・ジャズ」と呼ばれる大編成のビッグ・バンドでアンサンブルと各楽器の即興ソロが流行しました。1940年代になると「ビ・バップ」(これ以降のスタイルは「モダン・ジャズ」という言い方をすることが多い)と呼ばれる複雑なリズム・旋律をもつスタイルが現れます。
1950年代になるとそれまでの成果が統合され、録音技術の向上もあって多くの素晴らしい演奏が録音されて現在でも繰り返し鑑賞することが出来ます(もちろん1920年代からジャズ演奏の録音は残っていますが)。
ただし、「ニューオリンズ・ジャズ」以降のスタイルのジャズは消滅したわけではなく現在に至るまで世界中で演奏し続けられています。ここではジャズ音楽の最先端がどうであったか、ということを考えていきたいと思います。
1960年代に入る頃最先端のジャズ演奏家たちは何を考えていたか、現在の目から見てまず考えられることは、「即興演奏の自由度を増してさらに高度な表現をすること」にあった、と思います。
つまり、1950年代までの即興演奏はもとの曲の和音進行に基づいたもので、和声の複雑な分解・再編成は極限まで試みつくされ、進歩的演奏家たちの間でなにか違う道はないかという模索が始まりました。
トランペットのマイルス・ディビスは1950年代に大きな成果を上げたコンボ(小編成のバンド)のメンバーを一新してテナー・サックスのジョン・コルトレーン、ピアノのビル・エバンスたちと、それまでの和声解釈と異なる現在「モード奏法」と呼ばれるやり方を完成させます。
アルト・サックスのオーネット・コールマン、ピアノのセシル・テイラー、テナー・サックスのアルバート・アイラーたちはさらに自由な即興のやり方を模索して行きます。
「ジャズ」はもともと西洋音楽とアフリカの音楽の融合からはじまったと初めに書きましたがここでまた、すでに無調や偶然性を取り入れた現代音楽、即興性の強いアフリカやクレズマー(ユダヤ系音楽)やフラメンコなど、さらにはインド音楽などあらゆる音楽からの影響を受けて「ジャズ」は発展を続けたのです。
本日は、1950年代末から1960年代はじめの彼等の演奏から聴いていきますが、最先端のジャズの変遷をたどるのに、ジョン・コルトレーンとビル・エバンスの演奏の変化に注目してみましょう。
1. "If I Were A Bell" Miles Davis Quintet "Relaxin'"1956

1950年代のマイルス・ディビスのクインテットの演奏から聴きましょう。
マイルスのトランペット、レッド・ガーランドのピアノ、ポール・チェンバースのベース、フィリー・ジョー・ジョーンズのドラムにテナー・サックスのジョン・コルトレーンというメンバーで、ミディアム・テンポにのってスタンダード・ナンバー(当時の流行歌)が演奏されます。
各自の即興演奏は決まった和音進行に基づいています。コルトレーンのテナーに注目してください。まだどこかぎこちないですが、独特の音色・個性的なフレーズを聴くことが出来ます。

1958年のマイルス・コンボは、テナーにコルトレーン、アルト・サックスにキャノンボール・アダレイ、ピアノにビル・エバンス、ベースはチェンバース、ドラムにジミー・コブ、という6人編成になります(この曲ではアダレイは参加してませんけれど)。
この曲もスタンダード・ナンバーですが、コルトレーンのソロは細かい音符を連ねた独特な「シーツ・オブ・サウンド」と呼ばれるスタイルを完成させています。

マイルス・コンボから独立したコルトレーンは、和音進行に基づいた即興演奏の極限に挑戦するかのように自作のこの曲に挑みます。
テーマ・メロディは単純ですが、和音進行が極度に難しい曲です。音階練習のようだという酷評もありましたが、良く聴けば歯切れの良い音色で起伏するメロディー・ラインの連続がなんとも美しいと思いませんか?
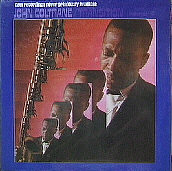
"Giant Steps"で和音を複雑化し・分析していく即興方法を極め、さらに「モード奏法」と呼ばれる和音は極度に単純化してさらに自由に即興する手法をもマスターしたコルトレーンは、次にはすべての音楽的制約をなくして即興演奏するという「フリー・フォーム」の域へ進出していきます。
この曲はその名も「変遷」というコルトレーンのオリジナルで、基本的に一つの和音が基になっている「モード奏法」の曲ですが、ところどころ叫び声のような表現が聴かれます。
ピアノはマッコイ・タイナー。ピアノのソロで「モード奏法」がよく分かると思います。基本の音階から自由に別の音階に移動したり戻ったりして自由にメロディー・ラインを作り出しています。
ベースはジミー・ギャリソン、ドラムはエルビン・ジョーンズ。このドラムも凄い!コルトレーンのサックスに反応して素晴らしい即興演奏をしています。4ビート・ドラミングの最高の演奏の一つであると言えるのではないでしょうか。
コルトレーンの細かい音符を連ねていくスタイルの完成には、ジョーンズのようなドラマーの存在が不可欠であったと思います。
5."Dear Load" John Coltrane Quartet "Transition" 1965
同時期の録音からバラードも聴きましょう。ドラムはロイ・ヘインズが代役になっています。
"Transition"では目立たなかったベースのギャリソンがおもしろいベース・ラインを弾いています。

「フリー・フォーム」に突入したコルトレーンはコンボのメンバーをベースのギャリソン以外一新します。
テナーにファラオ・サンダース、ピアノに奥さんのアリス・コルトレーン、ドラムはラシッド・アリです。
"Giant Steps"の頃に作られたコルトレーンの曲ですが、ここでは和音進行にとらわれない自由な即興が行われます。
リズムにも注目してください。原曲は四拍子ですが、ドラムは4ビート・ドラミングではなく痙攣するような、うねるような連続する音でバンド全体をスゥイングさせています。
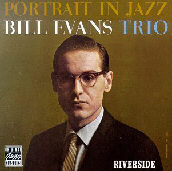
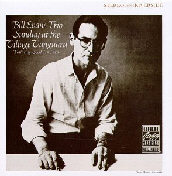
さて、2.で聴いたマイルス・コンボにいたピアニストのビル・エバンスは60年代以降のジャズで最も重要な演奏家の一人です。
50年代半ばから注目されていましたが、なかなか自分のコンボを作ったりレコードを出したりしませんでした。
ついに1959年、ベースのスコット・ラファロ、ドラムのポール・モチアンという理想のパートナーを得てトリオの活動を積極的に初め、素晴らしい作品を次々と発表しました。
まず聴くのはシャンソンの「枯葉」ですが、それまでのジャズ・コンボの演奏と違い、ピアノ、ベース、ドラムが対等に互いに応答しながら即興演奏を作り出しています。ベースもドラムもは四分音符で伴奏するのではなくお互いの演奏に絡んでいきます。エバンスのピアノはストレートなノリと言うより、「円を描く」ような独特の感覚で恐ろしくスゥイングしています。
「不思議の国のアリス」はディズニーのアニメの主題歌ですが全く独自のジャズになっています。残念なことにこの録音から数日後、ベースのラファロは24歳で事故死してしまいました。

ラファロの死後、エバンスは何人ものベース奏者と共演しますが、なかなか理想的なパートナーと出会えませんでした。
私は1964年に一枚だけ発表されたこのレコードのゲイリー・ピーコックがラファロと同等以上の技量のベーシストだったと思います。
このトリオは一時レギュラーで活動していたのですが、何らかの理由でピーコックはエバンスの元を離れ次回以降お聴かせするフリー・ジャズの演奏家たちと行動を共にし、多くの名演奏を残します。
エバンスの演奏はあくまでも和音進行を基にしています。