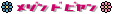触れた唇はやわらかく優しく、忍び込む吐息は甘く。
それは、めまいがするほどの一瞬だった。
真っ赤な顔をして部屋を走り出て行く君の、小さな後ろ姿が、かわいらしく見えてしょうがない。
唇にかすかに残る感触が、この胸の動悸が、全身に熱く広がって、僕を夢心地にさせる。
こんな幸せが、まだ待っていたなんて。
そっと目を閉じて、このまま、死んでしまってもいいと思えるくらいの。
すべては、君ゆえに。
・・・
コンコン、と遠慮がちなノックが聞こえる。
幸福に酔う僕は、この夜を大事に過ごしたくて、いつもの調子。
「誰?」
「…あたしよ。開けてもいい?」
「!…どうぞ」
静かにドアを開け、暗闇に身をすべらせて君がそこに立っている。
喉元で脈打ちはじめる鼓動。さまざまな憶測が頭をよぎる。絶望、消失、そして期待。
「あの…さっきは、ごめんね」
うつむき加減の君。表情は見えない。
僕は不安とないまぜになりつつある、この気持ちを懸命に見つめて笑う。
「どういたしまして。とても嬉しい事件だったよ。今、乾杯しようと思ってたところだ」
「…悪いけど、それ、やめて」
「なぜ?」
「だって…あたしね、つい、その…してしまったんだもの。つい、ふらふらっと。だから、やめて」
「本気じゃなかったってことかい?」
「…分からない」
「オレには分かるよ、マリナちゃん。君は、少なくとも最初の頃よりは、オレのことを好きになりはじめてるってことがね」
「…」
「自然に、君の思うようにしていたらいい。きっと、そのうち分かる」
「呪文みたいに唱えるのはやめて」
「術にかかるかどうかは君の自由だよ」
「シャルル!」
僕のことをどうでもいいと思っているなら、あやまりに来たりなんかしない。
真剣に向き合ってくれる、そんな君だから僕は。
「ここへ来て、マリナ」
複雑な表情をした君の顔が、戸惑う口元が、部屋の薄明かりに照らされる。
「シャルル、あたし…」
「だまって」
僕は腕を伸ばして君を捕らえる。君は困ったように掴まれた腕を見つめる。
「…君にキスしても、もう怒らない?」
僕は腕に少し力を込めて君を誘う。君の眼差しが揺れる。
「逃げないでいてくれるなら、するよ」
宵闇の帳に包まれて、恋人はこの手の内に。
他には何もいらないと思えたなら、どんなにか。