
クリックすると下記へスクロールされます。
1.ピアノは、人間の内省的な心を表現するのに最も適している。
8.手首の旋回運動。
10.ベダルの使い方。
1.ピアノは、人間の内省的な心を表現するのに最も適している。
バロック時代は、積極的な時代と呼ばれています。
この時代の音楽家は宮廷や教会に仕えており、家具職人や宮廷画家などと同じように、音を通じた絢爛豪華な饗宴を提供する必要がありました。
音楽の創作の目的は、作曲家の個人的な心情を歌うことよりも、公に対して、職人としての良い仕事を提供することだったのです。
音楽の表現は、積極的で、明るく軽い音色が好まれ、音量の基本は常にフォルテで演奏されました。ピアノ(弱音)は、フォルテを引き立てる対比の表現として用いられました。積極的な表現が主流だったバロック時代に対して、ロマン派時代は、消極的な時代と呼ばれています。
時代は、フランス革命を頂点とした啓蒙思想を経験し、教皇や皇帝を頂点としたヒエラルキーを前提にした封建的社会を絶対視しなくとも良くなってきました。一人ひとりの個人が、自分が何者であるかを思索できる時代になったのです。
ロマン派時代の音楽は、作曲家自身の内面にむかって語りかけるモノローグのような内省的表現になってきます。音量の基本はピアノ(弱音)が主流で、長いスラーや、穏やかな表情など消極的なものが、音楽表現の基本となります。
そもそも「ピアノフォルテ」と呼ばれていたピアノが、ピアノという名称に落ち着いた理由は、それまでの鍵盤楽器では得られなかった繊細なピアノ(弱音)を発音することが可能になり、内省的な人間の心を語ることにふさわしい楽器だったことを象徴していたからではないでしょうか。「音楽には文法がある」と言われていますが、これはどういうことかというと、簡単に言えば、音楽による「語りかけの原理」ということだと思います。
人が、実際の会話を交わす様子を観察してみると、伝える内容によって話す語調が変わることに気がつきます。たとえば、自分の伝えたいことが重要なことであればあるほど、人の注意を引くために声が大きくなるし、はやる気持ちから話す速度も速くなります。
逆に、自分が自分に対して語りかけるモノローグ(独り言)の場合は、小声でつぶやき、ゆるやかな口調になっています。自分に対して語っているので、声は小さくて良いし、せきこんで速く話す必要もありません。それと同じように、音楽では、外側に向かって重要なことを語りたいときにフォルテになります。その時、演奏の速度は速めになります。バロック時代の音楽は、そういった積極的表現の傾向が強い時代だったのです。
それに対して、自分が自分に向かって内省的に語りたいときは、ピアノ(弱音)になります。また弱音のときは、やや遅めに演奏されます。ロマン派の音楽は、そういった消極的表現の時代でした。
したがって、たとえば「アンダンテ」というテンポは、バロック時代では速いテンポに属していましたが、ロマン派では遅いテンポに属すようになります。また同じ曲でも、弱くゆっくりと演奏すればするほどロマンチックな表現となります。
古典の時代では、積極的なものと消極的なものとの中庸が保たれた時代でした。ピアノを演奏する時は、バロック音楽や前古典派を演奏する以外は、基本的に小さい音を基調にします。名ピアニストの生の演奏を間近で聴くと、その音が大変小さいことに、聴く人皆一様におどろかされます。もちろん和音の柱などをフォルテで演奏されるときは、オーケストラに匹敵するほどのエネルギーを感じさせますが、しかし、普通に音楽を語りかけるところでは、小さい音が表現の基本になっているのです。
フォルテというのは絵の具の原色と同じで、色彩の変化を与えません。ところが、ピアノは、淡い色彩と同じで音色の無限の変化をつけることができるのです。名ピアニストは、小さな音を用いて、空間にマネやモネのような名画家のように、旋律や響きを虹のような変化をつけながら音楽を表現していきます。聴く者すべてが、その変幻自在な色彩感の変化に魅了されるのです。
ピアノという楽器を美しく演奏しようとすれば、まず弱音で色彩感を豊かに描くことができるように、心がけなくてはならないでしょう。
昔のピアノの先生は、指の力で鍵盤を叩いて大きな音を出す奏法を指導する先生が多かったようです。今日でも、ある音楽教室からやってきた生徒の楽譜には、「指先に全身の力を込めて、指を高く上げて鍵盤を叩く」と書き込んであり仰天することがあります。
このように指を高く上げて鍵盤を叩く奏法を「小ハンマー症候群」、あるいは「ハイフィンガー奏法」と呼ばれています。
小ハンマー症候群は、ピアノのアクションがあまり発達していなかった頃の古い奏法で、19世紀のヨーロッパでもまだそういう奏法が残っていたそうです。しかし、今日では、名のあるクラシックのピアニストで、ハイフィンガー奏法で演奏するピアニストは誰一人としていないでしょう。
しかし、日本の音楽教室では、明治時代からすでにハイフィンガー奏法は伝統として受け継がれた経緯があり、こうした悪しきテクニックの習慣が未だに残っていることがあるのです。なぜこういう奏法が日本で残っているのかというと、おそらく日本人は響きに対して鈍感だからではないでしょうか。
たとえば、西欧の人々は、古代から石造りの家に住んでいました。教会やお城、また一般の人々の家もみな石造りです。そういう造りの建物の中は音がよく音が響きます。響く部屋の中では、普通に話していても、人々は声の響きの心地良さというものを意識したでしょう。
まして音楽を奏でようと思えば、いかに声や楽器の音を美しく、色彩ゆたかに響かせるかということが人々の関心ごとになったのは容易に想像されます。和音という考え方も、そういう響く環境があったからこそ、自然発生的に生み出されたという説があります。
西欧の人々は、響きの美しさというものをもっとも大切にする、「響き人間」なのです。それに対して、日本人は古代から、紙(障子や、ふすま等)と木でできている家に住んでいました。そういう環境では、音はまわりの素材に吸収され、響きません。
そのために日本人は、響きに対して鈍感であり、邦楽などでは音が美しく共和する和音という考え方が生まれなかったといいます。西欧の人々が、雅楽の合奏を聴けば、あの不協和音のうなりに耐え難い不快感を感じるようです。
日本人の音楽の関心事は、和太鼓や津軽三味線の音楽のように、音を出した瞬間の情熱や情念に向きがちで、音を出したあとの響きの美しさに関してはあまり重要視されていないような気がします。
つまり日本人は、リズムの躍動感を好む「リズム人間」の傾向が強いと思います。西欧と日本のピアニストを聴き比べてみると、響き人間とリズム人間との表現の差を感じることがあります。
ピアノという楽器は、ハンマーで弦を叩いて発音しますから打楽器としての側面を持ちます。しかし、打鍵されたあとの響きの余韻は長く残りますから、豊かに響いた弦の振動は、弦楽器のそれと共通のものを感じさせます。したがってピアノは、弦楽器とみなすこともできます。
リズム人間の日本人は、ピアノを打楽器に近いあつかいで演奏する傾向があり、ハイフィンガー奏法は、打楽器的にピアノを発音させるには都合が良かったのだと思います。しかし、響き人間である西欧の人々は、ピアノを弦楽器として捉えていて、その奏法は、手首の旋回に委ねられます。良いピアニストとそうでないピアニストの差は、響きに対していかに感受性があり、センスが良いかの差にかかっていると言っても過言ではないでしょう。
もちろん、響きだけを重視し過ぎてしまうと、音楽表現全体としてのバランスを崩してしまいますから、常にリズム感と響きとの美しさの中庸性がとれていなければならないのは言うまでもありません。
しかし、日本人は、リズム感の方に指向が傾き過ぎるので、響きに対しては常に意識していないとならないでしょう。ピアノの音に豊かな響きを与える奏法は、手首の旋回による奏法です。
たとえばコルトーは、自分の教則本に、手首の動きは、自動車のエンジンに相当し、指の方は、その力を伝えるためのタイヤと同じなのだと述べています。つまり、ピアノは、指の力や肘などでは出さない。音を出す直接の原動力は、手首の旋回運動であり、指の方は、その力を伝えるための支えであるというのです。
手首の旋回運動は、ヴァイオリンの弓使いや、歌唱のときの腹筋による横隔膜の支えと同じ働きに相当します。手首の旋回運動によって発音されたピアノの音は、響きが豊かで伸びがあり、音楽を歌わせやすいのです。手首が、音楽の呼吸をごく自然に導きます。スタッカートでさえ、手首の旋回運動を用いれば、弦楽器のピチカートのように、柔らかい響きの美しいスタッカートになります。
指を動かすことができるのは、関節があるからです。ピアノを弾く場合、もっとも使う関節は、もっとも大きい第一関節(手の付け根の関節)です。
第一関節がへっこんでいると、指全体の動きも悪くなり手が固まってしまいます。この第一関節を出すには、手をジャンケンのグーの形にしてみると簡単に出るようになります。その第一関節が引っ込まないように軽く指を開いていけば、ピアノを弾く時の手の形ができます(図1)。速いフレーズを弾くときは、指を立てることになりますが、メロディーや和音を柔らかい音色で弾く場合は、指のおなかの部分を用いるために、指を伸ばして弾く奏法が選択されることがあります。
指を伸ばして弾いてもピアノの音が豊かに響くのは、手首の旋回による力のためですが、その力を合理的に指先へ伝えるためには、第一関節だけは必ず出しておく必要があります。図1 手をジャンケンの形にする。
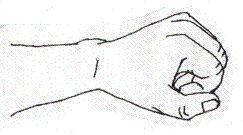
指を伸ばす奏法でも、第一関節は出す。
第一関節が引っ込んでしまった悪い手の形(図2)では、第二、第三関節を酷使してしまい、すぐに腱鞘炎になってしまいます。
腱鞘炎とは、手を開いたり閉じたりする運動を繰り返すことで、指の腱を包み込んでいる腱鞘という「さや」を摩擦で傷めてしまう病気です。
またハイフィンガー奏法のように、各指の関節を必要以上に動かしている場合も、腱鞘炎になってしまいます。一流ピアニストの指の動きを観察してみると、どんなに速いパッセージでも指そのものの動きは目立ちません。ところが、やたらに音が大きく、ガンガンと叩いたような汚い音を出す人は、指の動きそのものが目立ちます。こういう奏法では、腱鞘炎を含めて、何らかの手の故障を招くことになります。図2 悪い手の形。
ピアノを弾く手のかたちができたら、こんどはそれをほんの少し外側に傾けます。
ピアノを弾くとき、各指の重さは、粒のそろった音を発音させるために、平均化されていなくてはなりません。軽い3、4、5群の指を鍵盤に定着させるために、手全体を外側に少し傾けることで手全体の重量のバランスをとるわけです。手全体を外側に傾ける方法は、両肘を少し腋に近づけます(図3)。
たとえば、両肘をぴったり腋につけて指を伸ばせば「前にならえ」のかたちになって、1の指が上に起きていることが確かめられるでしょう。これは何を意味するのかというと、ピアノを弾くときに、両肘を腋に近づければ近づけるほど、重い1、2群の指は軽くなり、逆に軽い3、4、5群の指が鍵盤に定着するということです。
もし肘が上がっていれば、重い指がますます重くなり、軽い指は鍵盤上で浮くことになり、そうなると、軽く浮いた指では音が出ないので、音を出そうとするあまり、指に力を込めて無理やり鍵盤を叩こうとする結果になります。図3 両肘を腋に近づける。
クラシック音楽をピアノで演奏する場合は、イスは前半分に座るようにします。
なぜそういう座り方をするのかというと、腰をしっかり安定させるためと、場合によっては上半身の重さを腕や手を通じてピアノの鍵盤にかけるためです。
ジャズピアニストは、よくイス全体にドカッと座ってしまう人が多いのですが、これは、上半身の重さをわざとかけなくしている。つまり腕の重さだけを使って弾くことで、軽音楽としてのジャズを、文字通りライトな表現にするためだと思います。
そうすると、ライト(明るく、軽い、積極的)な時代の音楽であるバロック音楽を演奏するときも、イスに深めに座ることでライトな表現がしやすくなることがあるかもしれません。それに対して、ロマン派の音楽は、音色や雰囲気を成熟したレフト(落ち着いた音色、重い、消極的)な表現にしなくてはならないので、上半身を効率よく使うことで、和音などを重めで深い響きを伴った音色にしやすくなります。
イスの高さの調節は、鍵盤の演奏者の肘の高さとの関係を考慮する必要があります。その高さの種類は、大きく分けて3種類あります。
1)肘が鍵盤の高さより低い場合(図4−1)。ホロビッツ、グールド型。
この設定にすると、両肘が横に出にくいので、手の重さが自動的に保たれ、指先が安定します。
実は、指の動きというものは、指の筋肉だけで動いているのではなく、指の筋肉そのものは腕の筋肉とつながっています。さらに腕は、肩や背中の筋肉で支えられています。つまり指先の安定は、元をたどっていけば背中の筋肉の差さえが不可欠なのです。
肘を鍵盤よりも低く設定すると、常に腕を持ち上げなければならないので、必然的に背中の筋肉が用いられ、そのことが指先の安定に貢献するわけです。
このポジションだと、指先の軽い動きを使ってテクニカルに演奏できると思います。しかし、その反面、つねに腕を持ち上げ続けなければならないので疲れやすいという欠点があります。からだの小さい子どもたちには、あまり良いポジションではないかもしれません。図4−1 肘が鍵盤より低い 2)肘を鍵盤より高い位置にした場合(図4−2)。バレンボイム、アシュケナージ型。
この場合、腕全体は、鍵盤に向かって下ろす形になり、腕が楽です。また腕の重さを利用した、いわゆる重力奏法がやりやすくなります。しかし、両方の肘が出っ張りやすいという欠点があります。その場合、やや胸を張ると、背中の筋肉が機能し、肘の出っ張りを抑えることができるでしょう。
また腕の重さが利用できますから、からだの小さい人や、子どもたちには良いポジションだと思います。図4−2
3)肘を鍵盤と同じ高さにする(図4−3)。バックハウス、ケンプ型。
この場合、腕は、持ち上げるでもなく、下ろすでもないというような中間になり、すべてが中立的なバランスとなります。これは教則本などで紹介されている、教科書的な標準型と言えるでしょう。図4−3
からだが、ピアノから離れれば離れるほど、ピアノの音は薄くなり消えていきます。逆に、ピアノに近づけば近づくほど、自然に音が大きくなるという法則があります。そのために、プロのピアニストは、意外なほどからだとピアノとの距離が近い人が多いようです。
また多くのピアニストは、上半身をいつでもやや前方に傾けて演奏する人が多いです。とくに深みのある響きを出そうとする時は、鍵盤が目前に迫るほど上半身を前に倒して弾いているのを観察できます。上半身を前傾姿勢にすると、演奏者にとって音が聴こえ過ぎてしまって、音、全体の響きが掴めないという人もいます。しかし、私には、全然問題ないように聴こえますが、どうなのでしょうか。
逆に、上半身を後ろに反って弾いてみると、響きが浅くなり音が消えていってしまいます。しかし、上半身を前に倒していくと、自然に音の厚みが増していくのを実感することができます。ロマン派の作品を弾くのなら、前傾姿勢がたいへん有効でしょう。
バロック音楽や、前古典派の作品を演奏するのなら、上半身を真っ直ぐにして弾いて良いと思います。ライトな音色、雰囲気にするには有効です。しかし、どんな場合でも、上半身を後ろに反って弾くということは、ありえないでしょう。
指先の安定は、元をたどっていけば背中の筋肉の支えでしたが、さらに元をたどっていくと、背中を含めた上半身の安定を支えているのが下半身です。下半身の安定は、腹の緊張によって支えられています。腹の緊張がゆるんでいると、背中は曲がり、腕か支えられなくなり、指先はフニャフニャしてしまいます。
また、実際に声を出して歌うときは、腹筋による横隔膜の支えで歌いますが、ピアノを歌うように演奏しようと思えば、無意識のうちに、実際の歌う時と同じように、腹が緊張します。腹が緊張するというのは、魂と精神を明晰にさせるためにも大切なことです。
武道家や書道家などが、気を入れようとすれば、必ず腹にある丹田という場所を意識します。丹田は、おへその下から3センチほど下で、そこから少し奥まったところにあります。魂のある演奏をするためには、丹田を中心とした腹の緊張が不可欠です。魂のない弾き方をしている人は、必ず腹がゆるんでいます。
丹田に熱い魂が感じられるようになったら、今度は、頭にある精神を涼しく保つ必要があります。演奏に熱狂するあまり、頭まで熱くなってしまえば、理性を失ったルーズな演奏に陥ってしまいます。腹から、どんなに熱い魂が上ってきても、頭にある冷たい精神を下ろしていき、胸のあたりで暖かい心に中和されるように中庸性を保っていなければならないでしょう。
演奏中は、心のバランスを保つことも大切なのです。
ピアノの音を出すには、多かれ少なかれ、手首の旋回運動が伴っている必要があります。その時の、基本の旋回方向は、右手は下方向から左旋回(時計の逆回転)、左手は、下方向から右旋回(時計回り)になります(図5)。
図5
その旋回運動を、実際のメロディーに応用させるために、初めに「ドレミファソ」の五つの音列を使って練習してみると良いでしょう。その次に「ドミソ」や「ドミソド」のような広いスパンを練習してみます(譜例1)。
譜例1 反行型の音型は、左右の手首が対称的に動く。 転回形のアルペジオにおける旋回運動。
次に長い音を弾く時の旋回運動を練習してみましょう(譜例2)。
譜例2 長い音を弾く時の、旋回運動。 シューマン「コラール」〜ユーゲントアルバムから。
四分音譜は、長いとも短いともどっちとも言えない音符です。四分音譜を一まとまりの流れで演奏する場合は、音形に沿った手首の旋回運動を施します(譜例3−1)。
譜例3−1 バイエル10番
四分音譜の、一音一音の響きを重視する場合は、それぞれの音に手首の旋回運動を施します(譜例3−2)。
譜例3−2 バイエル85番
フレーズのおしまいの仕方は、二つの音を使って練習すると良いでしょう(譜例4)。この練習は、腕を軽く保つためと、肩や腕などの無駄な力を抜くためにも良い練習になります。またスタッカートにも応用できます(譜例5)。
譜例4 譜例5
音階やアルペジオを弾くときに、1の指をくぐらせようとするあまり、肘を上げて無理やり1の指を運びこもうとする人がよくいます(図6)。
この方法だと肘を上げるたびに、鍵盤に対する手の角度が斜めに傾いてしまい、1の指に不必要な重さが加わってしまいます。そうすると手のバランスが崩れてしまい、音楽の流れが損なわれ、常に1の指で打鍵された音はアクセントがついてしまいます。図6.1の指をくぐらせる時の、肘の悪い動き。
正しい方法は、肘を変化させないで(上げないで)、1の指をくぐらせる、3の指や4の指の第2、第3関節のあいだに向かって折り込んでいきます。
手全体は、外側に倒しぎみにします(図7)。図7
アルペジオの場合も、肘は上げません。
アルペジオは、音と音との間が広いので、くぐらせる指の音と、折り込んだ1の指との間が途切れそうになります。そこで、くぐらせる指を、鍵盤上で手前に大きく滑らせることで音がつながるようになります(図8)。図8
広い音域にわたる音階やアルペジオは、両端の音域(加線がついた音域あたり)を弾く時に、よくからだがおいてきぼりになることがあります。そうすると、その音域は響きを失ってしまいます。ピアノの音は、からだが楽器から離れていくと、しだいに消えていく法則があります。腕や上半身の重さが、鍵盤にかからなくなってしまうのです。
そこで、音を均一にさせるためには、音域に合わせて上半身を手とともに移動させなければなりません。移動させる方法は、二通りあります。一つは、弾く音域側にからだを寄せていく方法と、もう一つは、音域に合わせて、からだ全体を移動して座り直す方法です。
グランドピアノのペダルは、普通、三本、足元に突き出ています。
よく使うのが、一番右側にあるダンパーペダルです。ハーピストが、ハープをつま弾いた後、音を消すために頻繁に両手を弦に当てている様子を目にします。ピアノのダンパーは、ハーピストの掌に相当するもので、鍵盤から指を離すだけで、弾いた音を自動的に消してくれる便利な装置です。
ダンパーペダルを踏むと、消音装置のダンパーが弦から離れ、弦が開放され、ピアノがハープのような状態になります。音を一つ打鍵するだけでも、全ての弦が共鳴し、倍音が増幅され、みずみずしい艶やかな音色になり、音量も増します。
したがって、ダンパーペダルは、成熟した消極的な方向性を持ったロマン派以降の音楽に多く使われることになります。印象派の作品では、ダンパーペダルを特別長く踏むことで、わざと滲んだ響きを演出することさえあります。
ところが古典派の音楽では、音楽は積極的なものと消極的なものの中庸性がほどよく保たれている時代ですから、ダンパーペダルを使うとしても、滲みが目立たないように、使用頻度は最小限に抑えられます。モーツァルト時代のピアノは、このダンパーペダルの役割をするレバーが、鍵盤の下に取り付けてあったそうで、膝を持ち上げて、このレバーを押して、ダンパーペダルの効果を出していたそうです。そのことから見ても、モーツァルトの時代は、よほどのことがないと、ダンパーペダル(レバー)を使わなかったでしょう。
現代のグランドピアノは、古典時代のピアノに比べて弦の数も多く、響板もよく響くようになっています。そのために、古典の音楽を演奏する時は、ペダルの踏み替えをより繊細に行なうことが要求されるでしょう。次に多く用いられるのが、一番左側にあるソフトペダルです。
ピアノは、音量が豊かになるように、一つの音に対して3本の弦が同時に鳴るようになっています(低音域では、2本の場合や、太い巻き弦が1本のこともあります)。
ソフトペダルを底まで踏めば、鍵盤と共にハンマーがずれて、ハンマーは、弦3本ではなく、弦を2本だけ打鍵することになります。鳴る弦の数が減ると、音量は、小さくなりますが、より繊細な表現が可能になります。それは、一つのメロディーをギター3本でユニゾンとして奏でるよりも、ギター1本で独奏として演奏した方が、音色やニュアンスがより繊細に表現できるのに似ていると思います(ピアノでは、弦1本だけを響かせることはできませんが、気持的には、そのような気持でソフトペダルを用いることになるでしょう)。また、ソフトペダルを半分ほど踏むと、音量をほとんど変えずに、音色だけを柔らかくすることができます。
ピアノは使いこむと長年の打鍵により、ハンマーのフェルトの部分が圧縮され、3本の弦の打鍵の跡がハンマーにつき、固くなります。固くなったフェルトの部分で打鍵すると音色は固くなりますが、ソフトペダルを半分ほど踏むと、3本の弦の跡がついてしまった固い部分を避けて、ハンマーの柔らかい部分で打鍵することができます。その結果、打鍵する弦は3本のままなので音量はほぼ変わらないのですが、音色だけは柔らかくなるというわけです。
このようにソフトペダルを半ペダルで踏むと、音色がたちまちシューマンの音楽のように、柔らかくロマンチックな音色に変わるので、病み付きになってしまいます。まさに魔法のペダルで、多くのピアニストが、ソフトペダルから足が離すことができないのが理解できるでしょう。中央のペダルは、グランドピアノの場合、ソステヌートペダルで、初めに打鍵した音のダンパーのみが上がり、音が残るようにしたペダルです。
これは、主に、長い保続音を維持しながら、両手で和音などを変化させるときに使います。また、一つのアクセントの効果を出すときにも使われます。
また、これは一つのアイデアだと思うのですが、バロックや古典のコラールの部分を、普通のダンパーペダルでは豊かに響き過ぎると感じた時に、ソステヌートペダルを踏みかえて、軽いすっきりとした響きにするのも面白いと思います。これは結局、普通に弾いているのと響き自体は同じですが、和音の繋がりがスムーズになって良いのです。