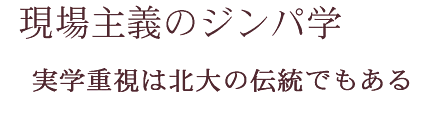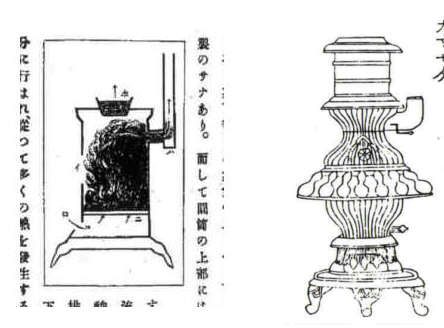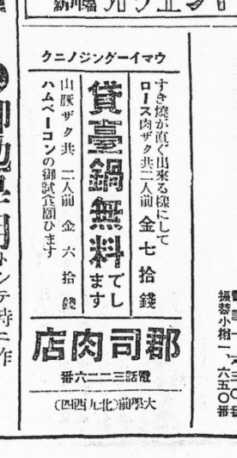|
丂慜夞丄巹偼僕儞僊僗僇儞偺尨宆偲尒傜傟傞椏棟偺柤慜偑係偮傕偁傞偲巜揈偟傑偟偨丅拞崙岅偱偼僐僂偲偄偆敪壒傜偟偄壩滸偵峫偲彂偔烤丄偦偺屻傠偵梤擏偑偮偄偨柤慜偺椏棟偑棦尒偺尒暦傪偼偠傔嵟傕懡偄嘆烤梤擏偱偡丅偙偺烤丄側偳偼俰俬俽偺戞俀悈弨偵傕側偄帤側偺偱丄倀俶俬俠俷俢俤乮俠俽俲摑崌娍帤乯傪巊偭偰偄傑偡丅摨僐乕僪偱偼柧挬懱偑庡傜偟偔丄僑僔僢僋懱偺烤偼摿偵壓晅偒偱偓偛偪側偄姶偠偑偡傞偺偱偡偑丄傗傓傪摼傑偣傫丅傕偟偐偡傞偲丄偙傟傜偺帤偑弌側偄婡庬偑偁傞偐傕抦傟傑偣傫丅偦偺偲偒偼偛姩曎婅偄傑偡丅偮偄偱偵偍抐傝偟偰偍偒傑偡偑丄偟傖傇偟傖傇偺 梤擏偺 梤擏偺 偼丄巹偑倞倫倗偱嶌帤偟偨傕偺偱丄廲朹丄墶朹偲傕侾僺僋僙儖扨埵偺慄偟偐堷偗傑偣傫偺偱丄傕偭偲傑偢偄帤懱偵側偭偰偄傞偺傪婥偵偟偰偄傞傫偱偡傛丅偦傟偐傜寧姦庬梤応偵偄偨偲偒嶳揷婌暯偝傫偑彂偄偨杮乽柹梤偲懘帞傂曽乿偱抦傜傟傞嘇撶梤擏丄摨偠偔偦偺寧姦偱偼嶳揷偝傫偺辍偐屻攜偵側傞掁扟栆偝傫偺嘊崅梤撶丄杒戝偺嵅乆栘撗擇愭惗偺嘋從梤擏偲係捠傝偺柤慜偑丄偙傟傑偱偵尰傟偰偄傞偐傜偱偡丅傒傫側僐僂儎儞儘乕丄僇僆儎儞儘乕偲偄偆帡偨怳傝壖柤傪晅偗偰偄傞偺偱偡偑丄摨偠椏棟偱偼側偄偺偐偳偆偐丅 偼丄巹偑倞倫倗偱嶌帤偟偨傕偺偱丄廲朹丄墶朹偲傕侾僺僋僙儖扨埵偺慄偟偐堷偗傑偣傫偺偱丄傕偭偲傑偢偄帤懱偵側偭偰偄傞偺傪婥偵偟偰偄傞傫偱偡傛丅偦傟偐傜寧姦庬梤応偵偄偨偲偒嶳揷婌暯偝傫偑彂偄偨杮乽柹梤偲懘帞傂曽乿偱抦傜傟傞嘇撶梤擏丄摨偠偔偦偺寧姦偱偼嶳揷偝傫偺辍偐屻攜偵側傞掁扟栆偝傫偺嘊崅梤撶丄杒戝偺嵅乆栘撗擇愭惗偺嘋從梤擏偲係捠傝偺柤慜偑丄偙傟傑偱偵尰傟偰偄傞偐傜偱偡丅傒傫側僐僂儎儞儘乕丄僇僆儎儞儘乕偲偄偆帡偨怳傝壖柤傪晅偗偰偄傞偺偱偡偑丄摨偠椏棟偱偼側偄偺偐偳偆偐丅
丂偦偙偱掁扟偝傫偑彂偄偨乽寧姦廫屲擭乿傪専嶕偟傑偡偲丄杒戝恾彂娰杒暘娰偵侾嶜偁傝傑偡丅庁傝偰挷傋傑偟偨傜丄掁扟偝傫偼媽惂峅慜崅峑偱丄傢偑暥妛晹偵偍傜傟偨娭惔廏愭惗偺恊桭偩偭偨曽偱丄徍榓侾俉擭偐傜侾俆擭娫寧姦庬梤応偵嬑柋偟丄悘昅僒儞働僀偵擖慖偟偨偙偲傕偁傞丄偄傢備傞彂偒庤側傫偱偡偹丅杮偼丄偦偆偟偨尨峞傪廤傔偨傕偺偱丄幚嵺偵彂偄偨偺偼杮傛傝俆擭憗偄俁俆擭偵彂偐傟偨傕偺偱偟偨丅偙傟偐傜攝傞帒椏偺侾枃栚偑丄埄夛偑拪弌偟偨売強傪娷傓掁扟偝傫偺乽惉媑巚娋撶乿偲偄偆侾復偱偡丅偱偼攝偭偰壓偝偄丅巹偑尒傞偲偙傠丄偪傚偭偲挿偄偺偱偡偑丄側偐側偐柺敀偄僸儞僩傪娷傫偱偄傑偡丅
帒椏偦偺侾
丂偦偺愄丄偐偺塸梇惉媑巚娋偑栔屆偺戝孯傪堷偒偮傟偰儓乕儘僢僷傪惾尀偟偨偲偒丄栰愴偵偍偄偰惙傫偵僸僣僕偺鄑傝從偒傪偟丄墦偔屘嫿傪悧傟偰嫿廌偵嬱傜傟傞暫巑偺搚婥屰晳偟偨偙偲偐傜丄惉媑巚娋撶椏棟偑惗傟偨偲偄傢傟偰偄傞丅偟偐偟丄尰嵼偺栔屆恖偼僸僣僕傪娵偛偲挿帪娫墫浈偱偟偰怘傋傞偺偑庡偱丄從擏偼傗傜側偄偲偙傠偐傜傒傞偲丄偳偆傕偙偺揱愢偼偪偲夦偟偄丅
丂岅尮偺慒媍偼偝偰偍偒丄巹偳傕偺娽偵怗傟傞惉媑巚娋撶偺傾僀僨傾偼丄杒嫗偺斞揦椏棟偱偁傞崅梤撶偐傜偒偨傕偺偱偁傞丅崅梤撶偲偄偆偺偼丄栔屆偺墱抧偐傜棃偨僸僣僕傪杒嫗偺峹奜偱嶰僇寧偺娫崟戝摛乮偙偙偑旈實偲偄偆乯傪怘傋偝偣偰旍堢偟丄徏偺巬偲徏梩傪栰奜偱擱傗偟丄揝斅傪忔偣丄偦偺忋偱梤擏傪從偒丄僄價偺桘偵僯儞僯僋偺擖偭偨僞儗傪偮偗偰怘傋傞悳傞栰庯偵晉傫偩椏棟偱偁傞丅徏偺栘偵懌傪偐偗墝偑傕偆傕偆偲棫偪徃傞拞偱怘傋傞偙偺椏棟傪丄壗偲偐擔杮偺壠掚偵帩偪崬傔側偄傕偺偐偲嬯怱偟偰偒偨偑丄戝惓廫擇擭崰偵側偭偰僐儞儘偺忋偵儘僗僩儖宆偺揝斅傪忔偣偰從偒丄忀桘丒嵒摐丒庰丒惗汭偲偄偭偨擔杮庯枴偺枴傪妶偐偟偨僞儗傪嶌偭偰傒偨傜丄埬奜偄偗傞偲偟偰惗傑傟偨偺偑寧姦棳惉媑巚娋撶側偺偱偁傞丅
丂乮偙偺拞娫偺俀俀俈帤徣棯乯
丂嵟嬤奺抧偱惉媑巚娋撶偑惙傫偵側偭偰偒偨丅寢峔側棳峴偩偑丄偨偩巆擮側偺偼丄梤擏傪嬦枴偣偢丄帟愗傟傪巟攝偡傞擏曅偺愗傝曽偼弌扡栚丄枴妎傪寛掕偡傞僞儗偑忀桘偵僯儞僯僋傪擖傟偨掱搙偺傂偳偔偍慹枛側傕偺偱丄梤摢嬬擏偺惉媑巚娋撶偑墶峴偡傞偙偲偱偁傞丅惉媑巚娋撶傪旤枴偟偔怘傋傞僐僣偼丄梤擏偺岤偝傪堦暘偖傜偄偵偟丄昁偢嬝慇堐偵懳偟捈妏偵愗傞偙偲偲丄擏曅傪嫮壩偱僒僢偲棤柺傪從偒丄乮擏廯偑偠傘偆偠傘偆弌傞傛偆偱偼壩偑庛偄乯栻枴偺擖偭偨僞儗傪偨偭傉傝偮偗偰怘傋傞偙偲偱偁傞丅敿從偒偖傜偄偑怘傋崰偲偄偆偲偙傠偩偑丄偳偆傕從栞從偒偺恖偑懡偔丄挿偔從偒偨偑傝徟偑偟偰偟傑偆丅徟偘傞偲晄枴偄偐傜惉媑巚娋撶偼僙儖僼僒乕價僗偑僄僠働僢僩偱偁傝丄帺暘偱從偄偰怘傋傞偵尷傞丅愜妏偺惉媑巚娋撶傕丄僞儗偑晄枴偔偰偼榖偵側傜傫偺偱丄寧姦棳偺僞儗偺嶌傝曽偺旈實傪丄壠尦偵戙偭偰揱庼偟傛偆丅
丂屲恖慜傪昗弨偲偡傞応崌丄梤擏屲昐栨偼丄側傞傋偔庒偄梤乮擏偺怓偑敄偔帀偑彮側偄乯偺丄偟偐傕擏曅偺戝偒偄傕偺偱搄嶦屻堦廡娫偖傜偄宱偨傕偺傪慖傇偙偲丄擏偼梊傔愗偭偰偍偒丄忀桘嶰崌偵嵒摐屲乑栨傪擖傟丄偪傛偭偲壩偵偐偗丄忀桘偺惗廘偄擋傪徚偟丄擪屲杮偺峣傝廯丄椦岀嶰乣巐屄偺峣傝廯丄擔杮庰堦崌傪擖傟丄峏偵桵巕堦屄偺峣傝廯偲惗汭戝堦屄傪僆儘偟偨峣傝廯傪擖傟丄壔妛挷枴椏丄搨恏巕彮検傪壛偊丄嵟屻偵偙傟傜偺枴傪梈榓偝偣傞偨傔偵僯儞僯僋堦屄偺峣傝廯傪擖傟傞丅僯儞僯僋傪擖傟側偄偲枴妎偵夋棾揰惏傪寚偔偙偲偲側傝僩儘僢偲偟偨僐僋偺偁傞枴偲側傜側偄丅
丂弌棃偁偑偭偨僞儗敿検偵丄愗偭偨擏傪擇乣嶰帪娫捫偗偰偍偒丄敿検偼從偄偨擏傪偮偗傞僞儗偲偡傞丅栻枴偲偟偰偼擪偲僷僙儕偺旝恛愗傝傪揧偊傞偲旤枴偟偔懻偗傞偙偲偆偗偁偄偱偁傞丅婫愡偵傛偭偰偼丄壥廯偲偟偰丄儈僇儞丒壞儈僇儞傪壛偊傞偲堦憌旤枴偟偔側傞丅撶偑側偗傟偽嬥栐偱寢峔偱偁傞丅枖嬍擪偺椫愗傝傗挿擪偲堦弿偵從偄偰怘傋傞偺傕夒枴傪揧偊傞偙偲偵側傞丅惀旕偍帋偟偁傟丅乮嶰屲丒堦丒擇堦乯
| 丂丂 |
嶲峫暥專
弌揟偼掁扟栆挊乽寧姦廫屲擭乿侾俇俆儁乕僕丄徍榓係侽擭俈寧丄掁扟栆暥廤姧峴夛亖尨杮
|
丂僕儞僷妛偲偟偰偼乽巹偳傕偺娽偵怗傟傞惉媑巚娋撶偺傾僀僨傾偼乿偐傜乽埬奜偄偗傞偲偟偰惗傑傟偨偺偑寧姦棳惉媑巚娋撶側偺偱偁傞乿偲偄偆偲偙傠傑偱傪嵟傕廳帇偟傑偡丅掁扟偝傫偼俀搙乽崅梤撶乿偲彂偄偰偄傑偡丅俀夞栚偺崅梤撶偼乽偙傟偼乿偲戙柤帉偱傕嵪傓偺偵丄傢偞傢偞崅梤撶偲彂偄偨傢偗偑偁傝丄偙偺屇傃曽偵帺怣傪帩偭偰彂偄偨偲巚傢傟傑偡丅奆偝傫傕偦偆巚偄傑偣傫偐丅偮傑傝丄崻嫆偲偟偰侾偮栚偼崟戝摛偱旍傜偣偨梤傪怘傋傞偺偩偲偄偆偙偲丄俀偮栚偼栰奜偱徏偺巬偲徏梩傪擱傗偟丄揝斅偱擏傪從偔偲偄偆偙偲丄俁偮栚偼僄價偺桘偵僯儞僯僋偺擖偭偨僞儗傪偮偗傞偲偄偆怘傋曽丄偙偺俁偮偼偙傟傑偱弌偰偙側偐偭偨忣曬偱偁傝丄抦偭偰偄傞恖偼彮側偄偩傠偆偲掁扟偝傫偑敾抐偟偰偄偨偲巚傢傟傑偡丅偙偺俁攺巕偦傠偭偨傕偺偑崅梤撶側傫偩傛偲偄偭偰偄傞傫偱偡偹丅
丂偟偐偟丄僀儞僞乕僱僢僩偱崅梤撶偱専嶕偟偰傕丄変偑僕儞僷妛偺儂乕儉儁乕僕埲奜偵弌偰偒傑偣傫丅峀偄拞崙偺偳偙偐偱偦偆偄偆儊僯儏乕傪尒偨偲偄偆側傜丄偄偔偮偐弌偰偒偰傛偝偦偆側傕偺偱偡偑丄僛儘側傫偱偡丅掁扟偝傫僆儕僕僫儖偺摉偰帤偺壜擻惈戝側傫偱偡偹丅崅偼崅怆丄僐僂儕儍儞偺崅偱偡偐傜僐僂偲撉傔偦偆側婥偑偡傞傫偱偡偑丄偳偆傕偙傟偼擔杮岅撉傒偱偁偭偰丄偁偪傜偱偼僈僆儕儍儞偲偄偆傛偆側偺偱偡丅梤擏偼儎儞儘乕偲壗搙傕撉傫偱偄傑偡偐傜丄梤堦帤側傜儎儞偲偄偆偙偲偼偼傢偐傝傑偡偹丅寛掕揑偵堘偆偺偼撶側傫偱偡偹丅乽曢傜偟偺拞崙岅扨岅俈侽侽侽乿偵傛傞偲丄撶椏棟偼壩撶偲彂偄偰僼僅乕僌僅乕丄搚撶幭崬傒椏棟偼嵐撶偲彂偄偰僔儍乕僌僅乕(1)偲偁傝傑偡丅偱偡偐傜崅梤撶偼僈僆儎儞僌僅乕偲偄偆偙偲偵側傜偞傞傪摼傑偣傫丅傑偨崙棫柉懎妛攷暔娰柤梍嫵庼偺廃払惗偲偄偆曽偑彂偄偨乽悽奅偺怘暥壔丂拞崙乿偵傛傟偽乽撶偼丄昗弨岅偱亀撶亁偲偄偆偑丄峀搶偱偼亀鑊亁偲偄偆乿(2)偦偆偱偡偐傜丄偙偪傜偺昗弨岅偺敪壒偵廬偊偽僈僆儎儞僋僁僆偱偡偹丅崅偩偗僇僆偲偄偆偙偲偵偟偰傕僇僆儎儞僋僁僆偱掁扟偝傫偑偮偗偨乽偙偆傗傫傠偆乿偲偄偆儖價偲偼丄偲偰傕崌抳偟偦偆偵側偄偺偱偡丅
丂偙偺乽悽奅偺怘暥壔丂拞崙乿偼丄烤梤擏偺烤偵偮偄偰傕夝愢偟偰偄傞傫偱偡丅廃偝傫偵傛傞偲偱偡偹乽偁傇傞偙偲傪烤偲偡傞偺偼丄杒曽偺丄偟偐傕傢傝偁偄怴偟偄偄偄曽偱偁傝丄尦棃偺偁傇傞偼亀從亁偱偁偭偨偺偩丅崱擔丄昗弨岅偼丄偁傇傞傪亀烤亁偵偟偰偍傝丄亀從亁偼丄偨偒栘傪擱傗偡応崌偵偼丄從偔偺堄枴傪帩偮偗傟偳傕丄椏棟梡岅偲偟偰偺亀從亁偼丄從偔傪堄枴偟側偄丅椏棟朄偱偄偆亀從亁偼丄嵽椏傪堦搙鄒傔偰怓偑曄偭偨傜丄僗乕僾傪擖傟偰枴晅偗偟丄庛壩偱擃傜偐偔幭崬傓偙偲傪偄偆乿(3)偺偩偦偆偱偡丅乽傢傝偁偄怴偟偄偄偄曽乿偲廃偝傫偼丄偁偭偝傝彂偄偰偄傞偗傟偳傕丄変偑僕儞僷妛偱偼丄偦傟偱偼嵪傑偝傟傑偣傫丅乽烤乿偼乽烤梤擏乿偺偨傔偵嶌傜傟偨帤偩偲偄偆愢傕偁傞傛偆側偺偱丄偦偺偁偨傝偺暥專扵偟傪偟偰偐傜屻擔島媊偟傑偡丅
| 丂丂 |
嶲峫暥專
忋婰乮侾乯偺弌揟偼嵅摗惓摟挊乽曢傜偟偺拞崙岅扨岅俈侽侽侽乿係俋儁乕僕丄暯惉侾係擭俋寧丄姅幃夛幮岅尋亖尨杮丄乮俀乯乮俁乯偼偄偢傟傕廃払惗挊乽悽奅偺怘暥壔丂拞崙乿俈俆儁乕僕丄暯惉侾俇擭侾寧丄擾嶳嫏懞暥壔嫤夛亖尨杮
|
丂徏梩偲偐徏妢傪擖傟偰鄮偡偲晽枴偑憹偡偲嶳揷偝傫傕彂偄偰偄傑偡偑丄嶳揷偝傫偼杒嫗偵偮偄偰偼壗傕怗傟偰偄傑偣傫偐傜丄棦尒偺婭峴暥乽枮巟堦尒乿傪撉傫偱偄側偄恖偵偼丄側偤徏梩偱鄮偟婥枴偵偟偰晽枴傪偮偗側偗傟偽側傜側偄偺偐傢偐傝傑偣傫偟丄偦偆偄偆偙偲傪堦愗抦傜側偄恖偵偼掁扟偝傫偺島庍偼怴忣曬偱偡傛偹丅偝傜偵乽僄價偺桘偵僯儞僯僋偺擖偭偨僞儗乿偼乽枮巟堦尒乿偱傕怗傟傜傟偰偄傑偣傫偐傜嬌傔偰巃怴側忣曬偱偡丅
丂偄偢傟奆偝傫偵偍帵偟偟傑偡偑乽枮巟堦尒乿偱棦尒偝傫偼丄偨傟偵偮偄偰偼忀桘儀乕僗偱丄傃傝偭偲偡傞枴偱層灒偑擖偭偰偄傞傜偟偄偲偄偆偖傜偄偟偐彂偄偰偄傑偣傫丅掁扟偝傫偺偄偆崅梤撶偺僞儗偼丄偙偺昞尰偱偡偲僄價偺桘側傞傕偺偑儀乕僗偱偁傝丄偦傟偵僯儞僯僋偺旝恛愗傝偐峣傝廯偑擖傞偲側傝傑偡丅偟傚偭傁偄偺偐娒偄偺偐丄偙傟偩偗偱偼傛偔傢偐傜側偄偱偟傚偆丅幚偼僄價偺桘側傞塼懱偼丄擔杮偺偟傚偭偮傞撶偺偟傚偭傞丄儀僩僫儉椏棟偺僯儑僋儅儉偺偵摉偨傞僄價偺嫑忀側偺偱丄偟傚偭傁偄偼偢側偺偱偡偑偹丅偲偵偐偔巹偺島媊偱偼弶傔偰弌偰偒偨怴偟偄挷枴椏偱偡丅
丂偲偙傠偑偱偡偹丄掁扟偝傫偼偱偡傛丄巆擮側偑傜乽戝惓侾俀擭偛傠乿偲偄偆徹嫆傪壗傕帵偟偰偄傑偣傫丅偟偐偟丄奆柍偱偼側偐偭偨偺偱偡丅幮抍朄恖杒擾夛偑弌偟偰偄偨嶨帍乽杒擾乿偺徍榓俁俁擭侾寧崋偵嵹偭偰偄傞擭昞乽擾椦徣杒奀摴擾嬈帋尡応抺嶻晹乿偺戝惓侾俀擭偺棑偵乽梤擏棙梡偺偨傔儘僗僩儖宆僕儞僊僗僇儞撶傪峫埬乿(4)偲婰嵹偝傟偰偄傑偡丅偙傟偼杒奀摴擾嬈帋尡僙儞僞乕偺偁傞曽偐傜嫵傢偭偨偙偲偱偟偰丄妋偐偵偦偺捠傝婰嵹偝傟偰偄傑偡丅掁扟偝傫偑悘憐傪彂偔俀擭慜偱偡偐傜丄偙傟偑崻嫆偩偭偨偐傕抦傟傑偣傫丅廫暘偁傝摼傞偙偲偱偡丅
丂偙偺擭昞偼乽杒奀摴偵偍偗傞擾嬈帋尡婡娭擭昞乿偲偄偆楢嵹偺帒椏夝愢偱丄寧姦偺擾彜柋徣寧姦庬媿杚応偐傜庬抺杚応丄庬梤応偲偄偆棳傟偲丄奐戱巊偑嶌偭偨恀嬵撪杚媿応偐傜杒奀摴庬抺応偺棳傟偺椉幰傪暪婰偟偨擭昞偱丄撶峫埬偼擾彜柋徣戧愳庬梤応寧姦暘応偺懁偵擖偭偰偄傑偡丅偝偐偺傏偭偰尒傑偡偲丄寧姦偱梤傪帞偄巒傔偰俇擭屻偵摉偨傞戝惓俁擭偺棑偵乽梤擏棙梡乮枴慩捫丅敂捫乯傪帋傓乿(5)偲偁傞偺傪尒偰丄僺僇僢偲偒傑偟偨偹丅敂捫偗偺屆偄峀崘偱偡丅偦傟傪帒椏偦偺俀偲偟傑偟偨丅
丂
帒椏偦偺俀
丂丂丂丂榋壴摪拝壸巙傜偣
媿擏敂捫
堦媿擏敂捫傪屼梡傂偺愡僴敓偺拞傛傝庢弌偟傆偒傫埥偼巻偵偰敂傪偸偔傂枖懘擏偺巆傝傪挋僴傊傞偵偼傛偔乛乢敂傪偮偗抲杮偺敓偵擖傟偰婥偺偸偗偝傞條屼巇晳抲側偝傟岓僴乀晠攕偺姵傂側偔傑偨枴傂偺曄傞帠側偟壖椷媿擏寵傂偺屼曽偵偰傕偦偺擋傂偡傞帠側偔堦搙屼怘梡偁傟偼懘枴傂岥偵堨傟暊偵枮傞掱偵巙偰偨偲備傞偵暔側偟桺屼怱摼偺偨傔椏棟曽峳憹婰偟抲檤偵側傓
丂搶嫗旜挘挰擇挌栚丂杮曑丂峃梴尙
堦搾悈偵偰偁傜傊偼枴傂傪偦偙偺傆備傊屼拲堄側偝傞傊偟
堦媧暔偵偰偡傞偵僴搾傪偞偮偲煑偨偰擏傪傛偒掱偵擖傟從墫傪偍偲偟敄壛尭偺偮備偵偟偰惵傒傪壛傊梡備傊偟枖栰嵷傕偺乀拞偵擏傪擖傟煑偰梡備傞傕帄嬌媂偟
堦偁傇傝擏偼孁埥偼偁傒偺忋偵忔偣傎傫偺傝偲偁傇傝偰從墫偐忀桘傪偮偗偰梡備傊偟枖僴晅偗從偵偟偰傕傛傠偟
堦桘偵偰梘傞偵僴敂傪偍偲偟擏傪傛偒掱偵偒傝儂儖僩桘枖僴層杻桘偵偰偁偘丅偐傜偟傪晅偗偰梡傂枖偼懘樤偝偟傒偵偟偰梡傂偰帄嬌傛傠偟
堦敂廯偼媿擏傪梡傂偨傞巆傝偺敂傪枴慩偵偡傝岎偤傛偔煑偨偰鍎敻埥偼摛晠枖僴戝崻摍偺椶傪擖傟偰梡備傊偟晽枴寢峔偵偟偰彮偟傕媿偺偵傎傂偡傞偙偲側偟
堦捫傕偺傪偡傞偵僴擏傪弌偟偨傞愓偺敂偵塟側偡傃戝崻摍偺椶傪堦墫偵偟偰堦拫栭掱捫偰梡備傊偟栟偲傕帪岓偵傛傝偰捫偐偘傫僴屼尒搇傂側偝傞傊偟
堦慛嫑傪捫傞偵堦墫偟偰懘嫑偵墫壛尭偺峴夢傝偨傞帪傪尒偰梡備傊偟枖墫巙偨傞嫑偼掱擻偒墫偐偘傫偺檤傪捫偰梡備傊偟壖椷壗昳傪捫偗偰傕寛偟偰媿偺擋傂偡傞帠側偟
堦擏傪嬌榓傜偐偵偡傞帪僴嵶壩偵偰堦帪娫掱煑偰梡備傊偟
崯奜梡傂曽怓乛乢偁傝屼帋傒偺忋偵偰椏棟曽偼桺屼岺晇偺掱曃偵婩傞檤偵側傫
怴敪柧
嶘偺敂捫
崯敂捫彚忋偺偣偮敂傪傛偔偸偔傂丅偝偟傒偵梡傤偰傛偟枖從暔偵傛偟扐偟巆傝偺敂偼壗昳傪捫岓嫟懘晽枴傛偟
丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂搶嫗丂楅栘媑暫塹惢
嶘偺幭庢
姀偺幭庢
怴敪偐傜偔傝丅巙偐偗
彫帣傛傠偙傇壻巕
塃拝壸巇岓娫晄憡曄屼帋偟偺忋屼昡敾曭婓忋岓
丂丂丂丂敓娰撪娎挰堦斣抧
戝擔杮撪崙怴敪柧
怘梡昳挷恑強丂丂丂丂丂丂榋壴摪
柧帯侾係擭俆寧俉擔晅敓娰怴暦晬榐傛傝
丂柧帯偺暥復側偺偱帺暘偱戺揰傪晅偗偰偹丄僈僋偑側偄偲偡傜偡傜撉傔側偄丅幚暔偼慻傒曽偵曄壔傪帩偨偣丄怳傝壖柤偑偁傞偺偱懡彮撉傒傗偡偄偺偱偡偑丄偲偵偐偔摨偠敂捫偗偱傕媿擏偲嶘擏偱偼愢柧暥偺挿偝偑戝堘偄偲偄偆揰偵拲栚偟偰壓偝偄丅敂偺棙梡傪彍偗偽丄媿擏偺椏棟愢柧係崁栚偵懳偟偰嶘偼侾崁栚偟偐偁傝傑偣傫丅偙偺堘偄偼丄怴偟偄怘嵽偱偁傞媿擏丄偟偐傕偦偺敂捫偗偑栚怴偟偐偭偨偐傜偩偲峫偊傞偺偱偡丅暥拞偺儂儖僩桘偲偼僆儕乕僽桘偺偙偲偱偡丅怘傋曽傪嫵偊側偗傟偽丄壠寁戞堦偺墱偝傫偳傕偼嵸偒姷傟偨嫑傪慖傫偱偟傑偆丅傑偨壗搙傕愰揱偟偰偍偗偽丄撍慠偺庰媞偵乽偙傟偼媿擏偺敂捫偗側傫偱偡偑丄偍岥偵崌偄傑偡偐偳偆偐乿側傫偰偹丄媞懁傕乽怴暦峀崘偱偼抦偭偰偄傑偟偨偑丄偙傟偑偦偆偱偡偐乿偲姶怱偟偰傒偣傜傟傞偭偰傕傫偱偡丅
丂偙偺峀崘偺偙傠偐傜係侽擭屻丄寧姦偱偼偦偺愄偼怴怘嵽偱偁偭偨媿擏傪丄枹抦偺梤擏偵抲偒姺偊偰傒偰偄偨傫偱偡偹丅枴慩丄庰敂傪偸偖偭偰鄤偭偨傝偟偨傫偱偟傚偆偹丅偱傕擭昞偵偼弌揟傗擭昞嶌惉幰偺柤慜偑婰嵹偝傟偰偄側偄偺偱丄偙傟埲忋偼傢偐傝傑偣傫偗偳丄壩偺側偄偲偙傠偵墝偼棫偨偸丅壗偐崻嫆偑偁偭偨傫偱偟傚偆丅
丂擭昞偲掁扟偝傫偺戝惓侾俀擭偛傠姰惉愢傪怣梡偡傞偲偱偡傛丄杒嫗幃偺忣曬偑庬梤応徃奿偺偙傠擖偭偨偲偡傟偽丄侾俀擭傑偱偺係擭娫偖傜偄丄傕偆彮偟屻偩偭偨偲偟偰傕俀擭偖傜偄偼杒嫗捈揱丄徏偺栘鄮偟傪幒撪偱傗偭偰傒偨丅僄價桘偑嶥杫偱庤偵擖偭偨偐偳偆偐傢偐傝傑偣傫偐傜丄彮側偔偲傕僯儞僯僋擖傝忀桘偺偨傟偱怘傋偨偙偲偑峫偊傜傟傑偡丅
丂徏偺栘偵懌傪偐偗偰怘傋傞偲偄偆榖偼乽枮巟堦尒乿偺楩偺慜偵懌忔偣戜偑偁偭偨偲偄偆曬崘偲丄屻偱弌偰偒傑偡偑丄媣曐揷枩懢榊偺彫愢偺徏梩鄮偟偑崿偠偭偰偱偒偨偺偱偼側偄偐偲巚傢傟傑偡丅墝偑傕偆傕偆偲棫偪徃傞拞偱怘傋傞偙偺椏棟傪丄偪傖傇戜傪埻傓乽擔杮偺壠掚偵帩偪崬傔側偄傕偺偐偲嬯怱偟偰偒偨乿偲彂偄偰偁傞偺偱偡偐傜丄彮側偔偲傕弶婜偼杒嫗幃偵嬤偄宍偱庢傝崬傕偆偲偟偨偺偱偟傚偆丅
丂偲偄偆偺偼丄彫扟偝傫偑庢傝擖傟偨揷拞幃梤擏挷棟朄偺揷拞岹攷巑傕偱偡偹丄撠擏椏棟偼榓晽偲偄偆傋偒嶌傝曽偵帄傞慜抜偱丄摨偠傛偆偵巟撨椏棟晽偐傜偺扙媝偵嬯怱偟偨傜偟偄偐傜偱偡丅戝惓係擭偺嶨帍乽椏棟偺桭乿偺僀儞僞價儏乕婰帠傪尒傞偲乽撠擏椏棟傕嬤崰梋掱曄偭偰嶲傝傑偟偨丂嶲峫偺偨傔偵屼棗傫壓偝偄偲帵偝傟偨偺偼屲擭慜摨揁偱嵜偝傟偨帋怘夛偺專棫偱偁傝傑偟偨丂擵偵埶傞偲攷巑偑撠擏椏棟尋媶偺帒椏傪巟撨椏棟偵媮傔偨帠偼栜榑偱丂廬偭偰摉帪偺椏棟偼巟撨廘枴傪扙偣側偐偮偨偺偱偁傝傑偡丅慠傞偵嵟嬤偵帄偮偰扺攽側椏棟偵撻傟偨擔杮恖偺偺岥偵傕婌偽傞乀傗偆偵岺晇偣傜傟傑偟偨偺偼堦抜偺恑曕偲巚偼傟傞偺偱偁傝傑偡丄嵍偵徯夘抳偟傑偡偺偼懄偪戝偵擔杮壔偟偨撠擏椏棟偺專棫偱偁傝傑偡乿(6)偲彂偄偰偁傞偙偲偐傜丄偦偆悇嶡偡傞傢偗偱偡丅
丂擔杮恖岦偒偵曄偊傞側傜丄側偤傕偭偲憗偔乽忀桘丒嵒摐丒庰丒惗汭偲偄偭偨擔杮庯枴偺枴乿偺偨傟嶌傝傪巚偄偮偐側偐偭偨偺偐偲偄偆媈栤偑摉慠婲偒傑偡傛偹丅掁扟偝傫偼丄偦傟偵偮偄偰壗傕愢柧偟偰偄傑偣傫丅擭昞嶌惉幰偼扤偐偺乽儘僗僩儖偱從偔傛偆偵側偭偨偺偼娭搶戝恔嵭偑偁偭偨擭偩偭偨偐側偁乿側偳偲偄偆巚偄弌榖偐傜丄戝惓侾俀擭偛傠偲妱傝弌偟偨偺偐傕抦傟傑偣傫丅偦傟偲傕掁扟偝傫偼丄撶杮懱偲偨傟傪暘偗偰峫偊丄杒嫗偺撶傪庤杮偲偟偰儘僗僩儖宆偼摉弶偐傜巊傢傟偰偍傝丄偦傟僾儔僗榓晽偺偨傟偑偱偒偨丅傕偟偔偼偨傟愭丄撶屻偲偄偆宱夁傪傑偲傔偰乽儘僗僩儖宆偺揝斅傪忔偣偰從偒乿乽擔杮庯枴偺枴傪妶偐偟偨僞儗傪嶌偭偰傒偨乿偲彂偄偨偙偲傕憐憸偱偒傑偡丅
丂偄傑偼撈棫峴惌朄恖擾嬈媄弍尋媶婡峔杒奀摴擾嬈尋媶僙儞僞乕偲偄偆偺偑惓幃側偺偱偡偑丄偦偺僙儞僞乕偺尋媶幰偱丄俀奒寶偰偺彂屔傪娗棟偟丄帺桼偵弌擖傝偟偰偄傞朸塣摦晹偺屻攜偼丄偦偆偟偨梤擏怘偺婰榐偺傛偆側傕偺偺懚嵼偼抦傜側偄偲偄偭偰偄傑偡丅乽杒擾乿婰嵹傪嫵偊偰偔傟偨曽傕丄戝惓侾俀擭愢偺棤晅偗偲側傞堦師帒椏偼尒摉偨傜側偄偲偄傢傟傑偡丅偡偖偵偼怴暦婰幰偺帹偵擖傜側偐偭偨偲峫偊偰侾擭屻丄偮傑傝戝惓侾俁擭偺杒奀僞僀儉僗傪挷傋偰傒傑偟偨傜丄俀寧偵戨愳庬梤応偺徏壀拤堦応挿偑乽変崙柹梤帠嬈偺慜搑丂帠嬈奐巒洧偵幍擭丂姱嬈柉嬈嫟偵椙岲乿偲偄偆挿偄戣柤丄偙傟偼尒弌偟偲偄偆傋偒偱偟傚偆偑丄偲傕偐偔曬崘傪俉夞婑峞偟偰偄傑偡丅偦偺拞偱梤擏徚旓偵傕彮偟怗傟傞偺偱偡偑丄從偒擏偑怘傋曽偲偟偰桳朷側傫偰偙偲偼堦尵傕彂偄偰偄側偄偺偱偡丅偝傜偵怴暦傪挷傋傑偡偑丄摉帪偺寧姦暘応擔帍傪尒偣偰傕傜偆偙偲傕峫偊偰偄傑偡丅曐懚偝傟偰偄傞偦偆偱偡偐傜丅
丂偦傟偐傜杒奀摴柹梤嫤夛偑徍榓俆係擭偵姧峴偟偨乽杒奀摴柹梤巎乿偑杒戝偲摴棫恾彂娰偵偁傝傑偡丅偦偺拞偵擔杮柹梤嫤夛庡嵜偱徍榓俀俋擭俉寧侾俆擔丄杮傪弌偡俀俆擭傕慜丄偄傑偺戨愳巗偑傑偩戨愳挰偩偭偨偙傠偺杒奀摴棫庬梤応偱奐偄偨乽庬梤応偺愄傪岅傞嵗択夛乿偑嵹偭偰偄傞傫偱偡丅岅傞恖偲偟偰偼擾椦徣杒奀摴擾嬈帋尡応偐傜嶳杮屷嶌丄彫椦惔屷丄岺摗棟嶰榊偺俁巵丄摴棫庬梤応偐傜柂揷岝懢榊丄拞懞孎媑丄嶳壓惔徏丄揷戙愮戙朳偺係巵丅暦偔恖偲偟偰擾椦徣杒奀摴擾帋抺嶻晹偺掁扟栆丄愮梩塸惛椉巵丄杒奀摴棫庬梤応偺媑揷柅丄崅捗掕梇丄嬤摗抦旻巵丄擔杮柹梤嫤夛偺搉夛棽憼巵傜偑弌偰偄傞偺偱偡偑丄僕儞僊僗僇儞偼俀僇強偟偐弌偰偒傑偣傫丅
丂侾偮偼丄榖偟巒傔偰傑傕側偔偺栄偺姞傝曽偺巚偄弌偵偮側偑傞偲偙傠偱偡丅偙偙偼戝帠側榖傪娷傫偱偄傞偺偱帒椏偵擖傟傑偟偨丅侾枃栚偺屻敿偑偦傟偱偡丅
帒椏偦偺俁
丂嶳杮乮屷乯丂偄傗偄傗崱偐傜尒傟偽梒抰側傕偺偱丄傎傫偲偺弶婜偵偼懱偺敿暘偯偮姞偭偨傕偺偱偡丅偦偺屻崱偺條偵僗僺乕僪傪偐偗偰娵姞傝傪傗傞條偵側偭偨偺偱偡丅
丂愮梩丂彫揷偝傫側傫偐摉帪姞傜傟偨偺偼奜崙幃偦偺傑乀偩偭偨丅偩傫偩傫曄偭偰棃偨偺偼丄憗偔姞傞偲偄偆偙偲偱偄傠偄傠峫偊弌偝傟偰棃偨傕偺側傫偱丄堦偮偺恑曕側傫偱偟傚偆丅
丂柂揷丂戝惓侾俀擭偵戧愳傊棃偨崰偵偼傕偆戝懱崱偺條側曽朄傪傗偭偰偄傑偟偨丅檼栄偺榖傪偡傞偲巚偄弌偡偺偱偡偑丄杒忦傊峴偭偨擭偵丄擖偭偰棃偨偽偐傝偺僔儏儘僢僾僔儍乕偺檼栄傪傗傜偝傟偨偑丄弸偄偺偵丄偼偠傔偰偩偐傜偆傑偔姞傟側偄丄幚媑応挿偼傗偐傑偟偔塢傢傟傞偟丄偦偺忋丄尒暔恖偼崟嶳偺傛偆偵偄傞偺偱丄慡偔恏偐偭偨偙偲傪乧乧丅
丂嶳杮乮屷乯丂偦傫側巚偄弌偱偼丄埥傞帪妢尨偝傫偐扤偐偑姞偭偨柹梤偑姞傝廔偭偰尒偨傜巰傫偱偄偨偙偲偑偁偭偨偱偡僫丅
丂愮梩丂偦偆塢偊偽戝惓俋擭偺俆寧偺檼栄偺帪偼丄挵擯揮偱悢摢巰傫偩偺傪壇偊偰偄傑偡丅柹梤偺昳庬偵傕傛偭偨偺偐傕抦傟側偄偑丄曐掕傕埆偐偭偨傠偆偟丄帪娫傕悘暘偐乀偭偨偐傜偱偟傚偆丅
丂媑揷丂檼栄慜偵帞晅傪偟偨傫偱偡偐丠
丂饫揷丂偦傟偼傗傝傑偣傫偱偟偨丅
丂愮梩丂偦偆偄偆晽偵巰傫偩応崌偺擏偺張棟偼丄摉帪傑偩僕儞僊僗僇儞椏棟偲偄偆傕偺偼側偔偰丄傒傫側僗僉從偵偟偰怘傋偨傕偺偱偡丅偦偟偰摉帪偺柹梤偼侾摢偱傕旕忢偵婱廳側傕偺偱丄崱擔偲偼慡慠姶偠偑堘偄傑偡僱丅
丂彫椦丂昦婥偵偱傕側偭偨傜戝曄偱丄屼斞偑僲僪傪捠傜側偔側偭偰偟傑偆丅乮徫惡乯
丂愮梩丂偦傟偵偼屷乆偵傕愑擟偑偁傞傫偱丄澦巰偟偨傜擾椦戝恇枠曬崘偟側偗傟偽偄偗側偄偲偄偆傛偆側偙偲偑偁偭偰乧乧丅
丂丂偄偄偱偡偐丅愮梩偝傫偑乽摉帪傑偩僕儞僊僗僇儞椏棟偲偄偆傕偺偑側偔偰丄傒傫側僗僉從偵偟偰怘傋偨傕偺偱偡乿偲徹尵偟偰偄傑偡丅僕儞僷妛幰偲偟偰乽摉帪乿偲偼偄偮偛傠傪巜偡偺偐丄偤傂抦傝偨偄偲偙傠偱偁傝丄巐曽敧曽挷傋偰偍傞傢偗偱偡丅
丂傕偆侾偮偼丄傕偆彮偟屻傠偺乽壗偐偲塢偆偲巒枛彂丂傛偔捛偭偨柤將僷僺乕偲働儕乕乿偲偄偆堦復偺拞偱丄傎傫偺嬐偐偱偡丅
帒椏偦偺係
丂搉夛丂偦傟偱偼偙傟偐傜偼暿偵榖戣偼愝偗傑偣傫偐傜丄壗側傝偲帺桼偵偍榖傪偟偰傕傜偆偙偲偵抳偟傑偡丅
丂媑揷丂僕儞僊僗僇儞椏棟偲偄偆偺偼丄壗帪崰偐傜傗傞條偵側偭偨傕傫偱偟傚偆偐丅
丂柂揷丂徍榓偺偼偠傔崰偐傜偱偼側偄偱偟傚偆偐丄偼偠傔偼孁偵偝偟偰傗偭偨偱偡僫丅
丂搉夛丂偦傟偼僨儞僈僋偱偟傚偆丅
丂愮梩丂堦僲悾偝傫偲偄偆恖偺巜摫偱戝暘晛媦偟偨傫偱偡偹丅
丂媑揷丂巺傪朼偖偙偲偼壗帪崰偐傜偱偡丅
| 丂丂 |
嶲峫暥專
帒椏偦偺俀偺弌揟偼柧帯侾係擭俆寧俉擔晅敓娰怴暦晬榐亖儅僀僋儘僼傿儖儉丄摨偦偺俁偼杒奀摴柹梤嫤夛曇乽杒奀摴柹梤巎乿侾俇侾儁乕僕丄徍榓俆係擭俀寧丄杒奀摴柹梤嫤夛亖尨杮丄帒椏偦偺係偼摨侾俇俋儁乕僕丄乮係乯偼杒擾夛曇乽杒擾乿戞俀俆姫侾崋俀俀儁乕僕丄乽杒奀摴偵偍偗傞擾嬈帋尡婡娭擭昞乿丄徍榓俁俁擭侾寧丄幮抍朄恖杒擾夛丄乮俆乯傕摨俀侽儁乕僕丄摨亖偄偢傟傕尨杮丄乮俇乯偼椏棟偺桭幮曇乽椏棟偺桭乿戞俁姫俀崋俆係儁乕僕丄戝惓係擭俀寧丄椏棟偺桭幮亖儅僀僋儘僼傿僢僔儏
|
丂帒椏偦偺俁偺慜偑杚梤將偺巚偄弌榖偱丄摴棫庬梤応挿偺媑揷偝傫偼僕儞僊僗僇儞偺偙偲傪暦偄偨偲偨傫偵丄戝媫偓偱巺朼偓偺榖傊偲桿摫偟偰偄傞丅堦尒俁恖偑岅偭偨傛偆偵尒偊傑偡偑丄岅傞傋偒懁偼枼揷偝傫偑敪尵偟偨偩偗偱偡丅搉夛偝傫傕愮梩偝傫傕暦偔恖偲偟偰嶲壛偟偨偺偱偁傝丄榖偡傋偒恖偑岅偭偰偄側偄偺偱偡偐傜丄僕儞僷妛偵偲偭偰偼偐側傝壙抣偑掅偄偲偄傢偞傞傪摼傑偣傫丅
丂愮梩偝傫偑敪尵偡傞側傜丄偄偭偦掁扟偝傫傕岅傞懁偵擖偭偰乭寧姦棳乭偵偮偄偰岅偭偰傎偟偐偭偨偲巚偄傑偡偹丅偟偐傕乽堦僲悾偝傫乿偲偼壗幰偐傢偐傝傑偣傫丅懡暘梤擏椏棟偺島巘偲偟偰壗搙傕棃摴偟偰偄傞搶嫗彈崅巘偺堦屗埳惃巕島巘偺偙偲偱偟傚偆丅敪尵幰偑惓妋偵巚偄弌偣側偐偭偨偐懍婰幰偑暦偒堘偭偨偐偟偨壜擻惈偑偁傝傑偡丅
丂偄傑巹偼乽杒奀摴柹梤巎乿偵偟偰偼僕儞僊僗僇儞偺夞屭偑彮側偄偙偲傪帵偟傑偟偨偑丄偦傟偼柍棟傕側偄偺偱偡丅偦傕偦傕偙偺嵗択夛偼丄摴撪偵偼戧愳偲寧姦偺屆偄娭學幰偑寬嵼偱偁傞偲抦偭偨娸嫤夛挿偑乽惀旕偦傟傜偺曽乆偺愄榖傪暦偒丄偄傠偄傠偺憐偄弌傪岅偮偰傕傜偮偰婰榐偟偰偍偒偨偄丄偦傟傜偑柹梤偑彨棃堦抜偲敪揥偡傞摜傒戜偵側傞(7)乿偲尵偄弌偟偨丅偦偙偱徍榓俀俋擭俉寧偵埉愳偱戞俈夞慡摴庬柹梤嫟恑夛偑奐偐傟偰娭學幰偑廤傑偭偨婡夛偵嵜偟偰丄梻寧偺擔杮柹梤嫤夛偺夛帍乽柹梤乿偵丄懍曬偺傛偆偵嵹偣偨傕偺偩偭偨偺偱偡丅
丂偦偺俀俆擭屻偵乽杒奀摴柹梤巎乿傪嶌傞偵摉偨傝丄偁偺嵗択夛偺敪尵幰偼戧愳偲寧姦偺屆偄恖偽偐傝俈恖偱丄偄傠偄傠幐攕傪孞傝曉偟偨嬯怱択偑庡偩偭偨偐傜柹梤巎偵傄偭偨傝丄偤傂廂傔偰偍偙偆偲偄偆偙偲偵側偭偨偺偱偟傚偆丅
丂巹偑偳偆偟偰乽柹梤乿偑掙杮偩偲抦偭偨偐丄偪傚偭偲扙慄偱偡偑丄暦偄偰壓偝偄丅梤擏偑側偔偰偼僕儞僊僗僇儞椏棟偼惉傝棫偨側偄丅偦傟偱巹偼尦寧姦庬梤応偙偲擾嬈丒怘昳嶻嬈媄弍憤崌尋媶婡峔偺杒奀摴擾嬈尋媶僙儞僞乕偱弶傔偰乽柹梤乿傪尒偣偰傕傜偄丄偙偺寧姧帍偼挷傋傞壙抣偑偁傞偲擣傔偨偺偱偡丅側傫偣愴慜丄愴屻偺憹怋丄帞堢偐傜徚旓偵帄傞尰応偵実傢偭偨恖乆偑偄傠偄傠彂偄偰偄傞丅僕儞僊僗僇儞傕弌偰偔傞偐傜丄弌棃傟偽慡晹栚傪捠偟偨偄丅倵倕倐們倎倲偱専嶕偡傞偲丄戝妛偱偼搰崻丄嶳宍丄擔杮丄搶嫗擾岺偺係戝妛偵偁傞偑丄杒擾尋偺寚偗偰偄傞崋傪帩偭偰偄偰丄搶嫗偐傜嬤偄偺偼嶳宍戝恾彂娰偱偟偨丅搶嫗乗嶳宍娫偼栭峴僶僗偱墲暅偟偨偐傜丄挷嵏偼侾擔偱傕幚幙俀攽俁擔偺椃偱偟偨偹丅
丂嶳宍戝偼侾侾俋崋傑偱偱丄偦偺屻偑側偄丅杒擾尋曐懚暘僾儔僗嶳宍戝偱傕俀侽侽崋傑偱偵偼丄偲偙傠偳偙傠寚偗傞丅側傫偲偐側傜側偄偐偲嵿抍朄恖擔杮抺嶻媄弍嫤夛偵栤偄崌傢偣丄偦偺寠偑慡晹杽傔傜傟傞偙偲傪抦傝丄搶嫗偼搾搰偵偁傞柹梤夛娰撪偺嫤夛帠柋嬊偵峴偭偰僐僺乕偝偣偰傕傜偄傑偟偨丅偙偺嫤夛偼擔杮柹梤嫤夛偺屻恎側傫偱偡偑丄摂戜壓埫偟丄婥偑晅偐側偐偭偨丅巹偼嫤夛偺乽僔乕僾僕儍僷儞乿傪島撉偟偰偍傞偑丄栤偄崌傢偣傞偙偲傕側偄偺偱丄僷僜僐儞偺乽偍婥偵擖傝乿偵擖傟偰偄側偐偭偨偺偱偡丅
丂偦偆偄偆宱堒偑偁偭偰丄巚偄偑偗側偄弌揟偑傢偐偭偨傢偗偹丅偍帥偝傫宯偺恾彂娰偵堄奜側杮偑偁偭偨傝偟傑偡偐傜丄杮傪扵偡偲偒偼愭擖娤傪幪偰丄偱偒傞尷傝帇栰傪峀偘偰摉偨傞傋偒側偺偱偡丅偦傟偱傕傑偩尒晅偐傜側偄偺偼丄椺偊偽愴慜偺僑儖僼嶨帍丅僑儖僼嶨帍梡偲彂偄偰偁傞惉媑巚涞偺峀崘尨峞偑巆偭偰偄傞偺偱丄壗帍偐尒晅偐傟偽丄偦偺偙傠僑儖僼傪傗偭偰偄偨僴僀僜僒僄僥傿乕偺偍媞傪屇傏偆偲偟偨偙偲偑徹柧偱偒傞丅
丂巹偵尷傝傑偣傫偑丄挷嵏擔悢傪偱偒傞偩偗墑偽偡偨傔偵丄僔儖僶乕妱堷偲偐柍椏偍偵偓傝偺挬怘晅偒偲偄偭偨埨偄儂僥儖傪巊偄傑偡丅搶嫗傑偱偼嬻偱傕丄偦偺屻偺堏摦偼傕偭傁傜栭偺崅懍僶僗偵偡傞丅旘峴婡丄俰俼傛傝埨偄偟丄儂僥儖戙偲巚偊偽廫暘堷偒崌偄傑偡丅偙傟傑偱偱嵟挿嫍棧偼攷懡搶嫗娫丅惉揷儂僲儖儖娫偺旘峴婡傛傝俆帪娫偼挿偔偐偐傞丅偡偭偐傝帺怣傪偮偗傑偟偨偹丅
丂栭峴僶僗偱偔偨傃傟偰梻擔丄杮偑撉傔側偄偺偱偼壗偵傕側傜側偄丅崀傝偨傜捈偖僶儕僶儕巇帠偵偐偐傟傞懱椡偑側偒傖偄偐傫偺偱偡丅偦偺偨傔偵偼暯慺偐傜偁偪偙偪抌偊傞丅僷僜僐儞偺儌僯僞乕偼栚偵傛偄偲偄偆偺偑巹偺帩榑偱偹丄偦偺徹嫆偵傑偩怴暦傪撉傓偺偵晄帺桼偟偰偄傑偣傫偧丅
丂巕嫙偺偙傠偺壧棷懡偵乽帺枬崅枬攏幁偺偆偪乿偲偄偆偺偑偁傝傑偟偨偐傜丄偦偺掱搙偵偟偰偍偒傑偡偑丄嵗択夛偺婰帠偵偼乽岅傞恖偺棯楌乮帺屓徯夘偵傛傞乯乿偑晅偄偰偄偰丄柂揷偝傫偲嶳杮屷嶌偝傫偼丄偙偺偲偒俇俆嵨偱偟偨丅柂揷偝傫偼戝惓俋擭偐傜侾俀擭傑偱暫屔導偵偁偭偨杒忦庬梤応偵柋傔丄杒忦攑巭偵傛傝乽戧愳偵堏傝偦偺擭偺屲寧枛偵昦婥傪偟偰擇働寧媥傫偱寧姦傊峴偒丄徍榓幍擭擇寧偵戧愳傊乿偲偁傝傑偡丅嶳杮偝傫偼柧帯係侽擭偐傜寧姦堦嬝(8)偲偁傝傑偡偑丄戝惓侾俁擭斉偺乽擾彜柋徣怑堳榐乿丄侾係擭斉偲侾俆擭斉乽擾椦徣怑堳榐乿偺俁嶜偵偲傕偵柤慜偼嵹偭偰偄傑偣傫丅懡暘宖嵹儔儞僋傛傝壓偩偭偨偣偄偱偟傚偆丅
丂暦偔懁偺愮梩偝傫偺柤慜偼戝惓侾俁擭斉偼戧愳丄侾係擭偐傜寧姦懁偵嵹偭偰偄傑偡丅戧愳偺婰榐偐傜徍榓俈擭偵戧愳偑摴挕偵堏娗偝傟偨偲偒丄嶳揷婌暯偝傫偲堦弿偵戧愳偵堏傝丄傑偨寧姦偵栠偭偨(9)偙偲偑傢偐傝傑偡丅戝惓侾俀擭斉偼応挿偲媄巘偩偗偱媄庤偼嵹偭偰側偄偟丄偦偆偄偆宱楌偐傜丄愮梩偝傫偺乽摉帪乿偼戧愳偲寧姦偺偳偭偪偺偄偮偛傠傪巜偡偺偐敾抐偱偒傑偣傫丅
丂偦傟偵偟偰傕丄俀侽儁乕僕傎偳偺嶨帍偵偱偡傛丄侾侽儁乕僕偵傕媦傇嵗択夛傪媗傔崬傫偩偲偙傠偵柍棟偑偁偭偨偺偱偡丅暵夛偵偁偨傝丄搒崌偱懍婰幰傪屇傋偢丄変乆悢恖偑乽晄姰慡側婰榐傪偲偮偰偄傞偩偗偱偡偐傜丄偳側偨偑壗傪塢傢傟偨偐丄堦尵敿嬪娫堘偄側偟偲偄偆栿偵偼嶲傝傑偣傫偗傟偳傕丄婱廳側彨棃偺帒椏偲偟偰傕偙偺婰榐傪巆偟偰偍偒偨偄(10)乿偲巌夛幰偑岅偭偰偄傑偡丅壗夞偐偺楢嵹偱丄偨偭傉傝嵹偣偰偔傟偨傜傕偭偲傛偐偭偨偺偱偡偑丄巇曽偑偁傝傑偣傫丅幚偵惿偟傑傟傑偡丅
丂柺敀偄偺偼師偺侾侽寧崋偵偱偡傛丄偙偺嵗択夛偱楌戙応挿偱堦斣偺婥擄偟壆偲偄傢傟偨徏壀拤堦偝傫偵乽庬梤応偺愄傪岅傞嵗択夛強姶乿傪彂偐偣偰偄傑偡丅徏壀偝傫偼澦巰傗攑梤偑懕弌偟偨帪戙傪夞屭偟丄偦偺棟桼偼乽柹梤帠嬈偺戝寁夋乿偼僩僢僾僟僂儞偩偭偨偙偲偵傛傞丅偮傑傝乽嫮偄孯敶姱椈撪妕偑丄崙榑庩偵擾嬈奅傕丄妛幰傕媄弍幰傕嫇偘偰旕擣偡傞偺傪丄柍棟偵忋偐傜壓偊偲墴偟愗偮偨偲塢偆楌巎揑側帠幚偑丄嵟傕婎杮揑側尨場偲側偮偰偄傞偲巚偆丅偟偐偟崱偐傜巚偆偲丄孯敶姱椈傕埆偄柺偽偐傝偱偼側偔丄柹梤偺崱擔偁傞偺傕偙偺楌巎偺帓暔偱偁傞偲偄偆偙偲偑偱偒傞偺偱偁傞丅乿偲偄偭偰偄傑偡丅傑偨丄寁夋払惉偺媫偓夁偓傕巜揈(11)偟偰偄傑偡丅偱傕丄偍堿偱僕儞僊僗僇儞偑惗傑傟丄彅孨偼僕儞僷偑偱偒傞偟丄巹偼僕儞僷妛偺尋媶偑偱偒傞丅偲傕偵偛嬯楯側偡偭偨愭恖偨偪偑偄偨偙偲傪朰傟偪傖偄偐傫偺偱偡丅
丂偊乕偲丄偙偺乽杒奀摴柹梤巎乿偵偼偱偡偹乽杒奀摴柹梤巎擭戙昞乿偑晅偄偰偄傑偡丅婰帠偲戧愳庬梤応丄擾椦徣庬抺杚応寧姦庬梤応偲俁偮偵嬫暘偟偰偁傝丄侾擭暘偢偮婲偙偭偨偙偲傪彂偄偰偄傑偡丅寧姦庬梤応偺暘傪尒偰偄偒傑偡偲丄戝惓侾俀擭偵偼惂搙夵妚偱戧愳庬梤応寧姦暘応偲柤慜偑曄傢傝丄挿嶈徛偲偄偆恖偑暘応挿偵側偭偰偄傑偡丅偦偟偰偱偡傛丄偦偺壓偵乽梤擏棙梡偺偨傔儘僗僩儖惢僕儞僊僗僇儞撶峫埬乿(12)偲偁傞傫偱偡丅偝偒傎偳偺乽杒擾乿偺擭昞偲摨暥偱偡偟丄俀俁俈儁乕僕偐傜偺乽梤擏椏棟偍傛傃壛岺媄弍偺晛媦乿偲偄偆復偵偱傕丄宍側偳傪偞偭偲偱傕愢柧偟偰偄傟偽椙偐偭偨偺偱偡偑丄偦傟傕尒摉偨傝傑偣傫丅
丂偪傚偭偲擭戙偑栠傝傑偡偑丄擭戙昞偺戝惓俉擭偺寧姦庬梤応偺崁偵偼乽抺嶻帋尡応梡抧撪偵寧姦庬梤応暪抲丄柺愊俈係侾俆挰曕丄柹梤偺帞堢娗棟丄夵椙斏怋堢惉巜摫丄惗嶻暔偺挷惍壛岺丄帞椏峩嶌傪峴偆丅寧姦庬梤応偺娗妽偼杒奀摴挕娗撪丄戧愳庬梤応偼晎導丄柹梤媄弍楙廗惗婯掕偵傛傝侾俋柤嵦梡丄揃杮徆擇応挿偲側傝巟応挿寭柋乿(13)偲偁傝傑偡丅摉帪摴撪偺柹梤偼侾侽侽侽摢懌傜偢偱偟偨偑丄摴挕偺旜嶈桬師榊撪柋晹挿偼乽柹梤偼丄懘偺悢嬨昐梋摢偵夁偓偞傟偳傕丄嬤帪擾彜柋徣偺彠椼偵敽傂丄帞堢婓朷幰挊偟偔憹壛偟丄擵偵墳偢傞偺摢悢晄懌側傞偺惙嫷傪掓偟嫃傟傝丅庩偵懘偺拁怋偼栜榑丄檼栄検偵墬偰悳傞壚椙側傞惉愌傪嫇偘偮乀偁傞傪埲偰丄擾壠偺暃嬈偲偟偰丄堦斒慉朷偺揑偲側傝嫃傟傝乿(14)偲嫻傪挘偭偰曬崘偟偰偄傑偡丅
丂堦曽乽抺嶻偲抺嶻岺寍乿偺戝惓侾俁擭俁寧崋偵乽帠柋幒傛傝乿偲偄偆僞僀僩儖偱擾彜柋徣抺嶻嬊挿偺嶰塝幚惗偝傫偑柹梤帺媼嶔傪庢傝忋偘丄偦偺拞偵乽戝惓敧擭寧姦庬梤応偱擇昐摢偺梤偺旂傪攳偓丄懘偺擏偼懲旍偺拞偵撍崬傫偩帠偑偁傞丅懄偪擏偺廀梫偑尒晅偐傜柍偮偨堊傔偱偁傞丅慠傞偵崱擔偵墬偰偼丄杒奀摴偼梤擏偺堷挘扂傪偡傞惃偱偁傞丅搶嫗偵墬偰傕妱朆偺愭惗偑梤擏傪攧偮偰偄傞揦傪憑偟夢偮偰丄慟偔尒晅偗弌偡巒枛偱偁傞乿(15)偲彂偄偰偄傑偡丅戝検張暘偐傜俆擭偨偪丄悽偺拞曄傢偭偨偐傜柧傞傒偵弌偟偨偲偄偆偙偲側偺偱偟傚偆偐丅墷廈戝愴偺塭嬁偱梤栄妋曐偱戝憶偓傪偟丄慜偺擭偵柹梤侾侽侽枩摢寁夋傪棫偰偨偽偐傝側偺偵丄庬椶偼傢偐傝傑偣傫偑丄摴撪偺俆暘偺侾傕偺梤傪偨偩偨偩柍懯偵幪偰偨巎幚偼丄擭戙昞偵婰嵹偡傞壙抣偑廫暘偵偁傞偲巹偼巚偆偺偱偡偑丄擭昞曇廤幰偼偙偆偟偨宱堒傪抦傜側偐偭偨偺偐丄抦偭偰偄偨偗傟偳柍帇偟偨偺偐丄媈栤偑巆傝傑偡丅偙偺堦帠偐傜傕丄撶峫埬偺婰嵹偑夦偟傑傟傞傢偗偱偡傛丅
丂偲暥嬪傪偄偆偩偗側傜娙扨丄巹偼怴暦傪挷傋偰傒傑偟偨偹丅偦偆偟偨傜丄傗偼傝寧姦偱憡摉梤偑巰傫偩偲偄偆塡偼戙媍巑偺帹偵傕擖偭偰偄偨偺偱偡丅戝惓俉擭俀寧俀俉擔偺杒奀僞僀儉僗偺乽梤栄惌嶔丂乧媈栤偺澦巰乧乿偲偄偆尒弌偟偱摉帪偺崙夛偱偺幙媈偑嵹偭偰偄偨偺偱偡丅偦傟傪撉傒傑偡偲乽暦偔強偵嫆傞偲杒奀摴偵墬偰悢廫摢杮擭偺姦偝偱澦傟偨擾彜柋徣偼擵傪旈偟偰嫃傞偲塢傆帠偱偁傞晇嫋偱側偔擇廫屲僇擭堦昐枩摢傪怋偟偰峴偔偲塢傆帠偑幚嵺擛壗側傜偆偐丄枖梤偵梫偡傞杚憪傪嵧攟偡傞偲搚抧偼僪僐偵媮傓傞偺偐夁嫀侾働擭娫偺宱夁偲彨棃偺尒崬擛壗乿偲丅戙媍巑偺柤慜偼偁傝傑偣傫偑丄埾堳夛偱幙栤偑弌偨偺偱偟傚偆丅偦傟偱乽媍夛偵婲偮偨偙偺幙媈偼摴壠擾柋嬊挿偑曋媂擾憡偵戙偮偰愢柧傪梌偊偨乿偲偄偆偙偲偱丄擾彜柋徣摉嬊偺摎曎偑彂偄偰偁傞偺偱偡偑丄梫偡傞偵柧帯帪戙偺幐攕偺尨場偼傢偐偭偨偺偱丄偦偺懳嶔傪偪傖傫偲棫偰偰俀俆僇擭寁夋傪棫偰偨偲愢柧偟偨偆偊偱乽嶐擭偺寧姦偺帞堢偺忬懺側偳偼寛偟偰旈偡傞帠側偟惉掱丄嶐擭柹梤偺澦巰偟偨偺偼戝暘悢偼懡偄偑懘懡偄偺偼戝惓屲擭偵崐廎偐傜擖傟偨擇昐摢偺梤乗擇昐摢擖傟傞偲偄傆擛偒梋傝
仦宱尡偺柍偄丂堊帪婜偺戰傃曽傪尋媶偟愭偯岦傆偱帞傆偨傕偺埥偼泂傔傞傕偺傪擖傞偑媂偐傞傋偟偲懄偪庬晅傪岦傆偱偟偨幰傪桝憲偟偨傞偵桝憲拞慏偺拞偱梋掱壊懄偪恊偑庛傝戝暘巰嶻傪惗傑偟偨晇傟偑妴傕嶐擭暘曍偡傞帪婜偵側傝偰堦偺尨場傪堊偟彯枖嶐擭婥岓偺晄弴側傝偟偨傔偵杚憪庩偵崻嵷椶偺弌棃埆偔梊婜偺廂妌傪摼偢枖杒奀摴偼堦嶐擭埲棃擾嶻暔偑岲宨婥傪掓偟恖晇偑懌傜偢捓嬧偼崅偔庤夢傝寭偨偲偄傆傛偆側帠傕偁傞晇惀偵偰嶐擭偼戝暘偵澦巰偑懡偐偮偨偺偩偑乿(16)偲偹丅婰帠偺拞偺乽壊懄偪恊偑庛傝乿偼柲偺岆怉偲巚偄傑偡偑丄嶰塝偝傫偺慜擟幰偱偁傞摴壠偝傫偑廰乆乽暦偔強乿偺懡悢澦巰傪擣傔偰偄傑偡丅巰傫偩偐嶦偟偨偐偼暿偲偟偰傕俀侽侽摢巰朣偼擭昞偵擖傟傞傋偒帠審偩偲巚偄傑偣傫偐丄奆偝傫偼丅
丂偪傚偭偲榖偑枮廎傊旘傃傑偡偑丄嶌壠偺峀捗榓榊偺帺揱偲偄傢傟傞乽擭寧偺偁偟偍偲乿偺拞偵乽柹梤昐摢傪杘嶦偡傞乿偲偄偆堦復偑偁傝傑偡丅峀捗偑庤傪壓偟偨懱尡択偐偲巚偭偨傜丄偦偆偱偼側偔偰愴慜偵枮廎偺奐戱懞傪朘栤偟偨傜乽枮廎惌晎偑崚暔傪嫙弌偝偣側偑傜丄柹梤偺帞椏傪攝媼偟偰偔傟側偄偺偱丄嶰昐摢偺拞昐摢傪杘嶦偟側偗傟偽側傜側偐偭偨榖乿傪懞挿偐傜姱椈斸敾偺堦椺偲偟偰暦偐偝傟偨丅偦傟傪嶨帍偺乽夵憿乿偵彂偄偨傜丄杒奀摴偐傜擾嬶偑撏偐側偄偲偆嬯忣偺晹暘偲堦弿偵偡偭偐傝嶍彍偝傟偰暥復偑傔偪傖偔偪傖偵側傝乽彂偔偲偄偆偙偲偼杴偦堄枴偺側偄偙偲偵側偭偰偟傑偆偺偱偁傞丅偦偺暥復偑懢暯梞愴憟慜偵巹偑嶨帍偵彂偄偨嵟屻偺暥復偵側偭偰偟傑偭偨丅乿(17)偲偄偆偙偲偱偟偨丅峴惌偵懳偟偰堦愗暥嬪傪偄傢偣側偄偲偄偆尵榑摑惂偺徹尵側傫偱偡丅愴屻敿悽婭傪夁偓偨崱丄偳偆傕傑偨偦偺曽岦偵栠傝偮偮偁傞傛偆側婥偑偟傑偡丅奆偝傫傕梤傒偨偄偵丄偨偩偍偲側偟偄偩偗偱偼偄偐傫偺偱偡傛丅
| 丂丂 |
嶲峫暥專
忋婰乮俈乯偺弌揟偼擔杮柹梤嫤夛曇乽柹梤乿俉侽崋俈儁乕僕丄徍榓俀俋擭俋寧丄擔杮柹梤嫤夛亖尨杮丄乮俉乯偼摨俉儁乕僕丄摨丄乮俋乯偼撪妕報嶞嬊曇乽怑堳榐乿戝惓侾俁擭係俆侾儁乕僕丄戝惓侾俁擭侾侽寧丄撪妕報嶞嬊亖嬤僨僕杮丄摨戝惓侾係擭俁俈俋儁乕僕丄戝惓侾係擭俋寧丄摨媦傃戧愳抺嶻帋尡応屲廫擭巎曇廤埾堳夛曇乽戧愳抺嶻帋尡応屲廫擭巎乿俀俁係儁乕僕丄徍榓俆俇擭俈寧丄杒奀摴棫戧愳抺嶻帋尡応亖尨杮丄乮侾侽乯偼擔杮柹梤嫤夛曇乽柹梤乿俉侽崋侾俇儁乕僕丄徍榓俀俋擭俋寧丄擔杮柹梤嫤夛亖尨杮丄乮侾侾乯偼摨俉侾崋俉儁乕僕丄徍榓俀俋擭侾侽寧丄摨丄乮侾俀乯偲乮侾俁乯偼杒奀摴柹梤嫤夛曇乽杒奀摴柹梤巎乿俀俆俀儁乕僕丄徍榓俆係擭俀寧丄杒奀摴柹梤嫤夛亖尨杮丄乮侾係乯偼杒奀摴抺嶻嫤夛曇乽抺嶻嶨帍乿戞侾俉姫侾崋俀俆儁乕僕丄旜嶈桬師榊乽戝惓敧擭偺杮摴抺嶻嬈悥惃乿丄戝惓俋擭侾寧丄杒奀摴抺嶻嫤夛亖尨杮丄乮侾俆乯偼拞墰抺嶻夛曇乽抺嶻偲抺嶻岺寍乿戞侾侽姫俁崋係傌乕僕丄戝惓侾俁擭俁寧丄拞墰抺嶻夛亖尨杮丄乮侾俇乯偼戝惓俉擭俀寧俀俉擔晅杒奀僞僀儉僗俀柺丄杒奀僞僀儉僗幮亖儅僀僋儘僼傿儖儉丄乮侾俈乯偼峀捗榓榊挊乽擭寧偺偁偟偍偲丂壓乿俋俇儁乕僕丄暯惉係擭俆寧丄島択幮亖尨杮
|
丂偦偆偦偆丄奆偝傫偺拞偵偼杮廈弌恎幰偑偄傞偩傠偆偟丄摴嶻巕偱傕僗僩乕僽偱愇扽傪暟偄偨宱尡偼側偄偐傕抦傟側偄丅傕偟偐偡傞偲丄愇扽偲偄偆崟偄峼暔傪尒偨偙偲偑側偄偐傕抦傟傑偣傫側丅偲側傟偽摉慠丄儘僗僩儖偲側傫偧傗偱偟傚偆偐傜丄偨傑偨傑尒偮偗偨柧帯係侽擭戙偺彫妛俇擭惗偺棟壢偺杮傪尒偣傑偟傚偆丅挊嶌尃曐岇婜娫偑廔傢偭偨偄偄恾夝偩偐傜巊偆偺偱偁傝傑偟偰偹丄奆偝傫傪彫妛惗埖偄偟偰偄傞傢偗偱偼偁傝傑偣傫偐傜岆夝偺側偄傛偆偵丅偼偄丄僗儔僀僪偺嵍懁偺恾傪尒偰壓偝偄丅
丂偙偺杮偱偼乽僗僩乕僽偼拻揝偵偰憿傝偨傞墌摏忬偺偺傕偺偵偰丄擵傪悩偊晬偔傞鋓偲丄墝傪壆奜偵敳偔傋偒墝撍偲傪嬶傊丄慜懁偵偼擱椏傪擖傞乀岥傪桳偟丄懘壓晹偵偼嬻婥偺擖傞傋偒壓岥偁傝偰丄墌摏偺撪晹擇岥偺拞娫偵揝惢偺僒僫偁傝丅帶偟偰墌摏偺忋晹偵偼捠忢悈傪擖傟偨傞敨傪旛傆乿(18)偲愢柧偟偰偄傑偡丅偙偺恾偺僀偑忋偺岥丄儘偑壓偺岥丄偦偺拞娫偺僯偑僒僫丄偮傑傝儘僗僩儖側傫偱偡丅傢偐傝傑偡偹丅
丂丂丂丂丂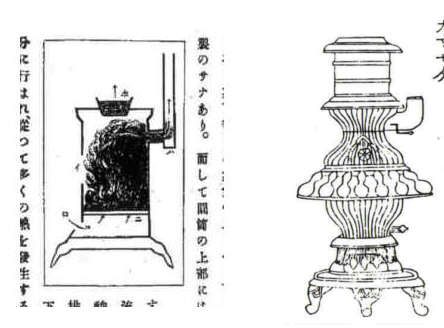
丂偙偺僒僫偲偄偆扨岅偼丄巹偼抦傝傑偣傫偱偟偨偹丅峀帿墤傪堷偒傑偟偨傜乽堫傗敒偺曚傪懪偪棊偲偡偵梡偄傞擾嬶丅妱抾傪墶偵暲傋偨彴檣乮偟傚偆偓乯偵帡偨傕偺乿偲偁傝傑偟偨丅巚偆偵戝偒側孂傪墶偵抲偄偨傛偆側傕偺傜偟偄偲巚偄傑偟偨丅傕偭偲傢偐傝傗偡偄愢柧偼側偄偐偲傎偐偺崙岅帿揟傪挷傋傑偟偨偑丄嵹偭偰偄側偄丅偮傑傝峀帿墤傕戞係斉偳傑傝偱戞俆斉偱偼徚偊偨屆偄梡岅偩偭偨傫偱偡偹丅偙偆偟柧帯偑墦偔側偭偰偄偔傫偩側偲幚姶偟傑偟偨丅
丂偦偺柧帯偺僥僉僗僩傪懕偗傑偟傚偆丅乽崱擱椏傪僒僫偺忋偵抲偒丄擵偵揰壩偡傞偲偒偼丄嬻婥偼壓岥傛傝墌摏撪偵棳捠偟偰惙偵擱從偟丄傛傝偰惗偤傞扽巁姠巣偼忋晹偺墝撍傪捠偠偰壆奜偵攔弌偣傜傟丄奃酁偼僒僫偺娫寗傛傝懘壓晹偵棊偮傞傪埲偰丄擱從偺嶌梡偼廩暘偵峴偼傟丄廬偮偰懡偔偺擬傪敪惗偡傞偙偲傪摼乿(19)傞偲丅傢偐傝傑偡偹丅
丂杒戝惗嫤偺僕儞僷僙僢僩偼幍椫傪戄偟偰偔傟傑偡傛偹丅偁偺幍椫偺拞偵寠偺奐偄偨慺從偒偺墌斦偑擖偭偰偄傞偱偟傚偆丅壩嶮偲偐栚嶮偲屇偽傟偰偄傑偡偑丄偁傟傕儘僗僩儖偺拠娫偲偄偊傑偡丅栘扽傪傛偔擱傗傞偨傔偵偼嬻婥偲愙怗偡傞柺愊傪憹傗偡昁梫偑偁傝傑偡丅偦傟偱壩嶮偺傛偆側巟帩嵽偺忋偵扽傪抲偒丄掙偺曽偐傜偁偺寠傪捠偟偰嬻婥偲愙怗偱偒傞傛偆偵偡傞傢偗偱偡丅僕儞僷僙僢僩偵偼抍愵傕晅偄偰偄傞傫偱偟偨偭偗丅抍愵偱愵偖偲捠婥岥偐傜傛傝懡偔偺嬻婥傪憲傝崬傑傟偰壩偑嫮偔側傝傑偡偹丅栘扽傗恉偺応崌偼埻楩棤偲偐偁傫偐傪尒傟偽傢偐傞傛偆偵丄暯傜側偲偙傠偱傕擱傗偡偙偲偑弌棃傑偡偑丄愇扽偼偦偆偼偄偒傑偣傫丅奿巕忬偺儘僗僩儖偺側偄愇扽僗僩乕僽偼側偄偲偄偭偰傕偄偄偱偟傚偆丅
丂僗僩乕僽偱愇扽傪暟偔偲丄偳傫偳傫擱偊偰奃偵側傝傑偡偐傜丄擱偊曽傪尒偰偼愇扽傪偮偓懌偨偡丅寢峔柺搢偔偝偄偺偱晛捠偼挋扽幃偲偄偭偰丄擱從幒偺忋偵搩偺傛偆側宍偺挋扽幒偑偁傝丄偦偙傊愇扽傪梊傔擖傟偰偍偔偺偱偡丅搩偺掙偵偁傞愇扽偑擱偊偰奃偵側傞丅搩偺拞偺愇扽偺廳傒傪巟偊偒傟側偔側傞偲丄掙偺愇扽偑擱從幒偵棊偪偰擱偊丄奃偼嵱偗偰儘僗僩儖偺栚傪捠傝丄奃偩傔偵棊偪傞丅偙偺僒僀僋儖傪孞傝曉偟偰丄偐側傝偺帪娫傎偭偨傜偐偟偰傕擱偊懕偗傑偡丅偱傕偦偺偆偪偵丄愇扽偺奃偑儘僗僩儖偺栚偺娫偵媗傑偭偰壩椡偑棊偪偨傝偟傑偡偐傜丄偦偺偲偒偼僨儗僢僉偲偄偆奲宆偺揝朹偱丄壩傪偐偒夞偡朹偱偡側丅僨儗僢僉偱儘僗僩儖偺栚偺娫傪偮偮偄偰奃傪棊偲偟偰丄嬻婥偺捠傝摴傪偮偗偰傗傞偺偱偡丅
丂戝掞儘僗僩儖偺慜抂偵撍婲偑偁傝丄偦偙偵寠偑奐偄偰偄傞偺偱丄僨儗僢僉傪偦偺寠偵堷偭妡偗偰丄慜屻偵梙偡傞偲儘僗僩儖慡懱偑慜屻偵摦偄偰丄栚媗傑傝偵側偭偰偄偨奃偑棊偪傑偡丅偮傟偰挋扽晹偐傜傑偩擱偊偰偄側偄愇扽偑壩偺忋偵棊偪偰丄擱從傪帩懕偝偣傞傢偗偩丅杒戝儓僢僩晹偱偼暯惉侾侾擭傑偱愇扽僗僩乕僽偑巊傢傟丄傒傫側惓偟偄暟偒曽傪曌嫮偝偣傜傟偰傑偟偨傛丅
丂偦傟偐傜僗儔僀僪偺塃懁丄偙傟偼柧帯俆擭偺嫗搒怴暦偵嵹偭偰偄偨崙嶻僇乕僿儖偺斈崘側傫偱偡丅斈崘偲偼丄偄傑偺峀崘丄僇乕僿儖偲偼僗僩乕僽丅乽僇乕僿儖僲媊僴姦儝杊僊抔儝庢儖僲婍僯僔僥懘梡壩敨壩酀摍僯彑儖僐僩枩乆僫儖僴悽僯柧僫儖強僯僔僥屌儓儕挐乆砷`愩儝懸僞僘枻僯嫀恏枹僲擭拻憿夛幮僿屼壓栤傾儕幮梻擔栭岺晇儝嬅僔庬乆曋媂儝峫僿恾柺僲捠儕拻憿僔屼屬奜崙恖儗僀儅儞巵僲堦棗儝儌宱敪攧彑庤僯旐嬄晅僞儕奧僔懘宍僞儖儎惣梞帄曋僲婍儝敎曧僔拻憿僴歚僯榓晽僲岺晇儝恠僗僲儈僫儔僘塱梡僲堊僲崙嶻僲琦儝梡僼儖僲屘僯榓梞廤惉僲婍僩儌堗僣儀僔乿(20)丅乽僗僩乕僽攷暔娰乿偲偄偆杮偵丄柧帯俋擭偺搶嫗擔擔怴暦偵崙嶻僗僩乕僽戞侾崋敪攧偲偄偆婰帠偑偁傞(21)偲彂偄偰偄傑偡偑丄偙傟偼彮側偔偲傕偦傟傛傝偼係擭屆偄椺偱偡丅傕偭偲傕崙嶻偲偄偆堄枴偱偼敓娰偱偼傕偆埨惌擭娫偵嶌偭偰傑偡偐傜丄慡慠彑晧偵側傝傑偣傫丅偦偆偄偆娭學偱敓娰偵偁傞敔娰崅揷壆壝暫塹帒椏娰偱偼侾侾寧俀俆擔傪僗僩乕僽偺擔丄擱偊傞壩偱側偄寧擔偺擔偺曽偱偡傛丄僗僩乕僽偺擔偲寛傔偰丄枅擭壩擖傟幃傪嵜偟偰偄傑偡丅扙慄偮偄偱偵偄偊偽丄傗偼傝柧帯俆擭偵垽抦偱懴壩惈偺偄偄搚偑尒偮偐偭偨偺偱悾屗暔偺僇乕僿儖傪嶌傞偺偵乽悳儖壚僫儕僩乿(22)偲偄偆婰帠傕偁傝傑偟偨丅側偵偟傠嫗搒偺僇乕僿儖偼俀俋墌傕偟偨偺偱丄摡婍側傜埨偔偱偒傞偲帋嶌偟偨偺偐側丅傕偟偐偡傞偲丄儘僗僩儖傕悾屗暔偩偭偨偐傕抦傟傑偣傫丅
丂偨偩丄偙偺斈崘偺奊偼儘僗僩儖傪偼偭偒傝帵偟偰偄傞偺偑庢傝暱偱偡丅恾偺塃偺壓偺曽偵偪傚偭偲撍偒弌偨撍婲偑偁傝傑偡偹丅巹偼偁傟偑偦偺偙傠偺僒僫丄儘僗僩儖偵偮側偑傞撍婲晹偩偲尒傑偡丅偁傟傪僨儗僢僉偲屇傇揝惢偺奲朹偱慜屻偵梙偡傇傞偙偲偵傛偭偰丄儘僗僩儖偺栚偵媗傑偭偨奃傪棊偲偡巇妡偗偵側偭偰偄傞偼偢偱偡丅
| 丂丂 |
嶲峫暥專
忋婰乮侾俉乯偲乮侾俋乯偼偄偢傟傕偼岝晽娰曇乽彫妛棟壢島媊恞忢彫妛戞俇妛擭乿俇俀儁乕僕丄柧帯係侾擭俋寧丄岝晽娰亖嬤僨僕丄乮俀侽乯偼杒崻朙曇乽擔杮弶婜怴暦慡廤乿係侾姫俀俁俈儁乕僕丄柧帯俆擭俉寧晅嫗搒怴暦俁俉崋丄暯惉俆擭係寧丄傌傝偐傫幮亖尨杮丄乮侾俉乯偼摨俁侽俇儁乕僕丄摨摨丄柧帯俆擭俋寧晅垽抦怴暦俀係崋丄摨摨丄乮俀侾乯偼怴曚塰憼挊乽僗僩乕僽攷暔娰乿俈俆儁乕僕丄徍榓俇侾擭侾俀寧丄杒奀摴戝妛恾彂姧峴夛亖尨杮丄乮俀俀乯偼仏仏仏仏
|
丂戝晹壆梡偺僗僩乕僽側偳偼戝偒偄偺偱丄愇扽偺擱從幒偑戝偒偔丄廬偭偰儘僗僩儖傕戝偒偄丅傑偨宍傕昁偢偟傕悈暯偱側偔偰丄撌偲偄偆帤偺忋敿暘傒偨偄側妴岲偩偭偨傝偟傑偡偺偱丄偦偆偄偆偺傪巊偊偽摨帪偵擏曅傪偄偔偮傕從偗傞偱偟傚偆丅巹偼儘僗僩儖偱從偄偨宱尡偼側偄偺偱偡偑丄嬥栐傛傝偼揝斅偵嬤偄從偗曽偵側傞偲巚偄傑偡偹丅
丂偦偆偦偆丄尋媶拠娫偺庒偄恖偐傜暦偄偨榖偱偼丄壛嶳梇嶰偺庒戝彨側傫偲偐偲偄偆塮夋偱丄晹幒偺嬤偔偺儅儞儂乕儖偺奧傪巊偭偰從偒擏傪傗傞僔乕儞偑偁傞偲偐丅晹堳偨偪偼尒偨偙偲偑偁傞傛偆側撶偩側偲偄偄側偑傜怘傋偪傖偆偦偆偩偑丄偁傟側傜帀傪棊偲偡寗娫偑側偔側偭偨偄傑偺僕儞僊僗僇儞撶偲摨偠峔憿偩偟丄岤偄偐傜偆傑偔從偗傞偐傕抦傟傑偣傫偑丄幍椫偑偮傇傟側偄偐偹偊丅帋偡婥偵傕側傝傑偣傫側偁丄偼偭偼偭偼丅
丂偙偺杒奀摴柹梤巎偺擭戙昞偺彂偄偰偁傞捠傝側傜丄寧姦庬梤応偺恖偨偪偼丄戝惓侾俀擭偵彮側偔偲傕梤擏傪從偔偨傔偵儘僗僩儖偺傛偆偵寗娫偺奐偄偨揝斅傪嶌偭偨偩偗偱側偔丄偦傟傪僕儞僊僗僇儞撶偲屇傇偙偲傕峫偊弌偟偨偲偄偆偙偲偵側傝傑偡丅傕偟嬵堜摽嶰偝傫偑枮揝偺戅幮捈慜偵挷嵏晹挿偵側偭偰偄偰丄偦偺偲偒偵崅梤擏傪僕儞僊僗僇儞撶偲柦柤偟偨偡傟偽偱偡傛丄偁偔傑偱壖掕偺榖偱偡傛丅柦柤偐傜傢偢偐俁擭屻偵丄寧姦偵偼僕儞僊僗僇儞撶偲偄偆柤慜偲椏棟朄偑揱傢偭偰偄偰丄偦傟偱乽儘僗僩儖惢僕儞僊僗僇儞撶乿傪乽峫埬乿偟偨偙偲偵側傝傑偡丅傕偆傂偲偮丄嬵堜偝傫偑枮揝偵擖幮偟偨搑抂偵丄僕儞僊僗僇儞撶偲柦柤偟偨偲偡傟偽侾係擭屻偱偡偐傜丄柤慜偲從偒曽偼揱傢偭偰偒偦偆側婥偼偟傑偡丅偟偐偟丄偙偺応崌側傜枮廎偠傖偙傫側撶傪巊偭偰偄傞偲撶傕揱傢偭偰偄偰傕偍偐偟偔側偄偲巚偆偺偱偡偑偹丅
丂懡暘偙偺擭昞偺偄傢傫偲偡傞偲偙傠偼丄揝撶偦偺傕偺偱側偔偰丄儘僗僩儖偱從偔梤擏偺怘傋曽傪巜偟偰丄偄傑偱偄偆僕儞僊僗僇儞撶偲偄偆堄枴偲庴偗庢傟偽丄偦傟側傜偁傝偦偆偩偲偼巚偄傑偡偑丄偳偆偟偰寧姦庬梤応柤暔偲偄傢傟傞偖傜偄峀傑傜側偐偭偨偺偱偟傚偆偐丅巹偺挷傋偱偼戝惓侾俀擭偺杒奀僞僀儉僗偵偼梤擏椏棟偺婰帠偼尒晅偐傝傑偣傫偱偟偨丅偝傜偵侾俀擭慜屻丄偦傟偐傜彫扢怴暦側偳偵寧姦庬梤応娭學偺婰帠偑偁傞偐偳偆偐崱屻挷傋偰傒傞偮傕傝偱偡偑丄婰帠傪憑偟弌偟偰儗億乕僩偵偟偰尒傛偆偲偄偆恖偼偄傑偣傫偐偹丅摉帪偺怴暦偼儁乕僕悢偑憹偊偰俉儁乕僕寶偰偐側丄儅僀僋儘僼傿儖儉偼俁寧偱侾姫偵側偭偰偄傑偡偐傜丄撉傒峛斻偑偁傝傑偡傛丅偼偭偼偭偼丅
丂掁扟偝傫偺杮偼丄偙偺柹梤巎偺杮傛傝侾俋擭傕慜偵弌偰偄傑偡偐傜丄柹梤巎擭戙昞偺乽儘僗僩儖惢僕儞僊僗僇儞撶峫埬乿偺崻嫆偼丄掁扟偝傫偺堦尵乽戝惓侾俀擭崰乿愢偟偐側偄偺偱偼側偄偐偲媈傢傟偰傕巇曽偑側偄偺偱偼偁傝傑偣傫偐偹丅屻偺島媊偱弌偰偒傑偡偑丄戝惓侾俀擭傑偱偵偼嬥栐偱從偔乽梤擏偺栐從偒乿偲偄偆椏棟朄偑岞偵側偭偰偄傑偟偨丅偦傟側傜丄嬥栐傛傝偙偭偪偼拻暔偱忎晇偩偟丄杒奀摴傜偟偄偩傠偆偲丄恎嬤側愇扽僗僩乕僽偺儘僗僩儖偱從偒巒傔偨偲偄偆偙偲偱偟傚偆偐偹偊丅
丂孞傝曉偟偵側傝傑偡偑丄掁扟偝傫偑彂偄偨傛偆偵丄杒嫗偺崅梤撶傪乽擔杮偺壠掚偵乿帩偪崬傕偆偲乽嬯怱偟偨乿偺偼杮摉偱偟傚偆偹丅側偤偦偆峫偊傞偐偲偄偆偲偱偡偹丄杒奀摴戝妛怴暦偺弅嶞斉傪挷傋偨偐傜偱偡丅僕儞僷妛偺島媊傪巒傔傞偵摉偨偭偰丄搶杒掗戝擾壢戝妛丄懄偪杒奀摴掗崙戝妛偼撿枮廎揝摴姅幃夛幮丄棯偟偰枮揝偵懡偔偺懖嬈惗傪憲傝崬傫偱偄傑偡偐傜丄戝妛怴暦偺巻柺偱偼嫵庼傗偦傟傜俷俛嬝偐傜偺敪尵丄尨峞偱僕儞僊僗僇儞偲偄偆扨岅偑弌偰偔傞壜擻惈偑偁傝傑偡丅偦傟偱偄偮弌偰偔傞偐傪挷傋偰傒偨傫偱偡傛丅
丂杒奀摴戝妛怴暦偼戝惓侾俆擭憂姧偱丄憂婎俆侽廃擭傪婰擮偟偰杒奀摴掗崙戝妛怴暦偲偄偆柤慜偱惗傑傟傑偟偨丅係嶜侾慻偵側偭偨偦偺弅嶞斉偑杒戝恾彂娰偵偁傝傑偡偑丄巹傕帩偭偰偄傑偡丅偄傑偺杒奀摴戝妛怴暦偼丄杒戝偺愭惗曽傪偼偠傔暥壔恖偲偐抦幆恖偲偄傢傟傞傛偆側曽乆偵尨峞傪埶棅偟偰彂偄偰傕傕傜偆偙偲傪堦愗偟偰偄傑偣傫偑丄偦偺愄偺戝妛怴暦偼偳傫偳傫傗偭偰偄傑偟偨丅嶌壠側傫偐偵傕彂偐偣偰偄傑偡丅偦傟偵掗崙戝妛偺愭惗偼丄悽娫偺僒儔儕乕儅儞傛傝寧媼偑崅偐偭偨偟丄戝妛惗傕僄儕乕僩偲偄偆偙偲偱丄戝妛怴暦偺峀崘傪尒傞偲丄晛捠偺怴暦偲偁傑傝曄傢傝傑偣傫丅娽嬀丄彂愋丄梞暈丄孋側偳偑弌偰偄傑偡丅愭惗偼僜僼僩丄妛惗偼妏朮偲妛惗暈丄傗偼傝峀崘傪弌偟偰偄傑偡丅
丂偄偮偩偭偨偐丄暥妛晹摨憢夛庡嵜偺懖嬈廽夑夛偵侾恖偩偗妏朮傪旐傝丄妛惗暈傪拝偰偒偨懖嬈惗偑偄偨丅尒偨傜偦偺妏朮偼偲偑偭偨妏偺憗堫揷宆側偺偱丄崙棫戝妛偺偼傕偭偲妏偑娵偄傫偩偲嫵偊偰偁偘偨偑丄儗儞僞儖偱偼偙傟偟偐側偐偭偨偲偄偭偰傑偟偨偹丅偦傝傖傑偢偄偭偰傫偱丄係寧偺廽捗偱揮暍偟偨偲偒偺儓僢僩晹偺憡朹偲俀恖偱丄屆偄妏朮傪杒戝暥彂娰偵婑晬偟傑偟偨傛丅偩偐傜暥彂娰偵偼俀屄偁偭偰丄拞墰恾彂娰儘價乕偺揥帵撪梕偵傛偭偰丄巹偺傛傝鉟楉側斵偺妏朮傪忺傜傟傞偙偲偑偁偭偨偐傜丄尒偰偍偔傛偆偵偹丅
丂扙慄偼傗傔偰丄掗崙戝妛怴暦偺屆偄曽偐傜尒偰偄偒傑偡偲丄杒戝偺偦偽偱丄偦傟傑偱巟撨偦偽偲偄偆屇偽傟偰偄偨査椏棟偺侾偮傪儔乕儊儞偲屇傇傛偆偵偟偨尦慶偲偄傢傟傞抾壠偑丄徍榓俀擭俆寧偺侾侾崋偵弶傔偰峀崘傪弌偟偰偄傑偡丅岼娫偄傢傟傞傛偆偵抾壠怘摪偱偼偁傝傑偣傫丅僐僺乕偼乽悽奅堦偺偍偄偟偄椏棟偼巟撨椏棟偱偡丅媺橉丄導恖橉懘偺懠偺屼橉崌偵偼惀旕巟撨椏棟乿偱愗傟偰乽抾壠丂戝妛槵壢慜乛揹榖擇幍乑幍乿偲摨堦宱塩偲巚傢傟傞乽朏棖丂撿巐惣巐乛揹榖嶰嶰乑屲乿偲偄偆俀峴傪憓傫偱乽傪屼棙梡壓偝偄丅擔巟恊慞偼愭偢怘暔偺棟夝偐傜偲怣偠傑偡乿(23)偱偟偨丅偦偺屻抾壠偼偢乕偭偲偙偺僐僺乕傪弌偟懕偗傞偺偱偡丅屄恖揑偵偼丄巹偑侾擭栚偺偲偒庰傪攦偄偵峴偐偝傟偨惓栧岦偐偄偺戲揷彜揦丄偄傑偼僙僽儞僀儗僽儞傪宱偰從偒擏揦偵側偭偰偄傞揦偑丄偦偺偙傠偼彫娫暔傗暥朳嬶傪埖偭偰偄偨偺偱偡偹丅扷撨傜偟偄恖偑曄側尵梩偱掁傝慘傪悢偊偨偺偱丄暦偄偨傜儘僔儎岅偩偲偄偆丅栧慜偺彫憁廗傢偸宱傪撉傓偲偄偆偑丄惓栧慜偼庰壆傕堘偆偲嵃徚傑偟偨偹丅
丂偦傟偐傜摿偵拲栚偟偨偺偼徍榓俁擭侾寧偺俀侽崋偺孲巌擏揦偺峀崘偱偡丅偄偆側傟偽戄偟撶晅偒彌從偒僙僢僩偁傝傑偡乗偱偁傝丄杒戝惗嫤偑屩傞僕儞僷僙僢僩偺慶愭偺峀崘偲偄偊傞偐傜偱偡丅偙傟偼偹丄愴屻偺偙偲偩偑丄擏壆偝傫偑梤擏傪攦偭偨偍媞偵僕儞僊僗僇儞撶傪戄偟偨帪戙偑偁偭偨偐傜丄偦偆偄偆尒抧偐傜傕慜椺偲偟偰廳梫側偺偱丄帒椏偦偺俆偵偟偰尒偰傕傜偆偙偲偵偟傑偟偨丅偄偄偱偡偐丄撉傒偼乽戄偟戜丄撶柍椏偱偟傑偡乿偱偼側偔偰乽戄偟戜撶丄柍椏偱偟傑偡乿偲撉傓丅戜撶偲偄偆屆偄尵偄曽偩偐傜丄偡偖巚偄晜偐傇暯偨偔偰暘岤偄彌從偒撶偱偼側偔偰丄愺傔偺揝撶偱偟傚偆丅偙偺戜撶偺掕媊偵偮偄偰偼儁儞僨傿儞僌偵偟偰丄偄偢傟幁傗嶘偺戜撶偺榖偑弌偰偔傞嶥杫夞屭択偺島媊偱庢傝忋偘傑偡丅
丂僓僋僓僋偲揔摉側挿偝偵愗偭偨擪偺僓僋偼偄偄偲偟偰丄嵍懁偺嶳撠偲偄偆擏偑傢偐傝傑偣傫側偁丅専嶕偡傞偲壂撽偱僀僲僽僞傪巜偡偲偄偆儁乕僕偑弌偰偒傑偡偑丄杒奀摴偵偼挅偼偄側偄偟丄侾寧偩偐傜孎偼怮偰偄傞偟偹丄壠撠偱偼側偄偲偡傟偽搤柊偟側偄壼埼幁偱偟傚偆偐丅
帒椏偦偺俆
丂丂丂丂丂丂丂丂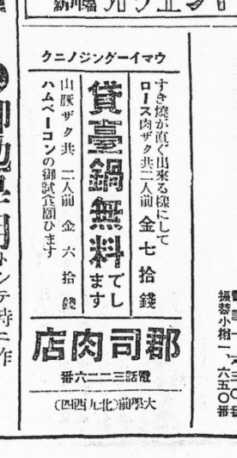
丂徍榓俁擭俀寧偺俀侾崋偵偼丄敄栰偺壀揷壆杮揦偑巟撨椏棟偺壠掚弌挘挷棟奐巒偲偄偆戝偒側峀崘傪弌偟偰偄傑偡丅侾恖慜俁昳偐傜俆昳丄侾墌偐傜俆墌偱乽屲恖慜埲忋偵偼巟撨恖徲媊郷傪弌挘偣偟傔傑偡乿偲偄偆愢柧偵丄僜僼僩傪偐傇傝丄拞崙暈傪拝偨徲偝傫偺幨恀(24)傪揧偊偰偄傑偡丅嶥杫偱傕偙偺偙傠偐傜巟撨椏棟偺働乕僞儕儞僌偑巒傑偭偨偺偱偡偹丅
丂偙偺崋俀柺偵乽枮娯強乆偺乛嫶杮嵍屲榊巵乛柤梍嫵庼偲側傞乿偲偄偆僀儞僞價儏乕婰帠偑嵹偭偰傑偡丅 儣獊創瘞亗獟啈簮鰩亗茓蓳瘓陦簭h偵偁偮偰屻擭偺搶嫗戞堦崅摍妛峑醕帪偺槵旛栧偵嵼妛偣傞崰偺堩榖偼桳柤偱偁傞丄壞栚燍愇巵偲憡実傊偰枮廎椃峴偺嵺偺堩榖摍偼燍愇巵偺枮娯強乆偵傛偮偰桳柤偱偁傞丅堦擔嫶杮巵傪偦偺帺揁偵栤傊偼嬘慠偲偟偰嫻傪扏偄偰嵍偺擛偔岅偮偨丅乿偲慜抲偒偟偰嫶杮偝傫偺択榖傪彂偄偰偄傑偡丅乽梊旛栧偱拞懞孨乮惀岞乯偑婋偔媦戞偟巹偑棊戞偟偨傫偱嶥杫擾妛峑偵棳傟崬傫偩傫偱偡偦偺崰偺嶥杫擾妛峑偼挌搙夁搉婜偰奜恖嫵巘傕杦傫偳傤側偔側傝慟偔朚恖偑嫵庼偺怑偵廇偒弌偟偨崰偱偡偐傜悘暘怓傫側柺敀偄崰傕偁傝傑偟偨偑嶥杫擾妛峑傪弌偰偐傜娫傕側偔撈堩偵棷妛傪柦偤傜傟傑偟偨偑偦傟偑泬偵柺敀偄傫偱偡傛丅壗偟傠偦偺崰偺棷妛惗偼崱偺條偵暥晹徣偺偄傆帠傪暦偐側偄偱壗擭偱傕傤偨傕傫偱偡丅搶戝偺屆嵼孨側傫偐傕偦偺摴偱偼鐱乆偨傞傕傫偱偟偨偑杔傕嶰擭偺棷妛婜尷偑愗傟偰偐傜擇擭埲忋傕嫃偨傫偱偡嬥偝傊偁傟偽嫃怱抧偑偄偄傫偱乧乧乮偙偙偱欒乆戝徫乯暪偟婣偮偰偐傜嵅摗憤挿偵幎傜傟傑偟偨丅偦偺帪偵嵅摗孨偵栺懇偟傑偟偨偑枹偩偵壥偟傑偣傫偑乮撈徫乯乧乧丅傕堦搙棷妛偝偣偰屶傟偨傜崱搙偼柦椷捠傝偵婣傞偲尵偮偨傕傫偱偡偑乧乧僴僴僴丅(25)乿偲偹丅乽枮娯偲偙傠乛乢丣乿傪峫嶡偡傞偲偒偵徻偟偔傗傝傑偡偑丄俀妛婜偑巒傑偭偰偄傞偺偵偱偡傛丄棷妛偠傖側偄傫偩偐傜偁偺栺懇偼庣傜側偔偰傕偄偄傫偩偲偄偆棟孅偱丄嫶杮偝傫偼桰乆偲燍愇偲偺椃峴傪妝偟傫偩偲嶡偣傜傟傑偡丅
丂摨擭侾侽寧偺俁俀崋偵抾壠偼晹壆傪峀偔偟偰椏棟傕堦憌嬦枴偡傞偲夵抸棊惉斺業偺峀崘傪嵹偣偰偄傑偡偑丄偦傟偵傕埶慠偲偟偰乽巟撨椏棟乿偲偟偐彂偄偰偄傑偣傫丅(26)偙偺偙傠偺怘摪偺峀崘傪傒傞偲丄撠撶俀侽慘丄媿撶俁侽慘偑憡応偩偭偨傛偆偱偡丅
丂偝傜偵尒偰偄偒傑偡偲丄摨擭侾侾寧偺俁係崋偱偼撿俁惣俁偺塱妝尙偑巟撨椏棟晹傪奐愝偟偨偺偱乽弌慜恦懍偵屼墐夛弌挘椏棟巇弌偟偼摿偵曌嫮巇岓乿(27)偲峀崘偟偰偄傑偡丅梻擭偺徍榓係擭偵偼戝捠惣俆偺惛梴尙偲偄偆揦偑乽惣梞椏棟偲巟撨椏棟乿(28)偲偄偆峀崘傪弌偟偰偄傑偡丅戝惓俈擭壞偵嶥杫偱奐偐傟偨奐摴俆侽擭婰擮杒奀摴攷棗夛偺愜傝乽撈摿偺摴嶻梤擏椏棟乿偲偄偆怴暦峀崘傪弌偟偨惛梴掄偲柤慜偑帡偰偄傞偺偱丄婥偵側傝傑偡傛偹丅偱傕惛梴掄偼攷棗夛偺夛婜拞偵偼俀夞杒奀僞僀儉僗偵峀崘傪弌偟偰偄傞(29)偲偄偆偖傜偄偟偐挷傋偰側偄傫偩偑偹丅埬奜媑揷攷偝傫偲埄夛偑嶥杫偱偼墶峧偺師丄俀斣栚偺僕儞僊僗僇儞揦偲嫇偘偰偄傞惛梴尙偵偮側偑傞偺偐傕抦傟傫丅徍榓俀俀擭偐傜僕僊僗僇儞傪攧傝暔偵偟偰偄偨惛梴尙偼晉婱摪棤丄偄傑偺僷儖僐偺棤庤偵偁偭偨偲彂偄偰偄傑偡丅
丂偙偺峀崘偱偼戝捠惣俆偱応強偑堘偄傑偡偑丄戞俀師悽奅戝愴偺偲偒丄敋寕偝傟偰壩嵭偵側偭偨応崌丄墑從傪嵟彫尷偵怘偄巭傔傞偨傔丄嶥杫偱傕斏壺奨偱偼寶暔偺嫮惂慳奐丄偮傑傝寶暔傪庢傝夡偟偰娫妘傪嬻偗傞偙偲偑峴傢傟偨偲偄偆榖偑偁傝傑偡偐傜丄偦偆偟偨偙偲偱堏揮偝偣傜傟偰丄愴屻偵僷儖僐棤偱嵞奐偟偨偙偲偑峫偊傜傟傑偡丅偑丄巹偼傑偩偦偙傑偱偼挷傋偰偍傝傑偣傫偐傜丄榓梞拞偳傟偐偱戝惓俈擭偛傠偐傜梤擏椏棟傪採嫙偟懕偗偨壜擻惈傪巜揈偡傞偩偗偵偲偳傔傑偡丅
| 丂丂 |
嶲峫暥專
忋婰乮俀俁乯偺弌揟偼杒奀摴戝妛曇乽杒奀摴戝妛怴暦暅崗斉侾乿係俇儁乕僕丄暯惉尦擭係寧丄戝嬻幮亖尨杮丄尨巻偼徍榓俀擭俆寧侾俉擔晅杒奀摴掗崙戝妛怴暦侾侾崋係柺丄
帒椏偦偺俆偼摨俉俀儁乕僕丄摨丄尨巻偼徍榓俀擭侾寧俋擔晅摨俀侽崋係柺丄
乮俀係乯偼摨俉俇儁乕僕丄摨丄尨巻偼摨擭俀寧俇擔晅摨俀侾崋係柺丄
乮俀俆乯偼摨俉係儁乕僕丄摨丄尨巻偼摨崋俀柺丄
乮俀俇乯偼摨侾俁侽儁乕僕丄摨丄尨巻偼徍榓俁擭侾侽寧侾擔晅摨俁俀崋係柺丄
乮俀俈乯偼摨侾俁俉儁乕僕丄摨丄尨巻偼摨擭侾侾寧俆擔晅摨俁係崋係柺丄
乮俀俉乯偼摨侾俁俋儁乕僕丄摨丄尨巻偼摨擭侾侾寧侾俋擔晅摨俁俆崋侾柺丄
乮俀俋乯偼戝惓俈擭俉寧侾係擔晅杒奀僞僀儉僗挬姧係柺偲摨侾俆擔晅摨亖儅僀僋儘僼傿儖儉
|
丂偲傕偁傟乽儔乕儊儞乿偑弶傔偰杒奀摴掗崙戝妛怴暦偺巻柺偵尰傟偨偺偼徍榓俆擭俋寧偺俈俈崋(30)偱偟偨丅慜偺擭偺俇寧丄係俁崋偵扠彫楬偺昐棷壆偑壥幚怘摪偵僼儖乕僣丒僷乕儔乕偲怳傝壖柤晅偒偱丄俇寧侾擔偐傜奐愝偲愰揱偟偰偄傑偡丅(31)偦偺壥幚怘摪偵壛偊偰乽堦斒椏棟敪昞乿偲偁傝丄怘摪傕暪愝偟偨傫偱偡偹丅偦偺拞偺巟撨偦偽偲偄偆暘椶偺拞偵乽儔乕儊儞乿偲乽僠儎僔儐儊儞乿偲俀昳偺柤偑偁傝傑偡丅昐棷壆偺峀崘偼丄偦偺屻偪傚偄偪傚偄嵹傞偺偱偡偑丄俀夞栚偺儔乕儊儞偲偄偆扨岅偑擖偭偨偺偼徍榓俇擭係寧(32)偱偟偨丅
丂徍榓俆擭侾侽寧偵偼乽杒嫗幃巟撨椏棟奐巒乿偲嫞攏応捠揹掆慜偺徏搰壆媔拑揦(33)偑搊応偡傞偺偱偡偑丄抾壠偼埶慠偲偟偰儔乕儊儞偲偐巟撨偦偽偲偄偆尵梩偼巊傢偢丄偍壴尒婣傝偵巟撨椏棟傪偲偐丄搤偩偐傜巟撨椏棟傪偲偄偆峀崘偽偐傝偱偡丅偆偪偼傟偭偒偲偟偨巟撨椏棟揦偱偁傝丄偄傠偄傠偁傞査椶偺拞偺侾昳偑儔乕儊儞偲屇傇椏棟偵夁偓側偄偲丄屩傝崅偐偭偨偺偱偟傚偆丅梻俇擭俇寧偺俈俈崋偵偼抾壠扨撈偺峀崘偲扠彫楬偵戞擇朏棖偲偄偆巟揦傪奐偄偨偲摨帪偵俀審偺峀崘傪弌偟偰偄傑偟偨丅(34)
丂壀揷揘偝傫偺乽儔乕儊儞偺抋惗乿偵嵹偭偰偄傞乽儔乕儊儞擭昞乿偼乽徍榓俆擭崰乣丂嶥杫偺媔拑揦偱丄儔乕儊儞偑棳峴偡傞乿(35)偲彂偄偰偁傝傑偡偑丄徍榓俈擭枛傑偱偺掗崙戝妛怴暦宖嵹偺抾壠偺峀崘偵偼儔乕儊儞偄偆扨岅偼側偔丄抾壠敪徦愢偑夦偟傑傟傞傛偆側愰揱怳傝側傫偱偡傛丅
丂徍榓俈擭俇寧偺俋係崋偵撿侾惣俋偺儈僇儈丄扠彫楬俇偺儈僴僩偲偄偆摨堦宱塩傜偟偄俀尙偺儗僗僩儔儞偺峀崘偼乽巟撨椏棟偼杮奿揑側愝旛傪抳偟傑偟偨丅墐橉媦傃僋儔僗橉偵惀旕屼棙梡壓偝偄乿(36)偲偄偭偰偄傑偡丅
丂偁偁丄朰傟傞偲偙傠偱偟偨丅巹偑挷傋偨尷傝偱偼丄徍榓俀擭偵偼僆儕僄儞僩偲偄偆揦偑僂僒僊椏棟(37)偺峀崘傪弌偟偰偄傑偡偑丄梤擏偱偼側偄丅弶傔偰梤擏偑弌偰偒偨偺偼徍榓係擭侾侽寧偵弌偨係俉崋偺乽僂僆僩僇丄僕儍僘欫帰昽両乿偲偄偆戣偱俵俽惗偲偄偆恖偑彂偄偨枮廎僴儖僺儞偺尒暦婰偺拞偵偁傝傑偟偨丅價乕儖傪堸傒側偑傜乽寱偵撍偒偝偟偰梤擏傪從偔僇僼僈僗椏棟傪怘傋傞偺傕偆傟偟偄帠偩乿(38)偲偁傝傑偡丅埲慜偵傕怘傋偨偙偲偑偁傞傛偆側昞尰側傫偱偡偹丅偙偺僇僼僈僗偲偄偆偺偼僐乕僇僒僗偺偙偲偩偲丄暿偺杮傪傒偰傢偐傝傑偟偨丅
| 丂丂 |
嶲峫暥專
忋婰乮俁侽乯偺弌揟偼杒奀摴戝妛曇乽杒奀摴戝妛怴暦暅崗斉侾乿俀俆俁儁乕僕丄暯惉尦擭係寧丄戝嬻幮亖尨杮丄尨巻偼徍榓俆擭俋寧侾擔晅杒奀摴掗崙戝妛怴暦俇俁崋俁柺丄
乮俁侾乯偼摨侾俈俁儁乕僕丄尨巻偼摨係擭俇寧侾俈擔晅摨係俁崋俁柺丄
乮俁俀乯偼摨俀俋俀儁乕僕丄摨丄尨巻偼摨俇擭係寧俇擔晅摨俈俁崋俀柺丄
乮俁俁乯偼摨俀俇俀儁乕僕丄摨丄尨巻偼摨俆擭侾侽寧俇擔晅摨俇俆崋係柺丄
乮俁係乯偼摨俁侾侽儁乕僕偵抾壠扨撈暘丄俁侾侾傌乕僕偵椉尙暘丄尨巻偼摨擭俇寧侾侾擔晅摨俈俈崋俀柺偲俁柺丄
乮俁俆乯偼壀揷揘挊乽儔乕儊儞偺抋惗乿俀俁係儁乕僕丄暯惉侾係擭侾寧丄拀杸彂朳亖尨杮乮俁俇乯偼摨俁俉侾儁乕僕丄摨丄尨巻偼摨俈擭俇寧俈擔晅摨俋係崋侾柺丄
乮俁俈乯偼摨俈俉儁乕僕丄摨丄尨巻偼摨俀擭侾俀寧仏擔晅杒奀摴掗崙戝妛怴暦侾俋崋係柺丄
乮俁俉乯偼摨侾俋係儁乕僕丄摨丄尨巻偼摨係擭侾侽寧俈擔晅摨係俉崋係柺丄
|
丂偙偙偱丄偪傚偭偲曽岦傪曄偊偰傒傑偟傚偆丅係偮偵傕側偭偨僕儞僊僗僇儞椏棟偺儖乕僣偵偮偄偰丄杒嫗偵廧傫偩偙偲偺偁傞恖偺婰榐偐傜扵偭偰傒傞偙偲偵偟傑偡丅巹偼杒戝恾彂娰偺奐壦偺杮傪尒偰偄偰丄墱栰怣懢榊偝傫傪尒偮偗傑偟偨丅宑墳偺拞崙暥妛偺愭惗偩偭偨恖偱徍榓侾侾擭偐傜俀擭敿丄棷妛偟偰偄傞傫偱偡丅墱栰偝傫偼徍榓侾俆擭偵乽悘昅杒嫗乿傪弌偟丄暯惉俀擭偵搶梞暥屔偑暅崗偟偰偄傑偡丅偦傟偺拞偺乽墠嫗怘晥乿偵丄棦尒偲巙夑捈嵠偑僕儞僊僗僇儞傪怘傋偵偄偭偨惓梲極偑弌偱偄傞傫偱偡偹丅攝偭偨帒椏偦偺俇乮侾乯偑偦傟偱偡丅慡暥偱偼偁傝傑偣傫丅
丂嵶偐偄偙偲偱偡偑丄偙傟偼搶梞暥屔偺堷梡側偺偱丄揦柤偵偼怳傝壖柤偑偁傝傑偣傫偑丄暉晲彂揦偐傜弌偨乽墱栰怣懢榊悘憐慡廤乿偺乽墠嫗怘晥乿偱偼乽偟傛偆傛偆傠偆乿偲儖價偑晅偄偰偄傑偡丅壗偐崻嫆偑偁偭偨偺偐丅偦偆彂偐傟傞偲僙僀儓僂儘僂偑惓偟偄偲抐尵偟偰傛偄偺偐帺怣偑側偔側傝傑偡偹偊丅
丂墱栰偝傫偼徍榓侾俋擭偵乽悘昅杒嫗乿偵憹曗夵掶傪巤偟偨乽杒嫗璧婰乿傪弌偟偰偄傑偡丅惓梲極偼徍榓侾俈擭偵暵揦偟偨偺偱乽墠嫗杒嫗乿傕壗偐昅偑擖偭偨偐偲挷傋傑偟偨偑丄堷梡売強偼慡偔摨偠偩偭偨丅
丂乽彉乿偱乽偙偺彂偺撪梕傪撉墈偝傟傞彅孨巕偼丄偮偹偵徍榓廫堦丒廫擇丒廫嶰擭醕帪偺杒巟帠忣傪擼棤偵昤偐傟偮偮堦撉偣傜傟傞偙偲傪朷傫偱傗傑側偄丅(32)乿偲偁傞偺偼丄尰忬偲堘偆偙偲偼彸抦偟偰偄傞偗傟偳乽傢偨偔偟屄恖偵偲偮偰偼偄偼偽丄醕帪偺婰擮挔(33)乿偩偐傜奜偣側偄偲偄偆偍抐傝側傫偱偡偹丅
丂偦傟偐傜乽惔恀夞乆乿偲偄偆偺偼僀僗儔儉嫵傪怣偠傞夞懓偺椏棟偲偄偆偙偲偩偦偆偱偡丅傑偨丄擔戝偺愭惗偩偭偨屻摗挬懢榊偝傫偑偹丄墱栰偝傫偲摨偠傛偆偵搤偺栭丄惓梲極偱僕儞僊僗僇儞傪怘傋傞忣宨傪彂偄偰偄傞偺偱帒椏偦偺俇乮俀乯偵偟傑偟偨丅師偁偨傝偺島媊偱柧傜偐偵偡傞偙偲側傫偩偗偳丄偙偺屻偵乽擔杮偱偼丄榓揷嶰憿夋攲偑偙偺梤擏撶傪採嫙偟偰丄姍憅桼堜働郷偺亀郷偺傗亁偱嵜偟偨偺偑偙偺惉媑巣娋椏棟偺娭搶偵墬偗傞殔栴偲側偮偨偺偱偁傞丅(34)乿偲懕偔偺偱偡傛丅傆偭傆偭傆丅
丂偦傟偐傜徍榓侾俀擭偐傜俀擭娫杒嫗偵偄偨朄妛幰偺戧愳惌師榊偝傫傕乽戝偒側梤擏壆乿偲偟偰彂偄偰傑偡偐傜乮俁乯偲偟傑偟偨丅
帒椏偦偺俇
丂乮侾乯
丂杒嫗偼屆偄搒偱偁傞丅偟偨偑偮偰偆傑偄傕偺傗偺悢傕傑偨恟偩懡偄丅側偐偱傕搤偺妝偟傒偺堦偮偲偟偰偼丄壗偼偝偰偍偒梤偺擏傪嫇偘側偔偰偼側傞傑偄偑丄梤偺擏偲塢傊偽慜栧奜偺惓梲極偼梋傝偵傕桳柤偱偁傞丅埫偄揦偵攪擖傞偲丄傑偯懡惃偺抝偑姷傟偨庤偮偒偱崗傫偱傤傞梤擏偺旤偟偄慛峠怓偑娽偵煄傒傞丅姦偄惎嬻偺傕偲丄拞掚偺楩傪埻傫偱曅懌傪檣偵嵹偣偰偍偺偑偠偟梤傪從偄偰怘傋傞烤梤擏偼崑夣側庯偦偺傕偺偲偄傊傛偆丅偳偆偐偡傞偲偪傜偪傜愥偑傆傝偼偠傔偨斢側偳丄奜搮偺嬢傪棫偰偰塓傑偒忋傞鄚偲恀峠側墛偵懳偡傞偲偒丄挿偄敘傪偲偮偰擏曅傪從偔変恎偑屆偄悽偺杺弍巘偺擛偔偝傊巚偼傟偰偔傞丅烤梤擏偵懳偟偰栰嵷撶偺側偐偵梤擏傪擖傟偰幭傞偺傪 梤擏偲徧偡傞丅偙傟偼幭偡偓偰偼傛偔側偄丅傎偲傫偳愻傆掱搙偱堷偒忋偘丄悢庬椶偺栻枴傪帺暘偱岲傒偵挷崌偟偨傕偺傪偮偗偰怘傋傞丅梤偺擏偵偼晄巚媍偵徯嫽庰傛傝傕敀姡帣偺曽偑傛偔崌傆丅亙棯亜 梤擏偲徧偡傞丅偙傟偼幭偡偓偰偼傛偔側偄丅傎偲傫偳愻傆掱搙偱堷偒忋偘丄悢庬椶偺栻枴傪帺暘偱岲傒偵挷崌偟偨傕偺傪偮偗偰怘傋傞丅梤偺擏偵偼晄巚媍偵徯嫽庰傛傝傕敀姡帣偺曽偑傛偔崌傆丅亙棯亜
丂惓梲極偺傎偐丄搶埨巗応偺搶萊弴丄惣扨偺惣萊弴丄嫟偵梤擏娰偲偟偰偦偺柤傪抦傜傟偰偼傤傞偑丄惓梲極偺傗偆側屆傔偐偟偄庯偵偼朢偟偄丅惣萊弴偼寑応怴乆媃堾偺偡偖朤側偺偱丄偳偆偐偡傞偲寑拞丄塏乮摴壔栶乯偑壗偐偺偒偮偐偗偵丄偡偖偙傟偐傜惣萊弴傊峴偮偰堦攖傗傜偆側偳塢偮偰娤媞傪徫偼偣傞偙偲偑偁傞丅偨偟偐傢偨偔偟偑偙傟傪暦偄偨偺偼塏偲偟偰堦棳偺攏晉榎偱偁偮偨傗偆偵婰壇偡傞丅斵帺恎夞嫵搆偱偁偭偰丄撠傪怘傋側偄偙偲偑崯応崌偺徫択偵棙偄偰傤傞偺偱偁傞丅奧偟杴偦梤擏娰偵墬偰偼庡恖偼傕偲傛傝彫憁偺枛乆偵帄傞傑偱幓偔強堗乽惔恀夞乆乿埲奜偺傕偺偼柍偄偺偱偁傞丅
丂惓梲極丄搶萊弴丄惣萊弴偼梤擏傪寵偼側偄恖偱偁傞尷傝擔杮恖偺娫偱傕愭偯抦傜側偄傕偺偼柍偄敜偱偁傞丅偙傟偑烤梤擏偱側偔偰烤媿擏偲側傞偲偪傛偮偲抦傜側偄恖偺曽偑懡偄偐傕抦傟偸丅愰晲栧撪楬搶偺塈鑹偟偰傤傞偲峴偒夁偓偰偟傑傂偝偆側彫偝側揦丄偩偑堦搙揦愭傊攪擖傞偲弴斣偑棃傞傑偱偐側傝懸偨側偗傟偽側傜側偄傎偳懡惃偺恖偱偄偮傕枮堳偱偁偭偰丄帺暘偱僞儗傪偮偗側偑傜媿擏傪從偄偰從栞偺娫偵漰傫偱怘傋傞弴彉偼烤梤擏偲摨偠偙偲偱偁傞丅梤擏偵朞偒偨偲偒丄偦偟偰暊堦攖偵媿擏傪怘傋偨偄偲偒丄偙偺烤媿擏偵傑偝傞傕偺偼側偄丅偙傟傕搤偺娫偺怘傋傕偺偱丄偄偮傕姦偄晽偑悂偒偼偠傔弌偡偲偁偺埫嶼偺忋庤側旍偮偨恊栮偺婄偲嫟偵丄揝楩偺忋偱徟偘偮偔忀桘偲擏偺鄚偲偑娽慜偵郺乆偲棫偪偙傔傞巚傂偑偡傞丅
丂傑偨杒嫗忣庯偺堦宨偱偁傞丅
乻墱栰怣懢榊乼
乮俀乯
丂亙棯亜杒暯偺搤偼丄慜栧奜偺惉媑巣娋椏棟偲偁偮偰丄椺偺桳柤側惓梲極傊偲弌妡偗傞丅愥偑偪傜偮偔姦晽檢楏偺栭丄栰揤偵暟偒壩偱丄梤擏傪偮偗從偒偡傞庯偒偼丄偦偺嵍偺曅媟傪忋偘偰敘偱偮乀偔嬺傋曽偲崌偣偰丄擛壗偵傕杒巟撨偺搤偺庰惾傪報徾怺偔崗傒偮偗傞丅
乻屻摗挬懢榊乼
乮俁乯
亙棯亜梤擏偼曄側廘偄偑偡傞偺偱丄寵偄側恖偑懡偄偑丄巹偼偦偺廘偄偑婥偵側傜側偄偺偱丄梤偺擏傕杒嫗偱戝偄偵怘偭偨丅梤偺擏偺枴偼丄偦偺擏曅偺愗傝曽偵傛偭偰嵍塃偝傟傞丅杒嫗偺椏掄偵偼丄梤偺擏傪敄偔愗傞摿庩媄検傪帩偭偰偄傞偩偗偱丄崅偄媼椏傪庴偗偰偄傞僐僢僋偑偄偨丅杒嫗偺媿奨偵偼丄戝偒側惔怲帥乮夞嫵帥堾乯偑偁偭偰丄僩儖僐宯偺夞嫵搆偑憡摉懡悢廧傫偱偄傞偑丄偦傟傜夞嫵幰偼楯摥幰偲偄偊偳傕丄愨懳偵撠傪怘傢側偄丅屘偵斵摍偼乽夞乆乿偲彂偄偨屗奜偺壆戙揦偱怘帠傪偟偰偄偨丅偦偙偱偼愨懳偵撠偺帀偡傜巊傢側偄偐傜偱偁傞丅巹偼慜栧奜偵偁傞戝偒側梤擏壆傊傛偔怘偄偵峴偭偨丅搶嫗偱僕儞僊僗娋椏棟偲偄偭偰偄傞傕偺偼丄仭仭偦偺壠偺擏偺從偒曽傪恀帡偟偨傕偺偺傛偆偵巚傢傟偰側傜側偄丅偙傟傪梫偡傞偵丄摨偠偔擏怘偲偄偭偰傕丄拞崙偲擔杮偲偱偼戝偒側奐偒偑偁傞丅偦偺憡堘偵偮偄偰偼丄椉崙偺晽搚媦傃楌巎揑側増桼偵偮偄偰怺偔峫偊偰傒側偗傟偽側傜側偄偲巚偆丅亙棯亜
乻戧愳惌師榊乼
丂墱栰偝傫偼壗夞傕怘傋偵偄偭偨傜偟偄偺偵丄偙偺傛偆偵僄價桘偺偨傟偵偮偄偰壗傕怗傟偰偄傑偣傫偑丄嶳揷惌暯偝傫偑乽堸怘嶨婰乿偺拞偱壼桘偵偼俀捠傝偁傞偲彂偄偰偄傑偡丅嶳揷偝傫偼乽慺恖偵弌棃傞巟撨椏棟乿偲偄偆愴慜偺拞崙椏棟偺嫵壢彂傒偨偄側杮傪彂偄偨恖偱偡丅嶳揷婌暯偝傫偲柤慜偑帡偰偄傞偗偳丄暿恖偱偡偐傜娫堘偊側偄傛偆偵丅
丂愴屻彂偄偨乽堸怘嶨婰乿偼僇僄儖偑嬄揤偟偰偄傞奊偺昞巻偱偹丄偦偺奊傗戣帤傪堷偒庴偗偨偺偑丄擔揥夛堳偩偭偨彂壠偺嶳揷惓暯偝傫丅偪傚偄偪傚偄梄曋傪娫堘偊偰攝払偝傟傞偺偱抦傝崌偭偨拠偩偦偆偱偡偑丄巹偑帩偭偰偄傞偙偺杮偺偹丄斷偺棤偺乽憰涥丒嶳揷惓暯乿偺惓偺侾帤偩偗報嶞偟偨帤偺忋偵挘傝晅偗偰傞丅攳偑偟偰妋偐傔偰偼偄傑偣傫偑丄壓偺帤偼惌偵堘偄側偄偲巚偭偰偄傑偡丅
丂椏棟偺曽偺嶳揷偝傫偵傛傟偽偱偡傛丄侾偮偼忀壼巕傕偟偔偼壼巕桘偲偄偆傋偒偱丄壼偺棏偲忀桘傪堦弿偵幭偰丄偦傟傪晍偱崡偟偨傕偺丅忀桘偼挷枴椏丄棏偼偍偐偢偵偡傞丅傕偆堦偮偼彫壼傪壗擔偐墫悈偵怹偗偰偍偔偲丄壼偑捑揳偡傞丅偦偺墿妼怓偺忋悷傒偑壼桘丄捑傫偩彫壼傪壼忀(35)偲偄偆偦偆偱偡丅偨傟偵巊偆偺偼忋悷傒廯偱丄杒戝挷嵏偵傛傞偦偺惢朄側偳偵偮偄偰偼丄偄偢傟婡夛傪傒偰榖偟傑偟傚偆丅
丂嶳揷偝傫偼丄偙偺杮偱丄応強偼偳偙偲彂偄偰偄傑偣傫偑丄傗偼傝僕儞僊僗僇儞偵怗傟偰偄傞偺偱丄偦傟傪帒椏偦偺俇偱徯夘偟傑偟傚偆丅擔業愴憟偑廔傢偭偰偐傜棳峴傝偩偟偨偲愱栧壠偑偄偆偺偱偡偐傜丄巹偼偣偭偣偲柧帯係侽擭慜屻偺怴暦傪撉傫偱偄傞偺偱偡偑丄奐揦偟偨偲偄偆婰帠偼傑偩尒晅偐偭偰偄傑偣傫丅慜慄偱怘傋偰埲棃梤擏偑岲偒偵側偭偨偲偄偆暫巑偺榖偼偁傝傑偟偨偑偹丅
帒椏偦偺俈
丂崱梤擏偺捈壩從偵偼丄從梤偺奜偵烤梤擏偑偁傞丅朚恖偼擵傪惉媑巣娋椏棟枖偼惉媑巣娋撶偲堗傂擔業愴憟屻棳峴偺挍傪尒偣丄慟偔恖岥偵鋂鄑偡傞傗偆偵側傝丄搶嫗偵傕擵傪屇暔偵偡傞揦偝傊弌棃偨丅烤梤擏偼婫愡椏棟偺堦偮偱丄斢廐偵巒傑偮偰斢搤偵廔傞偺偑捠椺偱偁傞丅
丂梤擏偼愭偯彌從擏偺傗偆偵敄偔愗傝丄擵傪怘幰帺傜昮丄庰丄忀桘傪崌偣偨廯偵怹偟丄敓壩敨偺擛偒傕偺偵壩傪暟偒丄揝慄忋偱從偒側偑傜怘傋傞丅從偔帪偵廯傗帀朾偑壩拞偵棊偪偰奃偑棫徃傞偺偱壆奜偺堾巕偱偡傞丅慠偟搒夛偺椏棟揦偱偼撶傪暁偣偨傗偆側宍偺暔乆偟偄揝斅偵寠傗寗娫傪愗崬傫偩摿庩側摴嬶傪巊偮偰嫃傞丅梤擏傕彌從摨條從偒夁偓偰偼巪偔側偄丅曅柺偩偗從偄偰怘傋傞偺偑岻幰側怘傋曽偱偁傞丅庰偺偄偗傞恖偼崯偺椏棟偵偼昁偢從庰懄偪敀姳帣偺攖傪曅庤偵丄妿偮堸傒妿偮怘傋傞丅
丂偟偮偙偔丄傕偆堦偮丄烤梤擏儖乕僣愢傪巟帩偡傞杮傪嫵偊傑偟傚偆丅偦傟偼惵栘惓帣乮傑偝傞乯偲偄偆搶杒戝偺愭惗偑戝惓侾係丄侾俆擭偵杒嫗棷妛偟偨偲偒丄傗偼傝惓梲極偱怘傋偨偺偱偡偹丅枮廎恖偺撠擏岲傒偺榖偑愗傝棧偟偵偔偄偺偱丄偦偺傑傑偵偟傑偟偨丅惵栘偝傫偺偊傜偄偲偙傠偼丄偨偩彂暔傪撉傫偱曌嫮偟偨偩偗偱側偔丄杒嫗偺夋壠偵棅傫偱摉帪偺杒嫗側偳偺晽懎夋傪昤偐偣巆偟偨偙偲偱偡丅乽杒嫗晽懎恾奊乿偲偟偰搶梞暥屔僔儕乕僘偵偁傞偺偱丄偦偺奊偺拞偵烤梤擏偺撶偑側偄偐偲尒偨傜丄奊偼側偐偭偨偺偱偡偑丄搶杒戝偺拞崙暥妛偺撪揷摴晇偝傫偺夝愢偑偁傝傑偟偨丅帒椏偦偺俉乮侾乯偑惵栘偝傫丄摨乮俀乯偼撪揷偝傫偑庰嵷娰偲偄偆椏棟揦偺偙偲傪彂偄偨偆偪偺侾晹暘偱偡丅
帒椏偦偺俉
乮侾乯
亙棯亜塃偺乽挼恄擏乿偲偼撠擏傪搾幭偟偨傕偺偱偁傞丅奧偟涋偑恄慜偵挼晳偡傞傪乽挼恄乿偲堗傂丄崯偺晽偼崱傕枮廎偵峴偼傟偰傤傞偝偆偱偁傞偑丄懘偺嵺恄慜偵嫙傊傞惖傪乽挼恄擏乿偲堗傆偺偱偁傜偆丅崯偺晽懎偵娭偟偰惔偺釾恊墹偺乽殏掄嶨榐乿姫嬨乽枮廎挼恄媀乿偺瀶偵徻嵶偑尒偊偰嫃傝丄懘傟偵嫆傞偲恄傪釰傞嶰擔慜偐傜枅擔挬曢惖傪擇摢偯偮專偢傞偲塢傆偙偲偱偁傞丅帶偟偰乽绗墍怘扨乿偺乽敀曅擏乿偺瀶偵乽枮廎僲挼恄擏嵟儌柇乿偲桳傝丄挼恄擏偼敀擏懄偪撠傪娵偺傑乀搾幭偟偨傕偺偨傞偙偲偑抦傟傞丅嬤恖偺乽瀽揤淚憄榐乿姫嶰廫幍乽媔敀擏乿偺瀶偵傕丄枮廎恖偼敀擏傪彯傃丄慜惔帪戙媨拞偺挬夑側偳偵傕昁偢崯偺擏傪梡傤偨桼傪婰偟偰偁傞丅巣偔偺擛偔挼恄擏偼枮廎椏棟偱偁傞偐傜枮廎捠峴偺崅怆庰乮從庰乯偵傛偔崌傆傢偗偱偁傜偆丅崱惀偲摨條偺昡尵傪烤梤擏偵廇偄偰墲乆捠恖偐傜暦偐偝傟傞丅烤梤擏偲偼朚恖娫偵偼扤偑晅偗偨偐惉媑巚娋椏棟偺柤偱捠偮偰傤傞栔屆椏棟偺堦庬偱丄杒嫗偱偼慜栧奜丄擏巗偺惓梲極偺柤暔偲側偮偰傤傞丅懘傟偼桍偺恉偱暟壩偟偰揝壦傪妡偗丄梤偺擏偵忀桘丒橄偺桘丒桕側偳傪崿偤偰嶌偮偨廯傪拝偗偰從偒側偑傜怘傋傞偺偱偁傞偑丄惀傪怘傋傞偵偼從庰傪堸傑側偗傟偽杮摉偺枴偑弌側偄偲堗偼傟偰傤傞丅亙棯亜
乻惵栘惓帣乼
乮俀乯
丂巗応偵壨奍偺弌傑傢傞偙傠偼丄偦偺擭偺嵟傕偆傑偄梤擏偑庤偵偼偄傞婫愡偱傕偁傞丅偦傟傪惣岥戝梤偲屇傇偺偼丄惣岥偡側傢偪挘壠岥偐傜攦偄偗偗傜傟偨栔屆偺梤偑丄挿偄摴掱傪孮傪側偟偰丄嶳娫偺惔棳傪堸傒丄傗傢傜偐側憪傪怘傋側偑傜丄杒嫗摽彑栧奜偵偁傞梤巗応傑偱塣偽傟偰偔傞偐傜偱偁傞丅
丂梤偺擏傪偁偮偐偆偺偼傕偭傁傜夞嫵搆偱偁傞丅梤偺擏偺椏棟朄偼偄傠偄傠偁傞偑丄梀杚柉偺曽朄傪偦偺傑傑揱偊傞烤梤擏偼擔杮偱傕僕儞僊僗僇儞撶偲偟偰恊偟傑傟偰偄傞丅偙偺奍偲梤偺椏棟偼偄偢傟傕杒嫗偺婫愡偺摿暿椏棟偲偟偰婌偽傟傞丅
乻撪揷摴晇乼
| 丂丂 |
嶲峫暥專
帒椏偦偺俇乮侾乯偺弌揟偼墱栰怣懢榊挊乽悘昅杒嫗乿乮搶梞暥屔俆俀俀乯係係儁乕僕丄暯惉俀擭俋寧丄暯杴幮亖尨杮丄摨乮俀乯偲乮俁係乯偼屻摗挬懢榊挊乽巟撨媦枮廎椃峴埬撪乿侾俈俈儁乕僕丄徍榓俈擭俆寧丄弔梲摪亖尨杮丄乮俁乯偼妛弍暥專晛媦夛曇乽崙暥妛擭師暿榑暥廤丂忋戙乿侾俋俋儁乕僕丄戧愳惌師榊乽挅幁棩椷峫乿丄徍榓俆俇擭侾寧丄朁暥弌斉亖尨杮丄
乮俁俀乯偲乮俁俁乯偼墱栰怣懢榊挊乽杒嫗璧婰乿彉俁儁乕僕丄徍榓侾俋擭俀寧丄擇尒彂朳亖尨杮丄
乮俁俆乯偼嶳揷惌暯挊乽堸怘嶨婰乿俀俆係儁乕僕丄徍榓俀俉擭俋寧丄奌巕幮亖尨杮丄帒椏偦偺俈偼摨侾俇俁儁乕僕丄摨丄帒椏偦偺俉乮侾乯偼惵栘惓帣挊乽惵栘惓帣慡廤乿俋姫係俋侾儁乕僕丄乽壴挙乿傛傝丄徍榓係俆擭侾俀寧丄弔廐幮亖尨杮丄
摨乮俀乯偼惵栘惓帣尨曇乛撪揷摴晇曇乽杒嫗晽懎恾恾晥乮俀乯乮搶梞暥屔俁侽乯乿俈俇儁乕僕丄徍榓俁俋擭侾俀寧丄暯杴幮亖尨杮
|
丂偙傟傜偺帒椏偐傜傕杒嫗偺烤梤擏偑僕儞僊僗僇儞偲偄偆柤慜偺椏棟偺尨宆偱偁傞偙偲偼丄偐側傝妋偐偩偲傢偐傞偱偟傚丅偦傟偵懳偟偰偱偡偹丄從梤擏傪僇僆儎儞儘乕丄傕偟偔偼僐僂儎儞儘乕偲撉傓偺偼丄偪傚偭偲柍棟側偺偱偼側偄偐丅弶傔偺曽偱廃払惗偝傫偺撉傒曽傪堷梡偟傑偟偨偑丄從攧偼僔儏僂儅僀偲屇傫偱偄傑偡傛偹丅擔杮岅揑敪壒偱偡偐傜丄姰帏側偼偢偼偁傝傑偣傫偑乽僗僌栶棫偮椏棟偺拞崙岅乿偵傛傟偽從偼峀搶偱偼從烤偺堄枴偱傛偔巊傢傟傞偲偁傝丄敪壒偼倱倛倎倧(36)偲彂偐傟偰偍傝丄僇僆偲偼敪壒偟側偄偲巚傢傟傑偡丅偙傟偼拞崙偐傜偺棷妛惗彅孨偵嫵偊偰傕傜偄偨偄偲偙傠偱偡偑丄從梤擏偼僐僂儎儞儘乕偲偼敪壒偟側偄壜擻惈偑戝偱偡丅嵅乆栘撗擇愭惗偼烤偺妶帤偑側偄偟丄帤媊偑嬤偄偐傜偲撈帺偺敾抐偱從偺帤傪彂偄偨偺偱偼側偄偱偟傚偆偐丅
丂偦傟偵烤偼丄傁傝傁傝偡傞傛偆偵從偔偲偄偆堄枴傜偟偔丄桳柤側杒嫗偺傾僸儖偺娵從偒偼烤姏偲彂偔傫偱偡偹丅偦傟偐傜僀儞僞乕僱僢僩偱烤梤擏傪挷傋傑偡偲丄偄傑偼娤岝媞偵偼梋傝庴偗側偄傛偆偱丄偁傑傝尰傟傑偣傫丅娤岝椃峴擔婰偺懡偔偼梤擏偺偟傖傇偟傖傇傪怘傋偨榖偱偡偹丅偨偩丄峀偄拞崙偺偙偲偱傕偁傝丄惣堟偺曽偱偼從梤擏傪僇僆儎儞儘乕偲屇傃丄僔僔僇僶僽丄孁從偒偩偲偄偆椃峴婰傕偁傝傑偡偺偱抐掕偼偱偒傑偣傫丅
丂偲偙傠偱丄拞崙岅偺帿彂偱偼丄僕儞僊僗僇儞偼烤梤擏偲柧夣偵掕媊偝傟偰偄傞傫偱偡傛丅棦尒偑柦柤偟偨傢偗偱偼偁傝傑偣傫偑丄壖偵徍榓俆擭偐傜巊傢傟弌偟偨偲偟偰傕丄傕偆俈侽擭埲忋偵傕側傞偺偱丄偪傖傫偲偟偨擔杮岅偺柤帉偲拞崙恖偑擣傔偰偍傞丅乽徻夝擔拞帿揟乿媦傃乽怴擔娍帿揟乿偲偄偆俀嶜偺擔拞帿揟傪堷偄偰傒傑偡偲丄偳偪傜傕偱偡傛丄僕儞僊僗僇儞撶偼柤帉偱偁傝丄烤梤擏(37)偲偟偰偄傑偡丅徻夝偺曽偼丄壛偊偰乮栫仭亙愢偺棯帤懱偲尒傜傟傞帤亜乽僕儞僊僗僇儞椏棟乿乯偲偁傝丄偳偆傕僕儞僊僗僇儞椏棟偲偄偆応崌傕摨偠偲偄偆偙偲傜偟偄偺偱偡丅
丂僩僢僾儁乕僕偵彂偄偨偙偲傕娷傔偰丄巹偑偄傑傑偱榖偟偨拞偱偼丄堦斣憗偔僕儞僊僗僇儞椏棟偲偄偆柤慜傪擔杮偺崙撪偱岞偵偟偨偺偼棦尒偝傫偲側傞丅巹偼傕偭偲屆偄暥專偼偨偔偝傫抦偭偰傑偡偑偹丄偙偙傑偱偱戝楢偺擔壺岎娊夛偼彍偄偰乗偱偡傛丄彮側偔偲傕嶳揷婌暯偝傫偺杮傛傝侾擭憗偄丅偦偙偱師夞偼丄枮揝偺偛彽懸偱枮廎傪夢傝丄杒嫗傑偱峴偭偰偒偨椃峴婰丄棦尒偺乽枮巟堦尒乿傪嬦枴偟傑偡偑丄傕偟偐偡傞偲丄斾妑偵巊偆偐傕抦傟傑偣傫偺偱丄偒傚偆攝偭偨墱栰偝傫偺乽墠嫗怘晥乿偺僾儕儞僩傪帩偭偰偒偰壓偝偄丅廔傢傝傑偡丅
| 丂丂 |
嶲峫暥專
忋婰乮俁俇乯偺弌揟偼栘懞弔巕丄摗嶳榓巕丄屶徦桬嫟挊乽僗僌栶棫偮椏棟偺拞崙岅乿俀俁俉儁乕僕丄暯惉俆擭俉寧丄幠揷彂揦亖尨杮丄乮俁俈乯偼杒嫗奜崙岅妛峑曇乽徻夝擔拞帿揟乿侾侽係俈儁乕僕丄徍榓俇侾擭9寧丄岝惗娰偲戝楢妛崙岅妛堾曇乽怴擔娍帿揟乿俇俆俀儁乕僕丄徍榓俇侾擭俁寧丄搶曽彂揦亖偄偢傟傕尨杮
|
|