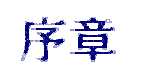
たとえ簡素であっても、花嫁の部屋というものはある種の華やかさを持っている。でも、 あたしの部屋にはそんな雰囲気はない。涙なんて出やしない――でも、心の中はもう ずたずたの泥まみれだ。 「リディアさま、どうか袖をお通しください……。もう時間もございません。早くしないと お父上に怒られます……」 あたしばかりじゃなく、ナディーヌも怒られるね。心の中で毒づく冷静さがあったことに、 あたしは少しだけ面食らった。 あたしはこの村の長の娘として生まれた。その上、あたしには兄がいる。だから、それは、 生まれ落ちた瞬間から決定されていたような運命だった。だから、あたしは嫌だった。 ああ、ナディーヌ。優しいナディーヌ。あたしよりちょうど十年上で、いつも侍女としてでは なく、姉さんみたいに接してくれた。顔が細く尖っているのが嫌だと言って、いつも 長い髪の毛を肩のあたりに垂らしているナディーヌ。 でも、そんな「姉さん」も、しきたりや政治――男の世界の決定事項には逆らえない。 「姉さん」は、あたしをかばってはくれない。 花嫁衣装に袖を通したら、負けだ。絹とレースでできた豪華な服は、あたしの一生を鳥籠に 縛ってしまう拘禁服だ。意地でも着るわけにはいかないから、あたしは生まれてはじめて 「姉さん」と喧嘩した。口論し、泣きじゃくり、取っ組みあってひっかきあい……。 ナディーヌのきれいな黒髪はぼさぼさに乱れ、褐色の肌にはいたるところひっかき傷が できている。もろい花嫁衣装はあちこち破れ、踏みつけられて黒ずみが激しい(あたしに とってはいい気味だ)。当の花嫁であるあたしはというと、やっぱり顔じゅうひりひりと 痛い。激戦の結果、部屋の鏡はみんな割れてしまったので確認はできないけど、たぶん ナディーヌの顔とどっこいにひどいありさま。ナディーヌはとっくの昔にその役目を完全には 果たすことはできなくなって、泣きだしそうな顔をしている。ごめん、ナディーヌ……。 結婚って、何なの? ある日突然、娘は結婚の相手の名を知らされる。両家の間で どんどん話は進み、やがてめでたく結婚式。花嫁も花婿も当日初めてお目にかかって、 「はじめまして」と「誓います」の二言が交わされただけで気がついたら夫婦になってる。 それが良家の習わし。確かに、昔は違った。けれども、今はそういう時代ではない。 しかたない。 でも、あたしは自分の人生をあきらめきれない。まだ、あたしは恋だってしたことがない。 というより、恋というものがどんなものなのか、想像もつかない。 責任は半ばナディーヌにある。ナディーヌは恋というものを知っている(らしい)から。 いつだったか、ナディーヌが窓から帰ってきたことがあった。それも、二階の窓から、夜遅く。 『あら、リディア、起きてたの? ……このことは、内緒にしてね』 窓の外、屋敷から少し外れた暗い茂みの中に、なごり惜しそうな視線を送るナディーヌが、 うらやましくてたまらなかった。くやしかった。 家って何? 村って、社会って? ……そう、普段いい服を着ていいものを食べるのは、 いずれ何かの役に立つため。待遇が良ければ良いほど、果たすべき何かは重大になってくる。 父さんは、いつもそう言ってる。 でも、頭は納得しても、心は納得していない。知らなければ、こんなに焦がれやしない―― でも、あたしは見た。よりによって、「姉さん」――ナディーヌの恋に浮かれる姿を。 あんなにはしゃいで、うきうきして、きらきら輝いて、数日に一回、逢うほんの少しの 時間のためだけに、長い時間を惜しげもなく浪費するナディーヌ。彼のために、長い つきあいのあたしだって知らない、とびっきりのすてきな笑顔を用意しているのだろう。 あたしはくやしい。 だから、この袖には手を通してやらない。 あくまで意地を通す決意をした瞬間、あたしはナディーヌの顔を見てしまった。 しょぼくれ途方に暮れたナディーヌの顔……まるで隠したクルミをなくしたヤマネのようだ。 すると決意はいきなりどこかへ消し飛んでゆく。そうやって決意と優柔不断の間の堂々巡りを 繰り返していると、突然ドアがバタンと開いた。そして、そいつはあたしの部屋にまるで 無頓着に侵入してきた。 「用意はできたのか」 あたしは反射的に、手近な枕をそいつに投げつけた。でも、憎ったらしいことに、そいつは 平然と枕を受け止め、正確にベッドへ投げ返した。 「兄さん、不作法よ! いくら兄と妹でも、レディの着替え中に……」 「着替える気もないくせに」 そう、そいつはあたしの兄さん、ヒューゴー。腰まで届く髪をバンダナでかきあげ、 その鋭い視線を妨げないようにしている。勇敢さと強さとたくましさ、するどさにおいて このあたりの村でかなう戦士はいない。自慢の兄、ヒューゴー。まぶしすぎる、 あたしの兄さん……そして、今日ほどこんな兄を持ったことをくやしく思ったことはない。 兄さんの意志は父さんの意志。絶対に実現する――実現される。普段理不尽な要求は 絶対にしないがゆえに、なおさらだ。 兄さんはナディーヌの肩に手を置き、そっと抱き寄せた。ナディーヌも兄さんの胸に 少し寄りかかると、その場を下がった。……この雰囲気、言葉なしでも通じる意志。 ……そう、兄さんがナディーヌの恋人。身分違いもあまり関係ない。アールヴは普通子供を 一世代に一人か二人しかつくらないから、子供さえできてしまえば兄さんたちの望みは叶う。 そう、血を分けた兄の望み、仲良く育った「姉さん」の望みは叶うのに、あたしの 望みは天高く、こんなに煌いて見えるのに絶対に触れることはできない。 「リディア、仕方ないのだ。シャナラの長は強い。シャナラは近年、とみにその勢力を 増してきている。丸耳の脅威が増しつつある今、森に生きることがアールヴの宿命なら、 森に住む者同士で結びあってゆくしかない。そして、結ぶなら今なのだ」 兄さんはあたしを真上から見下ろすように話している。兄さんは剣の達人で、魔法の達人。 手にする武器「ブレードロッド」は文字通り剣身を備えた魔法の杖で、それを手に戦場を 駆け巡るとき、敵はことごとく打ち斃される運命にある。……いや、ただでさえ 刃物のように鋭い兄さんの威厳に、こうやって向かい合っているだけで一秒ごとに あたし自身がどんどん萎縮してゆくのがわかる。 「政略結婚なんか……」 あたしはとうとうその言葉を口にした。事実とは言え、その響きを耳で味わうことだけは 勘弁してほしかったのだ。でも、こうやって兄さんと向かい合っているあたしには、 事実を告げて兄さんを告発する以外、ない。 そして、その弱々しい抵抗を、兄さんは無情にもピシャリとさえぎった。 「今はそういう時代なのだ」 「…………」 「早く用意しろ」 「…………!」 あたしの目はほとんどすがるように兄さんを追った。だが、その一縷の望みも 儚く振り切って、兄さんは部屋を出ていった。 ナディーヌはなぜかかえって困惑している様子だった。 「……リディアさま。どうか、ご用意を」 ナディーヌはドレスを差し出した。そのドレスは汚れ、破れ、――そしてぶるぶる 震えていた。それに気づいても、あたしにはナディーヌの顔を見る勇気がなかった。 あたしには痛いほどわかった。しきたりにはまるで無力なナディーヌ。あたしの侍女の ナディーヌ。……そして、兄さんが大好きなナディーヌ。いろいろなナディーヌが、 唯一「姉さん」であることだけを許さない。あたしはナディーヌが好き。そして、 ナディーヌだって……。 「……リディア。何が、望みなの?」 この瞬間だけ「姉さん」に戻ったナディーヌが訊いた。卑怯すぎる――他の大半の 時間は「姉さん」以外のナディーヌだったのだから。 あたしは涙があふれてくるのを感じた。……そう、それでも――ナディーヌはあたしの 優しい「姉さん」だった。侍女という身分に縛られてはいるけれど、家族も同然の かけがえのないひとだ。 「あたしは――」 恋が、してみたい。 「あたし、……」 そう、姉さん。あたしにあこがれを与えたのは、絶望的なまでに焦がれる想いを 植え付けたのは、他ならぬ姉さんなのよ。 あたしは――! ……そう、言えなかった。それは些細な望み。そう教えられてきたから。否、もっと違う、 あたしを縛る漠然としたなにか、あたしを規定しようと画策する心の中の蠢動。 正体はわからない。どうでもいい。あたしは泣いた。泣いている間は、目を上げなくて済む。 目を上げたら、今、視線を動かしたら、――姉さんの瞳を覗き込んでしまう。 姉さんはあたしの背中を優しく撫でた。どうやらあたしは姉さんの膝に顔をうずめて 泣いているらしい。あたしは慌てて後ろを向いた。 「ナディーヌ……ドレス、置いてって」 「でも……」 姉さんの声も震えていた。できるだけ、あたしはその声を聞かないようにした。 「あたしだけで大丈夫。少し……ほんの少しでいいの。独りにして」 「…………」 ナディーヌは部屋を出ていった。ドアを閉めるときに見せたその顔は、ほんの少し困って、 ちょっぴりだけ泣きべそをかいているような無表情だった。 ドアは静かに閉まった。姉さんらしい。――困っていようが昂っていようが、姉さんは 常に感情を抑制できる。それが姉さんとあたしの差であり、だからあたしはそれを マネしようとしているし、嫉妬してもいる。ともかく今は無理な注文だ。役者が全員 袖に引っ込み、緊張の糸が解れると、あたしはくたっとなってベッドに身を投げた。 今は、クッションの柔らかい肌触りが心地よかった。そう、今は――今は! 未来に 重大な選択の岐路が待っているとしても、今はこの数分間だけの「今」が一番大切だった。 (家族って……こんなものなのかなぁ……) あたしはふとそんなことを考えた。すると、悲しくて……涙が止まらなくなった。 涙を受け止めてくれたのはクッション。あたしにとってこの世界での安らぎといえば、 相変わらずこのクッションだけだった。