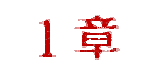
アールヴという種族を知っているだろうか。俺は、今、彼らの村に向かっている。 アールヴ族は背の高い、森に住む浅黒い肌の種族だ。人間との外見上の一番の相違は 耳が尖っていることだろう。人間は彼らを軽蔑して「長耳」と呼ぶし、彼らも人間を 「丸耳」と蔑む。森を傷つけることを好まず、魔法にたけ、温和で、知的な雰囲気を好む というのが彼らの一般的な性質である。人間の中には彼らのことを「妖精」と呼ぶ者もいる。 それくらい実態が世間に知られていない種族なのだ。 知られていないが、接触はある。旅人が森を通過するとき、狩人が森に踏み入ったとき、 木の葉のざわめきの向こう、枝々の織りなす暗い深淵の向こうに、その存在を感じることが あるという。一般にはその程度のつきあいだ。 だが、人間が森を拓き、耕作地や町を新たに築こうとするとき、もっと不幸な 接触が起きる。戦争だ。生きる場所を奪おうとする者と奪われる者との熾烈な殺し合い。 アールヴ族を根絶してはじめて、人間は森を根こそぎにできる。武力の掟を行使できるのは 一国の王だけだ。そのため、アールヴ族の身近に住む村の住人よりも、町の学者の方が、 研究によってむしろ彼らについて詳しく知っている。 いずれにせよ、充分良識ある世界に住んでいる者ならば、彼らとは積極的に 接触しようなどとは考えまい。お互いに無知なる者同士の接触は、ストレスと不幸を招く。 彼らの村に近づく人間は、悪意ある弓矢の標的とされるだろう。 だが、俺の手持ちの食糧も、残りは微々たるものでしかない。人間の町や村では、 俺は大手を振っては歩けない。剣呑な道ではあるが、一度彼らの村に寄らない限り、 この森は通過できない。 俺は、フェリクス。だが、人間の世界では、俺は「イブリースのフェリクス」として 知られている。かつては栄光ある騎士団の軍団長であり、今は祖国を滅ぼした卑怯者として 逐われる身だ。「叛逆の悪鬼」――イブリースの通り名は、卑怯者にふさわしい悪名として 俺につきまとう。そして、俺の鎧が――戦場ではパーソナルマークとなる鎧の個性が、 皮肉にも俺を「イブリース」であると主張している。……だが、いまさらこの鎧を 脱ぐつもりはない。この鎧とこの剣だけが、俺に残された数少ない友なのだから。 俺はイブリースのフェリクス。だが、俺は、そんなご大層なシロモノではない。 本当は、俺はただの負け犬だ。俺の今の命は、決して戦ってかちとったものではない。 ただ単に、俺は生き残ってしまったにすぎない。 暗い森が、かすかに明るくなってくる。コケやシダの絨毯が敷き詰められた地面を、 クマザサの茂みがとってかわる。重く湿った空気の香りが、懐かしい乾いたものへ。 森の奥、暗闇の中から漏れてくる何かの動物の鳴き声が、頭上で奏でられる小鳥の 雑多な合唱に。この人間世界の外縁、さいはての森が懐に包み込んでいるもののすべてが、 みるみるうちに心地よいものに変わってゆく。 ひとの生活するところが始まるのだ。それが丸耳の住処であれ、長耳の住処であれ、 放浪の身にはぬくもりを予感させる。一言で言えば、俺にとってそれは限りない眩しさだ。 いくら肌に感じ、憧れ、羨んでも、もはや俺の身体はそれに耐えきれない。 だから、俺は町ではひっそりとした暗がりの中にしか一時の安息所を見つけることが できない。 そこは、鄙びた宿だった。排他的なアールヴの村で宿を見つけること自体 難しいことだったが、ともかく俺は直観的にそれを見つけた。どこであれそれは 二種類に分類される――善良な住民の居住区と、ならず者やごろつきの溜り場と。 俺が平穏に存在できるとすれば、後者だ。 アールヴの集落では騒ぎは起こしたくなかった。いや、それは人間の町でも同じことだ。 厄介事は充分に味わってきた。……見るべきものはもう、見てしまった。 「おい、親父。部屋は空いているか」 幸いにもこの宿の親父は気さくな男らしい。白髪と赤ら顔の、どちらかというと 人間に近い顔の造作をした男だ。肌が浅黒く、線が細く整っているというアールヴ族の イメージからはややかけ離れているようだ。そいつは埃まみれのカウンターにどっかと 足を乗せ、昼間っから酒を飲んでいる。 「貧乏宿屋にゃ空き部屋しかねえさ。さもなきゃ丸耳野郎に……しかも、スネに傷持ってる 野郎は野宿するっきゃねえや」 確かに、この床の埃の量からすると客はほとんど入らないようだ。この程度の罵倒は 大目に見るべきだろう。俺だって、国を逐われるまではアールヴを随分と馬鹿にしていた ものだ。無知と偏見――その痛みは味わってしまえばこれほど辛いものはないが、 その辛さを相手に理解してもらえることはほとんど至難である。 「俺がお尋ね者だと、なぜ考える?」 「丸耳が他にどんな用事で長耳の村に来る?」 親父は俺の勿体ぶった口調を真似して言った。まあ、確かに丸耳の俺がここにいる 理由は他に見つからない。俺の洞察力が大甘なだけだ。 「手前ぇ、わしもダテに宿屋のあるじなんざやってねぇ。手前ぇみたいな連中はみんな、 疲れきって、やつれきって、そりゃひでぇツラで来やがるからな、一発でドンピシャリだ」 「酒ごときで曇るような目はしちゃいない、というわけだな」 「おうよ、ったりめぇよ。いいこと言うじゃねえか」 上機嫌で親父は革袋を傾けた。豪勢なことだ。しかも、この匂い――そんなに上等では なさそうだが、この親父に買える酒ではない。ヌーヴォーだ。一番酒の芳醇な匂いが、 こちらまで漂ってくる。 「近々さるおえらいさんと村長の娘の結婚式があるんだよ。んで、ちょっとおこぼれに あずかってきた。今ならこの村の連中の気も緩んでいるからな、手前ぇも無事に村ん中に 入れたってわけさ」 あきれた。要するにこの酒は、どこかの倉庫か酒蔵から、無料で失敬してきた酒らしい。 ……ま、この親父程度の――いかにもノロマで、抜けていて、とてもスリなどできそうに ない男にさえこんな芸当が可能なのだ。よほど村には人がいないか、本当に気が 緩んでいるかのどちらかなのだろう。 「ほらよ」 突然こちらに放り投げられた革袋に、俺は少々面食らった。親父のにたにた顔が さらにその笑みを広げる。その意図を汲み取ると、俺もにっと笑って酒に口をつけた。 俺はよほど物欲しそうな顔をしていたのだろう――たまたま親父が気のいい酒飲み だったので、御相伴に与れるという訳だ。一口含んでその香りを楽しむと、喉を灼く 爽やかな圧力に身を任せた。酒はいい。たった一口の酩酊が、放浪の身には限りなき 贅沢の果実と感じられる。革袋を親父に返すと、俺は財布を開いた。俺としては金貨を 払っても惜しくないくらいの贅沢だった――だが、この親父には金貨は宝の持ち腐れだ。 この親父が金貨などを使おうとしたら、盗んだ金と勘違いされるだろう。俺は親父の 掌に一枚、また一枚と銅貨を置いた。親父は銅貨四枚で納得した。 「旨かったぜ。……部屋、借りるぜ」 「何部屋でも使ってくれや。どうせ客なんか来やしねぇんだから」 俺の背中へ、親父は酔っ払った頭が許す限りの理性的な忠告の言葉を投げた。 「本当に、面倒なんか起こすんじゃねえぞ。……わしまでしょっぴかれちまうからな」 いい忠告だ。 黒髪のアールヴ族の真っ只中にいる金髪の丸耳野郎。おまけに、平和でのどかな森の民の 中で、煌く金属の甲冑を身に纏っている奴は俺ひとりだ。無論、兵士や番人は 武装しているが、粗末な革の防具を着用しているだけだ。金属の多用は、燃料として 木を伐採し、鉱毒によって森を蝕むのでアールヴには禁忌なのだ。 そう、丸耳の俺は本来なら昼間はこの宿から出るべきではない。だが、食糧があまりに 逼迫している。そして、必要な物を買うことのできる店が開いている時間は昼間しかない。 アールヴの村は、丸耳の目には一瞬廃墟のように見える。家々はすべて蔦に覆われて 建っているからだ。家の半数は樹木をそのまま大黒柱に使っており、その光景が印象を さらに際立たせる。樹木にまとわりついた家の間にそうでない家を押し込んだような 家並みは、雑然としか言いようがない。道も、荷車の幅に合わせてレール状に石畳が 敷かれているだけで、あとは草が生い茂るにまかせてある。無秩序な家並みのせいで、 路地たるや複雑怪奇なラビリンスの風を呈している。 その路地に、雑貨屋らしき店があった。商品の陳列具合と看板からして、そうに違いない。 「よいお越しで」 これがアールヴ流の「いらっしゃいませ」である。 「携帯食糧が見たい」 「こちらで」 眠そうな目をした小太りの親父は、手元の包みをひょいと取り上げた。だが、遠い。 遠すぎる。俺の手が届かない。 「ご主人。それでは品物が見えない」 「はあ、ご勉学がお好きのようで、目をお悪くなされましたか」 「違う、俺はそれを手に取って見たいのだ」 俺が一歩近づくと、親父は一歩退いた。明らかに丸耳と剣とを警戒している。 俺は何もしない、というつもりで手を開いて見せた。 「生憎ですが手前どもでは現金払いしか……」 いや、現金がないというわけではない。万引きなどしないからそれを見せてくれ。 五分くらい頓珍漢なやりとりが続いた後、親父はようやく包みを俺に手渡してくれた。 包みに見えた物は木をくりぬいて作られた箱で、その中に木の実や焼き菓子などが ぎっしりつまっている。 「このレレムブリアラス(焼き菓子のことらしい)はアールヴの主食で、木の実を 碾いた粉を固めて焼いたものです。栄養が濃縮されていて、丸耳の麦スポンジ (パンのことらしい)一個よりこちらのほうが体によろしいようで」 親父の口上をまとめるとこうなる。一箱で二食、都合一日分の食糧になるらしい。 他にも何か言っていたようだが、俺には理解できなかった。まあ、かさばらないので 都合がよさそうだ。だが、値段を聞いて慌てた。 「一つにつき銀貨一枚にしておきます」 「待て、高い」 人間のそれの五倍はする。俺は踵を返した。もう少し負けろとのゼスチャーなのだが、 親父は事もなげに言いやがった。 「いずれのお越しの際にもよろしく」 アールヴの「ありがとうございました」だ。俺はぐうの音も出なかった。所詮元騎士の 俺には商人並みの気の利いた駆け引きなどできない。俺は降参することにした。 「すまん、親父、もう少し負けてくれ」 「では、一つにつき銅貨八十枚ということで」 二割引きか。それでも丸耳レートで四食分。情けない交渉の末、結局俺は金貨一枚 支払って二週間分のレレなんとかを手に入れた。俺が金貨を渡すと、親父は不安そうに それを眺め、何度も噛んだりして確かめていた。 ……ああ、そうか。親父も不安なんだ。俺が騎士だったころ、俺の使う金貨はそれ自体の 価値以上の価値を持っていた。俺が騎士の座を逐われたとき、俺の使う金貨はその価値を 百分の一にまで落としていた。そして、このアールヴの村では、金貨はその真贋さえ 疑われる。金貨自体は何も変わっていないのに。そう、あの宿屋の親父が金貨を使うことが できないのと同じ理由で、俺も金貨から価値を奪っているのだ。安い男なのだな、俺は。 ……だが、俺は、心の痛みは感じないことにしている。 結局、金貨二枚分の高い買い物をして、俺はその店を出た。瞬間、石が飛んできた。 躱しざまにそちらを見ると、物陰から子供がこちらを窺っていた。俺が睨んで一歩 踏み出すと、ガキどもはわっと囃し声をあげて逃げ去った。路地にいる他のアールヴを 刺激するわけにもいかないので、俺も足早にそこを立ち去ることにした。 俺が騎士だったころ。それはなるべく考えないようにしている。だが、こうして流浪の 旅を続けていると、過去は生々しい痛みを伴って甦ってくる。かつて、俺の相棒は 「騎士の右腕」、すなわち長剣だった。馬上において、はたまた地上において、土嚢に 囲まれた陣地の中、石造りの城壁の上、……白兵戦を共に生き延びたのは 飾り気のない長剣だった。今、俺の友はブロードソードだ。定尺より短めの幅広の小太刀、 俗に「喧嘩用」とまで綽名される乱戦用の剣。室内で、路地で、額を接するような ごったがえす戦場で生き延びるための剣。獅子の牙は、犬の牙になってしまった。 「馬鹿野郎、どこ見て歩いてやがる!」 角を曲がろうとして、俺はアールヴに弾き飛ばされた。つまらないことを考えていたので 全然注意していなかったのだ。 「ボーッとしてんじゃねえ、丸耳野郎」 「失礼した」 俺は相手も見ず、適当に謝って逃げた。どうせ、どんなに丁寧に謝っても喧嘩に なるのなら、早めに逃げたほうがいい。……負け犬には、牙を剥く機会さえない。 怒号はすぐに聞こえなくなった。 角を何回か曲がると、広い通りに突き当たった。俺はいきなり通りに出ずに少し 様子を見た。どうやらこれはこのアールヴの村に存在する唯一の道路――整備された 軍用の幹線道路――らしい。向こうの方では何やら積み荷を降ろすのに手間取っている。 この手の道路は、平時は商業用、非常時は軍用と相場が決まっているのだ。荷車を 引いているのは巨大なカエルだ。コウモリの皮翼のような巨大な翼を持ったそれは、 でかく、重たく、不器用そうで、繊細な工芸品など運搬できまい。但し、重くて かさばる物を運ぶにはよさそうだ。現に、荷車に乗っているのは樽や大きな木箱だ。 そういえば、宿屋の親父はさるおえらいさんの結婚式があるとか言っていた。 あれは親父がくすねていた、結婚式の引き出物のワインの樽だろう。しかし、 えらい量の樽だ。大盤振る舞いとはこのことだ。 「きゃっ!」 背後に衝撃を感じ、俺は俯せに吹っ飛んだ。まるで無防備だったので、危うく 顔をすりむいたうえに舌を噛み切って死ぬところだった。出血こそしなかったが、 甲冑の重みと倒れた衝撃で息がつまりそうになった。後頭部が痛いのは、ぶつかった ときに相手の額が見事に直撃したせいだ。 「ごっ……ごめんなさい! どこのお方か存じませんが、申し訳ございません!」 見ればそれはアールヴの小娘だ。鼻を直撃したらしく、地面にへたり込んだまま 赤くなった鼻を押さえている。その無理な体勢のまま、小娘はぺこぺこ謝りだしたので 、俺はかえって警戒した。どこへ行ってもヨソモノとは差別され、軽く扱われるものなのだ。 それが丸耳ではなおさらである。こうして謝られると、何か裏がありそうでこわい。 「は? あ、いや、こちらこそ、どうも」 俺はしどろもどろになりつつ、必死で謝った。……俺は、何をしているんだ? ついさっきまでひがんでひねくれたアウトローを気どっていたので完全に調子が 狂っているのだ。目の前の小娘が、漆黒の髪と浅黒い肌、つぶらな瞳のちょっとした 美人だからということもある。少なくとも、すっきり細めの整った顔立ちは、俺好みだ。 もっとも、俺好みといったところで、あえて丸耳の俺に近付こうとするアールヴの女は いないだろうが。 そう、調子が狂っている本当の原因は、そこにある。俺に近付くはずもない少女。 有名なアールヴ紬の絹織物をふんだんに使った服を着た少女。 「えっ……いやその、……」 言葉は未だ戻らない。全身をさいなむこの焦燥感は、トラブルに巻き込まれたとき のものだ。俺にはわかる。負け犬はトラブルの香りには敏感なのだ。 「……、失礼したな」 俺は急いでその場を立ち去ることにした。……今日になって何度目だ、こうやって 尻尾を巻いて逃げ出すのは? ともかく、つまらないゴタゴタに巻き込まれるのは ごめんだ。 だが、俺の右腕はしっかりと攫まれていた。甲冑越しでも感じ取れる、腕に巻きつく その柔らかい感触。それは線が細く頼りなく、振り払えばすぐに突き放せるほど脆い 抱擁だった。しかし、小娘の、大木にしがみつくリスのような必死の形相に、俺は一瞬 躊躇した。一度躊躇してしまえば、もはやそう簡単に邪険にはできない――。 「何のつもりだ」 小娘はそう判断したのだろう。だが、何に必死なのか知らないが、俺には関係の ないことだ。娘は追われている。それだけで充分だ。充分迷惑なのだ。 「なかなか上品な家庭で育ったようだな。だが、頼るなら他をあたってくれ」 騎士の右腕にしがみつくという行為は、貴婦人が相手に庇護を要請するというゼスチャー なのだ。古き良き時代、騎士が敬虔で神聖な存在だった時代には、か弱き女性にとって、 それは拠り所だった。……無論、今もその習慣は生き続けているが、ごく上層の階級に 限られる――それも、「無償の愛」に基づく行為ではなく、利害計算に基づいた欲得ずくの 行為としてである。今は、常に政治上の現実のみが正義なのだ。ましてやこの ゴロツキの俺にとっては、それは至上命題でもある。 「逃げるんだったらさっさと行ってくれ! 俺は道を急いでいるんだ」 「お願いします……助けてください」 小娘はすがるような目で俺を見た。俺は、その瞳の輝きに耐えられなくなった。 俺には―― 「そんな目で俺を見るなッ!」 遅かった。大勢の足音が近付いてきた。トラブルだ! その靴音は、金属の靴底の ものだ。鎧の継ぎ目のこすれあう、嫌な音もする。そして、何よりも嫌な、歩くたびに 甲冑と剣のたてる、あのガチャガチャという音。 騎士どもが来た。