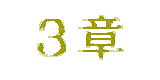
そのとき、俺は軍団長だった。 正式にはロルカ王国軍・征アルファート大将帥。ロルカは当時、急速に膨張しつつある アルファート王国に、深刻な恐怖感を抱いていた。ロルカばかりか、周辺諸国はみなその影に 怯えていた。北のパーリシャド王国がアルファートによって半年のうちに征服されると、 それは現実となった。アルファートは後顧の憂いを断ち、いよいよ版図拡張の野望を実現に向けて 動きはじめたのだ。 そして、戦がはじまった。 当初の懸念を覆して、我が軍は緒戦に大勝利をおさめた。敵に奪われた領土を奪回し、古い 国境線を突破、我々は快進撃を続けた。そして、アルファートの都まであと数日という、至近の 城塞まで確保した。 だが、やはりそれは無理に無理を重ねた戦だった。日に夜をつぐ強行軍によって、味方には 疲労と不満がたまっていた。補給線も伸びきったため、本国からの物資も滞りはじめていた。 俺の副官のホルヘは、さすがに愚痴はこぼしはしなかったが、若い連中は我慢などしなかった。 口々に不満を漏らし、当直もさぼりがちになりはじめていた。この戦は、もう限界の 一歩手前まで来ていたのである。 国王親征の戦では、大将帥など下級参謀よりも軽く扱われた。ましてや勝ち戦で 独り意気高揚としている国王に、俺が何を言おうと無駄であった。だが、さすがに そのときばかりは俺は、戦闘指揮官として、また、兵士たちを束ねる長として、 王に忠告する義務があると思った。そこで、俺は王に注進した。 ロルカ王は、王の地位にふさわしく、格幅のいい男だった。濃い髭と眉毛が、 いかにも叡智を蓄えた賢者のような印象を、彼に与えていた。 『何だね、フェリクス君。言いたまえ』 無論、王の言葉は形だけのものだった。なぜ、そのとき俺は気づかなかったのだろう? 王は、食事中だった。その口に入る料理は、とても豪華で多かった。 突然、王は不快そうに自分の顔を叩いた。蚊が一匹、血をたっぷり吸ってつぶれていた。 見れば、王の周りを数匹の蚊が飛んでいる。 なぜ気がつかなかったのだろう! 蚊が少ないこの時期に、かくも王の周りだけ蚊が 多いのだと。痩せ衰えて血色の悪い兵士には寄りつきもしない蚊が、なぜ王に まとわりつくのだと! ……俺は、ただ黙っていた。ただかしこまって、そこで頭をうなだれていた。 ……俺に何が言えよう。あらゆる言葉をつくしたところで、おそらくは何も 通じない相手だ。俺は、どうすれば忠義を果たせる? どうすれば、兵士を救ってやれる? 悩む俺を尻目に、王は黙々と食事を続けていた。突然、王はナイフとフォークを 床に叩きつけた。勢いよく立ち上がったはずみで、テーブルの上から皿が二、三枚落ち、 盛大に割れた。兵士三人の一日分の食料が、床にこぼれた。だが、俺は眉一つ ひそめることは許されなかった。 『……その方の魂胆など知れておるわ。……さぞかしねたましいのであろう、余が』 俺は混乱した。ねたましい? ……王の論理は、俺には到底理解できなかった。 『王自ら兵を率い、敵を一掃する。お主ら将軍連中には、さぞや頭の痛いことであろうのう。 ……国王が戦にことごとく勝利してしまっては、野戦の将軍など、不要じゃからのう』 王は格幅のいい腹をゆすりながら、神経質そうに歩き回った。何度もしごかれる 口髭の向こうの目は、そのゆがんだ口元とは裏腹に、笑ってはいなかった。 『勝ち戦の途中じゃ。うぬが何を言おうが、余は歩みを止めるつもりはない。 アルファートが滅びるか、降伏せんかぎりはな』 王は語尾を震わせながら、そう言い放った。どうやら、あちらはあちらで怒りに 燃えているらしい。とどめの捨て台詞が、その王の口から漏れた。 『……忠臣面の逆臣めが』 結局、俺は王の御前で何一つ喋らなかった。 その日の午後、自ら謹慎していた俺の部屋に、伝令が来た。威勢だけの、 がらんどうの鎧のような男だ。伝令は、何を読み上げるでもないのにしゃっちょこばって、 重々しくかつすらすらと簡潔に、王の勅命を伝えた。 『大将帥フェリクス殿。来たるべき大攻勢に備え、我が軍の進路と敵の内情を探るべし。 ついては、麾下の手勢一〇騎を率い、御身自ら状況を視察されたし』 そういうことか。伝令はそそくさと去った。彼もさすがにその命令が俺にとって どんな仕打ちか悟り、気を利かせてくれたか――あるいは単に彼自身にとばっちりが 来るのを恐れたのか。ともかく、俺は、王をえらく怒らせてしまったらしい。 さもなくば、軍団長自らが斥候などに出されるものか……。 『……こ、これが、へ、陛下の、一国のあるじの仕打ちですか、……!』 ホルヘが激昂した。蝋でじっくり煮た上物の革の籠手を石の床に叩き付け、蹴飛ばし、 それから俺の目の前であることに気がつき、身悶えした。縮れた栗色の長髪が、 むさ苦しく宙を舞う。……俺はいい部下を持った。俺の処遇にここまで怒り、 苦しんでくれる奴は、ほかにいるだろうか? 『言葉を慎め、ホルヘ。気持ちだけで充分ありがたい』 『ですが……』 『命令だ。俺は、行く。お前は残れ。ペレスの小隊を連れてゆく』 『軍団長殿! 恐れながら、私の部隊の方が、……』 『……優秀だ。後の戦に残しておきたいほど、な。そして、ペレスの隊の馬は あいつの性格を反映して、よく手入れがされている。しかも早い馬ばかりだ。残念だな』 なおも悔しげに歯がみするホルヘに、俺は手を振ってみせた。 『それより、一番奥の井戸にワインを放り込んでおいてくれ。バカ家老は陛下専用の 井戸なんて言っているが、なあにかまうもんか。別に書いてあるわけじゃない。 ……残り1本の酒で、兵士みんな集めてしみったれた宴会やろうぜ』 『はい、そればかりは、命に代えても!』 その、無理に笑いつつも悔しそうな複雑な表情が、ホルヘの見納めになった。 俺はお気に入りの葦毛の馬を選んだ。こいつはタフで、むらっ気たっぷりの馬だ。 のろまな兵士がうかつに近付くと、手と言わず足と言わず、すかさずガブリとやる。 大将自ら世話してやらなければいけない不遜な馬など、古今東西くまなく探しても、 こいつぐらいのものだろう。だが、なぜか俺はこいつを気に入っていた。あるいは、 自由気ままでやんちゃな性格が、俺にはうらやましかったからかもしれない。 厩舎を出ると、ペレスの隊はすでに馬場に整列して俺を待っていた。ペレスは 顔中に傷を持つ、凶悪な面構えの男だが、その実子供と馬に優しく、観察力も鋭い。 俺の葦毛――兵士から『茶色い山犬』と恐れられている――に噛み付かれない、 俺以外では唯一の男だ。実力からすれば充分に副官は務まる男なのだが、 野戦で殺し合わせるよりもむしろ斥候に向いている。 『行くぞ!』 俺たちは城を出て、森の縁を巡回した。アルファートは森の多い国で、 この城も前方を大きな森に塞がれている。部隊を急速に展開させることが 困難なので、守りづらい城だ。 『おかしいですな、軍団長殿』 ペレスが眉をひそめた。その日に限って、敵兵は姿を見せないのだ。……もし、 ここで敵に遭わなかったら。もし、俺が傷一つ負わずに帰還すれば。王は、 敵の戦意は極めて低いと判断して、そのまま進軍を続けるだろう。だが、 それ以上に我々の疲弊が限界まで来ているのだ。もし、これ以上敵の懐深くに侵入し、 そこで痛撃を受ければ、我々は退くも攻めるも能わず全滅する。 『……いっそ、味方同士で傷つけあって、敵に遭ったことにしようか』 『何を呑気なことをおっしゃる。……罠、かもしれませんに』 俺は我に返った。最後尾を守っているペレスを、俺は思わずまじまじと見つめた。 そして、そのとき俺の目に、それが映った。振り返った空に、木立の間から うっすらと細い煙が見える――。 『……敵襲だ! 全員、全速で城に帰還せよ!』 俺は馬首を返すと、力の限り拍車をかけた。馬はいななき、口から泡をこぼしたが、 気にしている場合ではない。 俺は、憑かれたように馬を奔らせた。行きに三十分かけた道のりを、 俺はその半分の時間で駆け抜けた。そして、そこには―― 轟音。悲鳴。顔を火照らせる火柱と、息をつまらせる黒い煙の悪臭。血の臭い。 石と煉瓦の城壁が、そこを守る兵士とともに崩れ落ちる。風を切る弓矢の行き交う音。 そこは、俺がさっきまでねぐらにしていた城だったはずだった。 敵は、同時に俺たちを見つけた。戦場の音にまぎれて、彼らが何を言ったのかは 聞こえはしなかった。だが、聞くまでもなかろう。次の瞬間には、石弓と短弓、 長弓からの一斉射撃が俺たちに襲いかかった。どんな距離だろうが確実に射殺す つもりだろう。鋭い音とともに、俺の鎧を矢がかすめた。だが、すべてを心得た 俺の狂暴な馬は、俺が拍車を当てる前に猛然と地面を蹴っていた。我に返った俺は叫んだ。 『全員、被害にかまわず前進せよ! これより城内の友軍と合流……』 俺は、顔がこわばるのを感じた。振り向いた目の前で、弓矢の針刺しとなった ペレスが、声も立てずにゆらりと落馬した。次の瞬間、主を失った白馬が、 悲痛ないななきとともに倒れた。馬もまた、首筋を数本の石弓に貫通されていた。 倒れ、まだヒクヒク痙攣している白馬をよそに、俺の馬はかまわず全速で疾走した。 俺の視界は、敵兵で満たされつつある。反射的に、俺は鞍にくくりつけた長剣を抜いた。 弓兵の驚愕に満ちた顔がどんどん近付いてくる。そいつらの目が見分けられるまでに接近―― 見渡すかぎり、そこは兜と剣と、槍や矛、斧のゆらめく金属の海だった。 だが、俺の葦毛は躍りあがった。最前線は退避しそこねた弓隊で、他に さしたる武器を持っているわけではなく、接近さえしてしまえば何も怖くない。 そもそも人間を何とも思っていないこの狂暴な馬は、たてがみを振り乱し、 甲高い凶悪な声でいなないて、蹄を振り下ろした。蹄鉄の下で、兵士が踏みつぶされる。 兵士に噛み付き、そのまま口でそいつを投げ飛ばす。ひるんだ兵士どもに、 俺は高い所から長剣の刃を叩き込む。凶悪な牡羊――俺の鎧の随所に施された意匠と その戦いぶりからついた綽名だ。身動きの取れない戦陣の中で、兵士どもは恐怖に駆られ、 逃げ惑った。俺は、勝手に開ける道を、ひたすら走った――たまに襲いかかってくる 馬鹿者を斬り捨てながら。悪名はあげておくものだ。 俺は、この敵の海の中で、ひたすら友軍の無事を祈った。だが、……。敵は整然と 隊列を保っている。特に、城門や城壁を破壊するバタリング部隊は、整然とその巨大な 破城槌を城門に叩き付けている。破城槌は巨大な丸太の杭で、数人がかりで城門や 城壁に叩き付け、突入経路を確保する兵器だ。大がかりなだけに、城壁から攻撃する 兵士にとっては目標にしやすい。それがほとんど抵抗を受けていないのは、もはや 城門の一つないし複数が破られたということだ。奴らは、さらに多くの突入経路を 確保すべく、せっせとありったけの城門を破壊して回っているのだ。この城は 二重壁なので、内側の壁を破る際には、バタリング部隊はあまり役に立たない。 狭すぎて、身動きがとりにくいのだ。 俺は、破られた城門から飛び込んだ。その瞬間に、二番目の城門も こじ開けられてしまった。俺は、破城槌に取りついた敵兵を背後から斬り捨てると、 敵兵の作った隙間から馬を城内に躍らせた。その瞬間、頭上で鈍い音がした。 城全体に響き渡るような振動、敵兵の慌てふためく声……怪訝に思って振り向いた 俺の視界を、ゆっくりと瓦礫が塞いでいった。数秒の意識の空白の後―― 何が何だかさっぱりわからず、俺の意識は真っ白になっていたらしい――、 もうもうと立ちこめる土ぼこりの中で、俺は城壁の上にあった見張楼が俺の背後に 崩れ落ちたことを知った。あと少しで俺は―― 『お若いの、ご帰還のようじゃな』 そこには宮廷魔術師のアルバラードがいた。やせっぽちのくせに腹と顔には 肉がたっぷりついた、奇妙な風体の男だ。彼は半分禿げあがった頭を振り振り、 ひょこひょこ近付いてきた。小さい頃に足を怪我したためらしい――おまけに、 爪先のやたら長い、変な靴を履いているためだ。普段は格子模様のローブを まとっている彼が、今日はくすんだ黒いローブを羽織っている。 『……あんたの魔法か』 『魔法……といえばそうじゃな。あんたの姿を敵の中に見つけてな。あんた、 やたら目立つでのう。あんたに一番近い第二城門をわざと手薄にしてあんたを 迎え入れたというわけじゃ。あとは、兵士に命じてあのうっとうしい見張り台を 敵めがけて叩き落とさせた、とまあ、それだけじゃがな。打ち合わせなしで あんたと見事に呼吸があっていた、というのはほとんど魔法じゃよ』 見れば、城壁の上から兵士がさかんに土嚢を落としている。 『……魔術師殿。あんたの指揮は確かに見事だが……あれは、敵に土嚢の階段を 作ってやってるようなものではないのかな?』 『その点もぬかりはないよ。あの土嚢には、土に混じって槍の穂先や折れ釘や矢尻が 混じっているのだ。おいそれとは通れん。充分、時間稼ぎにはなる。その間に、 あんた、残った兵を纏めて逃げる段取りを整えてくれい』 『だが……逃げると言っても、どこから?』 『正面からさ。この門の向こうに、わしが道を作る。どうせ、このままでは 全滅じゃ……わしに任せてみてはくれんか』 俺は、実は彼を高く買ってはいなかった。軍師としては一流だ。だが、このような 乱戦で、果たして彼の能力はあてになるのか? 彼はの魔法たるや、 奇っ怪な掛け声とともに、炊事係が顔をしかめるような弱っちい火をちょろちょろ 絞り出せる程度だ。俺はじっと彼の目を見つめた。深く落ち窪んだ彼の目には、 決意と哀願と自信と悲愴感――ともかく彼の感情のすべてが折り込まれていた。 『……お任せしましょう』 『かたじけない。このわし、一世一代の地獄の炎を、この世に呼び出して見せましょうぞ』 俺は馬を放置し、城内に走って戻った。あの馬は利口な馬だ――敵がいるときは、 決して味方に噛み付きはしない。 俺はホルヘを探した――だが、心に湧きあがる不安だけはどうしても 拭い去ることはできなかった。ホルヘが指揮を執っているならば、こんな無様な 戦にはならないはずだ……。 いくつもの階段が複雑に入り組んだ先に、この城の展望台――俺の戦闘指揮所がある。 俺は、その前まで来てためらった。二、三歩の間、廊下に踏みとどまって、 ようやく俺はその中に足を踏み入れた。 そこには重苦しい空気が流れていた。そこから見える限り、緑の森に覆われた アルファートの大地を埋め尽くす人の群れは、すべて敵兵だった。そして、 そこには……やはり、ホルヘはいなかった。アリエルとハイメという二人の若い騎士が、 そこで指揮を執っていた。 『……閣下、よくぞご無事でお戻りになられました』 『……ホルヘは?』 二人は悲痛な面持ちで、城門の一つを見つめた。そこは、さっき俺が通ってきた門だった。 『……敵襲とともに、陛下が直接陣頭指揮を執られました……最初の一撃でした』 俺は唇を噛んだ。我々は騎士・騎兵中心の部隊だ。それに対して、アルファートは 歩兵を中心とした構成の軍団を組織している。一対一なら、歩兵は騎兵に 勝ちうべくもない。だが、数を揃えやすく、ありあまる戦力で相手を圧倒するのが 歩兵なのだ。そして、騎兵は、突撃までにある程度の距離を空走することを必要とする。 奇襲を被った場合、泡を喰って騎兵を城外に送り出したりしたら―― ホルヘ。そのとき、お前は絶望していたのか? それとも、それでも何かを 俺に期待していたのだろうか? ……すまない……。 俺は、涙をこらえきれなかった。俺は、二人とは反対側の壁の方を向いた。 そこには、巨大な紋章旗――翼を拡げた火竜が鎮座する、赤い玉座をあしらった 深紅の旗が、居丈高に飾られていた。この期に及んで、旗は己の武力を高らかに誇示していた。 『……陛下は?』 『一時的に錯乱していましたが……今はお休みのようです』 『魔術師殿の魔法か?』 『はあ、まあ……背後から、あの鉄の杖で、ガツンと』 『……適切な魔法だな。だが、少々遅かったようだな』 俺はため息をついた。ハイメの金髪が、力なく揺れた。いつもは女のようにひっつめる くせっ毛が、今日は無造作なざんばら髪になっている。アリエルは、鳶色の髪を いらいらと掻きむしった。光の当たりぐあいによっては、その色はエリンカの赤銅色の髪に そっくりの輝きを放つ。エリンカ……俺は―― 『いいか。もう、俺たちの負けだ。これ以上、無駄死にする必要もなかろう。 生き残った奴を正門前に集結させろ。五分以内だ。敵が城壁によじ登ってきても、 もう気にするな。……撤退する』 二人は目をみはった。 『……できるのですか?』 『魔術師殿が請け負ったのだ。俺は信じる』 アリエルの顔が曇った。 『アルバラード殿は……多分、死ぬ気です』 『…………?』 『……ご存じなかったのですね。アルバラード殿は、ホルヘ殿の父君でした』 俺はしばらく何も言えなかった。ややあって、俺は声を絞り出した。 『……国王陛下に万一のこともなきよう、充分気をつけて用意しろ』 眼下には、持ち場を離れた兵士たちが続々と正門前に集結しつつあるのが見える。 ここまで耐えしのいだ、いい兵士たちだ。……だが、魔術師殿の魔法いかんによっては、 彼らには陛下を守る肉の盾となってもらうより他にない。 俺が駆けつけた時には、兵士はあらかた集まっていたようだ。 『これで全員か?』 『はい、将軍閣下』 俺は、驚愕の感情を微塵も見せぬように、事務的に訊いた。ハイメもそれを 理解しているらしく、事務的に答える。……それほどまでに兵士の数が激減していたのだ。 通常、城を守っている方が攻めるよりも安全なはずだから、内心では誰もが意気消沈していた。 『そろそろ、客席は満席のようですな』 頭上から、おどけた声が降ってきた。偉大なる宮廷魔術師、五つの地獄の炎の支配者、 アルバラード殿だ。無論、全員を励ますつもりなのだろうが、ここまで打ちひしがれた 集団にその声では、逆効果だ。 『皆々がた、ご無事で何より。あいや、この疲れる戦も、今日この日、今をもって 終了ですぞ。私めが責任を持って、皆々がたを国元へ送り届けて進ぜよう』 だが、兵士たちは日頃から魔術師というより道化師に近い彼の言動に慣れていたので、 にわかには――いや、誰も信じようとはしなかった。俺も、危うく疑問の声を 投げそうになり、慌てて押し殺した。かわりに、やんわりとたしなめてみた。 『魔術師殿、どうでもいいが、そんな大声では、城外の敵に我々の位置を 察知させるだけではないのか?』 だが、魔術師殿は城壁の上で、大仰にローブを振って高らかに笑ってみせた。 『なんの、フェリクス殿。我が魔法の力はここへきて究極まで研ぎ澄まされて おりまするぞ。……今、この瞬間にも、城の外と中はわしの力によって完全に 隔たっておりまするぞ』 それに気がついた者たちは、黙りこくった。やがて、全員がそれを理解し、 その場は水を打ったように静まり返った。……そう、この壁を隔てて、すぐ向こうまで 敵は迫ってきているのだ。だのに、喚声はおろか、物音ひとつ聞こえもしないのだ。 『……魔術師殿の、魔法か……?』 俺の声に少なからずこめられていた畏敬の念に、魔術師殿は大いに満足していたようだ。 彼はうれしそうにうなずくと、さらに複雑に両手を動かした。ごてごてと いろいろな飾りを付けた杖が、華麗な軌線を描いて宙を舞った。一同はどよめいた。 一瞬にして壁が透け、向こうの様子が大写しに映し出されたからだ。 『心配はいらぬ。我が手並み、大船に乗ったつもりでご覧じあれ』 壁の「絵」に、数人の騎士が現れた。全員馬を失っており、徒歩でこそこそと 表の様子を伺いながら、物陰をつたってゆく。……俺とアリエル、ハイメと国王だ! 俺は目を丸くした。思わず、彼らがこっちにいるか確認する。見れば、未だ 気絶したままの国王をのぞいて、全員がきょろきょろ同じことをしている。 『いたぞ!』 一行は、敵に見つかったようだ。彼らは算を乱して逃げ出した。その逃げっぷりたるや 狼狽丸出しで、みっともないことこのうえない。だが、追うアルファート兵も、 その常軌を逸したスピードに、なかなか追いつけない。 『なかなかいい逃げっぷりだぞ!』 『逃げろ逃げろ!』 兵士たちはこの滑稽な追いかけっこに、立場も身の安全も忘れてやんやと 囃し立てている。そのうち、相当な人数の敵兵士が群がってきたころ、 彼らは突然爆発した。紅蓮の炎の中で燃える仲間をなすすべもなく見守っていた 彼らの中で、突然声が上がった。 『だまされるな! これは陽動だ!敵は正門に陣取っているぞ!』 その声は、多分アルバラードが作り出した幻覚だったのだと思う。だが、 そんなことを知る由もない敵兵は、第二の罠めがけて突進してきた。 『よいですか! これが脱出の唯一の機会ですぞ!ご無事で、……』 轟音。絶叫。閃光。次の瞬間、それは俺の五感をすべて奪った。そして、 目の前にはがらんとした空間が開けていた。間抜けなほど平和な空の青、 そしておおらかな地面の褐色。広範囲にわたり崩れた城壁は、飴のように融け、 ぐにゃぐにゃにねじ曲がっていた。そこには、敵など一兵たりともいなかった。 そこは、滑稽なまでに平穏に、平和に、俺の目には映った。 全軍は何かに押されるように、進軍を開始した。馬の足音と、ぜいぜいうなる 呼吸の脈動が鞍を震わせて、俺は初めて気づいた。それは、死滅した世界の平穏だった。 ……魔術師殿、め! 俺は怒りにすら似た感情を、やっとの思いで胸の内で 押し殺した。五つの地獄の炎の支配者だと! よくもまあ、名乗っていたものだ ――悪びれもせずに! 奴は、本当に地獄の火炎を地上に呼んだのだ――自らの命と 引き換えに! あれだけいた敵兵は、おそらく……俺は息がつまるような恐怖を感じた。 文字通り、だ。多分、彼らは一瞬のうちに蒸発して――そして、この俺の吸っている、 くすぶる淀んだ空気は……。俺の周囲では、兵どもが盛んに反吐を催していた。 この異臭に息がつまった者、そして――それに気づいた者。それでも全軍は、 通常行軍速度で進軍していた。今は余計なことなど考える暇はない。 故郷へ帰ること――それだけでいいのだ。 『敵襲!』 そして、敵は襲ってきた。蒸発した友軍の惨状から立ち直り、残存兵力をまとめて 復讐戦を挑む気らしい。そして、それでもなお敵の方が圧倒的に大勢だった。 『全軍紡錘陣形を取れ! 密集して耐えしのぐ! 余計なことは考えるな! 故郷の家族のことだけを考えろ! 生き延びろ!』 俺の叱咤とともに、全軍は紡錘状に布陣した。皮肉にも、この陣形だけが今回の 俺の戦のまともな成果だった。 『全軍、三舎速だ!』 紡錘陣の前衛となったハイメと、殿軍となったアリエルが同時に叫んだ。一舎は 通常行軍速度における一日の行軍距離を示しており、これは陣形を保ったまま 実現しうる最高の速度である。 『目前の敵のみを切り捨てよ! あとはかまうな! 手柄など、もはや必要ない! 被害にかまわず前進せよ!』 ハイメの甲高い声が、全軍を震わせた。彼は参謀席でこそ冷静で無口な男だが、 ひとたび戦場に出れば、阿修羅のごとき戦の鬼と化す。その華奢でなよっとした 小柄な風体とは裏腹に、前線兵士よりも突出して敵を刈る、狂戦士となるのだ。 伝説の殺戮小鬼「レッドキャップ」や人食い鬼婆「ブラックアニー」に なぞらえられるのも無理はない。ある意味、彼は「凶悪な牡羊」の俺以上に 敵に嫌われているかもしれない。事実、自分の言った「眼前の敵のみ」はどこへやら、 当たるを幸い、手当たりしだいに敵を殺している。その愛剣も、鎧も、 金色のしなやかな髪も、華奢な身体のすべてが赤く染められてゆく。 突然、俺の脇で荷物を積んだ馬がわめきだした。……いや、俺は、 この兵士たちが誰を守って戦っているのか、ようやく思い出した。 『陛下、ご無事で』 『お……おお、し、しろ!』 王は錯乱状態だった。わけのわからぬ、だが確実に俺の神経を蝕むうわごとを、 ただひたすらぶつぶつ続けていた。俺は魔術師殿を見習って再びこの邪魔者を 殴り倒そうとしたが、やめた。……やはり、魔術師殿のそれは魔術だった。 鉄の自制心がなくば、適当な手加減などできはしない。俺はことさらにそれを 無視すると、背後に視線を回した。 そして、俺は―― 俺の目では、どうしてもアリエルの姿は捉えることができなかった。 騎兵の三舎速に対して、敵の歩兵の分厚い層は、執拗に食らいついていた。 敵は、極限まで防具を薄く、そして一撃の威力のある武器を装備した 軽装歩兵の部隊だった。これが有名なアルファートの 「ブレスト・アンド・サーコート」部隊か……極限の装備で、ごく短時間だが 騎兵に匹敵する機動力と突進力を発揮する、驚異の歩兵隊。とりわけ、 森林と起伏の多いこの地方では、歩兵の利点をも失わない彼らは、ほぼ無敵である。 騎兵は一戦闘行動を終えた後で再配置するまでに時間がかかり、かつ脆い。 敵に突入、多大な被害を与えつつも全滅、などという醜態はざらに聞く。 『アリエル!』 俺は叫んだ。それが虚しいことであることは承知していたが、それでも 叫ばずにはいられなかった。 『アリエル!』 俺はやりきれなかった。部下がぼろぼろ死んでゆくこんな戦だが、それでも やめることはできなかった。それから一日と半分、全軍は三舎速進軍を続けた。 最寄りの味方の城にようやくたどりついたとき、口を開こうとするものは 誰一人としていなかった。あのハイメでさえ、半分昏睡状態で進軍を続けていたようだ。 ……そして――。 * * *