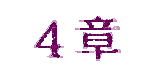
急造りの陣地の土嚢の陰で、騎士が矢傷にうめいている。介護兵も従卒もおらず、 手当てすらもままならない。どのみち、鏃が奥深く動脈を両断している。 止血帯がみるみるうちに血を吸って赤くぶよぶよに膨れ上がる。「止血虫」と呼ばれる、 要するにウジに傷口を食わせたところで、手遅れだ。緩めた鎧の中で、皮膚が張りを失う。 急速に失われてゆく体温。荒げる呼吸もだんだんとか細いものになり――命の糸は、 突然にぷっつり途切れる。ひとつの死が、またひとつ戦場の点景に加わる。 長にはなにもできない。己の無力さをただ噛みしめながら、せめてもの涙を流してやるだけ。 「アベル……」 「はい……」 答える参謀長の声にも、いつもの豪快さはない。むさっくるしいほど手入れの悪い髭からも、 いつもの雑草じみた生気は感じられない。 「お主とは……何年だったかなぁ」 しばらくその髭は、力なく震えていた。しばらくしてから、やっとのことで髭は か細い声を絞り出した。 「……あれは、この前に丸耳どもが侵略してきたときですな……あんたに惚れ込んで、 五つ沼の村からこの村に越してきたのが、ちょうど四十年前でしたかな。……あれから、 いろいろありましたなぁ……」 「お前が肩に矢傷、儂が脇腹に刀傷、仲良くやつらの捕虜になって……あの時は、 死ぬと思った……丸耳ってのはひどいやつらだった」 「……あぁ。無抵抗の年寄りを平気で殴り倒す、縛り上げた上で剣でいたぶる…… 味方が助けに来なければ、あるいは……な」 「本当に心底ひでえやつらだったが……ひでえのは俺たち長耳……」 「……森に生きるはずのアールヴが……」 長はあたりを見渡した。そこは、既に灰の海であった。陣地に築かれた土嚢。 それは、戦の後、どちらが勝つにしてもいずれかの勝利者が森を蘇らすための 腐葉土である。その灰と合わせたとしても……この森は復活できるのだろうか? 森がなければ、アールヴは丸耳と何ら変わるところがない。慈愛遍く森の女神の恩寵を 自らかなぐり捨て、アールヴにどうやって生きろというのだ? この戦は、もはや……長は思わざるを得ない。コーバルスまで引きずり出し、 我々はどこまで行ってしまうのだろうか? 感傷にふけっていた二人が目を上げると、そこにはアールヴの少女が立ち尽くしていた。 黒い髪、黒い瞳……その熟れつつある蕾のような華やかな少女のことを、 二人はよく見知っていた。だが、今日ばかりは様子が違った。 「ナディーヌ! どうした、逃げたんじゃないのか」 彼女は泥まみれで、髪などモップのようにぐしゃぐしゃだ。服はもう雑巾よりも目が荒く、 その穴からのぞく肌のあちこちは擦過傷だらけだ。なによりも、彼女の瞳に生気がない。 「ナディーヌ、まさかお前……シャナラの奴らに、そのう……ひどい目に遭わされたのか?」 無神経な参謀長でも、さすがに直截的な表現は避けたようだ。 彼女の目に、涙がにじんできた。 「…………」 長はナディーヌが、先に落とした家人よりもしぶとく家に粘っていたことを思い出した。 ヒューゴーなら無事だとあれほどくどく諭しておいたのに……彼女は陣地の中に 走ってきた。参謀長は矢から彼女をかばおうと立ち上がった。 「いかん、ナディーヌは……!」 参謀長はナディーヌを抱きかかえた。衝撃で彼女の服が破れ、背中に刻まれた 鞭の痕が参謀長の目に映った。思わず彼は目をそむけたため、参謀長は 彼女の背中の中央にある、その致命の刺し傷を見ることはなかった。 「ナディーヌは死んでいる! 彼女の中に、魔法の火の玉がひそんでるぞ!」 参謀長は思わず長のほうを向いた。その瞬間、彼の腕の中でナディーヌは爆発四散した。 「…………!」 衝撃は大きかった。土嚢の一部が吹き飛ばされ、騎士の何人かは炎にやられて即死した。 長は参謀長が陰になってくれたので無事だった……が、参謀長は肉片も残さず消え去った。 長は咳き込んだ。焼けた土の臭い、髪と肉のはぜる煙が鼻と喉を刺激して痛い。 この臭いが、友のなきがらの全てなのだ。 長は茫然としていた。長年の友人が、文字通りこの世から消え去ったのだ。 土嚢の陰から、節くれだった手がにゅっと伸びてきた。その手には禍禍しい 鋭く長い爪が光っている。続いて禿頭が、らんらんと光る眼が、そしてしわくちゃで いぼだらけの顔、乱杭歯が剥き出しになった口がのぞいた。シュウシュウという 動物じみた吐息に気づいた騎士が剣を抜いたが、遅かった。たちまち二、三匹のコーバルスに まとわりつかれ、騎士は地面に倒れこむ。 分断された前線を呼び戻すには、既に手遅れである。長が死ねば、この戦いは終わりだ。 あるいは、ヒューゴーがこの村を再建するやもしれない。だが、そのためには あのサダルメリクを、悪くても相討ちで仕留めておくことが不可欠なのである。それに…… ヒューゴーがナディーヌを喪ったと知ったら、彼が立ち直るのはいつの日のことになるのだ……? 一匹のコーバルスが、乱杭歯の間から血と涎の糸を滴らせ、長のほうを向いた。その目には、 貪婪な殺戮への渇望がなみなみと湛えられていた。じめっとした、穴居動物特有の むっとする臭いが、灰と血の臭いに混じり、鼻腔を疲弊させる。そう、ここは五感で触れるもの 全てが灰と血で彩られた、地獄だ。 「人間……爆弾……」 もう、勝てない。長は思った。そう、奴はは死人を爆弾にして突入させるような男なのだ。 そういう思考ができる男……そんな奴が、敵なのだ! 時代は変わった。騎士と称する 馬鹿者が無謀に突撃すれば戦闘と呼べる、華やかな時代は終わったのだ。 神はこの地上を見放した。人間の死は、単に数字に置き換わる。これからの戦では、 丸耳も長耳も含めて幾万もの人が意味もなく、わけもわからずに殺されるのだ。もはや、 神のみか人にも看取られることなく、たったひとりで。 長は恐怖した。もう、いい。ここで儂は終わろう。これ以上……儂は何も見たくない! 見るべきものは、充分見た! コーバルスがその猿臂を振りかざした。長は安堵した。これで儂は死ねる。 友のもとに逝ける。もう、何も見なくてもいい! 長は目を閉じた。これで、いいのだ……。 「たかが洞窟のテナガザルが、父上に何をするか――――っ!」 刹那、コーバルスは断末魔の悲鳴をあげた。頭上から降ってきた声の主によって、 コーバルスは胴をすっぱり断ち切られ、絶命したのだ。血を吸ったブレードロッドは、 喜々として日の光にきらめいている。横合いから、巨大な鳥の顔が血まみれの獲物を かっさらい、嬉々として呑みこむ。気づいたコーバルスが、一斉に甲高い悲鳴を上げた。 それを片っ端から、巨大な鳥は丸呑みにしてゆく。グリフィンにとって、森に数多く 生息するコーバルスは、格好の餌なのだ。グリフィンだけではなく、竜も……要するに、 アールヴは戦う目的だけでそれらを飼っているわけではないのだ。 「愚か者! なぜ逃げなかった!」 長はヒューゴーを怒鳴りつけた。怒鳴りつける一方で、長は胸が高鳴るのを感じた。 もしかして……! 時代は変わらないかもしれない。無差別な殺戮が愚か者の殺しあいに とって変わるということはないかもしれない。それを食い止めるのがヒューゴー…… この長の自慢の息子かもしれない! 一方で、これはヒューゴーの復讐なのだろうかと 恐れもした。ナディーヌを救えなかった罰として、なかなか殺してもらえないという……。 ヒューゴーは父の方を向いた。そして、ニッと笑った。 「父上。こいつはここに残しておきます。では」 そして、ブレードロッドを手に駆け出した。漆黒の長髪と真紅の血飛沫が彼の進路を彩る。 「黒い血飛沫」の異名のゆえんたるゆえんのものだ。 彼は古い騎士だ。その若さにもかかわらず、思考回路は古い騎士だ。長は安堵した。 愚かな騎士らしく、敵の大軍の中に単騎突入してゆく男なのだ。 ヒューゴーになら……ヒューゴーになら! 長はこれほど嬉しいと思ったことはなかった。 止められるかもしれない!