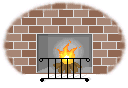「雨を降らせてくれだと、馬鹿なことを言うな。今月の分の雨降りはもう終了している。」
「一時間だけでいいのです、気象局長。お願いします!」
「ヨシノ君、優秀な気象官の君なら、街に雨を降らせるのにどれだけの資源と費用が必
要か、知らないわけではあるまい。」
「わかっています。費用は私の給金から差し引いて頂いて構いません。」
「何故急に、しかも冬至祭で街が賑わっているこの夜に、雨降りが必要なのだ?」
「確か局長は、故郷の星の生まれでしたよね?」
「……もう五十年も前のことだ。それが何か?」
「『ホワイト・クリスマス』という言葉が故郷の星にあったのを、憶えていませんか?」
「彼女がはじめて、気象官としてこの移民星に赴任してきた時、言っていたのです。」
「……いつか、この移民星に、雪を降らせることができたら、みんな喜ぶだろうな、と。」
「……馬鹿馬鹿しい。そんな無茶な試みに、貴重なこの星の資源を使わせるわけにはい
かない。」
「局長!」
*
帰り道の街角は、冬至の訪れを祝う人々で、いつもよりも賑わっていた。
いつもより豪華な夕食を楽しみに出かける家族連れ、特別な夜を二人で過ごす、恋人達。
両側に立ち並ぶ店先には、ささやかながらも、色とりどりのあかりが燈され、冷たい
空気の中で明滅している。
一年で一番永い夜の、僅かなひとときに。
気象局長は、先程の会話を想いだしながら、ふと澄んだ夜空を見上げた。
「クリスマス」と呼ばれる、ずっと昔から伝わる、移民星の冬至の祭り。
赤い服装に身を包んだ老人が、子供達にプレゼントを配る習慣は、今でも残っている。
でも、遠い昔、故郷の星で、この祭りにどんな由来があったのか、どんな想いでこの
祭りを祝ったのかを知るものは、もう、ほとんどいない。
それでも、つつましい移民星の暮らしの中で、人々は今でもこの冬の夜を祝い続ける。
りん、りん、りん。
物思いを破るように、不意に、高く澄んだ音色が、くるくると転がってきて、つま先
に当たった。
びっくりして足元を見下ろすと、緑色の取っ手に銀色の花を幾つかつけた、小さな鈴
があった。
そっと拾い上げると、空気よりもひときわ冷たく、りん、と音を奏でる。
ぱた、ぱた、ぱた。
その鈴の音を追って、小さな足音が、気象局長の前に走ってくる。
「この鈴は、君の?」
道端に転がった鈴を、慌てて追いかけてきた女の子が、まだ白い息を切りながら、頬
を真っ赤にしてうなずく。
毛糸のマフラーについたふわふわした球と、黒いおさげの髪が、ちょこんと揺れる。
「大事に、するんだよ。」
ちいさな手に、緑色の取っ手を差しだす。
受け取ったその手は、大切そうに取っ手をぎゅっと握ると、軽やかに賑やかな街並へ
と駆け戻ってゆく。
「ありがとう、メリー・クリスマス!」
女の子の後ろ姿に揺れる、白いマフラーの飾り玉に合わせて、りん、りん、りん、と、
澄んだ響きが駆けてゆく。
冬の夜に響く鈴の音色は、懐かしい、何かに似ている、気がした。
「ヨシノ君は、まだいるかね。」
気象局長は、水色の通信板を取りだして、若い気象官をコールする。
「……一時間だけだ。費用は君の給料から差し引いておく。」
『……十二回払いでお願いしますよ、サンタクロース。』
通信板の先から、こぼれるような言葉と、笑顔が、届いた。
*
星間旅客船の離陸予定は、午前0時。 それは、ちょうど、冬至の祭りの終わる時刻。
元気象官の娘は、空港の硝子ごしに燈る、賑やかな街灯りを見ながら、そんなことを
思っていた。
気象官として初めて赴任した、この乾いた移民星。
それから今まで、まるでこのお祭りのように、賑やかに、あわただしく時が過ぎてい
ったような気がする。
そうして、そんな特別な時は終わりを告げ、私はまたこの移民星から、元の通りに去
ってゆく。
そんな想いを浮かべながら、ほっと、硝子窓に息を吹きかける。
娘の薄く曇った硝子の向こうに、不意に、白い粒子が、ひとつ、舞い降りた。
ひとつ、また、ひとつ。
硝子窓に当たって、すうと、溶けて消えて。
「え……?」
娘は、慌てて空港から、硝子の外の空気へと飛び出した。
身を切る夜風に震えながら天を見上げると、遠い群青の空の彼方から、幾つも、幾つ
も降りてくるのが見える。
ちいさい、あまりにもちいさい、雪の結晶が。
風にさらされながら、しんしんと、音のない音を奏でながら、雪は降りてくる。
周囲の、人が営む灯りに、ちらちらと輝きながら。
それは大地に降りても、それを白く覆うこともなく、ただ消えて還ってゆく。
明日には残らずに、冬至祭のこの夜の、この瞬間を、静かに優しく、祝福するように。
瞬間にいくつも浮かんでは、消える、言葉のように。
「ヨシノ君……。」
娘は、夜天を見上げたまま、そっと、つぶやきを返した。
*
氷の結晶が夜風に舞う街の中、夜空からの贈り物にざわめく街の中を、若い気象官は
駆けてゆく。
弾む息が、夜気にふんわりとその軌跡を残してゆく。
実際のところ、若い気象官の理論と技術では、可能性は五分にも満たなかった。
でも、ほんの小さな粒子だけど、触っただけで消えてしまう、はかない結晶だけど。
確かに、この星に雪が舞い降りていた。
ひとつ、ひとつ。冬至祭の街の灯りに、真白く輝いて。
その小さな白いひとひらに、勇気と、言えなかった言葉を、込めて。
移民星の、このささやかで特別な夜が、終わりを告げる前に。
星間旅客船が、この小さな星を飛び立つ前に。
クリスマスの街を、若い気象官は駆けてゆく。
*
りん、りん、りん。
まだ雪の舞う街角で、片方の手を母親に弾かれながら、女の子は小さな緑の鈴を鳴らす。
「ねえ、お母さん、この白いふわふわ、何だか、鈴の音に似てるね。」
りん、りん、りん。
祝福するように、やわらかく鳴る鈴の音と、静かな雪の調べに包まれて、一番永い夜は、
まだ続いてゆく。
やがて、またいつもと変わらない、朝が、訪れるまで。
|