旅の間のペリーヌ母子は割合平穏な日々を送っています。ペリーヌの工夫によるインド衣装での写真屋の商売が結構うまくいっていた為、決して豊かではないものの経済的にも比較的安定していたようですし、なによりもマロクールへ行くという目的をしっかり持っていました。この時点では少なくともペリーヌはビルフランと両親の間の葛藤などは知らずにいましたし、祖父に会える日を楽しみにしていましたもんね。
勿論、行く先々で様々な事件が起こり、危険な目に遭ったり、トラブルに巻き込まれたりもするのですが、比較的平穏で幸福な日々ではなかったかと思います。
母と旅をしていた間のペリーヌはとても明るい表情をしていました。後半は暗い表情を見せることも多かった為、余計にそれが際立っていたように思います。母と一緒だった頃のペリーヌは凄く子供っぽく見える部分が多分にあって、後半の大人びた雰囲気になったペリーヌとは別人のように思える時もあります。
第一話から順番に見て行くとさほどでもないのですが、最終話まで見て再度第一話に戻ると結構強くそれを感じます。顔も前半と後半では随分違ってますしね。(^_^;)
彼女らの旅に影が差し始めたのはアルプス越えによる無理がたたり、母が病に倒れた辺りからでしょうか……。ペリーヌは一人で写真の商売をしようとしますが、子供では誰も相手にしてくれず、二人は収入の途を絶たれてしまいます。
漸くパリに到着した頃にはもう殆どお金は残っておらず、家馬車や写真の道具、そして大切なお友達のように接していたロバのパリカールまでも売りに出さざるを得なくなってしまいました。しかしそうして得た僅かなお金も母の医者代や薬代であっと言う間に消えていってしまいます。マリはこのままではどうしようもなくなることを悟り、マロクールへの旅立ちを決意しますが、その時には彼女の体は到底そんな旅に耐えられる状態ではなくなっていました。
「神様、どうかこの哀れな母親の願いをお聞き届け下さい。あの子をこのパリでたったひとりぼっちにしてしまうなんてことだけはしないで下さい。」
マリの祈りにはまだ13歳にしかならない子供を残してこの世を去らなくてはならなくなった母親の子を思う強い思いに満ちています。
年端もいかない子供にとって親の庇護をなくしてしまうということは極めて厳しい境遇に置かれることになってしまうことは想像に難くありません。
実際、マロクールへ向けてひとりぼっちでの旅を始めた時のペリーヌはひどく弱々しく頼りなく感じられるような面があったように思います。意地悪なパン屋のおかみさんに贋金だと言われてなけなしの五フラン銀貨を巻き上げられた時など、特にそれを強く感じました。
母と一緒にいた頃ならペリーヌはあんなに簡単に逃げ出したでしょうか? 商売敵の二人組の写真師たちにも食って掛かってやりこめたり、時に気弱なことを言ってしまうマリをいつも励ましていたのはペリーヌでした。その頃のペリーヌを思い起こすともう少しパン屋のおかみさんに食い下がって激しく抗議していてもおかしくなかったのではないかと思うのです。
しかし周囲の冷たい目に耐えきれず逃げ出してしまったペリーヌ。母を亡くしてひとりぼっちになってしまった心細さ、そしてペリーヌの心に生まれた不安と怖れのようなものがあのような反応になって現れていたのではないでしょうか。
旅をしている間はどちらかというとマリの方が頼りなく感じられることが多くて、ペリーヌはしっかりした娘という印象が強かったのですが、母という大きな後ろ盾を持っていたことの安心感があったればこそ、ペリーヌは明るく自由にのびのびと振る舞うことが出来たのではないかと思うのです。
マリの祈りも空しく、やがて天に召される日がやってきます。マリもそれを自覚してペリーヌを枕許に呼び寄せて、これから行こうとしているマロクールに住む祖父が決してマリやペリーヌを歓迎しないであろうことをペリーヌに告げます。そして、
「おじいさまもはじめはあなたに冷たく当たるかもしれないけど、そのうちにあなたが素直で正直な子だと判って好きになってくれます。」
「人に愛されるにはまず自分が人を愛さなくては。」
と、いう言葉を残して静かに息を引き取ります。
ここがペリーヌ物語の前半のクライマックスだった訳ですが、マリの最後の言葉は物語のこれからの展開を暗示しています。実際にペリーヌは最初はビルフランに孫であることを告げられずにいましたが、やがてビルフランも孫とは知らないままにペリーヌが好きになり、そしてペリーヌは最後に幸せを掴みます。
娘をこの世の中にひとりぼっちで残して逝ってしまうのはマリにとってどんなに不安で心残りなことだったでしょう。いくらしっかりしていると言ってもまだ13歳にしかならない少女なのですから……。
しかしそれと同時に自分の育てたペリーヌならば、いつかきっと幸せを掴むことが出来るとマリは確信していたのでしょう。
「ペリーヌ、お母さんには見えますよ。あなたが幸せになった姿が……。幸せになりますよ、ペリーヌ」
それまでは娘を一人残していく不安感で心が一杯だったのが、この言葉を言った時のマリはなんだかとても安らかな表情をしていたように思います。死の瞬間、マリの魂は時空を越えて未来を垣間見たのかも知れません。そして、
「お父さ〜ん、おかあさ〜ん、私幸せよ〜、安心してね〜。」
と、ペリーヌが最終回に丘の上で叫んだ言葉が耳元に届いていたのかも知れない、なんて考えるのはちょっと想像が飛躍し過ぎてるでしょうか……。
「人に愛されるにはまず自分が人を愛さなくては。」
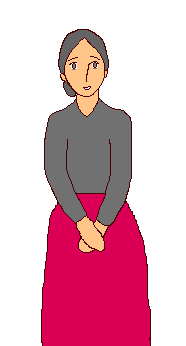 と、いう台詞は第21話の死の直前だけではなく、実は第9話でも同じことをマリは言っています。ペリーヌがロッコとピエトロという二人組の写真師をやり込めたことに対して、その夜、マリが「人にはもっと親切にしなくては」と教え諭す場面ですね。マリにとっては座右の銘のようなものだったのかも知れません。
と、いう台詞は第21話の死の直前だけではなく、実は第9話でも同じことをマリは言っています。ペリーヌがロッコとピエトロという二人組の写真師をやり込めたことに対して、その夜、マリが「人にはもっと親切にしなくては」と教え諭す場面ですね。マリにとっては座右の銘のようなものだったのかも知れません。そのあと、マリは写真機を盗みにきたロッコとピエトロを庇おうとしました。ペリーヌは説教された時にはしぶしぶ納得したという感じではなかったかと思うのですが、その後のマリの行動には深く感銘を受けたようです。
このエピソード自体はきれい事過ぎるような感もあるんですが、いろいろなエピソードを通じて、時には優しく時には厳しくペリーヌを導いていこうとするマリをペリーヌは心から尊敬し、愛していて、そして誇りに思っていたんですよね。
「お母さんはおじいさまの考えておられるような人ではありません。お母さんはとても優しくて頭のよい、そして大変きれいな人でした。」
「そうか、そうだったろう、お前をこんなしっかりした娘に育て上げた人だ。きっと立派な人だったに違いない。」
第50話でペリーヌとビルフランの間に交わされた言葉です。母を尊敬し、敬愛していたペリーヌにとってビルフランが母に対する考えを改めてくれたことは自分のことと同じくらいか、もしかしたらそれ以上に嬉しかったに違いありません。
前半の旅の部分は原作にはないアニメオリジナルのストーリーなのですが、マリの人となりを描いたことによってペリーヌの母への想いがより鮮明になり、物語に深みを与える役割を果たしていたと言えるでしょう。