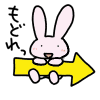5.続くらす♪
で。
わかった?なっとく♪なんて書いてみたものの
これだけでわかるわけないよね(笑)。
プログラム的には、クラスというのは変数の型だと思ってもらえれば
だいたいあっていると思うの。
というか記述もまったく変数宣言だし。
C言語なんかだと数値型の変数の宣言で、
int a; /*int型の変数 a の宣言*/
なんて書くよね?
構造体なんかは、
struct MyuStruct {
int m_intValue;
char m_charValue;
};
なんていう型宣言をしておいて、実際に使用するところでは
int main( int arvc, char* argv[] ) {
struct MyuStruct s; /*MyuStruct型の変数 s の宣言*/
......
}
なんて書くよね?
C++でのクラス宣言はこれとまったく同じなの♪
(もちろんJavaでもおなじ仕組みだけど)
class MyuClass {
public:
int m_intValue;
char m_charValue;
....
};
なんていう宣言をしておいて、
int main( int arvc, char* argv[] ) {
MyuClass c; /*MyuClass型の変数 c の宣言*/
......
}
なんていうように使うの♪
で、ここで宣言された変数 c はMyuClass型のインスタンスと呼ばれるの♪
そんなわけで前節ではクラスは定義だって書いたけど、
プログラミングのとくいなみんなは、
クラスは型。
インスタンスは変数。
って覚えてね。