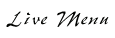G3' 05 Japan
Joe Satriani / Steve Vai / John Petrucci
|
|
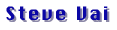
ペトルーシの演奏が予定より5分ほど”押し”てしまった為(各人の持ち時間は一様に45分)どうなるかと思っていたら、その後の機材セッティングは”巻き”で行われたようである。 所定の20分が15分程度に短縮された為か、トイレから戻るとすぐにステージ脇からギターとベースの音が聞こえてきた。 どうみてもギターテクニシャン、ベーステクニシャンが調整の為に弾いているようには思えない程の音量とテクニック。人の声をギターやベースで表現するというあの懐かしき「Yankee Rose」のイントロを再現しているのだ。 客席はそれに煽られるように大歓声の中、一斉に立ち上がる。 まさかセッティング中にオールスタンディング状態になろうとは思いもしなかった。 このパフォーマンスに急かされるようにセッティングは急ピッチで進められ、半ば強引に終了。 それを待っていたかのようにヴァイを中心にメンバーがステージに登場。最後には真打ち登場とばかりに真紅の皮パンも眩しいビリーシーンが姿を現した。 今回のヴァイのバンドはベースにビリー・シーン、サイドギターにデイブ・ウェイナー、サイドギター&キーボードに名手トニー・マカパイン、ドラムがジェレミー・カールソンという布陣。 トニー・マカパインなんて個人でG3に参加できるぐらいの逸材。それにバンドのアンサンブルでキーボードを弾くなんてのも勿体ないぐらいの腕前である。(かっては自身のアルバムでショパンのエチュードをピアノで披露している。) それにビリー・シーンである。 人気を決定づけた「デイヴ・リー・ロスバンド」の超絶弦楽二重奏コンビが時を越えて、こうして同じステージに立っている事に私は感慨を覚えた程である。前述した「Yankee Rose」のPVの映像が脳裏を掠めたのは私だけではないだろう。 これからのライヴを象徴するかのような壮大なギターイントロ(「I'M BECOMING」)はサスティナーによる効果音とアーミングで我々観客の心を鷲づかみするには充分であった。 だが、それはこれから始まる煌びやかで激しいロック”ショウ”の序章にすぎず、次の「AUDIENCE IS LISTENING」において”Vai ”弾頭はいきなり爆発した。 「AUDIENCE IS LISTENING」と言えばデイヴ・リー・ロスバンド脱退後のメジャーソロデビューアルバム「Passion & Warfare」にも収録されたライヴでは定番の曲。しかし、その凄さは生半可なものではなかった。 髪を振り乱し、狂ったように弾くヴァイとビリー。 なんと途中にはヴァイがビリーに覆い被さるような形でベース版「二人羽織」までやって会場は絶叫の渦に包まれた。ビリーの「二人羽織」ベースは今に始まった事ではないが(Mr.Big時代にも来日公演でvoのエリック・マーティンと行った事がある。まだ二人の関係が悪化する前の事だろうか)このコンビは夢にまで思い描いていただけに、冒頭からのスーパーサプライズな出来事に私は涙した。 ヴァイとビリーがステージの舳先まで乗り出して客に弦を触らせるという荒技まで飛び出した後、ドラムのリズムに乗ってヴァイが絶叫する。 「コンニチワー」 只のお決まりの挨拶なのにヴァイの勢いに乗せられ我々も絶叫でレスポンス。 メンバー紹介でもやはりビリーには一番の歓声があがっていた。 そして再び、ヴァイが絶叫する 「BUILDING THE CHURGE !」 「BUILDING THE CHURGE !」 マカパインのキーボードのフレーズをユニゾンで妙技、両手タッピングで応えるヴァイ。 最新アルバムに収録された「BUILDING THE CHURGE」は、時に師匠筋のサトリアーニぽさも感じさせるスペイシーさも併せ持つが、やはりどこを切ってもヴァイ印が現れるフレーズの数々。 曲の最後には弦をピックではなく”空手チョップ”で叩いて音を出すという格闘系の技まで飛び出す、正しくヴァイのエンターテイナーぶりが発揮された瞬間であった。 「BUILDING THE CHURGE」の後、間髪入れずに始まった曲(「THE REAPER」)もどこか耳馴染みのある曲である。(多分、映画「ビルとテッドの地獄旅行」でも披露されていた曲だと思うが....) この曲でもヴァイの遊び心−すなわちそれは高度なテクニックに裏打ちされたものであるのだが、アームを使って不協和音の如く響く効果音、タッピング、スライド、そしてギターのピックアップに向かって叫び声を上げ音を拾わせる.....等々。 ヴァイにとって”もうひとり”の師匠であるフランク・ザッパの影響も匂わせた曲であったがヴァイらしいメロディラインやフレーズも満載であった。 煌びやかな曲の後は一転し、静かなキーボードの調べが会場を包む。 「My good firiend ....Yoshiko」と意味深なヴァイの紹介で始まった「WHISPERING A PRAYER」はディレイやコーラス、ワウペダルが効果的に使われた曲だ。 それにボリューム奏法?を屈指しながら微妙な響きをアームで調整しメロディを奏でていく。 フィードバック?を得る為に微妙に立ち位置を変えるという細かさも印象的であった。 メロウな「WHISPERING A PRAYER」が終わると、スポットライトがビリーを捉え、それに呼応するかのように猛烈な早弾きを披露する。 我々、観客も歓声でその演奏に賛辞を送るが単独ライヴでない為か、ソロタイムは意外と短かい。 やがて全てを遮るようにヴァイの超絶タッピングのフレーズが鳴り響くと、一拍おいてビリーがそのフレーズにユニゾンで被せていく。まさしくあの「Shy Boy」のイントロと同じだ。 いや、私は「Shy Boy」が始まったのではないかと一瞬、勘違い、期待してしまった。 だがその「I'M THE HELL OUTTA HERE」には大きな見せ場が用意されていた。 ビリーのソロを合図に、ヴァイ、デイブ・ウェイナー、マカパインと順にフレーズを引き継いでいくというギターファンなら誰もが見たかった光景が展開される。 最後には同時にお互いが同じようなフレーズを弾き弦楽四重奏が完成する。 『壮絶』という一言では片付けられないような4人のコンビネーションに私は我を忘れてしまった。 攻撃的なプレイの数々の後はマカパインの荘厳なキーボードのフレーズとジェレミーのドラムのリズムが絡み合いながら増幅していく。 そしてヴァイがあの聞き慣れたメロディを弾き始めると歓声が一斉にあがった。 前日の公演まで全く披露されなかった名曲「FOR THE LOVE OF GOD」がここ名古屋で初めて披露されるなんて思いもしなかっただけに嬉しさも一入である。流麗と激しさを体言したかのようなメロディラインはいつでも我々の心を捕らえて離さなかった。 「FOR THE LOVE OF GOD」の長めなアウトロは正にヴァイの独壇場。折れるのではないかというぐらいアームを激しく叩き、回転させ挙げ句の果てにはヴァイが自らの舌を弦に這わせスライドするという常人では考えつかない(考えついてもやらないだろう 笑)技まで繰り出し大団円。 『聞かせる』よりも『魅せる(見せる)』を忠実に実行したライヴもこうして幕を閉じた。 私にとって実物のヴァイに会うのは1999年のサイン会以来、2回目であったが、ステージ上で見る彼は実物以上に大きく見えた。 確かにステージと客席の距離感がそうさせたとも言えなくもないが原因はそれだけではないだろう。 多分、ロックスター、パフォマーとしての”オーラ”がそうさせたと言えるのではないだろうか。 常人のレベルを超えたテクニック、いわゆる”変態フレーズ”を絡ませながらも美しいメロディラインを構築していく音楽センス、それらを最高の状態で提供していくプロデュース能力。どれをとっても秀でている。 そして今回、再認識させられたのは「人を楽しませる」という気概が全編を通して満ちあふれていたこと。 自身のパフォーマンスはもちろん、誰もが見たかった4人によるソロ回し、二人羽織、相互タッピング....全て高度なテクニックが為せる技であるが、これら全て「どうしたら(見せたら)観客に喜んでもらえるか」という意識にたって練られた結果であると思う。そう考えればヴァイはロックスター、パフォマーだけでなく”エンターティナー”であると断言出来るのだ。 ”エンターティナー”スティーヴ・ヴァイは僅か45分という短い時間、我々を夢の国へ誘ってくれたのだった。 
眩いばかりのロックショーの後は、G3の立案者、ジョー・サトリアーニの登場である。 サトリアーニは私の大好きなギタリストの一人である。それだけに思い入れも深い。 中近東的なフレーズを弾きながら穏やかに始まったライヴは、派手な演出も何もなく 拍子抜けするぐらいだ。それはサトリアーニが身につけていたステージ衣装(?)でも言えることであった。 プライベートでも使っているような帽子を被り、最近お馴染みのサングラス姿。 トップバッターのジョン・ペトルーシに迫るぐらいの普段着である。 ただ唯一、ロックギタリストとしての証を表していたのは上半身を覆う黒のTシャツに書かれたサイケデリック書体の「Cream」という文字。 いわゆるロックTシャツなのだが、これだけ世界に名だたるギタリストがステージにロックTシャツで現れるというのも珍しい。(しかし、これには理由があった。「Cream」と言っても35年前のエリック・クラプトン、ジャック・ブルース、ジンジャー・ベイカー、伝説のCreamではない。今年、再結成したRe・Union「Cream」のTシャツなのだ。当然、再結成ライヴが行われたロンドン、アルバートホールの会場でしか売っていないものである。(注:現在はネットでも購入可)しかもそのライヴが行われたのは僅か4日前だ。では何故? それは名古屋と渋谷に店を構える有名ビンテージギターショップ「Nancy」の店長が当日午前中、サトリアーニが来店した際にプレセントしたものであったのだ。店長は店のHPでも語っていたようにRe・Union「Cream」のライヴに参加したお方。 サトリアーニは前回の来日時にも来店し店長とはそれ以来、ビジネス上でも良好な関係を築いているらしい。−ただ店長曰く「プレゼントしたTシャツを着て出てきた時はひっくり返った」そうなのだが.....) また他の二人と大きく違っていたのは、トリの強みか、それとも創始者の特権か、ステージ後方の幕?にCGで作ったと思われる幾何学模様を描写していたことである。曲毎に、またはフレーズ毎に色彩豊かに模様が変化していく様は非常に美しく、その幾何学模様の上にサトリアーニの姿が影絵のように投影される効果も面白かった。 長めのイントロの後、静寂が一瞬ステージを包み観客誰もが次の展開を息をのんで待った。 1曲目は「UP IN THE FLAMES」。最新アルバム「Is There Love In Space ?」に収録されたミディアムテンポの曲である。 1曲目としては意外な選曲ではあったが、どこをとってもサトリアーニらしい音使い、メロディライン。一瞬にして会場はサトリアーニ色(いろ)に染められていった。 2曲目はドラムのクローズド・ハイハット−「チー、チー、チー」の連打でスタートする。お馴染みのギター・ハーモニクスがリズムと絡まるように聞こえてくればもう何の曲か判る筈だ。「SUMMER SONG」はもう何回聞いたか判らない。また今も昔も私のギター練習曲である。 耳馴染みのリフが始まれば、客席では「Oh〜」と大歓声が上がる。いかに観客がこの曲を待ち望んでいたか判るというものである。 今回、メンバーはドラムにジェフ・キャンピテリ、ベースにマット・ビソネット、サイドギター&キーボードにギャレン・ヘンソンという鉄壁な編成。いつもながらにジェフのドラムはタイトでキレがあり気持ちが良い。「SUMMER SONG」でもそれが充分に実証された形となった。 3曲目の「HORDES OF LOCUSTS」も最新アルバムからミディアムテンポの曲。ベースソロを挟み、サトリアーニのギターが縦横無尽に駆けめぐる。アームをふんだんに使い、叫び声の如くギターから音を発散させ視覚的にも非常に面白い。 3曲目の後、サトリアーニは初めてマイクを取って語り始めた。 「コンバンワ ゲンキデスカ ワタシハ ジョー・サトリアーニデス。アノネ、ワタシハ ニホンゴガ スコシシカ ワカリマセン......」 (日本語が判らないと言いながらも「アノネ...」ときた時は流石にずっこけてしまった。 笑) メンバー紹介を経て始まった4曲目はイントロのミュート掛かったアルペジオで場内は大きな歓声に包まれた。 「ALWAYS WITH ME , ALWAYS WITH YOU」は以前も書いたが私にとって非常に思い出深い曲。そして何度も何度も練習した曲。 これまで生でも何度も聞いてきたが、ご本家はやはり巧い。巧すぎる。テクニック、雰囲気、余韻、トータルの面で完璧である。 5曲目「SEARCHING」も最新アルバムからの選曲。 やはりnewアルバム発売以降、初の日本公演となるとどうしてもそのアルバムのプロモーション的な役割も大きくなってしまうようだ。 ここでギターはノーマルな6弦から7弦ギターに持ち替えての演奏である。もちろん、アイバニーズのサトリアーニ・シグネイチャーである。 ワーミーペダルによる効果音が摩訶不思議な旋律を生み、我々観客を幽玄な世界へ導いてくれる。ステージバックの幾何学模様もサイケデリックな色使いで曲に相乗効果を与えた。まるで音楽の麻薬である。 また時には座り込んで弾いたりとサトリアーニには珍しくアクションも加わって見せ場も多いステージとなった。 宗教的とも言える高潔なイメージが場内を支配してしまったのを察知してか、「SEARCHING」の終了後、マットがサトリアーニの代りにMCで 「キ・ラ・ク・ニ」 と観客を和ませると場内の雰囲気も一気に氷解していく。 6曲目は最新アルバムのタイトル・トラック「IS THERE LOVE IN SPACE」。 冒頭から激しくワウペダルのウネリが響き渡る。ヴァイもワウの使い方は巧いが、サトリアーニを聞いてしまうと次元の違いを感じてしまうくらいだ。 サトリアーニがギターを弾くきっかけとなったというジミ・ヘンドリックスはロック界におけるワウペダルの先駆者であるが、現代ではサトリアーニが”革新者”である 事は間違いない。 最新アルバムが続いた後は懐かしい曲の復活。「WAR」は生では久しく聞いていない曲である(もしかして初めてか?)。 スリリングでかつメロディアス。フレーズがCD以上に『唄っていた』のは錯覚ではないだろう。 8曲目はギャレン・ヘンソンのキーボードが薄く場内を満たすとすぐにサトリアーニがテクニカルなフレーズで追随する。 やがて有名な(女性のしゃべり声の)SEが流れ始めると印象的なメロディラインをマットとギャレンが醸し始める。そこに切り込んでくるようにサトリアーニのギターが最初はメロディアスにそして徐々にスピードを増し速いパッセージを披露していく。 「FLYING IN A BLUE DREAM」は本日のライヴを集大成と言えるぐらい素晴らしい出来であったのは言うまでもないだろう。 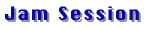
G3のライヴで最もエキサイティングな時間。それはJAMだ。 ステージに残ったサトリアーニが他のメンバーを呼び込む形でJAMは始まった。 マイク・ポートノイ、ジョン・ペトルーシ、スティーヴ・ヴァイ.....がステージに再び現れると始まったのはジミ・ヘンドリックスの「FOXY LADY」。 JAMで一番の見所はなんと言っても各人のソロタイム。この1曲目から火を噴くようなプレイが続出し我々、観客を魅了した。 ソロはペトルーシ−ヴァイーサトリアーニという流れで回されていったが各人が色々なアプローチでフレーズを組み立てていくのは非常に興味深い。 同じようなフレーズでいくのか、全く違ったアプローチで切り返すのか。 正に自らのセンスとテクニックの見せ所でもある。それだけにエンディング・ソロは壮絶を極めることとなった。 JAM2曲目はZZ TOPの「LA GRANGE」。 私にとって聞き覚えの無い曲であったが、なんとなくサトリアーニの「BIG BAD MOON」に似ているような気がした。もしかして元ネタ発見なのか。 ドラムがマイク・ポートノイからジェフ・キャンピテリに交代、ビリー・シーンも呼び込まれステージはいっそう華やかになった。 おまけにビリーはベースと共にボーカルも担当するのだ。(ビリーの負担を軽減する訳ではないだろうがマット・ビソネットもステージに残りベースを弾いている) この曲でも再びペトルーシ−ヴァイーサトリアーニという順番でソロが綴られていったがその間の他のメンバーの様子をのぞき見ると結構、面白いものがあった。 ベースのマットがビリーとじゃれあっていたりとコミカルな動きを見せ演奏でない部分でも我々を楽しませてくれている。 それにサトリアーニとヴァイがステージ上でなにやら楽しげに喋っている姿には感動すら覚えた程であった。 ヴァイとサトリアーニと言えば「師匠と弟子」あるいは「先生と生徒」という関係である事はつとに有名であるが、二人揃って同じステージに立つこと、そしてあの二人が喋っていることなどビデオやDVD、あるいは雑誌に掲載された写真でしか味わえなかった感動が目の前で再現されている事だけで胸一杯になった。 それにヴァイが少年時代、ギターと弦だけを持って、近所でギターを教えていたサトリアーニの処に通うようになり.....と今に繋がるヴァイの歴史を考えるとどうしてもその情景さえ浮かんで微笑ましくも思えてくる。 ここにも「人との出会いの妙」を感じてしまうのだった。 JAM最後の曲は日本のロックファンに馴染みの曲をという配慮だろうか。 ディープ・パープルのロッククラシック「SMOKE ON THE WATER」。 サトリアーニにとってディープ・パープルは少なからず縁あるバンドであることは熱心なサトリアーニファンには先刻承知の事だろう。 1993年末、日本公演を控えたディープ・パープルからリッチー・ブラックモアが脱退。急遽、代役に立ったのがジョー・サトリアーニであった。 私は当時の事を今でもはっきり覚えているが、やる気の失せたリッチーの代りにサトリアーニが来ると(新聞の広告で)知って驚きと共に喜んだものだった。 それが10年の時を越えて再現されるとは非常に感慨深い。 超有名なギターリフが3人のギタージャイアンツによって一斉に奏でられると客席は大きく揺れた。ボーカルはマット・ビソネットだ。 ギターソロはオリジナルを忠実に再現しながらも、最後には感情にまかせてもの凄い早弾きを披露してしまうペトルーシ、旋律だけがかろうじて感じられるヴァイのアレンジしまくりのソロフレーズ、唄心をフレーズに込めるサトリアーニ。 2ndソロはそれ以上に凄い事になった。もはやソロを順に回すということから逸脱して各人、おのおの好きなフレーズを弾きまくっている。 だが当然の如くそれは曲を破壊するものではない。 特にタッピングによる三重奏(もしかしてビリーも入れて四重奏?)は圧巻であり今回のG3ライヴを最も象徴するシーンの一つであった。 記念すべきG3のライヴはこうして幕を閉じた訳だが、ギター好きにとっては堪らない「至高な3時間」であったと思う。 誠実さがプレイにも滲み出ていたペトルーシ、超絶な技をこれでもかと見せつけるヴァイ、もはやテクニックがどうのというレベルを超越した異次元な存在、サトリアーニ。個性豊かな3人がそれぞれ自らの力=技を屈指して披露していく様は圧巻という言葉しか見つからない。 3人を『三本の矢』に例えるのは失礼かもしれないが、そもそも彼らが1本の矢だとしてもそれは強固な”折れにくい矢”であるだろう。 だが、その”折れにくい矢”が3本集まったとしたら、それはより大きな力を持つに違いない。その力を生み出す源は『三本の矢』の逸話の真理である”人の和”。 「和を以て貴しと為す」 と説いたのは聖徳太子であるが、和を持って団結しなければ絶妙なプレーも望めないのは何もスポーツの世界だけではあるまい。 音楽の世界で団結とは不相応な感じもするが、あのJAMでのスリリングな演奏を聞けば「和」という言葉の持つ違う側面も透けて見えてくるような気がする。 「和」という実に東洋的な思想さえ根底に感じた今回のG3ライヴ。 ステージを去る彼らの後ろ姿に日本古来のサムライの姿が重なって見えたのは幻覚だったのか。 いや、見間違えではない。 彼らこそ”真のギターサムライ”であったのだ。 |
| 戻る |