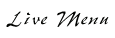PAUL GILBERT
" PAUL THE YOUNG DUDE" ツアーライヴ
|
|
|
激しく弾きまくるポールと8フィンガーで流れるように弾くT. J。 個性の違いが際だつ瞬間だ。 それにポールとT. Jで『二人羽織ギター』(T. Jの背後からポールが覆い被さるようにしてT. Jのギターをピッキングする。フィンガリングはもちろんT. J)という初期Racer X時代やMr.Bigで披露していた超絶技巧曲芸まで飛び出したのはギターファンにとっては嬉しい驚きだった。(T.Jのギターを借りながらもピッキングすると聞き慣れたポール・サウンドになっていたのはさすがプロと言う他なかった。) T.Jのソロコーナーとジャムセッションの興奮そのままにポールの「ワン、ツウー、ワン、ツウー、スリー」のカウントで始まったのがまた恐ろしく速い、高速インストナンバー「Let The Computer Decide」。 私の僅かな記憶ではポールとしては珍しく7弦ギターを使った曲の筈。複雑で勢いのあるリフ、ストリングスキッピングを屈指したソロフレーズ... それらが渾然一体となり音の波状攻撃を我々、観客に仕掛けてくる。 我々はもうノックアウト寸前 !! だがポールはそんな激しい演奏の後も飄々として、突然 「It's Friday Night ?」 と我々に問いかける。 当然、答えはノーだ。− 本日は木曜日 それからポールと「ゲツヨウビ(月曜日)」「カヨウビ(火曜日)」...とやりとりがありその都度「ノー」と律儀に答える我々。 いよいよ「モクヨウビ(木曜日)」となれば、一同「Yeah !!」と盛り上がる。 だが、ポールの日本語もこれでは終わらず、手のひらを掲げて順番に指を指し示し「クスリユビ」「コユビ」とやりだしたもんだから会場は大爆笑!!! 結局、「ヒトサシユビ」に到達するまで『日本語特訓コーナー』は続いたのたがコレには正直な処、苦笑するしか無かった。(もうこの時ばかりはロックのライヴに来ているという感覚は無くなっていたので(笑)) MCの後、16曲目は鼻歌交じりに始まった「Girls Who Can Read Your Mind」。この曲もポールのライヴではお馴染みの曲。 ポールらしいポップ感覚が随所に散りばめられ、先程のハードな「Let The Computer Decide」とは対極をなすものである。 ポールはこの時、小さめのジャンプスーツ(?)のようなものを着ていたのだが、演奏終了後は胸の途中まで止まっていたボタンを外し、上半身を露出。 「Sexy」と掛け声が掛る中、”今度こそ”の「Friday Night (Say Yeah) 」が始まった。 「Friday Night (Say Yeah) 」だけではないが、こういうポップな曲がいかにビートルズやチープトリック、トッド・ラングレン等の影響を受けているか伺いしれて非常に興味深い。 「Friday Night (Say Yeah) 」の後、ポールが「T.Jサン ボクノトモダチ」と言って、お互い背中合わせにしてジャムりながら始めたのは「Girls Watchin」。あのジミ・キッドおじさんとの共演アルバム「Law Blues Power」トップを飾る曲だ。 冒頭の交互にフレーズを繰り返し掛け合いをする姿は昔のジャムセッション的なライヴでは定番で有ったスタイルだが、今やこのようなプレイスタイルを踏襲しているバンドも少ない(ギターソロ自体、無いバンドも最近は多い)。 ゆえに非常に新鮮に感じるのだ。もちろん途中のギターソロもCD同様、ポールとT.J仲良く分け合ったのは言うまでも無いがエンディングはポールの18番、ストリング・スキッピングで見事に決めた。まさに”シンクロ・ナイズド・プレイング”で息のあった演奏を聴かせたポールの勢いはここにきて一段と増し、聞き慣れたリフをクリーンな音色でゆっくり弾き始める。 Racer X の「Superheroes」だ! 「ワン、ツー、スリー」のカウントで歪んだ音をノーマルな速さで繰り出せば、あのRacer XのCDそのまんまだ。 まさか「Scarified」に続いて「Superheroes」までRacer Xの曲を披露するとは全く持って嬉しい誤算。 だが、現実はそんなに甘くはなかったことか。 イントロを弾ききったところで「Superheroes」は”尻切れとんぼ”的にあっさりと終了してまったのだ。 ただでさえ「Superheroes」はアドレナリンをレッドゾーン振り切れるほど沸騰させる曲であるのにイントロだけで終わらせるとは........この押さえられない気持ちは一体、何処にぶつければいいんだ !! という私の気持ちなどお構いなしに間髪を入れずに次の曲へ移るポール。 キーボードのシーケンスフレーズで始まった、この曲は「Burning Organ」に収録されたマイ・フェーバリットな「Bliss」ではないか。 ポールお得意なジミ・ヘンを彷彿とさせる曲調、ブルースロックフィーリングに溢れたオブリガード、そしてエンディングのこれでもか!というぐらいの攻撃的な早弾き。 こうなると現金なもので先程までの尻切れトンボな「Superheroes」の演奏で萎え始めた私の気持ちも、これで一気に雲散霧消したのだった。 ポール一行はこの曲で一旦、ステージを降り「ライヴ1部」終了となったが拍手は依然として鳴り止むことは無かった。 その拍手は誰の先導もなく激しく、やがて規則正しい手拍子になり会場の誰もがポールの再登場を待ち望んでいる事をアピールしたのだった。 〜 UNCORE 1 〜 そんな大きな声援が後押しとなったのか、わずか数分のインターバルでポールとバンドのメンバーはステージに再登場した。 ポールもTシャツに着替えて非常にラフな格好だ。冒頭のブルーのアイシャドウには辟易した私だが今はその化粧も取れ、普段のポール・ギルバートに戻っている。 そのポールが今度はなにやらメモを取りだし、こう切り出した。 「ダレカ ステージニ アガッテ ボクヲ タスケテクレマスカ ?」 即座に客席では一斉に手が挙がり、男達の「ハイ、ハイ」という野太い声が大きく響き渡った。 しかし、さすがに野郎を舞台に上げる訳も無くポールは横のベースのライナス・ハリウッドと相談しある女性を指名。その娘(こ)を客席から直接、舞台に上げた。 ポール自身「スゴイ Tシャツ」という感想を述べたようにその娘はキューピーの顔が大きくプリントされた赤のTシャツを着て非常に目立っていた。 おそらく そのTシャツの派手さが選ばれた要因のようだ。 その彼女も選ばれた事にかなり興奮している様子でハイテンションぶりがひしひしとこちらにも伝わってくる。 結局のところ、彼女は日本語でバンドのメンバー紹介をやって貰うという大役の為、選ばれたのだがまたまた日本語を絡めたこの心憎い演出には感心させられた。 彼女はポールから渡されたメンバー表を元にドラムスのスコット・クーガン、ベースのライナス・ハリウッド、ギターのT.Jヘルムリッチ、コーラスのケイトとヘザー(ちなみにケイトはポールの妹、ヘザーはT. Jの奥さん) と次々に名前をはっきりとした口調でコールしていく。そして最後に 「そして そして ギターとリードボーカルは ?」 の彼女の問いに観客も「誰だあ〜」と茶目っ気たっぷりに反応。 彼女もそれに乗せられ 「ポール・ギルバート!」 と絶叫で応え、場内は今日、最も熱い瞬間を迎えたのだった。 しかし、彼女の仕事はそれだけでは無かった。 次の曲紹介という名誉ある大仕事が待っていたのだ。 それも興奮の為、うまく口が回らず途中でタイトルが途切れてしまうというちょっとしたハプニングが有ったもののそれが功を奏してより大きな盛り上がりとなったのだった。 なにせ次の曲があの名曲「Green-Tinted Sixties Mind」である。 その半端でない盛り上がりはみなさんにも容易に想像がつくだろう。 ドラムのスコット・クーガンの「オールライト、オールライト」という観客を煽るシャウトとほぼ同時に始まった聞き慣れた印象的なタッピング・フレーズ。 私は「Green-Tinted Sixties Mind」を初めて聞いたあの時の情景を今でもはっきりと思い出す事が出来る。 歌が始まれば、ほぼメインボーカルをT.Jが担当。前述の「I Feel The Earth Move」でも既に実証済であったが、T.Jは歌も非常に巧い。 声質もMr.Big時代のエリック・マーティンを少し彷彿とさせ、この曲を初めて聴いた頃の時間へと誘(いざな)ってくれたのだった。(そういえば ポールが一人で唄っていた頃はキーを下げていたように思うが、今回はMr.Big時代と同じノーマル・キーだったのかもしれない) 色んな思いが走馬燈のように去来した「Green-Tinted Sixties Mind」は再度、タッピングのフレーズでエンディングを迎え大きな拍手となった。 次に余韻を浸る間もなく始まったのが、またまたあの曲。 「Masa Itou 」。 私が参加したインストア・イベントでは2会場とも、この曲がオープニングであったがポールはよっぽど気に入っているのだろうか。 もちろん長年、お世話になっている伊藤政則氏への感謝の気持ちもあるのだろうが、CDではシークレットトラックであったこの小曲をイベントだけでなくライヴでも披露するという選曲には結構、驚かされた。 でも「マサ・イトー」と連呼するこの曲もやはりキーワードは『日本語』。 今回のライヴでも選ばれて然るべき曲であったのだ。 「Masa Itou 」が終われば、まるでメドレーのように次の曲が始まる。 これはRacer Xの最新アルバム「GETTING HEAVIER」に収録された「Heaven In '74」ではないか。 またもやRacer X。それもライヴでは日本初披露の曲である。ポールのライヴでRacer Xの曲を3曲も聴けるなんてかなり得した気分だ。曲調もポールらしいポップなもので歌詞の途中に「ビートルズ」「エルトン・ジョン」「ZEPPELIN」「ZZ TOP」とお馴染みのROCKバンドが登場してくるのは非常に楽しい。 「サンキュー ナゴヤ」というポールのシャウトで締めくくった「Heaven In '74」でアンコール第1部も終了。 メンバーがステージを去っても場内は騒然とした雰囲気の中、大きな歓声に沸き「ポール ポール」という掛け声が激しい拍手と共に一糸乱れず続いた。 〜 UNCORE 2 〜 あまりにその拍手の激しさの為、先程よりも時間短くステージに復帰するポール達。 服装も先程のままだ。 だが、中央のマイクスタンド前に立ったポールはすぐに演奏を再開する事はなかった。セットリストを取り出しこう順番に読み上げ始めたのだった。 「I Like Rock 」 「My Religion」 我々、観客もその都度、「Yeah」と応えたが 3曲目に「Down To Mexico」 と言うやいなや「No」と激しい反応が..... 確かに、後にゲットした本物のセットリストにも3曲目にも「Down To Mexico」と記述してある。 では ポールが順番を間違えたのか ? いや、そうではない。これも予定通りなのだ。 ポールはいかにも「やっちまった(順番間違えた)」という戯けた表情を見せるが 私にしてみれば「やられた〜」という感じである。 こんな楽しげな演出が出来るのもロックスター然としていない、身近にいそうな「ロック兄ちゃん」という親近感を我々に抱かせるキャラクターの賜物だろう。 イングヴェイやリッチーではこうはいきません。 そんなアットホームな雰囲気な中、「Down To Mexico」は大きな手拍子にかき消される事もなく特別なイントロを伴って始まった。そして、いつものジミ・ヘン風のイントロをポールが奏でれば場内は興奮の渦と化した。 私もポールの曲の中で唯一、弾く事が出来る(かも?)の曲だけにその興奮ときたら尋常ではない。 「Down To Mexico」はポールのソロ作品では最も初期の曲に分類されるがライヴではここぞという時、必ず演奏される、いわば定番の曲。しかし、ここにもT.Jヘルムリッチという得難いパートナーを得てこの曲も進化したようだった。(ギターソロをT.Jと分かち合ったのだ) 「Down To Mexico」が激しいエンディングで幕を閉じればすぐにポールのカウントで始まった「Purple Haze」は驚きの選曲だった。ジミ・ヘン風の「Down To Mexico」からジミ・ヘン本家のカバー。 ポールはその昔、「Tribute to Jimi Hendlix」というカバーライヴアルバムまで出しているくらいだからこの選曲には頷けるものがあった。 演奏もギターソロではポールとT.Jのギターバトルが繰り広げられお互いありったけのフレーズ、技巧を繰り出していくアグレッシブなその様は時代を超えてジミ・ヘンが二人降臨したかのようだった。 まさに饗宴という言葉に相応しい熱い演奏であったのだ。 エンディングのギターのフレーズがグイングインと場内をいつまでもループする中、ポール一行は順番にステージを去り、再び戻ってくることは無かったのだが今回も色々、ポールは我々に楽しい思い出を残してくれた。 特にその中で目立ったのは「日本語」を多用したライヴ上の演出である。以前からポールの日本語への傾倒ぶりは有名であったがそれがライヴでも実証されたという事でもある。 またRacer Xの曲を3曲もセットリストに加えた事も嬉しい驚きであった。特に「Scarified」は驚嘆に値する演奏であった。 そんな演奏面での最大の功労者はサイド・ギターのT.Jヘルムリッチであった事は疑いの余地はないだろう。 ギターの腕前は言うに及ばず、その歌声は多くのポールファンの心も捉えたはずだ。(元々はex.ネルソンのブレッド・ガーズドが参加する予定であったがスケジュールが合わず、彼の友人であるT.Jが参加する事になったらしい。いわばT.J参加は偶然の産物だったのだ。) ポール・ギルバートと言えば 誰もがイメージするのは”とてつもなく難しいギターフレーズを軽々と弾きこなす”ギタリストの姿であろう。 もちろん、今回もそのような見せ場は満載であった。またボーカリストとしても今や、堂に入った立派なものだ。それに正統的ヘヴィ・メタルからポップソングまで何でもござれのコンポーザーとしてのポールとまさに八面六臂な活躍ぶり。 それら様々な顔を見せるポールに今度は「エンターティナー」としての顔が加わった事を今回のライヴで私ははっきりと確信した。 人を楽しませるというのは世の東西を問わず、非常に困難な作業だが『日本語』をキーワードとした今回の演出は日本長期滞在を経たポールだからこそ可能だった訳で、日本人の喜ぶツボというものを十分心得ていたと思われる。(「堂本兄弟」などでのTV出演は『日本式エンターティメント』を学ぶ良い修行の場となったに違いない。) 「エンターティナー」としても開眼したポール・ギルバート。 次はどんな顔を見せてくれるか非常に楽しみである。 |
| 戻る |