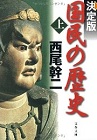BC900年ころ 日本の九州北部へ稲作農耕が伝わる
共同通信社の KYODO NEWS(共同ニュース)に記載された2003年(平成15年)5月19日付けの記事によると、日本の国立歴史民俗博物館(千葉県)は、加速器による放射性炭素(C14)年代測定法を使って、福岡市の雀居遺跡(弥生早期)など数カ所から出土した土器の中にこびりついたコメを測定し、いずれも紀元前900年前後と判明したことを、5月19日に発表した。同時期とされてきた東北地方や韓国の土器のコメの測定結果も似た年代だったという。
日本への稲作の伝来は、当HP年表の基礎資料とした「年表式日本史小辞典(芳賀幸四郎監修、文英堂、1988年)」ではBC300年ころとしており、「日本全史(講談社、1991年)」ではBC350年ころ、「市販本 新しい歴史教科書(西尾幹二ほか13名著、扶桑社、2001年)」ではBC400年ころとしている。
近年は、BC400年ころとされていたようであるが、一気にBC900年ころにまでさかのぼった。
【稲作の伝来ルート】
西尾幹二著「決定版 国民の歴史 上」(文春文庫、2009年)p.114-115 に、次の記述がある。
なお、引用文中の(注)とタイトル以外の太字は、当サイト管理人が施したものです。